��S�ҁ@�Y�Ƃƌo��
��P�́@�_�{�Y��
�@��P�߁@�J��ȑO�̔_��
���J����̔_��
�@�{���̐�Z�����ł���A�C�k�l�́A�����������ł��邪�A�S���_�k���s��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�ɂ߂ėc�t�ł͂��������Â�����_�Ƃ�m���Ă����B���Ȃ킿�A�_�앨�͌I�i�����`�j�E�B�i�r���o�j�E���i�A�^�l�j�Ȃǂɂ������A���̊p�������͖̋Z�ō�����ߚ{�i�V�c�^�c�v�j�₩�܂������ēy�������A��q���܂��Ď{��E�����������A�����Ђ��̕�͊L�������Ɏ����ďn�������̂���E�ݎ��Ƃ������n�I�Ȃ��̂ł���A�����͎�Ƃ��ĕw���q�̎�ɂ���čs��ꂽ�B�����Ď��l���͕��H���Ƃ��A�܂��A�����Ђ��͑����錴���Ƃ��Ă����Ƃ����B�i�u�V��k�C���j�v�j
�@�A�C�k�̃R�^���́A���R��⋙�J�ɕ֗��ȂƂ���ɍ���A�����͖F���Ȓn����A�傫�Ȃ������͂�ŁA�ԁX�ƔR���邽���ɂЂ��ʂ���߂Ȃ���k���A���a�Ȑ����𑱂��Ă����̂ł���B
�@�������A���O�˂��������ĉڈΈ���x�z���A�ˎm�ɑ���m�s�ɑウ�ďꏊ��ݒ�A���Ղ�ʂ��ăA�C�k�Ƃ̌������悤�ɂȂ��Ă���́A�a�l�̉��������R�ɐ���ɂȂ�A�₪�āA����畽�a�ȃR�^�����傫�ȕω��𐋂���悤�ɂȂ����B���Ƀ����N�V�i�C�ȓ�A���Ȃ킿�A��c�Ǐꏊ�����̒n���́u���O�n�v�Ƃ����ď��O�˂̗̒n�ɂȂ�A���R�ɘa�l�̒�Z����҂������Ȃ�ɂ�A����ɔ��R������̂͒ǂ��A���ʁA�A��������̂͂��̒n�Ɏc���Ęa�l�ƌ𗬂��A���R�ɔ_�k���̋Z�p���C�����Ă������B
�@�����ڂ��Ĉ����Q�N�i�P�W�T�T�j�ɒ����̒������u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�̃����N�V�i�C�̍��ɂ���
�@�u���̕ӂ͊i�ʂ̍��R�Ȃ��A���R�Â��Ȃ�B�ߎR�ɔ������A�I�A�B�A���A�卪�̗ށA���i��j�͏��q�̋ƂƂ��B�����l�H���́@����̌I�A�B�A�G���A�����A���̗ނ�H���A�c�c�v
�Ƃ���A�܂��A�����R�A�S�N�̒����ɂ��ď������s��\�Y�́u�ڈΎ��n���l�^�v�ɂ��A
�@�E�����@���n�O�S�\�A�I�A�B�����B�ڈΔ��n�l�S�B
�@�E��c���@���n�ܕS�\�ؗ]�A�ڈΔ��n�O�S�B
�@�E�����@��������B
�ȂǂƂ���悤�ɁA���̎���͂����܂ł������S�̐����ł���A�_�k�͕w���q�̕��Ƃɂ������Ȃ����x�̂��̂ł��������Ƃ���Ă���B
�@�Ȃ��A�]�k�Ȃ��疾���P�P�N�i�P�W�V�W�j�J��̏��ɂ����V�y������̒��ɁA�A�C�k��Łu�g�C�^�E�V�i�C��v�Ɩ��t����ꂽ��i���݂̔��_��̂��Ƃňꕔ�s�s�����H�ƂȂ��Ă���j�����������A���g�C�^���͔��d��������A���E�V���͂�������A���i�C���͗���̂��Ƃ��w���A�����āu���d��������y�n�v���Ӗ����Ă�����̂Ǝv���A�R�^���̃��m�R���������̕t�߂ł����Ђ�������Ă������Ƃ���A���̖����t����ꂽ���̂ƍl������̂ŁA���łɂ��̒n�тł��A�C�k�ɂ�錴�n�_�Ƃ��c�܂�Ă������Ƃ�����������̂ł���B
�ƒ{�̎��{
�@�ڈΒn�ɘa�l������悤�ɂȂ��������́A�n���B��̌�ʋ@�ւƂ��ė��p���ꂽ�B
�@���_�n���ɔn�̋L�^�������̂́A���ۂ������N�ԁi�P�V�S�P�`�P�V�S�V�j�ɋL�^���ꂽ�Ǝv���钘�ҕs���́u�ڈΏ��ɕ����v�ŁA��ʂɂ��āA
�@�P�A���g�V���@���i�V���@��c�I�C
�@�@�i�O���j�~�n���V���ԃn�n�j�ʌːؒn�Ɛ\�����o�A�c�c
�Ƃ���A�܂��A�����V�N�i�P�W�P�O�j�́u�ڈΒn���X���ʐ}�v�ɁA
�@�E�����N�V�i�C�@�n���l�\�ܕD�c�c
�ƋL����A�����Q�N�i�P�W�T�T�j�́u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�ł́A
�@�E�����N�V�i�C�@�y�n�����\��D�̂����ƒu�n�l�\�D����
�@�E��c�ǃ��I�C�@�n�͓�\�ܕD����O�D����
�@�E�����@�n�͎O�\���D����Z�D����
�ƋL�����ȂǁA���X�ɔn�̎��{�������Ă��邱�Ƃ�\���A�܂��A��ʏ�ɂ���B��ɂ��������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����B�������A�����T�N�i�P�W�T�W�j�ڈΒn�ł͊��n����ьx�q�m�̎g�p����n�̂ق��́A��ʐl�����炷�邱�Ƃ͋֎~����A�_�k��^���p�ɕK�v�ȂƂ��ɂ͊��n��݂��t�����邱�Ƃɒ�߂��Ă����̂ŁA�����N�V�i�C�Ȗk�̔n�͊��n�Ɍ����Ă����킯�ł���B�������A�����ڂ�ɂ�Ă������ɔn�̎��v�������Ȃ�A���n�����ł͂���ɉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ŁA���v���N�i�P�W�U�P�j�T���ɂȂ��Đ����l�͂������A�o�Ґl�ł����R�Ɏ��炷�邱�Ƃ�������邱�ƂɂȂ����B����ǂ��A�n�𑼂���ړ����邱�Ƃ͋ɂ߂č���������߁A����ɂ͏\�����ӂ��͂炢�A�ʍs�ȂǂɕK�v�ȂƂ��͂��ł�����Ƃ��������Ŋ��n����A���L���������͔̂ɐB���Ďq�n��Ƃ����̂����ʂł������B���̂悤�ɂ��ĉڈΒn�ŁA��������ʐl�ɂ���Ă����炳��͂��߂��̂ł���B
�@����A���̋L�^�Ƃ��ẮA�O�f�u�ڈΎ��n���l�^�v�̎R�z���̍��̒��ŁA
�@�u���ܕD���쑺��蔃����v
�Ƃ���̂����߂Ăł��邪�A���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ��Ĕ������ꂽ�̂��ڍׂɂ��Ă͕s���ł���B�����炭�����̋��́A�n�Ɠ��l��p�Ɏg��ꂽ���̂ł��낤�B
���˂̊J��
�@�����S�N�i�P�W�T�V�j�z�O���˂̉Ɛb��R���Y���q���Z���A���{�̋����ĉڈΒn�̊J����u���A�R�z���ɈڏZ���Ęh�̑��̊J���ɂ��������Ƃ������Ƃ́A���Ɂu��R�ҁA��P�́A��S�߁A�㖋�{��������v�̍��ŋL���Ă���̂ŁA�����ōČf���邱�Ƃ͏ȗ����邪�A���_���J��̑��n�Ƃ��ċM�d�Ȏ���ł���B
�l��˂̊J��
�@�����R�N�i�P�W�V�O�j�@�P���ɎR�z�S�͕����Ȃ̊NJ��ɂȂ��ēl��˂̎x�z����Ƃ���ƂȂ�A�P�Q���ɔˎm������l�Y�͎R�z�S�̊J���W�𖽂����A�P�O�]�ˁA�R�O�]�l���������ē��A�����B���̂����R�z���i�����Ó������A�l���j�ɂ͂V�ˁA�P�W�l������A�c��͒��������ɓ��A���ĊJ���ɒ��肵���B���ꂪ���_�n���ɂ�����W�c���A�̏��߂ł���B�@���������S�N�W���ɔp�˒u�����s���A�����W���I�Ȍ��͐����̐������v���s���A�l��˂͓l�쌧�ƂȂ�A���̎x�z��Ƃ����ĎR�z���͊J��g�̒����n�ƂȂ����B���A�҂͂��̂܂܂��̒n�Ɏc�������̂́A������͊J��g�̕ی�ɊÂēk�H����ɂƂǂ܂�A�����P�T�N�i�P�W�W�Q�j�O��ɂ͂ǂ��ւƂ��Ȃ����U���Ă��܂����Ƃ����B����������l�Y�͓l��A�炸�A����Ɉڂ��Ĕ_�Ƃ��c���A�����W�N�_�Г��ɁA�P�R�N�ɂ͊���Ɉڂ苳���ƂȂ����B
�@�����������Ƃ��琄�@����ƁA�l��˂Ƃ��Ď��ۂɊJ���ɏ]�������̂͂W�������x�Ǝv����B
�@��Q�߁@����Ƃ̊J��
�J��K�n�̒���
�@�����V���{���a�����A�����Q�N�i�P�W�U�X�j�U���ɂ͔ːЕ�҂��s���ĉƘ\�i�낭�j���팸���ꂽ�m���́A�����ɑ傫�ȑŌ������̂ł������B�����łS�N�V���A�p�˒u���ƂƂ��Ɏm���̉Ƙ\�͐��{�Ɉ����p���ꂽ���A���ɂ̕��S�����������債�����߁A�U�N�ɐ��{�͉Ƙ\��ҋK�����߂ĕ��S�̊ɘa��}�����B����ɁA�W�N�V���ɂ͍�����̗��R�ɂ���āA���̉Ƙ\��ҋK�����ꎞ�����~�߂��A�����ė����N�W���ɂ́A�Ƙ\�E���T�\���S�p�����Ɏ����āA���悢��m���ւ̎��Y���Љ�I�ȑ���Ƃ��Ď��グ����悤�ɂȂ����B
�@���������Љ�w�i�̂��ƂŁA�����É��ˁi�����j�ˎ哿��c���́A�@�u��S���\�N���̔ˎm�f���c���̓��ɑa���A�����b�h�����̑�����h���ɑ��炴��v
���Ƃ�J���A�����P�O�N�i�P�W�V�V�j�T���~���P�P������s�ɗa�����āA���̗��q�����Ɛb�̎��Y�ɏ[�Ă邱�ƂƂ����B�����Ė��É��ɗ{�\�H��������ƂƂ��ɁA���Ɛb�̏A�Y�̓����J�����ߖk�C���̊J����u���A���N�V���ƐE�g�c�m�s�̂ق��p�c�O�ƁE�Ћˏ�����h�����ĊJ��K�n�̒����𖽂����B
�@��s�͂��悻�R�����ɂ킽���āA���g�ʼn^����̂��܂肩����Ȃ��y�n��I�肷����j�œ���e�n���������ʁA���[���b�v��̗���ɓK�n��I��̂����A�P�O�����{�Ћˈ�l�قɎc���ċA�����A�u�J��g�Ǔ��_�U���R�z�������V�y�������T���v�Ƃ��������o�����B
�@����ɂ���āA���悢�擖�n�ւ̈ڏZ�J��̋c����������Ɏ������B
�ڏZ�l�n�q�� �i�ʐ^�P�j

�ڏZ�l�n�q�� �i�ʐ^�Q�j

�������ˎm�̓��A
�@�����P�P�N�T���V�y�����L����P�T�O���i�P�͖�R�E�R�������[�g���j�̖������t���o��A���N�U���P�R���������̂Œ����ɏ����Ɏ��|����A�g�c�m�s��X����I��ŖړI�n�ł���V�y������ɐ攭�������B
�@�攭����s�͓����i�삩��D�Ŕ��قɓ����A�������𐮂����̂����H���[���b�v�Ɏ���A��������������⑪�ʂ��s���Ȃ���n�Ƃ̂��������s���ƂƂ��ɁA���H�̊J��A�Z���������Ă�ȂǁA�ڏZ�l����̂��߂̏�����i�߂��B
�@�������Ă��̔N�P�O���ƂP�P���A�J��g�D�D�P�v�����ۂȂǂłP�T�˂V�Q�l�ƒP�g�҂P�O�l���v�W�Q�l�i���N�����S�P�l�A�o���T�l�j�̑�P���ڏZ�҂��}���A�����ɔ��_���n��Ƃ��ċL�O���ׂ��A�g�D�I�A�{�i�I�J��̋Ƃ�����������ƊJ��������̒a�����݂��̂ł���B
�@�Ȃ��A�����������P�Q�N�ɑ�Q���ڏZ�҉Ƒ������̎҂P�S�˂ƒP�g�҂S�l���}���A����ɂP�S�N�ɂ͑�R���ڏZ�҉Ƒ������̎҂P�S�˂ƒP�g�҂V�l���ڏZ������ȂǁA����Ɍˌ��������A�J��̎��Ƃ����X�Ɛ��ʂ��グ�Ă������B�����ڏZ�҂̉Ƒ������́A���قőD����芷���A�ĂёD�Ń��[���b�v�l�̉��܂ŗ��Ă͂����ŏ㗤���A��������Ă������ꂼ��̉ƂɌ��������Ƃ����B
�@�����P�P�N����Q�T�N�܂ł̔N���ʈڏZ�҂͎��̂Ƃ���ł���B
�@�����P�P�N��P���ڏZ�ҁi�P�T�ˁE�P�g�҂P�O���j�Z�����ɈڏZ�i���Ə̂��j
| �Ƒ��ږ� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�l |
| �g�@�c�@�@�m�@�s | ���j�m�� |
| �p�@�c�@�@�O�@�� | ��F�̌Z |
| �p�@�c�@�@��@�F | �@ |
| ���@���@�@�ׁ@�� | �@ |
| �i�@�c�@�@�@�@�� | �@ |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| ���@�c�@�@���V�� | �@ |
| �Ɂ@���@�@�M�@�� | �@ |
| �g�@�c�@�@���@�Y | �@ |
| �y�@��@�@��@�� | �@ |
| ��@�@�@�d�@�M | �@ |
| �u�@���@�@�v�O�Y | �@ |
| �R�@�c�@�@�M�@�� | �����P�V�N�ޏ� |
| ���@�@�@�C�@�M | �����P�T�N�ޏ� |
| ���@��@�@���@�� | �@�@�V |
| �P�g�� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@��@�@���@�� | �����P�Q�N��ƈڏZ �����P�U�E�S���̍ێ��S |
| ���@��@�@�c�ߏ� | �@ |
| ���@��@�@�E�@�L | �ʏ̓�O�Y�Ə̂� |
| ��@��@�@���@�� | ���������s�ɉ���� |
| �ԁ@���@�@���@�q | �@ |
| �V�@��@�@�F�O�Y | �@ |
| ���@��@�@�P��Y | �@ |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| ���@���@�@������ | �@ |
| �A�@���@�@��@�� | ���Ə̂� �����P�S�E�U�E�Q�ޏ� |
�@�����P�Q�N��Q���ڏZ�ҁi�P�S�ˁE�P�g�҂S���j�o�_���ɈڏZ�i���Ə̂��j
| �Ƒ��ږ� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�l |
| ���@�c�@�@�i�@�j | �����P�W�N�ޏ� |
| �g����@�@���@�Y | �@�@�V |
| ���@���@�@���@�� | �@�@�V |
| ���@�@�@�@���@�Y | �����P�T�N�ޏ� |
| �g�@�c�@�@���@�� | �@ |
| �s�@�z�@�@��@�� | �@ |
| ���@��@�@���@�� | �����Q�P�N�ޏ� |
| ���@��@�@�K�@�N | �@ |
| �X�@�@�@�@�x�@�� | �@ |
| ���@���@�@���@�� | �ʏ̏����Y �����P�T�N�ޏ� |
| ���@��@�@�@�@�� | �@ |
| �g�@�c�@�@���@�� | �ʏ̐��� �����P�U�N�ޏ� |
| ���@���@�@�v�@�� | �����P�W�N�ޏ� |
| ���@�V�@�@���@�� | �@�@�V |
| �P�g�� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@���@�@�~�@�Z | �@ |
| �с@���@�@��@�F | �ʏ̊��\�Y |
| ��@��@�@�O�@�� | �����A�蓌���ŕٌ�m �E�Ɨ߂������Ɖ]�� |
| ��@���@�@�ǁ@�� | �_�� |
�@�����P�S�N��R���ڏZ�ҁi�P�S�ˁE�P�g�҂V���j�O��������s��ɈڏZ�i�V�Ə̂��j
| �Ƒ��ږ� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�l |
| ���@�x�@�@���@�� | �����P�V�N�ޏ� |
| �߁@���@�@�`���Y | �����P�W�N�ޏ� |
| ���@�R�@�@�T�@�� | �@ |
| �ҁ@���@�@���@�� | �@ |
| ��@���@�@�@�e | �ΐe�����P�U�N���S �⑰�����P�V�N�ޏ� |
| ��@���@�@�ǁ@�� | �@ |
| ��@�F�@�@�@�@�� | �����P�W�N�ޏ� |
| �R�@���@�@���@�g | �@�@�V |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| �C�@���@�@�V�@�� | �@ |
| ���v�ԁ@�@���@�M | �@ |
| �с@���@�@��@�R | �@ |
| �с@�@�@�@�F�@�� | �@ |
| ���@���@�@�@�@? | �@ |
| �P�g�� | |
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@���@�@�����Y | �����������P�Q�N�ڏZ |
| �@��@�@�L�@�g | �@ |
| �с@�@�@�@�g�@�� | �@ |
| ��@���@�@�@�@�L | �@ |
| ��@�c�@�@�T�@�g | �@ |
| �Ё@�ˁ@�@�[�@�� | �@ |
| ���@��@�@���@�� | ���� |
�����P�T�N�ڏZ�ҁi��ˁE�P�g�҂U���j
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| �s�@���@�@���O�Y | �{�\�w���҂Ƃ��ĉƑ��ږ� |
| �@���@�@�ՎO�Y | �P�g�� |
| �ց@�@�@�@��V�� | �@�V |
| �c�@���@�@��@�g | �@�V |
| ���@���@�@���O�Y | �@�V |
| ���@��@�@���@�� | �@�V |
| �V�@��@�@�쎟�Y | �@�V |
�����P�V�N�ڏZ�ҁi��ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| �Ё@�ˁ@�@���@�� | ����Ɖƕ}�S���A�ψ��Ƃ��ĈڏZ�N��Q�O�O |
| ���@�@�@���@�s | �~�A���͔|���t�Ƃ��ĈڏZ |
�����P�W�N�ڏZ�ҁi��ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@�o�@�@�����q | �ޏ�ҕ⌇�Ƃ��ĈڏZ |
| �{�@���@�@��@�� | �@�V |
�����P�X�N�ڏZ�ҁi�V�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�l |
| �n�@��@�@��@�w | �ޏ�ҕ⌇�Ƃ��ĈڏZ |
| �_�@�ˁ@�@�F�@�g | �@�V |
| �с@�@�@�@���@�Y | �@�V |
| ���@�c�@�@�Ǒ��Y | �@�V |
| �с@�@�@�@���\�� | �@�V |
| ���@���@�@���@�� | �@�V |
| �ā@�c�@�@��@�g | �@�V |
�����Q�P�N��l���ڏZ�ҁi�P�S�ˁj����s��t�߁i��V�Ə̂��j
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�l |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| �с@�@�@�@���@�g | �@ |
| �́@���@�@�⎟�Y | �@ |
| ���@��@�@��@�� | �@ |
| ���@�c�@�@�`�@�� | �@ |
| �F�@�V�@�@���@�� | �����Q�Q�N�ޏ� |
| ���@�c�@�@���@�Z | �@ |
| ���@�c�@�@���@�� | �@ |
| �ׁ@��@�@���\�Y | �@ |
| ���@���@�@�v�O�Y | �@ |
| �v�ۓc�@�@���O�Y | �@ |
| ���@��@�@�x�O�Y | �@ |
| �^�@��@�@���@�G | �@ |
| �|�@���@�@�`�@�� | �@ |
���N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�T�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�l |
| �K�@���@�@���l�Y | �@ |
| �K�@���@�@�Ɂ@�d | �@ |
| ���J��@�@�F���Y | �@ |
| ���@��@�@�v���Y | �@ |
| ���@���@�@�r�@�� | �@ |
�����Q�R�N�ڏZ�ҁi�T�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@��@�@�����Y | ���_����x�z�l�Ƃ��� |
| ��@�c�@�@�y�@�� | �h�̑��֓��A |
| ��@���@�@�v�@�� | �@�@�V |
| ��@�c�@�@�쎟�Y | �@ |
| ��@���@�@���@�� | ��c���ֈڏZ |
���N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�T�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@�]�@�@���@�� | �@ |
| �Ɂ@���@�@�F���q | �@ |
| ��@�@�@�d�@�� | �@ |
| ���c�@�펟���q�� | �@ |
| ���@���@���E�q�� | �@ |
�����Q�S�N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�V�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| ���@���@�@���@�� | �@ |
| ��@���@�@���@�\ | �@ |
| ���J��ɍ��E�q�� | �@ |
| ���@�Y�@�@�ׁ@�� | �@ |
| ���X�@���E�G�� | �@ |
| ���J������E�G�� | �@ |
�����Q�T�N�⌇�ڏZ�ҁi�R�ˁj
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| �́@���@�@�y���Y | �@ |
| �k�@��@�L���q�� | �@ |
| �~�@���@�@���@�� | �@ |
�����Q�T�N�ڏZ��
| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |
| ���@���@�@�L�@�� | ��c���̓���_��p�x���Ƃ��ĈڏZ |
�א��_�@�̋z��
�@�����P�P�N�V���攭���Ƃ��ē��n�����l�X�́A��P�����A�҂̎��ꏀ����i�߂��̂ł��������A���Ƃ�肩���͔_�ƂɊւ��Ēm�����o�����Ȃ��S���̑f�l�ł���A�J��g�̏��シ��m���_�@�i�א��_�@�j�ɂ��āA���ꂩ������Ă������Ƃ������̂ł������B�����P�P�N�Q���J��g�́u���m�_��ݗ^�K���v��݂��A�\�ܒ����ȏ�J�����s���҂ɂ́A���Ɖۗ�������ь��p���k��h�����Ē�����������ĊJ�����������邱�ƂƂ��Ă����B
���[�N�g�p�̍k���@(�ʐ^�Q)

���A�����g�p���ꂽ�v���E�@(�ʐ^�R)
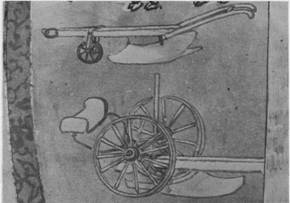
�����������Ƃ���X���J��֔��َx���Z�p����[���Y�ق��R�������S���������A��A�\���L�v���I�i�����j�Ȃǂ̐��m�_��������ĊJ���̎w���ɗ��ꂵ�A�����܂��R���R�O�O�O�قǂ��r�N�������ĈڏZ�҂̎�������������B
�@����������B�̈З͂�������ꂽ�g�c�m�s�́A�������̓������l���A�k���T���w���̕X���v�炢�ɂ��ĊJ��ւɏo�肵���B����ɁA���N�P�P���ɂ͈ڏZ�l�̒�����Ɛg�̎҂S���i����E�L�E���엊���E�s�z�c�ߏ��E��㕶���j�����d���Ǝ�����֔_�ƌ��p���k�Ƃ��Ĕh�����A���n�̎�舵���A���m�_��̎g�p�A�n��̐���Ȃǂɂ��Ď��K������ȂǁA�_�@�̌����ɓw�߂��̂ł���B����ɁA���P�Q�N�Z����܂��āA���k��l�ƍk�n�S���������A��ė������d���Ǝ����ꊩ�Ɖۈ��O�c�ȑ�����A�n���m�_�@��̎�舵�����͂��ߎ�q�̍w���A�k��Ȃǂ̎w�������ق��A�O�N���ꂵ����[����A�w�����o�肵�Ă����k���R���������ė��āA�Ăэr�N�����̉��������Ă����Ƃ����ł������B
�@�J��������ł́A���������J��ւ̉����ɑ������Ď{�݂̏[���ɐϋɓI�Ɏ��g�݁A�k���E�k�n���͂��߁A�e��v���E�⏊�v�̔_�@��̐����ɓw�߁A�_���U���̊�b���ł߂Ă������B
�ƒ{�̓���
�@�א��_�@��i�߂邤���Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ����n�̎���ɐB���ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B�Ȃ��ł������P�S�N�i�P�W�W�P�j�R���ɂ́A�J���n�ɐڑ����Ă���V�y���̒n�P�P������Ċ������L�q���݂��A�܂��A���ْn�������Y�n�R�����w�������ق��A�J��g���d���Ǝ����ꂩ����y���V��������Y�n�P���̑ݗ^���ēy�Y�n�̉��ǂ�}�����B����ɁA�암�n�����玓���P�O�����w�����A���d�����ꂩ���Y���P���̑ݗ^����ȂǁA�ƒ{�̑��B���J���ƕ��s���Đi�߂���悤�z�����ꂽ�B
�@���̔N�W���ɊJ��g�������c���������@���A�J�Ƃ̏���̂��ߗm��Y���P�����������ꂽ���Ƃɂ���i�Ƌ��̎��{�@�^���������ꂽ�B
�@���̂ق��A���N�����ɂ���K�͂Ȗq����Ђ̐ݗ����i�߂��A�g�c�m�s���В��Ƃ����c���q����Ђ�n�݂��A���N��������c�ǂɎ{�݂�݂��ċ��̎��玖�Ƃ��n�߁A�������Ƃ��g�����������B�������A�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�̑�~��Ǝ����s���Ŏ��S���鋍�������o�����ߎ��Ƃ͕�����A���Q�X�N�q����Ђ͉��U���邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A����ƊJ���n�ł͂R�O�N�ɂ��ׂĂ������p���A�����̈ꕔ�𖼌É��Ɉڂ��A���̑�����O�q��Ɉڂ����B
�@�Ȃ��A�����肳���J�i�ނɂ�Ēn�͂�����ɏ��Ղ��Ă����̂ŁA�����P�W�N�i�P�W�W�T�j���߂ăN���o�[�A�`���V�[�Ȃǂ̍�t�����s���A���̌�N�X���ʂ����Ď����̐��Y�𑝂₵�A�Q�O�N�ɂ͐V���䗿�q�ꂩ�玓�n�P�T���A�Y�n�P���A���Q�P�N���������n�R�T���̕����������ĈڏZ�l�ɔz�z���炳���A�Q�������_�Ƃւ̈ڍs����āA�͔�̑��Y�ɂ���Ēn�͂̈ێ�����ɓw�߂�悤�ɂȂ����B
��n�����n �i�ʐ^�P�j
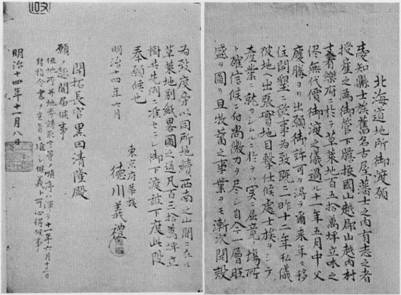
�J�n���̌o�c
�@�攭���n�����l�X���A�F���i���܂����j�����蕥���A��ؗނ��O�����i�ꔽ���͖�P�O�A�[���j����t���������\���Ȑ��ʂ�����ꂸ�A�H�܂��앨�Ƃ��ď����E����ǂ��E���瓤�E�؎�Ȃǂ��܂������S�ł̏ł������Ƃ����B�������A���̋ꂢ�o�������Ĕ_�ƋZ�p�̏K���ɓw�߂����ʁA���E�召���E����E���сE�Ƃ����낱���E���E��Ȃǂɂ킽���č�ځA��t���ʂ�Q�����₵�Ă������B
�@�����̋L�^�����t���ʂ��݂�ƁA�����Q�O�N�̓�O���㔽�Z���A�P�R�N�̋㔪���O���ܐ��A�P�S�N�̘Z�����Z���A�P�T�N�̔��Z���㔽�ܐ��A�P�U�N�̈��Z���ܔ��ꐤ�A�P�V�N�̈�l�꒬���������Ƃ���A���N�ڏZ�҂̑����ƍ�t���ʂ̑����ɂ�Ď��n�����㏸���Ă������B
�@�����P�T�N�����A�J��ڏZ�҂̔_�ƌo�ς̊T�����u�k�C���_�Ɣ��B�j�v�ɂ���Ă݂�ƕʕ\�̂Ƃ���ŁA�o�c���x�͂Ƃ��Ȃ킸�A�ڏZ�l�e�˂��_�ƂƂ��Ď����o�c���m�����邱�Ƃ�����A���̂��߁A����Ƃł͊J����߂̋K��₻�̘g�������ʂ̑ݗ^�ȂǁA������ی��^���Ă����B�������A���A�҂̈ꕔ�ɂ͎m�C�̑ޔp���݂���ł������B
��O�q��i�ʐ^�P�j

�@�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�R������ƊJ��������ł́A���A�ȗ��V�N���o�߂������тɏƂ炵�ď����x�̉��v���s���A��������ɈڏZ�l�Ɉ˗��S���N��������悤�Ȓ��ڕی�̐��x��p�~���A��˓�������̖ʐς�����n���ēƗ����c�̐��_�𑣂����j���Ƃ�ƂƂ��ɁA�Ɨ��̌����݂̂Ȃ��҂ɂ́A�����ė�����x�����Ă܂ł����_��F�߂�Ƃ����[�u���Ƃ����B�����ē���ƊJ����������u����ƊJ���n�v�Ɖ��̂����B����ɂ���āA���̔N���˂̑ޏ�A���҂��o�����Ƃ����B
�����J��҂̔_�ƌo�ϊT���@�i�k�C���_�Ɣ��B�j�h�@���P�T�C�P�W�W�Q�j
| �@�@�@���@�� ���@�� |
�u���v�O�Y | �g�c�@���Y | �R�c�@�M�� | �ɓ��@�M�� | �g�c�@�m�� | �����@�ב� | �����@���� | |
| �� �t �� �� | �� | �@�@�@�� �S�D�O�R |
�@�@�@�Q�D�P�O | �@�@�@�O�D�W�R | �@�@�@�P�D�O�R | �@�@�@�Q�D�U�W | �@�@�@�P�D�X�T | �@�@�@�P�D�S�O |
| �c | �@�@�@�O�D�R�O | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�@ �\ | �@�@�@�@ �\ | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�@�\ | |
| �e�@�@���@�@�� | �@�~ �R�O�Q�D�S�O |
�@�P�W�Q�D�V�T | �@�@�T�R�D�R�S�T | �@�@�V�S�D�P�O | �@�P�V�V�D�P�W | �@�P�Q�R�D�T�V�T | �@�@�T�R�D�T�O | |
| �o�@�@�� | �с@�@�ā@�@�� | �@�@�~ �X�V�D�T�O |
�@�@�V�W�D�O�O | �@�@�V�W�D�O�O | �@�@�V�S�D�V�T | �@�@�X�V�D�W�O | �@�@�X�V�D�W�O | �@�@�T�O�D�O�O |
| �ݖ��E���E�Ζ� | �@�@�@�V�D�R�Q | �@�@�P�W�D�U�S | �@�@�Q�O�D�X�Q�T | �@�@�P�X�D�V�S | �@ | �@�@�P�X�D�T�W�S | �@ | |
| �߁@�@���@�@�� | �@�@�R�T�D�O�O | �@�@�Q�T�D�O�O | �@�@�Q�O�D�O�O | �@�@�R�O�D�O�O | �@ | �@�@�T�O�D�O�O | �@ | |
| ���@�@�o�@�@�� | �@�@�R�U�D�O�O | �@�@�T�O�D�O�O | �@�@�Q�P�D�O�O | �@�@�@�U�D�W�S | �@�P�Q�O�D�O�O | �@�@�R�U�D�O�O | �@�@�S�R�D�O�O | |
| �_�@�@�@�@�@�v | �@�@�S�O�D�O�O | �@�@ | �@�@�P�T�D�O�O | �@�@�R�S�D�W�O | �@�@�S�R�D�U�O | �@�@�P�X�D�T�O | �@�@�P�Q�D�O�O | |
| �v | �@�Q�P�T�D�W�Q | �@�P�V�P�D�U�S | �@�P�T�T�D�S�Q�T | �@�P�T�U�D�P�R | �@�Q�U�P�D�S�O | �@�Q�Q�Q�D�W�W�S | �@�P�O�S�D�O�O | |
| ���@���@���@�� | �@�@�W�V�D�Q�W | �@�@�P�P�D�P�P | �@���P�O�Q�D�O�W | �@���@�W�O�D�P�R | �@���@�W�S�D�R�O | �@���@�X�X�D�R�O�X | �@���@�T�O�D�O�T | |
�J��n�i�ʐ^�Q�j

�@�������A���̐��x�̎��{�ɂƂ��Ȃ��Ĕ_�ƌo�c�����肳����{�݂ɂ��ẮA�t�ɐϋɓI�ȕ��Ƃ�ꂽ�B���Ȃ킿�A�������Ђ̐ݗ��i���A�{���X�Ǖt�߁j�A���r���~���x�̎��{�A�֍�E�q�{�̏���Ȃǂ���Ȃ��̂ŁA���ɗ֍�⏕�K����݂��āA�唞�E�哤�E����Ȃǂ̗֍�����サ�A�n�͂̈ێ����i�A���D�_�Ƃ̖h�~�ɓw�߂��̂ł���B���̂悤�ɁA���ړI�ȉ����̔p�~�ɂ�����炸�A���̒n�Ɏc�����ڏZ�҂����́A�����o�c�̈ӗ~������ɂȂ�A����Ȍ�A��t���ʂ���ю��n���͔���I�ɑ������A��ɎY�n�̐U���ɂ���Ėq���E���Ȃǂ̎����앨�͋}���ɑ����A�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�ɂ͑���t�ʐς̂S�������߂�Ɏ������B
���Ƃ̏���
�@�_�Պ��̕��ƂƂ��ĘV�c�w���q�ɂ�鐻�ԁE�����Ȃǂ����コ�ꂽ�B���Ԃ͖����P�P�N���A���X�̂P�P���A���َx�����狳�t�P���������A�����ԏ���݂��ĈڏZ�l�ɑ��Ă��̕��@���C�������A������p�����čs�킹���̂ŁA�P�T�N�ɂ͓�Z�ܘZ�ԁi��Ԃ͖�P�E�W���[�g���j������Ɏ��������A����_�Ƃ��ĈȌ�}���Ɍ������A�P�W�N�ɂ͑S���s���Ȃ��Ȃ����B
�@�����������P�Q�N�ɋ��t�������Đ������@���K���A�P�T�N�ɂ͎O�O��сi��т͂R�E�V�T�L���O�����j�̐��Y���グ�����̂́A����܂��}���ɐ������A���ԂƓ��l�A�P�W�N�Ȍ�͔p�Ƃ���Ă��܂����B
�@�܂��A���A�n�т͎R�K�ɂ��b�܂�Ă����̂ŁA�{�\����������A�����P�Q�N�ɂ͎펆�Q�����̑|�����s��ꂽ���A�o�����Ȃ��������߂킸����Δ��l�㏡�i��͖�O�E�P�W�������[�g���j�̎������ɂ����Ȃ������B���̌�K�c��A���t���A���̐����ƂƂ��Ɏ����ʂ��Q���������A�P�V�N�ɂ͎펆�R�����A�����ʎO�ΎO�l�܍��ŁA�傫�Ȕ��W���݂�Ɏ���Ȃ������B
�@���ƂƂ��ĉi���������̂ɗ{�{������B�����̗{�{�͌o�ϓI�Ȗʂ������łȂ��A�ڏZ���̑����������ő����̌o�������蒼���Ɏ��s�ł��鎩�M�������Ă����̂ŁA�N�X�̗��E����{�Ƃ��������Ĕ̔��܂��͎��Ɨp�Ƃ����ƂƂ��ɁA�{�ӂ�̔엿�������コ�ꕁ�y���W�����̂ł���B
�@�Ȃ��A�����P�V�N�Ɉ��m�����n�̐l���؎��s�����t�Ƃ��Đ����̋Ƃ��N�����A�܂��A�����P�T�N�ɂ͒ґ��������ł�Ղ��@�B���w�����Ăꂢ����ł�Ղ�̐����ɒ��肵�����̂́A�����s���ȂǂŒ��~�̂�ނȂ��Ɏ������B�܂��P�V�N�ɂ͓���ƊJ��������ɂ����Ă��p�c�O�Ƃ��S�����āA�ł�Ղ����s�������A�������@���c�t�ł��邤���ɔ̘H�������Ƃ������Ƃ������āA�����ƂƂ��Ɏ����̈��E���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�h�̑��E��c���k��
�@���d���Ǝ�����Ŕ_�ƋZ�p���C�����ċA�����Ɛg�N�𒆐S�Ƃ��āA�ڏZ�l�̎q���P�g�̈ڏZ�҂������A�����P�S�N�P�P���J��������̎������ɏ������A���n�̎��{�Ɣ_�@��̊Ǘ��ɓ�����Ɛg�ɂ��g�D���ꂽ�B�����Ɛg�ɂ̐N�́A��^�̐��m�_�@��������Ċe�ڏZ�_�Ƃ̉����ɕ������Ƃ���Ȏd���ŁA�u��B���v�Ə̂����B��������ɂ�������Ȃ������́A���P�T�N�R�����悻�P�O���ŗ���ɋ����o�c�_���n�݂��A�u�h�̑��k�Ɂv�Ɩ��t�����B
�@�����́A���m�_�@����g�p���A�ŐV�̒m�����X���ĊJ���ɒ��肵�A�܂��A�k�n��k���̖q���݂���ȂǁA�悭�������B�������A�P�X�N�i�P�W�W�U�j�P���k�ɂ͉Ђ��N�����A�X���V�~�V���i�E���@�j���̑���Ȕ_�@���S�Ă��Ă��܂��Ƃ����Ж�Ɍ�����ꂽ�����A�n�͂̌��ނȂǂ��������̂ŁA���̋����o�c�����Ɍ�������A�Q�O�N�H�������čk�ɂ����U�A�������Čl�o�c�Ƃ����B
�@�܂��A�����P�U�N�J�i�Ђ���������c�ǒn�т̊J���ɂ��h�̑��k�ɂɌ��킢�A���P�V�N�ڏZ�l�̎q���S�A�T�����c�����Ė�c���k�ɂ�g�D�������A����͑O�҂̂悤�Ȋ������݂�ꂸ�A�Ԃ��Ȃ����U�����B
�h�̑��k�Ɂi�ʐ^�P�j

�c�N�ɁE�N��
�@�����P�W�N�R���A����ƊJ��������ł͏����x�̉��v���s���A�Ɨ����c�̐��_�𑣂��ƂƂ��ɁA�u����ƊJ���n�v�Ɖ��߂����Ƃ͊��ɏq�ׂ����A�����������v�Ɠ����Ɉψ��Ћˏ���́A����̔_�Ƃ̒S����Ƃ��ėc�N�҂����߂邱�Ƃ��l���A�m���̎q��Ő����N�P�Q����P�U�̎҂��W���A���e���痣���ĈڏZ�����邱�ƂƂ��A���P�X�N����R���N�ɂQ�S����c�N�ɂɎ��e�����B�����̂����A�܂��w�Z����̏I����Ă��Ȃ��҂͊w�Z�ɒʂ킹�A�]�ɂɔ_�Ƃ̎�`���ɍs�������莖�����̋��n�����炳���A�܂��A�w�Z����̏I����Ă���҂͖�c���q���ɂ�k�ɂ֔h�������肵���B�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�ɂ͐N�ɂƉ��̂��Ęh�̑��ֈړ]���A�S������̏I�����܂��ĊJ���ɐ�O�������Ƃ����B����ɁA���̒����珫���̎w���҂�{�����邽�߁A�J���n�̔�p����w����o���ĎD�y�_�w�Z�_�|�`�K�ȁi��̖k�C����w�j�֗V�w�������B�܂��A���̐N�������Q�O�ɂȂ����Ƃ��ɏ\�����i�꒬�͖�P�w�N�^�[���j���̓y�n��^���A�h�̑��Ŏ����o�c�������肵���̂ŁA�̂��ɔ��_�̒����I�Ȗ������ʂ������l���𑽂��y�o�����B���������̔��ʁA�J��ɑς����˂Ē��r�ŒE�����A�A������҂����������Ƃ����B
�@���Ȃ݂ɂ��̗c�N�ɂ���o�Ċ����l�X�ɁA����_�꒷�̑哇�b�A�����̓��c���O�Y�A�����̏��쉳���A�{�{�Ƃ̔����g�V���A�哇�f���A�o�^�[���̔����ҍ匴���Ȃǂ��������B
�@�����P�X�N����Q�P�N�܂ł̗c�N�ɐ��͎��\�̂Ƃ���ł���B
�c�N�ɐ��i�����Q�R�N�N�ɂƉ��́j
| �����P�X�N | �X�� | �����Q�O�N | �W�� | �����Q�P�N | �V�� | |||
| �� ���@ �@�@�b | �� | �� | �ԁ@�с@ �ܘY�g | �� | ���@��@ �� �� | �� | �� | |
| �� ���@ �g�V�� | �� | �� | ���@�@ �� �s | �� | ��@���@ �f�@�� | �� | �� | |
| �t �@�@ �h�@�g | �@ | �@ | �`�@�@�@ ���V�� | �� | �ԁ@�с@ ���@�� | �� | �@ | |
| ���@�_�@ �v�@�l | �� | �@ | ��@��@ �Y�o�g | �� | �@ | ���@��@ ��@�g | �@ | �@ |
| �|�@�z�@ �x�@�� | �@ | �@ | ��@�ԁ@ ��@�g | �� | �� | ��@���@ ���@�� | �� | �� |
| ���@�@ ���O�Y | �� | �� | �l�@���@ �ǁ@�� | �� | �@ | ��@���@ ���@�L | �� | �� |
| �A�@���@ �~ �Y | �@ | �@ | �X�@��@ �ҁ@�` | �� | �@ | �ׁ@��@ ���@�� | �@ | �@ |
| ���@��@ �����Y | �� | �@ | ���@���@ �Y�@�� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| �X�@�{�@ �鎟�Y | �� | �@ | ��Ɏɐ��ɂȂ����l ���@�c�@ ���O�Y |
�@ | �� | ��Ɏɐ��ɂȂ����l �� �ˁ@ �����q�� |
�� | �@ |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ��Ɏɐ��ɂȂ����l �[�@��@ ���@�� |
�� | �@ |
���@ ����@�吳�P�P�N�܂ł����l
�@�@�@����@�����Q�R�N�h�̑��ֈړ]�A�N�ɂƉ��̂܂ł����l
�@�@�@����@�r���ޏꂵ���l
�����n��ւ̓��A
�@�����P�X�N�i�P�W�W�U�j�U���t�ߑ�\�Z���Ō��z���ꂽ�u�k�C���y�n�����K���v�ɂ��A����`��͗�������c�ǂ���ё�̏�ɁA�Q�O�N�P�O���q��R�U���X�U�T�T���̑݉����������A���̂�����c�ǒn��ւQ�T�N�T���Ɏ��̂Q�S�˂�����Ƃ��ē��A�������B
�@�T��@�h�O�Y�@�с@���O�Y�@���J��@�ыg�@����@�P�O�Y�@�͌��@�F��@�X�{�@���l�Y�@���J��@�ċg�@�J���@�~���Y�@�����@�~���Y�@���J��@�����Y�@�͍��@�`�O�Y�@�~���@�e���Y�@�����@�㎟�Y�@���Y�@�]���@���Y�@�����Y�@���Y�@���E�G��@���Y�@�����@���Y�@�����@�i��@���l�Y�@�i��@�����q�@��c�@�����@��c�@�Ջg�@���J��@�o���@���Y�@�r���q
�@�����̓��A�҂́A�n�q��E�����|�������^����A���n�܂ł̐H�Ƃ�_�@��E��q�݂̑��t�����Ȃ��ꂽ�B
�@�܂��A�V�y���ɓ��A�����s�����O�Y�͗{�\���D�݁A��c�ǂ̑ޏ�҂̕⌇�Ƃ��ē��ʈڏZ���A�X�т̒��ɋ����\���Ď\�����������̂�A���D���܂Ő������B��Ɏ��͂ɂ͂R�O�˂قǂ����A���A���̕t�߂�_��̒��̖�c�ǔ_�ꒆ�A�����s���i�s�����~�j�ƌĂ��悤�ɂȂ�A��N���̕������g�s���h�Ə̂����悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@����Ƃ͕ʂɗ����n��ɂ��Q�T�N���玩��ږ��Ƃ��Ĉ��m��������A���A����E�l���E���ÁE��m��Ȃǂ̊J���ɏ]�������B�����u�L���O�N�v�Ə̂��A�R�N�Ԃ͎ؒn�����Ə�����A���̌�̏��엿�͔�������Q�T�K���炢�ł������B
�@�������ė����n��ɂ�����_�Ƃ��A�ڏZ�҂̊J���ɂ��Q���{�i�����A�Q�W�N�i�P�W�X�W�j�ɂ͔��n�L�Ŕ��꒬���A���ňꔪ�Z�����A����T�T�O�l�A����U�O�l�ƂȂ����B
�@���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�X���ɂ́A�䗿�n���O�Z�Z����������_�n�݂ƂȂ�A�S�N��c���̏���Îs���畨�Вn������̔_�n�����ĂQ�P�˂̎���_���ł����B���̂Ƃ���l�ɑ���ݕt���́A�ō��Q�R�P�U�~�A�Œ�S�O�O�~�ł������B
�@�X�N�X���ɓ���_��̏���n���������A��c�ǁi�s���n��j�Q�X�ˁA�ʐϓ��O���ꔽ�ꐤ��\���A���ϔ����R�R�~�Q�T�K�A���v�V���R�X�Q�P�~�U�O�K�A������n��U�ˁA�l�꒬���A���ϔ����P�V�~�A���v�U�W�O�O�~�ł������B
����_��̕�
�@�����P�P�N�V������ƊJ��������̑n�݈ȗ��A�W�N�ڂ��}�����P�W�N�Q���A�悤�₭�J��̐��ʂ��グ����Ƃ͂����A���̂قƂ�ǂ�����Ƃ̎�����ی�ɂ��h�����Čo�c���ێ�����ɂ������A���̂܂ܕ��u����Ƃ��́A�o�ϓI���W�͂��납�A�_�ƂƂ��Ď���Ɨ��̂ł���ł͂Ȃ������B���̂��߁A����܂ł̏����x�̉��v��f�s���A���̖��̂��u����ƊJ���n�v�Ɖ��߁A�P�W�N�x����������Ē��ڂ̕ی��^���Ȃ����j���Ƃ邱�ƂƂ����̂ł���B
�@���Ȃ킿�A�P�W�N�x�Ɍ���l���ݗ^�ĂƂ���E�唞�E�哤�E���̎l��ɂ��ẮA��t���ꔽ���ɂ��P�~����⏕���邱�ƂƂ������A����Ȍ�͈�̒��ڕ⏕��ł���A�Ɨ����c�𑣂����Ƃɂ����̂ł���B�������ĈڏZ�l�̒��ł��̈ӂ�̂��Č��n�ɂƂǂ܂�҂ɂ͐����Ɍ����������Ē�o�����A�O�r�ɐ��Ƃ̌����݂��Ȃ��A������]����҂ɂ͗����ݗ^���邱�ƂƂ����B���̌��ʁA�R���ȍ~�W�˂̑ޏ�A���҂��o�����Ƃ����B�c���҂ɑ��Ă͈꒩�L���ɔ����āA�˂��Ƃɑ唞��U�A�ꂢ�����U�i�ꂢ����ɂ��Ă͈�U�P�T�K�̊����Ō����Ɋ�����j��ςݗ��Ă����邱�Ƃɂ����B
�@����ɁA�����Q�P�N�i�P�W�W�W�j�X���J���n��������p�~���A����ɑウ�āu�J���n��v��u���A��̎����͂��ׂđ���ɈϏ����邱�ƂƂ��āA���̑��ē��R��ڈψ��Ћˏ���ɈϔC�����B���̂����A����܂ł̐A�����x��p�~���A���쐧�x�Ƃ��Ă��̒n���ێ����邽�߈ڏZ����͋��c���d�ˁA����l�̋������邢�͊J���n�̎����@�Ƃ������ׂ��u���_������J���n����v�i�s���ҎQ�Ɓj���߁A�����Q�Q�N�V���P������`��㗝�E�ƗߊC���V���i�Q��ڊJ���n�ψ��j�A���������C��Q��̂��Ƃɔ��_�_�Ђɂ����ċ��z�����s���A���悢�擿��Ƃ̕ی�𗣂�A����l�Ƃ��Ď��厩�c�ɓ����b�����ꂽ�̂ł���B
�@�J����Ɋւ��铿��Ƃ̎x�o�́A�����Q�T�N�i�P�W�X�Q�j����őS����߂邱�ƂɂȂ������A���N���ɂ�����J���n�̈ڏZ�l�ː��U�W�ˁA�l���U�O�Q�l�A��t���ʎl�ܔ������]�ł���A�n�ƈȗ��x�o�����o��̑��z�͂P�U���R�Q�W�W�~�]�ł������Ƃ����B
�@�������ē���ƊJ���n�́A�m���A�Y�̂��߂̌o�c������ꉞ�I�����A��ʏ���҂��W���A�����Ȃ���A�L�����_�����W�ɏd��Ȗ������ʂ��������A�����S�R�N�i�P�X�P�O�j�ɂ͔_����ː��R�P�X�ˁA�P�T�R�P�l�ɒB���A���̐����n�ς͎��ɓ�O���ܒ����]���߂�Ɏ����Ă����B����Ƃł́A���ˎm�炪�悤�₭����_�Ƃ��ēƗ��ł���ɂȂ������Ƃ�F�߁A�ڏZ�l�V�T�˂ɑ����O���㔽�]�i��˓����蕽�ψ���]�j�̕����������n�����߁A�S�T�N�y�n���L���̈ړ]�o�L�����������̂ŁA���悢�掩��_�Ƃ��ēƗ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@����ƊJ���n�͖����S�T�N�R���Ɂu����_��v�Ɖ��̂��A���̑��̏���l�Ƃ̊W��ۂ��o�c�𑱂������A���̔_�n����ɂ���ď��a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�P�O���P�T���ɗR������W�D�͔[�߂�ꂽ���A�n�݈ȗ��V�O�N�ɂ킽�蔪�_���ɂ�����Y�ƁA�����E����e�ʂ̐U���Ɋ�^�������т́A���M���ė]�肠����̂�����B
�@��R�߁@�_�ꋻ������
�@���_�̊J���͋������ˎm�̑g�D�I�W�c�ڏZ�ɂ���đn�n����A�������A��ɒ��j�I�Ȗ������߂Ă����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����A�����A�����̐i�߂�J������ɂ��A���Ó��i���A�l���j�̒|���_��A�R��̐ΐ�_��A�㍻�����i���A�t���j�̗�ؔ_��A����̓���_��A�㔪�_�̑�֔_��ȂǁA�召�������̔_���q�ꂪ�������őn�݂���A�_���Ƃ��Ă̔��_���J������Ă������̂ł���B
�@�����̂����A��Ȃ��̂������Ă݂�Ǝ��̂Ƃ���ł���B
�ΐ�_��
�@�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�������C���S�I�]���̊I�]�j�Y���A�R��n��Ɉ�Z�Z�Z�]�����̕��������ĊJ���ɒ��肵�u�I�]�J���n�v���J�݂������A���R�P�N���m�������S���⑺�̐ΐ�ш�Y�����������āu�ΐ�_��v�Ɖ��߁A����o�c�@�ɂ������p�����B�_��̋K�͂Ƃ��ẮA����O�Z�����A�q���n�O�Z�����A�A���n��Z�����]�A���Z�n��܁Z�����A�R�јZ���㒬���ŁA����l�S�U�˂����ĊJ�����s�����B
�@�o�c�ɂ������Ă͖q�{�v�z�y���āA�����闪�D�I�_�ƌo�c���獇���I�_�ƌo�c�ɓ]�������邱�Ƃɓw�߂��B����ɁA�����R�T�N����ƒ{������}���Ėq������c���A���̔N�A�����J����D�G��Y�n�P���Ǝ펓�n�P�����w�����Ĕn�C�̔ɐB�ɓw�߂����߁A�R�V�N�x�̎�t�Y�n���P�Q���A���Y�X���ɑ��A�S�Q�N�ɂ͎�t���n���U�X���A���Y�U�X���Ƒ������A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�̔_�ꏊ�L�n�͎�Y�n�R���A�����Y�m�펓�n�U���A���B�Y�m�펓�n�X���𐔂���Ɏ������B
�@�܂��A�{���ɂ����Ă������R�X�N�C�M���X����D�ǎ������Q���A�S�S�N�ɂ͓������C�M���X�����Y���P�������ꂼ��A�����Ċ�b���̔ɐB�ɓw�߂��B����ɂ���āA�S�O�N�ɂ͎�t�����P�T���A���Y�P�P���ł������̂ɑ��A�吳�T�N�ɂ͎�t�����R�S���A���Y�R�S���ɒB����ł���A�_��̏��L���Ƃ��Ă��吳�Q�N�̎��_�ŃG�A�[�V���[���Y���W���Ǝ펓���U�O���A���G�펓���P�V���𐔂���Ƃ������W�Ԃ�ł������B
�@�������ėD�Nj��n�̔ɐB�ɓw�߂����ʁA�����R�X�N�̖k�C�����Y���i��A���邢�͂S�R�N�̑�P�ً�O�W�S�{�����i��A���̑����X�̋��i��ɂ����ėD�G�Ȑ��т����߁A���̐��ʂ�������Ȃ����������B
�@����Ɏ��琻�����݂��A�����S�O�N�������O�Γ�l�O���������ăo�^�[�ܓ�܋ҁi��҂͂U�O�O�O�����j�������̂��͂��߁A�N�X���Y��L���đ吳���N�i�P�X�P�Q�j�ɂ͌܌܁Z�Z�҂��A�u����o�^�[�v�Ɩ��t���āA�k�͊����A��͐_�˂܂ł��̘̔H���g�������̂ł������B
�@�����S�S�N�W���吳�V�c�����{�ɂ���A�{���s�[�̍ہA���̍���o�^�[���k�C���{���n�g���A�������悳��A�������グ�̌��h�ɗ������̂ł������B
�@���̂悤�ɖq�{�̐U���ɗ͂𒍂����ق��A��ɏ���l�ɂ��A�т�_�k�����サ���̂ŁA�吳�Q�N�x�ɂ͔������A�q���n�Z�������A���q�n�O�܁Z�����Ƃ����_�p�n���J������A����҂��P�O�O�˂𐔂���Ɏ��������A���a�U�N����тP�O�N�̂Q�x�ɂ킽��k�C�����L�����n�J�������ݕt�K���ɂ���Ď���_�n�݂̓����J�����ƁA���������_�n��������Ď���_��n�݂��A�_���������̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ȗD�ꂽ�_��o�c�ƁA�R�z�S�Y���n�{�Y�g�����Ƃ��Ē{�Y�Ƃ̔��W�ɐs�������_���ΐ�ш�Y�́A�吳�P�O�N�P�O���A�����{�Y���\�����A���J�͂�����ꂽ�B
��ցi��������j�_��
�@�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j���̐l���J��Ў��Y�E��㓿���q�E���ւ̈���쎟�Y�E���d�g�̂S�l���A�k�C���̑�B���Ƃ��u���A�����[���b�v�Ǝ��g�����׃c�i���A�㔪�_�ƕx��̈ꕔ�j�ɂ܂�����n���I�肵�A��Z�l�㔽���݂̑��t�����A�ږ������āu��֔_��v��n�݂����B
�@�_��ł͈ږ��̈��Z�Ɉӂ�p���A�Ў������āA�w�Z��a�@��ݗ������B����ɁA���_�s�X�n�Ɂu��֏��X�v��݂��āA���������̎d���ꋟ����Y���̏W�ה̔��Ȃǂɓw�߂Ĕ_��o�c�̈����}�����̂ŁA�������͂P�Q�O�˂̏���_�𐔂���܂łɂȂ����B�������A���̔_�����O�ł͂Ȃ��A��P�����E����̕s���̂�������ė��_�҂����o�������߁A�_��o�c�͋}���Ɉ������A�吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j�ɓ���Ƃɏ��n����āu���[���b�v�_��v�Ƃ��čĊJ����邱�ƂƂȂ����B
�@���a�X�N�i�P�X�R�S�j��哿��`�e�́A�_�ꒆ�Z�O�㔽��������A���L�����n�J�������ɂ���ĂR�W�˂̎���_��n�݁A���[���b�v�_���������B
��ؔ_��
�@�����Q�X�N�i�P�W�X�U�j�����̗�؋`�@�E����莟�Y�E��t���̔��R�������A�㍻�����i���A�t���j�n���ɊJ���K�n��O�㎵�����A���̑���O�㒬���A�v��O�Z�����݂̑��t�����āu���_�_��v�i�̂��ɗ�ؔ_��ɉ��߂�j��n�݂��A���m���ƕ��䌧���珬��l�P�R�˂���A�������̂Ɏn�܂�B���̌�A���N�ږ����W���吳�V�A�W�N����ɂ͂P�Q�O�˂قǂ𐔂���܂łɂȂ������A���̒���ɖK�ꂽ�_�����Q�ɂ��_�ƌː��͋}���Ɍ������Ă������B���̌��ʁA�㍻�����A���V�A������i����������A�t���j�Ȃǂ̂S�O���˂������Ă��̌o�c�͌p�����ꂽ���A���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�V���A�_�n�����@�ɂ�蔨���ܒ����A�̑��n���꒬���A���v�l��Z���������ɔ�������A�S�O�˂̎���_���n�݂���Ĕ_�������B
�v���Ĕ_��
�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�X���������v���Ă̐l����L�ƕ��������όS���v�c���̐�����v�i��L�̋`���j�E��؎��E�ē���Ղ̂S�����A���u�C�^�E�V�i�C�n���i���A�ԉY�j�Ɋ��L�����n�܁Z�Z�����݂̑��t�����u�k�C���v���ĐB���g���_��v�i��ʂɇ��v���Ĕ_�ꇁ�ƌĂԁj���J�݂��A���R�P�N�R�����������珬��l�Q�Q�ˁA�U�O�]�����ڏZ�������̂��n�܂�ł���B
�@���̔_��n���͓D�Y���n�т������A�ǍD�ȏ����ɂ���Ƃ͂����Ȃ����̂ł��������A�R�V�N�ɂ͍����n��Z�ܒ����A����l�V�U�ˁi��抄�͂P�ˈ�Z�Z�Ԏl���ňꖜ���W���j�𐔂���Ɏ������B
�@���������̔_��́A�����S�Q�N�i�P�X�O�X�j�R���_�ސ쌧���S�䒬�̐l���c���O�̏��L�Ɉڂ�u���c�_��v�Ə̂���邱�ƂɂȂ����B���c�_��͂���ɎR�ь܁Z�Z�����̕����������Ĕ_��ɕғ����A���O�Z�Z�����A�q���n�ܒ����A���q�n�ꔪ�O�����A���H����ƍ��킹�Ĉ�Z�Z�Z�����̔_��o�c�Ƃ������A�܁Z�Z�����̎R�т͔_�꒼�c�Ƃ��A���͏���l�i�����S�T�ˁj�̐d�i����j�Y�p�Ƃ��ĕ����������A�c�_�̉����Ɍ�����ꂽ�B
�@���c�_��͐Έ�{���Y���Ǘ��l�Ƃ��đ�P�����E���ɂ��D������ƁA���̒���ɖK�ꂽ�s�i�C����Ȃǂ��o�����o�c�𑱂����̂ł��������A�_��剪�c���O�͌o�Ϗ�̎���珺�a�S�N���ق̐l�ߓ������Y�ق��P���ɏ��n�A����ɋߓ����珺�a�T�N�i�P�X�R�O�j�R���A�X���O�ˌS�܌˒��̍��������Ɉڏ����u�����_��v�Ə̂���邱�ƂƂȂ����B
�@�����_��ł͈ɓ��F���Y���Ǘ��l�ɒ�߂Ď��Ƃɒ��肵�A���Ɏl�A�ܒ����̑��c���Ƃ��s����������Ɏ��s�A���肩��̌o�ώ�����������Čo�c���������A���a�X�N�P�Q���X�s�厚�����̐X�M��������Ђɋ����̂����ڊǂ��ꂽ���A�P�U�N�P���ɂ͂���ɔ��؊��s�̏��L�Ɉڂ�u���ؔ_��v�Ƃ��Čo�c���i�߂�ꂽ�B
�@�������āA���т��т̌o�c��̕ύX�ɂ�菬�쑈�c���₦�Ȃ��������A���ɔ��؊��s�͂P�U�N�P�Q���A����l�ɑ��ď���_��̉�����ʒm�������߁A�{�i�I�ȏ��쑈�c�ɔ��W�����B���P�V�N�S����P��̒���ٔ����牄�X�U���N�A�P�U��ɋy�ԐR���̌��ʁA�Q�P�N�S���Ɋe�˂̏���n�͏]���ǂ���ƌ��肳�ꂽ�̂ł������B
�@���a�Q�P�N�P�O���u����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�v���{�s���ꂽ���Ƃɂ��A���ؔ_��ɂ��Ă����Q�Q�N�R������_�n�̔������s���A�Q�T�N�P�Q���܂ł̊Ԃɔ�������A�̑��n���������A�v�O��Z�������R�V�˂̔_�Ƃɔ���n����A����_���n�݂��ꂽ�̂ł���B�@�������āA�v���ĐB���g���_���\���c�_���\�����_���\�X�M����������\���ؔ_��ƕϑJ���Ă����̂ł��邪�A���̊Ԃɂ����鏬��_��A����K��ɂ��ĎQ�l�܂łɈꕔ�L�ڂ���Ǝ��̂Ƃ���ł���B
�@�k�C���v���ĐB���g���_��K��
�@���H�@�{�g���j���X���_�U���R�z�S���_���m�y�n�n�v���ĐB���g���_��m�̃V�{�K���j��������Z�V�������m�g�X��
�@�����@�{�g���_��m�y�n�n����l��˃j�t�ꖜ���W���g�V�b�����j���`�ݕt�X�����m�g�X��
�@��O���@�{�g���_��m����l�^�����g�~�X�����m�n���m�����j�˂�ːЎʋg���Y�֓y�n�ݕt�菑���_�ꎖ�����j���o�X�x�V
�@�y�n�ݕt��
�@���V�M�g���_��K��������d���ʎ��������x���m�ʖ����፤���d���b����m�y�n��ݕt�퐬���x�ːЎʏ����Y�֍��i�����
�@�N����
�@�ݐВn���y���Z��
�@��l�@�����@��
�@�ݐВn���y���Z��
�@�ۏؐl�@�����@��
�v���ĐB���g���䒆
�@�������x��
�@�_�U���R�z�S���_���v���ĐB���g���_��m����
�@�ꖢ�J�n�ꖜ�@�ݕt��n��
�@��
�@�ꉽ�@�������N�������j����
�@�ꉽ�@�������N�������j����
�@�ꉽ�@�������N�������j����
�@�ꉽ�@�������N�������j����
�@�Y
�@�E�V�ʖ����፤���d�����߃n��ݕt�n�S�������퐬��g���փJ�ًc��������
�@�N����
�@��l�@�����@��
�@�ۏؐl�@�����@��
�@�v���ĐB���g���䒆
�@��l���@�{�g���n�����l�j�V�m���i�����m�g�F�����g�L�n��\�Z���m�_����n�V���n�{�_��O���_�׃X�R�g�A���׃V
�@����@�{�g���_��m����l�n�ڏZ����J����y�r�����|���j�W������n���كg�X
�@��Z���@�{�g���_��m�y�n�n�ݕt�������l�P�N�Ԉȓ��g�V���������U�����̃m�O�����Z�T�����m�g�X
�@�掵���@�{�g���_��m�ݕt�n�n���N���V�^�������z���ؐ��������V��V�������z���n�ϐ����Z�T���g�L�n�ݕt�n�S�����Ԋ҃Z�V�������m�g�X�A���ꍇ�j���e�������n�y�����|���j�v�Z�V��p�����Z���R�g�����X
�@�攪�H�@�{�g���n�{�g���_��m����l�j�V�e���ؒn����Z���m�N�����j�����Z�V���m�j�b��m�y�n�n�������n����������m�y�n�n�꒬���m�n�σ����^�X�����m�g�X�ރ����^�X���n�σm���n�{�g���m�w��j�]�t�׃V
�@���H�@�{�g���_��m����l�n�ڏZ�ܔN�ڃ������^�n�����L���N�\�ꌎ�O�\���������j�t�����m���엿���[�t�X�x�V
�@��\���@�{�g���_����m���H�y�r���a�m�J�݃n�������j�������m���{�g���m���S�g�V���x���j�����m������l�m���S�g�X
�@��\����@�{�g���_��ݕt�n���m���n�{�g���m���������X�V�e���j���̃V���n���p�X���R�g�����Y
�@��\����@�{�g���_��m�ݕt�n�n�ꏊ�m�s���j�˃����h���n�d�Y�p�n�g�V�e�ݕt�n�σm�\���m��ȓ������J�m�}�}���u�Z�V�����R�g�A���׃V
�@��\�O���@�g�����n�����p�m�׃��K�v�A���ꍇ�n�ݕt���m�y�n�g�]�w�g���Ԋ҃Z�V�������m�g�X
�A���ꍇ�j���e�Ɖ��拎�����m��p�n�������n�N�Ǝ҃������n�L���z�m�O����l�m���S�g�X
�@��\�l���@����l���j�ޓ]��N�n�����m���̃j�e���쌠�����l�j�������^�Z���g�X���g�L�n�K�X�{�g���m��������N�׃V��V���葱�j�w�L���s�V�^���҃n�����i�L�҃g�X
�@��\���@�{�g���j���e����l�j���^�X�������n�y�d�Y�p�n�n�{���ƌ����m�N�i���`�����O�\���N�j�j���L�����^�m�葱�����s�X�����m�g�X
�@��\�Z���@�{�g���n�{�g���_��m����l�j�V�g�������y�r�x�z�l�m���A���{�g���_��K���ꕔ���Вu�V�ȃe����_��m�g�X�x�V
�@��\�����@�{�g���_��m����l�n�Ό����~���|�g�V���ʓ�n�������T�Y��V�̃i�N��H���������j�V���������̖ʃ��Q�X�����m�g�F�����Ѓn�ޏꃒ���Y���R�g�A���׃V
�@�v���ĐB���g���_��
�@�g���@������v�@��
�@�����O�\��N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����@����L
�@�x�z�l
�@�i�u�ԉY���y�j�v���j
���c�q��
�@�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�D�y�̖{�c�������v���Ĕ_��̗אڒn�ɁA���Z�ܒ����A�q��܁Z�����A�R�є��Z�����Ȃǂ݂̑��t�����A�S�Q�N�V�������������ĕt�^���ꂽ���ƁA�����̐��c���Ɉڂ�u���c�q��v�ƂȂ�A��Ƃ��ċ{�錧���珬��l�����ĊJ�������ʂ��グ���B
�@���̌�A�吳���N�i�P�X�P�Q�j�P���Ǘ��l�̓n�ӕl���Y���ꊇ�������A����ɁA�T�N�ɉv�������̏��L�ƂȂ�u�v���q��v�Ɖ��̂��ď���o�c�𑱂������A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�X������l�̗v�]�����A�_�n���v�ɐ旧���čk��҂U���ɑS�n�����Ėq�������B
�{���_��
�@�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�V���D�y��̋{����O��������i���A�l���O��j�ŁA�����Z�����A���̑��O�O�������݂̑��t�����A���m�E�V���E�ΐ쌧�Ȃǂ��珬��l���ڏZ�����ď���o�c���s�����B�_��͑吳���N�̒��ׂłQ�W�˂̏���l�𐔂���Ɏ��������A�R�x�ɘA�Ȃ�u�˒n�тŕ\�y�̗������������Ƃ����������������Čo�c�s�U�ƂȂ�A���a�P�X�N�ɑS�n���̕���K�O�Y�ɏ��n���Ĕ_��o�c������B
�@��ケ�̒n�ً͋}�J��n�Ƃ��āA�����n���꒬�ܔ����]�����������ƂƂ��ɁA��O�꒬���̔�����������A�Q�˂̍k��҂ɔ���n���ꂽ�ق��A�q��Ƃ��Ďl�㒬�l�������R�z�q��g���ɔ���n���ꂽ�B
��֔_��
�@�����R�U�N�������̋g�c��V���E���X�ؓS�ܘY�E���E�G��E���{�����̂S�����A����E��V����i���A�R�z�j�̒n��ɂ����ē��Z�����݂̑��t�������̂��͂��߁A���S�S�N�i�P�X�P�P�j����ɗאڒn�ɓZ�����݂̑��t�����A��������킹�āu��֔_��v�Ə̂��A��Ƃ��č��{�������Ǘ��ɓ����蕟�������珬��l�����Čo�c�����B
�@�������A���̒n�т͌X���}�ōk�n�ɓK����ʐς����Ȃ��A�킸���ɔ�����܁Z�����A���̑��͐A���n��h���ђn�ȂǂƂ����ŁA����l���R�T�˂ł������B�������A�ł�Ղ�E�ꂢ����̕s���̒������ė��_������̂����o���A�_��͌o�c�s�U�Ɋׂ����̂ŁA�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�V�J�P�g�Ɉڂ�A����ɁA���a�S�N�i�P�X�Q�X�j���َs�̏��ьF���Y�Ɉڂ�Ƃ����o�߂����ǂ����B���̌�A���a�X�N�ɂ͖��L�����n�J�������ݕt�K���Ɋ�Â��Čl�O�����]���R�O�˂̏���l�ɏ��n����A����_���n�݂��ꂽ�B
�ᏼ�_��
�@�����R�U�N�ɔ��ق̎ᏼ�p���E�ᏼ�����Y�̂Q�l���A����ƎR��̒��ԋu�˒n�тɂ����Ĉ�Z�Z�l�����]�݂̑��t�����A���m���̂ق���Ƃ��ē��k�n�����珬��l���W���ē��A�������B
�@�����̖����ɂ͔��l�܁Z�������J��������l���T�O�˂ɒB�������A���D�_�Ƃɂ��n�͂̌��Ղ�Y�͂̒ቺ�ƁA���_�҂̑��o�Ƃ����o�߂����ǂ�A�_��͌o�c�s�U�ƂȂ������߁A���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�Q�����َs�̖���P�g�E��[�ߔV���ɔ��p���Ĕ_���������B���̌�A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�U���A�����s�̎O�䕨�Y������ЂɈڂ�A����ɁA�Q�V�N���؊��s�����������Ėq��o�c���v�悵������������Ɏ���Ȃ������B
�����_��
�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�O�d���̏d�쌒���Y�E�ێR�P��炪�A������̍���n��ɖ��J�n�݂̑��t�����Ĕ_��o�c�ɓ��������A�R�W�N�Ɏ����Ă��J��i�W�̂��Ƃ��݂��Ȃ��������ߕԒn���������B
�@���R�X�N�Q���ɂ́A���쌧�̒����푾�Y�ق��Q��������ܒ����݂̑��t�����Čo�c���A�S�P�N�������݂�Ɏ������B����ː��͂T�X�˂ɋy���A���̒n�т͋u�˔g��n�тł��邽�ߕ\�y�̗��o���͂Ȃ͂������A���Y�����ނ̈�r�����ǂ�A���_�҂����o���Čo�c����ƂȂ����B
�@���̂��߁A�吳�S�N�i�P�X�P�T�j�k�C����B��s�ɏ��n����A���̌㐔��ɂ킽�菊�L�҂��ς��A���a�Q�O�N�X���ɂ͓Ȗ،��̒����C�O�Y�ւƈڂ����B
�勴�_��
�@�����S�R�N�i�P�X�P�O�j���J�d�Y�ɕt�^���ꂽ�y�n��܁Z�������A���̔N�����̕����V�����������ď���o�c���s�����B����ƉԉY�̋��E�n�т��牪�̎R�Ɏ�����ŁA����l�P�T�˂���A���������A�吳�U�N�����̑勴�V���Y�ɁA���X�N�ɂ͊�����Б勴�{�X�ɏ��L�����ړ������B�勴�{�X�ł́A�X���h�̖ƒ����������̑�̗��_��ƍ��킹�Čo�c���Ă������A���S�n�悪����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ���Ĕ�������A���ꂼ��k��҂ɔ���n���ꂽ�B
�|���_��
�@���Ó��i���A�l���j�ŋ��Ƃ��c��ł����|���K�オ�A�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�ɖ��J�n�̕����������āu�|���_��v��n�݂��A����o�c�ɓ������Ƃ����Ă���B�������A��̓I�ȓ��e�ɂ��Ēm���|���肪�Ȃ��͎̂c�O�ł��邪�A�吳�N�Ԃ��珺�a�����ɂ����āA�_��ʐώO�Z�O�����A����l�Q�T�˂����e���Ă����Ƃ����B
�@�l�����w�Z�ɓ���n�_�̍��������ɔ_�ꎖ���������āA���ӈ�тɑ����̍�����A�͂��뉀���ɂ�������Ă����̂ŁA�����̐l�X�͂����ʼn^����Ȃǂ��s���e����ł����B���a�S�O�N�ɍ����g���H���̂��ߎ�̏������̂��ꂽ���A���Ȃ����̖ʉe���Ƃǂ߂Ă���B�܂��A�S�T�N�R���ɂ͋L�O���Ƃ��Ē��̕������Ɏw�肳��Ă���B
�㓡�_��
�@���������A�����n��ɂ��_��o�c���s�����̂��������B�����Q�S�N�i�P�W�X�P�j�ɔ��������Z���n���̑�n�k�ɂ���Ў҂ƂȂ����������S�O�鑺�����̐l�㓡�����Y�͐����Ƃ��c��ł������A��Ќ�c�̂�g�ݓn�����A�����X���������Ō㓡�_����o�c�������A���̌�R�V�N�����ɓ]�Z�����B���̂���̔_��o�c�ɂ��āA�����R�V�N�����Њ��A�V�Α����u�k�C�����s�ē��v�Ɍ㓡�_��̈ړ]�O�̋L�^�Ƃ��āA
�u�X���Ǔ�����_��Ƃ��̂��ׂ��͐Αq���������n���ɑ�����̂݁A�����y���_��E���쐼�_��i���쐼�q�݂̌o�c�ɌW��j�E�g�c�_��E����_��E�㓡�_��i���Z�c�́j�E�k�_��i�z���c�́j���ɂ��āA�ډ�������J�����ɂĖ����������_�Y���̌���ׂ����̂Ȃ����@���B�v
�Ƃ��̒n���̔_��̗l�q���L����Ă���B
�n�Ӗq��
�@�����R�U�N�H�c���R���S�ۊ����̓n�ӕ����Y�E�ē��P���Y�̂Q�����A����������҂ɖq��n�݂̑��t�����o�c���v�悵���B�������S�O�N�ɓ����ɒ�o���ꂽ�u�n�����v�̒��œn�Ӗq��ɂ��Ă͎��̂悤�ɕ��Ă��邪�A�ē��q��ɂ��Ă͂ӂ�Ă��Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA�ē��P���Y�͒��肵�Ȃ������悤�ł���B
�@�u����������҃j�A�����n�����샒�ȃe����k���m�������n���L�n�A�������n���уj�ڃV����m�����n���L�n�A�����n���уj�A���A�ݕt�ʐϔ��\�O��O�S�\���ؑS�n����r�V�J���T�������n�j�R�V�N�u�V�R���v�u�u�i�v�u�n���m�L�v�u�z�[�v���m�a�у��i�V�����T�V�e�����V�n�\��y�O�l���m����ڌܐ��T����ڃm�ז��i���ΎR�D�A���e�n���엀�i���T���������q���m�d���j��J���X
�@���q��n�����O�\�Z�N�i��j���m�ݕt�j�V�e�O�\���N�x�������t�\���N���ȃe�S�������X���\��i���@���n�H�c���R���S�ۊ����m�l�@�����ݕt�Ɠn�ӕ����Y�j�V�e�����������ډ��Γc�i���i�����m���V�e�V�J�Ǘ��o�c�m�C�j�����V��������
�@���ݖq����j�n�Y�āA���샒���Z�e�\�l�˃A�����R�`���l�Z�ˁE�ΐ쌧�l��ˁE�H�c���l��ˁE�ȖE���E�y�q�k�C���m�Ҋe��˃j�V�e�Y�Đ�厵�ˁA���쌓�Y�Ďl�ˁA������O�˃i���g�X�������h��ӁE���앍�߃��Η��V�e���j�������҃m�@�V�Y�}���ݏ\�l���A�N�X����U�P�m�Y�o�A���g�]�t�Y�n���N�Αq��ԏꃒ�o�e���كj�A���X���ݍk�n�n���\�����P�j�V�e����l�K�H�p�g�V�e��o�E���E�n�鏒�E�唞�E�����E�����E��冋o�����k��V�c�c�A���x�������n�ǍD�j�V�e�V�������������O�N�ԑP�N�����ʃ������Z���g�]�t
�����n���אB�m�ړI�i���V��N�n�אB�j�ړI���ύX�V�O�\��N�\������N�ډ��n�����A���e�Y�m�^���p�j���V������
�@��������{�Ɂi��j���q����O��ԊǗ��l�m�ꃋ���j�˃��o����ȗ����H�����������j��X������~�j�B�V���V�e�ؒY�����m�����n���������ܘZ�S�~�i�����g�]�t
�@�C�ݍ����������q�ꖘ��O�\���P�@�ד��A�����S�i�R�j�j�V�e�n�ԃ��ʃX�x�V
�@�V���j�V�ꔽ���Z�\�K���m�J�������^�t�����č������n�ꔽ����\�ܑK�T���O�\�K�m���엿�������X
�ƕ���Ă���B
���̑��̔_��E�q��
�@�O�L�̔_���q��̑n�݂ɂƂǂ܂炸�A���������ɂ͔_����J�݂�����̂��������B�g�����׃c�i���A�x��j�ɋg�A�_��E���c�_��E���_��A����ɓn�Ӕ_��A�R�z���ɐV�֔_��A�����i���A�㔪�_�j�ɐΐ�_��Ȃǂ̂ق��A�����̔_���q�ꂪ�J���ꂽ���A�����͎R�ԋu�˒n�тœy�n�����������������߁A�o�c������ɂ߂Đ����������̂͏��Ȃ������B
�c�̓��A
�@�����Q�N�i�P�W�U�X�j�J��g�ݒu�ȗ��A�{���ւ̈ږ�����͑������Ă������A�P�X�N�i�P�W�W�U�j�ɖk�C�������ݒu����A�Q�T�N�u�c���ڏZ�j�ՃX���v�́v����߂��ĕ{������̏��_���U�v�A�ی쐭�ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B���Ȃ킿�A�c�̈ڏZ�̏���A�ݕt�\�葶�u���x�i�ڏZ�҂̋�̓I�ی���@�ŁA�ː����R�O�ˈȏ�̏W�c�łP���N�P�O�ˈȏジ���ڏZ����ꍇ�P�˂ɂ��P���T�O�O�O�̑ݕt�n���R���N�������炩���ߗp�ӂ��Ă����Ƃ������x�j�̗̍p�A�n�q�D�Ԓ��̊���������̑��̓n���ی�Ȃǂ�ϋɓI�ɍs���悤�ɂȂ����B
�@���������ږ������w�i�Ƃ��āA���_����ї����n��ɂ�������������吳�����ɂ����āA�e�{������̒c�̓��A���݂�悤�ɂȂ����̂ł���B
�@�����R�V�N�i�P�X�O�S�j����R�X�N�ɂ����č�ʌ��̓��A�҂Q�O�˂�����n��̖Ζؔ_��ցA�܂��A�㔪�_�����n��Ɋ��c�̂V�ˁA���n�c�̂P�P�ˁA�����c�̂U�ˁA�i�\�}�b�J�n��ɕ���c�̂T�ˁA�g�����x�c�ƃT�b�N���n��ɉz��c�̂Q�V�ˁA�Z�C���E�x�c�n��ɐÉ��c�̂V�˂ȂǁA��Ƃ��ď㔪�_�n��ɓ��A���J�����s�����B
�@�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�ɂ́A�����s�Y��c���Ƃ������c�̂Q�V�ˁA���T�N����ɂ͊��c�́E�É��c�̂�����֓��A���A����ɂU�N�A�k�C���ږ���W�ɂ��Z�C���E�x�c�ɋߓ��p���q���\�Ƃ��ĂT�˂P�W���̕���c�̂����A����
�ȂǁA���J�n�̊J��������ɍs��ꂽ���A��������s�X�n����P�U�L�����[�g���ȏ�̉��u�n�ɂ���A���H��ʂ̕s�ւƁA�����ē��A�n�͌X�Βn���������ߕ\�y�̗������͂Ȃ͂������A�����̈��������d�Ȃ��Đ��Y�͔N�X���ނ��ė��_�҂��������A���N�ɂ��čr�p�n�Ɖ������Ƃ�����������B
���ږ�
�@�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�֓���k�В���A�����Ȃ͈ڏZ�҂ɑ��ĂP�˓�����R�O�O�~�̈ڏZ�⏕������t���鋖�ږ����x���߁A���������̎��Ƃ����s���ċ��ږ����ƂƏ̂����B���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�u�k�C������_�ڏZ�⏕�K���v���߂Ă��̎��Ƃ��g�����A����_�ƂȂ�ړI�Ŗ{���ɈڏZ���ē���n�݂̑��t�����A���邢�͖��L�����n������ē��A����ꍇ�A�P�˂ɑ��ڏZ�⏕���R�O�O�~�ȓ��A�Z��ݕ⏕���Ƃ��ĂT�O�~����t�����B
�@���̋��ږ����x�Ɋ�Â��āA���a�T�N�y���P���y�V���x�n��i���A�㔪�_�j�ɂR�ˁA�U�N�W�ˁA�V�N�R�ˁA�U�N�R��ɂP�ˁA�W�N�T�b�N���i���A�x��j�ɂT�ˁA�Ɠ��A���A�������A�҂́A�����~���Ԃ͐d�i����j�Y�̐��Y�③�ނɏ]���������A�����̌͊��Ɠy�n�̔敾�Œ������_������̂������A�蒅�������͔̂����ɂ������Ȃ������B
�@��S�߁@�ꂢ����͔̍|�Ƃł�Ղ�
�ꂢ����̕��y
�@�ꂢ����͐���P�U�O�O�N�O��ɃI�����_�l�ɂ���ăW�������璷��ɓ`����ꂽ���̂Ƃ����A���̌�A����n�сi�b��E�M�Z�E���Ȃǁj���o�ď��X�ɖk�i���A�P�W���I�̏��߂���ɂ͊��ɖk�C���ɕ��y���āA����n�тɂ�����~�r�앨�Ƃ��Ē蒅���������Ƃ����B�������{�i�J��g�j���܂��{���_�Ƃ̊J����i�߂�ɂ�����A���X�Ƃ���ɒ��ڂ��A�d�v�앨�Ƃ��ĊO���Y��q�ꂢ����𐔁X�A�����삵�ēK���i���I�ʂ̂����A������J��ڏZ���ɖ����z�z����ȂǕ��y�ɓw�߂��̂ł������B
�@�����ɂ�����ꂢ����́A�����P�P�N����ƊJ��������ɂ����ĊJ��g���d���Ǝ����ꂩ��A�[���[���[�Y��W�U�̔z�z���č�t�������̂��n�܂�Ƃ���A���̌�A�D�y����ړ������X�m�[�t���[�N��ƂƂ��ɍ͔|���ꂽ���A���ʂ͂�������ǍD�œ��n���̓K�앨�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���̂��߂ꂢ����̍�t�ʐς͋}���ɑ��������̂ł���B�����̔_�Ɠ��v�i���_�E�R�z�����j�ɂ��A�Q�U�N�̓����ɑ��R�R�N�ɂ͎O��ܒ����𐔂��A���悻�P�Q�{�̑����������A�������A����t�ʐς̂R�O�p�[�Z���g���߂鐨���ł������B
�@���̂悤�ɂꂢ����̍�t�����̗v���́A���n���̋C�y�ɓK�������̂ł��������Ƃ͓��R�ł��邪�A�܂���ʂł́A�����푈��ɂ�����o�Ϗ�̕ω��ɂƂ��Ȃ��A�唞�E�����Ȃǂɑ����Ăꂢ����������Ƃ���ł�Ղ����r���𗁂т�Ƃ����A����I�Ȕw�i������������ł���B
�ł�Ղ��̐U��
�@�ꂢ����������Ƃ���ł�Ղ��́A�����P�S�N�i�P�W�W�P�j�ɒґ��������킳�т��낵�ŎC�艺�낵�ЌI����A���P�T�N�̔���ړI�Ƃ��ē������珬�^�̐����@�B���w�����Ē��肵���̂��n�܂�ł��������A�Z�p�����n�Ȃ��ߕ��~�܂肪�����A�o�������Ŏ��x�̃o�����X���Ƃꂸ�����s���ƂȂ�Ԃ��Ȃ����~�����B���̂��߁A�P�V�N�ɂ͂����ƊJ��������̒��c�Ƃ��A���K�͂̑傫���{�݂�݂��Ď��Ƃ̐U����}�낤�Ƃ������A���ׂĐl�͂ɗ���Ƃ����c�t�ȕ��@�ł��������߁A�o���v���锼�ʐ��Y�͏オ�炸�A�������̘H�������Ƃ������Ƃ������āA������킸���T���N�Ŏ��Ƃ�p�~�����̂ł������B
�샍���ł�Ղ��� �i�ʐ^�P�j
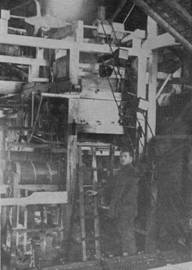
�@���̌サ�炭�́A�킸���ɂQ�A�R�˂̂��̂����Ƃɂ���B�Ŏ��Ɨp�����邭�炢�ŁA���̔��B���݂�ɂ͎���Ȃ������B
�@�������A�����Q�T�N�i�P�W�X�Q�j�͈�玟�Y�A���쏕���Y�A�g�c�m��炪�������J�n���A�����͂𐅎Ԃɕς��ĘJ�����Ȃ��A�������������߂Ē��ڂ��W�߂������B����ɁA���Q�U�N���Ƃɒ��肵������Ǐ��́A�ł�Ղ������_�n���ɂ�����_���H�ƂƂ��čł��K���ŁA�L�]�Ȏ��Ƃł��邱�Ƃ���A�я푥��ƃO���[�v������A��i�n�ł����t�����ʌ��̕��@�����Ȃ���A�����H���̉��P�𑱂����B���̌��ʁA�R�O�N�ɂ͂��Ɂu�샍���ł�Ղ���v���l�Ċ����������Ƃ́A���M�ɒl������̂ł������B���̐�����́A��ʂ��E�d��ʂ��E�ےʂ��E���b���E�摗��E������Ȃǂ̑��u���P���͂��߁A���ׂĐ��Ԃɂ�铮�͂���ƍH���ɓ������ďȗ͉����A��肢�������������������߂���@��n�Ă����̂ł���B���̉���I�ȋZ�p���ǂɂ��A�J���n���c����ɂ͈�U���іځi�S�T�L���O�����j�̂ꂢ���傩��ł�Ղ�Z�ҁi��҂͂U�O�O�O�����j���������ł����A�������A��ڎO�Z�U���O�̌�������������̂ɂU�A�V�l�̘J����v���Ă����̂ɑ��A���Y���~�܂�����A�O�҂Ƃ��悻�Q�{�ɏ㏸���A���v�o�����R���̂P���x�Ƃ����D���т��グ��悤�ɂȂ����̂ł���B
�@����������o�҂̓w�͂ɂ���āA���̗L�v������ʂɔF������Ăł�Ղ�M�͋}���ɏ㏸���A�����R�O�N�ɂ͐����ː����Q�S�˂ł������̂ɑ��A�R�V�N�ɂ͂Q�S�P�˂𐔂���Ɏ���A���Y�ʂ����O������O�Z�ҁA���Y�z�X���T�R�T�W�~�ɒB���A�����̂���Ƃ���ɂ͕K��������������Ƃ����Ă��ߌ��łȂ��������Ă����B
�@�Ȃ����̊Ԃ̂Q�W�N�ɂ́A���쏕���Y�E�g�c�m���̐��Y�����ł�Ղ�S��������Ɣ�����łR�����v�ƗL���͂����B
�@����������@�̕��y�ɂƂ��Ȃ��āu���_�ЌI���v�͂܂��܂��������A�����ꂢ����̍�t���������R�X�N�ɂ͎O��Z�꒬���Ƃ������ٓI�ȖʐςɒB���Ă����B�܂��A�����̕i��͂ł�Ղ�ܗL�ʂ̖L�x�ȃA�[���[���[�Y�A�v���C�X�e�[�J�[�A�A���[�r���[�e�B�E�I�u�E�w�u�����Ȃǂ���Ƃ��č͔|����Ă����B
���_�ЌI�����Ƒg��
�@�ł�Ղ����Ƃ̕��y�ɂ�薾���R�U�N�i�P�X�O�R�j�P�Q���A���Ƒg���@�ɂ���āA�u���_�ЌI�����Ƒg���v�̐ݗ��F���A���R�V�N�S���ɑn��������J���Ē芼�Ȃǂ��c�������B�������A�������������I�̍������f�₵�āA�ł�Ղ�̌����ƂȂ�ꂢ���傪�u�R�p�؊����v�̐����Ɍ�������Ƃ����ٕς������āA���̓��Ƒg���͑����ݏ�ԂƂȂ�A���Ƃ̔������݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@����������ł́A�g���̑��������J�n��]�ސ������܂����̂ŁA���R�W�N�T�����炽�߂đn��������J�ÁA�芼���̑����c�����ĂV���F�A�������玖�Ƃ��J�n�����B���Ƒg���͔��_���̂ق��������E�����E�X�̊e�������Ƃ��A����g�����ɓ��c���O�Y�A���g�����ɐ���Ǐ����A�C�i�����S�S�N�ȍ~�g�����U�܂Ő���Ǐ����g�����߂�j�A���i�������s���ĕi���̌���A�ב���̉��P����}��A�i�����E���E�Ԃ̂R�����ɋ敪�A���W�����S������ъC�O�ɂ܂ł��̖�������悤�ɂȂ����B���ɁA�����R�W�N����܂œ����s��ɂ����đ�P�ʂ��߂Ă�����t���Y�̂ł�Ղ��"�������A�S�O�N�ɂ͑������S����P�ʂ̍��l�Ŏ����������悤�ɂȂ������Ƃ́A���Ƒg���̈̑�ȋƐтł���A�����̎Y�Ǝj����M���ׂ����̂ł��������A�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j�V���ɂ͉��U�̂�ނȂ��Ɏ������B
��P�\�@�ł�Ղ�̏��W�i���_�ЌI�����Ƒg���j�i�ʐ^�P�j
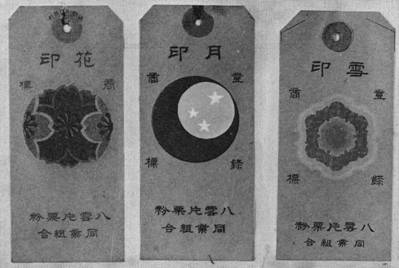
��Q�\�@�ЌI���̑܋l�Ɣ��l�i�ʐ^�Q�j

�@�Ȃ��A�������Ĕ��_�ЌI�������Y���グ�A���������߂�Ɏ������̂́A������ł�Ղ��@�����A�����Ƒg���̉^�c�ɐs����������Ǐ��̌��тɕ����Ƃ��낪�傫�������B�����������Ƃ���A�吳�V�N�W���J���T�O�N�L�O���T�ɍۂ��A��B���J�҂Ƃ��ē����������玟�̂悤�ȕ\�������̂ł���B
�@�g�j�{���b�����ƃm�s�U���J�q�����������@�B�m�s���j�݃��g�׃V������\�Z�N�V�K���P�j���S�V����l���ܐ������������b�������탒�ďo�V��C�j�J��ȃL���Y�����Z�����j���e�e�n�ÑR�g�V�e�V�j��q�׃j�b�����ƃm�u���������j�����X�j���Ƒg�����g�D�V�e�J���z�ƃm���W�j���V�ȃe�����m��������v�Z���n���J�����j�̃X�x�V䢃j�J���\�N�L�O�������N���j���葴���у��\�ՃV�L�O��t�������V���Z�e���Ӄm�Ӄ��\�X
�@�吳���N�����\�ܓ�
�@�k�C��������
�@���l�ʌM�O���@�U�@����
�ł�Ղ�i�C�Ƃ��̌���
�@�吳�R�N�i�P�X�P�S�j��ꎟ���E���̂ڂ����ɂ���āA�ꂢ����ł�Ղ�͈��d�v�ȊC�O�A�o�i�ƂȂ����B���̂��ߊ����R�z�S�_��ł́A�k����A��|�Ȃǂ̋Z�p�w���ɓw�͂��Ȃ���A�������ʕS�U��ڕW�Ɍ����ꂢ����̑��Y�����サ���̂ŁA�܂���̑������ɂ��ł�Ղi�̖\���Ƃ����܂��āA������u�ł�Ղ�i�C�v�Ƃ����D����悵���̂ł���B
�@���n���Ƃ��Ȃ�ƒn���̘J���͂ł͊Ԃɍ��킸�A���������瑽���̐l�X�����@��o�ʂƂ��ē���A�^���̂��ߓ��{�C���ʂ̋�������n��A��ďo�҂��ɂ������߁A���_�̗��قɂ͕K���n�������݂�����悤�ɂȂ�A�܂��A�_�Ƃ̂Ȃ��ɂ͋������v����������ĕ������̂������قǂł������Ƃ����B
�@�������吳�V�N�ɐ푈���I�����A���W�N�u�a���̒����ƂƂ��ɁA���[���b�p�ɂ����Ă��I�����_��h�C�c�̂ł�Ղs��ɕ��A����悤�ɂȂ�ƁA����قǍD�����ւ����ł�Ղ�͉��i���}���ɖ\�����A�������A�����Ă�����Ȃ��Ƃ����ɒ[�ȕs���Ɋׂ����B���̂��߁A�ł�Ղ����Ƃ͋}�]���ĕs�̎Z���Ƃɗ������݁A�����̐ݔ��͕��u����čr���ɂ܂����A�����H��͂قƂ�ǂ��e���Ђ��߂�悤�ɂȂ����B
�@�܂��A�ꂢ����̍�t�ʐς͍D���ɂ܂����đ������Â��A�A��ɂ��A��œy�n��ӂ߁A�ΎR�D�y��������ߐs�����Ƃ����ł���A���̕s�������ɂ���Čo�c����ƂȂ����_�Ƃ́A�r��ʂĂ��y�n���c���ė��_�]�Z������̂����o���A�_�ƌː��̒������������������ƂƂȂ����̂ł���B
��P�\�@�ЌI�����Ƒg���ݒu�O��ɂ�����ł�ՂY�y�ː�
| �݁@�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�O | �݁@�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�� | ||||||
| �N�� | �Y �o �� �� | ���@�@�@�@�@�@�i | �����ː� | �N�� | �Y �o �� �� | ���@�@�@�@�@�@�@�i | �����ː� |
| �� �Q�U |
�� �V�C�X�Q�T |
�~ �� �S�R�T�D�W�V�T |
�� �T |
�� �R�W |
��@ �� �P�C�U�Q�P�C�X�Q�T |
�~ �@�� �X�S�C�U�R�T�D�R�V�T |
�� �Q�T�P |
| �Q�V | �P�Q�C�T�U�O | �V�Q�W�D�S�W�O | �V | �R�X | �P�C�V�S�Q�C�V�V�T | �P�P�R�C�Q�W�O�D�R�V�T | �Q�S�U |
| �Q�W | �P�S�C�O�O�O | �W�S�O�D�O�O�O | �W | �S�O | �P�C�U�R�U�C�T�V�T | �P�P�S�C�T�U�O�D�Q�T�O | �Q�T�W |
| �Q�X | �P�T�C�T�U�O | �P�C�O�P�P�D�S�O�O | �P�P | �S�P | �P�C�V�S�X�C�R�O�O | �P�U�Q�C�U�W�S�D�X�O�O | �Q�Q�T |
| �R�O | �T�T�C�O�O�O | �R�C�X�U�O�D�O�O�O | �Q�S | �S�Q | �Q�C�O�T�V�C�W�V�T | �P�U�Q�C�T�U�V�D�P�Q�T | �Q�T�P |
| �R�P | �X�V�C�U�V�T | �U�C�Q�T�P�D�Q�O�O | �R�R | �S�R | �Q�C�W�R�R�C�O�T�O | �Q�O�U�C�W�P�Q�D�U�T�O | �Q�W�W |
| �R�Q | �P�W�X�C�V�Q�T | �P�P�C�X�T�Q�D�U�V�T | �R�W | �S�S | �S�C�Q�Q�U�C�P�O�O | �R�O�O�C�O�T�R�D�R�S�O | �R�S�O |
| �R�R | �R�T�W�C�P�Q�T | �Q�T�C�S�Q�U�D�W�V�T | �U�U | �� | �@ | �@ | �@ |
| �R�S | �U�Q�W�C�R�Q�T | �S�V�C�U�Q�S�D�R�V�T | �W�X | �P | �Q�C�U�W�X�C�P�Q�U | �Q�P�Q�C�S�S�O�D�X�T�S | �S�O�V |
| �R�T | �P�C�P�V�U�C�T�Q�T | �X�U�C�S�V�T�D�O�T�O | �P�U�V | �Q | �R�C�X�O�V�C�T�O�O | �Q�X�R�C�O�Q�T�D�O�O�O | �S�Q�P |
| �R�U | �P�C�X�S�O�C�S�V�T | �V�S�C�U�S�Q�D�V�T�O | �Q�O�T | �R | �T�C�O�W�R�C�S�Q�T | �R�V�Q�C�W�R�X�D�T�O�O | �T�O�X |
| �R�V | �P�C�Q�R�W�C�X�R�O | �X�T�C�R�T�W�D�O�P�O | �Q�S�P | �S | �V�C�O�S�V�C�U�V�T | �T�O�V�C�V�P�U�D�O�O�O | �T�U�S |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �T | �T�C�S�U�R�C�U�V�T | �V�T�R�C�T�W�X�D�Q�O�O | �T�U�W |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �U | �P�O�C�R�T�O�C�O�O�O | �P�C�U�O�Q�C�O�O�O�D�O�O�O | �T�V�R |
���@�P�ҁ��P�U�O�恁�U�O�Ogr= �P�D�R�Q�Q�W�|���h�i�����u����_�ꔭ�B�j�v�j
�@��T�߁@��q�p�ꂢ����͔|�̓W�J
��q�p�ꂢ����ւ̓]��
�@�����N�ォ��吳�����ɂ����锪�_�E�����n���̂ꂢ����̐��Y�́A�ł�Ղ��̂��߂̌����p�Ƃ��ēW�J���Ă����̂ł��������A��P�����E����ɂ�����ł�ՂƂ̐��ނɂ���āA���_�]�o�Ȃǔ_�ƌː��̌����ƂƂ��ɁA��t�ʐς����������������B�������A�ˑR�Ƃ��Ă��̒n���̓K�앨�Ƃ��čk�삪�������A�����ނˎl�Z�Z�������x�̍�t�����ێ�����A�����������Ԃɂ�鐔�����̍H��ɂ��A���N��̂ł�Ղ��Y����Ă����B
�������A�����p�ꂢ���吶�Y�D���̂Ȃ��ŁA����ɊÂ邱�ƂȂ��A����������q�p�ꂢ����̐��Y����͂��߁A�i��̉��ǂ�u�a�\�h�̌����ȂǂɎ��g��ł�����o�҂����̓w�͂��������сA�₪�āu�j�ݏ��v����v�i��Ƃ����q�p�ꂢ����̎�Y�n�ւƔ��W����̂ł���B���Ȃ킿�A������ł�Ղ�����l�Ă�������Ǐ��⊝���R�z�S�_��̎����������͂��߁A�吳�S�N�ɓ���_�ꎖ�������ݒu�����u���_�n�鏒�������v�͔̍|�����Ȃǂɂ��A��q�p�ꂢ���吶�Y�̐�i�n�Ƃ��Ă̒n����z���������̂ł���B
�@�j�ݏ��́A�吳�P�Q�N���납��u�a��𐫕i��Ƃ��č͔|����n�߂Ă������A�����O����̎�q�̕����\�����݂ɑΉ����Ă�����Љ�����Ƃ���A��q�p�Ƃ��Ē蒅���A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�ɂ͊��ɖZ�Z�U�i�����U�O�L���O��������j���ڏo����܂łɂȂ��Ă����B���̐��ʂ́A�����ꂢ����̈ڏo�n�тƂ��Ēm���Ă����둾���̈�Z�Z�Z�U�A���Α��̎O�Z�Z�U�A�L�����̓�l�Z�Z�U�i��������e�����_����j�Ȃǂ��͂邩�ɂ��̂����̂ł������B
�@���_���ɂ������q�p�ꂢ����̈ڏo�ʂ̐��ڂ��݂�ƁA���a�W�N�ɂ͌ܖ��Z�Z�Z�Z�U�Ɣ���I�ɑ������A�P�P�N�Z����Z�Z�Z�U�𐔂���ȂǁA�Ȍ�̈ڏo�ʂ͑S���ڏo�ʂ̂P���O����߁A�P�X�N�ɂ͎��Ɉ�O�Z�Z�Z�U�̏o�חʂ𐔂���Ɏ���A�k�C���ɂ�����ꂢ����̎�Y�n�Ƃ��Ă̒n����z�����̂ł���B
��q�ꂢ����̈ڏo�� (��k�C���_�Ɣ��B�j�U�)
�i�P�ʁ@��U�j
| �N�� | ���a�R | �S | �T | �U | �V | �W | �X | �P�O | �P�P |
| �k�C�� | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �U�O�Q |
| ���_�� | �W | �P�U | �Q�U | �P�V | �R�Q | �T�U | �R�U | �S�O | �U�Q |
| �N�� | ���a�P�Q | �P�R | �P�S | �P�T | �P�U | �P�V | �P�W | �P�X | �Q�O |
| �k�C�� | �P�C�O�Q�V | �W�W�S | �U�R�S | �T�R�P | �X�V�T | �P�C�Q�V�Q | �P�C�Q�T�R | �P�C�R�T�S | �U�V�W |
| ���_�� | �W�R | �V�Q | �W�Q | �T�R | �P�O�T | �P�P�Q | �P�Q�O | �P�Q�R | �P�S |
�ꂢ���唽�����ώ��x(���_��)(��k�C���_�Ɣ��B�j�h�)
�x�@�o�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�吳�T�C�P�X�P�U�j�i�P�ʁ@�~�j
| �k���� | ���n�� | ���� | ��q�� | �d��� | �엿�� | �{��� | ���k���� | �|�y�� | �x��� | �^���� | ���۔� | �v |
| �O�D�T�O | �O�D�Q�O | �O�D�P�T | �Q�D�O�O | �O�D�S�O | �S�D�O�O | �O�D�Q�O | �P�D�O�O | �O�D�Q�O | �P�D�Q�O | �O�D�U�O | �O�D�Q�O | �P�O�D�U�T |
| ���� �i�U�j |
�P�� | ���z | ���� �v�� |
���� | �P�U�� �e�� |
���� �i�Y�j |
�Y�� �P�� |
���蕽�� �͔|�ʐ� |
�P�˓� ���菊�� |
�P�˓� ���菃���v |
| �R�O | �~ �O�D�S�T |
�P�R�D�T�O | �Q�D�W�T | �U�D�P�O | �Y �P�Q�D�T�O |
�R�D�V�T | �R�D�U�S | �� �S�D�O |
�Q�S�S�D�O�O | �P�S�T�D�U�O |
�ꂢ����̎R�i�ʐ^�R�j

��q�p�ꂢ���吶�Y�̔��W
�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�T���Ɂu�A���h�u�@�v�����肳��A�u�V���ɍ����ɐN�����A�܂��͊��ɍ����̈ꕔ�ɑ��݂��Ă���a�Q���̂܂��h�~���A�D�ǂȎ�c��ۑS���邽�߂̌��u�����{����v���ƂƂȂ����B���Q�U�N�Y�̎�q�p�ꂢ���傩��A�r�[���X�a�E�u�a�E�֕��a�E���ޕa�E�͕a�E���{�a�E��o�a�i���a�R�O�N�x���畲����o�a����������j��ΏۂƂ���A�t���O�̌���̐R������n�߂āA��q�p�ꂢ����͔|���߂�ށi�فj�ꌟ���A�ꂢ���吶�璆�R��ɂ킽��ޏꌟ���A�@����̐��Y�������Ƃ����S�i�K�ɂ킽��O�ꂵ���h�u���������{�����悤�ɂȂ����B�܂��A�u�h�u�⏕���v���C������A�a���̔�������ޏꌟ���̗�������s����悤�ɂȂ����B
�@����ɁA�̎�_�Ƃ͂��̐A���h�u�@�̋K������ق��A�Q�V�N�T���ɐ��肳�ꂽ�u�k�C����n�鏒���Y�̔�������v�Ƃ��́u�{�s�K���v�ɂ��A���Y�҂̓o�^�A����̔z�t�����A�̎�ނ̑I�肨��ѐ��Y�Ǘ��Ȃǂɂ��ċK�����������A���Y�҂̎��i�v������߂��āA�]���̂悤�Ɏ��R�Ȑ��Y�͔F�߂��Ȃ����ƂƂ��ꂽ�B
�@�����������������Ƃ�������I�ω��������������A���ɖ����ȗ��ꂢ����̐��Y�n�Ƃ��Ċm�ł���n�ʂ��߂Ă��������́A�ˑR�Ƃ��Đ�i�n�ł���n�ʂ͕ς�炸�A�n���Ǔ��ɂ����Ă͋T�c���ƂƂ��ɂ��̎�Y�n�Ƃ��Ă̒n�ʂ�ۂ����̂ł���B
�@��U�߁@�Y�n�̐���
�Y�n�̎���
�@���v�R�N�i�P�W�U�R�j�T���ڈΒn�l���ɂ��n�̎��{��������Ă���A�ڏZ���̊ԂŎg��p�n�̎��炪�i�߂���悤�ɂȂ����B���������̏ڍׂ�m���|����͂Ȃ��A��̓I�Ȃ��̂ƂȂ�Ɩ��������ɂ����闎�����˒�����̋L�^�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�����P�P�N�U�����������œ��������������̎����m�_�C��ɗ������q��i�S�U���W�V�O�Ŕn�P�U�T���j�ƁA�������ɗ������x�R�ǖq��i�Q�S���W�X�T�T�Ŕn�V�Q���j�̂Q�q�g���J�݂���Ă����Ƃ����L�^������ł���B
�@�Ȃ��A�����P�S�N�i�P�W�W�P�j�W������X���ɂ����čs��ꂽ�V�c�̓��k�E�k�C�������K�ɍۂ��A�����S�������狟���̏�n�P�O���̎�z���˗��������˒�����ɏo����A�˒����؊��Y�͏��v�n����肻�낦�č����o�����ƔF�߂���L�^�Ȃǂ�����B�܂��A���P�T�N�T���ɂ͊�茧�����̐l������ܘY������ɖq����J�݂��Ĕn�Q�Q������q���A���̔N�V���ɂ͖�c���q���ɂŔn�P�O�O�]�����͂��ߋ��E�E�{�Ȃǂ����炵�Ă����Ɠ`�����Ă���B
�@���_�ɂ�����n�̎��{��`������̂Ƃ��Ă͖����P�T�N�̔ӏH�A�h�̑��k�ɂōk�n�k���q���ݒu�A����ɂP�U�N�A��P��ڏZ�̕���E�L�E��㕶���̂Q�����A�ԉY���ʂŖq����o�c���A�S�O���]��̖k�C���a��i�ʏ̃h�T���R�����{�����Ƃ����L�^�����邪�A���l�͂܂��Ȃ����Ƃ�p�~���Ęh�̑��k�ɂɏ��n�����Ƃ����B���̂���̔n�́A�̍����P�E�Q���[�g������P�E�R���[�g�����炢�̓y�Y�n�ŁA�g�r���ʔ����邢�͏�p�ɂ��Ă��Ă������A����ɔ_�k�p�Ƃ��Ẳ��ǂ����グ���Ă����B
�@���������w�i�ɂ����ē���ƊJ��������ł́A�����P�S�N�S�������y���V�����\�Y�n�ꓪ����y�Y�n�̉��ǂ��v�悵�A����ɂP�V�N�u�암�Y��P���v�Ə̂����Y�n���ړ����Ďg������ь�z�ɗp���A�P�W�N�ɂ͊J��g����g���b�^�[��Y�n�݂̑��t�����Ęh�̑��k�ɂɔz����ȂǁA�Y�n�̉��ǂɈӂ�p�����B����ɁA�Q�O�N�ɂ͐V���䗿�q�ꂩ�玓�n�P�T���A�Y�n�P�����A���Q�P�N�ɂ͎��n�R�T���̕����������Ē��X�Y�n�̉��ǂ�}�����B�܂��A�Q�R�N�ɂ͔��َ��C�q�ꂩ��ɐB���n�Ƃ��Ĉ��G��R���������Ĕn�C�̉��ǂ����サ�A�R�P�N�ɂ̓y���V�����\�킨��уg���b�^�[��̎�Y�n���w���A����ɁA���̔N�q��g�������ȂǁA���̉��Ǒ��i�ɗ͂𒍂����̂ł���B
�@�����R�T�N�ɎR�z�������������ĂQ�����������{�s�����O���ʂ��āA�e�n�ɔ_�ꂪ�n�݂���A�_�ƌː��̑����ƂƂ��ɂꂢ����ł�Ղ�̍D���ɂ��k�n���g�債�A����ɂ�Ĕ_�k�p������ǂ���Ē{�͊����y���͂��߁A�_�k�n�̎��v���܂��܂������Ȃ����B���̂��߁A�����R�X�N�ɐ������`�ق��P�S���ɂ�苍�n�̉��ǂƑg�������݂̗��v��}�邽�߁u�R�z�S�Y���n�g���v��g�D����Ȃǂ̓���������A�n�C�̓������������������āA�����S�P�N�ɂ͔��_�������Ŏ��ɂP�R�Q�O���𐔂���Ɏ������B
�@�܂��A���̔n�C���ǂɈӂ�p�������Ƃ͗������ɂ����Ă����l�ł���A�����R�U�N�ɂ͖�c�ǂ̔_�Ƃ��g�����W�O�l�������āu��c�ǎY�n�g���v��g�D���A�V���䗿�q�ꂩ���Y�n�u���L���[�o�[�Y���v���w�����ĎY�n�̉��ǂɓw�߂��̂ł������B
�@�����R�S�N�P�O����P�ً�O���S�n�C�{�����i����_�����ɊJ�Â��ꂽ�̂��͂��߁A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�X����R�ً�O�P�O�S�A�����n���i��A����ɁA�U�N�X���ɑ�T�i����_�����ɊJ�Â����ȂǁA��K�͂ȋ��i����_�Ɣ��ق����Ƃ��Č��݂ɊJ�Â��ꂽ���Ƃ���݂Ă��A�������ɔn�Y�n���_�̒n�����z����Ă������Ƃ����������m�邱�Ƃ��ł���B
�@���������n�C���ǂɓw�߂Ă�������A���Ȃ킿�A�����S�S�N�W���Q�R���c���q�i�吳�V�c�j�̖{���s�[�ɍۂ��A���_�w�ɂ����ėD�ǎ��n�R�X����䗗�ɋ������ق��A���ɗ����c�y�����L�̎��n�A���W�F�[����k�C���Y���n�A����������_�����Ɖ��̂��Č��サ���̂ł������B
���_���Y���i��(���_���w�Z) �i�ʐ^�P�j

���َs�ق��P�O�S�{�Y���i�� �i�ʐ^�Q�j

�@�@�@
��n���̗U�v
�@�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�ɔn���NJ��������z����A���t�ɒ������Ĕn�C�̉��ǔɐB���̑��n���Ɋւ����������ǂ邱�ƂɂȂ�ƂƂ��ɁM�n���Ɏ�n�q��R�M��n�琬���P�A��n���P�T���ݒu����邱�ƂɂȂ����B����́A�����A�����J�푈�̌o��������{�R�n�̗����F������A�n���̈�V���}���邱�ƂɂȂ������ʂł���Ƃ����B���̕��j�Ɋ�Â��k�C���ɂ͎�n�q����A��n���ꂩ���̐ݒu�����܂����̂ł���B
�@�Y�n���ǂɔM�S�ł����������Ƃ��ẮA���̌v��ɐڂ���Ƒ����s�����N�����ĂS�O�N�Ɋ������g�D���A��ɂ͂Ƃ��̔��َx���������M�F���A�ψ����ɔ��_�����{����ܘY��������A�ב����������ƒ�g���ēK�n���������y���i���A�L�Áj�ɑI��A�U�v�^����W�J�����B���S�P�N�n���ǂ̎��n�����̌��ʁA�������K�n�ƔF�߂��A�S�Q�N�X���T�����t�����������āu��������n���v�̊J�݂����肳�ꂽ�B
�@���̎�n���͑��ʐςX�U�U�����]�A�펞�U�O�]���̎�Y�n�����炵�A�S�����{����T����{�ɂ����Č��������{���ĂS�����{�����W�O���Ԃ���t���ԂƂ������A�قƂ�ǔ��_�̐l�����p�����Ƃ�����قǂł������B
�@�������āA���̒n���ɂ�����Y�n���ǂɓw�߂����߁A������������吳�����ɂ킽��R�n�琬�ɍv������ƂƂ��ɁA���̒n�����{�����w�̔n�Y�n�Ƃ�����䂦��ƂȂ����̂ł���B
��������n���@�i�ʐ^�P�j
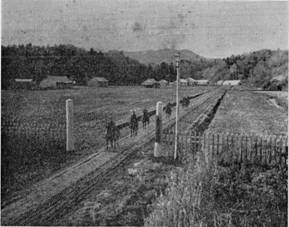
�@���̎�n���́A���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�u�_�U��n���v�Ɖ��́A����ɁA�Q�P�N�T���u�_�U��{�q��v�Ɖ��߂��Ĉ�ʉƒ{����҂̎w���Ɩ��ɂ�����Ȃǐ����̉��ς��o�����A�Q�S�N�T���������Ĕp��ƂȂ����B
�����n�̎���
�@�_�k�p�n�𒆐S�Ƃ���n�C�̉��ǂ��i�߂������@�����̖����ɂ͋����n�̎��������ɂȂ�A�����Ȃǂ𗘗p���ċ��n��J�Â���Ă����B�����S�S�N�i�P�X�P�P�j�V���ɂ͔��_���n�����ƊJ���n����p�n�i���A�{�����n���j�S���R�����̖������n���ċ��n���ݒu���A���̔N�W���ɑ�P��̋��n����J�Â����B���ꂪ��w�̎h���ƂȂ�A���̌�e�틤�i��ɓ��܂�����̂�A�����E���l�Ȃǂ̋��n�N���u�ɐi�o������A���ً��n�ɏo�ꂵ�ėD��������̂��������Ƃ����B
�@���̌�A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�R�z�S�Y���n�{�Y�g��������_��Ȃǂ̌㉇�ɂ��A���z�̔�p�𓊂��ē��_���ɑg���������Ƌ��n���V�݂��A�U���ɑ��n�_�Ђ��ړ]���ĕ�[���n���s�����B���n��́A�n������E�������E�������E���イ�ɂȂǂ̎{�݂���������A�Ȍ�͂P�S�N�܂Ŗ��N�t�H�Q�n���s��ꂽ�B���ɂU�N�P���ɒn�����n�Ƃ��Č��F����Ă��琷��ɂȂ�A�T���u���b�h�A�A���O���A���u�A�A���u�Ȃǂ̌y��n�n�����{������̂��������āA��������n�S������Ƃ�������l����悵�A���ق��͂��ߊ֓��E���ȂǁA�����̋��n�ɂ��o�ꂷ��悤�ȗD�G�n�Y����قǂł������B
���_���n��i���A�{���������j �i�ʐ^�P�j

�n�����F���_���n��i���A���a�E���_���~�n�j �i�ʐ^�Q�j

�@�������A���_���n�͏��a�R�N�ɊJ�݈ȗ��A��ɐԎ��ɔY�܂���Ȃ�����h�����Ă��̖�����ۂɂ����Ȃ��������A�P�S�N�X���̏H�G���n���Ō�ɁA���P�T�N�̒n�����n�K���p�~�ɂƂ��Ȃ��ċ��n��͕�����邱�ƂɂȂ����B�����Ă��̋��n��Ւn�́A���_�̔����p�g�����n���{�Y�g�������Ă������A�Q�P�N�̎���_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ�荑����������Ƃ���ƂȂ�A���̌�A��Ƃ��Ĕ��_���w�Z�̕~�n�ƒ������_�a�@�~�n�ɓ]�p���ꂽ�B
�R�p�����Ƃ��Ă̎Y�n
�@���_�͑�������R�n�̍w���n�Ƃ��Ďw�肳��A�����߂ɂ���Đ������̔n�������グ����Ă����B���Ȃ݂ɓ����푈�����̖����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�ɂ����钥���n�̕��ω��i�́A�U�Δn�łQ�T�~�A�W�Δn�łS�O�~�A�X�Δn�łR�R�~�Ƃ����ł������B
�@���̌��т����Y�n���ǂƑ��܂��āA�����A�R�p�n�̒������s��ꂽ���̂Ǝv���邪�A�_�ƌː��͂������k�n�̑����ɂ�Ĕn�C�����͌������A�����S�S�N�i�P�X�P�P�j�ɂ͔��_�������łP�U�V�X���𐔂������ƁA�����͈�i��ނ𑱂��A�吳�T�N�i�P�X�P�U�j�̂P�V�P�W�����ō��Ƃ��Ă��悻�P�T�O�O����O�サ�Ă����B
�@�������A���a�U�N�i�P�X�R�P�j���F���ς̂ڂ����ȗ��A�ĂьR�n�w���͂������嗤�A�o�n�̎��v�����������B���̂��ߍ��́u�D�lj��n����K���v�����z���A�_�яȂ����������t���Ē��Ԏ�n�̔ɐB�����サ�����߁A�T���u���b�g�n�A�A���u�n�Ȃǂ̌y���A�y���V�������n�̏d��͎���Ɍ������A�d������A�������킪��@���߂�悤�ɂȂ����B�������Ă������͖����͂���������Ȃǂ��A�e����߂�悤�ɂȂ����̂ł���B
�@���ɏ��a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�S���ɂ́A�����n�̎�t��Ɛ肵�Ĕn�i�̉��ǔɐB��}�����u��n�����@�v�A����ɁA�D�G�R�n�̊m�ۂ⒥����ړI�Ƃ����u�R�n�����ی�@�v�Ȃǂ����肳��A�n�Y�͌R�n����̒��Ɋ��S�ɑg�ݍ��܂ꂽ�`�Ԃł������B�������s��ɂ���Ē��f���A�R�n�����ی�@�͂Q�O�N�P�P���ɔp�~�����ƂƂ��ɁA��n�����@���Q�R�N�V���̎�{�@�̐���ɂƂ��Ȃ��Ĕp�~���ꂽ�B����ɁA�Q�T�N�T�����肳�ꂽ�u�ƒ{���Ǒ��B�@�v�ɂ���āA�n���悤�₭�ƒ{��ʂ̋K��ɂ��Ƃ���ƂȂ����̂ł���B
���n�Y�̓���
�@�u�n������v�Ƃ���ꂽ�펞���͂������A���ɂ����Ă��_�Ƃ͈ˑR�Ƃ��āu�{�k�E�芠�E�n���v�Ƃ����`�ԂŐi�߂��Ă����B���̂��߁A�k�n�E�m�i��j�n�̂��Ȃ��_�Ƃ͂Ȃ��A�o�c�K�͂̑傫�Ȕ_�Ƃł͂Q���ȏ�����炷����̂����Ȃ��Ȃ������̂ŁA�n�C�����͂Ȃ��������𐔂��A���a�Q�V�N�i�P�X�T�Q�j�����ł́A���_�E���������킹�ĂQ�O�S�Q���ŁA���Ă̑S�����ɕC�G����������Ă����B
�@�������A���a�R�O�N�O�ォ�玔�{�����͌����X�������ǂ�͂��߁A���ɂR�O�N��㔼�ɂ́A����Ƃ��č��x�o�ϐ������ł��o���ꂽ���ƂɂƂ��Ȃ��A�_�Ɛ��̋}���Ȍ������݂���悤�ɂȂ����B����ɁA�@�B�Y�Ƃ̔��B�ɂ���Ĕ_�Ƃ��@�B�����i�߂��A�n�k�v���E���̑��̒{�͔_�@��p�������͂��߁A�������A���H����̍D�]�ɂ��_���ɂ������Ԃ����y���ĉהn�Ԃ�n���肪�s�K�v�ƂȂ�A�n�͂��̌��p�����������͎���Ɍ������Ă������B����͓��������ł͂Ȃ��S���I�ȌX���ł���A�S�O�N�ɂ͑S���̎��{�����͂V�R�P���ƂȂ��ĂQ�V�N�����̖�R���̂P�ƂȂ�A�T�R�N�ɂ͂킸���U�T���𐔂��邾���ƂȂ����B�_�Ƃ̋@�B���ɂƂ��Ȃ��Ă��̌����X���͂���ɑ������̂Ƃ݂��A���܂�n�͊��l�̊ς����悵�Ă���ł���B
�@�Ȃ��A�n�̎��{�ː��E�����̐��ڂ͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B
�N���ʔn�̎��{������
| �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� |
| �����P�P | �P�P | �����Q�V | �P�V�W | �����S�R | �P�C�R�R�Q | �吳�P�T | �P�C�T�W�P | ���a�P�V | �P�C�S�O�S |
| �P�Q | �P�V | �Q�W | �P�T�U | �S�S | �P�C�U�V�X | ���a�@�Q | �P�C�T�X�V | �P�W | �P�C�T�P�X |
| �P�R | �S�V | �Q�X | �P�S�U | �S�T | �P�C�R�P�T | �R | �P�C�U�R�O | �P�X | �P�C�T�Q�U |
| �P�S | �U�V | �R�O | �P�U�T | �吳�@�Q | �P�C�Q�X�T | �S | �P�C�U�R�Q | �Q�O | �P�C�R�X�U |
| �P�T | �P�P�P | �R�P | �Q�P�V | �R | �P�C�T�P�X | �T | �P�C�U�V�O | �Q�P | �P�C�P�Q�O |
| �P�U | �P�R�R | �R�Q | �Q�P�T | �S | �P�C�U�Q�S | �U | �P�C�V�O�S | �Q�Q | �P�C�Q�X�Q |
| �P�V | �S�O�U | �R�R | �Q�U�U | �T | �P�C�V�P�W | �V | �P�C�T�W�P | �Q�R | �P�C�Q�T�Q |
| �P�W | �R�W�R | �R�S | �S�T�O | �U | �P�C�T�R�X | �W | �P�C�S�W�T | �Q�S | �P�C�R�X�W |
| �P�X | �R�R�R | �R�T | �V�W�T | �V | �P�C�S�X�U | �X | �P�C�T�V�V | �Q�T | �P�C�T�Q�Q |
| �Q�O | �R�S�T | �R�U | �W�V�O | �W | �P�C�Q�P�Q | �P�O | �P�C�T�X�Q | �Q�U | �P�C�U�Q�T |
| �Q�P | �R�V�T | �R�V | �V�R�Q | �X | �P�C�Q�P�U | �P�P | �P�C�T�X�Q | �Q�V | �P�C�U�R�W |
| �Q�Q | �Q�O�U | �R�W | �W�R�S | �P�O | �P�C�R�R�R | �P�Q | �P�C�Q�W�V | �Q�W | �P�C�U�Q�Q |
| �Q�R | �Q�R�P | �R�X | �X�O�R | �P�P | �P�C�T�O�X | �P�R | �P�C�Q�V�P | �Q�X | �P�C�T�W�R |
| �Q�S | �Q�O�U | �S�O | �X�U�W | �P�Q | �P�C�T�T�X | �P�S | �P�C�R�S�X | �R�O | �P�C�S�T�W |
| �Q�T | �P�V�O | �S�P | �P�C�R�Q�O | �P�R | �P�C�S�V�O | �P�T | �P�C�R�X�R | �R�P | �P�C�R�T�X |
| �Q�U | �P�W�S | �S�Q | �P�C�Q�Q�Q | �P�S | �P�C�T�T�V | �P�U | �P�C�S�S�T | �@ | �@ |
�{�\�͗������Ƃ̍����O�̔��_���̐��l�ł���
�_�p�n�̎��{�ː��E�������ڒ�
| �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |
���{���� | �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |
���{���� | �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |
���{���� |
| ���a�R�Q | �X�P�S | �P�C�S�T�U | ���a�S�P | �U�R�U | �V�P�P | ���a�T�O | �P�U�W | �P�V�R |
| �R�R | �W�W�W | �P�C�R�T�P | �S�Q | �U�O�Q | �U�W�O | �T�P | �W�W | �X�Q |
| �R�S | �W�V�V | �P�C�P�S�O | �S�R | �T�W�T | �U�R�W | �T�Q | �U�U | �W�P |
| �R�T | �W�V�O | �P�C�O�W�S | �S�S | �T�S�Q | �T�V�W | �T�R | �U�T | �U�T |
| �R�U | �W�Q�P | �P�C�P�X�U | �S�T | �S�U�R | �S�W�O | �T�S | �U�S | �U�S |
| �R�V | �V�X�X | �P�C�P�P�U | �S�U | �R�T�T | �R�T�W | �T�T | �S�X | �S�X |
| �R�W | �V�V�O | �X�X�R | �S�V | �R�O�S | �R�O�U | �T�U | �S�R | �S�U |
| �R�X | �V�R�W | �W�P�T | �S�W | �Q�T�T | �Q�T�X | �T�V | �R�X | �S�S |
| �S�O | �U�U�O | �V�R�P | �S�X | �Q�P�S | �Q�P�V | �@ | �@ | �@ |
�i�_�Ɗ�{�����j
�@��V�߁@���_�Ƃ̐i�W
�����̉萶��
�@�����P�R�N�i�P�W�W�O�j�J��̌��ʓI�Ȑi�W�̂��߁A�{�͂������L�{�����_�Ƃ̌o�c���u�����ڏZ�l��́A�����ɂ��L�y���q���ɂ̐ݗ��ɂ��ċ��c���A���̏�����i�߂Ă������A���P�S�N����Ƃ̑���o��������A�u������Ж�c���q���Ɂv��ݗ����A�������F��c�ǂɎ{�݂�����Ėq�����͂��߂Ƃ���ƒ{�̎��玖�Ƃ��J�n�����B�В��͋g�c�m�s�A�����ē͉���c�ߏ��ŁA�O���ɏ�����̂͂P�T�N�Ƃ����A���̔N�V���ɂ͓����S�Q���̂ق��A�n�����A�P���A�{�Q�T�R�H�����炵�Ă����Ƃ����B
�@���̌�A�В��̐E�����胍���h���ɗ��s���̌Óc�m�s����A�����P�W�N�P�O���J���n�ψ��ЋˑO��ɂ��Ă����Ȃ̒��̈�߂ɁA
�@�u�c�c�����c�c�ډ���c���ɂĖq�����ׂ��Q���������Y��������������̐l�̂ɕK���Ȃ��m�炴��ΔV�����v������̂Ȃ��k��ɔV����������@�����Ƃ�����ׂ��F�F�F�����c�c�R��ǂ����H�����̕K�v��m��^����ʂ֗̕��\���J����̎��Ɏ���Ή�����c���̖q�����g��������ߖT��A�O�ӑ��̎��v�ɂ����炴��ׂ��c�c�v
�Ƌ����̎��v�ɂ��Đ����A���_�̏������ɂ��ċ������Ă���B
�@���������āA�q���ɂł͂��������l��������Ƃ��Ėq���̎��{�o�c���}��ꂽ���̂Ǝv���邪�A�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�̂܂�ɂ݂��~��̂��ߎ������s�����A���S���鋍�������o�Ď����㎸�s�ɏI������B���̂��߁A���N���̖q���ɂ����U���ēy�n�E��������ђ{���̑S����ƊJ���n�������̂����A�R�O�N�ɏ�O�i���A�n�c�j�֎{�݂��ڂ��Ėq����J�݂��A������͖��É��ɉ^��Ŏs�����n�߂��Ƃ����B
�@����A�������̖����Q�S�N�A�_�ƌo�c�����̂��߃A�����J�ɗV�w���Ă��������×Y���A�����A����ɓy�n�̕����������đ傫�ȋ��ɂ����āA���_���o�c�����̂ŁA���̉e�������̂��悤�₭��ʂɂ����������炷��X�����݂���悤�ɂȂ����Ƃ������A�j���ɖR�������̌o�߂͕s���ł���B
�@�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�R��̐ΐ�_��Ŗq�����Ƃɒ��肵�A�C�M���X���烑�[�A�V���[��Y���Q����A�����A���S�O�N�o�^�[�������J�n���Ă��璅�X���B�g�[��}��A�吳���N�i�P�X�P�Q�j�ɂT�T�O�O�ҁA�U�N�ɂ͂U�T�O�O�҂̃o�^�[���u����o�^�[�v�Ƃ��Ė{�B���ʂ֔���o�������Ƃɂ��Ă͑O�q�������A�܂������������_�Ƃ̐��҂Ƃ��ĉʂ������Ɛт͑傫�Ȃ��̂��������B
�@�Ȃ��A�吳�S�N�����i�����]���̒Z�p���ɑウ�ă��[�A�V���[�펓�������A�܂��A���T�N�ɂ͍��������Y�������ŏ��߂ĂƂ�����z���X�^�C���펓�����A����ɂU�N�ɂ͓���Y�������đ��B��}��ƂƂ��ɁA��������w�����ăo�^�[������ƂƂ��ɁA�W�N�ɂ͂���܂������ŏ��߂ĂƂ���������S�O�g���l�߂̃T�C�������݁i���̃T�C���͈ꕔ��������ĎO��q����Ɍ�������Ƃ����j����ȂǁA�ꕔ�Ďu�Ƃ̌o�c�ɂƂǂ܂���̂ł������Ƃ͂����A���_�Ɠ����ւ̑f�n������������B
�@�܂��������ɂ����Ă��A�吳���N�ɐX���Έꂪ�L�u�R�V�l�����Ē{���g�������A�،Ó����烑�[�A�V���[��Y���R�V�����w�����A����ɂV�N�ɂ��֓��g�V���ƂƂ��ɒ{���P�O��������ȂǁA�L�{�����_�Ƃւ̈ڍs�����݂��Ă����̂ł���B
���_�Ƃւ̓]��
�@�����_�Ƃ̎厲���Ȃ����ł�Ղ��p�ꂢ����͔̍|���S�����ɂ߂����A�u�L�{�����_�Ɓv���u������p�����萶���Ē{���̎��{�n�����܂���������A�吳�V�A�W�N����̎��{�����͂킸���ɂQ�O�O�����O�𐔂���ɂ����Ȃ������B
�@�������A��P�����E����ɖK�ꂽ�ł�Ղi�̑�\���́A�����̔_�Ƃɒv���I�ȑŌ���^�����B�k�n�͂����闪�D�_�Ƃ̂�������Ēn�͂̌��ނ�r�p�������A���̂��ߔ_�Ƃ͐��v�̈ێ�������ƂȂ�A�ꋓ�ɗ��_�]�Z����҂����o���Ĕ_�Ɛ��͋ɓx�Ɍ������A�_���n�т̗l������ς�����Ɏ������̂ł���B
�@������������@�ɒ��ʂ��������̔_�ƍĐ��̂��߁A��o�҂����͉p�m���W�߁A�E�f�������Ďu�������̂������������ꂽ�u���_�v�ւ̓]���ł������B���Ȃ킿�A���Ռ��ނ����n�͂���݂����点�A���n�ɗ��������_�̔_�Ƃ��Č����肳���铹�́A���̒n�̋C�y�ɓK���������_�ȊO�ɂ͂Ȃ��Ƃ����l���ɗ������̂ł���B
�@���̂悤�Ȉ����v�ɒ��ʂ��A����ɋ����������̓���_�꒷�哇�b�́A�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j�_����̔_����������Ċe�����Ɂu�{���g���v��g�D�����A���_�Ƃւ̓]���@�^�̏�����}�����B�����āA�_�꒷���炪�A�ѕۏؐl�ƂȂ��Ėk�C����B��s���玑���������A���P�O�N�ɖ�c���E��V�̗��g�����m�����E�،Ó������玓���������w�����Ď��{�����A���̐U�����i��}�����̂ł���B�܂��A���P�P�N�ɂ͔~�����\�Y���A������Ђ̕��H��U�v�ɕK�v�ȓ����������m�ۂ��邽�߁A�،Ó��E�m���E�����ʂ���T�W���̎������w�����A��ʔ_�Ƃ⏬��l�ɑݗ^���ė��_�̕��y�ɓw�߂��B
�@�������āA�W�@�ցE�L�u�E�_����̈�̂ƂȂ����w�͂ɂ��A�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�̂U�X�S���ɑ����P�R�N�ɂ͂P�P�O�U���ƂȂ�A���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�ɂ͂Q�O�O�O�����A���T�N�ɂ͓����Q�S�V�U���A���{�ː����V�W�V�˂ɒB���A���ʂR���P�W�V�T�A���̋��z�S�U���W�W�W�P�~�ƂȂ�ȂǁA���_���_�Ƃ��Ėڊo�܂������W�𐋂����̂ł���B
�@�����̑��B�ɂƂ��Ȃ��đ͉X(�������䂤)�삪���Y����A�k�n������ɔ�悭�ƂȂ�A����ɁA�e�����ɐݗ����ꂽ�_�����ǎ��s�g�����_��̑��W�@�ւ̎w�����A���ѕi�]��A�͉X�쏧���Ȃǂ̑��Y����u�����̂ŁA���̌o�c���Q�����P���ꂽ�̂ł������B
�@�Ȃ��A�������ł���c�ǂ̐ē��g�V�傪�句���A�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɖ�c�ǒ{���g����ݗ����ė��_�̐U���ɓw�߁A���a�Q�N�ɂ͖،Ó���������Q�R��������ȂǁA�ϋɓI�ȗL�{�����_�Ƃւ̓]�����i�߂��Ă����B
���������H��̗U�v
�@�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�R��̐ΐ�_��Ńo�^�[�������̂��͂��߂Ƃ��A�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�ɂ͘h�̑��ō��������Y�������̕�������w�����ăo�^�[������ȂǁA�������Y���ꂽ�����͌l�o�c�̐����Ɉˑ�������Ȃ������̂ł���B
�@�������A�吳�X�N���_�_�Ƃ̊��H�𗏔_�ɋ��߂Ĉȗ��A�ϋɓI�ɓ������B�ɏ��o���A���P�O�N�ɂ͈�ʔ_�Ƃɂ����y���Ď��瓪�����R�P�R���ƂȂ�A�Ȃ������̌X���ɂ������B���̂��߁A�����ؑ���ܘY���͂��ߔ~�����\�Y�E����Ǐ��E���쒼����L�u�����v��A���Y����鋍���̘̔H�m�ۂ̂��ߗ�����Ђ̕��H��U�v�ɂ��Ėz���������A������Б��ł͕��H��ݒu�̍̎Z�x�[�X�Ƃ��āA�����S�O�O�`�T�O�O���ɒB���邱�Ƃ������Ƃ��Ď����A���̎�������Ԃ܂��ł������B
�@���̕��H��U�v�̉ۂ́A���_���_�̐����ɂ������d����ł��邾���ɁA���������Ă̗U�v�^���Ɛΐ�_��⍡���_��̋����o���́A�~�����\�Y�ɂ������̐V�K�����Ȃǂ̓w�͂ɂ���Ă悤�₭�K�v�������m�ۂ��A��Б��ƔM�S�Ɍ��������ʁA���P�P�N�U���k�C������������Ђ����_�Y�Ƒg���̂ł�Ղ�H����������ĉ��{�݂Ȃ���W������A�����̎�����J�n�����̂ł���B
�@�������āA��������ɑS���L���̗��_�n�Ə̂�����b���z���ꂽ�̂ł��邪�A���P�Q�N�V���ɂ͓��Ђ����_�H������݂��Ė{�i�I�ȑ��Ƃ��J�n���A���������ł͂Ȃ��A�אڂ��闎���E���������ʂ̋������D�ԗA���������ďW�ׂ����̂ł���B
�����W�����ƕ��q�@�i�ʐ^�j

���_�̕s���Ƌ�������
�@�O�q�̂悤�ɂ悤�₭�O���ɏ��A���肵�����ɂ݂��������̗��_�ł͂��������A���̓]�����ƂȂ�����ꎟ����́A�C�O����̓����i�̗A�����������Ă킪���̓��ƊE���������A����ɉ����Ē����ɂ킽��s���̉e�����A���Y�����̒ቺ�������Ђ̎��ꐧ���ȂǂƂȂ��Đ��Y�҂ɂ�������ȂǁA�S�ʓI�ɗ��_�Ƃ��s���ȗ���ɂ�����A�K�������y�ςł����ł͂Ȃ������B
�@���ɁA�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�X���̊֓���k�Ђɒ[��������i�A���ł̈ꎞ�Ə�������A�����O���Y�����i���������č��Y�����i�͑��ʂɑ؉݂���ȂǁA�s���͂܂��܂����������Ԃł������B�����������Ƃ���A���Ɖ�Ђł͌��������i�����������A��������̋����ɂ��s���i���i�Q�����j�������A���������̐�����}�������߁A���_�Ƃ͑傫�ȑŌ�����ł������B���̂����A�Q�����̓o�^�[�̐��������ƂȂ�ɂ�������炸�A���̔������ꉿ�i������߂Ĉ����ł���̂ɑ��A���Y�҂��q���̎���p�Ƃ��ĉ�Ђ���w������E�����͑����Ȋ����ƂȂ�ȂǁA�s�����ȓ_�����������B
�@���̂悤�ɁA��Б��Ɛ��Y�ґ��Ƃ͏�ɗ��Q���Η����A���ҊԂ̕������₦�Ȃ������B
�@�������A�ߏ�Q�����ɂ��Ă̕s���_�Ƃ��āA���Y�҂����������邱�ƂƂȂ�A���_���������̗͂������đg�D�I�ɍH����o�c���A����ɁA�̔��@�ւ�݂��ė��_�Ƃ̋��łȊ�b����邽�߁A�吳�P�S�N�i�P�X�Q�T�j�T���Y�Ƒg���@�Ɋ�Â��u�k�C�������g���v�����A���P�T�N�R���ɂ͑g�D��ύX���āu�k�C�������̔��g��������v�i�����j�Ƃ��A�S���I�g�D�֔��W�̑��|���肪����Ă����B
�@���̂悤�ɁA���_����芪���[���ȏ�Ԃ��A���ڊԐڂ��킸�A�]�������ɂ����铖���̗��_�ɂ����Ȃ��炸�e�����y�ڂ��Ă������̂Ǝv���邪�A���ꂪ��̓I�Ȗ��Ƃ��Č��ꂽ�̂͏��a�U�N�i�P�X�R�P�j�̂��Ƃł������B���Ȃ킿�A���N�V�������ɂ������{�����i������Ёi���a�Q�N�X���k�C�����������Ђ����̕ύX�j�̔��_�H��ł́A����܂łP���P�S�K�V�Ђł��������̂��X�K�R�ЂT�т܂ňꋓ�ɂR�U�E�S�p�[�Z�\�g�ɋy�ԓ����̒l�������s�����̂ł���B
�@�������A�������̎���ꐧ�����\�肵�Ă��邱�Ƃ��ʒm���ꂽ���Ƃɂ���āA�ɂ킩�ɖ�肪�\�ʉ������B�����ɑ���ˑ��x�����߂������_���̋����͂������傫���A�������ł��������B�����A���Ɖ�Г��Ɏ������������엏�_�g���Ə̂���g�������������A���̑g���ɂ͂��������傫�Ȗ��ɑΏ�����\�͂͂Ȃ������B���̂��߁A���̍ہA���ڎ���̎�ŋ������������悤�Ƃ���_���c���h�ƁA��ނȂ����u�Ƃ��Ă����e�F�����Зi��h�̓�h�ɕ�����A�݂��ɂ��̂�������đ����Ƃ����A�����鋍���������N�����̂ł���B
�@�_���c���h�͂P�O���Q�O���ɉ���J���A���炪�o�����āu���_�g���v���������A����̎�ŋ������������悤�Ɛ}���Ă����B�������A���������_���c���h�̓����ɂ�����炸�A��Ђł͂P�Q�����ɂT���̎��ꐧ�����{��ʍ����đ������{���邱�ƂƂ������߁A���悢�掖�Ԃ͐[���������B���̎��Ԃ�J�������n���x�����͋}����A�n���E�O�R�E��u�E�_�U�̊W�e���������ė�����K��A�P�������c�����̂ł���B���̌��ʁA�@�P�A�����Ƌ��c���ĉ�Ђ̐��������������������邱�ƁB
�@�Q�A���Y�҂͍����Б��̂����Ȃ�\�o�������Ă��u���Y�����͐��Y�Ҏ��珈�����邱�Ƃ𗧑O�Ƃ��e�����Y�Ƒg���ɂ����ċ��������A�e�Y�Ƒg���͖k�C�������̔��g��������i�����j�ɉ�����������ɂ�菈�����H����v���Ƃ������Ƃ���B
�@�R�A�P�Q���������ɗ�����ɉ����̎葱�������邱�ƁB
�@�S�A��Ђ̏��v�����͂��ׂė�����狟��������̂Ƃ����Y�ҌX�Ŕ̔����Ȃ����ƁB
�Ƃ��������������̕��j�������Ƃ̊ԂɊm�F���ꂽ�B
�@����ɁA�����Ɠ��Ɖ�Ђ̊Ԃł́A���V�N�P���P�T���u���������Ɠ����i�̓����������v�\���A
�@�P�A�������ӔC�������ē��Ɖ�Ђ̕K�v�Ƃ��錴���������������邱�ƁB
�@�Q�A���Ɖ�Ђ́A�o�^�[���̔����Ȃ����ƁB
�@�R�A�����͗����̐����̔������Ȃ����ƁB
����|�Ƃ���O�匴�����m�F���A�����镪�Ɛ��x���m�������̂ł���B
����{�����i�i���j���_�H��@�i�ʐ^�P�j

�k�C�����_�̔��g���A����_�����H�� �i�ʐ^�Q�j

�@�������āA���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�P���u���_���_�̔����p�g���v���ݗ������ƂƂ��ɁA�����̔��_�o�������݂����A�Q���������{�����i������Д��_�H��̐ݔ��𗘗p���āA�o�^�[�̐������J�n�����̂ł���B�����̏W�����́A���_�̂ق��둾�E�������E�������E���I�Ȃǂɋy�сA���N�W����������H��̌��������ɐ����H��̐V�݂ɒ��肵�A�X�N�R�����瑀�Ƃ��J�n�����̂ŁA���Y�����͂���瓝������ɉ����č����I�ɏ��������悤�ɂȂ����B�Ȃ��A���̊Ԃ̂W�N�P�O���ɑ���{�����i������Д��_�H��́A�������ي�����Д��_�H��ƕς���Ă����B
�@���̂悤�Ȍ����������������s���Ă���Ԃɂ��A�����̓��������͑����̈�r�����ǂ�A���a�W�N�ɂ͂R�O�S�O���A���{�ː��V�W�R�ˁA�P�˕��ςR�E�W���ƂȂ�A����ʂ͎��ɂQ���Q�P�S�O�ɒB���Ă����B
�@�������A���������̌����ɂƂ��Ȃ������앨�͔̍|�Ƃ��̌��������낻���ɂȂ��Ă������߁A�������ቺ���A���Y�����̂V�O�p�[�Z�\�g���Q�����ɂȂ�Ƃ����V���ȓ���ɒ��ʂ����̂ł���B
�@���̂��߁A�k�C���{�Y������A�k��_�w�����̑��W�@�ւɂ�鑍�������̌��ʁA�_���y��̉��ǂƖq���͔̍|�Z�p�ȂǂɊւ���K�Ȏw�����j�����Ă��A�����앨�𒆐S�Ƃ���֍�̌n�������ꂽ�{�i�I�ȁu���_�����v�̊m�����}���Ă������̂ł���B
�g���R���i�X�Ђ̍���
�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�T���������B�̑�G�Ƃ�������u�g���R���i�X�����v�ɂ��`�������Y�����G�Ǔ��y�����ɔ������A�S���{���E�����|�Ɋׂꂽ�B���̔N�P�O���ɂ͓������암���ɂ����ُ̈�ȗ��Y�����������̂ŁA�������̑S�{���i���P�S�U���A�Y�R���j�ɂ��Č��f�����{�����Ƃ���A���S�R���i�R�O�p�[�Z�\�g��j�A�Y�R���i�P�O�O�p�[�Z���g�j�Ƀg���R���i�X�������������ꂽ�B
�@���̂��߁A���ł͋}���哯�����ɑ��h�u�̐�����������ƂƂ��ɁA�����ɑ��Ă����₩�Ȗh�u�ǂ̏o����v�����A���n�ɖh�u�ǖ{����u���Č��f�Ǝ��Âɖ��S���������̂ł������B������암���ɂ����Ă��S����������v���͂��Ă��̑�ɂ�����A���f���̐ݒu����h�u��Ƃ̕��S�A���ނ̒��B�ȂǑS�ʓI�ȋ��͂𑱂������ʁA���̐��ʂ�����A���P�Q�N�S���ɂ͊��S�Ƀg���R���i�X������o�ł��邱�Ƃ��ł����B�������āA�҈Ђ�U��������암���̃g���R���i�X�Ђ́A�Ƃ肠�����I�~����ł����̂ł���B
�@�������A���Ԃ�[���Ɏ~�߂��F�������́A���̔N����ɑS���{���̌��f�����{���邽�߁A�W�_���ɌĂт����đS����ۂƂ���u�h�u�g���v���������A�������炪�g�����ƂȂ�A�e�����Ɍ��f�����̑���݂���ƂƂ��ɁA�����ɑ��{�i�I�Ȗh�u�ǂ̏o��v�������B�����ɂ����Ă����̗v���ɉ����h�u�ǂ�ݒu���A���f�����Ď��Âɓw�߂����ʁA�g���R���i�X�ɂ�鑽���̎����̐��B��a���A�܂��A�����ۗL�����������A���̂����A�ɐB��Q�ƂȂ鑼�̎�������������Ƃ������ʂ����킹�āA�����Ԃ�ǍD�Ȑ��т��グ���̂ł���B�������A�ߗג����ŋ��𑼊Ǔ��ֈڏo����ꍇ�́A�����܂ň����t���Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ɑ��A���Ɍ������i��L���铖���̋��́A���ł��ڏo�ł���Ƃ��������I�Ȍ��ʂ����ꂽ�B
�@���������̔��ʁA�d��Ȏ��Ԃ��������Ă����B���Ȃ킿�A��Y���̂������̂قƂ�ǂ��g���R���i�X�Ɋ������Ă������Ƃł���B���̂��ߓ����ł́A
�@��A�����������퉲���͓j�E�����ɕt���A��[�퉲���ɂ͍w�����i�̌܊���⏕����B
�@��A���������퉲���ɂ��Ă͊e�{�Y�g���ɂ����āA�ӔC�������Ď��Â���B
�Ƃ������j�ł���ɑΏ��������A�����̊�����Y���̂��������������͂Q���ŁA���̑��͕��������ł��������߁A�{�Y�g���̎��Âɂ܂Ƃ���ƂȂ�A�X�V�͔F�߂��Ȃ��Ƃ�������ł������B���Ƃ����������ł����ۂɂ͎�t���s�\�ł���A���Âɂ���ĉ���Ƃ��Ă������p�����Â�K�v�Ƃ��邽�߁A��t���̓K������������s�\������̂ŁA�_�ƂɂƂ��Ă͑傫�ȑŌ��ł���A�������_�̑O�r�ɂ��傫�ȏ�Q�ɂȂ肩�˂Ȃ����ł������B���̂��ߒ����́A�����̕����H�꒷�A�������ق̐{���H�꒷���̑��̗L�u�ƂƂ��ɁA�ĎO�ɂ킽�蔪�_�̎����i���A�늳�S��Y���̍X�V���Â������ʁA�e�ՂɊ�����j��ύX���Ȃ������������A�U���Q�T�����ɜ늳��Y���S���̍X�V��F�߁A�܂��A�w�l��Y���ɂ��ĉ��i�̌܊����⏕����邱�ƂɂȂ�������łȂ��A��Y���̍w���ɂ��Ă������̐ϋɓI�Ȃ�������ɂ��A�}���ɐV��Y�������邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�������ӂ̔茚��
�@�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j����_����̊e�����ɒ{���g�����������A���_�_�ƍĐ��̂��ߗ��_�ւ̓]���������Ă���A���W�ւ̋��̓������ǂ������Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł��邪�A���ꂩ�炿�傤�ǂQ�O�N�ڂɂ����鏺�a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�ɂ́A���������R�S�X�S���A����ː��W�R�T�ˁA��˕��ςS�E�Q���𐔂���܂łɂȂ����B
�@���̗��_�U�N�Q�O�N���L�O����ƂƂ��ɁA���_�_�Ƃ̐U���ɍv�����Ă��������Ɋ��ӂ̈ӂ�\�����߁A���_���_�̔����p�g���̕~�n���ɁA���g���E�������_�H��E�������ٔ��_�H��̎O�ҋ����ɂ���āA������u�������ӂ̔�v�����������B��́A�����Q�E�Q�W���[�g���A�����������炢�̎��R�ɁA���̓����������䐴�̊������ɂ�������_���̊�с@�����Ɋ������Ɛ[�����ݍ��܂ꂽ���̂ŁA�W���Q�������̊W�҂�_�����W�܂�A�������ӍՂƂƂ��ɐ���ȏ��������s�����B
�������ӂ̔�@�i�ʐ^�j

�@����́A�������̓������ǂ�A���Ɉ��肵�����_�̈�ɒB�����_���̐S����悭�\���������̂ŁA�Ȍ�͖��N����Ȋ��ӍՂ��������Ă���B�������A���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�ɂ͎��{�����R�U�Q�R���𐔂���Ɏ��������̂́A�푈�̉e�����A����_�Ƃ��Ă��̌サ�炭�͌����̌X�������ǂ����̂ł���B
�{�����j�a�̔���
�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j����P�Q�N�ɂ����ăg���R���i�X�����ɔY�܂���Ȃ�����A�S�_������̂ƂȂ��Ă����o�ł����̂ł��������A�P�V�N�Ɏ����č��x�͒{�����j�a�̔����ɂ��A�ĂёŌ����邱�ƂƂȂ����B
�@�{�����j�a�ɂ��ẮA�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�Ɏ{�s���ꂽ�u�{�����j�\�h�@�v�Ɋ�Â��A���N�P�����̗Տ������ƃc�x���N���\�n�����ɂ���ė\�h�u�����Ă����B�Ƃ��낪���j���̔������݂�ƁA���a�P�P�N�ɂT���A�P�Q�N�ɂP���A�P�R�N�ɂS���Ɣ�r�I���Ȃ��������A�P�S�N�ɂP�W���A�P�T�N�ɂQ�Q���A�P�U�N�ɂQ�W���Ə��X�ɑ���������A�P�V�N�ɂ͂R�R���̜늳���𐔂����̂ł������B
�@���̂��ߒ��́A�S���_�Ƃ̗����Ƌ��͂�ƂƂ��ɁA�����{�Y�ۉƒ{�q���W�̑������ɂ���āA���̖o�ł������đS�{���̌��j���������{�����̂ł���B���̌��ʁA��Վ������łP�U�O���A��O�������ł͂T�Q�������A���v�Q�S�T���̜늳�����o�����_�Ƃ́A�o�c���o�ϓI�ɂ��傫�ȑŌ����邱�ƂɂȂ����B�������āA�_�Ƃ͕s���̂����ɂ��̔N�𑗂������A���N���{���ꂽ�����ł͜늳���͂킸���S���Ƃ����D���тɏI���A���̌���傫�Ȕ������݂邱�ƂȂ����ڂ��Ă���B
�펞���̗��_
�@���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�R���k�C���̓��Ɖ�Ђ͖k�C�����_���Ђɓ�������A�����̖������ي�����Д��_�H��������̐����H��������ɋ��_���Ђ̍H��ƂȂ����B�܂��A����ƕ��s���Ĕ_�ƒc�̂̍ĕҐ����i�߂��A�����E�k�A�E�Y�Ƒg���k�C���x���̎O�c�̓����Ƃ����`�ŁA�����͓��N�P�O���ɉ��U�����B
�@�������āA���_���Ђ̖��̂��ƂɑS���̓��Ƃꂵ�A�펞���������̒��Ŋe�펖�Ƃ��܂��Ĕ��W�𑱂��邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�푈���������Ȃ�ɂ�Ă��ׂĂ��펞�̐����ɑg�ݍ��܂�A�_�ƌo�c�ɂ����Ă��n�͂̈ێ����i�����Ƃ��闏�_�́A�āE���Ȃǂ̎�H���o���P��`�Ƃ��鐭��ɉ�����A����ł͐���̊g��ɂ���Ēj�q�s�N�҂̉�����A�R���H��ւ̒��p�������ƂȂ��āA��J���͂͑������ʼnƂ𗣂�A�c���ꂽ�N���͕w�l�Ǝq����ɉc�_�𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ԂƂȂ����B���̂��ߍk�n�͎���ɍr�p���A�����̊Ǘ����v���ɂ܂������A��������������X��������Ă����B
�@���a�P�W�N�ɂ͔_���Y�Ƒg���A���n�{�Y�g������������Ĕ_�Ɖ�ƂȂ�A��ɂ͒������A�C����Ƃ����悤�ɁA�펞��������i�Ƃ��т����Ȃ������ʁA�����̓��������͂R�O�O�O��������A�I���̂Q�P�N�ɂ͂Q�O�U�W���ƁA���a�S�N�̎��瓪���܂Ō�ނ����̂ł���B����ɁA�I��ɂ���ĕ����҂�C�O���g�҂��}���A�H�Ɠ��蔲���邽�߂̔_�Ɛ��Y�����͂���������������A�y�n�Ƃ����y�n�͉\�Ȍ���H�Ƒ��Y�Ɍ�����ꂽ���߁A�����̎���͎���ɍ���ƂȂ�A�����̐��Y�͒��������������B�Q�Q�N�̓��v�ɂ��A���������Q�P�W�T���A����ː��V�P�Q�ˁA�P���N�̎Y���ʂP���R�V�R�O�ŁA���a�P�U�N�ɔ�ׂ�Ɠ����łS�O�p�[�Z���g�A���ʂłS�W�p�[�Z���g�̌��ƂȂ�A���_�̑O�r�ɕs�����犴��������ł������B
���_�N������
�@���m�̐��E�ɒ��悤�ȓ����̗��_�o�c�̑O�r�ɂ́A���܂��܂ȏ�Q������A�������̖��ɒ��ʂ����̂��܂����R�ł������B�������_���͂��̋��ɗ����������A���_�U���ɂЂ�������g�̂ł��邪�A���a�S�N�ɔ��_���{�����lj�̗L�u�R�P�����A�i����ǂ�ڎw���]���̃G�[�A�V���[�ɑウ�āA�D�y�ߍ݂���z���X�^�C����i�I�����_�̃z���X�^�C���̎Y��ŁA���炾���傫���A�����̂͂�_�������č���ʂ����ɑ����̂������j�����R�P�������A�����̊�b�i��̂��Ƃ�������肵���̂��A���̓w�͂̌���ł������B
�@�܂����̂���A���_�o�c�ɂ��ď�ɋN���鐔�����̖��������������A������������Ă䂱���Ƃ���_���O���[�v�u���_���_�Ȋw�������v�Ə̂���g�D���������B������̑g�D�́A����̌����{�݂⎖��������������A���̌�������u�����肵�����̂ł͂Ȃ��A������������O���[�v�ɂ����Ȃ��Ƃ�������܂łł��邪�A�_��⓿��_��A���Ɖ�Ђ̋��͂����āA�y��̉��ǁE�h���т̑����E�����͔̍|�i���ɐԃN���o�[�j�E�������̌��������Ȃǂ̏����Ɏ��g�݁A�������_�̔��W�ɐs�������̂ł������B���a�Q�P�N�ɂ́A�b��̕����Ό��q�����u�t�ɏ����ĕ�����J�Â������A���ꂪ���݂Ȃ��p�����Ă���~�����_�w�Z�̎n�܂�ł���B
�@���A���_�o�c�̊�@�ɓ��ʂ����������a�Q�Q�N�A�k�C�����_����������Ёi�Q�P�N�P�Q�����_���Ђ����g�A�����Ƃ̑O�g�j���S���̍H��Ɂu���_�N������v�j�v��z�t���A�����闏���̌������Ăт������B���̌��ʁA������v�������͂��߁A�S���e�n�ɑ��X�Ɨ������������ꂽ�̂ŁA����ɑS���I�ȘA���g�D����铮���ɔ��W���A���N�V���Q�V����y�@�_�w�Z�őn������J����u�k�C�����_�N�����A���v���������ꂽ�̂ł���B�����ď���ψ����ɂ́A���_���_�Ȋw���������ォ�痏�_�o�c�̉��P�����Ɍo���L�x�Ȃ����A�����̑n���ɂ��s�����������̑��c�������I�C���ꂽ�B�܂��A���N�P�Q���ɂ͒����e�������͂��߁A�O�a�E�����E���z�E���ɁE�둾�Ȃǂ̊e�������܂߂āA�����Q�O�̒P�ʒc�̂������ė������_�n���A�����g�D���ꂽ�B�Ȃ��A�k�C�������A�́A�R�O�N�P�Q�����k�n���ɋ����g�債�Ėk���{���_�N�����A���Ɖ��̂��A����ɁA�R�W�N�P�Q���ɂ͑S���ɍL�߂ē��{���_�N�����A���Ƒg�D�����߁A���W�I�g�傪������ꂽ�B���̗����̔�����������ψ����ƂȂ������c�����́A�S�Q�N�P�Q���ɗE�ނ���܂ŁA���悻�Q�O�N�ɂ킽�肻�̐E�߂Ċ����̂ł������B
�@�܂��A���c�ψ����E�ނ̂��ƂS�R�N�ɏ�C�ψ��ƂȂ��������̉����F���́A�S�T�N���畛�ψ����߁A����ɁA�T�R�N���瓖���o�g�Ƃ��ē�l�ڂ̈ψ����ƂȂ�A�S���I�ȗ���ŗ��_�E�̔��W�ɐs�����Ă���B
�@�Ȃ��A�S���V�u���b�N���c��݂̘A���𗬂�}��A�����ɂ����鋤�ʖ����������c���邽�߁A�S�U�N�P�P���ɖk�C�����c���ݗ����A�����������F������ɐ�����Č��݂Ɏ����Ă���B
�@�܂��A���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�Q���ɔ��_�n���A���ł́A�S�����̏��q�������g�D���A�������P�ɗ͂𒍂��ł���B
���_�Ɠ��̊C�O���K
�@���a�Q�R�N���������O�L�u�k�C�����_�N�����A���v�i�ȉ��A�����Ə̂��j�́A�u�k�C���̗��_�𐢊E�I�����ɓ��B������B�v���߂ɁA�k���ɂ����闏�_�̎��Ԃ��������k�C���Ɏ�����悤�ƁA���a�Q�V�N�T���ψ������c���������w�Ƃ��Đ����ƁA�k�C���o�^�[�A���_�_�����̑��W�c�̂̌o�ϓI�����ēn�����A��P�N���ɂ킽��f���}�[�N�A�X�F�[�f���A�m���E�F�[�A�h�C�c�A�I�����_�A�A�����J�̏������_�ƂɏZ�ݍ��݁A�o�c�̎��Ԃ�̌����A�Q�W�N�P�O���A�������B�A���㓹���e�n���͂��ߊ�茧�Ȃǂŏ���u�����s���A����Ɂu���̌����f���}�[�N�v�����_�o�c�̉��P�ɓw�߂��̂ł���B�����������c�ψ����̓n�����K���_�@�Ƃ��āA�������͂��ߊe���_���ƒc�̂̌㉇�̂��ƂɊC�O���K�̂��ߓn�q���闏�_�Ƃ��N��ǂ��đ�������悤�ɂȂ�A���ʋߔN�C�O����̎��K������������悤�ɂȂ�A���ۓI�Ɍ𗬂�[�߂�悤�ɂȂ����B
�@�������Đ������̊C�O���K���͔_�����P�̌����͂ƂȂ��Ċ��Ă���B
�@�܂��A����Ƃ͕ʂɓ������a�S�W�N����T�U�N�܂ŁA�u�N���{�����N�A�ƒ�w�l�C�O���C���Ɓu�����̑D�v�ɑ��Ă�����e�E��萔���̐N�w�l���Q�����A����A�W�A�A������K��A�F�D�Ɛe�P��[�߂��̂ł���B
�{�Y�U����
�@�����m�푈�̉e�����ĉƒ{�����������X���������悤�ɂȂ������Ƃɑ��A���A������ъW�@�ւł́A����n�тɂ�����{���̈���I���W��}�邽�߁A�e��̒{�Y�U�����W�J�����B
�@���Ȃ킿�A���͏��a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�u�{�Y�U���T���N�v��v�𗧂āA�g�����_�Ƃ̉����h�ɏ��o���A���Q�S�N�ɂ́u�k�C���ƒ{�ݕt�K���v�A������A���L�����̑ݕt���x��n�݂����̂ł���B���̐��x�́A�����_�Ƃɑ��s�����܂��͔_�����o�R���đݕt���A�ݕt���������Y�����ŏ��̎q����Ԕ[���邱�Ƃɂ���Ė����ŕꋍ��������Ƃ������̂ŁA�����K�ȐU����Ƃ��Ċ��}���ꂽ���̂ł��������A���̐��x�͈ꉞ�R�P�N�x�őł���ꂽ�B�������A�ԊҎq���̍đݕt�͂S�U�N�x�܂ő������Ă����B
�@�����ɂ����Ă͂����������x�̎{�s���āA�Q�T�N�S���u���_���ƒ{�ݕt���v�𐧒肵�A�Q�T�N�x��֒n��i���A�㔪�_�j�A��c�����n��i���A����j�Ɋe�P�O�����͂��߁A�Q�U�N�x��֒n��w�G�[�A�V���[��V���A�Q�V�N�x���Ó��i���A�l���j�A��O�n��i���A�M�c�j�ւT����]�݂����B����ɁA���P�Ƃ̎��ƂƂ��ĂQ�U�N�x����Q�X�N�x�܂Ŗ��N�P�O�������w�����Ė����_�Ƃɑݕt���A�R�Q�N�x�ɂ͂��̊�b���͂T�R���ɒB�����B�����ݕt���ɂ��ẮA���N�t�H�Q��u�ݕt�����{�Ǘ��i�]��v���J�Â��Ď��{�Ǘ��ɓw�߂��̂ł���B
�@�܂��A���a�R�R�N�S���ɓ��́u��ʌo�ϔ_���ƒ{�Y�U�����v�𐧒肵�A���_�U���̘g�O�ɂ����ה_���Ƃ�ΏۂɁA�߂�r�E�{�E�Ȃǂ̒����ƒ{���W�c�I�ɓ������邱�Ƃ����サ�A���̎��Ƃ����{����s�����ɑ��ĕK�v������ݕt����Ȃǂ̎{����u�����B����ɑΉ����ē����ł́A���N�U���u���_����ʌo�ϔ_���ƒ{�Y�U�����v�𐧒肵�A��Ƃ��Č{�E�̒����ƒ{�̑ݕt���Ƃ��s�����ƂƂ��A���_�E�������_���Ƌ����g����J��A�{�{�_�Ƌ����g����ʂ��A�S�T�N�x�܂Ŗ��N�Q�O�O���O��A�{�V�A�W�O�O�O�H�̗\�Z���v�サ�āA��ה_���Ƃ̌o�c����̈ꏕ�Ƃ����̂ł���B
�@���̂ق��A���͒{�Y�U����̈�Ƃ��āA�����̎��{�Ǘ��̉��P��}�邽�߁A�Q�U�N����S���I�ɓ����o�ό��莖�Ƃ����{���邱�ƂƂ��A���{�����̎Y���\�͂�I�m�ɔc�����Ă��̌�����������Ƃ�ڎw���A���_�Ƃ�g�D���āu�����o�ό���g���v�ݗ������サ���B����ɂ�蓖���ł́A���N�������ƂɒP�ʑg����ݗ����A�x������ѓ��̘A����ɂȂ���u���_�������o�ό���g���A����v��ݒu���A�o�c���P�̂��߂̈�팟��Ɠ����̂̌���ł����팟������{�����̂ł���B
�l�H�����̕��y
�@�k�C���ɂ����鋍�̐l�H�����́A���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�ɔ_�яȂ���Â��Đ�t�s�̒{�Y������ŊJ�Â����A�l�H�����u�K��̏o�Ȏ҂𒆐S�Ƃ��āA�^����̔_�Ǝ�����{�Y���Ŏ����I�ɍs�����̂��n�܂�Ƃ����Ă���B���̌�A�P�W�N�Q���ɓn���E�w�R�E��u�E�_�U�x���Ǔ��̊W�Z�p���P�O�����������ɎQ�W���A�l�H�����̍u�K����J�Â������Ƃ��A���n���ւ̕��y�̒[���ƂȂ����B
�@���̐l�H�����̌��p�ɒ��ڂ������_�_�Ɖ�A�P�ʒc�̂Ƃ��Ă͂܂������S���ɐ�삯�āA�����Ɏ��Ƃ��J�n�����B�Ƃ����������A�A�����J����A��������Y���h�J�[�l�[�V�����E�K���@�i�[�L���i���[���h���琸�t���̎悵�A���c�F�����L�̃z���X�^�C���펓���g��O���[�Y���h�Ɏ������Ď�ق������̂������ɂ�����l�H�����̎n�܂�Ƃ����A�Ȍ�A�Z�p�̐i���ƂƂ��ɂ��̌��p���悤�₭�F�������悤�ɂȂ����̂ł���B
�@���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�R�����_���_�Ɖ�����g���Ĕ��_���_�Ƌ����g���������������A���̂��납��l�H�����ɑ���w�����j���悤�₭�m�����A�{�i�I�ɂ��̕��y��}��ƂƂ��ɁA������Y���̑I���ƕ����ɂ������Y�����{�Ǘ���̐ߌ����}��ꂽ�B
�@�Ȋw�Z�p�̐i���ɂ��A���a�Q�S�N�W�����납��u�����N�G���_�ɏՉt�v�ɂ�鐸�t�̗Ⓚ�@�ɂ���Ē������͕ۑ����\�ƂȂ�A��ٗ��̌���Ɖ������A���ɉ���I�Ȑi���������炳�ꂽ�̂ŁA�Q�T�N�T���A�����J�̓V�R�����ǃ��b�`���̍D�ӂɂ��A�V�J�S�s�̃J�[�`�X�L�����f�[�q��̗D�G��Y���Q������̎悵���P�P�����̐��t�̕������邱�ƂɂȂ����B���̐��t�́u���Ԑ��t�v�ƌĂ�A�V�J�S����H�c�܂ŋ�A����A�������_�яȉƒ{������ɓ��������ƋD�Ԃœ����ɓ������A�T���P�Q���ɂP�O���̎����Ɏ������ꂽ���A���̌��ʁA�t���̎O�֖L�����L���g�A�C�_���b�^�E�R�����_�C�N�E�A�[�`�X���h�P����������ق��A���N�Y�����o�Y�����B���̗Y�����g�A�C�_���b�^�E�}�X�^�[�s�[�X���h�Ɩ�������A��Ɏ�Y���Ƃ��Ė،Ó��_�Ƌ����g���̐l�H�������łT�N�ԋ��p����A�D�G�Ȑ��т��グ���Ƃ����B
�@���̐l�H�������L���{�i�I�Ɏ��{�����悤�ɂȂ����̂́A���a�Q�Q�N�ɐ��肳�ꂽ�u�ƒ{�l�H�������{�ݕ⏕�K���v�����{����Ă���ł���A����ɂ�蓹���ɓ��N�P�W�����A���Q�R�N��ꂩ�����͂��߂Ƃ��āA�Q�U�N�ɂ͑������ォ�����ݒu���ꂽ���A���̔��ʁA���ꂪ�����C���ƂȂ�A���������Ɖ^�c�ɍ�������A�L�{�_�Ƃ̔��W��j�Q����̂ł͂Ȃ����ƌ��O������Ԃł������B
����_�Ƌ��ϑg���k�n���x���i�ʐ^�P�j

���_�l�H�������i�ʐ^�Q�j

�@���̂��ߓ��́A�u�ƒ{�l�H�������T���N�v��v�𗧂āA�l�H�����Ԃ̑g�D����^�c�̍�������}��A�{�݂̏[���ƋZ�p�ʂ̌���ɓw�߂邱�ƂƂ����B�����đS�����P�P�̃u���b�N�ɕ����A���ꂼ��Ƀ��C���X�e�[�V������݂��ėD�G��Y���̔z�u���v�悵�A����i�n���E�w�R�j�ɂ����Ă͒n���I�v���Ɠ������x�Ȃǂ��l�����āA�����Ƀ��C���X�e�[�V�������u����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�������āA���a�Q�V�N�S���ɓ��쐶�Y�_�Ƌ����g���A����i���쐶�Y�A�j�����_���_�Ƌ����g���̐l�H�������{�݂���u����ƒ{�l�H�������v��ݗ����ĐV�������A���㏊���Ƃ��Č���@�[���A�C�����B
�@���a�Q�X�N�x�́A���_���Ɨ������̈ꕔ�����킹�ĂP�T�T�Q���Ɏ������A����ɁA���ْn�族�_�����g�����͂��߁A���ё��E��쑺�E�X���E�������E���������E�k�w�R���E����������ђm�����̊e�_���ɂP�O�U�P�����̐��t�������B��ِ��т��Q�V�N�x�W�O�p�[�Z���g�A�Q�W�N�x�łW�U�E�Q�p�[�Z���g�ł��������A�Q�X�N�x�͂W�X�p�[�Z���g�ƒ������サ�A�l�H�����ɑ���ˑ��x�͂܂��܂����܂��Ă������B
�@����������ɑΉ��������_���_�Ƌ����g���́A���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�P���A����R�W�i��P�Q�U�������[�g���j�̐l�H��������V�z���ē��쐶�Y�A�ɑ݂��t�����A�������B�Z���^�[�Ƃ��Ď��Ƃ̊g�[�Ɛ��i�ɔ��������A����ɓ��쐶�Y�A�ł͂R�V�N�P�O���o�_���U�O�Ԓn���ɐl�H��������V�z���A����Ɉړ]���ċƖ��̏[����}�����B
�@���̌ケ�̐l�H�����Ɩ��͂S�Q�N�S���z�N�����ɈڊǁA����ɂS�W�N�S���ɂ͓���_�Ƌ��ϑg���ւƈ����p����A�k�n���x���ݒu�ƂƂ��Ɂu�k�n���ƒ{�f�Ï��v�Ə̂���A�����Ǔ���Ώ۔͈͂Ƃ��ĉ^�c����Ă���B
�ƒ{�ی��q�����Ɨ��_������
�@�������͂��߂��̑��̉ƒ{�q���̌����ʂ��Ē{�Y�̐U���Ɋ�^���邽�߁A���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�R���Ɍ��z���肳�ꂽ�ƒ{�ی��q�����@�ɂ���ē��͏����߁A�Q�X�N�܂łɑS���l�Z�����ɉƒ{�ی��q�����̐ݗ����v�悵���B�����Ă��̈�Ƃ��ĂQ�V�N�V���P�Q���u�k�C�����_�ƒ{�ی��q�����v���A�������P�O�O�Ԓn���i�����Ə��L�n�j�ɊJ�݂���A���㏊���ɋ{�X������}�����̂ł���B
�@���̉q�����͑n�ݓ����A�������E���_�E�����E�X�E�����E�����E�P�K�E���D���̔����������NJ����Ƃ��A�ƒ{�q���v�z�̕��y�ƌ���A�ƒ{�`���a�̗\�h�i���̌��j�a�E�n�̓`�����n���a�j�Ȃǂɓw�߁A�ƒ{�̓������B�Ɋ�Â��L�{�c�_�̐��i�Ɋ�^�����̂ł���B
�@�܂��A���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�V���k�C�����_�����K���̌��z�ɂ��A�k�C��������������k�C�����_�������Ɖ��̂��A�������������J�n���ꂽ�B�����Ă��̋Ɩ��̓K���ȉ^�c��}�邽�߁A�Q�S�N�V���ɓ����������_���ݏ����ݒu����A�R�z�S��тƌ�u�x���Ǔ��i�]�s���E��Εʒ��E�����s���������j��S�����邱�ƂɂȂ����B�Ȃ��A���̓����������͖،Ó����ݏ��̒S�����ɑ����Ă����B
�@���̒��ݏ��́A�O�L�ƒ{�ی��q�����̐V�݂ɂƂ��Ȃ��Ă���Ɉړ]���A�k�C���������������i�Q�V�N�V�����z�j�Ɋ�Â��������̌����ƁA���̕i�����P���傽��C���Ƃ��Ċ֘A�Ɩ���S�����Ă���B���̌�A�����ɂ킽��@�\�̕ύX�̂��ƁA�S�U�N�X���ɊNJ����َs�Ɠn���E�w�R���x���Ǔ��Ɋg��A����ɁA�S�W�N�T���Ɂu�k�C�����_���������_�x���v�Ɖ��̂���ƂƂ��ɁA�]���̋��Ɍ�u�x���Ǔ��̓��q�E���s�E��J�E���c�̊e�S�������������čL�扻����Ƃ���ƂȂ����B
���_�ƒ{�ی��q�����i�ʐ^�P�j

�@�Ȃ����_�ƒ{�ی��q�����́A�������̂S�O�N�S���A���̈ꕔ�@�\���v�ɂ�蔟�ىƒ{�ی��q�����ɓ�������A�܂��A���_�������͂���܂ł̎������Ŕ_�Ɖ��Ǖ��y���Ƃ��炭�������Ă������A�S�X�N�P�P���ɑ������P�O�W�Ԓn�ɐV���ɂ����z�A�����Č����{�݂����Ă���Ɉړ]�����B
�@�������A���a�T�T�N�x���̋@�\���v�ɂ�藏�_�������͔p�~����邱�ƂƂȂ������A�T�U�N�S���Вc�@�l��������������쎖�Ə������������̎{�݂����̂܂�A�����i�ԎR���Y�j�ȉ��R���ɂ��]�����l���Y�Ғc�̂�����ƃ��[�J�[�Ɉ�������鍇���̂ق��A���Y���\�_���Ԃ̌����������{���Ă���B
�@��W�߁@���x�W�_�n��̌���
���_�U���@�̐���
�@�I�����O��ɓ����̓����������������������A�������͗��_�̊�@�Ƃ������ꂽ�̂ł��邪�A�H�Ǝ������ɍD�]����ƂƂ��ɖk�C���_�Ƃ̐U����Ƃ��āA���_�Ƃ̐U���𒆐S�Ƃ����X�̎{�u�����A���������̑��i�E�����_�Ƃ̉����E�L�{�_�Ƃ̑n�ݎ��ƂȂǂ��i�߂��A�Q���D�]���������B
�@����A���ɂ����Ă����a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�A���_�U���̊�Ղ��m�����A���_�̋}���ȕ��y���W�Ɣ_�ƌo�c�̈���Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āu���_�U���@�v�𐧒肵�A�W���V������{�s�����B���̖@���́A�܂����ɏW�_�n��̐��x�̐ݒ�������A���̒n��̔_�Ƃ̔��B��}�邽�߁A���_��U�����邱�Ƃ��K�v�ƔF�߂�����̒n����A�s���{���m���̐\���Ɋ�Â��_�ё�b���w�肷�邱�Ƃ��߂��B
�@�s���{���m���́A���̏W�_�n��̎w����邽�߂ɂ́A���̒n����߁A���̒n����ɓ������ǂ̒��x�������邩�A�����̎����x���ǂ̒��x�ɂł��邩�A�������Y�҂̋����W���g�D���ǂ̂悤�ɐ������邩�A���Ɛݔ����ǂ����邩�A�����̉��Ǒ��B�̂��߂̎{�݁i�l�H�����{�݂Ȃǁj������̕ی��q���{�݂��ǂ����邩�A���_�o�c�̎w���̐����ǂ���肠���邩�A�Ȃǂɂ��Ă̌v��A���Ȃ킿�A�u���_�U���v��v�����̎葱���ɂ���č쐬���Ĕ_�ё�b�ɒ�o���A��������_�ё�b���K���ł���ƔF�߂��ꍇ�A���̒n����W�_�n��Ƃ��Ďw�肷��Ƃ������̂ł���B
�@�������Ďw�肳�ꂽ�W�_�n��ɂ́A�����闏�_�U������̏W�������m�ɑł��o���ꂽ�̂ł���B���Ƃ��A�L�{�_�Ƒn�ݎ��ƁE���Ǝ{�ݍ����������̗Z�ʊm�ہE���n���ǎ��ƂȂǁA���_�U���v������{���邽�߂̕K�v�o��͗\�Z�͈͓̔��ŕ⏕����ƒ�߂�ꂽ���̂ŁA���a�R�O�N�x����W�_�n��̌��ݎ��Ƃ��W�J���ꂽ�B
�@���̐��x�Ɋ�Â��{���̏W�_�n��́A�R�O�N�x�̎������̂��ƂR�P�N�x�͔��_�n����܂ވ�ꂩ���A����ɂR�Q�N�x�ɘZ�������w�肳��č��v��l�����ƂȂ�A����ɕ�܂����s�����͂P�S�T�ŁA�{���̎�v���_�n�т͂��̂قƂ�ǂ��W�_�n��Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�̂ł���B
���_�n��W�_�n��̎w��
�@���a�Q�W�N�i�P�X�T�R�j�V���_�яȒ{�Y�ǂ́A�O�L�u���_�U���@�v�̐���ɐ旧�����_�o�c���s���ɓK�����A���R�I�E�o�ϓI���n������������n���I�肵�A�n����̗��_���Y�̌o�ω��𑣐i���A�c�_�̈���m���Ɨǎ������ȗ��_���Y���̋������s�����闏�_�n��̌��݂�}�邽�߁u�W�_�n�挚�ݗv�́v�\���A���̒n��I���⎑�����B�ɂ��Ă̍ו�����߂�ꂽ�B
�@���̗v�̂́A�������_�U����Ƃ��ė��_�W�������犽�}����A�e�n��Ƃ��������Ēn��w���ڎw���Ē�͂��߂�ꂽ�B�����ɂ����Ă����N�P�Q���A���������ĂɎ����ꂽ���_�n��A���Ȃ킿�A���������E���_���E�������E�X���E�������̌܂������̊W�҂��W�܂��āA�n��w����邽�߈�ۂƂȂ��ĉ^�����邱�Ƃ����߁A���Q�X�N�P���W���ʂɑ��Ē���o����ȂǁA�^�����J�n�����̂ł���B���̌��ʁA���̐i�߂�n��ݒ��ƂƂ����܂��Ēn��w��̉\�������܂��Ă����̂ŁA���悢�����Ԑ����������邽�ߏ��v�̏�����i�߁A���N�S���u���_�n�捂�x�W�_�v�搄�i�ψ���v���������A��ɔ��_�����A����ɂ��̑��̊e�����������߂��B�܂��A�k�C���W�_�n�挚�݊������C�ψ��ɓc�����_�n���𐄂����ƂƂ����̂ł���B
�@�k�C���W�_�n�挚�݊�����i����E���_���O�j�����z���X�^�C������j�́A�����������Ă���P�V�n��̑�\�҂𐔎��ɂ킽���ď㋞�����A������o�������n��P�V�ɂ��đS���̎w��������̂ł������B�������āA���a�R�O�N�W���_�яȂ́A�S������\�����̂U�X�n��̂�������R�P�n����w�肷��Ɏ��������A�k�C������͌��݁E���H�E����ʁE����E����E�_�U�̂V�n��Ɍ����A���_�n��͎c�O�Ȃ���w�肳��Ȃ������B
�@���̌�A�W���痏�_�Ƃ̏��Ȃ���������n��ɕ�܂��邱�Ƃ͕s�K���ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E�������Ƃ���A�������̗����Ēn�悩�珜�O���A�V���Ɍv�揑���쐬���Ĕ_�яȂ֒�o�����̂́A�R�O�N�P�Q�����̂��Ƃł������B�܂��A�w����邽�ߕK�v�ȗv���ł����������̈ꌳ�W�ׂ̖����A��X�̋Ȑ܂͂����������R�P�N�P���܂łɊe�����Ƃ����ꂼ�ꋦ�肪�������Ē��s���Ă����B����ɁA�R�P�N�Q���ɂ͏]���̑g�D��ύX���u���_�n��W�_���݊�����v�Ƃ��āA�n��w��̂��ߋ��͂ȉ^����W�J���邱�ƂƂ����B
�@�������ď��a�Q�X�N�ȗ��A�W�@�֒c�̂̋��͂̂��ƂɎw��ɂ��ĉ^�����Ă������ʁA�R�P�N�i�P�X�T�U�j�X���Q�P���_�яȍ�����Z�Z�����������āu���_�W�_�n��v�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�̂ł���B
�@�_�яȍ�����Z�S����
�@���_�U���@�i���a��\��N�@����S���\�j��O���A��l���y�ё掵���̋K��ɂ��A���a�O�\�N�\�\���_�яȍ�����\�����i���_�U���@�Ɋ�W�_�n����w�肷�錏�j�̈ꕔ�����̂悤�ɉ�������B
�@���a�O�\��N�㌎��\���
�@�_�ё�b�@�͖��Y
�@�_�U�����W�_�n��̕��̎��Ɏ��̂悤�ɉ�����B
�@���_�W��@�k�C���@�R�z�S�̓��@���_���A��������
�@���_�n��@�����S�̓��@�������A�X��
�@�i�W���̂ݔ����j
�@�W�_�n��Ƃ��Ďw�肪���肵�ړI��B���������߁A�P�O���P�P�����_�n��W�_���݊�����̑�����J�Â��Ă�������U�����B�����ē����Q�T���A���_�n��̗��_�U���𐄐i����ƂƂ��ɁA�߂��J�݂��\�肳��闏�_�������ɑ��鋦�͑̐����m�����邽�߂ɋK����߁A�u���_�n��W�_�����c��v���������A��ɂ͓c�����_�����A����ɐ쑺�����������A����X�����A�ɓ����������ق�������I�o�����B
�@�܂��A�W�_���݂ɋ��͂��A�n�����_���̗��_�U���Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�P�P���Q�V���ɔ��_�����_�����c���g�D���A��ɓc�������A����ɋv�ۓc���_���_�Ƌ����g���������Ă��ق��A�ו��ɐ�啔���݂��āA���ꂼ�ꊈ����W�J�����̂ł���B
�@�W�_�n��̋�̓I�Ȍv��̎����Ǝw���ɂ�����@�ւł���u���_�n��W�_�������v�́A�R�Q�N�P�������_�������ٕʊقɊJ�݁A���㏊���ɋ{�X����ƒ{�ی��q�����������߂���A���悢��W�_���݂̏��ɂ����̂ł���B
�@�����̌v��ɂ��ƁA���_�n��̌����͓����T�S�U�T���A���ʎl����Z�Z�Z�i���_�������R�R�S�O���A�O�����Z�Z�j�ł��邪�A���̎w��ɂ��T�N��ɂ́A�����X�Q�O�O���A���ʈ�Z���i���_�������S�T�O�O���A�Z���j�ɑ��B�A���Y������̂ł���A����I�Ȍv��Ƃ��ĕ]������A���ꂪ������͂��̒n���̌o�ςɑ傫�Ȍ��ʂ������炷���̂Ɗ��҂��ꂽ�̂ł������B�Ȃ��A���̌v����������邽�߂ɁA���̏��_����{�v���Ƃ��ďグ���g�̂ł���B
�@�P�@�y�n���p�̑��i
�@�y�n�̗��p�敪�𖾂炩�ɂ��邱�ƁB�k�n�E���n�E�ђn�ɋ敪���y�n���ō��x�ɗ��p����ƂƂ��ɖ����p�n�̊J���𑣐i����B
�@�Q�@�y�n�����̐���
�@���Ë��r�����������A�q�y���s���A�y�n���p�傷��B���w�k�E�S�y�k���s���ƂƂ��ɑ͉X��̑��Y���͂���n�͂̑��i������B
�@�R�@���n����
�@�i�N�q���n�A�̑��n�Ȃǂ�S�ʓI�ɉ��ǂ��Đ��Y�����コ����B
�@�S�@�_�q���̐���
�@�y�n�̗��p�𑣐i���邽�ߔ_���A�q�������A���_�o�c�̍����I�^�c���͂���B
�@�T�@�_�@��̐����Ɠ���
�@�y�n���ǁE�k�y���ǁE���n���ǂȂǂɕK�v�ȑ�^�_�@������đ��₩�ȉ��ǂ��͂���B
�@�U�@�y�n�ۑS
�@�k�y�h���т̑����ƐX�ю����̕ی쑢���A�R������̂��ߎ��R���Ƃ��s���_�n�̕ۑS���͂���B
�@�V�@���_�{�݂̐���
�@���ɂ̍����I�ȉ��P���͂���A�T�C���E�͔�ɂ��v��I�ɐ������o�c���@�̉��P���͂���B
�@�����������j�̂��ƂɊW�_���̓w�͂Ƃ����܂��āA���_�Ƃɂ�鑐�n���ǂ�{�ݐ������ƂȂǂƂƂ��ɓ����������ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ���ʁA���_�n��̏W�_���ݎ��Ƃ͑����̐��ʂ��グ�A���a�R�V�N�R���R�P���W�_��������������̂ł���B
�@��X�߁@�������{�̐���
�������{�̐���
�@�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j�ꂢ����ł�Ղ��̕s������E���A�P�v�I�Ȕ��_�_�Ƃ̈����}�邽�ߗ��_�Ƃ֓]����i�߂Ă���A���̌㏇���ȑ����X�������ǂ��Ă��������́A�����m�푈�֓˓��̊�@���͂���a�P�T�N�i�P�X�S�O�j�̂R�U�S�Q�����s�[�N�Ɍ������͂��߁A�I�풼��̂Q�P�N�ɂ͂Q�O�U�W���ƂȂ�A���a�S�N�����̓����ɂ܂Ō�ނ���ł������B
�@�������A���̐���������Ɉ��肵�A���⓹���u�����e��̗��_�U����ɂ���ĂQ�U�N���납��悤�₭�̒���������ꂽ�����A�Q�W�A�Q�X�A�R�P�N�ȂǂƑ�������Q����̂��тɋ������ꂽ�L�{�_�ƐU���̎{��ɂ��A�����_�Ƃ̉�����n�͂̈ێ��������}��ꂽ���߁A���̊Ԃɂ����Ă������ȑ����X�������ǂ邱�Ƃ��ł����B
�@���̌�A���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j�������Ƃ̍����ɂ���Ď��{�����͂R�W�P�R���i�W�U�Q�ˁj�ƂȂ�A����ɐ܂��琄�i���ꂽ�W�_�n�挚�ݎ��ƂƂ����܂��āA�Ȍ�͒����ɑ����𑱂��A�R�X�N�ɂ͂U�O�O�O���A�S�W�N�ɂ͂W�O�O�O���A�����ĂT�R�N�ɂ͂��ɑ��N�̖ڕW�ł������P�����ɒB�����̂ł���B
�@�������A����̎��{�ː��́A�Q�V�N�ȍ~�ɂ����鏔���x�̎{�s�A�J��_�Ƃ̓����̓����Ȃǂɂ���đ������A�R�Q�N�ɂ͂W�U�Q�˂ɒB�����̂ł��邪�A���̌�ɂ�����J��_�Ƃ̗��_�␅�c��Ɣ_�Ƃւ̓]���Ƃ��������ł͂Ȃ��A���x�o�ϐ�������̉e�����āA�_�ƌo�c�̋ߑ㉻�ɑΉ��ł��Ȃ������_�Ƃ�A��p�ғ�̂��ߗ��_������̂����o�������ߌ����̈�r�����ǂ�A�S�R�N�ɂ͂T�U�W�ˁA�S�W�N�ɂ͂S�R�Q�ˁA�����ĂT�R�N�ɂ͂R�T�Q�˂ƂȂ�A�R�Q�N�����̂S�P�p�[�Z���g�ƂȂ����̂ł���B
�@�����������{�ː��̌����ɔ��������{�����̑����́A���_�ƌX�̌o�c�K�͂̊g����������̂ɂق��Ȃ�Ȃ����A����́A���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�P�P���ɂ�����u�{�Y���̉��i���蓙�Ɋւ���@���v�̐���A����ɁA�S�O�N�U���́u���H���������Y�ҕ⋋�����b��[�u�@�v�̌��z�ɂ���g�s���������x�h�Ȃǂɂ��A�����Ɉꉞ�̈��肪�݂�ꂽ���Ƃ��A����������ɓ��ݐ点��v���̈�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���ł��낤�B�������A�R�X�N�x������{���ꂽ�_�ƍ\�����P���Ƃɂ�闏�_��Ր����A���Ɂu�n����鎖�Ɓv�Ƃ��Ē��c�琬�q���ݒu���ĂS�P�N�x����琬���̎�����J�n�������ƁA����ɁA�k�C�����_�ߑ㉻�v��i�S�P�`�S�U�N�x�j�A��k�C�����_�ߑ㉻�v��i�S�U�`�T�Q�N�x�j�Ȃǂ̗��_�U����Ɋ�Â��č��肳�ꂽ���̌v��A�u�����P�����̎����v��ڕW�ɐi�߂�ꂽ�e�펖�Ƃ̐��ʂł������B
���̎��瓪����(���̂P�@�����_��)
| �N�� | ���� |
| �����P�P | �R |
| �P�Q | �P�P |
| �P�R | �P�O |
| �P�S | �Q�V |
| �P�T | �T�Q |
| �P�U | �U�S |
| �P�V | �T�Q |
| �P�W | �T�Q |
| �P�X | �R�U |
| �Q�O | �S�W |
| �Q�P | �T�U |
| �Q�Q | �T�S |
| �Q�R | �U�O |
| �Q�S | �T�P |
| �Q�T | �U�W |
| �Q�U | �T�P |
| �Q�V | �T�U |
| �Q�W | �T�W |
| �Q�X | �V�R |
| �R�O | �V�Q |
| �R�P | �V�U |
| �R�Q | �S�O |
| �R�R | �R�T |
| �R�S | �R�U |
| �R�T | �R�U |
| �R�U | �S�O |
| �R�V | �W�S |
| �R�W | �X�Q |
| �R�X | �X�U |
| �S�O | �W�V |
| �S�P | �P�O�P |
| �S�Q | �P�W�U |
| �S�R | �P�U�Q |
| �S�S | �Q�U�V |
| �S�T | �P�W�V |
| �吳 �Q | �Q�T�V |
| �R | �P�V�Q |
| �S | �P�V�S |
| �T | �P�W�S |
| �U | �Q�P�S |
| �V | �Q�T�U |
| �W | �P�V�U |
���̎��瓪����(���̂Q�@�����_��)
| �N�� | ���@�� |
| �吳�@�X | �Q�O�P |
| �P�O | �R�P�R |
| �P�P | �S�S�W |
| �P�Q | �U�X�S |
| �P�R | �P�C�P�O�U |
| �P�S | �P�C�P�U�O |
| �P�T | �P�C�R�R�W |
| ���a�@�Q | �P�C�T�U�O |
| �R | �P�C�V�X�O |
| �S | �Q�C�O�Q�T |
| �T | �Q�C�S�V�U |
| �U | �Q�C�T�R�P |
| �V | �Q�C�V�T�T |
| �W | �R�C�O�S�O |
| �X | �R�C�R�X�R |
| �P�O | �R�C�P�X�U |
| �P�P | �R�C�Q�X�X |
| �P�Q | �R�C�O�T�X |
| �P�R | �R�C�Q�W�Q |
| �P�S | �R�C�S�X�S |
| �P�T | �R�C�U�S�Q |
| �P�U | �R�C�U�Q�R |
| �P�V | �R�C�S�W�X |
| �P�W | �Q�C�X�X�T |
| �P�X | �R�C�P�O�W |
| �Q�O | �Q�C�V�U�W |
| �Q�P | �Q�C�O�U�W |
| �Q�Q | �Q�C�P�W�T |
| �Q�R | �Q�C�P�V�T |
| �Q�S | �Q�C�P�P�W |
| �Q�T | �Q�C�P�X�T |
| �Q�U | �Q�C�Q�O�P |
| �Q�V | �Q�C�R�O�W |
| �Q�W | �Q�C�U�O�Q |
| �Q�X | �Q�C�V�O�V |
| �R�O | �R�C�Q�O�V |
| �R�P | �R�C�R�O�S |
�����̎���ː��E��������ы������Y�ʒ�
| �N�@�� | �ˁ@�� | ���@�@�� | ���Y�ʂ� |
| ���a�R�Q | �W�U�Q | �R�C�W�P�R | �V�C�Q�X�W |
| �R�R | �W�T�U | �S�C�P�R�U | �W�C�P�V�S |
| �R�S | �W�T�W | �S�C�T�T�Q | �X�C�O�S�V |
| �R�T | �W�T�X | �S�C�U�O�W | �X�C�X�U�W |
| �R�U | �W�P�X | �T�C�Q�P�T | �P�O�C�O�S�S |
| �R�V | �W�O�R | �T�C�Q�R�X | �P�O�C�R�R�V |
| �R�W | �V�V�U | �T�C�V�R�R | �P�P�C�W�O�R |
| �R�X | �V�S�R | �U�C�O�R�W | �P�P�C�X�W�P |
| �S�O | �U�V�R | �T�C�U�T�P | �P�P�C�X�T�W |
| �S�P | �U�S�X | �T�C�V�P�T | �P�P�C�X�P�U |
| �S�Q | �U�O�O | �U�C�O�W�R | �P�Q�C�U�T�V |
| �S�R | �T�U�W | �U�C�S�V�P | �P�S�C�P�W�W |
| �S�S | �T�S�S | �U�C�X�Q�X | �P�T�C�S�T�W |
| �S�T | �T�O�S | �V�C�Q�O�X | �P�U�C�S�O�V |
| �S�U | �S�V�W | �V�C�S�X�S | �P�V�C�R�O�T |
| �S�V | �S�S�X | �V�C�U�X�T | �P�W�C�Q�Q�W |
| �S�W | �S�R�Q | �W�C�R�V�O | �P�X�C�O�V�W |
| �S�X | �S�P�Q | �X�C�O�V�S | �Q�O�C�Q�Q�V |
| �T�O | �R�X�P | �X�C�P�O�U | �Q�P�C�T�O�S |
| �T�P | �R�W�S | �X�C�S�W�S | �Q�S�C�P�Q�S |
| �T�Q | �R�T�X | �X�C�X�S�W | �Q�U�C�X�R�O |
| �T�R | �R�T�Q | �P�O�C�W�P�S | �Q�W�C�X�Q�W |
| �T�S | �R�S�W | �P�O�C�U�P�X | �R�P�C�U�P�Q |
| �T�T | �R�R�W | �P�P�C�Q�R�U | �R�P�C�R�R�O |
| �T�U | �R�Q�W | �P�P�C�W�S�Q | �R�Q�C�R�V�T |
| �T�V | �R�P�S | �P�P�C�X�R�Q | �R�R�C�T�O�W |
���@�P�@����ː��E�����͔_�Ɗ�{�����ɂ��
�@�@�Q�@�������Y�ʂ͊e�_�����ƕɂ��
�@�������A�������������P�����̖ڕW�B���̐��ʂ́A���N�̖������Ȃ���ꂽ���̂́A���肩��̑S���I�ȋ����̎����ɘa�̉e�����A������A�����̐��Y�ߏ��肪�N���[�Y�A�b�v����A���a�T�R�N�ȍ~�̓��������u���ɉ����āA���Y�����̓���I�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���_�E�ɂƂ��Ă��ĂȂ���������ƂȂ����̂ł���B���̐[���Ȏ��ԂɑΏ����āA����g��^�����͂��߂Ƃ���K�Ȏ{��ɂ���Ă��̑O�r�Ɋ��H�����������A�����܂ő�����ꂽ���_���̓w�͂ƁA�y�n��{�݁A�_�@��ɑ��鑽�z�̓����ɕ��闏�_�o�c�̓��������҂����̂ł���B
�@��P�O�߁@�{�{
���ƂƂ��Ă̗{�{
�@���É��R�[�`���Ƃ�����i�킪���܂ꂽ�قLj��m���͗{�{������ł��������A���̈��m������̈ڏZ�҂ɂ���ĊJ�ꂽ�����ł́A���A���X���畛�ƂƂ��Č{�����炷����̂����������B���Ȃ킿�A�����P�Q�N�i�P�W�V�X�j����ƊJ��������łQ�U�H����ƋL�^����Ă���A�Ȍ�P�S�Q�H�A�Q�X�Q�H�A�U�O�O�H�A�V�Q�X�H�ƔN�X���������ǂ�A�̔��܂��͎��Ɨp�Ƃ���A����ɁA�{�ӂ�̔엿�������コ�ꂽ�̂ł���B
�@�����P�S�N�ɌÓc�m�s���V�퍕�F�R�[�`�����ړ����Ă���{�{�ƌĂ���ɒB�����Ƃ������A���̂���{�{�̕��y����r�I���������̂́A�P�Ɍo�ϓI�Ȗʂ���łȂ��A�ڏZ���̑����������ɂ����đ����Ȃ�Ƃ��{�{�ɑ���o�������������߁A���̕��ƂƈقȂ�e�ՂɎ茜���邱�Ƃ��ł������炾�Ƃ����B���������ĕ��ƂƂ��čL�����y���i���������A�i����O�q�̍��F�R�[�`�����͂��߃R�[�`���A�n���{���O�i�Q�R�N�A�������`���ړ��j�A�o�t�H�[�s���O�g���A���F���O�z���A�o�t�u���[���X�ȂǑ���ɋy���̂́A�̌^�E���^�Ƃ��Ɍ��݂̂��̂�菬���������Ƃ����B
�{�{��̒a��
�@���_�ɂ�����{�{�v�z�͂܂��܂����サ�đS�_�Ƃ����炷��܂łɂȂ�A�i��̉��ǂƎ��{�Ǘ��̉��P�ɂ���ĔN�X���Y�������������A���ɘh�̑��i���A����j�̔����g�V���͗{�{���ƂɔM�S�ŁA�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�ɓ�������n�[���[�h�n���F���O�z����P�Y�P�O�����ړ����A���̑��B�ɂ���ď�����Ƃ��čL���s���n�点�����߁A���������̕��y���݂�悤�ɂȂ����B���̌�A�h�̑��������ɑ哇�E�я��E�u���Ȃǂ̗{�{�ꂪ�ݗ�����A���̂ق��ɂ��A�T�O�H����P�O�O�H���x�̕��ƓI�Ȏ��炪�����ɂ݂���悤�ɂȂ����B
�@�����{�{��ł́A�����R�W�N�ɓ�������d�Z���z�i�Ӂj������w���A�����ŕč��T�C�t�@�[�А��z����P����w�����Ďg�p�����Ƃ���A���̐��т��ǂ������̂œ��А��z����Q���A�������B�܂��A�D�y���_������琗��Q�������ƂƂ��ɁA�L�k���Ӌ@�����ěz���\�͂̑��i�Əȗ͉���}�����B����Ɍ������d�˂����ʁA�����������i�琗��j�����ė{�{���Ƃ̔��W�ɍv���������Ƃ́A���M���ׂ����Ƃł������B
�@�܂��A���̑��̗{�{��ł��z������w�������莩��l�Ă���ȂǁA���Ƃ̐L�W��}�����̂ŁA�N�ԛz�������P������H�𐔂��A���̑��������͑����͂������k�͈�����ʁA��͔��ٕ��ʂ܂ōL���̔������B�Ȃ��A�U�O�����A�P�O�O�����͖{���e�n�̂ق��A�O�O�E�������ʂֈڏo���A�{������Ƃ��ď��M�E�D�y�E���فE�����E�������ʂɏo�ׂ����ł������B�������{����Ă����i��Ƃ��ẮA�n�[���[�h�n���F���O�z���A���É��R�[�`�������������B
�@�Ȃ��A�����{�{��ł͑吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɓ_���@���l�Ă��ĎY���������コ������������Ă���A���̗{�{��ł����̕��@��p���Đ��т��グ���̂ł���B
���_�Ƌׁi����j�g��
�@�{�{�ː��́A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�łP�Q�V�V�ˁA�S�N�łP�S�R�O�ˁA�U�N�ɂ͂P�U�O�Q�˂𐔂��A�������A�T�O�H�ȏ�̎��{�ː������ł��P�U�Q�˂ɒB���Ă����B���������{�{���Ƃ̔��W�ɑΉ����āu���_�Ƌבg���v�Ƃ����\�����킹�g�����������A��ׂ̉��ǂ�Y���̔̔����̑����݂̗��ւ�}�邽�ߊ������Ă������A���̌�A��X�̎���ɂ��W�ׂ̓��ꂪ����ƂȂ���U�����Ƃ����B
��O�E���̗{�{
�@���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�h�̑��̏����������A�A�����J����A�g�L���\���n���F���O�z���P�Y�Q���A�����ĕi����ǂ��茜���A�T�N�ɂ͑哇�{�{��œ������n���E�b�h�_��n�A�g�L���\�����F���O�z���̎헑��A�����A���ꂼ�ꐗ���琬�̔��������A���̂��납��e�˂ɑ����������炳��A������A�{�{�̍Ő����ɓ������̂ł���B
�@�������A���a�P�Q�N�V���A�����푈�ڂ����ȍ~�A������J���͕s���Ƃ������Ԃɒ��ʂ��A�{�{���_�̉����̏�Ԃ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B����ɁA�����m�푈��̗{�{�́A�_�Ǝ��Ɨp�̒�掔�{�������Ă͎����̒��B������ƂȂ�A���{�H���͂������傫����ނ����B���̔��ʁA���~�����ُ̈�ȍ����Ȃǂ̂��߂̍����������������A�{�����v�̑����Ǝ�����J���͂̍D�]�ɂ���āA�Ăі{�i�I�ȗ{�{��������邱�ƂƂȂ����B
�@���Ȃ킿�A���a�Q�W�N�ɗ���̔����{�{�g���ĊJ���āA�}�b�^�[�z�[�����P���H�z������A�z���E�琗�E�̔����J�n���A�R�Q�N�ɂ͑哇�{�{����ĊJ����ƂƂ��ɁA�_�Ƃɂ�镛�ƂƂ��Ă̗{�{���������Ă����̂ł���B����ɂ�莔�{�H�������X�ɑ������A���a�Q�S�N�̂U�S�W�R�H�A�Q�V�N�̂P���Q�O�V�V�H�ɑ��A�R�P�N�ɂ͂P���X�R�T�P�H�ɒB�����B
�@����̐��ڂɂ�Č{�̎��{�`�Ԃ�Z�p�ɒ������ω��������A���a�R�T�N����ɂ̓P�[�W�{�{�����コ���悤�ɂȂ����B����́A�I��Ɏ��玺���d�ˁA������������ė��̓I�Ɏ��{������̂ŁA���ʐςő��������{�ł��邽�߂��̌�͋}���ɕ��y���A���݂ł͂قƂ�ǂ����̕��@�ɂ���Ď��{����Ă���B
�@����������ɂ����Ă��A�_�Ƃ̕��ƂƂ��āu���œ����A�����Ō����A�앨�ŔN���v�Ɛ�`���ꂽ���A�����R�W�N�i�P�X�O�T�j�łP�O�H�����X�Q�ˁA�T�O�H�����S�S�˂𐔂��A���{�T�X�T�H�A���S�W�X�H�Ƃ����L�^�����邪�A���ꂩ��݂�Ƃ������ɕ��Ƃ̈���o�Ȃ������悤�ł���B
�@�吳�P�T�N�i�P�X�Q�U�j�ɂ͉������\�����S���\�H�����{���ė{�{�Ƃ��J�n���A�����ɕ��ݏo�����̂ł��������A���a�Q�N�̉āA�`���a�̔����ɂ���Ĉ��ɂ��ĉߔ��������S���A�邪�����Ă��̎��{�������Ƃ��́A�����ڂ��R�Ƃ��ĂȂ����ׂ�m��Ȃ������Ƃ����B����������l�̘J�ꂪ���P�ƂȂ�o���ƂȂ��āA����ɗ{�{���ƂƂ��Ē蒅���Ă����̂ł���B
�{�{�_�Ƌ����g��
�@�{�{���悤�₭�������͂��߂����a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�P�P���R���u���_���{�{�_�Ƌ����g���v���ݗ����ꂽ�B�g�����͂P�W�X�l�A�o�����͂U���X�O�O�O�~�ŁA����g�����ɓs�z�B�O���A�C���A�����̍w���E�i��̉��ǁE�̘H�̊J��Ȃǂ�ړI�Ƃ��Ă��̋@�\�����邽�߁A�g�����͌����ȓw�͂𑱂����̂ł������B���������w�͂ɂ���đg���̐��������܂�A�������{�{�ƊE�͂܂��܂����W���ɂ��������߁A�R�Q�N�ɂ͑g�����R�P�O�l�A�o�����z�R�O���T�O�O�O�~�ɒB���A�{���戵���Q�O�O�O���~�A�����戵���Q�T�O�O���~�ƂȂ����̂ł���B
�@�������A����̐��ڂɂ���đg���͌o�c�s�U�ƂȂ�A���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�U���Q�X�����U�̂�ނȂ��Ɏ������B
���_���{�{�_�Ƌ����g���i�ʐ^�P�j

�@�Ȃ��A���a�R�W�N�U�����͒�ʌo�ϔ_���ƒ{�Y�U�����̋K��ɂ���āA���̑g���ɑ��R�X�N�R���̏��Ҋ����ƁA�����S���̘A�ѕۏ�v���ɁA�{�w�������P�Q�O���~��ݕt�����̂ł���B�Ƃ��낪�g���́A���肩��̌o�c�s�U�̂��ߊԂ��Ȃ����U�̒���������ꂽ�̂ŁA���ۑS�̂��ߓ��ɏ��Ҋ������J��グ�ĕٍς����߁A�g������P�V���P�V�S�S�~�̏��҂ƁA�A�ѕۏؐl�̗����P�S������U�O���~����Ăꂽ���̂́A�Ȃ��S�Q���]�~�̖����ҋ����c���ĉ��U�����̂ł���B
�@���������āA���͕ۏؐl�ƂȂ����������Ƌ��c���A�ɗ͒����ɓw�߂����ʁA�Q�P���T�O�O�O�~�̏��҂����ł������̂́A�������̂��̂��g�����ɑ���]�݂Ƃ������i�̂��̂ł���A����ȏ㋌�����ɕ��S�������邱�Ƃ͖����ł���Ɣ��f�����c�������́A�S�P�N�P���Q�O���̒��c��ɍ��Q�P���R�Q�T�U�~�̕������Ă��ċc���A���Ɍ����������Ƃ������قȍs���P�[�X���������̂ł���B
�{�{�̌���
�@�P�[�W�{�{�����Ɉڍs���A�����H���{���\�ƂȂ�����f���ď��a�R�U�N�ɂ͎��{�ː��V�T�T�˂łR���Q�O�O�O�H���A�O�r�ɂȂ���]���������ł������B�������A���̒���ɂ����鍂�x�o�ϐ�������̂���������_�Ɛ��̋}���Ȍ����̉e���ƁA���ƓI�X����p���Đ�ƓI�ȌX�������߂�ƂƂ��ɁA�ɂ������܂ފ��q���ʂ�����s�X�n���ӂł̎��{���h�������Ƃ����悤�ȏ��}�����A���̂悤�Ȃ��Ƃɂ���ē]�p�Ǝ҂����o���A���{�ː��͂S�O�N�łS�P�O�ˁA�S�T�N�łQ�Q�Q�ˁA�T�O�N�łP�P�P�˂Ƃ����悤�Ɍ������A�T�O�N�ɂ͂킸���T�O�˂𐔂���ɂ����Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�@����A���{�H���͏��a�S�V�N�ɂ���܂ōō��̂R���V�U�V�O�H�𐔂��A�e���{�҂��Ƃ̌o�c�K�͂��g�債�����Ƃ������Ă������A���̌�͎��{�ː��ƂƂ��Ɍ��������ǂ�A�T�R�N�ɂ͒����ԕۂ����Q���H������Ɋ������̂ł���B
�@�N���ʎ��{�ː�����щH���͕ʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A���̌����X���͂Ȃ����������̂Ɨ\�z�����B
�{�̎��{�ː�����ю��{�H���i�_�Ɗ�{�����j
| �N�@�� | �ˁ@�� | �H�@�@�� |
| ���a�R�Q | �X�Q�V | �R�O�C�O�X�R |
| �R�R | �W�W�U | �Q�T�C�U�P�R |
| �R�S | �W�Q�U | �R�O�C�U�U�R |
| �R�T | �W�P�X | �Q�R�C�O�W�O |
| �R�U | �V�T�T | �R�Q�C�O�P�T |
| �R�V | �V�S�V | �Q�W�C�V�R�W |
| �R�W | �V�R�W | �R�Q�C�X�V�R |
| �R�X | �T�R�W | �Q�O�C�Q�X�Q |
| �S�O | �S�P�O | �Q�O�C�V�U�T |
| �S�P | �S�O�X | �Q�O�C�O�S�S |
| �S�Q | �S�O�S | �Q�W�C�Q�W�P |
| �S�R | �R�S�O | �R�P�C�S�U�W |
| �S�S | �Q�X�X | �Q�S�C�T�W�V |
| �S�T | �Q�Q�Q | �Q�V�C�O�V�O |
| �S�U | �Q�O�O | �R�U�C�X�T�W |
| �S�V | �P�W�X | �R�V�C�U�V�O |
| �S�W | �P�T�R | �R�V�C�S�W�W |
| �S�X | �P�Q�X | �R�O�C�Q�U�P |
| �T�O | �P�P�P | �Q�T�C�S�P�T |
| �T�P | �V�P | �Q�P�C�U�P�R |
| �T�Q | �T�O | �Q�O�C�O�S�U |
| �T�R | �T�T | �P�W�C�S�U�P |
| �T�S | �T�S | �P�S�C�S�U�P |
| �T�T | �S�V | �P�O�C�O�V�V |
| �T�U | �R�V | �P�O�C�R�S�T |
| �T�V | �Q�X | �P�O�C�Q�P�V |
�@��P�P�߁@�{���̑��̉ƒ{
�{�̓��@
�@�����_�ɂ����ď��߂Ď��炳�ꂽ�̂́A�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�̂��ƂƎv����B����́A����`��̉��B���s�ɐ��s���ă����h���ɓn�����C���V���i�Q��ڊJ���n�ψ��j���A��c���q���ɂ̎����ēł��鉡��c�ߏ����ĂɁA���̐����l���ɂӂ�Ȃ���A������܂܂������đ����Ă��������P�V�N�P�P���R�O���t���̎莆�̂Ȃ��ɓ��@������Ǝv���邩��ł���B���Ȃ킿�A���̎莆�̂Ȃ��ɂ́A�i�O���j���č��n�ɓ��薈���H�V�ɕK������Ɖ��ؓ��i�����c���i�n���j�A����͓����Ɍ��炸�ł��Ă��F�R��j�O�A�l�Ђ������A�傢�ɂ��̎������o����B�A���Ă͌�Z�]�ĊY�i����R���֒m�������Ƃ�z�N���ĕp��ɂ��̎�������Ƃ���]�Ɋ������B�����Ƃ���ɐ��̑������w�����āA���̐�������ɂ��邱�Ƃ͌ł��꒩��[�ɂł��邱�Ƃɂ͔V�����A�����悸�O�A�l�����݂Ɏ��{���A���אB�����҂��Č�X�̌����ɏ[�邾���Ȃ�Ƃ��i�����߂���艓���Ɏ���̓��Ȃ�j�������邱�ƂA�䓙�̏�ɔM�]������H���ǂ̈�[�Ƃ�������A���悢��؎��̑��B���A���@�̏n�B�ɏ]���A���ɔ̔��E�O�ւ̐�������v��ׂ����Ƃ���ɌA�������шʂ�萔���̕�����������A��Z����S���A�[�Ɏ��{�̈ӂ͖����ɂ��炸��B�K�Ɏ^���Ȃ�ΓĂƕЋˌZ���Ƒ��v�炢�A��z�͋́X���邱�Ƃɂĕق��ׂ���ԁA�������̌v�悱��L�肽����B�E�͍��̒n�ɗ���Ԃ��Ȃ��ˑR�̂��Ƃ�\���悤�Ȃ�ǂ��A���ꑥ�����[���b�p�������̎d���ɓ���P�\�Ȃ��閧�̓`�Ɍ����B�i�㗪�j
�@�i�������̎莆�́A�s�z�ȎO���u���̑n�Ɓv�����p�������A�ł��邾�������̊������c���Ȃ���A�Ƃ���ɂ���Ă͌��㕗�ɈӖA�������A�ǂ݂₷���Ȃ����Ă��邱�Ƃ����f�肵�Ă����B�j
�@�Ƃ������B���̎莆�����������͂��������Ћˈψ����Ƒ��k���A���т��琔���̓��w�����Ė�c�ǂ̖q���ɂɉ^�сA�n����x�[�R�������ꂽ���A�����̐l�̍D�݂ɍ��킸�������Ȃ������Ƃ����A���ꂪ�����炵���n�܂�Ǝv����B
���ƓI�ȗ{��
�@�{�͕��ƂƂ��Ă̕��y���i�܂��A�����̖�����悤�₭�_�ƂɂP�A�Q�������炳��͂��߂����̂́A�S�̂Ƃ��Ă͂킸���Ȃ��̂ŁA��ނ̓��[�N�V���[��ƃo�[�N�V���[��ł������B
�@���̌�A�吳�R�N�i�P�X�P�S�j��ꎟ��킪�ڂ������A���H�H�i�̐����H��Ƃ��Ĕ��قɃn���H�ꂪ�ݗ�����A�܂��A���̑O�N�ɂ͓����ɂƒ{�ꂪ�V�݂��ꂽ���Ƃ������āA�ɂ킩�ɗ{������ɂȂ�A���{�������}���ɑ��������B�������A�ƒ{�̖h�u�Ԑ�����������Ă��Ȃ����������Ƃ��ẮA�W�c�I�Ȏ��{�ɂ���đ�ʂɜ�a���邨����ƁA���i�̕s���肪���O���ꂽ���Ƃ������āA�����܂ł����Ƃ̈���z�����A�W�N�ɐ푈���I������Ɛ��E�I�ȕs���Ɍ������A�{�͍Ăщ��~�������ǂ��Ă������B
�@���a�N��ɓ����Ă�����A�Ⴂ�����̂܂ܖڗ������������Ȃ��A�_�ƂłȂ����̂����ƂƂ��Ďs�X�n�ŁA�������c�тȂǂŎ��{���Ă����ɂ����Ȃ������B�����m�푈�̏I������������̌X���͂��炭���������A�H�����̕ω��ɂƂ��Ȃ��ē��H�̐�߂銄���������Ȃ�A���i�̏㏸�������Ĕ_�Ƃ̎������Ƃ��čl������悤�ɂȂ��Ă����B����ɁA�]���͎�Ƃ��Ăł�Ղ���c�т��ς��������قƂ�ǂł������̂ɑ��A�z���������o����Ă���͑�����������\�ɂȂ�ȂǁA��̕ω����݂���悤�ɂȂ����̂ł���B
��ƓI�{�ւ̈ڍs
�@����������̕ω��ƂƂ��ɁA���a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�f���}�[�N����������@�����y����Ă��玟��Ɏ��瓪�����������A��ނ����G�킩�烉���h���[�X�Ȃǐ����̑������̂����炳���悤�ɂȂ����B����ɏ��a�R�R�N���炢����u��o�����v�ɂ��̓������}���A�R�U�N�ɂ͔��_���_�Ƌ����g�����A����ɂ������؊�n�Ƃ��Ĕ_�яȂ���u�{�Z���^�[�v�̎w������B���_���ł͏o�_���U�O�Ԓn�Ɏ{�݂�݂��A���c�������ĉ^�c���n�ߗ{�̏���ɏ��o�����̂ł���B�������A���̗{�Z���^�[�ɂ͐��̋Z�p�������Ȃ����Ƃ������āA�^�c�͂Ȃ��Ȃ��O���ɏ�炸�A�������A���a�S�O�N�ɋT�c�ɓ��쐶�Y�A�̎�Z���^�[���ݒu���ꂽ���Ƃ������āA���܂�L�W�݂͂��Ȃ������B
�@���a�S�O�N�P�Q�����͔N�ԂQ���T�O�O�O���̂ƎE��̏������\�Ƃ���u����{���Z���^�[�v�̋Ɩ����J�n����ƂƂ��ɁA�n���A�\�[�Z�[�W�A�x�[�R���Ȃǂ̉��H�H��̗U�v�Ɋ֘A���A�����⏕���ė{�ؑ��B������A�S�P�N�x���琔�N���ɂ킽��D�ǎ�Y�Ǝ펓�̓����ɗ͂𒍂����B����ɂ���Ď�����̌X���݂͂�ꂽ�̂ł��邪�A���҂����悤�ȐL�W���݂��Ȃ�����łȂ��A���{�����͂悤�₭������Ԃ𑱂����������̂́A���{�ː��͂ނ��댸�������ǂ����̂ł���B
�@���������o�߂̂Ȃ��ŗ{�͔_���Ƃ̕��Ǝ�����I���A��ƓI�{�Ɋ��H�����߂�҂ɂ���Ĉێ�����A��K�͂Ȍo�c�`�Ԃ��݂���悤�ɂȂ��Ă����B���a�T�R�N�ɂ́A�l�ł͍ō��S�O�O�]����M���ɁA�T�O���ȏ�����炷����̂��P�S�˂𐔂��A�܂��A������Д��_�t�@�[�����̓��_��ł͂P�V�O�O�]�������炷���K�͌o�c���i�߂���ȂǁA�{�؋Ƃɂ��傫�ȕϊv���K��Ă���A�����Ɋ��҂���Ă���B
�@�̎���ː�����ѓ����̐��ڂ͑O�y�[�W�̕ʕ\�̂Ƃ���ł���@
�̎���ː�����ѓ����̐��ڒ�
| �N�@�� | �ː� | ���@�� |
| ���a�R�Q | �P�Q�T | �Q�W�X |
| �R�R | �P�Q�W | �Q�W�X |
| �R�S | �Q�O�X | �U�S�W |
| �R�T | �Q�O�X | �U�U�Q |
| �R�U | �S�T�O | �P�C�T�S�Q |
| �R�V | �Q�X�Q | �P�C�Q�R�R |
| �R�W | �P�U�X | �V�O�P |
| �R�X | �P�U�P | �U�V�U |
| �S�O | �P�U�P | �X�U�P |
| �S�P | �P�Q�V | �V�X�Q |
| �S�Q | �P�T�O | �P�C�P�T�Q |
| �S�R | �P�P�S | �X�U�V |
| �S�S | �U�U | �X�R�R |
| �S�T | �V�W | �P�C�R�T�P |
| �S�U | �U�U | �P�C�S�W�T |
| �S�V | �T�Q | �W�V�S |
| �S�W | �S�X | �X�V�V |
| �S�X | �S�X | �P�C�R�O�X |
| �T�O | �R�S | �P�C�R�P�U |
| �T�P | �Q�X | �P�C�Q�W�Q |
| �T�Q | �R�S | �R�C�P�R�V |
| �T�R | �R�Q | �R�C�X�R�T |
| �T�S | �R�O | �Q�C�O�U�T |
| �T�T | �Q�S | �Q�C�R�R�W |
| �T�U | �P�V | �Q�C�P�P�R |
| �T�V | �P�T | �P�C�X�O�Q |
(�_�Ɗ�{����)
�߂�r
�@�����ɂ�����߂�r�́A�吳�S�N�i�P�X�P�T�j�ɗ���̏����������A�w�R�S�ّ�����Q�����w�����Ď��炵���̂��ŏ��ł���B��ꎟ����ɂ͗r�ѐ����A�߂�r�̑S���I�ȑ��B�v�悪���Ă��A�����ɂ����Ă���������サ�����Ƃ������āA�����̂��������Ŏ��{�����悤�ɂȂ����B
�@�������A�����͂��������т��������Ă��A��������Ƃ��낪�Ȃ��ď��u�ɍ������Ƃ����A�܂��吳�P�R�N�ɂ́A����_��ő傫�ȋ@�B�Ńz�[���X�p���̐������n�߂Ă������A���܂�\���̗ǂ����̂ł͂Ȃ������Ƃ����B���̂����A�߂�r�̎�����@���悭������Ȃ��������߁A�����K�X���N�����Ď��S������̂������A���ǂ͗ǂ����т��グ�邱�Ƃ��Ȃ��A�₪�Ďp�������Ă������B
�@�����m�푈���I��������ƕ����s��̂��߁A�Ăт߂�r�����炳���悤�ɂȂ�A�N���ƂɎ��瓪�����������Ă������B���ɁA�Q�T�N�ɂ̓I�[�X�g�����A�����߂�r�P�P�S�����A�������ƂƂ��ɁA�{�B�������ʂɈړ�����āA�قƂ�ǂ̔_�Ƃł��ꂼ��Q�A�R���ȏオ���炳���悤�ɂȂ�A���i���������͂P���W�O�O�O�~�O��̍��l�������Ă����B�܂������́A�ߗ��i���s�����Ă������ߌ��т̉��i���ǂ��A�e�˂ł��ȒP�Ȗa�ы@���g���Ėю������A�Z�[�^�[�E��܁E�����Ȃǂ���҂݂��Ă������A�ҕ��@�̔��B�Ɩ{�i�I�Ȗa�эH��̏o���ɂ��A���Y���������Ɩю��܂��͐��n�ƌ�������ȂǁA�傢�ɗ��p���ꂽ���̂ł������B
�@�������A���a�Q�W�N���Ɋ̕g�i�Ăj�ے������������ꂽ���Ƃ��͂��߁A�ߗ�����̍D�]������̑����ɂƂ��Ȃ��A�����̊W�Ɛl��s���Ȃǂɂ���Ď���Ɍ������A�R�S�N����ɂ͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B
�@��P�Q�߁@����_�n�݂Ɣ_�n���v
���L�����n�̊J��
�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�O�ォ��吳�����ɂ����Ă̍��L���J�n�̑�n�Ϗ����́A�{���ɂ�����y�n�J���𑣐i���������A���̔��ʁA�s�ݒn�储��і��L�����p�n�傷�镾�Q�������炵�A�y�n�̍����I�ȊJ����j�Q����v���Ƃ��Ȃ��Ă����B����������n�ϖ����p�n�̊J���𑣐i����ƂƂ��ɁA�����Ȏ���_��n�݂��邽�ߒn��ɑ��ĉ�������߁A����Ɉ���ł́A����J���҂��W���Ă���ɓy�n�w��������݂��t���A���L�����n���J������v�悪�u�k�C��������B�v��v�̈�Ƃ��Đi�߂�ꂽ�B
�@��̓I�ɂ́A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�W���Ɂu���L�����n�J�������ݕt�K���v���{�s����A��l�������ܒ����ȓ��ōw�����i�͂Q�O�O�O�~�ȉ��ł��邱�ƂŁA���������̋������ꍇ�́A�y�n�w�������͒��ڒn��Ɏx�����A����҂͔N�����R�E�T�p�[�Z���g�i�̂��ɂQ�E�T�p�[�Z���g�ƂȂ�j�A�����u���܂��N�A���Ҋ�����܂��N�Ƃ��������Ő��{�ɕԍς���Ƃ������̂ł������B
�@�����ɂ����Ă͂��̋K���Ɋ�Â��A���a�S�N���玑���݂̑��t�����āA�ΐ�_��ŘZ�O�㒬���]���S�X�˂ɁA���[���b�v�_��i����֔_��j�ŘZ����]���R�W�˂ɁA����֔_��i���ьF���Y���L�j�Ōl�O�������R�O�˂ɉ�����āA���ꂻ�ꎩ��_��n�݂����̂��͂��߁A���a�P�R�N�܂łɓ�Z�������ܔ����]�A���S�P�R���Q�T�X�S�~�������ĂP�Q�T�˂̎���_��n�݂������A�N�x�ʁA�����ʑn�ː�����іʐς͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B
�N�x�ʎ���_�n�ː��ʐ�
| �N �x | �ː� | �n�ݖʐ� | |
| �@���a�S | �Q | �R�U���V�U�Q�O | |
| �@�T | �W | �P�Q�T���O�U�O�O | |
| �@�U | �S�O | �T�S�O���Q�V�P�U | |
| �@�V | �| | �| | |
| �@�W | �P�P | �Q�V�O���U�T�Q�Q | |
| �@�X | �S�U | �V�W�T���Q�T�O�U | |
| �P�O | �P�Q | �Q�O�Q���W�U�P�X | |
| �P�P | �P | �Q�R���P�W�Q�Q | |
| �P�Q | �R | �U�P���U�U�P�V | |
| �P�R | �Q | �R�P���W�Q�O�Q | |
| �v | �P�Q�T | �Q�O�V�V���T�T�O�S | |
�����ʎ���_�n�ː�����іʐ�
| ���@���@�� | �ː� | �� �@�@�@�� | |
| �� �� �_ | �R�V | �U�O�Q���R�Q�O�U | |
| �R �� �� �� | �X | �P�O�P���P�X�Q�S | |
| �V �� �� | �S�O | �T�R�W���U�R�O�X | |
| �� �� �� | �W | �P�Q�T���O�U�O�O | |
| �Z�C���E�x�c | �P | �Q�O���T�W�P�V | |
| �� �c �� �� | �R | �Q�V���Q�X�P�V | |
| �� �� | �Q | �R�U���V�U�Q�O | |
| �� �� | �P | �P�T���O�O�O�O | |
| �� �� | �P | �Q�Q���T�Q�P�R | |
| �y �� �P �� | �Q | �Q�V���P�O�O�R | |
| �V �� �R | �P | �P�V���U�O�P�P | |
| �S �� | �Q�O | �T�S�R���S�U�O�S | |
| �v | �P�Q�T | �Q�O�V�V���T�T�O�S | |
�����n�̎���_�n��
�@�����ɂ���������n�̎���_�n�ݎ��Ƃ́A�吳�P�T�N�i�P�X�Q�U�j�����̒�߂��u����_�n�ݑ��������ݕt�K���v�ɂ��N���Ď��{���邽�߁A���a�U�N�i�P�X�R�P�j�Q���Ɂu���_������_�n�ݑ��������ݕt�K���v�i���V�N�R���]�K���Ɖ��߂�j��ݒ肵���̂Ɏn�܂�B�����Ē���c���̒�����T���̎���_�n�݈ێ��ψ��������āA�K�����������{�����̂ł��邪�A�U�N�x����P�X�N�x�܂ł̊Ԃɓ]�ݎ����P�Q���U�R�O�O�~�������āA�ʐώl�O�l���������]��������A�U�V�˂̎���_��n�݂����B
�@�������āA������_�n���v�ɐ�s�����u�k��҂̔_�n�̎擾�v�{���ϋɓI�Ɏ��{�����̂ł��邪�A���̔N�x�ʌː�����ёn�ݖʐς͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B
�_�n���v
�@���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�P�Q���X���A���R���i�ߕ����甭����ꂽ�u�_�n���v�Ɋւ���o���v�ɂ���āA���肩�獑��ŐR�c���́u�_�n�����@�̈ꕔ�����āv��������A�킪���_�Ǝj�ォ�ĂȂ��_�n�̈����v�Ƃ���ꂽ���̂ł��������A�����łQ�P�N�U�����i�ߕ�����ēx�̊����������{�́A���N�P�O����_�n���v�@�Ƃ�������u����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�v�Ɓu�����_�n�����@�v�̓�@����z���A���炽�߂Ĕ_�n���v�̓O�ꐋ�s�������邱�ƂƂȂ����̂ł���B
����_�n�݈ێ������]�K���ɂ��n�݂��ꂽ����_�ʐϓ�
| �N�� | �ː� | �� �@�@�� |
| �@���a�U | �T | �Q�Q���W�T�O�O |
| �@�V | �X | �S�O���T�P�P�O |
| �@�W | �S | �P�U���X�W�O�O |
| �@�X | �P�T | �X�Q���W�O�O�W |
| �P�O | �P�V | �W�S���R�V�O�O |
| �P�P | �T | �R�V���V�T�P�Q |
| �P�S | �U | �R�S���T�T�P�Q |
| �P�X | �U | �P�O�S���X�U�P�R |
| �v | �U�V | �S�R�S���V�W�P�R |
�@���̎���_�n�ݓ��ʑ[�u�@�́A
�@�u����҂̒n�ʂ����肵�A���̘J���͂̐��ʂ������ɋ����邽�ߎ���_���}�����L�Ăɑn�݂��A�ȂĔ_�Ɛ��Y�͂̔��W�Ɣ_���ɂ����閯��I�X���̑��i��}��B�v
���Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���A�k�C���̏ꍇ�͍ݑ��n��̏���n�ʐώl�����A����n������镔���ɂ��Ă͐��{�������I�ɔ������邱�Ƃ��ł��A���̔�������_�n�̌���͔_�n�ψ���s�����ƂƂ��ꂽ�B
�@�܂��A�_�n�����@�́A
�@�u�k��҂̒n�ʂ̈��肨��є_�Ɛ��Y�͂̈ێ����i��}�邽�ߔ_�n�W�̒��������邱�ƁB�v
��ړI�Ƃ��A�_�n�ψ���̑g�D�Ȃǂɂ��ċK�肵�Ă����B
�@���������@���ɂ���ē����ɂ����ẮA��l�l�Z���������L����U�U�l�̕s�ݒn��ƁA�ۗL�ʐώO���ꔽ�����������y�n������邱�ƂɂȂ����ݏZ�n��ɂƂ��ẮA�܂��ɒv���I�ȑŌ��ł������B�������A�_�n�̔����͖@�̒�߂�Ƃ���ɂ�蒅�X�Ǝ��{����A���a�Q�Q�N�R���R�P���̑�P��A����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�Ō�̂Q�V�N�P�O���P�O���̑�Q�U��܂łɁA�c�꒬���A�����O�����]�A�̑��n����ܒ����]�A��n�P���T�T�S�U�ؗ]�̂ق��A�����Q�P���A�_�Ǝ{�݈ꎮ�������B�����͒n��̗����Ƌ��͂ɂ���āA���̑啔�����Q�Q�A�Q�R�N�̓N�Ő��s���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�Ȃ��A�����ɂ������ďd�v���ƂȂ����Ή��́A��������c�łP�S�S�~�A���łU�P�~�Z���K���ЂƂ����z�ł������B
�@����A�������ɂ����锃�����т́A�Q�Q�N�V���Q���̑�Q��Q�T�N�P�Q���Q���̑�P�W��܂łɁA�����꒬���]�A�̑��n�l�꒬���]�A��n�P�Q�W�R�ؗ]�Ƃ����ł������B
�@�܂��A�������Ĕ������ꂽ�_�n�́A�s�s�v���悠�邢�͖@�l��c�̂̎ؓ��n�A�������Ȃǂ̗�k��҂Ȃǂɑ��u��K�v�Ƃ��邲���ꕔ�̔��E�̑��n�������A���_���ɂ����Ă͂V�W�U�ˁA�������ɂ����Ă͉��x�P�P�P�˂̔_�Ƃɔ���n�������A�����̓y�n�̂قƂ�ǂ��]���̎ؓ��n�ł������B
�_�n��������
| �@�@������ ��@�� |
���@�@�@�_�@�@�@�� | ���@�@�@���@�@�@�� | |||||||
| ���@���@�n�@�� | ���@���@�@�� | ���@���@�n�@�� | ���@���@�@�� | ||||||
| �c | �P���O�O�O�O | �P�C�S�S�O�~�O�O | �\�@ | �\ | |||||
| �� | �Q�C�W�W�R���R�R�Q�W | �P�C�W�O�Q�C�S�U�Q�~�W�S | �Q�X�P���R�U�Q�W | �P�U�W�C�U�X�Q�~�T�Q | |||||
| �́@���@�n | �V�X�T���Q�O�O�V | �P�V�O�C�R�U�X�~�V�Q | �S�P���P�W�O�Q | �V�C�P�U�T�~�W�O | |||||
| ��@�@�@�n | �P�T�C�T�S�U���O�V�@�@ | �P�U�C�T�R�Q�~�O�O | �P�C�Q�W�R���R�W�@�@ | �Q�C�S�R�T�~�T�O | |||||
| ���@�́@�� | �����Q�P�� �_�Ǝ{�݈ꎮ�@ |
�@ | �@ | �@ | |||||
| �n�吔 | �݁@�� | ���ׂP�U�W�l | �@ | �S�R�l | �@ | ||||
| �s�@�� | ���ׁ@�X�V�l | �@ | �Q�O�l | �@ | |||||
�_�n���n����
| �@������ ��@�� |
���@�@�@�_�@�@�@�� | ���@�@�@���@�@�@�� | ||||||
| ���@�n�@�n�@�� | ���@�n�@�@�� | ���@�n�@�n�@�� | ���@�n�@�@�� | |||||
| �c | �P���O�O�O�O | �P�C�S�S�O�~�O�O | �\�@ | �\ | ||||
| �� | �Q�C�W�T�Q���R�O�P�W | �P�C�W�O�Q�C�S�U�Q�~�W�S | �Q�V�S���P�P�P�Q | �P�T�V�C�O�R�P�~�O�S | ||||
| �́@���@�n | �V�X�S���W�Q�O�O | �P�V�O�C�Q�T�V�~�U�Q | �S�P���P�W�O�Q | �V�C�P�U�T�~�W�O | ||||
| ��@�@�@�n | �P�T�C�T�S�U���O�V�@�@ | �P�U�C�T�R�Q�~�O�O | �P�C�Q�W�R���P�T�@�@ | �Q�C�S�R�T�~�T�O | ||||
| ���@�́@�� | �����Q�P���@ �_�p�{�݈ꎮ |
�S�X�S�C�V�V�T�~�R�U | �@ | �@ | ||||
| ���n�_�Ɛ� | �V�W�U�� | �@ | �P�P�P�� | �@ | ||||
�_�n�ψ���
�@���a�Q�O�N�P�P���Ɨ��Q�P�N�P�O���̂Q��ɂ킽���Ĕ_�n�����@����������A�_�n�����̖ړI�Ɠ��e���啝�ɉ��߂�ꂽ�����A���̔C�ɂ�����_�n�ψ���K�u���ƂȂ�A�������A�ψ��͒n���k��҂Ȃ�тɔ_�n���L�҂̌��I�ɂ��Ƃ���ƂȂ����B���̉����@�ɂ���P��̑I���́A�萔�P�O���łQ�P�N�P�Q���ɍs���A�ꍆ�ψ��i����w�j�ɍ�������A�������n�A����ΎO�Y�A�s�z�B�O�A���쏇�ܘY�̂T���������[���I�ƂȂ�A�O���ψ��i���쌓����w�j�����c�v���A�n�Ӌ�̂Q�������l�ł��������A�ψ��i�n��w�j���������[�ƂȂ�A���쒼���A���؊��s�A����l�Y�����I�����B�����ď����ɂ͔��쒼�����I�C���ꂽ���A���E�֎~�̐��߁i�O�c�@�c���I�������j�ɂ�莸�E�����̂ŁA�v�ۓc���H���J��グ��[�ɂ���Ĉψ����I���A�Q�R�N�P����ɑI�C����A����ɂ��̔N�T���v�ۓc��͓n�����ٔ_�n�ψ��A�����c��̉�ɏA�C�����B
�@�_�n�ψ���́A�킪���ɂ�����_�n�̈����v�ɑΏ����A���Ă̐R�c�Ɖ����ɓ�q���ɂ߂Ȃ�����A�悭���̋@�\���������A����_�Ƃ̑����ɂƂ��Ȃ��ĂQ�S�N�ɔ_�n�����@�̈ꕔ����������A�萔�P�O���̒��ŏ���ψ��Q���A�n��ψ��Q���A����ψ��U���ƂȂ�A���N�W���P�X���ɑ�Q��I�����s��ꂽ�B���̌��ʁA�ꍆ�ψ��i����w�j�ɉ��c���Y�A���R�k��̂Q���A�ψ��i�n��w�j�ɏ���l�Y�A���J���L�̂Q���A�O���ψ��i����w�j�ɔ��؊��s�A�s�z�B�O�A���c�v���A���쏇�ܘY�A��������A�n�Ӌ�̂U�������ꂼ�ꓖ�I���A�X���Q���̏��ψ���œn�Ӌ����ɑI�C���ꂽ���A���c��c���Ƃ̌��E�֎~�ɂ���Ď��C���A��C��Ɍ��R�k�삪�I�C����ĔC�����ݐE�����B
�@�Ȃ��A�������ł����l�ɔ_�n�ψ���ݒu����I�����s��ꂽ���A�Q�P�N�P�Q���̑�P��I���ł́A�ꍆ�ψ��ɖk���Ӎ�A���c�@�g�A��t�Δ��Y�A�Έ�g���A�F��ɗY�A�ψ��Ɍ㓡���Y�A�@��ۈ�A���c�e���Y�A�O���ψ��ɐē��g�V��A��c���Y�̒萔�P�O�������I���A��ɐē��g�V�傪�I�C���ꂽ�B
�@����ɁA�Q�S�N�W���̑�Q��I���ł́A�ꍆ�ψ��ɖk���Ӎ�A��t�Δ��Y�A�ψ��ɋ{�엘�F�A��c���Y�A�O���ψ��ɐ{���G�g�A���Y���A�ē��g�V��A�[�쏟�O�Y�A�O�R�e���A���J�쏟�̂P�O�������I�����B
�_�ƈψ���
�@�_�n�ψ���̎�ɂ���Ĕ_�n���v�̎����������ɐi�߂��A�H�Ƃ̐��Y������������O�̐����ɖ߂��������������ɑ������A����܂ł̔_�n�����@�ɑ����Ď��̒i�K�Ɉڍs���邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�R���u�_�ƈψ���Ɋւ���@���v�����z����A���N�W������u�_�ƈψ���v�̔������݂邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@����́A�]���̎���_�n�݂���є_�n�����ȂǁA�_�n���v�̎��{�@�ւƂ��Ắu�_�n�ψ���v���͂��߁A�H�Ƒ��Y�A���o�̎��s�A�c���@�ւł���u�_�ƒ����ψ���v�A����ɁA�_�Ɖ��ǎ��Ƃ̎���@�ւƂ��Ắu�_�Ɖ��Ljψ���v�̎O�ψ�����������̂ŁA�_���̎���I�ȗ���ɂ�����s���֗^�ɂ���āA�_�Ɛ��Y�̌���͂��Ƃ��o�c�̍�������}��A�_���̎Љ�I�A�o�ϓI�n�ʂ̌���ɍv������^�̔_����\�@�ւƂ��邱�Ƃ�O��Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂ł������B���̌�A�Q�X�N�ɂ́u�_�ƈψ���Ɋւ���@���v�Ɖ��߂��A�_�ƈψ���͎s���������ɑ��u���邱�ƂƂȂ�A�s���{���ɂ́u�s���{���_�Ɖ�c�v��u�����ƂɂȂ����B
�@�_�ƈψ���͎s�����s���ψ���ŁA�I���ɂ��ψ��ƑI�C�ɂ��ψ��őg�D����A�ψ��̑I�����Ɣ�I�����́A���̎s�������ɏZ����L����N��Q�O�Έȏ�̎҂ŁA�R�O�A�[���ȏ�̔_�n�̍k��҂���ѓ����̐e���A�܂��͂��̔z��҂Ƃ��ꂽ�B�I�C�ɂ��ψ��́A�_�Ƌ����g���Ɣ_�Ƌ��ϑg�����A�e�g�����Ƃɐ��E���������e�P���ƁA�c����E�����w���o���҂T���ȓ��̎҂����I�C���邱�ƂƂȂ��Ă���B
�@�_�ƈψ���̌����Ƃ��ẮA���s�@�ւƂ��Ē����̔_�ƂɊւ���s��������Ɨ����Ď��s����ƂƂ��ɁA�s�����̎���ɉ����ē��\����Ƃ�������@�ւƂ��Ă̐��i�����킹���Ƃ������̂ł���A���̎�Ȃ鎖���́A
�@�P�A�_�n�@���Ɋ�Â��_�n���̗��p�W�Ɋւ��钲���y�ю���_�̑n�݈ێ�
�@�Q�A�y�n���ǖ@���ɂ��_�n���̌��������Ɋւ��鎖������
�@�R�A�_�n���̗��p�W�̈����E���c�̖h�~�E�_�n����̉��P�E�_�ƐU���v��̎����Ɛ��i�E�_�ƌo�c�̍������E�_�������̉��P���Ɋւ��鎖�����������A�_�Ƌy�є_���Ɋւ��钲�������ƌ[����`
�@�S�A�_�Ƌy�є_���Ɋւ��鎖���ɂ��Ĉӌ������\���A���̍s�����Ɍ��c���邱�Ƃ��ł���B
�Ȃǂł���B
�@�����������x�̌o�܂ɉ����A���a�Q�U�N�V���Q�O�����̑I�������s���A���_���E���������ꂼ��̔_�ƈψ�����������̂ł��邪�A�R�Q�N�̒�������������_�ƈψ���͓��N�V���̔C�������܂ő������A���̌������̔_�ƈψ���ƂȂ����B�_�ƈψ��̑I������ёI�C�̌o�߂͎��̂Ƃ���ł���B
���a�Q�U�N�V���Q�O���I���i�C���@���a�Q�X�N�V���P�X���܂Łj
| ���_�� | ���I���ψ��i�P�T���������[�j�@�ɓ��M��E�a�������Y�E��ː����E���J�`�j�E���c�����E���c�v���E�с@�y��E�g�c���� �@�@�s�z�B�O�E��؋g���E�ɓ����g�E�@���c���Y�E�n�Ӌ�E���{�v���E�������� |
| ���c��E�i�R���j�@���R�k��E�O�j�E���؊��s | |
| ���_�����E�i�P���j�@���쒼�� | |
| �����ϐ��E�i�P���j�@�v�ۓc���H | |
| ������ | ���I���ψ��i�P�T���j�@��_�����E���c�T�l�Y�E���J�쏟�E����V���E�k���Ӎ�E�����P��E��t�Δ��Y�E�@��ۈ�E�F��ɗY �@�g�c��㔪�E�����`�t�E��㗘�H�E�|���@���E���Y���E��c���Y |
| �����E�ψ��i�T����������敪�s���j�@�ɓ��~��E�[�쏟�O�Y�E�ē��g�V��E�{���G�g�E�{���G�v |
���a�Q�X�N�V���I���i�C���@���a�R�Q�N�V���P�X���܂Łj
| ���_�� | ���I���ψ��i�P�T���������[�j�a�������Y�E���ю��Y�E�ɓ����g�E���c�v���E��؋g���E��������i�Q�X�N�W�����S�j �@�ߐ{�����E���J�`�j�E�с@�y��E����i�n�E�ɓ��M��E�g�c�����E���{�v���E���c�����E�_�ˎ����Y |
| ���c��E�i�R���j���؊��s�i�Q�X�N�P�P�����S�j��O�j�i�Q�X�N�X�����S�j�E���R�k�� | |
| ���_�����E�i�P���j�n�Ӌ | |
| �����ϐ��E�i�P���j�v�ۓc���H | |
| ������ | ���I�C�敪�s���Ȃ��玟�̂P�U���ݔC�@�����P��E��_�����E�[�쏟�O�Y�E���J�쏟�E��t�Δ��Y�E���Y���E���c�T�l�Y ��㗘�H�E�k���Ӎ�E�֓��g�V���@�����`�t�E�ɓ�����E�ɓ��~��E�@��ۈ�E�{���G�g�E���R���j |
���@���a�R�Q�N�S���P���������������ψ�����Ƃ�u���_�����_�_�ƈψ���v�u���_�������_�ƈψ���v�Ƃ��ĔC�����p�������B
���a�R�Q�N�V���I�� (�C���@���a�R�T�N�V���P�X���܂�)
| ���I���ψ��i�Q�R���������Q�S���j��t�����Y�E��؋g���E�ɓ��M��E��ؐr�ܘY�E�_�ˎ����Y�E���c�v���E�����F��E��c���Y�E �@����i�n�E�@��ۈ�E���J�슙���Y�E���q���O�Y�E���c�T�l�Y�E�ɓ����g�E�с@�y��E�ߐ{�����E���{�v���E�X�@�m��E���c�����E �@�����F�E���c�L��E�ѓ����Y�E��t�Δ��Y |
| ���c��E�i�R���j���R�k��E�ɓ��~��E�n�Ӌ�� |
| ���_�����E�i�Q���j�v�ۓc���H�E���J��M�` |
| �����ϐ��E�i�Q���j���c���Y�E�{���G�g |
���a�R�T�N�V���I���@�@�@�i�C���@���a�R�W�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�Q�R���������Q�T���j�q�n�����E��؋g���E�_�ˎ����Y�E�ɓ����g�E��t�����Y�E�{�c�h���E���J�`�j�E��ؐr�ܘY�E �@���J�슙���Y�E�ɓ��M��E�������O�Y�E���c�L��E���Y��O�E��c���Y�E����i�n�E���c�T�l�Y�E���c�����E��؋g���E�@��ۈ�E �@�����F�E������E�G��E�����`��E�ѓ����Y |
| ���c��E�i�R���j���R�k��E�n�Ӌ�E�O�֖L�� |
| ���_�����E�i�Q���j�v�ۓc���H�E���J��M�` |
| �����ϐ��E�i�Q���j���c���Y�E�{���G�g |
���a�R�W�N�V���I���@�i�C���@���a�S�P�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�Q�O���������[�j�q�n�����E���ؗNjg�E��؋g���E��ؐr�ܘY�E����i�n�E���Y��O�E�X�@�m��E���ِ��g�E�с@�ψ�E �@���c�M�g�E���@���v�E�@��ۈ�E������E�q��E�ѓ����Y�E�����F�E�с@���Y�E�ɓ��M��E���c�L��E�����`��E���J�`�j |
| ���c��E�i�R���j�ɓ��~��E��ؑP���E�����_�� |
| �Z�_�����E�i�Q���j�v�ۓc���H�E���J��M�` |
| �����ϐ��E�i�Q���j���c���Y�E��c���Y |
���a�S�P�N�V���I���C���@�@�@�i���a�S�S�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�U���������P�X���j�����F��E���c�v���E�ɓ����g�E�ɓ��M��E���t�����Y�E����i�n�E���c���Y�E�с@�v��E �@���@���v�E�����F�E�ɓ�����E���c�L��E�ѓ����Y�E��_�`��E��ؐr�ܘY�E���c�M�g |
| ���c��E�i�Q���j�ɓ��~��E���ؖ����v |
| ���_�����E�i�Q���j���c�����E���J��M�` |
| �����ϐ��E�i�P���j����@�� |
���a�S�S�N�V���I���C���@�@�i���a�S�V�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�U���������[�j�ɓ����g�E���@���v�E��_�`��E����ψ�E����i�n�E��t�����Y�E�M���M�`�E���c���Y�E�����F�E �@�����F��E�ɓ�����E�����M���E��c����E���c�v���E��ˁ@�~�E���؏d�Y |
| ���c��E�i�Q���j��ؑP���E�n�ӍD�j |
| ���_�����E�i�Q���j���ؖ����v�E�ɓ��~�� |
| �Z���ϐ��E�i�P���j����@�� |
���a�S�V�N�V���I���C���@�@�i���a�T�O�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�U���������P�W���j��t�����Y�E�\���E�E�����F���E����ψ�E�y��s�v�E���c�@�ہE�Γc���Y�E���J����o�v�E �@��ˁ@�~�E���������E����P�E�ɓ����g�E�����M���E��c����E�����@���E�a���ΐM |
| ���c��E�i�Q���j���c���Y�E�n�ӍD�j |
| ���_�����E�i�Q���j���ؖ����v�E�ɓ��~�� |
| �Z���ϐ��E�i�P���j����@�� |
���a�T�O�N�V���I���C���@�@�@�@�i���a�T�R�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�U���������[�j�ēc�d���Y�E���ٍF���E���ِ��g�E���J����o�v�E���������E�����@���E�\���E�E����ψ�E �@�y��s�v�E����P�E���c�@�ہE�Γc���Y�E��ˁ@�~�E��c����E�a���ΐM�E�����M�� |
| ���c��E�i�Q���j���c���Y�E�n�ӍD�j |
| ���_�����E�i�Q���j���ؖ����v�i���r�ŎO�j�ɍX�R�j�E�ɓ��~�� |
| �Z���ϐ��E�i�P���j����@�� |
���a�T�R�N�V���I���C���@�@�@�i���a�T�U�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�S���������[�j�ēc�x�j�E����P�E����ψ�E���J����o�v�E�\���E�E��c����E����t�v�E�����M���E�y��s�v�E �@�{���Ǝ��E��ˁ@�~�E���c�@�ہE���������E�a���ΐM |
| ���c��E�i�Q���j�n�ӍD�j�E�����ĕF |
| ���_�����E�i�Q���j�O�j�E�ɓ��~�� |
| �����ϐ��E�i�P���j����@�� |
���a�T�U�N�V���I���C���@�@�@�@�i���a�T�X�N�V���P�X���܂Łj
| ���I���ψ��i�P�S���������P�U���j�������F�E����P�E�{���Ǝ��E���{���j�E���c�@�ہE�����V��E���������E�C���O�m�E �@�ɓ����g�E����t�Y�E�y��s�v�E���J����o�v�E�ēc�x�j�E��c���� |
| ���c��E�i�Q���j���ؖ����v�E�с@���Y |
| ���_�����E�i�Q���j�n�ӍD�j�E���@���v |
| �����ϐ��E�i�P���j����@�� |
�@��P�R�߁@���̊J��
�W�c�A�_�Ɠ��A��
�@�����m�푈���I���ɋ߂Â��ƁA�ČR�̖{�y��P�͓���ǂ��Č������Ȃ�A�S���̎�v�s�s�͋�P�ɂ��œy�Ɖ����A��Ў҂��������ďZ��ƐH�Ǝ���͍ň��̏�ԂƂȂ��Ă����B�����������ԂɑΏ����Đ��{�́A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�T���Ɏ�����c�Ō��肳�ꂽ�u�k�C���a�J�Ґ�͉����{�v�j�v�ɂ���āA��Бa�J�҂̖k�C���W�c�A�_�v������肵���B���̋Ɩ����~���ɐ��s���邽�߁A���͓��N�U���u�k�C���W�c�A�_�Ҏ���v�j�v���߂����̋A�_�҂�����A�A�_�ɂ�鐶���̈����}��ƂƂ��ɐH�Ƒ��Y�Ɏ����邽�߁A�Q�O�N�x����N���Ƃ��ďW�c�A�_�ɂ��J��҂̎�����J�n�����̂ł���B
�@�����ɂ����Ă����̌v��Ɋ�Â��ĂQ�O�N�W���A���{����R�P���тP�Q�V�����A������i�t���j�E�Z�C���E�x�c�i�㔪�_�j�E���Ó��i�l���j�E��O�i�M�c�j�E��V�Ȃǂɕ��U���ē��A�����B�����͎�Ƃ��ĉ���o�g�҂ŁA�ړ��̓r���X�ŏI���m��Ƃ����ł��������߁A�̂��ɉ���ւ̋A�����F�߂���Ƒ啔���̂��̂͗��������̂ł���B
�@�܂��A���̔N�X���Ɍ�������J�C�����]�ƈ��i��\�ҁE�ѓ����Y�j�̈�c�R�U���тP�P�U���̂ق��Ɛg�j�q�R�S���Ə��q�P�R�����A���_��s��Ւn�ɓ��A���邽�ߗ��������B�������A���̂�����_�҂Q�O���т�����S�~��ɓ]�o�����̂ŁA�c��̏]�Ǝ҂������ėы��_�Ђ�g�D���A�O�����n���ɂ��������R�p�C���H������p�A���Ă̋@�B�H��Z�p�����Ĕ_�H�E���Y�E�����@�E���̑��̊��̏C�����Ƃ����c���Ȃ���A����s����_�k�K�n�̑ݕt���Ĕ_�Ƃɏ]���������A���Ƃ̐L�W���݂邱�ƂȂ��₪�ĉ��U�����B
�ً}�J��Ɠ��A��
�@�s��ɂ�鍑�y�̏k���ƁA���g�҂╜���҂̑����ɂƂ��Ȃ��A�H�Ƒ��Y�͓��{�l�̎����ɂ������ً}�ۑ�ł������B�����������Ƃ��琭�{�́A���a�Q�O�N�P�P���u�ً}�J�Ǝ��{�v�́v���߁A�S���I�Ȑ��J����J�n�����̂ł���B
�@����A���J���n�𑽂������Ă����k�C���ł́A���̐��{����ɐ旧���A�Q�O�N�P�O���u�k�C�����J����{�v�́v���߁A���L�n�E�䗿�n�E���L�n�Ȃǂ̔_�k�K�n�̑I��ƁA�ݕt���A�ɑS�͂������Ă����B
�@���R�p���_��s��Ւn���A�_�k�K�n��l�Z�������ً}�J��n�Ƃ��Ďw����A�����L�҂Ɨы��_�Ђ̈ꕔ�]�ƈ��́@�k��p�n�ɉ�����ꂽ���A���̓y�n�͂Q�T�N�T���ɘA���R�ɐڎ�����邱�ƂƂȂ��ĊJ��n���珜�O���ꂽ�B
�@���a�Q�P�N�T���ɑ�V�n��̉��A���L�ђn����Z�Z���Z�����]���J��n�Ƃ��đI�肳��A���̔N���_�z�R�̗��E�҂�O�n����̈��g�҂ȂǂP�T�˂����A���A�J��n�i�F��n��Ƒ��́j��n�݂��ĊJ�����Ƃ��J�n�����B���ɂQ�R�N�P���ɂ́A��������T��̓d�͔����@����ĊJ�������{���A����ɁA�P�T���~�̍H����������ĂP���Q�O�O�O���[�g���̔z�����s���ēd����V�݂���ȂǁA�J�Ƃ͐ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B
���̓��A�ː��@�@�i���a�Q�X�N�܂Łj
| �@�n�� �N�� |
�F�� | ��O | ���|�� | �g�x�g�}�� | �g�����x�c | �Z�C���E�x�c | �i���}�c�J | �L�\���y�^�� | ���� | �T�c�N�� | �u�C�^�E�V�i�C | �v |
| �Q�O | �@ | �P | �@ | �@ | �@ | �P | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �Q |
| �Q�P | �P�T | �@ | �@ | �@ | �@ | �S | �@ | �Q | �@ | �@ | �@ | �Q�P |
| �Q�Q | �@ | �@ | �@ | �@ | �T | �P | �R | �@ | �@ | �@ | �@ | �X |
| �Q�R | �Q | �Q | �@ | �@ | �Q | �Q | �P | �@ | �@ | �@ | �@ | �X |
| �Q�S | �P | �W | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �X |
| �Q�T | �@ | �@ | �Q | �R | �@ | �P | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �U |
| �Q�U | �@ | �P | �Q | �Q | �@ | �@ | �@ | �@ | �P | �@ | �P | �V |
| �Q�V | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �R | �@ | �@ | �R |
| �Q�W | �@ | �P | �@ | �Q | �P�R | �@ | �@ | �@ | �S | �@ | �@ | �Q�O |
| �Q�X | �Q | �P | �@ | �@ | �Q | �P | �@ | �@ | �P | �P | �@ | �W |
| �v | �Q�O | �P�S | �S | �V | �Q�Q | �P�O | �S | �Q | �X | �P | �P | �X�S |
�@���̂ق��A���N���ɏ㔪�_�̈ꕔ�ɑ�����Z�C���E�x�c�ɂS�ˁA�L�\���y�^���ɂQ�˂����A���A�܂��A�����n��ł�����҂ɂP�U�ˁA�t��ɂV�˂����A���ĊJ�����ݎ��Ƃ����{���ꂽ�B����ɗ��Q�Q�N�ȍ~�ɂ����ẮA����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ�薢���n�����ē��A������̂��������A�Q�X�N�܂łɔ��_�n��ɓ��A�����J��҂́A�ʕ\�Ō���悤�ɂX�S�˂ɒB�����B�����̓��A�҂ɑ��ẮA�c�_�����̑ݕt�A�Z��z�̕⏕�ȂǁA��X�̕⏕�{�u�����A�J�����ݎ��Ƃ��i�߂�ꂽ�̂ł��邪�A�����_�Ƃ̍k�n�ɔ�r���đ����̈�������w�����A���̋�J�͕��X�Ȃ�ʂ��̂�����A�J��̋ꓬ��������ꂽ�̂ł���B
�J��U����
�@���ً}�J�n�܂��Ĉȗ��A���a�Q�P�N����Q�V�N�܂ł̖k�C���̉ċG�́A��r�I���������̋C��Ɍb�܂�ĊJ��c�_�������ȐL�W���݂��Ă����B�������A�Q�W�A�Q�X�A�R�P�N�ƘA�����Ė{�����P������Q�A���Q�A���Q�́A�J��҂ɒv���I�ȑŌ���^���A�Ȃ�炩�̓��ʑ[�u���u���Ȃ�����A�c�_�̈ێ��p���͕s�\�Ƃ�����܂łɂȂ����B�悤�₭�J���̒i�K����o�c�K�͂̊g��Ɉڍs���悤�Ƃ���Ƃ��ɂ������Ă��̘A���V�Ђ́A���Y�̌����͂��납���̑����ƂȂ��Č���A�o�c��Ղ̎ア�J��_�ƂɂƂ��Ă͑傫�ȒɎ�ł������킯�ł���B
�@���������ɑΏ����Ĕ_�яȂ́A�R�P�N�x����s�U�n���Ȃǎ�X�̎{����u�������A���ɂR�Q�N�Ɂu�J��c�_�U���Վ��[�u�@�v�𐧒肵�āA�R�R�N�x���炢����u��ꎟ�J��c�_�U����v�����{���A���Z�[�u�̕��r���u���ĉc�_���P��}�낤�Ƃ������A���{�I�ȉ�����Ƃ͂Ȃ炸�A�Ǖ��I�ȂĂ�����ɂ����Ȃ��������߁A���x�o�ϐ����̒J�Ԃɂ����ꂽ���J��̎��E�͂��ڂ��Ȃ��ł������B
�@���̂��ߐ��{�́A���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�J��W�@���̉��������i�J��O�@�̉����j��}���āA�J��҂̉c�_���悤�₭�O���ɏ悹��ƂƂ��ɁA���N�_�яȂ́u�ߏ���A�n�����v�j�v�𐧒肵�āA��㖳�v��ɓ��A������ꂽ���߂ɐ������ߏ���A�n��c�_�s�U�n��Ƀ��X�����A�n��̈ӌ��Ɋ�Â��ĊJ��҂̈ꕔ���v��I�ɒn��O�ֈړ]�����A���������_�ƌo�c���s���J��҂̓y�n�ʐς��g�債�āA�o�c�̈����}�낤�Ƃ����̂ł���B
�@�����ɂ����Ă͂��̗v�j�Ɋ�Â��A�Q�P�N�ȍ~�ɂP�U�˂����A������T�����x�n��i�t���j��ΏۂɂS�˂̈ړ]���s�����̂��͂��߁A�R�U�N�ɂS�n��X�ˁA�R�V�N�ɂP�ˁA�R�W�N�ɂQ�n��U�˂Ƃ����悤�ɁA�J��_�Ƃ̈ړ]���u���ߏ���A�̒�����}�����B�Ȃ�����ɂ��ړ]��́A��˓�����R�T�N�x�P�T���~�A�R�U�N�x�ȍ~�R�O���~��������Ƃ��Č�t���ꂽ���A���̕��S�敪�͍����R���̂Q�A�����R���̂P�̊����ł������B
���_������
�@�J��W�@���̉����������s���A�J��҂̕��ɑ�������ɘa���}��ꂽ���̂́A����ɂ��Ă����͂�c�_��U�����锲�{��Ƃ͂Ȃ炸�A�������A�킪���̔_�Ƃ���芪���������܂��܂����̋ߑ㉻�ƍ\���̉��v���v������A�����������w�i�Ƃ��ď��a�R�V�N�x�i�P�X�U�Q�j�ɂ����āA�J��n�̎��Ԓ����i�J�������j�����{���ꂽ�̂ł���B���̌��ʁA�R�W�N�x�ɑ�U����������A�J��_�ƌX�̌o�c���e�ɂ��O�ɕ��ނ��A���ꂼ��K�ȑu�����邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A
�@���ޔ_�Ɓ����łɉc�_���m�����A�����ɗv���Ȃ�����
�@���ޔ_�Ɓ��c�_���m���ŐU����ɂ��A�����̕K�v�Ȃ���
�@��O�ޔ_�Ɓ��{�l�̊�]�ɂ��A�c�_��������Ƃ��āA���_�����̎{����u���邱�ƂƂ������
�ƈʒu�t���A
�@�P�A��ޔ_�Ƃɂ��Ă͊�{���ݍH���̊��������n�悩��܂��N�v��ŏ����n��w����s���ʌv������������ċ��̐����Ɣ_�p�{�݁A�ƒ{����є_�p�@�B�̓�����}��B
�@�Q�A��ޔ_�Ƃɂ��ẮA���łɊJ��_�Ƃ̑��Ɛ��Ƃ��āA��ʔ_�Ƃ̑ΏۂƂ��Ďw���������邱�ƂƂ��A�Œ艻���̂�����̂ɂ��Ă͂S�P�N���玩�n�����ɂ��؊����s��ꂽ�B
�@�R�A�O�ޔ_�ƁA�����c�_�̐U����������_�Ƃɑ��ẮA���_��]�҂ɂ͗��_�����A���̑��ɂ͕������u����ꂽ�B
�ȏ�̂悤�ȑ���R�W�N����S�Q�N�܂Ŏ��{���邱�ƂƂ����̂ł���B
�@�܂��A�O�ޔ_�Ƒ�̈�Ƃ��āA�V���Ɂu�J��җ��_������v���ł��o����A�R�X�N�x����ϋɓI�ɐi�߂��邱�ƂɂȂ����B���̑�ɂ�闣�_�⏕���́A�����S�T���~����t���ꂽ���A���̌㕨���̕ϓ��ɉ����đ��z����A�S�Q�N�x����T�O���~�A�S�S�N�x����T�T���~�A�S�U�N�x����U�O���~�i�\��҂ɑ��Ă͂T�O���~�j����t���ꂽ�B
�@���̑�Ɋ�Â��ď��a�R�X�N�x����S�T�N�x�܂łɗ��_���������̊J��_�Ƃ͕ʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A�����������_�҂̑唼�͕Ӓn���A�̊J��҂ł���A���̔w�i�ɂ́A��ʕs�ւ̂��ߐ��Y���̉^���A�~���Ԃ̏W���̐��Ȃǂ̏����������A�����d�˂ċ@�B����i�߂���A�o�c�K�͂̊g���}���Đݔ��������s���Ă��A���قǂ̎��v�͊��҂ł��Ȃ��Ƃ����Y�݂��������B����ɁA��N�J���͂̓s�s�ւ̗��o�̂��߁A�J���͕͂s�����ė��_������̂����o���A���̂قƂ�ǂ��s�X���邢�͖{�B�E���فE�����E�D�y�Ȃǂ̓s�s�ցA�J���҂Ƃ��ē]�o���Ă������̂ł���B
�@�Ő����̂R�Q�N�ɂ͂P�R�U�˂𐔂��������̊J��_�Ƃ��A�S�T�N�ɂ͂킸���ɂQ�R�˂��c�����邾���ƂȂ����B
�@�����������_�Ւn�́A�����_�Ƃ̍̑��n�A���L�܂��͕����L�̕��q�n��A�ђn�ɓ]�p�����Ȃǂ̗��p���}��ꂽ�B
�J��_�Ƌ����g��
�@���ϋɓI�ɊJ�J�n���ꂽ���̂́A���Ƃ͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A���A�҂̋���͌v��m��Ȃ����̂��������B���a�Q�Q�N�P�P���_�Ƌ����g���@���{�s���ꂽ���Ƃɂ���āA�J�Ƃɑ��鍑�̊e��⏕���₻�̑��̊J���̎���ꑋ���Ƃ��āA�܂��J��҂́A�J���E���݁E���Y�E�����Ȃǂ̑��i�ƈ����}�邽�߁A�e�n�ɂ����ĊJ��_���̐ݗ����i�߂���悤�ɂȂ����B
�@���a�Q�R�N�P�P���������ɂ����āu�������J��_�Ƌ����g���v���g�����Q�U���A�o�����P�W���~�������Đݗ�����A�g�����ɋg��F�Y���A�C���A�������𗎕���������ɒu���Ĕ��������B
�N�x�ʊJ��җ��_��
| �@�N�� �敪 |
�R�X | �S�O | �S�P | �S�Q | �S�R | �S�S | �S�T |
| �n �� �� | �T | �W | �T | �P | �Q | �S | �R |
| ���_�ː� | �X | �R�S | �P�T | �P | �Q | �U | �R |
�@�܂��A���_���ɂ����Ă����N�P�Q���ɂ́u�㔪�_�J��_�Ƌ����g���v�Ɓu�F��J��_�Ƌ����g���v���ݗ����ꂽ���A���̗��g���͂Q�X�N�V���ɍ������A���R�O�N�S���u���_���J��_�Ƌ����g���v�Ƃ��ĐV���ɔ����A�g�����P�O�R���A�o�����S���~�A�g�����ɓ������V���A�C�����B�����Ď������_��������ɒu���āA���A�҂̎���E���A�ɂƂ��Ȃ����葱���E���������̔z���E�J�����ݎ��ƁE�w�������Ȃǂɂ��������B
�@�������A�g���̉^�c��K�v�Ȋm��������Ȃ��A�⏕���Ƃ�Z�����Ƃ�ΏۂƂ������ۋ��ɑ啔�����ˑ�����Ƃ�������ł���A�������A�킸���̕��ۋ��͎�����ɂ������Ȃ��Ƃ����ŁA�ꂵ���^�c��������ꂽ�̂ł���B
�@�������A���X�ɉ����Ď{�s���ꂽ�e��{��ɑΉ����đg���Ɩ��͑�����ꂽ�̂ł��邪�A���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�A���̊J��җ��_���������x�̔����ɑO�サ�ė��_�҂��������悤�ɂȂ�A����ɁA�S�T�N�Ɏ��{���ꂽ�J��c�_�����������ƁA��������A�c�_�w������J��ی��w���x�̔p�~�ȂǁA�J��s���̏k�������ɂƂ��Ȃ��āA�����I�ɊJ��_���Ƃ��Ă̎��Ƃ͏I�����邱�ƂɂȂ����B���������āA�������J��_�Ƌ����g���Ɣ��_���J��_�Ƌ����g���́A�S�U�N�R���ɂ��ꂼ����U������J�Â̂����A���Z�l�𗧂ĂČ������P�N�ԂɎc���������s�����ƂƂ��A�c��̑g�����͈�ʔ_�Ƌ����g���ɉ����A�Q�O���N�ɂ킽��J��_���̋ꓬ�̗��j������̂ł������B
�@��P�S�߁@���_���̋�
�_�Ɖ��Ǖ��y����
�@�_�Ɖ��Ǖ��y���Ƃ́A�_�n���v��_�Ƌ����g���@�̎{�s�ȂǂƂƂ��ɁA���̖��剻����̈�Ƃ��ē���������̂ŁA���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�V���́u�_�Ɖ��Ǐ����@�v�̎{�s�ɂ���Ă��̏��ɂ������̂ł���B
�@���̖@���̎{�s�ɂƂ��Ȃ��A���͓��N�P�O���o�ϕ��ɔ_�Ɖ��ljۂ�V�݂��A�H�Ƒ��Y�B���̂��߂Ɏb��I�ɐ݂����Ă����u�H�Ƒ��Y�Z�p���v�����̎w�����ɂ����߂āA�����ɉ��Ǖ��y���Ƃ��������B�������āA�������_���_�Ƌ����g���������̒��ɁA�H�Ƒ��Y�Z�p���Ƃ��ēs�z�d�Y�����݂��A����ɂ��̎��Ƃ��^�c���邽�߂Ɂu���_�n��_�Ɖ��Ljψ���v���g�D���ꂽ�̂ł���B���Q�S�N�S���ɂ́u���_���_�Ɖ��Ǒ��k���v���ݒu����A�s�z�d�Y�i���a�Q�W�N�����ƂȂ�j�A��F�O�Y�̂Q�������y���Ƃ��Ĕz�u���ꂽ�B���x���������̉��Ǖ��y���́A���_�Ƃ̋Z�p���y�w���ɂ�����A�_�������̉��P��������Ƃ����T�[�r�X�ɓO���A�_�Ƃ̒���ُ������K�₵�Ď��n�w���ɂ��������B
�@���̌�A�����̐��ڂɂƂ��Ȃ����y���̐����A�Q�T�N�ɂ͂R���A�Q�U�N�ɂ͂S���ƔN�X��������A�Q�X�N�ɂ͔_�Ɖ��Ǖ��y���P����������ꂽ���A����ɑ����Đ������Ǖ��y���P�����z�u�����ȂǁA���x�̉����ɂƂ��Ȃ��Ē��������g�[����Ă������B
�@���a�R�Q�N�S�����������ɂ��u�������_�Ɖ��Ǒ��k���v�Ɠ������A�_�Ɖ��Ǖ��y���T���A�������Ǖ��y���P���ƂȂ�A���R�R�N�ɂ͓����̒�߂�Ƃ���ɂ��u�n���x�����_�n��_�Ɖ��Ǖ��y���v�Ɖ��̂��ꂽ�B
�@���X�ƈڂ�ς��_�Ə�ɑΉ����āA���y���̋Ɩ����e�ɂ��Ă��������ω����A���X�ɉ������������v�����ꂽ���A�R�X�N�ɂ͕��y���̑g�D�̐��̍ĕҐ������n�߂��A�u���y���Ƃ̍��V������}�邽�߁A�V���ɕ��y�w�������i�_�ƁE���N�E�����j���Z�p����ݒu���ĉ��Ǖ��y���̕��y�����̌v��̎����y�ьv��Ɋ�Â��������@�̎w���ɂ����炵�߂�v���ƂɂȂ����B
�n���k���n��_�Ɖ��Ǖ��y���i�ʐ^�P�j

�@���a�R�R�N�ɕ��y���J�݈ȗ����_�_�����ɂ��������������A�R�U�N�ɔ_���O�Ɉڂ��ēƗ����A����ɁA�S�O�N���_�ƒ{�ی��q�����ՂɈړ]�A�T�U�N�P���ɂ͓n���x�����_�Ŗ��o�����ՂɈړ]���Č��݂Ɏ����Ă���B��㏊���́A�s�z�d�Y�E����Y�E���O�Y�E�����@�L�E���c�q���ł���B
�ϐኦ��n�P��n�ѐU���Վ��[�u�@
�@���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�R���u�ϐኦ��n�P��n�ѐU���Վ��[�u�@�v�����z�{�s����A�{�����͂��ߓ��k�E�k���ȂǂP�S���{���̑S��ƁA����ɗאڂ���P�Q�{�����w����A���ꂼ��̎s��������������_�ƐU���܂��N�v��Ɋ�Â��č��������I�ɏ�������Ƃ������������ꂽ�B
�@�����ɂ����Ă����̖@���̎�|�Ɋ�Â��A�Q�U�N�P�P���u���_���_�ƐU���܂��N�v��v���������A�i�P�j�y�n�����̐����A�i�Q�j���Y�{�݂̊g�[�A�i�R�j�o�c�����̉��P�A�𒌂ɑ����Ɣ�Q���S�Q�P�V���~�]�ɋy�Ԏ��Ƃ̐��i���������̂ł������B���������̎��Ƃ́A���ʓI�ɂ͕K�����������̖ړI��B���ł��Ȃ������悤�ł���B���������āA�ϐኦ��n�т̖{�����͂��߂Ƃ���{���̋����v���̂��ƂɁA�}�@�Ɋ�Â��V���ȏ������ƂƂ��āA���a�Q�W�N����O���N�ɂ킽���Ĕ_���U�������������Ƃ����{����邱�ƂƂȂ������A�Q�W�A�Q�X�A�R�P�N�Ƒ�������Q�ɂ���āA�_�ƌo�c�͑啝�Ȍ�ނ�]�V�Ȃ�����A����܂��ڗ��������ʂ��グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�R�P��Q�Ƃ��̑�
�@�{�����P�������a�Q�W�N�̗�Q�ƕ����Q�A�Q�X�N�̑䕗�P�T���ɂ�鐅�Q�Ɨ�Q�A����ɁA�R�P�N�̗�Q�ƘA�����Ĕ�����������́A���������̗�O�ł͂Ȃ��A�_���ɑ傫�ȑŌ���^�����B���ɂR�P�N�̗�Q�͑吳�Q�N�ȗ��̋���Ƃ����A��Ɂu�R�P��Q�v�ƌĂ��قǔ�Q�͑傫�Ȃ��̂��������B
�@���������A���̗�Q�勥��̂��߁A�����̒����_�Ƃ͕��̗ݐς�]�V�Ȃ�����A�������A���̌Œ艻�ɂ���Đ[���Ȗ��ɔ��W�����̂ł������B���̂��ߓ��ł́A�R�O�N�Ɂu�_�ƕ��������i���v�𐧒肵�A�ϋɓI�ɔ_�ƌo�ς̍Č���}�낤�Ƃ���҂ɑ��āA���̉ݕt�����̑��̏����[�u���u���邱�ƂƂ����B
�@�����ɂ����Ă������̑[�u�ɑΉ����A���_�Ƃ̌o�ύČ��𐄐i���Ă��̌o�c�̈��艻��}�邽�߁A�R�P�N�P�O���ɏ��𐧒肵�A�����̕t���@�ւƂ��āA�_�Ƌ����g���E�_�ƈψ���E�J��_�Ƌ����g���Ȃǂ̑�\�҂���Ȃ�u���_���_�ƌo�ύČ��ψ���v��ݒu���A�K�v�Ȓ���E��������E����E�w�����s�����ƂƂ����̂ł���B
�@�܂��A�P�Q���J��̗Վ����c��ɂ����āA��Q�~�_�y�؍H�����c������A�����̉��ǍH����͐�̌�ݍЊQ�����H���A�����̎掖�ƂȂǂ����{���A�H�Ƒ�Ƃ��Ĕz���H�Ƃ̊m�ہA�J��ҋ~�ς̂��߂̂b�`�b�~���Ă̔z�z�Ȃǂ̑[�u���Ƃ�ꂽ�B
�}��������
�@���������A���̗�Q�����w�i�Ƃ��āA���a�R�Q�N�S���Ɋ��n�_�ƐU���̂��߂̓��ʗ��@����̉^�����N�����ꂽ���߁A�_�яȂ��͂��ߐ��{�@�ւɂ����钲�������̌��ʌ��肳�ꂽ�̂��A�R�R�N�T������́u�k�C��������P�v�j�v�ł������B����́A�o�c�s�U�ɂ���������_�Ƃ̉c�_���P�ɕK�v�Ȏ������A�_�ы��Ƌ��Z���Ɏ����������Ƃ��A�ᗘ�����̋��Z����u����Ƃ������̂ŁA�����Ƃ��Ă͍ł��L���ȉc�_���P�����ł������B
�@�������A����͖@���x�Ƃ��Ċm�����Ă��Ȃ��_�ɕs�������������߁A�{���̔_�ƊW�@�ւ͂������Ă��̗��@���ƁA�Z�������̊ɘa�ɂ��ċ��͂ȉ^���𑱂��A���ɂR�S�N�S���u�k�C������n����c�_���P�����Z�ʗՎ��[�u�@�v�i�}���������j�����肳��A�{�i�I�ȉc�_���P���Ƃ̊J�n���݂��̂ł���B���̖@���ł́A���̏����ɍ��v����u����n����U���n��v���w�肵�A���m���͂��̒n�悲�Ƃɂ�����p�x���猟�����A�V�`�P�O�N��ɓ��B���ׂ��c�_���P�v��𗧂Ă����A����ɂ���đݕt�K�i�̔F������_�Ƃɂ��ẮA�����ᗘ�̉c�_���P�����A������}�����������_�ы��Ƌ��Z���ɂ���Z���i�P�O�O���~�ȓ��j����邱�ƂƂ��ꂽ�B�����Ă��̐��x�͓����T���N�ԂŏI������\��ł��������A���̌���x�������������ꏺ�a�U�R�N�R�����܂łƂȂ�A�܂��A�Z�����x�z�����_��̂łP�S�O�O���~�A���̑��łX�O�O���~�ƂȂ��Ă���B
�@�����ł͂��̐��x���n�݂��ꂽ���a�R�R�N�x�ɁA��̓��Ə㔪�_�̂Q�n��łP�O�˂̔_�Ƃ��ݕt�K�i�̔F����A�c�_���P���s��ꂽ�̂��͂��߂Ƃ��āA���R�S�N�x�ɂ́A����E�x��E��V�ȂǂP�U�n�悪�w����A�������݂�_�@��w���Ȃǂ���̂Ƃ����c�_���P�v�悪���i���ꂽ�̂ł���B
�V�_�R�������ݑ�����
�@���a�Q�U�A�V�N�����Ƃ��Ă킪���̔_�ѐ��Y�Ƃ̖ڊo�܂��������ɂƂ��Ȃ��A�_�ѐ��Y���̉ߏ�X���Ɖ��i�ቺ�̌��ۂ��݂��A���Y�ƂƂ̏����i�����ڗ����͂��߂����߁A�悤�₭�������������ɂ��_�R�����U���{�]�܂��悤�ɂȂ����B����������̂Ȃ��Ō�������A���a�R�P�N�i�P�X�T�U�j������{����邱�ƂɂȂ����̂��u�V�_�R�������ݑ�����v�ł���A�����釀�V�������Â��臁�ł������B
�@���Ȃ킿�A�R�P�N�S���u�V�_�R�������ݑ������v�j�v�����肳��A�R�P�N�x����n��̏Ɍ��������_�R���������v������肵�āA�����I�Ȕ��W��}�낤�Ƃ�����̂ł���A���N�x����܂��N�̊Ԃɏ��o�ό��Ƃ��Ă̔_�R�����n����w�肵�A���ꂼ��̒n�悲�Ƃɐݒu����U�����c��Ɏ���I�Ȍv��𗧂Ă����A���̎��Ƃ̎��{�ɕK�v�Ȍo��ɑ��ĕ⏕���s���A���i��}�낤�Ƃ�����̂ł������B
�@�����͏��a�R�S�N�x�i�P�X�T�U�j�Ɍv������n��Ɏw�肳�ꂽ�̂ŁA��b�����̐����ƐU���v��̍���ɂ��������B�����Ă��̎��Ƃ��~���ɐ��i���邽�߁A�n����u���_�n��v�Ɓu�����n��v�ɕ����A�����E�c��c���E�_�ƈψ���E�_�Ƌ����g�����E���Ƌ����g�����E�y�n���Nj旝�����E�X�ёg�����Ȃǂ̂ق��A���N�N���u��N�w�l�g�D���\����҂Ȃǂɂ��A���ꂼ��̒n�悲�ƂɁu�_�R�����U�����c��v��g�D���A�����i�̑����I�ȘA�������ɂ��������B
�@���̌��ʁA���R�T�N�x�Ɂu���ʏ����n��v�Ƃ��Ēm���̎w����A���N�x����O���N�ɂ킽���ē��ʏ������Ƃ����{�����̂ł���B���Ƃ͓��ʕK�v�Ȃ��̂Ɍ���ꂽ���A���ɂR�U�N�x�ɔ��_���_�Ƌ����g�������Ǝ�̂ƂȂ��Ď��{�����_�������{�݂́A���_�n��Ǔ��_�ƂR�Q�V�˂Ƀe���t�H���E�X�s�[�J�[��ݒu���A�_���ɖ{����u�����݂ɒʐM�ł�����̂ŁA�_�Ə���Z�p�̎w���Ȃǂ̘A�����ł���悤�ɂ������̂ł���A�_�������ɂ����炵�����ւ͑傫�������B
�@�܂��A�����_�Ƌ����g���ł͋����W���P���̂ق����͌��p�~�X�g�@�P�X������ċߑ㉻��}��A���_�����Ƌ����g���ł͐��Y�����ɁA�����D�g�ꌚ�݂Ȃǂ̂ق����Q�T�m��Q������A�������Ƌ����g���ł͋��Q�T�m��U�������ȂǁA�o�c�̍�������}�����B�Ȃ��X�ёg���ł͉����@�_�łT��A�����łU�䓱�����A�y�n���Nj�ł͔n����q�y�Ȃǂ����{�������A����炪�_�R�����̖{�i�I�ߑ㉻�̑����ƂȂ����̂ł���B
��P�T�߁@�_�ƍ\�����P����
�_�ƍ\�����P���Ƃ̂˂炢�@
�@���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�U���ɐ��肳�ꂽ�u�_�Ɗ�{�@�v�Ɋ�Â��A���͍H�Ɨ\��n��������S���R�P�O�O�s�����ɂ��Ĕ_�Ƃ̋ύt�I�Ȕ��W�������ƂƂ��ɁA�_�Ə]���҂̒n�ʂ̌����ړI�Ƃ���o�c�̋ߑ㉻��}�邽�߁A�R�U�N�x����V���N�ɂ킽���Ė��N�x����n���I�肵�A�_�ƍ\���̉��P�Ɋւ���K�v�Ȏ��Ƃ������I�ɍs����悤�w���Ə������s�����j���߁A�u�_�ƍ\�����P���Ɓv��W�J���邱�ƂƂ����B
�@���̍\�����P�̊�{�I�ȍl�����Ƃ��ẮA�_�Ƃ��o�ύs�ׂƂ��Đ������邽�߂̗v���A���Ȃ킿�A�_�ƌo�c�̗v�f�ƂȂ�A�y�n�E�J���́E���Y��i�E�y�n���p�E���Y�\���E���H�̔���i�E���̂�����Ƃ��̌��т��Ȃǂ𑍍��I�Ɍ������A�v��I�ɉ��P���Ă������Ƃɂ���A�Ƃ�킯�A�_�ƌo�c�K�͂̊g��Ɛ��Y�̑I��I�g��E�K�n�K��E��Y�n�`���̊m���Ȃǂ���Ȃ˂炢�Ƃ��Ă����B
�@�܂��A�O�҂Ƃ��Ă������o�c�K�͂̊g��ɂ��ẮA�J���P�ʓ�����̏��������}�邽�߁A���U�_�n�̏W�c���E�y�n�̐����E���n����ѓy�n���ǎ��ƂȂǂ��s���A�啝�ȓy�n���p�̉��P��}��ƂƂ��ɁA�ƒ{�̓����E�c�_�̋@�B���𐄐i���Čo�c�̍������Ȃ�тɋߑ㉻���˂炢�Ƃ���B�����Č�҂ɂ��ẮA�o�ς̔��W�A���������̏㏸�ɂƂ��Ȃ����v�̓���������߁A���v�ɉ������_�Ɛ��Y�̊g���}��A�̔��◬�ʎs��ł̗D�ʐ���ۂ��߁A�K�n�K��E��Y�n�`����ϋɓI�ɐ��i����Ȃǂ̓_�����̊�{�I�Ȏw�j�ƂȂ��Ă����B
�@�܂����̎��Ƃ́A�_�n�̏W�c���E�����r���E�_���Ȃǂɂ������u��Ր������Ɓv�A�{�Ɍ��݁E�@�B�����E�W�ׁE�����E���H�{�݂Ȃǂ́u�o�c�ߑ㉻�{�݁v�̓�{���ĂƂ��A���̎��Ǝ�̂͂����܂ł������o�c�̂������Ă��Ă�Ƃ������̂ŁA�l���Ƃɂ��Ă͑ΏۂƂ��Ȃ����ƂƂ���Ă����B����ɁA���̎��Ɨʂ͑S�����ψ�n��łP���Q�O�O�O���~�ƂȂ��Ă���A���̂����R�O�O�O���~���Z�����ƂŁA�c��̂X�O�O�O���~���⏕���ƂƂȂ�B�����āA��n��̎��Ɗ��Ԃ͖�R�N�ŁA����ɁA�V���Ȓn��ő���Ƃ̔F�����Ɣ{�̎��Ɨʂ��s�����Ƃ��\�Ƃ��Ă����B
�@����ɑ��鎑�����B�ɂ��ẮA�Z���P�Ǝ��Ɓi��Ƃ��Čl�{�݁j�͔_�ы��Ƌ��Z���ɂ���R���T�Ђ̒ᗘ�����̓������@������A����ɁA�_�n��ђn�擾�̏ꍇ�����̒����Z���̓����J����Ă����B�܂��A�⏕���Ƃɂ��Ă͑��̂łT���A��Ր������Ƃɂ��Ă͖�V���̕⏕������A����ɁA���Ɣ��⏕���������������c�z�̂W���ɂ��ẮA�����ɂ���Z���i�U���T�Ёj�����邱�ƂɂȂ��Ă���A�����˂�o�ɂ��Ă̔_�Ƃ̕��S�͂��Ȃ�̌y���[�u���Ƃ��Ă����̂ł���B
�����ɂ�����\�����P����
�@������������I�Ȕ_�ƐU������̎��{�ɂ�����A�����ł͏��N���̏��a�R�U�N�Ɂu�_�ƍ\�����P�v��n��v�̎w����A�����̊e�W�@�ւƋ��c���d�ˁA���{�̐��̐����Ɗ�b�����𒆐S�ɏ�����i�߂�ƂƂ��ɁA���ɑΏ۔_�Ƃɑ��Ď��Ƃ̌[����`�ɓw�߁A���E�x������S���҂������Đ�������J�Â���ȂǁA��|�̓O���}�����̂ł���B
�@�������ĂR�V�N�x�Ɍv��𗧂āA�R�W�N�x���玖�Ƃ����{���ׂ�������i�߂��̂ł��邪�A���{�n��̑I��⎖�Ɠ��e�̌���Ȃǂ��x�ꂽ���߁u�t���v�n�������ɂ܂킵�A��ꎟ�̎��Ǝ��{�n��Ƃ��āu�͖k�v�E�u�����v�E�u�����v�̎O�n������肵�A����ɁA�n����鎖�ƂƂ��āu���_�������琬�q��v�̌��ݎ��Ƃ̎��{�����߁A�R�X�N�x����R���N�v��������Ē��肵���B
�@�����̌v��ɂ��A�����W�n��̊��ڂ��������ɂ����A�ꂢ����E�Ă��⊮��ڂƂ��A���̌v��̊�����ɂ����Ă͓����P�����̎����ڕW�Ƃ��A�����琬�q��̐ݒu�ɂ��{�B�e�n�ɗD�ǎ펓���̈ڏo��ڎw���Ƃ���ɓ��F���������B�������A�e�n��̐��Y�債�ė��_�o�c����������ƂƂ��ɁA��Y�n�`����ڎw�����߁A�y�n��Ր�����}��A�_�Ƌ@�B�����邱�Ƃɂ���āA���N�����X���ɂ���J���͂̕s����₢�A�c�_�W�c�̈琬�ɂ��ߑ㉻�𑣐i���邱�Ƃ��˂炢�Ƃ������̂ł������B
�@�ŏ��̒������_�Ō���ɂ܂킵���u�t���v�n��ƂƂ��ɁA�����Q�T�O�w�N�^�[���̗\��ɑ��Q�X�O�w�N�^�[���܂łɗp�n���g�傳�ꂽ���߁A�����琬�q��̍s���⊮���Ƃ�����ƂƂ��ĔF�߂��A���̓I�ɂ͂R�X�N�x����S�S�N�x�܂ł̂U���N�����{���ԂƂ��Ď��Ƃ�W�J���A�������_�̔��W�ɑ���̐��ʂ������炵���̂ł���B
�\�����P���Ƃ̊T�v
�@���a�R�X�N�x����U���N�Ŏ��{���ꂽ�����̔_�ƍ\�����P���Ƃ́A�n����鎖�ƂƂ��Ď��{�����琬�q��������A�l�n��ɂ�����⏕���Ƃ͑��z�Q���T�S�S���~�i�����A���E����⏕�P���Q�T�W�P���~�j�ɒB���A����ɗZ���P�Ǝ��ƂłP���U�P�O�S���~�̎��Ƃ��s��ꂽ�B
�@�����̎��Ǝ��{�n��͊��ɗ��_���̐i�n�тł��������A�Ȃ����������o�c�̋ߑ㉻���}���A��嗏�_�n�т̌`�����i�߂�ꂽ�킯�ł��邪�A���̎�Ȏ��Ƃ̊T�v�͎��̂Ƃ���ł���B
�P�A�y�n��Ր�������
�i�P�j�A��ʒ�����������
�@������̂ƂȂ�A�R�X�N�x�ʼnԉY�n��̂P�O�O�O���[�g���A��̏�n��̂Q�P�R�U���[�g���̐����A�S�O�N�x�ő�V�n��̂P�U�V�W���[�g���̐������s��ꂽ�B
�i�Q�j�A�����r�����Ɣ��_�_�������Ǝ�̂ƂȂ�A��V�n��̂Q�U�P�O���[�g���A����n��̂Q�P�O�O���[�g�������{�A�܂��A����Ƃł͏t�����n��̂Q�V�O���[�g���A�����n��̂Q�U�S�O���[�g���Ȃǂ����{���ꂽ�B
�i�R�j�A���n�������ǎ���
�@���_�_�������Ǝ�̂ƂȂ�A�t���n��łR�W�E�W�w�N�^�[���̑��n�����A���킹�Ėq��S�T�X�V���[�g����ݒu�����B
�i�S�j�A�k�y���ǎ���
�@�����_������̂̎��ƂŁA���w�y�̊��p��}�邽�߁A�R�X�N�x����R���N�ō���n�P�Q�T�w�N�^�[���̔��]�q�y�����{���A�������ւ̓]����}�����B
�Q�A�o�c�ߑ㉻�{�ݎ���
�i�P�j�A�g���N�^�[��������
�@�͖k�n��łW��i��Ƌ@�S�W��j�A�����n��łU��i���R�Q��j�A�����n��łR��i���P�X��j���͂��߁A����Ƃŏt���n��ɂU��i���T�V��j���A���ꂼ�ꗘ�p�g���P�ʂœ�������A����������̎����Ɍ������Ċ��p�̓����J���ꂽ�B
�i�Q�j�A�ƒ{�p���{��
�@���_�_�������Ǝ�̂ƂȂ�A�����P���R�X�R�T���[�g���̓��z���ǂ�z�݂��A��V�n��T�W�ˁA�P�T�R�O���̓����ɋ�������ƒ{�p���̊m�ۂ�}��A����������̊�Ղ������B
�i�R�j�A�Ǎ��ɁE�Ď��ɂ̌���
�@���ɑ����̊J��p�C���b�g�̕⊮�{�݂̈�Ƃ��āA�Ǎ��Ɂi�P�Q�X�U�������[�g���j�ƊĎ��ҁi�Q�U�E�V�������[�g���j�����݂��A�{�݂̌��p�傳�����B
��ꎟ�_�ƍ\�����P���ƕ⏕���Ǝ���
| �@�敪 �N�x |
���Ǝ�� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@�� | ���Ɣ� | ���@�S�@��@�� | |||
| ���@�� | ���@�� | ���̑� | ||||||
| �R�X | �y�n��� �������� |
��ʔ_�� �������� |
�� | �ԉY�n�扄�� �@�@�@�@�@�P�C�O�O�O�� �����P�C�Ë��Q �Ҕ����R�C��t���H�V |
��~ �P�C�X�X�X |
��~ �P�C�O�X�W |
��~ �R�X�X |
��~ �T�O�Q |
| ��m��n�扄�� �@�@�@�@�@�Q�C�P�R�U�� �����Q�C�Ҕ����R�C ��t���H�V |
�R�C�O�V�S | �P�C�U�X�O | �U�P�O | �V�V�S | ||||
| �S�O | ��V�n�扄�� �@�@�@�@�@�P�C�U�V�W�� �����Q�C��t���H�S |
�R�C�U�Q�X | �P�C�X�X�T | �V�Q�T | �X�O�X | |||
| �R�X | ��V�n�� ���� �r������ |
���_���_�� | �����@�@�U�W�O�� �@�V�S�D�Rha |
�V�C�X�T�S | �S�C�R�V�S | �P�C�T�X�O | �P, �X�X�O | |
| �S�O | �����P�C�X�R�O�� �@�X�W�D�Uha |
�Q�T�C�P�T�S | �P�R�C�W�R�S | �T�C�O�R�O | �U, �Q�X�O | |||
| �R�X | ����n�� ���� �r������ |
�����Q�C�P�O�O�� �Q�T�Q�D�Sha |
�@�P�T�C �U�U�U | �W�C�U�P�T | �R�C�P�R�R | �R�C�X�P�W | ||
| �R�X | �����n�� ���]�q�y ���Ɓ@�@ |
�������_�� | �k�N�T�Oha | �Q�C�S�O�O | �P, �R�Q�O | �S�W�O | �U�O�O | |
| �S�O | �k�N�R�Oha | �P�C�T�W�O | �W�U�X | �R�P�U | �R�X�T | |||
| �S�P | �k�N�S�Tha | �R�C�P�Q�O | �P�C�V�P�U | �U�Q�S | �V�W�O | |||
| �v | �@�@ | �@�U�S�C �T�V�U | �R�T�C�T�P�P | �P�Q�C �X�O�V | �P�U, �P�T�W | |||
| �R�X | �o�c�ߑ㉻ �{�ݎ��� |
�����n�� �g���N�^�[ �������� |
���p�g�� | �{�@�Q���ƕ��P�U�� | �T�C�Q�Q�V | �Q�C�R�X�R | �@ | �Q�C�W�R�S |
| �S�O | �{�@�S���Ƌ@�P�U�� | �V�C�X�X�V | �R�C�U�U�W | �@ | �S�C�R�Q�X | |||
| �R�X | �͖k�n�� �g���N�^�[ �������� |
���p�g�� | �{�@�V���Ƌ@�S�T�� | �@�Q�O, �W�W�Q | �X�C�T�T�T | �@ | �P�P, �R�Q�V | |
| �S�O | �{�@�P���Ƌ@�@�R�� | �Q�C�O�Q�R | �X�Q�U | �@ | �P�C�O�X�V | |||
| �R�X | �����n�� �g���N�^�[ �������� |
���p�g�� | �{�@�P���ƕ��@�X�� | �R�C�O�T�R | �P�C�R�X�V | �@ | �P�C�U�T�U | |
| �S�O | �{�@�Q���Ƌ@�P�O�� | �S�C�U�U�R | �Q�C�P�R�T | �@ | �Q�C�T�Q�W | |||
| �S�O | ��V�n�� �ƒ{�p�� �{�� |
���_�_�� | �����P�R�C�X�R�T�� �P�C�T�R�O�����T�W�� |
�P�U�C�T�Q�R | �V�C�U�U�T | �@ | �W�C�W�T�W | |
| �v | �@ | �U�O�C�R�U�W | �Q�V�C�V�R�X | �@ | �R�Q�C�U�Q�X | |||
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �P�Q�S, �X�S�S | �U�R�C �Q�T�O | �P�Q�C �X�O�V | �S�W�C�V�W�V | ||||
��_�ƍ\�����P���Ǝ���
�i�P�j��n��Ր�������
| �@�敪 �N�x |
���Ǝ�� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@�� | ���Ɣ� | ���@�S�@��@�� | ||
| ���@�� | ���@�� | ���̑� | |||||
| �S�Q | �t�����n�悩 ������� |
���_�� �_�Ƌ��� �g�� |
�� �Q�C�Q�V�R |
��~ �R�P�C�O�V�R |
��~ �P�V�C�O�W�X |
��~ �U�C�Q�P�S |
��~ �V�C�V�V�O |
| �S�R | �t�����n�悩 ������� |
�R�V�O | �S�C�S�P�W | �Q�C�S�Q�X | �W�W�R | �P�C�P�O�U | |
| �t�����n�悩 ������� |
�Q�V�O | �S�C�W�P�Q | �Q�C�U�S�U | �X�U�Q | �P�C�Q�O�S | ||
| �t���n�摐�n�� �����ǎ��� |
ha �R�W�D�W |
�U�C�S�T�Q | �R�C�Q�Q�U | �P�C�Q�X�O | �P�C�X�R�U | ||
| �t���n��q��u �ᕨ�ݒu���� |
�@�� �S�C�T�X�V |
�P�C�O�O�U | �T�O�R | �Q�O�P | �R�O�Q | ||
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �@ | �S�V�C�V�U�P | �Q�T�C�W�X�R | �X�C�T�T�O | �P�Q�C�R�P�W | ||
�i�Q�j�o�c�ߑ㉻�{��
| �@�@�敪 �N�x |
���Ǝ�� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@�� | ���Ɣ� | ���@�S�@��@�� | ||
| ���@�� | ���@�� | ���̑� | |||||
| �S�Q | �g���N�^�[ ���� |
�t����P�C�Q�C�R ���p�g�� |
�{�@�R�� ��Ƌ@�R�Q�� |
��~ �P�R�C�U�V�S |
��~ �T�C�X�S�P |
��~ �@ |
��~ �V�C�V�R�R |
| �S�R | �g���N�^�[ ���� |
�t����P�C�R ���p�g�� |
�{�@�Q�� ��Ƌ@�P�T�� |
�P�O�C�W�W�P | �S�C�V�Q�V | �@ | �U�C�P�T�S |
| �S�S | �g���N�^�[ ���� |
�t����P�C�Q�C �R���p�g�� |
�{�@�P�� ��Ƌ@�P�O�� |
�U�C�P�S�T | �Q�C�U�U�T | �@ | �R�C�S�W�O |
| �Ǎ��� �Ď��Ɍ��� |
�r���j���� �p�g�� |
�Ǎ��� �P,�Q�X�U�u �Ď��ɂQ�U�D�V�R�u |
�Q�C�O�R�W | �W�W�Q | �@ | �P�C�P�T�U | |
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �R�Q�C�V�R�W | �P�S�C�Q�P�T | �@ | �P�W�C�T�Q�R | |||
�i�R�j�Z���P�Ǝ���
| ���Ǝ�� | ��v�͈� | ���{��� | ���@�Ɓ@�� | ���@�Ɓ@�� |
| �{�@�@�@�@�� | �@�@�� �U�W |
�@�@�l | �@�U�W���X�C�U�P�U�u | �@�@�@��~ �P�Q�P�C�P�Q�V |
| �T�@�C�@�� | �@�@�R�W | �V | �@�@�@�@�@�R�W�� | �@�@�@�@�P�R�C�U�Q�O |
| �́@��@�� | �@�@�P�P | �V | �@�P�P��P�C�O�S�W�u | �@�@�@�@�@�R�C�U�P�O |
| �_�@�@�@�@�� | �@�@�@�W | �V | �@�@�W���U�S�T�u | �@�@�@�@�@�R�C�W�S�O |
| ���@�@�@�@�� | �@�@�@�P | �V | �@�@�@�@�@�P�R�� | �@�@�@�@�@�R�C�P�T�O |
| �_�@��i�[�� | �@�P�V�Q | ���p�g�� | �@�P�S���P�C�T�R�P�u | �@�@�@�@�P�T�C�U�X�O |
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �@�@�@�P�U�P�C�O�R�V | |||
(�n���Ǔ��_�ƍ\�����P���Ƃ̂����)
�R�A�Z���P�Ǝ���
�@�{�ɂU�W���A�T�C���R�W��A�͔�ՂP�P��A�_�ɂW���̂ق��A�g���N�^�[���p�g���̔_�@��i�[�ɂP�S�������݂��ꂽ�B�܂��A�����P�R���i�P�ˁj�̐V�K�������}��ꂽ�B
�����琬�q��
�@�_�ƍ\�����P���Ƃ̂Ȃ��ŁA�g�n����鎖���g�Ƃ��Ē������Ǝ�̂ƂȂ��Čv�悳�ꂽ�����琬�q��́A�������̎�Y�n�`���Ƒ��������牻���i�̎����Ɍ����A�q���̗a���琬�ƗD�ǎ����̂���{��ړI�Ƃ��āA���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j���Ƃɒ���A��ꎟ�A���ʂ��đO��T���N�ɂ킽���đ������ꂽ����I�Ȃ��̂ł������B
�@�I���J��n�Ƃ��ĐV�K���A�҂��}�����n�V�m�X�x�c�n��i�M�c�j���A�琬�q��̓K�n�ƑI�肵�����ł́A���肩��o�c�s�U�ɂ���ċꓬ���Ă����y�n���L�҂ƌ��̂����p�n�̔�����i�߁A�J����Y���܂߂ĂQ�W�S�w�N�^�[���]�̗p�n���m�ۂ����B�����ĂS���N�������ĂQ�O�S�w�N�^�[���]�̑��n������ƂƂ��ɁA�琬�����ɂP���W�R�U�������[�g���i�T�C���Q��A�A���A�͔�Պe�P��ȂǕt�݁j�E�_�@��i�[�ɁE�Ď��ɁE�q�v�Z��Ȃǂ����݂��A����Ƀg���N�^�[�Q�������ȂǁA���o��W�S�U�S���~�𓊂��Ė{�i�I�Ȉ琬�q��������B�i�������u���_�_�Ƃ̊T�v�v�j
�@�������āA����ƈ琬��������嗏�_�̌`����ڎw�������̂Ƃ��āA���̌��p�ɑ傫�Ȋ��҂��W�߂Ȃ���a�����̎�����J�n�����̂́A���������H���̊����ԋ߂��ȏ��a�S�P�N�U���R���ł������B
�@���̈琬�q��́A���R�W�_���̊��҂�S���Ă̊J�݂ł͂��������A�����I�ɂ��̌�̗a�����݂�ƁA�Ċ��Ԃł͂����ނ˂R�O�O���ȏオ���q���ď����̐��ʂ��グ���Ƃ͂����A�~���Ԃł͂��悻�T�O�`�U�O���̎��e�Ƃ����̂��ʗ�ŁA�o�c��s���S�ȏ�Ԃł������B���̂��߂S�V�N�P�P�����痂�N�T���܂ŁA�����I�ɓ~���Ԃ̗a���𒆎~���ď��ώ@���A���̌�Ăѓ~���a�������{���Ă݂����A�z�~�a�����͂悤�₭�X�O�����ɂƂǂ܂�ł������B
�q��̑����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �@�@�@��@�� ���Ǝ�� |
���@�Ɓ@�� | ���@�Ɓ@��@���@�� | ||||
| ���@�v | �⏕�� | ���@�� | ||||
| �� �� �� �� �� |
�� �� �� �� |
�� �n �� �� | �P�W�Vha | �Q�O�C�Q�Q�Q | �P�R�C�R�V�O | �U�C�W�T�Q |
| �q�@�@�@ �� | �R�C�Q�V�P�� | �W�C�Q�Q�W | �T�C�V�T�W | �Q�C�S�V�O | ||
| �q�@���@�� | �P�T�C�T�X�Q�� | �Q�C�W�V�T | �Q�C�O�P�P | �W�U�S | ||
| �琬������ | ���ɂP���W�R�U�u�C�T�C���Q�� �A���͔�ՂP��C�T�C���A�����|�_ �o���N���[�i�[�o�h�b�N |
�P�X�C�V�O�W | �X�C�O�Q�S | �P�O�C�U�W�S | ||
| �� �q �{ �� | ����P���@�@�@�@�@�T�S�u ���@�@�@���@�@�@�@�@�V���� |
�P�C�S�O�P | �U�S�P | �V�U�O | ||
| �_�@��i�[�� | �P���X�V�u | �P�C�Q�O�R | �T�T�O | �U�T�R | ||
| �g���N�^�[ | �{�@�@�@�S�S�D�T�o�r�@�Q�� ��Ƌ@�@�@�@�@�@�@�@�P�S�� |
�U�C�V�U�W | �R�C�O�X�X | �R�C�U�U�X | ||
| ���@�@�@ �v | �@ | �U�O�C�S�O�T | �R�S�C�S�T�R | �Q�T�C�X�T�Q | ||
| �� �� �� �P �� �� �� |
�p �n �� �� | �Q�W�S�D�R�Sha | �X�C�Q�S�Q | �@ | �X�C�Q�S�Q | |
| �d �C �� �� | �R�� �k���P�C�Q�O�O�l�ሳ�ː� |
�P�C�U�Q�V | �@ | �P�C�U�Q�V | ||
| �p �� �{ �� | �����ǁ@�@�k���Q, �W�W�U�� �������P���@�Z��R�˔z�� |
�Q�C�P�O�O | �@ | �Q�C�P�O�O | ||
| �q �v �Z �� | �Q���@�@�@�@�@�@�@�P�P�Q�u | �P�C�U�V�R | �@ | �P�C�U�V�R | ||
| �L �� �{ �� | �L�������{�݂Q���� | �V�R | �@ | �V�R | ||
| �A �� �� �H | �q�������ԁ@�@�@�k���W�U�� | �P�W�S | �@ | �P�W�S | ||
| �A���p������ | �P�� | �V�W�T | �@ | �V�W�T | ||
| ��@�A�@�� | �P�� | �X�R | �@ | �X�R | ||
| ���@�@�@ �v | �@ | �P�T�C�V�V�V | �@ | �P�T�C�V�V�V | ||
| �� �� �� �� �� |
�� �� �� �� |
�� �n �� �� | �P�V�D�Qha | �R�C�O�O�O | �Q�C�P�O�O | �X�O�O |
| �q�@�@�@ �� | �T�O�O�� | �Q�C�W�W�W | �Q�C�O�Q�P | �W�U�V | ||
| �q�@���@�� | �P�C�W�Q�O�� | �S�U�S | �R�Q�S | �P�S�O | ||
| �� �� �{ �� | ���E�̏d�v | �P�C�Q�Q�P | �T�O�O | �V�Q�P | ||
| ���@�@�@ �v | �@ | �V�C�T�V�R | �S�C�X�S�T | �Q�C�U�Q�W | ||
| �� �� �� �P �� �� �� |
�� �� �� �� | �@ | �S�T�U | �@ | �S�T�U | |
| �� �� �� �� | �P�� | �Q�V�W | �@ | �Q�V�W | ||
| ���n�p���� | �P�� | �P�T�U | �@ | �P�T�U | ||
| ���@�@�@ �v | �@ | �W�X�O | �@ | �W�X�O | ||
| ���@�@�@�@�@�v | �W�S�C�U�S�T | �R�X�C�R�X�W | �S�T�C�Q�S�V | |||
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���ł͂���ȏ�~���a���𑱂��Ă������̌����݂��Ȃ��Ƃ�������f�������āA�S�X�N�x�ȍ~�~���Ԃ͑S�ʓI�ɒ�~���邱�ƂƂ����̂ł���B
�@���̖q��́A�s�X�n�����V�L�����[�g�����ꂽ�u�˒n�тŁA�ł������n�т���͎s�X�n�S�i�╬�Θp�A���_��s��Ȃǂ��ቺ�ɍL����A����ɁA�����L��x��r���R�A��x�̏������]�ł���B�܂��A�̑����ɕ��q����Ă���ው�߂Ȃ���A�̂ǂ��ȋC���ɐZ���Ƃ����q�̓I�ȕ��i�����A���_�ƌ��т����ό��n�̈�Ƃ��Ē��ڂ���A���a�S�W�N����͊ό�����̎�Âɂ���g�q��܂��g���J�Â���āA�����̍s�y�n�Ƃ��Ē蒅������B
�@�����������ʁA�q��̎��͂͑����̋u�˒n�⏬�R�Ɉ͂܂�A�܂��A���L���n���݂邱�Ƃ���A���N�X�����{����P�P����{�ɂ����Ėk�C�����L�̂��܂��o�v���A�앨���r�炳��邱�Ƃ����������A���a�T�S�N�ɂ͓��q���̗a�����P�����P���Ď��S����Ƃ������̂��������A�F�����̏o��v�����ĎˎE�����̂ł������B���̎����ɂȂ�Ɩq��E���͓��邭�܂̌x���ɋ�J���Ă����Ԃł��邪�A�O�L���̂̔����Ȍ�͗a�������P����Ƃ������̂͂Ȃ����̂́A�t�߂łQ�����ˎ~�߂��Ă���B
�@�Ȃ��A�S�U�N�V���ɂ͒��E���[�Ԗ����A���q���̗a������{�����Ă����ہA�g���N�^�[���̂ɂ���ď}�E����Ƃ����ɂ܂����o�������������B
�@��P�U�߁@�@�B���̕ϑJ
���m�_�@��̓���
�@�J�������Ɏg�p���ꂽ�_�@��Ƃ����A�������肪�܁E������E������E�������Ȃǂł���A���m�_�@��̓����ɂ��Ă͑�P�͑�Q�߂ɂ����Ď�L�ڂ����Ƃ���ł��邪�A�����P�P�N�X�����A�Ԃ��Ȃ�����ƊJ��������ɂ����āA�J��g���َx�����d���Ǝ����ꂩ��h�����ꂽ�Z�p�����A�k���S���|���̃v���E�ōr�n��l�������k�N�����̂����̒n���ɂ����鐼�m�_�@��g�p�̏��߂Ƃ�����B����ɂ��J��������ł́A�ڏZ�l�̂����̓Ɛg�҂�q��̈ꕔ�̎҂����d���Ǝ�����Ɍ��Ɛ��Ƃ��Ĕh�����A�@�B�ނȂǂ̎�舵�������K�������̂ł���B�����͋A����A�J����̉������đ�_�o�c���v�悵�A�h�̑��i���A����j�ɑ�_�ɂ����Ăĉ��Ď��̔_�@�����݁A�T���L�v���E�A���[�p�[�A�V���X�~�V���A�J���`�x�[�^�[�Ȃǂ̗m���_��ɂ��J����Ƃɒ��肵���B���ʂ͏\���Ȑ��ʂ��Ȃ������Ƃ͂����A���m�_�@������Ĕ_�ƌo�c���s�����Ƃ������Ƃ́A�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ�����I�Ȏ����ł������B
�@�����̔����납��e�n�Ŕ_��o�c���s�����̂������Ȃ������A�Ȃ��ł������R�P�N�i�P�W�X�W�j�ɊJ�݂����R��̐ΐ�_��̏���_�Ƃł́A�S�Q�N����ɂ͒{�͔_�@��͍č��v���E�P�W��A�n���[�P�Q��A�J���`�x�[�^�[�P�Q����g�p���Ă����Ƃ����B
�@�J�����i�݁A���_���Y�̂ꂢ����͔|������ɂȂ�ɂ��������č�t�ʐς��g�傳��A�_�@�������Ɍ������ǂ���Ă������B���I�푈�O�ォ�炱��܂ł̕�����ɑ����āA�v���E�A�n���[�A�J���`�x�[�^�[�A�d�i�́j���Ȃǂ̐��m���_�@��A��ʂɎg�p�����悤�ɂȂ����B
�@�܂��A�n�Y�̏���ɂƂ��Ȃ��ē������������A�n�k�_�Ƃ����y����悤�ɂȂ�A�k����Z�p�̔��B�Ɖ^���\�͂̑���ɂ���āA�{�͔_�@���n�ԁE�n����̑䐔���������������������B
�@����_����ɂ�����吳�����̐��m�_�@��̕��y�͎��\�̂Ƃ���ł��邪�A�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�ɂ͉��ׂQ�Q�R��A�_�ƂP�˓�����P�E�R��ł��������̂��A�W�N�ɂ͉��ׂS�R�O��A�P�˓�����Q�E�R��ƂȂ�A�R���g�Ƃ��Čv�Z����ƂV�U�p�[�Z���g�̕��y���ŁA�����̂R���̂Q�̔_�Ƃ����S�Ȕn�k�_�Ƃ��c��ł����킯�ł���B
�@��ꎟ���E���I����A�_�Y�����i�̖\���ƁA�J��ȗ�������ꂽ���D�_�Ƃɂ��n�͂̒ቺ�ɂ���Ĕ_�ƌo�ς͋ɓx�ɔ敾�����B����𗧂Ē������ߓ���_��ł́A�_�������E�͔|�����Ȃǂ��s���ق��o�ώ������J�n����ȂǁA�ϋɓI�Ȕ_������ɏd�_�������āA�����쑝�Y��{�ɉ��ǂɉ�����^�����B�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�W���ɂ́u���͗��p�������v��V�݂��A�_�Y���̐��Y�ʂ̒ቺ�h�~�ƘJ���\���̌���̂��߁A���͋@�B�_��̗��p���y��}��A�g���N�^�[�A�G���W���A�X���b�V���[�A�X�v���[�_�[�A�G���V���[�W�J�b�^�[�A�O���C���_�[�A�f�X�N�n���[�Ȃǂ̗m����_����w���̂����A���̎g�p���@���������K����ƂƂ��ɁA�قƂ�ǎ���ɓ����������ŏ���l���̑���ʔ_�Ƃ̈˗��ɉ����āA�č��E�E���E�G���V���[�W�荞�݁A���̑��̍�Ƃ��s�����B�������A�����̓��͋@�B�_��̗��p���y�́A�K�����������̖ړI��B����ɂ͎���Ȃ��������A�G���V���[�W�J�b�^�[�ɂ�����Ƃ����낱���̐荞�ݍ�Ƃ́A�ɂ߂čD���т������A���̌��ʃT�C�������Ă���̂������A���_�̔��W�𑣐i���邤���ő傫�Ȗ������ʂ������B
�@�吳�P�Q�A�R�N��������ɁA���_�n���͍����キ�_�Ƃ��Q���X���������A�����̑����ƂƂ��Ɏ����앨��V�R�����n�͑���̌X���ɓ]���A����ɂ��_�ƌo�c�̏ȗ͉��Ƌ@�B���𑣐i����Ɏ������̂ł���B

| �@�@�N�@�� ��@�� |
�吳�R�N | �S�N | �V�N | �W�N |
| �v�@�@�@���@�@�@�E | �W�S | �P�P�U | �P�S�W | �P�S�V |
| �n�@�@�@���@�@�@�[ | �V�T | �X�V | �P�Q�X | �P�R�X |
| �J���`�x�[�^�[ | �U�S | �X�Q | �P�R�S | �P�S�S |
| �n�@�@�@�@�@�� | �T�O | �T�W | �W�T | �X�P |
| �n�@�@���@�@�� | �P�O�R | �P�P�W | �P�S�W | �P�R�V |
(�����@����_�ꔭ�B�j)
�@���̎���ɂ����鐼�m�_�@���n�ԁE�n����̑䐔���݂�Ǝ��\�̂Ƃ���ł��邪�A�v���E�A�n���[�A�J���`�x�[�^�[�Ȃǂ̒{�͔_��A�O����Ɉ��������Ĉ�w�̕��y���݂�����łȂ��A���Y��ߌ��̂��߂̓��͋@�B���̎g�p���V���ɂ݂���悤�ɂȂ�A�v���E�A�n���[�A�J���`�x�[�^�[�͂���������̎���ɒ������������A�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j�ɂ͉��ׂS�R�T��A�_�ƂP�˓�����Q�E�S��ł��������̂��A���a�T�N�i�P�X�R�O�j�ɂ͉��ׂT�T�P��A�P�˓�����Q�E�W��ƂȂ�A�R���g�Ƃ��Čv�Z�������̒{�͔_��̕��y���͂X�R�E�R�p�[�Z���g�ɒB���A�����ނˑS�_�Ƃ����S�Ȕn�k�_�Ƃ��c�ނ��ƂƂȂ����B
�@�n�k�_�Ƃ̕��y�ƂƂ��ɔn�Ԃ�n����̑䐔���������A�吳�X�N�ɔn�ԂX�U��A�n����P�S�R��ł��������̂��A���a�T�N�ɂ͂��ꂼ��P�T�Q��A�Q�O�R��Ƒ������A�啔���̔_�Ƃ����������L����Ɏ������B
�@�������ł��������̂́A�����@�A�E���@�A�G���V���[�W�J�b�^�[�A�w�[�J�b�^�[�Ȃǂ̒E�������W�̓��͔_��ނŁA�����̔_�Ƃł͂��邪�Q�����y����A�o�c�̍������Ɛ��Y��̐ߌ����}���Ă������B
�t�H�[�h�g���N�^�[�i�ʐ^�P�j

����_��ɂ�����g���N�^�[�ɂ��q������i�ʐ^�Q�j

�@����A�吳�̖����珺�a�ɂ����āA�{�͔_�Ƃ̔��B��w�i�ɂ��Ȃ���A���a�U�N�ɂڂ������������푈��������������ɂ�Ĕ_���s�N�w�̘J���͂����ꂵ�A���Y�͂������������߁A�]���̒{�k�芠��̍�Ƒ̌n���玟��Ɋe��ƕ���ɂ�����@�B�̉��ǁA�Z�p�J�������̉ߒ����o�āA���ɐ펞���̑�_���@�B�������̏���ɂ��A�Q���A���͂ɂ���Ƒ̌n�ւƈڍs�����̂ł���B
�@���a�Q�O�N�W���L�j�ȗ��̔s��ɏI���������̂킪���̔_�Ɛ��Y�́A�ɓx�Ɉ������ĐH�Ɠ�ɔY�܂���Â����B���{�͐H�Ƒ��Y�̏�����d�_�{��Ƃ��āA�����̐H�Ɗm�ۂɓw�߂��̂ł���B
�@�܂��A�I�풼�㐻�i�s��̕���k���ɂ���āA�ꋫ�ɗ������ꂽ�@�B�H�ƊE�́A�ꎞ�I�ɔ_�@���ɐi�o���ċ}������̂��A��Ƃ̈��艻��}�����B���̂��߁A��ʋ@�B�H�Ƃ̋Z�p�J���ƌ������i�߂���ƂƂ��ɁA���̏���������Ĕ_�@��H�Ƃ͒Z���Ԃł͂��������ُ�Ȕ��W�𐋂��邱�ƂƂȂ����̂ł���B���������Đ��Y������̂��ߏ]���̐l�͔_�@��͌����X�������ǂ�A����ɑウ�Ėh���p�E���n�p�{�͔_�@����B���A���͍k����@��g���N�^�[�̋}���ȐL�т��ڗ����Ă����̂ł���B
�_�@��N���\�i�����u����_�ꔭ�B�j�v�j
| �@�@�@�N�@�� ��@�� |
�吳 �X�N |
�P�O�N | �P�P�N | �P�Q�N | �P�R�N | �P�S�N | �P�T�N | ���a �Q�N |
�R�N | �T�N |
| �v�@�@���@�@�E | �P�S�V | �P�W�V | �Q�O�O | �Q�P�P | �P�X�W | �P�X�S | �P�W�V | �P�W�V | �P�W�W | �Q�O�W |
| �n�@�@���@�@�[ | �P�S�S | �P�W�S | �P�W�X | �P�V�U | �P�V�V | �P�W�Q | �P�V�S | �P�W�O | �P�U�S | �P�U�X |
| �J���`�x�[�^�[ | �P�S�S | �P�W�V | �P�X�R | �P�W�P | �P�V�X | �P�W�R | �P�V�U | �P�V�X | �P�U�T | �P�V�S |
| �n�@�@�@�@�@�� | �X�U | �P�P�U | �P�R�P | �P�S�Q | �P�S�P | �P�T�U | �P�T�V | �P�U�T | �P�T�P | �P�T�Q |
| �n�@�@�@�@�@�� | �P�S�R | �P�U�Q | �Q�O�Q | �Q�P�X | �P�X�Q | �Q�O�O | �Q�O�S | �Q�O�T | �P�W�P | �Q�O�R |
| �g �� �N �^ �[ | �\ | �\ | �\ | �P | �Q | �Q | �Q | �Q | �Q | �Q |
| �f�X�N�n���[ | �\ | �\ | �\ | �\ | �P | �P | �\ | �P | �P | �P |
| �d�@�@��@�@�@ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �Q | �R | �R | �R | �R |
| ���@�[�@�A�@�[ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �P | �P | �P | �Q |
| �X�v���[�_�[ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �P | �\ | �\ | �P |
| ���@�@���@�@�@ | �\ | �\ | �\ | �Q | �Q | �P | �P | �P | �P | �W |
| �X���b�V���[ | �\ | �\ | �\ | �P | �P | �P | �Q | �R | �P | �P |
| �G���V���[�a�J�b�^�[ | �\ | �\ | �\ | �P | �P | �P | �P | �P | �P | �S |
| �w�[�J�b�^�[ | �\ | �\ | �\ | �\ | �P | �Q | �Q | �Q | �S | �U |
| �E�@�@���@�@�@ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �V |
�_�p�@�B���̑��i
�@���A�_�Ƌߑ㉻�̂��߂̈�A�̎{��̂Ȃ��ŁA�������i�W���݂����̂͋@�B���ł���B
�@����́A�k�C���_�Ƃ��C�ۂ�y��ȂǂɌ����鈫�����̂Ȃ��ŁA���肵���_�ƌo�c���s�����߂ɂ́A�����ɐ������ꂽ�L�{���ƂƂ��ɁA�K����Ƃ̎��{�Ƃ������n���狁�߂�ꂽ���R�̌��ʂł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ������ɂ�����_�p�@�B�̓����́A�k�y���ǎ��Ƃ̂��߂ɏ��a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�̓��L�g���N�^�[�ɑ�\�����Ǝv���邪�A���̂��듹���͂��߂Ƃ���㕔�w���@�ւł́A�_�Ɛ��Y�̂�肢�������̊g���}�邽�߁A�@�B���̑��i�Ɏ��g�ގp�������߂Ă���A���a�Q�W�N�́u�_�Ƌ@�B�����i�@�v�̎{�s���_�@�Ƃ��āA��ʔ_�Ƃɑ��镁�y�Z����}�����̂ł���B
�@����ɁA�R�P�N�x�Ɂu�_�Ɖ��ǎ��������@�v�ɂ���Ď����ݕt�̓���������Ă���́A����܂ňꕔ�̗L�͂ȏ�w�_�ƂɌ����Ă������͋@�B��g���N�^�[�Ȃǂ��A��r�I�o�ϗ͂̎ア��ʔ_�Ƃɂ��e�Ղɓ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�@�B���̕��y�͎���ɐi�W���Ă������̂ł���B
�@���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�ɂ������v���͔_�@��y���Z���T�X�ɂ���Č���A��\�Ɏ����Ƃ���ł��邪�A�����̐�Ɣ_�ƂU�Q�T�˂ɑ��銄������݂Ă��A�����@�E�d���@�E���͒E���@�E���̓J�b�^�[�Ȃǂ��L�����y�����邱�Ƃ������Ă���A���_����̂Ƃ��铖���_�Ƃ̓����������A���������p�Ƃ��ĕK�v�����ׂ��炴����̂ł������̂ł���B
��v���͔_�@��y�䐔�@�@�i���R�T�Z���T�X�j
| �敪 | ���@�� �k�ϋ@ |
�_�@�p �g���N �^�[ |
�����@ | �d���@ | ���@�� �E���@ |
���@�� �����@ |
���@�� �����@ |
���@�� �U���@ |
���@�� �J�b�^ �[ |
���@�� �g���@ |
�_�p�g ���b�N �I�[�g �O�� |
| �l�L | �P�T | �R | �S�O�T | �P�P�U | �Q�X�V | �W | �Q�Q | �U | �S�Q�P | �Q�U | �W |
| ���L | �\ | �\ | �S�O | �T | �Q�R | �P | �P�Q | �T | �Q�T | �\ | �\ |
�@���ɂ�����@�B���̓����́A�a�Q���h���ɑ������I�ȐL�W�ł���A�_��̎�ނ�Y�̑����ɂƂ��Ȃ��A������앨�̖h���ɋy���Ƃł���B����ɂ͓��͕����@���Ȃ�����̌��ʂ��ʂ����Ȃ������̂ł���B���̂悤�ɖh���@�́A�_�Ɛ��Y�̈���ɏd�v�Ȗ����������Ĕ_�Ƃ̋ߑ㉻�ɐ[���Z�����A���݂ɂ�����_�ƋZ�p�̐i���̈ꗃ��S�����Ƃ�����B
�@���a�R�T�N�x����R���N�ɂ킽���Ď��{���ꂽ�u�V�_�R�������ݑ����Ɓv�̂Ȃ��ŁA�������_�Ƌ����g�������Ǝ�̂ƂȂ��ē����������͌��p�~�X�g�@�P�X��́A�����n��̔_���g���P�ʂɑ݂��o����ċ������p���}��ꂽ���Ƃ��@�B�����i�̍D��ł��낤�B
�@���̂悤�ɂ��āA�R�T�N�ȍ~�͊e��_�@��̓���������ɂȂ�A��O�̂�����u�{�k�芠�v�Ƃ�������Ƒ̌n�͍ĕҏW����A�l�͂���ђ{�͈ˑ�����E�p���āA�������͋@�B�𒆐S�Ƃ�����Ƒ̌n�Ɉڍs���������B�������̎��_�ẮA��Ƃ��ĕa�Q���h���p��Ƌ@��E�������ߒ��̓��͉��A����{�Y�p���n�����p�ȂǁA���Y�͂傳���邽�߂̔_�@��Ɍ����Ă���i�K�ɂ����Ȃ������B�Ȃ��A�����������͋@�B���i�s�̔w�i�ɂ́A�_�ƌX�̎��{�͂����܂���������Ƃ͂������ł��邪�A�_�Ɖ��ǎ������x�̑n�݂ɂ���Ď����Z�ʂ̓��������ꂽ���Ƃ��傫�ȗv���ƂȂ��Ă����B
�@�������A����ł́A�_�Ƃɂ�����J���͂̌������N���Ƃɐi�s����X���������Ă���A���̔��ʂł́A�n�͂̌��ނɂƂ��Ȃ��k�y���ǁA�엿���^�̑����A�K�i�Ȗh����ȂǁA���x�Ȑ��Y�����ێ����邽�߂ɑ傫�ȘJ���͂��v�������Ƃ������Ԃɓ��ʂ��A���������W��I�Ȕ_�ƌo�c�����҂���A��Ƒ̌n�̕ϊv�����߂���Ɏ������̂ł���B
�c�_�@�B���L�i�_�Ɗ�{�������ʕ\�j�@�@���R�W
| ��@�� | ���@�́@�k�@�ρ@�@ | �_�@�p�@�g�@���@�N�@�^�@�[ | ||||||||
| ��@���@�^ | �������^ | ���L�ː��� ��@�@�@�� |
�R�O�n�͖��� | �R�O�n�͈ȏ� | ||||||
| �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | |
| �l�L | �U�O | �U�P | �P�Q | �P�Q | �V | �V | �T | �T | �Q | �Q |
| ���@�L | �T | �Q | �\ | �\ | �V | �R | �T | �Q | �Q | �P |
���͍k�ϋ@���L�̐��ځi�_�Ɗ�{�������ʕ\�j
| �敪 | �g�@�@���@�@�N�@�@�^�@�@�[ | ���@�@�́@�@�k�@�@�ρ@�@�@ | ||||||||||
| �N�x | �@�l | ���@�L | �v | �@�l | ���@�L | �v | ||||||
| �R�V | �� �V |
�� �V |
�� �V |
�� �R |
�� �P�S |
�� �P�O |
�� �V�Q |
�� �V�Q |
�� �T |
�� �Q |
�� �V�V |
�� �V�S |
| �S�O | �R�R | �R�S | �P�P�V | �Q�T | �P�T�O | �T�X | �W�P | �W�Q | �\ | �\ | �W�P | �W�Q |
| �S�R | �P�V�X | �P�X�Q | �Q�U�U | �S�X | �S�S�W | �Q�S�P | �P�O | �P�P | �\ | �\ | �P�O | �P�P |
| �S�U | �Q�O�W | �Q�S�X | �Q�P�S | �T�X | �S�Q�Q | �R�O�W | �R�V | �R�W | �T | �R | �S�Q | �S�P |
| �S�X | �R�P�R | �S�P�X | �V�U | �P�T | �R�W�X | �S�R�S | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
�@�����������w�i�Ƃ��鏺�a�R�W�N�ɂ����铖���̊e��c�_�@�B�̏��L�͏�\�̂Ƃ���ŁA���͍k����@�̕��y�́A�����E��c�Ǘ��͐쐅�n�̐��c�n�тɑ�������ꂽ���̂́A�_�p�g���N�^�[�ɂ��Ă͂悤�₭�G�i�ق��j������}�����Ƃ������x�ɂ����Ȃ������B
�g���N�^�[�ɂ��f���g�R�[���̐荞�݁i�ʐ^�R�j

�i�P�j�_�ƍ\�����P���Ƃɂ�铱�����ꂽ�_�p�@�B
| �@�@�敪 �N�x |
���@�@�Ɓ@�@��@�@�� | ���@�@�Ɓ@�@�� | ���@�Ɓ@�� | |
| �{�@�@ | ��Ƌ@ | |||
| �R�X | �����g���N�^�[���p�g�� | �� �Q |
�Z�b�g �P�U |
��~ �T�C�Q�Q�V |
| �͖k�@�@�@�@�@�V | �V | �S�T | �Q�O�C�W�W�Q | |
| �����@�@�@�@�@�V | �P | �X | �R�C�O�T�R | |
| �S�O | �����@�@�@�@�@�V | �S | �P�U | �V�C�X�X�V |
| �͖k�@�@�@�@�@�V | �P | �R | �Q�C�O�Q�R | |
| �����@�@�@�@�@�V | �Q | �P�O | �S�C�U�U�R | |
| �S�P | �琬�q�� | �Q | �P�S | �U�C�V�U�W |
| �S�Q | �t����P�C�Q�C�R���p�g�� | �R | �R�Q | �P�R�C�U�V�S |
| �S�R | �t����P�C�R�@�@�@�V | �Q | �P�T | �P�O�C�W�W�P |
| �S�S | �t����P�C�Q�C�R�@�V | �P | �P�O | �U�C�P�S�T |
| �v | �@ | �Q�T | �P�V�O | �W�P�C�R�P�R |
�i�Q�j�U���R���_�ы��Ɠ��ʊJ�����Ƃɂ�蓱�����ꂽ�_�p�@�B
| �@�敪 �N�x |
���@�@�Ɓ@�@��@�@�� | ���@�@�Ɓ@�@�� | ���@�Ɓ@�� | |
| �{�@�@ | ��Ƌ@ | |||
| �S�V | �㔪�_�g���N�^�[���p�g�� | �� �@ |
�� �Q |
��~ �P�C�T�T�O |
| ��ؕ��@�@�@�@�V | �P | �T | �R�C�W�O�O | |
| �M�c�@�@�@�@�@�V | �P | �P�O | �T�C�Q�U�O | |
| �S�V�@ �`�S�X |
�R���P�@�@�@�V | �P | �P�O | �S�C�S�W�T |
| �R���Q�@�@�@�V | �@ | �U | �R�C�P�P�T | |
| �S�W | �㔪�_��Q�@�@�V | �@ | �Q | �P�C�V�U�O |
| �l���@�@�@�@�@�V | �P | �P�O | �T�C�X�V�T | |
| �����P�@�@�@�V | �P | �R | �Q�C�W�P�T | |
| �S�X | ����@�@�@�@�@�V | �P | �Q | �R�C�Q�O�T |
| ���ؑ�P�@�@�@�V | �P | �S | �T�C�Q�Q�O | |
| �R�z�@�@�@�@�@�V | �P | �P | �S�C�R�T�O | |
| ����@�@�@�@�@�V | �P | �R | �S�C�X�P�T | |
| �����Q�@�@�@�V | �P | �P | �R�C�O�Q�T | |
| ���ؑ�Q�@�@�@�V | �@ | �T | �T�C�V�V�P | |
| �v | �@ | �P�O | �U�S | �T�T�C�Q�S�U |
�@�������A���R�X�N�x������{�����_�ƍ\�����P���Ƃɂ���āA�Q�T��̃g���N�^�[�ƕt����Ƌ@�P�V�O������A�_�Ƌ@�B���p�W�c�ł���g���N�^�[���p�g�����W�n��Ɍ������ċ@�B����Ƒ̌n���m�������̂��͂��߂Ƃ��A�S�V�N�x����̐U���R���_�ы��Ɠ��ʊJ�����Ƃ̂Ȃ��ŁA�o�c�ߑ㉻�{�݂Ƃ��ĂP�O��̃g���N�^�[�ƕt����Ƌ@�U�S������A���l�ɍ�Ƒ̌n���m�������B
�i�R�j�e�펖�Ƃɂ�蓱�����ꂽ�_�p�@�B
| �@�敪 �N�� |
���@�@�@�Ɓ@�@�@�� | ���@�@�Ɓ@�@�� | ���@�Ɓ@�� | ���Ǝ�̖��� ���p�g���� |
|
| �{�@�@ | ��Ƌ@ | ||||
| �R�X�`�S�P | �ً}�����앨���Y�� | �� �T |
�Z�b�g �T |
��~ �X�C�R�R�V |
���_���_�� |
| �S�P | �[�؍͔|�p�@�B�������� | �Q | �Q | �U�C�S�T�U | �t���O�P |
| �S�Q | �����앨���Y�� | �R | �R | �V�C�P�O�Q | ���_���_�� |
| �S�R | �n����Y�_�Ɛ��i���� | �P | �T | �Q�C�W�W�T | �M�c |
| �S�S | �Ă�ؐ��Y�����ً}�� | �P | �S | �Q�C�S�R�O | �㔪�_�O�P |
| �S�V�`�S�W | �����앨���Y���������� | �R | �P�S | �Q�Q�C�S�R�T | �M�c�O�Q |
| �T�O�`�T�P | �ً}�e�������Y������ | �P�Q | �V�W | �P�O�W�C�X�X�U | �R��O�P�P |
| �T�Q�`�T�R | ���_�ߑ㉻�c�n�琬���� | �R�P | �P�R�V | �Q�U�W�C�W�U�S | �㔪�_�O�Q |
�@�܂����̂ق��A�e�푝�Y��ɂ����́A���Ȃ킿�A�����앨���Y��łQ�R��A�[�ؐ��Y������łR��A����c�_�@�B���i��łP��A�n����Y�_�Ɛ��i��łP��A����ɁA�T�Q�N�x������{�̗��_�ߑ㉻�c�n�琬���ƂłR�P��̃g���N�^�[�ƁA���ꂼ��ɕt����Ƌ@���Z�b�g�œ��������ȂǁA�@�B���͒������i�W�𐋂����̂ł���B�������A�ُꐮ���ɂƂ��Ȃ����͍k����@����g���N�^�[�w�̈ڍs�A���_�o�c�̍������E�ߑ㉻��ڎw���������Ȃǂɂ��l�L�g���N�^�[�̑����X���́A����ɂ������ċ��͂Ȃ��̂�����A���܂�{�k�芠��̌`�Ԃ͂قƂ�ǎp���������̂ł���B�����̎��Ƃɂ�蓱�����ꂽ�_�p�g���N�^�[����э�Ƌ@�͑O�y�[�W�ȉ��̕\�̂Ƃ���ł���B�@���̂悤�Ɋe�펖�Ƃɂ��_�p�@�B�̓������i�߂��Ă����̂ł��邪�A���̏��L�`�Ԃ͋����E���p�g���L���炵�����Ɍ��L�̑����X���������悤�ɂȂ�A���a�T�V�N�x�ɂ�����_�Ɗ�{�����ɂ��A�����̔_�p�@�B���L�_�Ɛ��Ƒ䐔������Ώ�\�̂Ƃ���ł���B
�_�p�@�B���L�_�Ɛ�����ё䐔
| ��@�@�@�@�@�@�@�@�� | �@�l�@���@�L | ���@���@���@�L | �� �p �g �� �L | ||||
| �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | �_�Ɛ� | �䐔 | ||
| ���@�́@�k�@���@��@�@ | �V�X | �W�P | �T | �Q | �| | �| | |
| �_ �p �g �� �N �^ �[ | �R�R�X | �T�V�T | �R�T | �P�T | �P�R�V | �V�O | |
| �t�H���[�W�n�[�x�X�^�[ | �Q�X | �Q�X | �U�T | �Q�Q | �W�O | �Q�U | |
| �w�@�C�@�x�@�[�@���@�[ | �P�R�R | �P�R�S | �U�T | �Q�U | �Q�W | �P�S | |
| �r�[�g�n�[�x�X�^�[ | �Q | �Q | �| | �| | �| | �| | |
| �|�e�g�n�[�x�X�^�[ | �P�P | �P�P | �P�R | �S | �| | �| | |
| ��p���͊���@ | �T�O | �T�O | �| | �| | �| | �| | |
| �R���o�C�� | ���@�E�@�^ | �T�V | �T�X | �| | �| | �| | �| |
| ���@�ʁ@�^ | �U | �U | �| | �| | �| | �| | |
| �ā@���@�p�@���@���@�@ | �U�X | �X�V | �| | �| | �| | �| | |
| ���@ �́@ ���@ ���@ �@ | �P�S�T | �P�S�T | �W�R | �Q�T | �R�W | �P�R | |
| ���@ �́@ �U�@ ���@ �@ | �U�U | �U�U | �Q | �P | �| | �| | |
| ���͓c�A�@ | ���@�s�@�^ | �R�S | �R�U | �X | �U | �| | �| |
| ��@�@�@�p | �R�U | �R�U | �| | �| | �| | �| | |
| �~ �� �J �[ | �o�P�b�g�^ | �P�X�X | �R�V�P | �| | �| | �| | �| |
| �p�C�v���C���^ | �W�U | �W�U | �| | �| | �| | �| | |
| �o �� �N �N �[ �� �[ | �Q�V�Q | �Q�V�R | �| | �| | �| | �| | |
| �_�@�p�@�g�@���@�b�@�N | �R�Q�O | �R�U�Q | �| | �| | �| | �| | |
�i���a�T�V�N�_�Ɗ�{�����j
�@��P�V�߁@�_���d��
�I�풼��̔_���d��
�@�I�퓖���ɂ�����d���n�т́A�s�X�n�Ƃ��̎��ӂ���ъ��ݔz�d���̕z�ݒn�ɉ������W���Ɍ����A���ꂩ����̋��������_���n�тɂ͓d�C����������Ă��Ȃ��������߁A���������v��J�[�o�C�g�Ŗ����������Ă���ɂ����Ȃ������B
�@���̂��ߔ��_���_�Ɖ�ł́A���a�Q�P�N�i�P�X�S�U�j�W���ɋߐڎ�v�n��ɑ��ĕ��S���H���ɂ��d�C�������Ăт����A������_���d�����ƌv���i�߁A�悤�₭�W�҂̋��c�������A��v�҂ɂ���đg�D�����_���d��������Ǝ�̂ƂȂ��ĂQ�Q�N�Q�����Ƃɒ��肵���B�������A���肩��̋ɒ[�ȕ����̌��R�ɂ�莖�Ƃ͓�q���A���x�����܂̊�@�ɒ��ʂ������A���̂NJW�҂̓w�͂ɂ���Đ蔲���A�U������V���ɂ����Ē����H���͊������A���邢�_���������c�܂��悤�ɂȂ����̂ł���B���̓d���H���́A�H����T�U�S���~�������đ�V�E����E�ԉY�ȂǂP�R�n��̂S�R�S�˂ɑ��ĂP�V�R�U�̓d�����Ƃ����ƂƂ��ɁA�S�W�˂ɑ����͗p�d�C���������̂ŁA�_���d���̑����ł������B
�@�܂��A��V�n��ł͏�����\�����Đ�ԓ��H�̖��[�܂œ��͗p�R������z�݂��Ă����̂ŁA���̉��̊J��n�ł���F��n��ɂ����ė��Q�R�N�P���ɓ�����d�͔����@�T�����A�H����P�T���~�������Ė�P���Q�O�O�O���[�g���̔z���H�����s���A�V���ɑ��d���J�n���ĊJ�����Ƃ̑��i��}�������Ƃ͓��M���ׂ����Ƃł������B
�@�����������̓d�����Ƃ��A�S�n��E�S�_�Ƃ�Ώۂɂ������̂ł͂Ȃ��A����n����ł����Ă��A���̋�������ƑΏۂ��珜�O�����Ƃ�������̂�����̂ł������B�������A�R�ԕӒn�ւ̏W�c���A�҂���������ɂ�Ė��_���ː��������������߁A���̐��ڂƂƂ��ɕӒn�ɂ�����_���d���̗v�]���Q�����܂��Ă����B
�@���̂��ߓ��́u�_�R�����d�C�������Ɓv���N�����A���a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j����T���N�v��ɂ�铹��̏����[�u�������āA�����͔��d�Ȃǂɂ��d�����i����u�����B���̐��x�ɂ���āA�Z�C���E�x�c�i�㔪�_�j�̓n�Ӌ���\�Ƃ���㔪�_���Ɣ��d�g�����W�P�˂��A���Q�T�N�ɂS�U�T���]�~�i��������⏕��P�R�O���~�j�̍H��������āA�o�͂P�R�L�����b�g�̏����͔��d�{���݂ɒ��肵�ĂQ�U�N�P�P���Ɋ����A�n����̉ƒ�ɓ_�����Ĕ_�������ɏ����������炵���B����ɁA�Q�V�N�V���ɂ͔z�d�����W���n��܂Ŋg�������̂ł������B
�@���a�Q�V�N�P�Q���ɂ́A�S���I�Ȗ��_���_�R���Ɖ�����Ƃ��āu�_�R�����d�C�������i�@�v�����肳��A�{�i�I�Ȗ@���x�Ƃ��Ė��m�����ꂽ�̂ł���B���̐��x�Ɋ�Â��R�P�N�T���ɔ��_���_�Ƌ����g�������Ǝ�̂ƂȂ�A����E�㉔��n��ƁA���݂̏㔪�_�n��̎��Ɣ��d�ɂ��z�d�{�݂�ڑ����A���킹�ĂP�U�O�˂ɑ��ċ������Ɨp��d�����ɂ��d�͋������s��ꂽ�̂��͂��߁A�R�R�N�ɂ͉��V�n��i�t���j�̂X�˂ɔz�d�����ȂǁA���X�ɔ_���̓d�����}��ꂽ�̂ł���B
�Ӓn�ɑ���d�C����
�@���a�Q�V�N�i�P�X�T�Q�j�ɍ��́u�_�R�����d�C�������i�@�v�𐧒肵�A�J��n����ї����Ɋւ���d�C�����ɑ��ĕ⏕����[�u���Ƃ����̂ł��邪�A���̑��̒n��ɂ��Ă͈ˑR�Ƃ��ėZ����ɂƂǂ܂�݂̂ł������B�������A�c���ꂽ���_���n�т͂�����Ӓn�ɑ����A���͂�Z�������őΉ��ł���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@���̂��߁A����ɓd�C�����̑��i��}��ړI�������āA���a�R�S�N�i�P�X�T�X�j�ɖ@���̉������s���A�����_���Ƃɑ��Ă�����⏕�ɂ��[�u���g�傳��邱�ƂƂȂ����B�������āA�����I�ɂ��d�C�������e�ՂɂȂ������Ƃɂ��A���_���n��͋������Ɨp��d���邢�͏����͔��d�Ȃǂɂ���ē������}���邱�ƂɂȂ����B
�@�������A�����ɂ����ċ������Ɨp��d�n�тƂ��Ďc��n��́A������d�C�������E�n��Ƃ�����n�тł���A�d�͉�Ђ̊��ݔz�d�����������čs�����̂ł��邽�߁A��Ђ̍̎Z�x�[�X�Ȃǂ̌���������������āA�K�������e�Ղɓ����ł���Ƃ��������̂��̂ł͂Ȃ������B
�@����������̂Ȃ��ɂ����āA�W�_���̓w�͂ɂ��A���E������ђ��̕⏕�Ȃ��璀���Ӓn�ɑ���d�C�������Ƃ��i�߂�ꂽ�B���a�R�T�N�P�Q�����N�̌��Ăł�������̓��n��ɋ������Ɨp��d�{�݂Ȃ���R�O�˂ɔz�d���A���R�U�N�P�Q���ɂ͏㔪�d�E�x��n��̂P�P�T�˂ɑ���{�݉��ǔz�d�Ȃǂ��͂��߁A�R�W�N�ɕl���n��P�R�ˁA�t��n��i�h�l�j�R�ˁA�R�X�N�ɕS���n��i�R�z�j�U�ˁA����O�Вn��V�ˁA����n��Q�T�ˁA������Ғn��W�ˁA�S�O�N�ɍ���n��R�ˁA�S�P�N�ɃK���r�Вn��i��c���j�T�˂ȂǂƁA�������ŐV�K�������}��ꂽ���A�S�Q�A�R�N�ɓ��������U�n��U�˂������āA���_�����т͂��ׂĉ������ꂽ�̂ł���B
��ʋ����d�C�ւ̐�ւ�
�@�������Ɨp��d�����ɂ���ēd�C�����͐i�߂�ꂽ�̂ł��邪�A���̎�v�҂͈�ʋ����n��ɔ�ׂēd�C�����͂���߂č����A���̂����A�{�݂̈ێ��Ǘ��ɂ��Ă��ӔC�킳��A������������ł������B���������Ă����̕s�����������邽�߁A�����������ꌳ�����ċ������Ɨp��d�{�݂�d�͉�Ђɋz���ڊǂ��A��ʋ����d�C�ɐ�ւ�����㕔�@�ւɂ����Č�������A�ĎO�Ďl���c��������ꂽ�B���̌��ʁA�k�C���d�͊�����Ђ���u�_�d�g���̘V���������{�݂���ʋ����n�Ȃ݂ɉ��ǂ��邱�Ɓv�������Ƃ��ċz������|���o����A���a�S�Q�N�x�����N�x�Ƃ���u�k�C���ɂ����鋤�����Ɨp�d�C�{�݂̖k�d�ڊǂU���N�v��v�����{����邱�ƂɂȂ����B
�@�����������x�^�p��w�i�Ƃ��āA���a�S�Q�N�x�ɗ����䗿�i��̓��j�̂P�O�˂��͂��߁A�S�R�N�x�ɕS���E�K���r�ЁE����O�Вn��ȂǂP�W�ˁA�S�S�N�x�ɉ���E�㔪�_�̂P�P�T�ˁA�S�T�N�x�ɏt���E����̂Q�V�ˁA�S�U�N�x�ɕl���̂W�˂ȂǁA�������Ŏ{�݉��ǎ��Ƃ��s���A���ꂼ��k�d�Ɉڊǂ��������A�S�˂̈�ʋ����d�C�ւ̐�ւ����s��ꂽ�̂ł���B
�N�x�ʓd���H�����{�\
| �敪 �N�x |
�n�@�@�@�� | ��v�ː� | ���Ǝ�� | ���Ɣ� | ���@�@�@�S�@�@�@��@�@�@�� | ���l | |||
| ������ | �s������ | ��v�ҕ��S | �k�d���S | ||||||
| �Q�T | �Z�C���E�x�c | �W�P | �n�Ӌ | ��~ �S�C�U�T�T |
�P�C�Q�X�W | �@ | �R�C�R�T�V | �@ | �@ |
| �Q�V | ���@�@�@�@�@�� | �H | �n�Ӌ | �H | �H | �H | �H | �@ | �@ |
| �R�T | ��@�@�m�@�@�� | �R�O | �������_�� | �Q�C�T�Q�R | �H | �R�P�V | �H | �@ | �@ |
| �V | ��@�@���@�@�_ | �P�P�T | ���_���_�� | �P�P�C�V�R�O | �U�C�V�Q�O | �W�P�U | �S�C�P�X�S | �@ | �@ |
| �R�W | �l�@�@�@�@�@�� | �P�R | �V | �P�C�T�V�S | �W�S�X | �Q�X�R | �S�R�Q | �@ | �@ |
| �V | �F�@�@�@�@�@�� | �P�W | �V | �Q�C�R�X�V | �P�C�W�U�T | �P�T�O | �R�X�P | �@ | �Ӓn�d�C���ǎ��� |
| �R�X | �S�@�@�@�@�@�� | �U | �V | �P�C�T�Q�O | �S�S�O | �W�Q�O | �Q�Q�O | �S�O | �@ |
| �V | ���@�@�@�@�@�� | �V | �V | �P�C�R�W�W | �T�P�Q | �T�W�W | �Q�T�W | �R�O | �@ |
| �V | ���@�@�@�@�@�� | �Q�T | �V | �T�C�W�O�R | �P�C�W�R�Q | �Q�C�X�X�R | �X�P�W | �U�O | �@ |
| �V | ���@�@��@�@�� | �W | �������_�� | �P�C�U�Q�S | �V�Q�U | �T�V�R | �Q�V�T | �T�O | �@ |
| �S�O | ���@�@�@�@�@�� | �R | �������_�� | �T�W�R | �R�O�O | �P�S�P | �P�Q�O | �Q�Q | �@ |
| �V | ���@�@�@�@�@�� | �R�S | ���_���_�� | �V�C�U�X�W | �Q�C�V�X�W | �Q�C�W�X�Q | �Q�C�O�O�W | �@ | �Ӓn�d�C���ǎ��� |
| �S�P | �K�@���@�r�@�� | �T | �V | �Q�C�Q�Q�P | �T�O�O | �P�C�S�V�P | �Q�T�O | �@ | �@ |
| �S�Q | ���@���@��@�� | �P�O | �������_�� | �P�W�T | �@ | �@ | �P�W�T | �@ | ��ʋ������� |
| �S�R | �S���E�K���r�� ���@�@�@�@�@�� |
�P�W | ���_���_�� | �Q�C�O�R�X | �P�C�Q�R�O | �V�P | �V�R�R | �T | �V |
| �S�S | ����E�㔪�_ | �P�P�X | �V | �P�R�C�R�O�X | �U�C�T�V�O | �S�R�T | ��R�C�P�Q�O �R�C�P�U�S |
�Q�O | �V |
| �S�T | �t���E���� | �Q�V | �V | �S�C�S�W�X | �Q�C�P�V�X | �P�C�P�U�O | �P�C�P�T�O | �@ | �@ |
| �S�U | �l�@�@�@�@�@�� | �W | �V | �P�C�S�Q�W | �X�R�O | �P�V�U | �R�Q�O | �Q | �@ |
(�����E�k�C���_�R�����d���̂���݁j
�@�N�x�ʓd���H���͏�\�̂Ƃ���ł���B
���͓d�C��������
�@���a�S�Q�N�i�P�X�U�V�j�ȍ~�A�}���ɐL�W���������̑���������ɂƂ��Ȃ��A���_�o�c�̋@�B���Əȗ͉��̂��߁A���͗p�d�C�̓����������v�]�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@����������w�i�Ƃ��Č�����i�߂��������ł́A���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�u�_�������͓d�C�������Ǝ��{�v�́v�����肵���B����́A�_�Ƌ����g������ѐ��Y�Ƌ����g���Ȃǂ����Ǝ�̂ƂȂ��āA�_�R�����d�C�������i�@�Ɋ�Â��čs���_�����d�C�������ƁA���Ȃ킿�O���d�C�ؑ֎��Ƃɑ��A������ѓ����⏕������t����Ƃ������x�ŁA�d�C�͌��Ƃ��ċ@�B����}�낤�Ƃ�����̂ł������B
�@�����A���_����̂Ƃ��铖���̓������瓪���͂W�R�V�O���A����ː��S�R�Q�˂ŁA�P�˕��ςQ�O���𐔂���ł���A����ɗv���闏�_�Ƃ̘J���ʂ͗e�ՂȂ�ʂ��̂����������߁A���ł͂��̗v�]�ɂ������Ă��̎��Ƃ����������i�����サ���B����ɂ���āA�S�W�N�ɏt���n��Q�U�˂�ΏۂƂ��铮�͓d�C�������Ƃ��s��ꂽ�̂��͂��߁A�S�X�N�ɔ��_�n��łP�V�W�ˁA�T�O�N�ɗ����n��łQ�W�˂ƁA�R���N�ɑ����Ɣ�U�S�W�W���~�𓊂��ĂQ�R�Q�ˁi�S�˂̂V�O�p�[�Z���g�j��ΏۂɎ��{���ꂽ�̂ł���B
�@���̌��ʁA���_�ƂɃo���N�N�[���[�i������p���u�j�A�~���J�[�A�o���N���[�i�[�Ȃǂ̓d�͋@��̓��������i����A�o�c�̋ߑ㉻���}��ꂽ�̂ł���B
�@��P�W�߁@�y�n���ǎ���
���w�y���p�̌���
�@�����̓y���́A�V�y����E��c�ǐ�E���̑��̗���Ƙh�̑��i����j�E�u�C�^�E�V�i�C�i�ԉY�j�E�R��̓D�Y�n�������ẮA�啔�����ΎR�D�y�ł���B����ɂ�������炸�A�����P�P�N�i�P�W�V�W�j�ɓ��A�̂��Ƃ��炭�͖��엿�ő����ʂ̎��n���グ�邱�Ƃ��ł����̂́A���ɒ����N�����Ē~�ς��ꂽ��̕��A���y�����������߂ŁA���̌㑱����ꂽ���D�I�_�ƌo�c�̂��߂ɁA�₪�Ĕ����\�y���ΎR�D�ƍ��������₹�����y�ɕς���Ă��܂����̂ł���B
�@�����������Ԃɒ��ڂ�������_��̎w���҂��A���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�ɂ��̉ΎR�D�Ƃ��̉��w�y�����p���Ĕ�悭�ȍk�y�ɉ��ǂ��A���Y���ʂ��グ�邽�߂̌����ɒ��肵�āA�X�A�P�O�N�ɂ킽��[�k�����̌��ʁA�����̐��ʂ��グ�Ă����B�܂����̂���k�C���_��������ɂ����Ă��A�R�z�S��т̍k�n��n���T�ڈȏ���@�艺�����Ȋw�I�Ȏ��n�������s���A���_�̑啔�����߂Ă���y�w�i�n�\���`�w���P�T�A�a�w���P�O�A�b�w���Q�T�Z���`���[�g���j�̂`�a�b�e�w�̂����A�ł��n���̔�悭�Ȃ̂͂b�w�i��R�w�j�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���߁A��R�w�j��H��̌�����������ꂽ�Ƃ����B
�@�܂��A���a�P�T�N�i�P�X�S�O�j�ɓ���_��Ɣ��_���_��́A�k�C���_��������̋��͂č������Ƒ�V����̓��ɂ��ꂼ�ꎎ�����Q�O�O�i�P���R�E�R�������[�g���j��ݒu���A�X�R�b�v�łP�ڂT���i�P�ځ��R�O�E�R�Z���`���[�g���j�̐[���Ɍ@��N�����A���w�k�����{���ĕ��ʍk�Ƃ̔�r�������s�����B����ɁA���̌����ɂ͖������ي�����Д��_�H��ł��y�땪�͂̂��߂Ɏ��������J�����A���Z�p�҂��P�N�Ԑ��P�O��̕��͂𑱂���ȂǁA�S�ʓI�ȋ��͂ɂ���Đi�߂��A���̎������ʂ͔_���ɑ���傫�Ȏw�W�ƂȂ����̂ł���B
�@�Ȃ��A���P�U�N�ɂ͍��w�v���I�Ƃ��̂�������͂Ȃǂɂ��Č������邽�߁A�F����������Ƃ���u���_�k�y���nj�����v��g�D���A�k�C���_���������k�C����w�Ȃǂ̎w����ƂƂ��ɁA�����܂����̌����ɑ��Ē���P�O�O�~���x�o���A���Ƃ̐i�W��}�����̂ł���B�������A�����͐펞�̐����ɂ������W����A�g���N�^�[�̔R�����肪����ȏ�Ԃł���A�������A�{�͂ɂ��P�ڂT���]�̍��w�k�v���I�̂�������s�\�Ƃ������ԂƂȂ��āA�v��͂��������f���邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�y�n���ǎ��Ƃ̑n�n
�@�����ɂ�����_�n���ʐς̂V�O�p�[�Z���g�͉ΎR�D�n�Ƃ����A�������A�ΎR�D�w�͓쓌�Ɍ������ɏ]�����Đ[���đe���A�k���Ɍ������ɏ]���������ׂ����Ȃ��Ă���A��x�̉e�����傫�����Ƃ������Ă���B
�@�܂��A�V�y����k���̓D�Y�n���c���E��֖~�n�i�㔪�_�j���̑��̎R�낭�n�тł͒n�����������A���n�ƂȂ��Đ��Y�����ɂ߂ĒႭ�Ȃ��Ă���̂���Ԃł������B
�@���������D�Y�n�т⎼�n�т����ǂ��Ĕ_�n�̐��Y�͂����邽�߁A�O�q�̍k�y���nj����Ǝ����������鏺�a�X�N�i�P�X�R�S�j�A����ƂƂ��Ė�c���̎��n�і�P�O�����ɂ��ď����āu�Ë��i����j�r���v���Ƃ����{�����̂��A�y�n���ǎ��Ƃ̏��߂Ƃ����Ă���B
�@���̎��Ƃ̐v�w���͓n���x����B�ۂ��s���A�z�����͑e�S�i�����j�₳���̌�����p���A�W�����͔���A�o���ɖؔ��̐���������c�t�Ȃ��̂ŁA������u�e�S�Ë��v�ƌĂ����̂ł������B
�@���̌�A�펞�H�Ƒ��Y�̗v���ɉ����A���a�P�U�N�ɍ������_�����s�g�����P�~�Ƃ�����R�T�����A���P�V�N�ɂ͗אڂ����V�n��ɖ�Q�O�������A����������߂Ĕr���y�ǂ݂���Ë��r�����Ƃ����{���ꂽ�B���ɍ������n��́A����ɂ�����y�n���ǎw���W���̎w����A���̎w���ړ��Ď��Ƃ����{�����̂ŁA���̎{�s���@����ʂȂǂɂ��čL���[������Ƃ��낪���������̂ł��邪�A�c�O�Ȃ��痂�P�W�N�ɂ́A���̒n���т���s�ꌚ�݂̂��ߗ��R�ɔ�������邱�ƂƂȂ����B
�@�Ȃ��A���a�P�V�N�ɂ͑�ւ̖~�n�𒆐S�Ƃ��āA��P�O�����ɑe�S�ɂ��Ë��r���H�������̐v�Ǝw���̂��ƂɎ��{���ꂽ�B�������A�~���H���̂��ߌ@��[�x�̕s���ƁA�t�і����r���̓��H���a���p�Ȃǂ̕s���̂��ߔr���s�ǂƂȂ�A�\���Ȍ��ʂ��ł��Ȃ��Ƃ����s���͂��������A�X�̔_�Ƃɂ�鎩�������̓y�n���ǎ��ƂƂ��Ă͍����]���������̂ł������B
�͖k�n��̓y�n���ǎ���
�@���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�ɂ́A�펞���ɂ�����ً}�H�Ƒ��Y��Ƃ��āu�k�C���y�n���ǂT���N�v��v�����Ă��A�r���Ƌq�y����v���ƂƂ��Ď��{����邱�ƂɂȂ����B�������A�����m�푈���̂��ߎ��ނ�J�͂̌��R�ƁA�y�n���ǎ��Ƃɑ���F���̒Ⴓ���d�Ȃ��āA�v��̐i�W�͗e�ՂȂ�ʍ���Ƃ��Ȃ������A�J���͂̕�[�ɂ͏����w�Z���͂��ߍ������w�Z�̐��k�Ɏ���܂ŁA�̈ʌ���Ə̂��ċΘJ��d�ɓ������ꂽ�B�܂����̔N�A�Ë��r���ɕK�v�ȓy�ǐ����̂��߁A�k�C�����_���Ђ̌o�c�ɂ�锪�_�y�ǍH�ꂪ�V�݁i�������j���ꂽ���Ƃɂ��A�������Ƃ����i����邱�ƂɂȂ����B�������āA�����ɂ����Ă͑��N�̌��Ăł������h�̑��i����j�E�u�C�^�E�V�i�C�i�ԉY�j�E�R��̊e�n��ɂ����āA���悻�P�O�O�O�����ɂ킽��D�Y�n�̓y�n���ǎ��Ƃ��ϋɓI�Ɏ��{����邱�ƂɂȂ����̂ł���B
���h�̑��n����
�@�h�̑��n��́A�n��̒��S�𗬂�Ă��郁���삪���̏㗬�ɂ���R�т̍r�p�ɂ��A�~�J�̂��тɓy�������o���ĉ͏������߁A�o���̂lj����̔_�n���������ĔN�X��Q�傷��ł������B���̂��߁A�����여�悩�牪�̎R��~�̉��njv��𗧂ĂĐ\�����A���̎��n�����ɂ���Ă��ꂪ�̑��ƂȂ�A������̐ؑւ��H���ƂƂ��ɉ����Q�T�W�O���[�g���ɋy�ԁu�h�̑���P�����r���a�v�̐v���Ȃ���A����������ď��a�P�W�N�P�P���ɒ��H�A�P�X�N�R���Ɋ��������̂ł���B
�@���̊����r���a�Ɋ֘A���āA�����r���ƈË��r���H�����n��Z���̋��͂ɂ���ď����Ɏ��{����A�Q�P�N�܂łɂQ�W�U���R�����̉��ǂƁA��Q�O�O�O���[�g���ɋy�Ԗ����r���H�������������B����ɁA�h�̑��ƃu�C�^�E�V�i�C�n��̋��E�ɂ�����A���̎R���瑾���q��k�����o�ėV�y����Ɏ���u�h�̑���Q�����v�����Q�S�Q�X���[�g���]���A�P�W�N�P�Q�����痂�P�X�N�R���܂ł̓~���Ԕ��ٓy�،��Ə��̒��c�Ŏ��{���ꂽ���A����͑啔����������n�悻���Ċe�E��Ȃǂ̋ΘJ�����ɂ���čs��ꂽ�B
���u�C�^�E�V�i�C�n����
�@�u�C�^�E�V�i�C�n��́A���̑啔�������؊��s�̏��L�n�ł���A����n�Ƃ��Ċ��p����_�n�ȊO�̕s�т̌�����J�����邽�߁A���a�P�U�N�ȗ��S���𒍂��œw�͂��Ă����̂ł��邪�A�P�U�O�O���[�g���́u�u�C�^�E�V�i�C��P�����v�ƁA�Q�Q�O�O���[�g���́u����Q�����v�̗��r���a������������Ď{�s�����Ɠ����ɁA����ɕt�т��閾���r���a�P���Q�O�O�O���[�g���ƂP�Q�P�����̈Ë��r���H���ɐϋɓI�Ɏ��g�݁A�P�X�N�܂łɂ�������������̂ł���B
�@���̌�A�I��O��̍������ɂ����āA���̎��Ƃ͂�������~��ԂƂȂ������A���H�Ƒ��Y�ً}��Ƃ��čĂѓy�n���ǎ��Ƃ����i����邱�ƂƂȂ�A�y�n���L�҂ł��锪�؊��s�͓��Ȃ�тɔ_�яȁA�_�ђ������ɂȂǂ̋��͂āA���a�Q�V�N�܂łɑS�n��S�Q�U�����̎��Ƃ����������C����ɓ��l�́A���N�̌v��ł������o�H�W�Ϗ�����i�S�R���N���[�g���A�S�V�Q�j���T�c���Ɍ��݂��A�N�ԂP������g���̑͐ϔ��y���n�̐o�H�_��ɉݎԗA�����Ĕ�|�q�y���s�������A����́A�D�Y�n�J���ɂƂ��Ă͓��M���ׂ�����ł��낤�B
�@����A���a�P�U�N�ɓ��n����̏���҂R�V�˂́A�n�傩�珬��n�̕����I�Ԋҗv�����A���̌�U���N�ɂ킽�菬�쑈�c��������ꂽ���A���ꂪ�t�ɏ���҂�c�������邱�ƂƂȂ�A�n��ւ̑R�S�͈�ʂŏ���n�ɂ�����y�n���ǎ��Ƃ𑣐i���铱�ΐ��Ƃ��Ȃ��Ă����B
�@�܂��A���a�P�W�N�H�A�u�C�^�E�V�i�C��P�T�O�O���[�g���̉��C�H�����S�z����������Ď��{����A���̗���Q�O�U�����ɂ킽�锨�n�̉��ǂ����i�����ƂƂ��ɁA�����Ɋ������݂���P�����̌��p����肢���������߂邽�߁A�S�������f���ėV�y����Ɏ����P�P�O�O���[�g���̔r���a���V�݂���A���n��ɂ�����y�n���ǎ��Ƃ̌��ʂ͒������㏸�����̂ł���B
���R��n����
�@�R��n��́A���a�̏����ɐΐ�_�ꂪ�_�n��n���Ď���_��n�݂��������A�]���̏���l���_�n�ɕt�����邩���p���̌����Ĉێ��Ǘ��ɂ����������A��ʂɔr���s�ǂ������A���Y�����ɂ߂ĒႢ�ł������B���̂��߁A�h�̑��A�u�C�^�E�V�i�C�n��Ɏ����ŏ��a�P�X�N�t����y�n���ǎ��Ƃ��v�悵���̂ł��邪�A�����m�푈�����Ȃ�̎����ł�����A�J�͂̕s���Ɣd����Ȃǂ̊W�������āA�v��͂��������~�̂�ނȂ��Ɏ������B���̌�A�ΘJ�w�k�̓����ƒn��w���҂̏n�S�Ȓɂ���Ď��Ƃ͂悤�₭���肳�ꂽ���̂́A���肩��̘J��������H�Ǝ���ȂǁA�ň��̏������d�Ȃ��đ����̍�����܂Ƃ����B�܂��A���Ƃ̐��s���߂����Ēn����w���ҊԂɈӌ����Η����A�Ăђ��~�Ƃ������ԂɂȂ����B�������A���̌㋦�͊W����������Ď��Ƃ͍ĊJ����A����ȗ��T���N�Ԃō���ɂ�閾���r���a�R�����Q�T�U�S���[�g���A���ǖʐϓZ�����A�t�і����r���X�W�W�X���[�g�����������A����ɁA�_�����C�Ƃ����a��C�����킹�čs�����ƌ��ʂ����߂��̂ł���B
�n����q�y �i�ʐ^�j

�k�y���ǎ��Ƃ̓W�J
�@�풆����яI�풼��ɂ�����y�n���ǎ��Ƃ́A�r���E�q�y�E�������O�厖�ƂƂ��Đi�߂��Ă����̂ł��邪�A���A���g�҂╜���҂ɂ��l���}���ƐH�Ɠ�����̂��߂́u�ً}�J����{�v�́v����ƂƂ��ɁA���a�Q�Q�N�x�i�P�X�S�V�j���ŏI�N���Ƃ����u�k�C���y�n���ǂT���N�v��v�̌p���Ƃ��āu�_���y����ǁv�������A���͂Q�R�N�x����P�Ǝ��ƂƂ��āA��ʌo�ϔ_�Ƃɑ���ΊD�w����ɑ��ď����̓����J�����̑��i��}�����B
�@�����ɂ�����_�k�n�̑啔���́A�J��ȗ��̔_�k�ɉ����A�����E�ߗӎ_�ΊD����ї��_�����Ȃǎ_���엿�̘A�p�ɂ���čk�n�̎_�������i�݁A�n�͂͌��ނ������ł��������߁A�H�Ƒ��Y�ɉ����邽�߂ɂ͂��̎_���y����ǎ��Ƃ̎��{�ً͋}��v������̂ł������B���̂��ߒ��́A�u�͔�Րݒu����K���v���߂ėL�@���엿�̑��Y�����シ��ƂƂ��ɁA�u�k�y���ǎ��Ə���K���v���߂ď��a�Q�U�N�x����_���y�닸�����Ƃ����サ�����A���ɂQ�V�N�́u�k�y�|�{�@�v�̌��z�Ƃ����܂��Ă���ɏ��コ��A�R�Q�N�x�܂ł̌p�����{�������Ēn�͂̑��i�u����ꂽ�̂ł���B
�@�܂��A�k�C���̔_�k�n�͑S���I�ɉΎR���y�E�d�S�y�Ȃǂ̓���y��n�т������A�_�Ƃ̈���U����j�Q����傫�ȗv���ƂȂ��Ă������ɒ��ڂ������́A�����S�y�k�E���w�k�ɂ���čk�y���ǂ�}�邱�ƂƂ��A�Q�U�N�x�����N�x�Ƃ���u��ꎟ�k�y���ǂV���N�v��v�𗧂āA�g���N�^�[����ѕt���_�@��Ȃǂ�����Ɠ���������čw�����A�����y�Y�A��ʂ��ĒP���ɑ݂��t����Ƃ��������̎��Ƃ����{���Đ��i��}�����B���̐��x�Ɋ�Â��A�S�y�k�E���w�k�ɂ��k�y���ǎ��Ƃ𑣐i���邽�߁A���a�Q�U�N�P�O���ɔ��_�����Ƌ����g���́A�n��y�Y�A���o�ď����c�R�O�^�g���N�^�[���A����ɁA�Q�W�N�T���ɓ��T�O�^�g���N�^�[���̑ݕt�����ق��A�Q�X�N�i�P�N�x�j�ɂ͓��ɃP�[�X�T�R�n�̓g���N�^�[���̑ݕt����ȂǐϋɓI�Ɏ��g���A����ƕ��s���Ď��Ǝ�̂ł��铯�_���ł͓��Ƀh�C�c�����w�k�v���I���w�����āA��ƌ����̌����}�����B�܂��A���̍k�y���ǎ��Ƃɑ��镉�S���y�����邽�߁A�_�ы��Ǝ����i�����N�T���E�P�N���u�E�T�N���ҁj���Z�������ȂǁA�����ʂɂ�����蓖�Ă��u�����Ă����B
�@�������A�c�O�Ȃ����ꎟ�k�y���ǎ��ƂɊւ���j���͂܂�ɎU���������x�ŁA���̎��Ɨʂ����m�ɒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɂ����Ă����Ƃ̎��{�o�߂ɂ��ẮA�Ȗ��ȒǐՒ������s���Ă��̍D���т��m�F����Ă��������A���肩��P�����R�P�N�̑��Q�ɂ����Ă��A�����k�y���ǎ��{�n��ɂ������Q���x���A�����{�n����͔�r�I�ɒႢ�Ƃ������Ƃ������ꂽ�B���̂��߁A�k�y���ǎ��Ƃ̕K�v�����ĔF������A���͂R�Q�N�ɉ��߂āu��k�y���ǂV���N�v��v�𗧂ĂāA���L�@�B�̓�����}�������p�����{�����̂ł���B
�S�y�k�E���w�k���{��
| �@�@�N�x �敪 |
�R�Q | �R�R | �R�S | �R�T | �R�U | �R�V | �R�W | �R�X | �S�P |
| �ˁ@��(��) | �V�W | �U�O | �T�O | �R�X | �T�R | �Q�R | �R�R | �P�T | �T |
| �ʁ@��(ha) | �V�U | �U�R | �S�U | �R�V | �S�U | �Q�Q | �Q�V | �P�P | �U |
| ���Ɣ�(��~) | �Q�Q�P | �P�Q�R | �X�R | �V�R | �X�R | �S�T | �T�S | �Q�R | �V |
�@�����ɂ�����k�y���ǎ��Ƃ̂����A�S�y�k�E���w�k�̂R�Q�N�x�ȍ~�̎��т͏�\�̂Ƃ���ł��邪�A���̂ق��ɏ��c�n�J�����ƂƂ��āA����Ə㔪�_�n��Ŕn����q�y�����{���ꂽ�葝���J�����i���ƂƂ��ĕl���n��őS�z����ɂ��q�y���Ƃ��s����ȂǁA���Ƃ͒����ɐ��i���ꂽ�B
�_�Ɗ�Ր����Ȃǂ����Ƃ���y�n����
�@���a�R�O�N��ɂ�����_���̕����́A�H�Ƒ��Y����`����_�H�Ԃ̏����i���̐����ƁA���Y������̂��߂̔_�Ɛ��Y��Ղ̋����Ɍ�����ꂽ�B�����������Ƃɂ��A���a�R�T�N�x����R�V�N�x�ɂ����Ď��{���ꂽ�u�_�R�������ݑ����Ɓv�̈ꕔ�Ƃ��āA�����ł͏㔪�_�Ɠ���n��ɂ����Ĕn����q�y�����{���ꂽ�B�Ȃ����̂ق��A�_�Ƌ����g����y�n���Nj�̒c�̉c���ƂƂ��āA���ꂼ��y�n���ǎ��Ƃ����{����Ă������̂ł���B
�@�܂��A���a�R�X�N�x������{���ꂽ�_�ƍ\�����P���Ƃ̂Ȃ��ł��A�o�c�ߑ㉻�{�݂̓����Z�b�g�ƂȂ����y�n��Ր������ƂƂ��Ċe��̎��Ƃ����{���ꂽ���A���̊T�v�ɂ��Ắu�_�ƍ\�����P���Ɓv�̍��ɋL�q�����Ƃ���ł���B
�y�뒲��
�@���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�V���_�яȖk�C���_�Ǝ�����Ɉϑ����A�����Ǔ��̔_�k�n�ƍ̑����q�n�܁Z�Z�Z������ΏۂƂ���y�뒲�������{���ꂽ�B
�@����́A�_�p�n�̓y�������w�I�ɕ��͂̂����A�_�ƋZ�p��y�n�̍k�y���ǂ𗝊w�I�ɐf�f���悤�Ƃ�����̂ŁA���̂��̎悵�āA���́E�y�����ǁE�{���̐ݒ���s���A���Y���̑����}��Ƃ����ړI�̂��ƂɁA�O�Z�Z�ԕ���Ɉ�_�̒����_�ŁA�v�S�U�V�_�̒����B�i�c�X�O�Z���`�~���U�O�Z���`�~�[�P���[�g���j���@��A�n�����������{�����̂ł���B
�@�������e�͊O�ƒ����Ɠ��ƒ����ɕ������A�O�ƒ����Ƃ��āA
�@�n�`�E�n���E��ށE�y���E�\���E�e���x�E�S���E�n�\���̗L���E�n�����̍���E�X�E�N�H�E�ۊQ���̓y��̏�ԂȂǂ���������A���ƒ����Ƃ��āA
�@�������I�E�ܗʁE�S�y�E�R���C�h�E���A�E�S���f�E�e�ʁE��d�E�ӎ_�z���́E�u���e�ʁE�u��������E���ΊD�E����y�E����O�a�x�E���g�E�S�_�x�̓��َ_�x�Ȃǂ���������A���̌��ʂ��u���_���y��n���}�v�Ƃ��č쐬�����̂ł���B
���c���������r������
�@���t���n�恄�@�t���n��́A���n�тŐ��Y�����Ⴂ�����A���N�͐삪�͂��ĉc�_�Ɏx��𗈂��Ă����B���̂��߁A���a�R�X�N�x�ƂS�O�N�x�ɂ����āA���c�ɂ���K�͓y�n���ǎ��Ƃ̒������i�߂�ꂽ�B����ɂ��S�O�N�x����S�S�N�x�ɂ����āA�V�y����̎x���ł��鉹����E���V��̈ꕔ�ƁA���̎��ӂ̗���R�S�E�S�V�����L���ɋy��Œ������ƂƂ��Ė����r���H���{�s���ꂽ�B
�@���̍H���́A�����Ɣ�P���X�T�T�S���U�O�O�O�~�������āA��ꊲ���r���H�R�X�Q�X���[�g���A�����H�P�V�����A��݂S�S�P�S�������[�g���A����傤�H�T�����A�����H�S�����A�y�����H�P�����A����r���H�Ƃ��ĂX�O�X���[�g���A�����H�R�����A����傤�G�P�����ƂȂ��Ă���A����̊����ɂ���Ď�v�ʐςU�Q�V�w�N�^�[���̔_�n�̐��Y�����m�ۂ��ꂽ�B
�@���k���n�恄�@�R��E�ԉY�E����n����܂��锪�_�k���n��́A�r����Ԃ��������ߗZ��Ⓑ�J�������Ɖ͐삪�͂��A�c����q���n���������Ĕ_�앨�ɔ�Q�������炷���Ƃ����яd�Ȃ�Ƃ����ł������B
�@���̂��߁A�S�S�N�x���獑�c�ɂ���K�͓y�n���ǎ��Ƃ̒������i�߂��A�S�U�N�x�S�̐v���܂Ƃ܂�A�S�V�N�x����T�T�N�x�܂ł̂X���N�v��ŁA�P�S�U�O�w�N�^�[���ɋy�Ԏ�v�ʐς�ΏۂɁA���������r�����Ƃ��J�n���ꂽ�B
�k���n�斾���r�����Ɓ@�ʐ^

�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�T���P�T�O�O���~�ŁA�����r���H�S�n�V���i���V�m�X�E�啽�E�u�C�^�E�V�E�ԉY�E�����E�{�O�E�R��̂V�����A�������X�O�R�W���[�g���j�ƁA����悤�V��������������A�_�n�̐��Y�����オ���҂���Ă���B
�@�������n�恄�@��V�E�n�c�E�l���̊e�n����܂��锪�_�����n��́A�Â�����J�������_�n�тł��邪�A�r���n���͎��R�͐�̂܂ܕ��u����Ă������߁A�Z����J�ɂ��o�����ɂ����Ό����͂�����N�����A�_�앨�ɑ傫�Ȕ�Q��^���Ă����B
�@���̂��߁A���a�S�U�N�x���獑�c�ɂ���K�͓y�n���ǎ��Ƃ̒������i�߂��A�S�X�N�x����T�W�N�x�܂ł̂P�O���N�v��ŁA��v�ʐςP�Q�P�T�w�N�^�[���ɋy�Ԕr���Ԃ̐����ɒ��肵���B
�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�W���T�W�O�O���~�ŁA�����r���H�R�n�S���i��V�E�n�V�m�X�x�c�E�n�c�E�|�����Ó��̂S�����A�������P���T�Q�Q�O���[�g���j�����邱�Ƃɂ��A���_�o�c�̈������ɑ傫����^������̂Ɗ��҂���Ă���B
�@���㔪�_�n�恄�@�㔪�_�n��̔r���n���͎��R�͐�̂��ߒf�ʂ������A�܂��͏��������A�����ċ��Ȃ��͂Ȃ͂��������߁A�Z����J�ɂ��o�����ɂ͔_�앨�ɔ�Q���A����ɒn�����̔r�����\���łȂ����߉c�_��傫�Ȏx��ƂȂ��Ă����B
�@���̂��߁A�S�X�N�x���獑�c�ɂ���K�͓y�n���ǎ��Ƃ̒������i�߂��A�T�R�N�x����T�W�N�x�܂ł̂U���N�v��ŁA��v�ʐςR�W�O�w�N�^�[���ɋy�Ԕr���Ԑ����ɒ��肵���B
�����n�悩��ς����� �ʐ^

�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�R���P�O�O�O���~�ŁA�����r���H�Q���i��ցE���r�������A�������U�U�O�O���[�g���j�����邱�Ƃɂ��A�o�c�̈������ɑ傫����^������̂Ɗ��҂���Ă���B
�����n��L��c�_�c�n�_����������
�@�����̗��_�n�т́A���Y�p�ɒ����e�͐쉈���ɔ��B�������A�����̒n�т��c�т���_�����Ȃ����߁A���Y���̏W�o�ׂɂ͊C�ݐ��𑖂鍑���T�����ɂQ�x�o�Ȃ���Ȃ炸�A���Ԃ�v���邤���~���Ԃ̏���ɂ����Ɏx��𗈂��Ă����B
�@���̂��߁A���a�S�V�N�x����k�C�������Ǝ�̂ƂȂ�A��V�n����N�_�Ƃ��ďn�c�E�l���E�R�z�Ȃǂ��c�т��A��c���n��̓��X�����c����ԏ���Ƃ̌����_���I�_�Ƃ��鑍�����P���R�T�W�P���[�g���ɋy�Ԕ��_�����n��̍L��_�������H���ꂽ�B
�@���Ɠ��e�́A�����V�E�T���[�g���A�ԓ������T�E�T���[�g���̂Q�Ԑ��ŁA�T�U�N�x�܂łɏt���n��̍����Q�V�V�����Ƃ̌����_����I�_�ł����c���n��܂ł��J�ʂ��A�ԗ��̒ʍs���\�ɂȂ����B
�@���̌�A�T�V�N�x����ܑ��H�����i�߂��A�T�W�N�x�S�ʊ�����ڎw���Ă���B
�@�Ȃ��A���̎��ƂɊ֘A���ďt���n��Ƒ�V�n������ԏ㍻���������A�S�V�N�x�Ɋ��������B
�@���̔_���ɂ���ė��v����ʐς́A��T�U�O�O�w�N�^�[���A�S�S�O�˂ŁA�_�{�Y���̏W�o�ׂ��^�_�Ƌ@�B�̉^�s�Ȃǂɗ��ւ������炳��A���_��Ղ̐����ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂Ɗ��҂���Ă���B
�����n��L��c�_�c�n�_���������� �ʐ^

����n�擹�c���n�J������
�@�ߔN�A�����̑������{�ɂƂ��Ȃ��A�ʍk�n�ʐςW�E�T�w�N�^�[���ł́A������Ղ��s���ƂȂ��Ă��Ă���B���̂��߁A����n��̋u�ˑ�n�ɓK�n�����߁A���a�T�Q�N�x�ɂ����ē��c�ɂ�鑐�n�J�����Ƃ̒������s���A�T�R�N�x����T�W�N�x�܂ł̂U���N�v��ŁA�P�T�S�E�W�w�N�^�[���ɋy�ԑ��n�����ɒ��肵���B
�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�S���U�Q�O�O���~�ŁA��ȓ��e�Ƃ��ẮA���q��p�n�P�T�S�E�W�w�N�^�[���i�����̑��\���q�n�T�O�E�W�w�N�^�[���j�E���H�R�H���U�R�R�O���[�g���E���̂ق��A�d�C�����{�݁E�ƒ{�ی�{�݁E�q��p�@�B�E�i�[�ɁE���F�{�݂ȂǂƂȂ��Ă���B����̊�����́A�Ċ��U�P�O���̓��p�琬���̗a�����A�Ǘ��^�c�͔��_���_�����s�����ƂƂȂ��Ă���B
�@�Ȃ����̎��Ƃ́A�������c��K�͑��n�J�����ƂƂ��Ē������s�����̂ł��邪�A�y�n�������������p�������Ⴂ���߁A���c�Ŏ��{���邱�ƂɕύX�������̂ł���B
���c�x��n��J��p�C���b�g����
�@���̒n��͔��_�s�X�n�����Q�O�L���̉��u�n�ɂ��邪�A�ߔN�A�����̑���������ɂƂ��Ȃ��q���̕s���𗈂����Ă��邱�Ƃ���A�㔪�_�n��_�Ƃ̋����v�]�ɂ��A���c�ɂ��J��p�C���b�g���Ƃ����{���ꂽ�B
�@���̎��Ƃ́A���a�S�P�N�x�ƂS�Q�N�x�Œ����v���Ȃ���A�S�R�A�S�S�N�x�̂Q���N�Ŏ{�s���ꂽ�B���e�́A�����Ɣ�R�V�T�W���U�O�O�O�~�ŁA�q���n�W�T�E�P�w�N�^�[���A���H�Q���R�W�W�O���[�g�����������ꂽ�B
���c�g�����x�c�n��_����C����
�@�����g�����x�b�P�����i���A�x��P�����j�́A���a�Q�U�N�x����Q�W�N�x�ɂ����Ėk�C������s�J�����ݎ��ƂƂ��đ������ǂ������̂ł���B���_����̂ɂ������̒n��́A�n�`���R�n�̂��߂P�˓�����̍k�n���g�債�ɂ�����ԂŁA�q���̉��ǂ��d�v�ƂȂ��Ă����B���̂��߁A�g���N�^�[�̓������K�v�ł���A������Ƃ̋@�B���ɂ��c�_�m����ڎw���A�ߑ㉻�A��������}�邤���œ��H�̋K�͍\�������ǂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�����������Ƃ��瓹�����Ǝ�̂ƂȂ��āA�S�S�N�x����S�U�N�x�ɂ����Ĕ_����C���Ƃ����{���ꂽ�B
�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�S�O�W�S���V�S�S�U�~�ŁA�H�Չ��ǂV�O�O���[�g���i�����T���[�g���j�A���T�����������B
����n�擹�c�����r������
�@����n��͓����ɂ�����Ă̎�Y�n�ł���A��c�ǐ�𐅌��Ƃ��Ė�c�Ǔ���H����搅���A���슲���p���H�ɓ������Ă���B���������̗p���H�́A���a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�Ɏ{�s���ꂽ�y���H�ŘR���������A�p���s���𗈂��������ێ��Ǘ�����������Ă����B���̂��߁A�T�P�N�x�ɂ����ē��c�ɂ�邩���r�����Ƃ̒������s���A�T�Q�N�x����T�U�N�x�܂ł̂T���N�v��Ŏ��Ƃɒ��肵���B
�@���̎��Ƃ́A�����Ɣ�R���P�T�O�O���~�ŁA��v�ʐςQ�O�V�w�N�^�[����ΏۂɁA�������R�X�W�T�E�P�X���[�g���i�����s�{�H��ԂW�P���[�g���j�̗p���H�����ǂ���邱�ƂɂȂ��Ă���B
����n��ߑa��_����������
�@���a�S�T�N�Ɏ{�s���ꂽ�ߑa�n���ً}�[�u�@�ɂ��A�ߑa�n��ɂ�����s�������Ǘ������I�Ȕ_���Ŕ_�ё�b���w�肷����̂̐V�݂܂��͉��ǂł����āA���̍H�����s�������{�s���邱�Ƃ������I�A�Z�p�I��������݂āA����������܂��͕s�K���ł���ƔF�߂�ꂽ���̂ɂ��Ėk�C������s���Ď��{���邱�ƂƂȂ����B����ɂ���ē����ɂ����ẮA�������N�_�Ƃ��Ă��і쏬�w�Z�Ɏ��钬�������������w����A�S�W�N�x����T�R�N�x�܂ŁA����E����ꂼ��T�O�p�[�Z���g�ɂ�鑍���Ɣ�P���P�U�S�T���~�������Ď��Ƃ����{���ꂽ�B��Ȏ��Ɠ��e�́A�H�Չ��ǂU�V�V�V���[�g���i�����U���[�g���j�A���P�����i�P�O���[�g���j�ł���B
�C�ݔ_�n�ۑS��
�@�����̊C�݂͒ᕽ����n�������A�Y�������Ȃ����ߍ����ɂ���Q�͔N�X�������A�N�H���������i�ތX���ɂ���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���w��̔_�p�n��ۑS���邽�߁A�_�ѐ��Y�ȏ��ǂ̕ۑS���ɂ����Ėk�C�������Ǝ�̂ƂȂ�A���̊e�n��̔_�n�ۑS�Ƃ����{����Ă���B
�� ���_�n��i�R��j
�@���Ɣ�@�X���X�O�T�O���Q�O�O�O�~
�@���Ɨʁ@���g��ݍH�Q�R�O�T���[�g���A�D�f��T�����P�O�O���[�g��
�@���ƒ���@���a�R�U�N�x
���ԉY�n��
�@���Ɣ�@�U���~
�@���Ɨʁ@���g��ݍH�P�R�S�O���[�g���A�D�f��R�����U�O���[�g��
�@���ƒ���@���a�T�P�N�x
����c���n��
�@���Ɣ�@�R���T�Q�U�W���Q�O�O�O�~
�@���Ɨʁ@���g��ݍH�P�Q�P�X���[�g���A���g��Q�S�X���[�g���A�˒�H�P�W��P�O�R�W���[�g���A�D�g��V�����U�O���[�g��
�@���ƒ���@���a�S�Q�N�x
������n��
�@���Ɣ�@�R���S�O�W�T���~
�@���Ɨʁ@���g��ݍH�P�O�U�W���[�g���A�˒�H�P�V��W�U�P���[�g���A�K�i�H�P�����P�O���[�g���A�D�g��P�����S�V���[�g��
�@���ƒ���@���a�S�U�N�x
�@��P�X�߁@��v�_�앨�k��̐���
�k��̊T�v
�@�����ɂ�����_�앨�̍k��ɂ��Ă̐��ڂ�����ꍇ�A�܂����ɏグ����̂́A������������吳�����ɂ����Đ���ɍ͔|���ꂽ�ł�Ղ��Ƃ��Ă̂ꂢ����ł��邪�A��ꎟ���E���̏I����͂ł�Ղi�̖\���ɂ��A����������q�ꂢ����֓]�����Ă�������ڂƂ��A�������A�L�����̎�Y�n�Ƃ��Ă̖������L�W���Ă������Ƃɐs����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��낤�B���̂����A���̎�q�ꂢ����ւ̓]���ƕ��s���Đi�߂�ꂽ�����̓����A���Ȃ킿�A���_�Ƃ̐U���ɑΉ����鎔���앨�̑����͓��R�̂��Ƃł������B
�@�������A�����P�Q�N�i�P�X�R�V�j�ɂڂ������������푈������������ɂ�ċ������ꂽ���Y�����́A�����̐H�ƍ�ځA�R���A�A�o�_�Y���̑��Y��ړI�Ƃ���v�搶�Y����n�߂�ꂽ���A����ɂ�肦�A�����E�Ƃ����낱���E�����앨�E�؎�Ȃǂ́A��t�ʐς┽���ڕW�܂Őݒ肳��A��萶�Y�ʂ̊m�ۂ��v�悳���Ƃ���ƂȂ�A�]���̍�t�ɑ傫�ȕω��������炵���̂ł������B���Ȃ킿�A�P�S�N�ɂ͎�v�앨�̂��ׂĂ����Ǎ앨�Ƃ��Ďw�肳��A���Y�m�ۂ�v����앨�Ƃ��āA�R���_�Y���E���������E�K�v�_�Y���E�A�o�_�Y���E�H�ƍ앨�E�H�ƌ����앨���Ƃ���Ă����B�������āA�H�Ƒ��Y�̂��߂ً̋}��ɂ��A�āE���E�ꂢ����Ȃǎ�v�H�Ƃ̋��o�����x������āA�����̔_�앨�����l�����A���ނ̂ق����ށE����E���Ȃ��сE�Ђ��E���Ȃǂ̗ނ�������t�����ꂽ�̂ł������B
�@�I���ɂ����Ă��A�H�ƕs���Ƃ�������̏�f���ċ��o���x���p�����ꂽ���߁A���̌X���͂��炭���������A�₪�ĐH�Ǝ�����肵�Ă���ɂ�āA�_�앨�̍�t�ɂ悤�₭�ω����݂���悤�ɂȂ����B���Ȃ킿�ł��傫�ȕω��́A������E��c�ǐ염���n�Ɍ���ꂽ���_�Ƃւ̓]�����������A���̐��ʂ��܂��傫�Ȃ��̂��������B����ɂ��Ă͓��ɍ������߂Čf������̂Ƃ��A�܂��A���̑��̔���̐��ڂ�ǂ��Ă݂邱�ƂƂ���B
�@�������痏�_����̂Ƃ����_�Ƃ̊m����ڎw���ĐU����}���Ă��������̔���́A���R�̂悤�Ɏ����앨����P�ʂ��߂Ă������̂́A���x�W�_���Ƃ̍ŏI�N���ɂ����鏺�a�S�R�N�x�i�P�X�U�W�j�ł����Q�S�O�R�w�N�^�[���ŁA�S�̂̂U�O�p�[�Z���g��ɂ������A���ށE�ꂢ����E���E���p�앨�Ȃǂ̊����앨�������ʐς��߁A�ˑR�Ƃ��ė��_����^�_�Ƃ̈��E���Ă��Ȃ������B�������A���̌�W�J���ꂽ��X�̗��_�U����ɂ������̑��B�Ɛ�Ɖ����i�ނɂ�A�����앨�̍�t���͔N�ɂ���č���������̂́A���悻�A�N�ɂ킽���đ��������A���a�T�P�N�ɂ͂T�R�V�X�w�N�^�[���ƂȂ�A�k�n�S�̂̂W�V�p�[�Z���g���߂�Ɏ������B
�@���̂悤�ɂ��ē����̔_�Ƃ́A���_��Ƃ��邢�͐��c��Ɣ_�Ƃ̒a�����݂����ʁA��O���̎�v�앨�͔N�X�����X���������A�S�U�N�ɂ͔��ނ͂قƂ�Ǐ��ł��Ă��܂��A�܂��R�U�N�����A�����앨�Ɏ����ō�t�ʐς̑����������j�Ȃǂ́A�č�����̑�ʗA���ɂ�鍑���������̒ቺ�ɂ���āA�S�X�N�ɂ͂킸���T�S�w�N�^�[���ƂȂ�A�����̂P�S�p�[�Z���g�ɂ܂Ō��������̂ł���B
�@����ɁA��Y�n�Ƃ��Ė������߂Ă�����q�p�ꂢ����́A�R�T�N�����̂S�O�O�w�N�^�[�����_�Ƃ��āA�Ȍ�͎���Ɍ��������ǂ�͂��߁A�S�P�N�ɂ͂R�O�O�w�N�^�[�����A�S�T�N�ɂ͂Q�O�O�w�N�^�[��������A���̌���Q�O�O�w�N�^�[����O�サ�Ă����Ԃł���B����́A���H�Ǝ���̈������������ɂ́A��v���앨�̂Ȃ��ōō��̔����J�����[���Y�ʂ��グ�邱�Ƃ��璘���������������A�{���t��p�̎�ގY��ꂢ����̋����n�Ƃ��āA�����ł͂��̕{���̏���ʂɂ���t�ʐς��������Ă������B�܂��A�R�T�N�O��ɂȂ�ƍ͔|�Z�p�̌����a�Q���h���̓O��A�̎�g�D�̊m���Ȃǂɂ�蔽�����ʂ͑������A�{���̎��v���ɑ��Ă͔������ʼn�����Ƃ����`�ō�t�ʐς͒���A�R�O�O�w�N�^�[���O��𑱂��A�S�R�N�ȍ~�͋}���Ȍ����������̂ł���B���������X���́A�{�B�{���ɂ������q�p�ꂢ����̎����̐����N�X�m�����A���̘̔H���k���������̂ƁA�o�c�̒P�����ƘJ���͂̌�������͔|�ʐς������������������̂ł���B
�@���̂ق��A���L���ׂ����̂ɂĂ�����邪�A������܂��������߂ďq�ׂ邱�ƂƂ��A���a�R�S�N�ȍ~�A�ŋ߂Q�O�N�Ԃɂ�����e��v�앨�̍k��ʐς͏�\�̂Ƃ���ł���B
�@�����@�����@���a�P�V�N�i�P�X�S�Q�j�ɐH�ƊǗ��@�����肳��A�Ă͐����ĉ��Ƌ��ϐ��x�ɂ�鉿�i�ۏ�ɂ���Đ��Y�ҕĉ��͑��̔��앨�ɔ�r���Ċ����ł���A����ɁA���{�Ƃ̌_��͔|�Ƃ������S��������闘�_�Ɍb�܂�A�_�Ƃ͈��S���č�t�����邱�Ƃ��ł������߁A���ɂ����鐅�c�����n�͑S���I�ɍ��܂��Ă������B
��v�_�앨��t�ʐς̐����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁFha�j
| �@�@�敪 �N�x |
���@�@�@�� | �ꂢ���� | ���@��@�� | ���@�@�@�� | ���p�앨 | �����앨 | ��@�@�� |
| �R�S | �P�V�U�D�S | �R�W�T�D�V | �R�P�W�D�S | �S�T�O�D�P | �R�P�R�D�R | �Q�C�S�O�R�D�T | �P�Q�U�D�W |
| �R�T | �Q�R�Q�D�Q | �S�O�R�D�W | �R�O�S�D�X | �H | �Q�X�S�D�S | �R�C�O�Q�U�D�S | �X�T�D�S |
| �R�U | �Q�T�S�D�O | �R�R�X�D�Q | �R�X�O�D�U | �R�X�O�D�O | �Q�O�T�D�U | �Q�C�W�R�O�D�X | �V�W�D�T |
| �R�V | �R�V�Q�D�W | �R�P�S�D�R | �R�V�U�D�R | �S�S�U�D�W | �P�R�T�D�R | �Q�C�X�P�X�D�R | �V�X�D�X |
| �R�W | �R�P�Q�D�X | �Q�X�S�D�R | �Q�U�U�D�S | �Q�S�P�D�P | �P�O�U�D�V | �P�C�X�R�U�D�V | �V�T�D�X |
| �R�X | �R�P�O�D�S | �Q�X�P�D�W | �Q�V�O�D�V | �H | �P�O�V�D�V | �R�C�P�O�P�D�V | �V�T�D�W |
| �S�O | �R�Q�O�D�P | �R�O�P�D�Q | �Q�P�X�D�X | �P�S�S�D�X | �P�R�R�D�W | �Q�C�W�O�T�D�W | �U�O�D�V |
| �S�P | �R�S�S�D�S | �R�O�O�D�W | �P�W�T�D�U | �P�T�P�D�V | �P�S�P�D�X | �R�C�Q�T�X�D�X | �U�S�D�Q |
| �S�Q | �S�P�P�D�R | �Q�S�V�D�W | �P�X�P�D�U | �P�R�U�D�O | �P�P�R�D�W | �Q�C�X�Q�R�D�T | �T�V�D�T |
| �S�R | �T�Q�V�D�W | �Q�T�W�D�W | �P�W�O�D�P | �P�P�T�D�O | �X�S�D�U | �Q�C�W�V�R�D�P | �R�X�D�X |
| �S�S | �T�T�V�D�P | �Q�Q�S�D�W | �P�W�U�D�R | �W�W�D�U | �P�P�V�D�S | �R�C�Q�O�Q�D�Q | �T�R�D�Q |
| �S�T | �S�S�V�D�U | �P�U�Q�D�X | �T�U�D�O | �V�R�D�U | �W�Q�D�Q | �R�C�R�V�O�D�R | �Q�P�D�V |
| �S�U | �S�Q�W�D�U | �P�X�Q�D�X | �T�S�D�R | �X�U�D�Q | �V�S�D�R | �R�C�T�S�S�D�X | �S�O�D�S |
| �S�V | �R�W�U�D�W | �Q�O�P�D�P | �R�V�D�S | �X�X�D�P | �V�Q�D�P | �R�C�V�V�V�D�U | �R�W�D�X |
| �S�W | �R�X�R�D�X | �P�W�R�D�R | �R�O�D�X | �U�O�D�O | �S�X�D�U | �R�C�W�X�W�D�P | �S�W�D�W |
| �S�X | �S�P�P�D�U | �P�W�P�D�S | �| | �T�S�D�P | �P�U�D�S | �S�C�O�T�V�D�S | �T�W�D�Q |
| �T�O | �S�R�S�D�O | �Q�S�Q�D�O | �Q�S�D�O | �P�P�T�D�O | �P�S�D�O | �T�C�O�V�Q�D�O | �P�P�P�D�O |
| �T�P | �S�W�U�D�T | �P�X�T�D�W | �P�U�D�V | �S�X�D�P | �P�T�D�S | �T�C�R�V�X�D�P | �S�U�D�S |
| �T�Q | �S�X�T�D�Q | �P�W�T�D�V | �P�T�D�S | �S�W�D�Q | �P�O�D�W | �S�C�U�R�R�D�X | �S�S�D�X |
| �T�R | �S�W�W�D�O | �P�W�O�D�P | �U�D�X | �S�S�D�V | �W�D�R | �S�C�R�X�T�D�P | �S�V�D�U |
�i�_�Ɗ�{�����j
�@�����ɂ����鐅�c�́A���Ԃ��Ȃ�����R��n��𒆐S�ɁA�S���Ŗ�Q�O�w�N�^�[���O��̍�t���ɂ����Ȃ������̂ł��邪�A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�P�P���ɗ���������n��ő��c���Ƃ��s���A���̗L�������m�F���ꂽ�̂��_�@�Ƃ��āA���c�ʐς͎���Ɋg�傳��Ă������B
�@���̓����A����n��ł͔����\�y�̉��������ΎR�D�w�ł��邽�߁A���c�����͕s�\�ł���ƍl�����Ă���A�e�ՂɎ^�����Ȃ������_���ɑ��A�������R�s�i���͂��ߔ_���L�u�����`�t�⍲�X�؉h���炪�M�S�ɐ������A�u����y�n���Nj�v��ݗ����đ��c���Ƃ̐��i�ɐs���������J�͓��M���ׂ����Ƃł���B
�@����ɁA��c�ǒn��ɂ����Ă��ɓ��T�O�Y�炪���N�l�ƂȂ�A�Q�W�N�V�����瑢�c���Ƃ��J�n�������A�Ί݂ł����c���n��̊��c�v����R�c�����������Ɍĉ����Ď��ƂɎQ�悵�A��c�ǐ썶�E���ݒn�тɂ����āu��c���y�n���Nj�v��ݗ��A�g�D�I�ȑ��c���Ƃ�������ꂽ�̂ł���B
�@�����������Ƃ������ɂ����鐅�c�����̂��������ƂȂ�A�Ȍ�e�n��ő��c���i�߂��A���a�R�Q�N�̒������������P�O�X�w�N�^�[���ɂ����Ȃ��������̂��A�S�S�N�ɂ͂T�T�V�w�N�^�[���ƂȂ�A�킸���P�Q�N�ԂłT�{�ȏ�ɑ��������̂ł���B�������A���̂��납�猰���ɂȂ����Ă̗]��ɑΉ����邽�߂̐��Y�����Ƃ��āA�S�U�N�x����J�n���ꂽ�u���]���Ɓv�A����ɁA�T�P�N�x�����ւ���ꂽ�u���c�����Ɓv�ɂ���āA���̍�t�ʐς͏��X�Ɍ������A�T�R�N�ɂ͂S�W�W�w�N�^�[���ɂȂ��Ă���B
�@���Ă�����@�����ɂ�����Ă�̗��j�I�w�i���݂�ƁA�����Q�Q�N�i�P�W�W�X�j�ɎD�y����������Ђ��c��ɐݗ����ꂽ�����A����Ƃ̉ƗߌÓc�m�F�i�}�}�j���劔��ɂȂ��Ă��̉�Ђ̐ݗ��ɎQ�����Ă������Ƃ��u�k�C���_�Ɣ��B�j�v�ɋL�^����Ă���̂ŁA�ڍׂ͕s���ł��邪���łɂĂ�ɂ��Ă̊S��������Ă������̂Ǝv����B���������̉�Ђ́A�s�ˎ��⌴���s���A�����̒ቺ�ȂǂƂ������������d�����ď�Ɍo�c�͕s����ł���A�Q�X�N�ɑ��Ƃ��~���A�R�S�N�ɉ��U�Ƃ����o�߂���݂āA���̎��т݂͂�ׂ����̂��Ȃ������̂ł��낤�B
�@�Ȃ��A�吳�����ɂ����ė���Ŏ��삳�ꂽ�Ƃ����L�^�����邪�A������ڍׂɂ��Ă͕s���ł���B
�@���a�U�N�i�P�X�R�P�j�ɖ��F���ς��ڂ������A�R�������傷��ɂ�ĖK�ꂽ�D���ɂƂ��Ȃ��A���a�P�O�N�k�C���ɐ����H��̌��v�悪���\�����ƁA�������܂߂��S���P�W�������ɂ���Ċ����ȍH��U�v�^�����W�J���ꂽ�B���̌��ʁA�����ւ̗U�v�͎c�O�Ȃ���������Ȃ��������A�P�P�N�Ɉ镪���i�k���j�A�m�ʁi�����j�ɐ����H�ꂪ���݂���A�����ɂ͖�������������Д��_���ݏ����ݒu����āA�Ă������앨�Ƃ��ĕ��y����邱�ƂƂȂ����B
�@���ݏ������߂Đݒu���ꂽ�����́A�܂��t���A�Ԉ����E��U�z�E���n�Ƃ�����Ƒ̌n���A�����̘J�͂�K�v�Ƃ������ߔ_�Ƃ̕s�]���A���݈��͏H�̎��n���I���Ɨ��N�t��������_�Ƃ��˕ʖK�₵�A�O�q��q���č�t���𗊂�ŕ�����Ԃł������Ƃ����B
�@����E��킪�ڂ������A�������{���ĕ҂���A���a�P�X�N�ɂ͖�������������Ђ��������V�H������A�k�C�����_�H�Ɗ�����Ёi���a�Q�Q�N�A���{����������ЂƖ��̕ύX�j�Ƃ��Ĕ��������B�����āA��������ƂĂ�����т����ی쏧��ł��o���ꂽ�̂ł��邪�A����n���ɂ͐����H�ꂪ�Ȃ��������߁A��t�ʐς͈ˑR�Ƃ��Ă킸���Ȃ��̂ł������B
�@���A�A���R�ɂ��������̐���̒��ŁA�Ă�ɑ���ی쏧���������ł���ꂽ�����A��ʂ̍����Ȃǂ������Ă��̐��Y�͌��ނ������A�Q�S�N����ی쏧��ĊJ�����ƂƂ��ɁA���������ɂ�č�t�ʐρE���ʂƂ��Ɏ���ɏ㏸����@�^���݂��͂��߂��B����ɁA�Q�V�N�ɍ����̓������P�p����A�Q�W�N�ɂ́u�[�ؐ��Y�U���Վ��[�u�@�v�����肳��āA�Œቿ�i�������ۏႳ�ꂽ���߁A�悤�₭�Ă�ؐ��Y�͋����̓����J���ꂽ�̂ł���B�R�S�N�ɂ́u�Ö����������v��v�����Ă��A�ɒB�̑䓜�����Г��쐻���������Ƃ��J�n�������Ƃ���A���̏���Ƃ����܂��āA�Ă�̍�t���͒������������������̂ł���B�Ȃ�����ɂ��A����܂ł̓��[������Д��_���ݏ��͑䓜������Д��_�����������Ɩ��̂��ς�����B
�@�����������w�i�Ƃ��������̂Ă�؍�t�́A�R�Q�N�̂P�W�R�w�N�^�[���ɑ��A�R�N��̂R�T�N�ɂ͂R�U�S�w�N�^�[���ƂQ�{�̐L�ї��������ď����Ɋ��҂����̂ł��邪�A�R�U�N�ȍ~�͂����ނˌ����X�������ǂ�͂��߁A�T�O�N�ɂ͂킸���X�w�N�^�[���ƂȂ�A�T�R�N�ɂ͂S�E�U�T�w�N�^�[���Ƌɒ[�Ɍ��������̂ł���B���̌����������̗v���͂��낢��l�����邪�A�풆����ʂ��ĐH�Ƒ��Y���������ꂽ�_���́A�H�Ǝ���̍D�]�ɂƂ��Ȃ���v�앨�̓����P�p�ɂ��A���v���̍������ƓI�_�Ɛ��Y�ւƓ]�����A�Œቿ�i������ۏ���Ă���Ă���A�����Ƃ��Ă͑��̈�ʍ앨���D�ʂł���A���i�̈��萫�����͂ƂȂ��č�t�ʐς͑������Ă������̂ł���B�܂��A�����ɂ����Ă��R�T�N�܂ł͏㏸�����ǂ��Ă���A���̍앨�Ɣ�ׂĎ��v���͗L���ɓW�J���Ă����B�������R�U�N�ȍ~�̔����́A��̑����͂��邪�R�W�N�܂ł͉��~��Ԃ������B����́A�P�˓�����̍k�n�ʐς����Ȃ������ɂ����ẮA�K�ȗA��̌n�̂��Ƃɍ�t�����ꂸ�A���������Q�A�R�N���x�ł��������߁A�n�͎��D�̌������Ă�́A�n�͂̌��Ղ𑣂����ʂƂȂ�A���������͉��i���̂��̂̒Ⴓ�����������A�Ăɔ�r����Ƃ��Ȃ�̍�������A�ĉ��̏㏸��L��Ȃǂɂ���Ĕ��n�̐��c�������i����A�����đ����̘J���͂��v�������Ă�́A����Ɍ�������Ƃ������ʂɂȂ������̂Ǝv����B
�@���a�S�R�N�i�P�X�U�W�j�ɁA����{�����i�{�ʁj�A�ʼnY�����i�k���j�A�䓜�i�ɒB�j�̂R�H�ꂪ�������Ėk�C�����Ɗ�����Ђ��ݗ�����A�����̎������͓��Г��쐻�������_�����������Ɩ��̂�ύX�����B
�@���a�R�Q�N�ȍ~�̂Ă�؍�t�ʐς���ю��ʂ̐��ڂ͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B
�Ă�ؐ��Y�̐���
| �@�@�敪 �N�x |
��t�ʐ� | ���@�@�@�� | ���@�@�@�� | ��t�ː� | t������ ���@�@�i |
| �R�Q | ha �P�W�R�D�V�U |
t �R�C�X�R�T�D�Q�V |
t �Q�C�P�S�Q |
�T�U�T | �~ �T�C�Q�T�O |
| �R�R | �Q�S�O�D�S�O | �T�C�P�W�R�D�O�P | �Q�C�P�T�U | �U�T�P | �T�C�Q�T�O |
| �R�S | �R�R�R�D�X�R | �V�C�Q�R�R�D�S�O | �Q�C�P�U�U | �V�V�Q | �T�C�Q�T�O |
| �R�T | �R�U�S�D�P�Q | �W�C�O�P�X�D�Q�U | �Q�C�Q�O�Q | �V�S�W | �T�C�Q�T�O |
| �R�U | �Q�V�X�D�Q�Q | �S�C�R�V�W�D�T�S | �P�C�T�U�W | �U�U�W | �T�C�S�U�T |
| �R�V | �Q�O�T�D�O�U | �R�C�X�R�S�D�Q�V | �P�C�X�P�X | �T�R�R | �U�C�O�P�T |
| �R�W | �P�P�X�D�S�U | �Q�C�Q�U�R�D�O�P | �P�C�W�X�S | �R�X�Q | �U�C�T�O�O |
| �R�X | �P�P�W�D�U�R | �Q�C�R�O�R�D�S�S | �P�C�X�S�Q | �R�R�V | �V�C�Q�R�U |
| �S�O | �P�T�W�D�Q�T | �R�C�W�U�O�D�P�T | �Q�C�S�R�X | �R�T�T | �V�C�Q�P�V |
| �S�P | �P�T�T�D�P�X | �S�C�O�V�O�D�X�S | �Q�C�U�Q�R | �R�S�R | �V�C�Q�O�O |
| �S�Q | �P�Q�O�D�P�Q | �S�C�O�R�O�D�T�P | �R�C�R�T�T | �R�O�Q | �V�C�R�R�O |
| �S�R | �P�O�P�D�O�O | �R�C�P�Q�P�D�U�S | �R�C�O�X�P | �Q�U�V | �V�C�T�O�O |
| �S�S | �P�T�W�D�Q�T | �R�C�W�U�O�D�P�T | �Q�C�S�R�X | �R�T�T | �V�C�U�T�O |
| �S�T | �V�U�D�P�O | �Q�C�R�X�T�D�O�S | �R�C�P�S�V | �Q�O�V | �V�C�W�R�T |
| �S�U | �V�X�D�Q�Q | �Q�C�T�V�W�D�Q�Q | �R�C�Q�T�T | �P�W�V | �W�C�O�U�W |
| �S�V | �V�S�D�S�Q | �Q�C�R�Q�T�D�Q�X | �R�C�P�Q�T | �P�T�T | �W�C�R�O�S |
| �S�W | �R�U�D�U�Q | �P�C�S�T�V�D�W�V | �R�C�X�W�P | �W�O | �W�C�V�X�X |
| �S�X | �P�T�D�V�R | �U�X�R�D�V�S | �S�C�S�P�O | �R�Q | �P�T�C�O�O�O |
| �T�O | �X�D�P�Q | �Q�X�V�D�P�V | �R�C�Q�T�W | �P�X | �P�U�C�O�O�O |
| �T�P | �U�D�R�W | �Q�T�O�D�W�V | �R�C�X�R�Q | �W | �P�V�C�O�O�O |
| �T�Q | �T�D�O�Q | �P�V�S�D�R�U | �R�C�S�V�R | �W | �P�W�C�P�Q�O |
| �T�R | �S�D�U�T | �P�Q�R�D�X�Q | �Q�C�U�U�T | �V | �P�W�C�S�V�O |
�@��Q�O�߁@�_�ƌː��ƌo�c�K�͕ʂ̐���
�_�ƌː��̐���
�@��ʂɔ_�ƂƂ����ꍇ�́A���ꑊ���̋K�͂̔_�n��ƒ{��L������̂�A�z�������ł��邪�A�_�Ɗ�{�����ł́A�i�P�j�P�O�A�[���ȏ�k�삷����́A�i�Q�j�ƒ{�ȂǔN�Ԕ̔��z���V���~�ȏ�i����ɂ���ċ��z�̕ω����������j�̂��̂��A�_�Ƃ��c�ނ��̂̒�`�Ɋ܂ނ��ƂɂȂ��Ă���A�������A�ȏ�̏����ɊY�����đ��̋Ǝ�ƌ��Ƃ���ꍇ�A�_�Ǝ�������Ƃ�����̂́u���팓�Ɣ_�Ɓv�A���̑��̎�������Ƃ�����̂́u���팓�Ɣ_�Ɓv�Ƌ敪����Ă��邱�Ƃ�O���ɒu���Ȃ���A���̎��Ԃ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�����čŏ��ɂ����Ƃ�肵�Ă����B
�@���������Ώ۔͈͂���݂����a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j�̑��_�ƌː��͂P�S�T�Q�˂ł��������A�P�O�N��̂S�Q�N�ɂ͂X�V�T�˂ŁA���悻�R���̂Q�Ɍ������A����ɁA�P�O�N��̂T�Q�N�ɂ͂T�X�R�˂ƂȂ�A�R���̂P���Ɍ�������Ƃ����������Ă���B����ϓI�ɂ݂�A�N�X�R�p�[�Z���g�������������ƂɂȂ�B���̂悤�Ȍ����̗v���͂��낢�닓������Ǝv�����A�I�풼��ɋً}�J��҂Ƃ��ē��A�������̂�R�ԕӒn�̎؉Ƃ��A���x�o�ϐ������W�J���ꂽ�R�O�N��̌㔼�ɂ����āA��N�w���s�s��H�ƒn�т֗��o����Ƃ�������A��p�҂�����������łȂ��A�_�ƌo�ς������������ɒ��ʂ��ē]����]�V�Ȃ�����A�R�T�N�ɍ��肳�ꂽ�u�J��_�Ɨ��_�����x�v�ɂ��J��_�Ƃ̗��_�����ɂƂǂ܂炸�A�����_�Ƃ̗��_�����o�������Ƃ��܂����ɋ������悤�B
�@�������A�J��_�Ƃ������̌o�c��Ԃ���݂đ��X�ɗ��_���邱�Ƃ͗����ł���Ƃ��Ă��A���ꂪ�Ӓn�̊����_�Ƃɔg�y���A����ɁA�s�X�n�⍑���������炳�قlj����Ȃ��_���n�тɂ��y�сA���Ă̏W�����S�˓]�o�ƂȂ�A���l�n�тƂȂ����Ƃ���������������ȂǁA�����Ƃ��Ă͑z�����ł��Ȃ��������ۂ������Ɍ���ꂽ�B�R�U�N�����ɂU�V�T�˂𐔂�����Ɣ_�Ƃ��A�P�O�N��̂S�U�N�ɂ͂S�O�O�ˑ������A���a�T�U�N�ɂ͂킸���ɂR�O�V�˂𐔂���݂̂Ƃ��������́A�����炭�A������\���ł��Ȃ��������Ƃł��낤�B
�_�ƌː��̐��ڒ�
�@�@�@�@�@�@�@�i�ˁj
| �@�@�敪 �N�x |
���@�@�� | ��@�� | ��� ���� |
��� ���� |
| �R�Q | �P�C�S�T�Q | �H | �H | �H |
| �R�U | �P�C�R�U�S | �U�V�T | �P�V�T | �T�P�S |
| �S�Q | �X�V�T | �T�Q�W | �P�W�V | �Q�U�O |
| �S�R | �X�R�O | �T�Q�U | �P�V�U | �Q�Q�W |
| �S�S | �X�P�U | �S�Q�S | �P�T�S | �R�R�W |
| �S�T | �W�O�S | �S�O�X | �P�T�V | �Q�R�W |
| �S�U | �V�S�O | �R�X�Q | �P�Q�W | �Q�Q�O |
| �S�V | �U�V�R | �R�U�R | �P�O�O | �Q�P�O |
| �S�W | �U�S�V | �R�R�P | �P�S�T | �P�V�P |
| �S�X | �U�R�U | �R�R�W | �P�R�O | �P�U�W |
| �T�O | �U�Q�O | �R�R�S | �P�R�P | �P�T�T |
| �T�P | �U�O�X | �R�S�Q | �P�P�Q | �P�T�T |
| �T�Q | �T�X�R | �R�R�X | �P�O�T | �P�S�X |
| �T�R | �T�W�O | �R�Q�S | �P�P�R | �P�S�R |
| �T�S | �T�T�W | �R�P�S | �P�O�S | �P�S�O |
| �T�T | �T�R�O | �R�P�P | �P�O�R | �P�P�U |
| �T�U | �T�P�Q | �R�O�V | �X�W | �P�O�V |
�S�T�C�T�T�N�F���E�_�ƃZ���T�X
�T�O�N�F�_�ƃZ���T�X
���̑��͔_�Ɗ�{�����ɂ��
�ȉ�����
�@���������_�ƌː��̐��ڂ͏�\�̂Ƃ���ł���B
�o�c�k�n�K�͕ʂ̐���
�@���킪���̔_�Ƃ́A�H�Ƒ��Y�����㖽�߂Ƃ��鋟�o������o�߂������A���a�R�O�N��ɂ͐�O�̐����܂ŕ��������H�Ɖ��A�����č��x�o�ϐ�������ɂ���Č}�����d���w�H�Ǝ���ւ̈ڍs�ɂ��ߑa�E�ߖ����ۂ��A�_�ƌo�c�̏�ɗ^�����e���͎��ɑ傫�Ȃ��̂��������B
�@���Ȃ킿�A���łɊ��x���G��Ă����悤�ɁA�_���l���̓s�s��H�ƒn�тւ̗��o�ɂ��J���͂̌����A�_�ƏA�Ǝ҂Ƒ��Y�ƏA�Ǝ҂Ƃ̊Ԃ̏����i���̑���Ȃǂ��A�傫�ȎЉ���ƂȂ����̂ł���B����ɑΉ����Ċ����_�Ƃ́A�_�ƌo�c�̍�������@�B����i�߂����A���_�Ւn�̎擾�ɂ��o�c�K�͂̊g��ȂǁA������o�c�̋ߑ㉻��}��K�v�ɔ���ꂽ�̂ł������B
�@���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�������������w�i�Ƃ��āA�����o�c�_�Ƃ̈琬��ړI�Ƃ����u�_�Ɗ�{�@�v��������z����Ă���A��肢�������̌o�c���P��Ƃ��āA�o�c�K�͂̊g��ɗ͂�������A���c�E���Ƃ��ɂP�˓�����̌o�c�ʐς�����Ɋg�傳���X�������ꂽ�̂ł���B�܂��A���_�ɂ����Ă��A���ɑ����������ڎw���Čo�c�K�͂̊g�傪�}�����������A�S�P�N�ɍ̗p���ꂽ���H���������ɑ���s�������x���_�@�Ƃ��āA�}���ȐL�W�����ǂ�悤�ɂȂ����B
�o�c�k�n�K�͕ʔ_�ƌː��̐���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��)
| �K�͕� �N�x |
�O�D�Tha ���� |
�O�D�T �`�P�D�O |
�P�D�O �`�R�D�O |
�R�D�O �`�T�D�O |
�T�D�O �`�V�D�T |
�V�D�T �`�P�O�D�O |
�P�O�D�O �`�P�T�D�O |
�P�T�D�O �`�Q�O�D�O |
�Q�O�D�O �ȏ� |
�v |
| �R�T | �S�O�P | �W�X | �Q�O�O | �Q�W�V | �R�P�S | �P�Q�R | �P�V | �| | �P | �P�C�S�R�Q |
| �S�O | �R�R�T | �S�X | �P�P�V | �Q�P�V | �Q�W�X | �P�S�X | �R�U | �S | �R | �P�C�P�X�X |
| �S�Q | �R�O�R | �| | �X�Q | �P�U�Q | �Q�O�T | �P�S�P | �U�P | �X | �Q | �X�V�T |
| �S�R | �Q�R�W | �S�S | �W�Q | �P�P�T | �Q�Q�R | �P�R�T | �W�U | �T | �Q | �X�R�O |
| �S�S | �Q�U�O | �R�W | �U�R | �W�V | �P�X�Q | �P�S�R | �P�O�V | �Q�Q | �S | �X�P�U |
| �S�T | �P�V�P | �R�T | �V�S | �V�W | �P�U�O | �P�S�S | �P�P�P | �Q�R | �W | �W�O�S |
| �S�U | �P�S�X | �R�T | �U�S | �U�S | �P�R�W | �P�Q�Q | �P�R�O | �Q�U | �P�Q | �V�S�O |
| �S�V | �P�P�X | �Q�Q | �T�V | �T�X | �P�Q�S | �P�P�Q | �P�P�V | �S�Q | �Q�P | �U�V�R |
| �S�W | �P�O�U | �Q�O | �T�S | �U�W | �P�O�T | �P�O�T | �P�P�X | �S�R | �Q�V | �U�S�V |
| �S�X | �P�O�S | �Q�S | �S�W | �T�V | �X�X | �P�P�P | �P�P�P | �T�U | �Q�U | �U�R�U |
| �T�O | �P�O�Q | �Q�R | �S�U | �T�P | �W�P | �P�P�W | �P�O�X | �U�O | �R�O | �U�Q�O |
| �T�P | �X�V | �Q�U | �S�U | �S�V | �W�P | �P�O�P | �P�P�O | �U�W | �R�R | �U�O�X |
| �T�Q | �P�O�P | �Q�Q | �S�S | �R�W | �V�T | �X�O | �P�O�X | �V�T | �R�X | �T�X�R |
| �T�R | �X�Q | �Q�R | �S�V | �R�Q | �V�O | �W�V | �P�P�R | �V�Q | �S�S | �T�W�O |
| �T�S | �V�V | �P�T | �Q�X | �Q�O | �R�T | �V�R | �X�Q | �P�O�V | �P�P�O | �T�T�W |
| �T�T | �V�P | �Q�Q | �R�U | �Q�U | �T�W | �V�T | �P�P�Q | �U�W | �U�Q | �T�R�O |
| �T�U | �U�O | �P�X | �R�R | �R�S | �T�R | �V�P | �P�O�V | �U�X | �U�U | �T�P�Q |
�@���̂悤�ȏ����Ƃ��āA�����ɂ�����o�c�K�͕ʔ_�Ƃ̐��ڂ��݂�ƁA���a�R�T�N�����͂T�`�V�E�T�w�N�^�[���w���S�_�Ɛ��̂Q�Q�p�[�Z���g���߁A�܂��A�T�w�N�^�[���ȉ��̑w���U�W�p�[�Z���g�����߂�Ƃ����ŁA���K�͌o�c�K�w���ɂ߂đ��������B����ɑ��A�S�O�N�ȍ~�ɂ͂V�E�T�w�N�^�[���ȉ��̑w�͔N�X�����̌X�������ǂ�A�t�ɂP�O�w�N�^�[���w�ȏ�̌o�c�K�͂����_�Ƃ��������Ă���B���Ƃ��Ɠ����̔_�Ƃ́A�ꕔ�̐��c��Ɣ_�Ƃ������A���_����̂Ƃ���_�Ƃ����|�I�ɑ����A�������A����������̌X�������܂����Ȃ��ŁA�o�c�K�͂̊g�傪�]�܂��͓̂��R�ł��邪�A���a�T�O�N��ɓ���ɒ[�Ɍ��ꂽ�����̎����ɘa�f���āA�T�S�N�����狍���̐��Y�������s���A���_�Ƃ��͂��߂Ƃ���W�҂̖͍��͓������������ł���B
�@��Q�P�߁@�_�ƐU���n�搧�x�Ƃ��̑Ή�
�_�U�n��̎w��Ɛ����v��
�@���a�R�O�N��㔼�ɓW�J���ꂽ���x�o�ϐ�������́A�n��̎Љ�\����o�Ϗ�ɒ������ω��������炵���B���ɏd���w�H�Ƃُ̈�Ƃ�������i�W�́A�_���J���͂��z�����Ĕ_�ƌː�������������v���ɂȂ�Ɠ����ɁA���v���ԂƂ�������y�n�̗������ɂ���āA�_�n�]�p������ɐi�߂���Ƃ����X�����݂���悤�ɂȂ��Ă����B
�@���̂��ߐ��{�́A���a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�V���Ɂu�_�ƐU���n��̐����Ɋւ���@���v�i�_�U�@�j�𐧒���z���āA�_�ƐU���n�搧�x�����{�����B���̐��x�́A�_�U�@�Ɋ�Â��_�Ƃ̌��S�Ȕ��W�ƍ��y�����̍����I�ȗ��p��}�邽�߁A�m�����_�ƐU���n��i�_�U�n��j�̎w���_�U�n�搮���v��̍���Ɋւ��ĕK�v�ȁu�_�ƐU���n�搮����{���j�v���߂Ĕ_�ё�b�̏��F����B���̊�{���j�ɏ]���Ďw������s�������́A���̗v���ɂ��u�_�U�n�搮���v��v�𗧂āA���̐����v����}�X�^�[�v�����Ƃ��Ă��ꂼ��̎��Ƃ��ƂɌʂ̌v�悪���肳��A���Ƃ����{�����Ƃ������̂ł������B
�@����������|�̂��ƂɁA���̔_�Ǝ{��͔_�U�n�搮���v�����{�ɂ��āA�����I�ɏW�����Ď��{����Ƃ����h�����_���h�ւƓ]�����A���ɍ��̕⏕�Ȃǂɂ�鎖�Ƃ̂����A�i�P�j�_�Ɛ��Y��Ղ̐����E�J�����ƁA�i�Q�j�_�Ɛ��Y�ߑ㉻�{�݂̐������ƁA�i�R�j�_�n�ۗL�̍��������ƁA�Ȃǂ͌����Ƃ��Ĕ_�p�n����ΏۂƂ��Ď��{�����ق��A�_�Y���̍L��I�ȗ��ʉ��H�A�ߑ㉻�{�݂̐������ƁA�ƒ{���Y�Ɋւ��鎖�ƂȂǂ́A�����Ƃ��Ĕ_�U�n���ΏۂɎ��{����邱�ƂɂȂ����̂ł���B���̂ق��_�U�n��ɂ́A�d�œ��ʑ[�u�@�ƒn���Ŗ@�ɂ����ď����ŁE�@�l�ŁE�o�^�Ƌ��ł���ѕs���Y�擾�łɂ��āA���ꂼ��y�����Ƃ���Ȃǂ̕X���u����ꂽ�B
�@�����ł͏��a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�P�O���A���̔_�U�@�ɂ��n��w��������Ƃɂ��A���̐��i�̐��Ƃ��āA���E�c��E�_�ƈψ���E�_�Ƌ����g���E�_�Ɖ��Ǖ��y���E���̑��_�ƊW�c�̓��̑�\�҂P�V������Ȃ�u���_���_�ƐU���������i���c��v��ݒu�����B�����āA�������P�O�N�Ԃ�z�肵���_�p�n���p�v��Ă�����A�u�_�p�n���v�Ɓu�s�X�����v�̏�n���p�敪�Ăɂ��Ĉ��̊��ԊW�҂ɏc�������A����ɂ��Ĉًc�̂����n���L�҂⌠���҂̐\�����Ă��ĕK�v�Ȓ������s���[�u���Ƃ����̂ł���B
�@����́A�O�q�̂悤�ɔ_�p�n���Ǝw�肳�ꂽ�ꍇ�͐��x��̕⏕��Z�������锼�ʁA�y�n���p�̐�������̂ɑ��A���Ƃ����ݐ��c�┨�ł������Ƃ��Ă��A���ꂪ�s�X�����Ɋ܂܂����̂ł���ꍇ�ɂ́A����_����̕⏕��Z���ɂ�鎖�Ƃ͍���ɂȂ�Ƃ������Ƃ��Ȃ����߂ł������B
�@�������āA�����̔_�U�n�搮���v��̍ŏI�ẮA�S�U�N�R���ɒ��_�ƐU���������i���c��̏��F�������āu���_�_�ƐU���n�搮���v��v�Ƃ��č��肳�ꂽ�̂ł���B
�����v��̊T�v
�@�������č��肳�ꂽ�_�U�n�搮���v��ɂ��A�����ł͊��ɔ_�ƍ\�����P���ƁE�����r�����ƁE���n���ǁE�C�ݔ_�n�ۑS�ƂȂǂɂ���Đ��Y��Ղ����X�����������Ƃ͂����A�v����莞�̔_�p�n�ʐς́A���ؗт��܂߂ĂU�V�Q�V�w�N�^�[���ɂ����Ȃ��ɂ������B���̂��߁A����ɖ����p�n�⌴��̊J����}��A�_���Ԃ̐����𑣐i���Ȃ���o�c�̋K�͂��g�債�A�o�c�̈����}��Ƃ��������I�ȓy�n���p�v����������邱�Ƃ���{�I�ȍ\�z�Ƃ��A���悻�P�S�O�O�O�]�w�N�^�[���̔_�p�n������ڕW�Ƃ��Ē�߂��B
�@���̌�A�Љ�o�Ϗ�̕ω��ɑΉ����A���X�ɑ������y���ȕύX��i�߂Ă������A���̐��ڂɉ��������̕��j�ɂ��傫�ȕϊv�𗈂��A���̂����炱�̌v��̌������𔗂��邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A���ɒm���ɐ\�����ď��a�S�X�N�x�Ɂu���ʊǗ��n��v�Ƃ��Ă̎w����A�T�O�N�R���ɉ��߂Ĕ_�U�n�搮���v������肵���̂ł���B������̌���A�K�v�ɉ����Đ����y���ȕύX���������Č��݂Ɏ����Ă���B
�@���̌v��ɂ��ƁA���ݔ_�p�n�ł���y�n�ł����Ă��A�C�ݕۑS�n��Ƃ��Đ�������n�сA�H�ꗧ�n�����n��i��c���j�Ȃǂ̓���n�т���ѓs�s�v��ɂ��s�X���̑ΏۂƂȂ���A���邢�͏W�����i����E����E�㔪�_�E��c���E�����j���ɉ�݂���_�p�n�A����ό��n�Ƃ��ĊJ����K���ƔF�߂�n��i��̓��E���̓��j�Ȃǂ�K�X�������ʁA����ł͎R�сE����ł����Ă����̊J���v��ɂ���������ڕW�̂P�Q�O�O�O���i�̂��ɂP�P�Q�O�O���ɕύX�j��B�����邽�߁A�͖k�E�㔪�_�E�����E�����̂S�n���ݒ肵�A���ꂼ�ꏊ�v�̔��n��n�����̊J�����v�悵�A���v�P�Q�O�O�O�w�N�^�[���̔_�p�n�m�ۂ�ڎw���Ă���B
�@�܂��A�����̔_�ƌo�c�͋����Ɛ�������ڂƂ��A�ꂢ����E�Ă�E������⊮�Ƃ���c�_�̌n�ł��邱�Ƃ����A���������āA�_�ƌo�c�`�Ԃ𗏔_��ƁE���_����E���c��ƁE��������̂S��ɕ��ނ��������A���ꂼ��ɖڕW�Ƃ���c�_�ތ^��ݒ�A���̖ڕW�ɉ����Ė����p�n�̊J���𑣐i���A�_�ƌo�c�K�͂̊g���}��ƂƂ��ɁA���a�R�W�N���납�猰���ƂȂ������_�Ւn�̕����擾���ۂ��������A���������ɂ��_�n�̏W�c����}�邱�Ƃ���Ă���B
�@�������āA�y�n��Ր�����O��ɑ�K�͂Ȏ����o�c�_�Ƃ̈琬��ڎw���A�����Ĕ_�Ƌ@�B����Ƒ̌n���m�����Čo�c�̋ߑ㉻�ɓw�߂邪�A���ɗ��_��ƌ^�̑����ɂ���Č����܂�鑽��������ɑΏ����āA�琬���̋������q��A���n�̋������p�A�������n�ʂ̑����A��|�Ǘ��̌���Ȃǂ�}��A�K�����n�������邱�Ƃ�ڎw�����̂Ƃ��Ă����B
�ڕW�c�_�ތ^�̕\
| �ށ@�@�^ | �o�c�_�p�n���ʐ� | ��@�@�ځ@�@�\�@�@�� | �J���͍\�� | ���@�@�{�@�@���@�@�� | �ڕW���� | |||
| ���_��� | ���@�@�Q�O�E�Oha ���̑��Q�E�Oha �v�Q�Q�E�Oha |
�E���� �@�@���@���R�O�� �@�@�琬���P�O�� �E�q�����P�V�E�Oha �E�f���g�R�[���R�E�Oha |
��J���Q�l �⏕�J���P�l |
�����Ɉ�R�S�O�u�A�T�C���O��Q�T�Om�R�A�A�����U�Om�R�A �͔����P�Q�O�u�A�i�[�Ɉ�U�U�u�A �g���N�^�[�T�O�o�r�P�E1/2��A ��Ƌ@�P�P�E1/2��A�i��^1/5�j�o���N�N�[���[�i�P�O�O�O���j��� |
��~ �T�A�O�O�O |
|||
| �� �_ �� | �� �P�T�E�Oha ���̑��P�E�Oha �v�P�U�E�Oha |
�E���� �@�@���@���P�W�� �@�@�琬���V�� �E�q�����P�O�E�Tha �E�n�鏒�O�E�Wha �E�Ă���O�E�Tha �E�f���g�R�[���R�E�Qha |
��J���Q�l �⏕�J���P�l |
�����Ɉ�P�V�O�u�A�T�C�����Q�O�Om�R�A�A�����T�Om�R�A �͔����P�O�O�u�A�i�[�Ɉ�U�U�u�A �g���N�^�[�T�O�o�r1/2��A ��Ƌ@�P�T�E1/2��A�o���N�N�[���[�i�U�O�O���j��� |
�S�A�R�O�O | |||
| ���c��� | �c �W�E�Oha ���̑��O�E�Tha �v �W�E�Tha |
�E���@���V�E�Tha | ��J���P�l �⏕�J���P�l |
�_�Ɉ�P�O�O�u�A�͔�Ɉ��P�O�O�u�A�_��Ɉ�U�U�u�A �g���N�^�[�S�U�o�r�P�E1/2��A��Ƌ@1/6��A�c�A�@���A ���͏����@���A�X�v���[�o1/5�A�o�C���_�[1/5�A �R���o�C��1/30 |
�S�A�R�O�O | |||
| �������� | ���P�S�E�Oha ���̑��P�U�E�Oha �v�R�O�E�Oha |
�E���@���P�O�O�� �E�q�����P�O�E�Oha �E�n�鏒�P�E�Oha �E�Ă���P�E�Oha �E���̑��Q�E�Oha |
��J���P�l �⏕�J���P�l |
�{�Ɉ�T�O�O�u�A�A�����P�S�Om�R�A�͔����Q�W�O�u�A �i�[�Ɉ�U�U�u�A�g���N�^�[�S�U�o�r1/5�A��Ƌ@�P�O�E1/5�� |
�S�A�O�O�O �i��b�P�O���j �i���T�O���j �i�f���S�O���j |
|||
�i���a�T�O�N�R�����_�_�U�n�����v���b����
�i���a�T�O�N�R�����_���U�n�搮���v�ފ�b�����j
�@�ڕW�c�_�ތ^�������Ǝ��\�̂Ƃ���ł���B
�@
�@��Q�Q�߁@��v�_�ƒc�̂̕ϑJ
���Y�g���̒a��
�@�����R�W�N�i�P�X�O�T�j�ɘh�̑��i���j�̗L�u���A�R�т̕������L��ړI�Ƃ��āA�Y�Ƒg���@�Ɋ�Â��u�h�̑����Y�g���v�̐ݗ��F�\�������ɒ�o�����̂��n�܂�ł���B
�@�������̖����R�R�N�A�u�k�C���_�Ǝ҂̐ݗ�����Y�Ƒg���Ɋւ��钺�߁v�����z����A�����ɂ����Ă���������サ�Ă����Ƃ��ł�����A�h�̑����Y�g���̐ݗ��͒����ɔF�ƂȂ����B����ɂ��A�g���������k�A�������������Y�A�ꖱ�������c���O�Y���A�C���āA�_�Ɩ@�l�g���Ƃ��Ĕ��������̂ł���B
�@���̑g���́A�����R�R�N�ɐݗ������_�Ƒg�������U���A����ɋ��͂Ȃ��̂Ƃ��āA���Y���̔̔���H�Ƃ̍w�����Ƃ��s�����̂ł��邪�A�g���^�c�̕s����Ɩ��n�Ȃ��Ƃ������đ��z�̕���������݁A�S�R�N�ɂ͊e���������S���ĉ��U�����̂ł������B�������A�g���̉��U�ɂ���Ĕ_���͋}���ɕs�ւ������A�Ăёg���̐ݗ���]�ސ������܂����̂ŁA�吳���N(�P�X�P�Q)�P�Q���ɑ����ؑ���ܘY�́A�����L�O�Ƃ��đS���I�ȑg�D�ł��鐶�Y�g���ݗ��̏�����i�߁A�u���_�엿�����w���g���A����v�̐ݗ��ւƔ��W���Ă������̂ł���B
���_�엿�����w���g���A����
�@�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�ɖk�C���_��ݗ�����A�����̖����ɂ͂��̉����g�D�͂قƂ�ǑS���ɕ��y���Ă����B�����āA�S�_��⒬���_��̒i�K�ł́A��������엿�̋����w�����s���Ă������̂����������A�S�O�N�ɖk�C����B��s���V���ɔ엿�����̑ݕt�Ɩ����J�n�������Ƃɂ���āA�k�C���_��ɂ�����엿�����w���̐����}���ɐi�W�����B
�@�k�C����B��s�̔엿�����ݕt������v��A(�P)�_�Ǝ҂Q�O�l�ȏ�A�сA(�Q)�ݕt���z�͈�l���ςT�O�~�ȓ��A(�R)�엿�̍w����_��̑��m���ȉ�ЂɈϑ����āA�ݕt���͂��̑���ɒ��ڎx�������ƁA�ȂǂƂ��Ă������A�k�C���_��ł��u�엿�w��������K�v���߁A�u��������j�V�e�i���D�ǃi���v�엿���������邱�Ƃɓw�߂��̂ŁA���̋����w�����Ƃ͒��N���W���������B
�@����������̂Ȃ�����A����ɂ���ꂵ�ĘA�����g�D���A���v�̐��ʂ��ꊇ���čw�����邱�Ƃɂ���Ĉ����E�ǎ��Ȕ엿������ł���Ƃ��đ吳���N�i�P�X�P�Q�j�P�Q���A�����U�����g���̑�\�҂�����ɏW�����đn��������J�Â��A�����L�O���ƂƂ��āu���_�엿�����w���g���A����v��ݗ������B�����āA��E����l�S�����E�_�ĂȂǂ𐧒肵�đ̐��𐮂��A�n�͂̈ێ��Ɛ��Y�̑����ɔ������̂ł���B
�@�������āA��P�ƂƂ��đ吳�Q�N�ɂU�g���Q�W�S�˂ŁA�哤�����T�T�V�O���A�߃����_�ΊD�R�U�X�O��(���܂�)���w���������A�吳�T�N�ɂ͂P�U�g���P�R�Q�O�˂𐔂��A�哤�����R���S�R�O�O���A�߃����_�ΊD�P���T�R�P�O�ۂɒB����قǂł���A���̔엿�����w���g���A�����Ɂu�Y�Ƒg���v�ݗ��̓��@�Ƃ��Ȃ����̂ł���B
�@�܂��A�吳�U�N�ɂ͗������I�m�ؑЂɑg�����Q�Q���������āu�����엿�����w���g���v���A������ɑg�����Q�R���������āu����엿�����w���g���v�����ꂼ��ݗ����ꂽ�B
���_���_��
�@�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�Q���ɔ_��߂����z����A���̔N�W�����_���ƎR�z�����̋�������u���_�O�ꃕ�����_��v��ݗ��������A�R�T�N�ɂQ�����������{�s���ꂽ���Ƃɂ��A�R�W�N�̒ʏ푍��ɂ����āu���_���_��v�Ɖ��̂��ꂽ�B�����āA�_��̖ړI�B����}�邽�߁A�����ɔ_���ݒ�i�Q�O�_��j���A���ɔ_�撷���A����ɑg���������đg�D�𐮂��A�_�撷�͔_��̕]�c�������˂đ���̑�\�҂ɏ[�Ă�ȂǁA���̉~���ȉ^�c��}�邱�ƂƂ����B
�@�_��́A�u�K�E�u�b��̊J�ÁA�_��̉��ǁE�����엿�̕��y�Ȃǂʂ̎��ƂƂ��A�S�P�N����S�N�Ԃ͗{�\����̈ꏕ�Ƃ��ĊȈ{�\�`�K���E�����E匊�����E�͔͌K���E�������̔����Ȃǂ�ݒu�����B�܂��A�R�V�N�ɍŏ��̔_�Y���i�]����J�Â��A����ɁA�S�Q�N����吳�U�N�܂ł̊ԂɂV��ɂ킽���K�͂ȋ��i����J�Â����B���̂ق��A�엿�̋����w���ɑ��ĕ⏕������t����Ȃǂ̎��Ƃ��s�������A�_��ɂ����Ă����т���ё͔�i�]����J�Â���ȂǁA�_�Ƃ̐U����}�����B
�@�܂��_��́A���쌓�̎�ނ��o�c���邽�߁A�吳�S�N�i�P�X�P�T�j�V���Ɏ��T�����x�m�W�R�Ԃ̂S�i���A���L���Q�P�R�Ԓn�ӂ�j�̔��l���l����l�������Ď��Ƃ��s�����̂ł��邪�A���a�W�N�i�P�X�R�R�j�V���_��������z��ɏ[�Ă邽�߂��̓y�n�p�����B
�@�_��̐ݗ������́A���N�x�o��̑啔�����̕⏕�Řd�����̂ł��邪�A�吳�V�N�x������ʊ��Ƃ��ĕ����������@���߁A���ꔽ���ɂ��ܗЁA�q��ꔽ���ɂ���Ђ̊����Œ������A�����ʼn��������������ȂǁA�o�ϓI��Ղ̊g�[��}��ƂƂ��ɁA�Z�p����u���čk������|�̉��P�w���ɓw�߂��B
�@�������_�́A���R�Ɩ����D�y�h�o���̂��w�����ɕғ�����A���N���ʂ̂������o�����̂ŁA��v�ȉč앨�Ƃ��Ĕ_�ƌo�ςɂ��傫�Ȗ�����S�����̂ł��邪�A�_��͂��̌_�牺�����⋟�o�ȂLj�A�̎����ɑ��Z���ɂ߁A���Ɍ_������S�ɗ��s���āA�Ɩ����̍w�����Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ������߂̋�J�͗e�ՂȂ��̂ł͂Ȃ������Ƃ����B
�@�_��͐ݗ��ȗ�������Ɏ�������u���Ă������A���Ƃ̐i�W�g�[�ɂƂ��Ȃ��Ɨ������������̌��z���}���ƂȂ����B
���̂��߁A���a�W�N�X���ɖؑ��Q�K���ĂS�O�̎�������V�z�i���A�����ٕ~�n���j���Ď��Ƃ̐��i��}�����B
�@���a�P�O�N�O��ɂ�����_��́A�S���I�ɂ��[���������Ƃ������ׂ������ŁA���̎��Ƃ�����ɂ킽�������A���ɂ��̎����ȍ~�͋��Q�⋥��̏P���A�푈�̂ڂ����Ȃǂ̂��߁A�_���ɑ��鐭��͂��߂ׂ̍��������߂��A�Ă�؏���E�a�Q���h���E�̎�ށA�c�ތo�c�E�z�����P�E�e�틤���E�����엿����E�_�Ǝ��s�g������E�u�K�u�b��E���Ə���E�o�ύX���v��w���E�_�ƕ�L�w���ȂǁA���ʂ��ɂ߂��̂ł������B
�@�������A�P�Q�N�̓����푈�ڂ����̂��ƈ�A�̓����@�����z����A�P�R�N������͔_�яȂɂ���Ĕ_�Ɛ��Y�̌v�扻���i�߂���ɋy�сA�_��͂��̐��i�@�ւƂ��ďd�v�Ȗ������ۂ���ꂽ�̂ł���B
�@�Ȃ��A�����A�n�����킸�A�����̐i�s�ɂƂ��Ȃ��A�_�Ƃ̍ĕҐ���c�̓����̘_�c�����܂�A�펞�_�Ɛ��Y�̊g�[������������ɐi�߂�ꂽ���A���a�P�X�N�P���_�ƒc�̖@�ɂ���ĉ��U�̖��߂��A�S���Ɂu���_���_�Ɖ�v����������܂ŁA��т��ē����̔_�Ɣ��W�Ɋ�^�����̂ł������B
�@���̔_��n�ݓ����̉�ɂ͐������`���I�ꂽ���A�����͊Ԃ��Ȃ��S�_��ɓ��I�������߁A�����R�S�N�S���ɕ⌇�I�����s���哇�b���A�C�����B���������l�͂R�V�N�S���Ɏ��C�����̂ŁA�����O��v���Y�𖼗_����ɐ��E����������ɑI���������A�O�䑺�����S�̂��Ɩ����R�X�N�P�Q���ɓ��l�̕��@�ɂ���đ����ؑ���ܘY����ɏA�C���A���a�Q�N�R���܂łQ�O�N�]�ɂ킽�肻�̐E�߂��B���̌�A���a�Q�N�S������V�N�P���܂œ���_�꒷�哇�b�A�V�N�R������P�O�N�R���܂Œ������c���O�Y�A�P�O�N�S������P�X�N�R���܂Ŕ��؊��s�����ꂼ���߂��B
���_���M�p�w���̔����p�g��
�@�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�R���u�Y�Ƒg���@�v�����肳�ꂽ���A����͂킪���ɂ����鋦���g���g�D�̖@���Ƃ��čŏ��̂��̂ł���A�����_���H�Ǝ҂��C�ӂɑg�����������āA�ϋɓI�ɋ����o�ώ��Ƃ��c�ނ��Ƃɂ���Čo�Ϗ�̏�Q��ŊJ���A���̒n�ʂ̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B���̖@���Ɋ�Â��g���ɂ́A�M�p�g���E�̔��g���E�w���g���E���p�g���̂S��ނ�����A���̑g�D�Ƃ��āA�����ӔC�E�L���ӔC�E�ۏؐӔC�̂R�킪�F�߂��A�V���ȏ�̑g����������Βn�������̋����đg����ݗ����邱�Ƃ��ł�����̂ƂȂ��Ă����B
�@�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�����Ŏ��̔_��ł������ؑ���ܘY�̒ɂ���Ă��̔N�Q���u�L���ӔC���_�M�p�w���g���v��ݗ����A�g�����Q�W�T���A����g�����ɖؑ��������A�C�A�������������ɒu���āA������Y�Ƒg���̑����ݏo�����̂ł������B�g���̎��ƖړI�́A�g�����̗a�����̕X���͂���A�����݂̑��t�����s���ƂƂ��ɑg�����̉c�_�܂��͐��v�ɕK�v�ȕ��i���w�����̔�����ق��A�����\��҂̒�������舵�����ƂȂǂł������B
�@�吳�V�N�T���Ɏ����������݂̖��L���i���A���_�_�����ݒn�j�Ɉړ]���A���̔N�V���Ɂu���Y���Ɓv��lj����āu�L���ӔC���_�M�p�w�����Y�g���v�Ɖ��̂����B
�@���N�@���̉����ɂ���āA�M�p�g����Y�g���̎��Ɗg���ƁA�s�X�n�M�p�g�����x�����������ƂƂ��ɁA�_�Ƒq�ɖ@���{�s���ꂽ���Ƃɂ��A���W�N�P���u�_�Ƒq�Ɂv�̔F���Ƃ�A�T����c���O�Y�A�~�����\�Y�̗����������o�c���鏤�Ƒq�ɂQ���i�����P�U�O�j�Ɛ����{�݂��P���T�Q�O�O�~�ŏ���Ď��Ƃ��J�n�����B
�@����ɁA�吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j�T���ɂ́u���p���Ɓv��lj����āu���_�M�p�w�����Y���p�g���v�Ɖ��߁A�X���Ɏ�������V�z�����B�����łP�T�N�U���A�R��ɔ_�Ƒq�ɂ̎x�ɂ�ݒu����ȂNJg�[�̈�r�����ǂ�A�܂��A���a�Q�N�u�̔����Ɓv��lj����āu���_�M�p�w���̔����p�g���v�Ƃ��A������Y�Ƒg���Ƃ��Ă̑S�@�\��������g�D�ɔ��W�����B
�@���a�R�N�U���ɑg�����ؑ���ܘY���ސE���A�V���Q��g�����ɔ��쒼�����A�C�������A�ؑ��g�����͑g���ݗ�����S�@�\��������g�D�ɔ��W����܂ŁA�����̍�����������A��Q��ŊJ���Ĕ��_�̎Y�ƐL�W�ɐs�������Ɛт͑���ł������B
�@���a�S�N�T���A��c���ɑg���̍w���i�z������ݒu���Ė�c���n��_���̗��ւ�}��A����ɁA���T�N�S���ɂ͗������̖�c�ǁE�s���E�n��A��҂Ȃǂ̊e�n��W�W�������i�P�U�N�R���ɒE�ށj�����Ď��Ƃ̊g�[��}��ȂǁA���Y�̊g�呝���Ɣ̘H�̊J��A��q�p�ꂢ�����Y�n�Ƃ��Ă̒n�ʊm�ۂ��͂��߁A�펞���ɂ�����_�ƌo�ς̈���ƁA�g�������̌��S���ɓw�߂��̂ł������B
�@���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�R���펞�̐��̋����ƁA�c�̓����̋@�^�ɑ������邽�ߐ��肳�ꂽ�_�ƒc�̖@�ɂ���āA���P�X�N�P�����U�𖽂����A�S���u���_�_�Ɖ�v�ɉ��g���ꂽ�̂ł���B
���_�_�Ƒq�Ɂi�ʐ^�P�j

���_�Y�Ƒg���i�ʐ^�Q�j

�@���̊ԁA����g�����͏��a�P�Q�N�V���ɑސE�A�P�S�N�S������P�U�N�X���܂Ŕ����g�V���A�P�U�N�P�O������P�X�N�S���ɔ��_���_�Ɖ�ݗ������܂ŋv�ۓc���H���g�����߂��B
���_���_�̔����p�g��
�@���a�U�N�i�P�X�R�P�j�̋��������A���Ȃ킿�A�����̖\���Ɣ��������̊�@�ɒ��ʂ������_�Ƃ́A�_�ƎҎ���̑g�D�ɂ���Đ��Y�������������A���_�̊�Ղ����łɂ��邽�߁A���V�N�P���u���_���_�̔����p�g���v��ݗ����đg�����ɂ͔��_�M�p�w���̔����p�g�����̔��쒼�����A�C�����B
�@�g���̎��Ƃ́A�����̉��ǁE�����̌���E�������̓����A�����̎������P�Ȃǂ���Ƃ��A�����̎��{�Ǘ��w���E�D�ǎ�Y���̗A���E�������lj�E���������n�i�]��E�Y�Ǝ��@�E�W���{�݂̐����E�T�C���̌��ݏ���E�����Ƒ����_���k���̐ݒu�ȂǁA�ϋɓI�Ȋ������s�����B
�@���Ɍn����P�̂��ߏ��a�P�P�N�T���ɃA�����J�̃J�[�l�[�V�����q�ꂩ��D�ǎ�Y���Q����A�������ق��A���L�ݕt��Y�������A�g�����c�Ƃ��ĕ��y�ɓw�߂��B����ɁA�P�W�N�Q���ɂ͐l�H�����u�K�����Â��A��������n�ɍs���ėǍD�Ȏ�ِ��т��m�F���Đl�H�����ւ̊S�����߁A�S���ɐ�삯�ĔN�X���̎{�݂����A�����̑��B���P�ɓw�߂��̂ł���B
�@�Ȃ��A���̑g���͐ݗ��������痎�����̖�c�ǁE�s���E�n��E��ҁE��̏�Ȃǂ̊e�n����܂��Ă������A�_�ƒc�̖@�ɂ����U���߂������Ƃɂ���āA�P�W�N�P�Q������������ċ��ύX�ƂȂ�A�������̑g�����͗������_�Ɖ�ɑ�����Ƃ���ƂȂ����B
�@�g���́A���Ƃ̊g�[�ɂ�ď��a�P�P�N�T���������Ɏ�������V�z���A���N�U���ɂQ�K��c���z����ȂǑ̐��̐������}��ꂽ���A�P�X�N�S���_�Ɖ�̐ݗ��ɂ���ĉ��U����܂Ŕ���g�������ݐE���A�g���̖ړI���s�ɂ��������̂ł���B
���_���_�Ɖ�
�@���a�P�Q�N�i�P�X�R�V�j�ɂڂ������������푈�́A����܂ł̔_�ƌ`�Ԃ���ς����A�푈�����̂��ߔ_�Ƃɂ����鋟�o�E�z���E���Y�E�J���͂ȂǁA�S�ʂɂ킽���ē������������ꂽ�B�����āA���̎��H�̂��߂P�W�N�R���R�P�ځu�_�ƒc�̖@�v�����z���ꂽ�̂��͂��߁A�u�_�ƒc�̎{�s�߁v�₱��Ɋ֘A����e��K�������z����A�X������{�s���ꂽ�̂ł���B����́A�����̔_�ƒc�̂����U���āA���퉺�̔_�ƍ������s�̂��߁A�_�Ɖ�ɓ��ꂵ�悤�Ƃ�����̂ł������B
�@���a�P�X�N�P���P���t�Ŗk�C�����������甪�_���_��E���_�M�p�w���̔����p�g���E���_���_�̔����p�g���̂R�c�̂ɑ��A�u�_�ƒc�̖@�攪�\�����m�K��j�˂葴�m�@�l�j�V���U�����Y�v�Ƃ̎w�߂��������A�e�@�l����͎w��̊����܂łɁA���Y�ژ^�E�ݎؑΏƕ\�E�g�D�Җ���Ȃǂ��ɒ�o���邱�Ƃ��w�����ꂽ�B
�@����A�����t�Łu���_�����Ɖ�v�ݗ��ψ��ɁA���؊��s�E�v�ۓc���H�E���쒼���E����Ǐ��E�я푥�E�O�j�E�F���呾�Y�̂V����������������w�����ꂽ�̂ŁA�����ݗ��ψ��ɂ���ď������i�߂�ꂽ�B�������āA��E�c���ב����̑��̔_�Ɖ�ݗ��Ɋւ���Č��̏����������ɐi�߂�ꂽ���A�����l���͍Ō�܂œ�q���A���Ɍ��_���݂Ȃ��܂܂R���Q�X���ɐݗ�����J�Â��ꂽ�B
�@���̂��߁A�����l���͊e���s�g�������ψ��Ƃ��đI�l���邱�Ƃɂ����̂ł��邪�A��������_���o�����u��y����m���E�n���������j��C�V�A�����Ď��n��g���O�c�̒��j��C�X���v�Ƃ����ɂȂ�A�^�ۗ��_�ɕ�����ĕ��������̂ł��邪�A���ǑI�l�ψ��̂̕Ƃ��茈�肵�A�������������㗝�Ƃ��ďo�Ȃ��Ă�������_���ے�����A��ɉF���呾�Y�A����ɔ��쒼���E�v�ۓc���H�A�ږ�ɔ��؊��s�����ꂼ�ꐄ����đ���͕���B
���_���_�Ɖ�i�ʐ^�P�j

�@�S���P���t�Ŕ��_���_�Ɖ�̐ݗ��F�ƉF����̓������߂����������Ƃɂ��A��Ƌ��O�c�̒��̎l�҂ɂ�鋦�c�̌��ʁA�����ɓn�Ӌ�E�͌������Y�E�ē������E���c�F���E����K�g�A�Ď��ɗс@�푥�E�č�`�Y�E�O�j��I�C���A�S���U���ɐݗ��o�L�����������B
�@�������Ĕ_�Ɖ�́A�_�ƂɊւ��鍑��ɑ������ď]���̎O�c�̂̎��Ƃ����A�^�c�̍�������}��펞���ɂ����鈫�����̂Ȃ��ŁA���Y�̈ێ��E���o�̐��i�E���~�̑����E��Ƒ��̉���Ȃǂɓw�߂��̂ł��邪�A���ɗ��_�̔��_�Ƃ��ẮA�玙�p�����ƃJ�[�C�����Y�ً̋}���ɂƂ��Ȃ������̊������Y��A�ꂢ���傻�̑��H�Ɣ_�앨�̋��o�ȂǁA�����̓��������̂ł��邪�A������v���͂��Ă悭����ɑΏ������B
�@���a�Q�P�N�i�P�X�S�U�j�Q���ɉF��������C���A���N�R���P�R��������쒼��������ɏA�C�������A���Q�Q�N�P�P���_�Ƌ����g���@�ƂƂ��Ɍ��z���ꂽ�u�_�Ƌ����g���@�̐���ɂƂ��Ȃ��_�ƒc�̂̐����ȂǂɊւ���@���v�ɂ���Ĕ_�ƒc�̖@�͔p�~����A���̖@���{�s�̓��i���N�P�Q���P�T���j���琔���Ĕ������ȓ��ɉ��U����邱�ƂɂȂ��Ă������A������u���_���_�Ƌ����g���v�̐ݗ��ɂ��A����Ɏ����̈�������p�����U�����̂ł���B
���_���_�Ƌ����g��
�@���A�A���R�w�߂̂��Ƃɍs��ꂽ����I�ȏ����x�̉��v�̂Ȃ��ŁA���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�Ɏ{�s���ꂽ�_�Ƌ����g���@�ɑΉ������W�_���́A���Q�R�N�P���ɐV�����g���ݗ��̓������N�����A�ݗ����N�l����i�n�ق��V�Q���ɂ��ݗ���������J�ÁA�芼�쐬�ψ��������ċN����i�߂�ȂǁA�����͏����ɐi�݁A���Q���W���Ɂu���_���_�Ƌ����g���v�n��������J�Â���Ɏ������B����ɂ����ẮA�芼�̏��F������I���ȂǏ��v�̎葱�����o�ĂR���R���ɒm���̐ݗ��F���B�����ĂR���Q�X���ݗ��o�L���������A���悢�斯��I�ȋ����g���Ƃ��Ĕ��������̂ł���B�ݗ������̑g�����͂W�T�X���ŁA�����͋v�ۓc���H�ȉ��P�V���A�Ď��͑��c�F���ȉ��R���ŁA����g�����ɂ͗����̌ݑI�ɂ���Ĕ��쒼�����A�C�����B
�@�������Đݗ����������g���́A�I�풼��̐H�Ɗ�@��v�z�����Ȃǂ̎����w�i�Ƃ��Ȃ�����A��E����g�����̋��͂Ȓc���̂��ƂɁA�����̖ړI�Ɍ����Ċe��̎��Ƃ𐄐i�����̂ł���B���ɁA���a�Q�T�N�T���g���Ԑ��t�h�Ƃ��Ē��ڂ𗁂т��A�A�����J����̓������t�̗A���ɂ��D�Ǔ����̐��Y�Ɏ��g�̂��͂��߁A�Q�V�N�ɂ͓��L�g���N�^�[�S��̑ݕt���āA�S�y�k�A���w�k�ɂ��k�y���ǎ��Ƃ��J�n�A����ɁA�u���h�[�U�[�P������Ēc�n�����Ȃǂ��s�������Ƃ́A�ݗ������̎��ƂƂ��ĉ���I�Ȃ��̂ł������B
�@���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�S���ɔ���g���������C���A���T���ɋv�ۓc���H���g�����ɏA�C�����B���傤�ǂ��̂���A���x�W�_�n��w��Ɋ֘A���āA�����̈ꌳ�W�ז��̉������}���Ƃ���Ă����Ƃ��ł���A�������Ƃւ̏o�҂Ƃ̐��͓I�ȐՂ���������ȂǁA������������̂ł��邪�A�R�P�N�X���ɂ͎w����邱�ƂƂȂ����̂ł���B�������A���x�W�_�n�挚�ݎ��Ƃɂ͐ϋɓI�Ɏ��g�݁A�������_���W�̋��͂Ȑ��i��̂ƂȂ邱�Ƃ͂������A�R�R�N������{�́u�_�Ɛ��Y�g�[�܂��N�v��v���������āA���Y�̔��z�{���v��̐��i�ɓw�߂��̂ł���B����ɁA���̐��Y�g�[�v��͑�E��O���ւƈ����p����A�g�D�������Ĕ��_���_�Ɛi�W�̌����͂ƂȂ��Ă����B
�@���̂ق��A�_�Ɣ��W�̕�̂Ƃ��Đs���������Ƃ͐��m��Ȃ����̂����邪�A���a�R�T�N�x����O���N�Ŏ��{���ꂽ�u�V�_�R�������ݑ����Ɓv�ɂ��R�U�N�x�̗L�������{�݂̊J�݁A�܂��A�R�X�N�x����́u�_�ƍ\�����P���Ɓv�A�S�O�N�ȍ~�́u�c�̉c���n���ǎ��Ɓv�A�u�c�̉c�q�y���Ɓv�A�u�c�̉c�Ë��r�����Ɓv�Ȃǂ̓y�n��Ր������ƁA����ɁA�S�W�N�x����́u�_�������͓d�C�������Ɓv�A�u�e�����W���H������Ɓv�A���邢�́A�T�P�N�x����́u���_�n�摍���f�����Ɓv�ɂ��o�c�ߑ㉻�{�ݐ������ƂȂǁA����̐��ڂɑΉ����A�n��_�ƐU���̂��߂̊e�펖�Ƃ����{���Ă����̂ł���B
�@���a�T�R�N�i�P�X�V�W�j�ɂ́u�_�ƐU���܂��N�v��v�����肵�A�ڕW�N���ł���T�V�N�x�̐��Y�z���A�_�Y���łS���V�O�O�O���~�A�{�Y���łS�W���P�O�O�O���~�Ɛݒ肵�A��˕��ςP�V�W�P���]�~���ڕW�Ƃ��Ċe��̎��Ƃ𐄐i���邱�ƂƂ��Ă���A���̎����Ɋ��҂����Ă���B
�@���̊ԁA�吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j�Ɍ��Ă�ꂽ��������w���X�܂͑g�����Ƃ̐L�W�ɂ���ċ����Ȃ�ƂƂ��ɘV�����������߁A���a�S�Q�N�i�P�X�U�V�j�P�P���Ɏ������ƓX�܂�V�z�����B����ɁA�S�T�N�U���ɂ͍ݗ��̔��_�w�O�q�ɂ����z���āA������u�_�����X�[�p�[�v��ݒu����ȂǁA�Ɩ��͈̔́E�K�͂Ƃ��Ɋg���̈�r�����ǂ����B�܂��A�e�틤�ώ��ƁE�c�_�w�����ƁA�����Ĕ_�Ɗ�Ր������ƂȂǁA�L�͂Ȋ����ɂ���Čo�c�̈���ƍ�������}��A���̂ق��A�R�����ƁE�ԗ��@�B���ƁE�������ƂȂǑ���ɂ킽���đg�����Ƃ��^�c���A�g���{���̎��Ƃł���M�p�E�̔��E�w���̊e�펖�Ƃ�ʂ��đg�����̔_�ƌo�c�͂������A���퐶���܂Ŗ��ڕs���̊W�ɗ��Ɏ����Ă���B
�@�������Ĕ��W�𑱂����g���́A���a�T�V�N�i�P�X�W�Q�j�S�����݂ŁA���g�����U�V�R���E�S�c�́A���g�����P�T�X���E�P�U�c�̂𐔂��A�E�����X�X�l��i�����g�D�ƂȂ����B
�@�Q��g�����v�ۓc���H�́A�P�P���N�߂ĂS�P�N�T���ɑޔC�A���̌�A�S�R�N�P�Q���܂ő��c�����A�T�P�N�T���܂ō��ؖ����v�A�T�V�N�S���܂ŎO�j�����߁A���g�����͂U��n�ӍD�j�ł���B
���_���_�Ƌ����g���i�ʐ^�P�j

�������_��狦���g���܂�
�@�������ɂ�����_�ƒc�̂̂͂��܂�́A�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�X���Q�S���_��߂ɂ���āA�g�����R�T�O���������Đݗ����ꂽ�u�������_��v�Ƃ݂��A�������͗������˒�����ɒu���ꂽ�B
�@����A�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�R���ɗ����Z���̋��Z�@�ւƂ��āu�s��v���ݗ�����Ă����̂ł��邪�A���̌�A�_���L�u����Y�ƒc�̖@�Ɋ�Â��F�c�̐ݗ��̋@�^�����܂�A�吳�U�N�V���ɑg�����U�O���A�o������T�O�~�������đn��������J���A�����ݕt�Ɨa�����̕X��}�邽�߁A�u�L���ӔC�������M�p�g���v��ݗ����ĂW���Q���ɔF���Ĕ����������A������܂�������������ɒu���ĉ^�c���Ă����B
�@����������̗v���ɉ����āA���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�P�Q���ɂ���܂ł̐M�p���Ƃ̂ق��A�w���Ɣ̔����Ƃ��čs�����ƂƂ��āu�L���ӔC�������M�p�w���̔��g���v�Ɖ��̂��A���W�N�R���ɂ́u�L���ӔC�v����u�ۏؐӔC�v�ɕύX���đg�D��������������łȂ��A���̔N�P�Q���ɂ͎����������ݒn�ɐV�z�ړ]���ċ@�\���[�������B����ɁA���X�N�P�P���ɂ͗��p���Ƃ̔F���āu�ۏؐӔC�������M�p�w���̔����p�g���v�Ɖ��̂��A�Y�Ƒg���Ƃ��Ă̑S�@�\��������g�D�ɔ��W�����̂ł���B
�������M�p�w���̔��g���i�ʐ^�P�j

�@�Ȃ����̊Ԃɂ́A�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�ݗ��́u�����엿�����w���g���v�i�Q�Q���j�Ɓu����엿�����w���g���v�i�Q�R���j�����a�W�N�i�P�X�R�R�j�ɔ��W�I�������đO�L�g���ɍ������A�܂��A���a�U�N�̋��������ɑΏ����ė��V�N�S���ݗ��́u�ۏؐӔC���������_�̔��w���g���v�i�g�����E���c�k���j���A���a�P�O�N�T�����l�ɋz����������Ȃǂ̐��ڂ��o�āA�܂��܂����W�𐋂��Ă����B
�@�����ڂ��ǂ����Ȃ�̏��a�P�W�N�R���A�_�Ə��c�̂�����_�ƒc�̖@�̌��z�ɂ��A���P�X�N�P���P���t�������āA�]���̔_��ƐM�p�w���̔����p�g���͓����ɉ��U�𖽂����A����ɉ������_�Ɖ�̐ݗ������ɑ������āA���N�Q���P���u�������_�Ɖ�v�ݗ��̔F���A�R���Q�S���ɐݗ��o�L���������A�g�����ɗ��������ґ����邪�A�C���Đ펞���ɂ�����^�c���s�����̂ł���B���������̔_�Ɖ�́A��q����_�Ƌ����g���̔����������ĕK�R�I�ɏ��ł��邱�ƂƂȂ�̂ł���B
�@���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�P�Q���{�s�̔_�Ƌ����g���@�ɂ��V�����g���ݗ��̓��������Q�R�N�P���ɋN������A�䊨���d���Y�ȉ��Q�O���ɂ��ݗ����N�l��Ɛݗ���������o�āA�R���V���������w�Z�ɂ����đn��������J�Â��A�R���Q�T���ɔF�������ƁA�S���P�U���ɐݗ��o�L�����������B�������āA���悢��u�������_�Ƌ����g���v���a�����A���݂ɂ�����g�D�̑����ݏo�����̂ł���B�ݗ������̑g�����͂S�Q�W���A�����X���A�Ď��R���̍\���ŁA����g�����ɂ͒��J��M�`���A�C���A�E���͂P�S���ł������B
�@�������A������c�ǒn��̔_���́A�n���I�Ȍ�ʕs�ւ𗝗R�ɓƎ��̑g����ݗ����ׂ�������i�߁A��c�ǁE���ÁE�n��E����ҁE��c�nj䗿�n����~�Ƃ���u��������c�ǔ_�Ƌ����g���v�i�g�����E�y��T���j�̐ݗ������߂Đ\�����A�Q�R�N�S���R�O���ɔF���Ĉꑺ��g�����ƂȂ������A���Q�S�N�V���Ɍo�c��Ղ̋����Ƃ����ϓ_���痼�g���ɂ���Ęb��������������A�������_�Ƌ����g���ɋz�������Ƃ����`�œ������������A��c�ǂɎx����u�����ƂƂ��āA�悤�₭���̐��̊�b���z���ꂽ�̂ł������B
�@�������ċ������ꂽ�g���́A�Q�S�N�X�������̈ߗ��s���ɒ��ڂ��đg�����c�̖a�эH���V�݂��A�z�[���X�p�����n�̐������J�n���Ĉ�ʂɊ�ꂽ���̂ł������B�������A�₪�Ĉߗ�����D�]����悤�ɂȂ萔�N�Œ��~���邱�ƂƂȂ����̂ł��邪�A����̐��ڂ����̂���ِF�̎��ƂƂ��Ă����Ă����ɓ��L�����B
�@���A�s����ȎЉ�o�Ϗ�̂��Ƃɂ����āA�����ɂ킽���Q�╗���Q�̉e�����āA�Ԃ��Ȃ��g���͑��z�̕����A�Q�U�N�ɔ_�Ƌ����g���Č������@�̓K�p���邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A�����Ƒg�������ϋɓI�ɍČ��v��̍���ɎQ�悵�Ă��̎�����}�����̂ł��邪�A�Q�W�N�ȍ~���ł�������Q����Ɍ�������Ȃnjo�c�����͂���ɂ̂�A��苭�͂ȍČ��v��������ėՂ����Ƃ����₳���̂R�O�N�P�Q���A�_�����čH�ꂩ��o���Ď������E�X�܁E�_�Ƒq�ɁE�E���Z��ȂǁA�U���V�S�R�������[�g�����Ď������ق��A�t�ߖ��Ƃɂ����Ă��ĊJ���ȗ��̑�ƂȂ�A�Č��r��̑g���ɑ傫�ȏՌ���^�����B
�������_�Ƌ����g���i���a�R�P�N���z�j�i�ʐ^�P�j

�������_�Ƌ����g���i���a�T�S�N���z�j�i�ʐ^�Q�j

�@���������ꋫ�ɗ������ꂽ�g���ł͂��������A�W�҂̋��͂ɂ���ė��R�P�N�X���Ɏ�������V�z����ƂƂ��ɁA�����Č��ɂ��S�͂𒍂����̂ł���B
�@����A�n����_�Ƃ́A����n��ŏ��a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j����A��c�ǒn��ŏ��a�Q�W�N����A���ꂼ�ꑢ�c���Ƃ��i�߂��A�o�c�`�Ԃɑ傫�ȕϊv�������炳��悤�Ƃ��Ă������肩��A���a�R�P�N�X���ɂ͗��������u���_�W�_�n��v�̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂ꂽ���Ƃɂ���āA�g�����܂��n��̗��_�U���Ɏ��g�ނ��ƂƂȂ����B�����āA�R�Q�N�x�ɍ��L�ݕt���Q�O�������Ė����_�Ƃ̉����ɓw�߁A�R�R�N�x�ɂ̓g���N�^�[�P�Z�b�g�����A�S�y�k�E���w�k�Ɋ��p���ēy�n��Ր������Ƃ����{�����B����ɁA�R�T�N�x�ɂ͔_�R�������ݑ��������ʏ������Ƃ̘g�̒��ŁA���͌��p�~�X�g�@�P�X�������ȂǁA�o�c��Ղ̋����g�[�ɓw�߂��B
�@�Ȃ��A�g���o�c��̂̎��Ƃ��݂�ƁA�y�n��Ր������Ɓi�ޏꐮ���E���]�q�y�E�����r���E�Ë��r���j�E�d�C���ƁE�_���������ƂȂǐ���������A���̂��ׂĂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�n����̓������݂鎑���Ƃ��āA�g���̔̔����Ƃ̂����ŕĂ̐L�ї����ł��������A�i�ڕʂł͏��a�R�X�N�ɋ������Y���Z���đ�P�ʂƂȂ�A�S�Q�N�ɂ͑��z�̂R���̂Q�����߂�Ƃ������������̂ł���B
�@�܂��A�g���{���̎��Ƃł���M�p�E�̔��E�w�����Ƃ̂ق��A�g�����̕�������Ɛ�������̂��ߋ��ώ��ƂƂ��Ē��E�Z�����ς����{���A�S�P�N�R���ɂ͊ȈX�ǖ@�ɂ��ȈX���������{�̔F���A����̔_����c�ǎx���Ɂu��c�Ǔ��ȈX�ǁv���J�݂��A�n����g�����̗��ւ�}���Ă���B
�@����ɁA�g���̉����g�D�Ƃ��Ċe�n��ɔ_���g���i�P�O�g���j�A���w�l���i�X�g���j�A�_���N������������A���Y�͂̑��i�Ƒg�����̌o�ϓI�A�Љ�I�n�ʂ̌����}�邽�߂ɐϋɓI�Ȋ������������Ă���B
�@�܂��A���a�T�S�N�P�O���ɂ́A���H��T�O�O�O���~�������āA�S�����^���Q�K���āA�R�P�T�������[�g���̎����������������̗אڒn�ɐV�z�����B
�@���g�����͎��̂Ƃ���ł���B
�P�A�Y�Ƒg������
�@�{�쐴���Y�@���A��U�E�X�`���A��P�S�E�R
�@���c�k���@���A��P�S�E�R�`���A���V�E�R
�@���J��M�`�@���A���V�E�R�`���A���P�X�E�R
�Q�A�_�Ɖ��
�@�ґ�����@���A���P�X�E�R�`���A���Q�O�E�T
�@�F��^�O�ܘY�@���A���Q�O�E�W�`���A���Q�P�E�R
�@���J��M�`�@���A���Q�P�E�S�`���A���Q�R�E�W
�R�A�_�Ƌ����g������
�@���J��M�`�@���A���Q�R�E�S�`���A���Q�S�E�S
�@�{���G�g�@���A���Q�S�E�S�`���A���Q�W�E�U
�@���J��M�`�@���A���Q�W�E�U�`���A���S�U�E�T
�@�ɓ��~��@���A���S�U�E�T�`����
�g��������ѐE����
�@���g�����@�P�Q�Q��
�@���g�����@�R�V��
�@�c�́@�U
�@�v�@�P�U�T
�@�E�����@�j�@�U
�@���@�U
�@�v�P�Q
�_���������
�@���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j�S���P���ɔ��_���Ɨ��������������A�s�����͔��_���ɕ�܂��ꂽ�̂ł��邪�A�NJ�����_�Ƌ����g���̋��͏]���ǂ���ł���A�����ɂ͈꒬��g���Ƃ������ƂƂȂ����B
�@���̎��_�ɂ����āA���_�_���Ɨ����_���̍����͈ꉞ�̉ۑ�Ƃ��Ď��グ��ꂽ���̂́A�����͌���̂܂܂Ƃ������Ƃœ�g���̐����ێ�����Ă����B�������A���̌サ���Ζ��Ƃ��Ē�N����A���ɂS�R�N�ƂS�V�N�ɂ͂��Ȃ��̓I�Ȍv��Ƃ��Ď��グ��ꂽ���A������܂��@���n�������f��ԂƂȂ��Ă����̂ł���B
�@����A�k�_������ɂ����ẮA�Љ�o�Ϗ�̕ϓ��ɂƂ��Ȃ��_�����A���l������g�����̗v�]�ɑΏ�����̐��Â����ڎw���A���a�T�O�N�x����u�_�������V�O���N�v��v�����肵�A�g�꒬����P���h��ڕW�Ƃ��č�����}��Ƃ����@�^����������Ă����B
�@���������A�S���I�ɐi�߂����鍇���@�^��w�i�Ƃ��āA���_�E�������_���̍����́A�Ăђ��_���̏d�_�����̈�Ƃ��Ď��グ���A�T�O�N�Q���ɂ͓��E�k�_������Ȃǂ̎w���@�ւƂƂ��ɁA������荧�k��J�Â��ꂽ�̂ł���B���̌��ʁA�u���_�E�����_���������i�����ψ���v���������ĐϋɓI�ɐ��i���邱�Ƃňӌ��̈�v���݂��B�������āA�T�O�N�S���J�Â̔��_�A�������_���̒ʏ푍��ɂ����āA���ꂼ�ꍇ�����i��}��Ƃ������c���Ȃ��ꂽ�̂ł���B���������āA���N�V���Q�S���ɊJ���ꂽ��P��ψ���ł́A
�P�A���������́A���a�܈�N�O������Ƃ���B
�@�Q�A���̂́A�u���_���_�Ƌ����g���v�Ƃ���B
�@�R�A�������́A�����_�_�����ݒn�ɒu���B
�@�S�A���a�T�O�N�P�Q���ɍ������i���c���݂���B
�@�T�A���a�T�P�N�P���ɍ����\���_����s���B
�@�U�A���_������������o�ĂQ�����{�����F��\������B
�Ƃ�����{���������肵�A����ɁA���T�P�N�P���P�S���ɍ����\���_��̒�����I���A���_���̗Վ�����ɂ����ď��F��҂���ƂȂ����̂ł���B
�@�������A�T�P�N�P���Q�R���ɊJ�Â��ꂽ���_�_���̗Վ�����ł́u�����͎��������ł���A���̐��̐������挈�v�ł���Ƃ��Ĕ��̈ӌ��������A����͕��������B�������ē��[�̌��ʁA�����^���Q�X�W�[�A���Q�U�U�[�ŁA�����ɕK�v�ȑ����̂R���̂Q�ɒB���Ȃ��������߂��̈Ă͔ی��Ƃ���A���͐U��o���ɖ߂��ꂽ�̂ł������B
�������_�Ƌ����g������x���i�ʐ^�P�j

���R���{�Y���Ђ̍���q��
�@��ʂɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ����A���R���Ɩk�C���͒{�Y����ɂ����đ��݂ɖ��ڂȈˑ��J�W�ɂ���B�܂�A���R���Y�̘a���͔N�Ԗ�Q�O�O���������Ɉړ�����A�܂��A������͓��p�펓����P�O�O�O���A���p��Y�q����P�T�O�O�����ڏo����Ă���ɂ������B
�@���������ƒ{�̌𗬂�w�i�Ƃ��Ȃ�����A���R���ł͑�ƒ{���������X�Ɍ����̌X���������A�������A�s�s���̊g��ƍH�Ƃ̏W�ρA�V�����⒆���c�ѓ��H�̊J�ʂȂnj�ʖԂ̐����ɂƂ��Ȃ��A���Ԏ��{�ɂ����ӓy�n�̎擾�Ƃ��̊J�����i�݁A�{�Y�p�n�̊m�ۂ�����������ȏɂȂ��Ă����B
�@���̂悤�ȏ��ŊJ���邽�߉��R���ł́A�������Y�̊�ՂɌb�܂�{�Y�̓K�n�Ƃ����k�C���ɖq��K�n�����߁A���p�����Y�q�ꌚ�ݍ\�z��i�߂Ă������A���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�ɂ��̍\�z�������Ɏ������܂ꂽ�̂ł���B�����Œ��͓��Ɩ��ڂȘA�����Ƃ�Ȃ���A����v���ɂ��ĉ��R���ƍĎO�ɂ킽����𑱂������ʁA����n��i����c�����j���悻�Q�O�O�w�N�^�[���ɂ��̖q�������邱�ƂɂȂ����̂ł���B���̒n��́A���a�����ɂU�O�]�˂����A�����̂ł��邪�A���̌㗣�_�҂����o���ď��a�S�X�N�ɂ͂킸���S�˂��c�������ƂȂ����ߑa�n�тł������B
�@�������āA���a�T�O�N�Ɏ{�݂̋�̓I�Ȍ��v�悪���肳���ƂƂ��ɗp�n�������s���A�T�P�N�x����q�ꌚ�݂��i�߂�ꂽ�̂ł���B
���R���{�Y���Жk�C������q��i�ʐ^�P�j

���R���{�Y���Жk�C������q��i�ʐ^�Q�j

�@���̎��ƌv��ɂ��A�܂��p�n�P�S�P�E�V�w�N�^�[���������������āA���Ǝ�̂ƂȂ�u�Вc�@�l���R���{�Y���Ёv�ɑ݂��t���A
�@�P�A�a���̐��Y�@�ɐB�����i���јa��j�P�T�O������ՂƂ��Ďq�����Y���s���A�琬�܂��͔��̂������n�ŕ���������ق����R�����ֈڏo����B
�@�Q�A�D�Ǔ��p���̈琬�@�k�C���암�n��̌����D�G�ȓ��p���q�����w�����A�펞�U�O�����߂ǂɈ琬�̂������R���ֈڏo����B
�@�R�A���p���f���̈琬�@���p�Y�q���i�������j���w�����ĘZ�������x�M�炵�A�琬��A���f���i�N�Ԉ琬�����W�O�O���j�Ƃ��ĉ��R���ֈڏo����B
�@�S�A�_�ƌ�p�Ҍ��C�@��K�͌o�c���u�����鉪�R�����_�ƌ�p�҂̌��C���s���B
�@�T�A���̑��@�ǎ��Ȋ����̈ڏo�E�k�C���ւ̘a���̋����Ȃǖk�C���Ƃ̘A�g�n�_�Ƃ��Ċ��p����B
�Ȃǂł���A���a�T�P�N�x����̎O���N�ԂŒc�̉c���n�J�����Ƃɂ�葐�n�X�V�w�N�^�[���̑����̂ق��A���ɓ��̊֘A�{�݂����邱�Ƃ��v��Ƃ������I�Ȃ��̂ł������B
���ؔ_��Ƒ����m�_��E���q��
�@�{�ґ�P�͑�R�ߔ_�ꋻ������̍��ŏq�ׂ��v���ĐB�Y�g���_��́A�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�ɊJ�݂���A���̌㉪�c�_���\�����_���\�X�M��������ЂƕϑJ���A���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�ɔ��؊��s�Ɉڂ�A�u���ؔ_��v�Ƃ��Čo�c���i�߂�ꂽ���A�i�N�ɂ킽�鏬�쑈�c�Ȃǎ�X�̋Ȑ܂����������̂́A�Q�T�N�P�Q���܂łɂ͂��ׂĉ������A�R�V�˂̎���_���n�݂��ꂽ�B
�@�X�M��������Ђ��甃���������̓y�n�́A���̑啔�������؊��s�̏��L�ƂȂ����̂ł��邪�A����_�n��͓D�Y�s�т̌��삾�����c�����B�_��唪�͂��̌�����J�����邽�ߓy�n���ǂɐS���𒍂��A����⓹��̓�����}���āA�����r���₲�݂ɂ��q�y�Ƃ��̕t�эH�������{�������Ƃɂ��ẮA��ɂ���G�ꂽ�B
�@���������͑����m�푈�������Ȃ�ł���A������Y�Ƃ����ČR�����Y�ɔ��Ԃ������A�����̐H�ƕs�����܂��Ɍ���Ԃɂ������B����������w�i�ɔ_��唪�́A���̓D�Y�n�̓y�n���ǂ��s���A�哤�E�����E�ꂢ����E���ڂ���Ȃǂ̍�t�����s�����̂ł���B���������̂���́A�J���͂����ꂵ�Ă��鎞���ł�����A�����X�E���E�H�c�Ȃǂ̊e�����珗�q�J���҂��W���A�H�Ƒ��Y�ɓw�߂��̂ł������B
�@����A���������J�����Ƃ��s�������ő��z�̎�����v���邽�߁A���Ԃ��Ȃ��u���ؔ_�Ƌ����g���v��ݗ����A�_�ы��ƒ������ɂ���Z�����Ď��Ƃ�i�߂��B
�@�������A���a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�P�Q���ɔ����a�v�������߁A���Ƃ̐��i�Ɏx��𗈂����ƂƂȂ��Čo�c�͈������A����ɉ����ĂQ�W�A�Q�X�A�R�P�N�Ƒ�����������Q�̉e�����Ď��Ƃ͐i�W�����A�Z�����������̕ԍόv������Ă��Ȃ��ɂȂ����B
�@���̂��ߒ��́A���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�W�@�֒c�̂ƂƂ��Ɂu�R��E�ԉY�n��J���������v��g�D���A�P���ɂ��ċ��c���d�ˁA���⓹�ɓ��������Ă��̑ŊJ����u����ƂƂ��ɁA�u���ؔ_��J�����ψ���v��ݒu���Ċe��̒������s�����B
�@���̊ԁA�R�U�N�ɂ̓J�g���b�N���_�w�Z�̌��݂Ƃ��A���c�ό�������Ђ̔����v��Ȃǂ����܂���肴������A������Z�@�ւȂNJW�҂ɂ�钲�������Ƌ��c���d�˂�ꂽ���ʁA�R�V�N�ɓ��c�ό��������̂����J������Ƃ����v�悪�����ꂽ�B�����Œ��͓��Ђ̗U�v�ɂ��ĐϋɓI�ȉ^���𑱂��A���⓹�c��ɂ������v�������̂ł������B���������̗U�v�^�����A��X�̎���ɂ���Ă��Ɏ������Ȃ������̂ł���B
�@�R�X�N�Ɏ���A�����m�D�D������Ђ����_�ꏊ�L�n�̊T�������A�_�n�擾�̂��߂̖@�l�ł���L����Б����m�_��Ɠ������m�q��i�В��E�H�R�@���j��ݗ��̂����A�q�{�E�q�����Y�̔���ړI�Ƃ��ē��n���i�����m�_��V�P���W�V�X�X�������[�g���A�����m�q��P�X�T�X���W�V�T�V�������[�g���j���A�R��R�V�V�Ԓn�ɖ{�Ђ�u���A�S�O�N�V���ɂ�����ꎮ���s���ĐV�������������̂ł���B
�@����ɂ��A�����̒����N���ɂ킽�錜�Ď����ł��������ؔ_��J�������A�悤�₭���������̂ł������B
��Q�́@�ы�
�@��P�߁@�J��ƐX��
�J��ȑO�̐X��
�@�u�J���ȑO�͖{�����鏈�R�тȂ炴��͂Ȃ��c�c�i�����j�v�i�J��g���ƕ��j�Ƃ���悤�ɁA�k�C���̑啔���͂����������錴�n�тɕ����Ă������Ƃ͖��炩�ł���A�V�y���A����͂��ߗY�g�A�������x�ȂǓn���������c������R����w�ʂƂ��A���Θp�ɖʂ��锪�_�E�����n�����܂��X�ю����̖L�x�Ȓn�тł������B�����L�x�Ȏ������A�J��ȑO�͂킸���ɐ�Z�����̎��Ɨp�ނ�R���Ƃ��ė��p����Ă���ɂ����Ȃ������B����ɁA���O�˂���������悤�ɂȂ��Ă�����A���̒n���ł͈ˑR�Ƃ��Đ�ƓI���݂͂��Ȃ��������A�ꏊ�����l���i�o���Ď���ɘa�l�̉z�~������̂��������A�܂��A����������������ɂȂ�ɂ�Ă܂��̎g�p�������͂��߂����߁A�C�ݕt�߂̎������X�ɔ��̂����X���ɂ��������̂Ǝv����B
���{�����ƐX��
�@���{�����̒n���ɒ����̎{�����y���������P�Q�N�i�P�W�O�O�j�̕��A�V�y����㗬�̐X�ю����ɒ��ڂ����ڈΒn�������p�|�����M�Z���́A���N�����A�ڈΒn�̂��Ƃɂ��đ�������C�ɂ�������N�ԏo�_��ɑ��A���̔��̂ɂ��Ďf�����o���A�Q���P�Q���ɋ��������̂悤�ȋL�^������B
�@�u�ѐ��������A�o�_��a�]�M�Z���i���j�V�B�\����f�V�ʏ����A�䒼�ԏ�B�v
�@�k�\���l���ىڈΒn�j����v���i�X��i���j�f�t
�@�i�O���j���E���b�v���ޖؓ��p�n���o�A�R�r�s�i���j�\�l�S���A�i�����j�f�V�ʔ�i�j�j�n�i��j��i�j�j���m�i��j��B
�@�\����@�����M�Z��
�@�i�ق��O�������j
�@�i�O���j
�@��A���ٕ����O�Ӎޖؔ��o���艓�j���A�������D�ŗ������x��V�������B�ڈΒn���E���b�v���ޖؑ��ꏊ�j�t�A���o���A���ٍ]���u��n�o�A�ΐl�ǂ��~���V�҂��L�i���j�V��ԁA�����R�эr�s�i���j�\�l�|���o���A��ؔ��o���𑊋A���X���o����`��v��n�o�A���فA���O���s���R�V�V�����i���j�V�A�ꏊ�n�����o���i���j�d�ƃj��i���j����B
�@�i�㗪�j
�@�\�\��
�@�����M�Z��
�@�i�ق��O�������j
�@���x�����L�t�^���Z��
�@����ɂ���ē��n���Ŗ{�i�I�Ȕ����s��ꂽ�Ǝv����̂ł��邪�A����Ɋւ��锰�̂̏ꏊ�A���@�A���̗ʂȂǂ�m���|����͑S���c����Ă��Ȃ��B
�@�����P�Q�N�ɖ��{����c�Ǐꏊ�܂ł��Ƃ��A�������A�ڈΒn�ł̘a�l�̋��Z�������悤�ɂȂ�ƁA�l�n�̉���������ɂȂ�A�a�l�̈ڏZ���悤�₭���̐��𑝂��悤�ɂȂ��Ė؍ނ̎��v�����R�ɑ������A�X�т̔��̂�������ɍs����悤�ɂȂ��Ă������̂Ǝv����B
�J���̏�
�@���������̓����ł́A���̗ʂ������Ȃ����Ƃ͂����Ȃ���A���̓I�ɂ͔��X������̂ŁA�����P�P�N�V�y������ɋ������ˎm�����A���������ł́A�Ȃ������т�������A�I�I�J�~�A�q�O�}�Ȃǂ��Ђ�ς�ɏo�v����ł������B�����̗ё����݂�ƁA�V�y���쉈���t�߈�т́A���`�_���E�h���E�J�c���Ȃǂ̋�����іƂ��āA�A�J�_���E�g�`�E�n���m�L�E���i�M�Ȃǂ��ɖ��A�C�ݐ��ɋ߂������ב�n�ɂ́A�J�c���E�i���E�V�i�E�N���E�Z���E�J�V���E�N���~�E�I���R����Ƃ��A�R�Ԓn�߂��ɂȂ�ɂ��������ăg�h�}�c�������A����Ƀi���E���`�_���E�J�G�f�E�u�i�E�g�`�E�z�I�Ȃǂ̍���т��ɖ��Ă����Ɠ`�����Ă���B
�@���̂悤�ȏ��֓��A���A����Ǝ��g�݊J�����Ȃ��Ƃ���Ƃ������Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��A�ڏZ�����l�X���܂����Ɏ�|���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂����ŁA���Ƃɋ��m�������́A����Ȃ���ɂ̂��꒚�A�܂�����꒚�������ė���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�����āA����田�̂����X�́A�ꕔ���Ɨp�ނ�d�Y�p�������āA�����͊J���̎ז����̂Ƃ��ĘA���A��Ă��̂Ă�ꂽ�Ƃ����B
���������̑���
�@���̒n���ł͂܂��܂��{�i�I�Ƃ�����ł͂Ȃ������Ƃ��Ă��A����Ɋe�n�ŊJ�i�߂��A�k�n���g�傷��ɂ�ĎR�n�̍r�p�������Ɍ�����悤�ɂȂ������߁A�R�ьo�c�̕��@�ɂ��Ď{�u������悤�ɂȂ����B���Ȃ킿�A�����T�N�i�P�W�V�Q�j�V���ɔ��َx���ł́A�e���ɂ�����Ɖ����z�p�ނ�d�Y�ށA����ɁA�������ꂼ�ꖳ���Ŕ��̂�����A���̋��O�ɒ����҂����t��������邱�Ƃ��֎~���A���U�N�R���ɂ́u�R�щ��K���v��z�B���ĐA�������シ��ȂǁA�ϋɓI�Ȏ{�u�����������B����ɁA�P�P�N�P�O���ɂ́u�����؎d�t���v�َx���Ǔ��ɕz�B���A�A�t���̂P�������̎����Ƃ��A�X����l���ɕt�^����K���݂��A�L�u�҂Ɋ��L�R��̎ؒn�A�������シ��Ȃǂ̕�����u�����B
�@���̏��Ɋ�Â��ĎR�z�����i�R�ǁj�̖������q�́A�����P�T�N���R�ɃX�M�T�O�O�O�{�A�q�m�L�R�P�O�O�{�̑��т��o�肵�A���ĐA�͂��͂��߂��B�������A�v�攼�ɂ��Ď����q���a�v�������ߖړI���ʂ������A�����Ԓn�����Ƃ������Ⴊ���邪�A���ꂪ�L�^�ł݂��铖�n���ɂ�����R�ѐA�͂̏��߂ł��낤�B
�@�܂��A����ƊJ��������ł͓��A���X�̖����P�R�N�A���d���Ǝ�����Ƀi�V�E�����S�E�u�h�E�E�E���Ȃǂ̂ق��X�M�E�q�m�L�Ȃǂ̕c�Q�O�T�O�{�̕����������o�肵�A���P�S�N�ɂ��̕����������ĈڏZ���ɐA���������̂��͂��߁A�A�N����{�̕c���ړ����ĐA�͂����B�����́A�����ǍD�ɐ��炵�Ă����Ƃ������A���n�т̂܂c����Ă����C�ݐ��̖h���т����̂���Ă���A�������܂ދ����ɍЂ����ꎟ��Ɍ͂�Ă��܂��A���a�̏��߂���ɂ͂��Ƀ����S���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����B
�@���̂ق��A�{�\����̂��߂̌K�c�͔̍|���s�����B�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j����A�J���n���������i���A�����×{�����_�a�@�n���j�ɉ��~�ѓI�Ȃ���J���}�c��A���t�������A�����͔��_�n���ɂ�����J���}�c�A�͂̏��߂ƌ����Ă�����̂ŁA��N���̂�Ƃꂽ���̂��������ɂ����ẮA�݂��Ƃȑ�ɐ������Ă����B
�@�����R�R�N�ɂ͋v���Ĕ_������L���u�C�^�E�V�i�C�i���A�ԉY�j����h�̑��i���A����j�ɂ����āA�J���}�c�̌����o�肵�A�R�T�N�ɐ��c�R�W�O�O�{�������R�U�O�O���[�g�����܂�ɐA���t�������A���ʂ͗ǂ��Ȃ������Ƃ������������B
����ƊJ��������A���юY�ꗗ�\�@�i����_�ꎑ���j
| �@�@�N�� ��� |
�����P�Q | �P�R | �P�S | �P�T | �P�U | �P�V | �P�W | �P�X | �Q�O |
| �ʁ@�@�� | �{ �T�S�O |
�{ �P�C�R�R�U |
�{ �Q�C�W�V�V |
�{ �W�C�R�O�Q |
�{ �W�C�T�O�Q |
�{ �P�O�C�S�U�O |
�{ �Q�C�W�P�T |
�{ �Q�C�W�P�T |
�{ �Q�C�W�P�T |
| �K�@�@�c | �R�C�R�O�O | �S�C�R�R�O | �P�U�C�R�O�U | �P�U�C�R�O�U | �P�U�C�R�O�U | �P�U�C�R�O�U | �U�C�R�R�P | �U�C�R�R�P | �U�C�R�R�P |
| �с@�@�� | �Q�C�O�W�O | �Q�C�R�W�O | �R�C�S�U�O | �S�C�Q�R�O | �S�C�Q�R�O | �P�P�C�S�X�U | �P�C�X�Q�T | �P�C�X�Q�T | �P�C�X�Q�T |
| �݂܂� | �| | �P�C�T�P�R | �T�Q�O | �T�Q�O | �T�Q�O | �T�Q�O | �R�R�O | �R�R�O | �R�R�O |
| �� �� �� | �| | �Q�C�X�O�O | �P�C�Q�O�O | �P�C�Q�O�O | �P�C�Q�O�O | �P�C�Q�O�O | �| | �| | �| |
| �@�@�� | �| | �W�T�O�O�O�O | �P�C�U�W�X�P�P�O | �X�O�S�T�P�U | �T�X�T�U�U�W | �X�O�O�O�O�O | �R�T�T�O�O�O | �S�O�O�O�O�O | �P�C�O�U�S�O�O�O |
| �܁@�@�� | �~ �P�V�O�D�O |
�S�R�T�D�O | �T�V�U�D�O | �T�X�U�D�T | �T�X�S�D�T | �V�S�O�D�O | �U�T�O�D�O | �V�V�U�D�O | �T�S�T�D�O |
�@�����w�Z�o�c�̌o��˂�o�͊e���Ƃ����ɋꗶ���Ă����B���̂��ߊw�Z�^�c�̈�����͂��邽�ߖ����P�V�N�i�P�W�W�S�j�ɔ��_���w�Z�ł́A������ƍ�������̒��Ԃ̓y�n�S�U���]���w�Z�тƂ��Ė��������������A���ؐA�͂̌v��𗧂Ăĕی�Ǘ��ɓ������Ă����̂ł��邪�A�R�P�N���̗����Z�ɐV�z�̎ؓ����ԍς̍����ɂ��邽�ߔ���n���A���̂��Ƒ��L����n�ɓ]�p���ĊJ���������߁A�N�Ƃ���ɂ͎���Ȃ��������A�����������Ƃ��炱�̒n����u�w�сv�Ə̂���悤�ɂȂ����B�R�T�N�T���Z�ɂ̐����ɖh���тƂ��ăg�h�}�c�P�W�O�{�̂ق��A�J���}�c�E�T�N���E�E���ȂǂT�Q�O�{��A���t���A�܂��A�S�O�N�ɂ͗V�y�����L�n�ɁA�X�M�E�J���}�c��P�O�O�O�{�������̎�ɂ���ĐA�͂��Ă��邪�A�����͊w�Z�ɂ�����A���Ƃ��Ă͌Â�����ł��낤�B
�@�����S�S�N���{�a���䗈���L�O���ƂƂ��āA��O���L�n�i���A�M�c�j�ɃX�M�X�O�O�O�{��A�͂��A�܂��A���_�E��ցE��O�̊e���w�Z�ɃA�J�}�c�E�J���}�c�E�N���}�c�Ȃǂ̕c����t���čZ����ɋL�O�A�������������A�����̂����A�X�M�E�A�J�}�c�͐��炪�s�ǂŁA��O���L�n�̃X�M�͑吳�S�N�ɃJ���}�c�ƐA���ւ������B
�吳�N�ォ��I����̑���
�@�吳����ɓ���Ɩ��Ԃɂ����Ă��Q���A�т��s����悤�ɂȂ��Ă������A�U�N�i�P�X�P�V�j�R���ɓ����ł́u���c�⏕�K���v��݂��ĕ⏕����t�̓����J���A�A�������シ��{����u���Ă����B�������A��ꎟ���E���̍D���̔g�ɏ���āA�R�т͋}���ɍk�n�������X�����݂�ꂽ�̂ɔ����A�吳�X�N�ɂ͐��E�I�Ȍo�ϋ��Q�ɂ��_�Ƃ̓]�o�ȂǂŁA��C�ɍr�p�n�����o���A�����ɂ����Ă����̖ʐς����Z�Z�����ɋy�ԏł������B���̂��ߓ����ɂ����ẮA���N�u�r�p�n���ѕ⏕�K���v��݂��A�r�p�n��c�n�꒬���ȏ�̑��сA�V�R���ђn�ܒ����ȏ�̑��тɑ��đ����̕⏕������t���邱�ƂƂ����B���̌��ʁA�V�R���т̂ق��A�k������̔��n�ɐA��������̂��������A�J���}�c�E�X�M�Ȃǂɂ��Ή����i�߂�ꂽ�B�������A�����̖��ԑ��т́A��Ƃ��ăJ���}�c���啔���ŁA�{�����L�̎����A�͂�����̂����Ȃ��������߁A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�ȍ~�A�����ł́u���c������t�v�Ɓu������A���ѕ⏕�v�����{���A�G�]�}�c�E�g�h�}�c�E�N���~�E���`�_���E�i���E���}�i���V�E�z�E�E�h���E�C�^���Ȃǂ̂����ꔽ���ȏ�i���a�P�O�N�ȍ~�꒬���ȏ�j�̑��юҁA���ɔ_�Ƃɑ��ĕc����t����ƂƂ��ɁA���є�A�h�ΐ��ݒu��̕⏕���s�����ƂƂ����̂ŁA���т�����̂��N�X�������A���a�P�U�N�ɂ͂R�R���U�O�O�O�{�̌�t���A�傢�Ɍ��ʂ��グ���B
�@���������ϋɓI�ȕ⏕����ɂ��A���L�т̑��шӗ~����������A���̎��т��グ�������̂ł��邪�A���a�P�U�N�ɑ����m�푈���ڂ�������ƁA���ڌR�����ނ��͂��߂Ƃ��āA�܂�����̑��R���Y�Ɗ֘A�̖؍ގ��v�͋}�����A�����̎��ނ��������邽�ߗ������������A�R�т͍r�p�̈�r�����ǂ�A���т̌��ʂ͑S�����炢�ł��܂����B
���̑���
�@���_�n���v�ɂ��ً}�J��n�Ƃ��āA�J���}�c�E�X�M�E�g�h�}�c�Ȃǂ̐l�H���ђn��V�R�і�ȂLjꔪ�l�������i���_���j�̖��L�n����������A����ɁA�R�я��L�҂����̏��L�𐧌�����邱�Ƃ�����āA���������A�т����ђn�p���悤�Ƃ���X��������A���̂��߁A�ꎞ�I�ɑ��т������Ƃ�����������Ȃ��Ȃ������B���̂����A���̕����p���ޓ��̎��v���܂��܂����傷�邱�Ƃɉ����邽�߁A���L�тɂ����Ė��v��Ȕ��̂��������A�������A���̐Ւn�̑��т͂قƂ�Ǎs��ꂸ�A���і��ϒn�͑����������ł������B���̂��߁A���鏊�Ő��Q��R���ꂪ��������댯�ȏ�ԂƂȂ�A���y�ۑS�̂���������J�����ׂ����ƂȂ����̂ł���B
�@�������A���a�Q�T�N���납��͐�������É����A�o�ώ�����悤�₭�D�]����悤�ɂȂ�ƁA�R�ю����̏d�v�����F������A�Q�T�N�P���ɂ́u���y�Ή����i�ψ���v���ݒu�����ȂǁA���y�Ή��̂��ߌv��I�ȑ��т����{�����悤�ɂȂ����B���ɂ��̔N�u���їՎ��[�u�@�v�̌��z�ƁA�J��ƗыƂ̒�����}�邽�߂́u�k�C���ً}���я�����v����сu���{�s�K���v�̐���́A���L�т̑��я���Ɉ�i�ƌ��ʂ����A�J���}�c�E�X�M�Ȃǂ̐A�͂ɂ���ĎR�n�̗Βn�����}���A���a�Q�W�N����ɂ͐�O�����̂��܂łɂȂ����B
�@�Ȃ��A���a�R�Q�N�������������̖��L�т͓O���O�����ł������B
�@��Q�߁@���L�тƖ��L��
���L�т̐���
�@�������ɂ����ẮA�����R�R�N�i�P�X�O�O�j�V���ɍ��L���J�n���������A����ɋ㒬���]���擾�����L�^������A���_�����͑����ȑO���瑺�L�тƂ��Ă̎擾�Ǘ����s���Ă������Ƃ������Ă���B
�@�����ĂR�T�N�Q���A�������{�s�ɂ�鍇���O�̎R�z�������A���̌v������A���V��R�i�R�z�j�ɓ�Z�����]�̍��L�n������B���̍��L�n�͋}�X�Βn�������������߁A���炭���������܂܂ł��������A�P�ǂȂ���Y�Ǘ��Ƃ�����|����A�����S�R�N����ɍ���A�������邱�ƂƂ��A���ىc�ы提����A�J�}�c�Q���T�O�O�O�{�̖������t���ĐA�������̂��͂��߁A���̌���lj��A���𑱂����B���ꂪ���L�сi�R�n�j�̐l�H�A���̏��߂Ƃ����A���̓y�n�͑吳�V�N�i�P�X�P�W�j�T���ɍ��L���J�n�����@�ɂ���Ė������t���Ă���B
�@�吳�P�P�N�P�P�����������ɂ���āA�����̌o�c�Ɍ���p�n���������̓����J���ꂽ���ƂɑΉ����āA���͓��N�P�Q���ɋ������q�n�����o��̋c�����Đ\�����A�P�R�N�ɎR��c�n��Z�Z�������܂�̍��L���J�n�̔��蕥�������̂��͂��߁A���P�S�N�ɂ͔����i���A�㔪�_�j�c�n�Z�㒬���]�Ə㉔��i���A����j�c�n���������]�̎w�蔄�蕥�������B�������A�����͎����㋤�����q�n�Ƃ��Ă̌��p���ʂ������A���͎�Ƃ��Đ��Y�p���Ƃ��ď������ꂽ�B����ɁA���a�U�N�i�P�X�R�P�j�ɂ��������������q�n�Ƃ��āA��ցi���A�㔪�_�j�c�n��Z�����]�̔��蕥���������A�����̂��ׂĂ͂Q�P�N�ɖړI��ύX���āu�����d�Y�сv�Ƃ��ĊǗ�����邱�ƂɂȂ����B
�@����狤�����q�n�������d�Y�т̑啔���̓J�o����Ƃ��A���̓u�i�E�C�^���E�~�Y�L�Ȃǂ̓тŁA�ё��͂���߂ĕn��ł��������A�����͂���炪���L�т̎厲�ƂȂ�A���a�P�R�N�ɓ�����B���̎w���̂��ƂɕҐ����ꂽ�u���L�ю{�ƈāv�̒��ɑg�ݍ��܂�A���Ƃ��i�߂����������A��ǂ��}��������i�K�ƂȂ��Ď{�Ƃ͌v��ǂ���i�܂��A�₪�ďI��ƂȂ����̂ł���B
���̒��L��
�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j����X�ю{�ƌv������āA���Q�U�N���V��R�ƎR��̗��c�n�ɃX�M�̑��т��s�����̂��͂��߂Ƃ��āA���L�т̈琬�ɒ��肵���B����ɂQ�X�N�ɂ́A���E���w�Z�������k�Ɉ��юv�z�y���A�����Ă��̎��v�������Ċw�Z�c�U��Ȃǂɏ[�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u�w�Z�ё����Ǘ����v���߁A���_���w�Z�ق��X�Z�ɓ�\�����]�̊w�Z�т�ݒ肵���B
�@�������A����̐i�W�ɂ�Ċw�Z���Ƃ̊Ǘ��͕s�\�ł��邱�ƂƁA�w�Z�c�U��͐̂ƈ���ē��R�������S�̂̒��ōl�����ׂ��ł���A�w�Z�тƂ��ē���w�Z�ɏ��������߂闝�R���Ȃ��Ƃ��������A���a�S�V�N�P�Q���ɓ�����p�~���A�����̂��ׂĂ���ʒ��L�x�ɕғ����A��̉������{�ƌv��̒��ň�т��}���Ă���B
���Ȃ݂ɁA�w�Z�єp�~���ɂ͂P�S�Z�łS�R�E�Q�U�w�N�^�[���ł������B
�@���a�R�Q�N�S�����������ɂ���ė������L�т�����ɕ�܂��A���L�ʐς��g�傳�ꂽ���A���̎��_�ɂ����Ă͋����_���̑��ђn�ɓ��Ɍ���ׂ����̂��Ȃ��A����т̂قƂ�ǂ��������L�тɌ���ꂽ�Ƃ������Ƃ��琄�@���Ă��A�������ł͑����ȑO����l�H���тɈӂ�p���Ă������Ƃ��킩��B
��P�\�@���L�т̌���i���a�S�X�N���݁j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁ@ha�j
| �@�敪 ��� |
�ʁ@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� | ||
| �l�@�H�@�� | �V�@�R�@�� | �����ؒn | ||
| ���@�ʁ@�� | �T�Q�R�D�O�S | �Q�X�P�D�R�Q | �Q�Q�Q�D�W�O | �W�D�X�Q |
| ���@���@�� | �i�X�O�D�X�U�j | �i�V�T�D�S�W�j | �i�P�T�D�S�W�j | �S�Q�D�T�U |
| �S�R�O�D�W�W | �P�S�Q�D�U�O | �Q�S�T�D�V�Q | ||
| ���@�@�@�v | �i�X�O�D�X�U�j | �i�V�T�D�S�W�j | �i�P�T�D�S�W�j | �T�P�D�S�W |
| �X�T�R�D�X�Q | �S�R�R�D�X�Q | �S�U�W�D�T�Q | ||
���i�@�j���͐X�ъJ�����c�ɂ�镪�����ђn
�@���̌㒬�L�т̑������Ƃ��悤�₭�O���ɏ��A�R�X�N�ɉ���ҁi���A��̓��j�̊J�_�Ւn�R�V�w�N�^�[���]���A�܂��A�S�O�N�ɊJ�_�Ւn��������V�c�n�̂X�O�w�N�^�[���]�ɂ��ẮA���ɐX�ъJ�����c�ƕ������ь_���������A�������щ\�n�W�P�w�N�^�[���]�ɂ̓g�h�}�c�𑁊��ɐA�т���ȂǍ��Y�����ɗ͂𒍂����B
��P�\�@���������̎R�т���ь���̏��L��
| �@�@�K�͕� �敪 |
�P�� �`�R�D�O |
�R�D�O �`�T�D�O |
�T�D�O �`�P�� |
�P�D�O�� �`�P�D�T |
�P�D�T �`�Q�D�O |
�Q�D�O �`�R�D�O |
�R�D�O �`�T�D�O |
�T�D�O �`�P�O�D�O |
�P�O�D�O �`�Q�O�D�O |
�Q�O�D�O �@�@�@�ȏ� |
�v | |
| �R�� | ���ѐ� | �P�X | �P�T | �S�P | �T�S | �U�V | �T�X | �W�X | �P�U�S | �P�O�P | �P�T�S | �V�U�R |
| �ʁ@�� | �S�Q | �T�X | �Q�V�V | �P�C�R�S�T | �P�C�T�U�X | �Q�C�O�P�V | �Q�C�T�S�Q | �P�Q�C�T�Q�V | �P�U�C�Q�P�T | �P�X�T�C�T�R�V | �Q�R�Q�C�P�R�O | |
| ���� | ���ѐ� | �P�T�W | �P�O�S | �W�U | �S�V | �T�R | �P�O�O | �Q�W�V | �S�R�V | �P�V | �T | �P�C�Q�X�S |
| �ʁ@�� | �R�R�P | �R�P�Q | �V�V�S | �S�T�U | �T�V�S | �Q�C�P�V�O | �P�V�C�Q�Q�O | �R�U�C�R�O�P | �Q�C�Q�P�O | �U�C�T�O�O | �U�U�C�W�S�W | |
��Q�\�@��L�ꌓ�ʐ��ѐ�
| �@�@���� ���� |
��� | ���팓�� | ���팓�� | �v | ||||||
| ��ꎟ �Y�@�� |
��� �Y�@�� |
��O�� �Y�@�� |
���@�v | ��ꎟ �Y�@�� |
��� �Y�@�� |
��O�� �Y�@�� |
���@�@�v | |||
| ���ѐ� | �O | �@ | �@ | �R | �R | �V�R�V | �@ | �Q�R | �V�U�O | �V�U�R |
| ��@�� | �O | �@ | �@ | �O�D�S�� | �O�D�S | �X�U�D�T�X | �@ | �R�D�O�P | �X�X�D�U�O | �P�O�O�� |
��R�\�@���L�ʁE����ʗі�ʐς���ђ~�ϗ�
| �@���L�� ����� |
���@�@�L�@�@�� | �s �� �� �L �� | ���@���@�L�@�� | ���@�@�L�@�@�� | ���@�@�@�@�@�v | |||||
| �ʁ@�� �i���j |
�~�@�ρ@�� �i�j |
�ʐ� | �~�@�ρ@�� | �ʐ� | �~�@�ρ@�� | �ʁ@�� | �~�@�ρ@�� | �ʁ@�@�� | �~�@�@�ρ@�@�� | |
| �Ƃǂ܂� | �S�O�T | �Q�C�S�X�P | �P�P�P | �V�X�T | �T | �Q�C�Q�T�V | �V�R�O | �R�T�C�S�U�W | �P�C�Q�T�P | �S�P�C�O�P�P |
| ����܂� | �S�S�O | �R�X�O | �V�T | �W�C�O�S�U | �P�X | �X | �P�C�T�W�S | �Q�O�O�C�U�O�Q | �Q�C�P�P�W | �Q�O�X�C�O�S�V |
| ���@�@�� | �@ | �@ | �V�U | �P�C�Q�S�T | �S�U | �R�U | �T�V�Q | �U�C�R�Q�P | �U�X�S | �V�C�U�O�Q |
| �� �� �� | �Q�C�P�P�Q | �W�C�X�X�O | �@ | �@ | �@ | �@ | �V�S | �R | �Q�C�P�W�U | �W�C�X�X�R |
| �Ђ̂��� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �Q�S | �W�C�O�P�R | �Q�S | �W�C�O�P�R |
| �V�@�@�R �L �t �� |
�Q�W�C�T�P�O | �S�C�W�O�X�C�X�U�O | �T�T�T | �U�T�C�U�S�O | �W�O�T | �X�S�C�S�W�O | �P�X�C�R�T�S | �Q�C�P�Q�X�C�O�O�O | �S�X�C�Q�Q�S | �V�C�O�X�X�C�O�W�O |
| �� �� �� | �Q�C�Q�R�P | �W�V�T | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �Q�C�Q�R�P | �W�V�T |
| �v | �R�R�C�U�X�W | �S�C�W�Q�Q�C�V�O�U | �W�P�V | �V�T�C�V�Q�U | �W�V�T | �X�U�C�V�W�Q | �Q�Q�C�R�R�W | �Q�C�R�V�X�C�S�O�V | �T�V�C�V�Q�W | �V�C�R�V�S�C�U�Q�P |
�@���a�S�X�N�x�����̐X�ю{�ƌv�揑�ɂ��ƁA���L�т̑��ʐς��X�T�R�E�X�Q�w�N�^�[���ŁA�������ʗтT�Q�R�E�O�S�w�N�^�[���A�����тS�R�O�E�W�W�w�N�^�[���ƂȂ��Ă���A����̐��炪���҂���Ă���B�Ȃ��A���L�т̌����͑O�y�[�W�̕\�̂Ƃ���ł���B
�@�܂��A���a�R�Q�N�S���������ƍ������_�ɂ�����R�т̏͑O�y�[�W�ȉ��̕\�̂Ƃ���ł���B
����_��ƎR��
�@�����P�P�N�ɓ���c�����A�m�����Y�̖ړI�������ĊJ��g�ɗV�y������P�T�O���̖��㉿�����n�����肢�o�A���ē���ƊJ���������n�݂����B�����ĈڏZ�l���W�̂����J�����Ƃɒ��肵�A���N�ی�w�������������ʁA���ˎm���悤�₭����_�Ƃ��ēƗ��ł���悤�ɂȂ�A����_��W�̐����n�ς́A�����S�R�N�܂łɔ��E�q��E�R�сE���H�~�n�����킹�ē�Z�O�ܔ��l���l���ɒB�����B���̂������O���㔽�l����O�����ڏZ�l�ɕ������n���ꂽ�̂ŁA�c���n�ς͈ꎵ�Z�����ܔ��㐤�����ƂȂ�A���n�͐�珬��l�ɂ���čk�삳�ꂽ�B
��P�\�@���сE���̂̏�
| �@�@��@�� ����� |
���@�с@�ʁ@�� | ���@�@�́@�@�ʁ@�@�ρ@�@���@�@��@�@�с@�@�@�@���@�@ | |||||||||
| �p �� �� | �v | �p�@�@�ށ@�@�� | �d�@�@�Y�@�@�� | �v | |||||||
| �l�H���� | �V�R�� | �l�H���� | �V�R�� | �ʐ� | �@�@�@�� | �ʐ� | �@�@�@�� | �ʁ@�� | �@�@�@�� | ||
| �j�t�� | ����܂� | �� �Q�C�U�X�O |
�| | �� �Q�C�U�X�O |
�| | �� �@ |
�@ | �� �@ |
�@ | �@ | �@ |
| ���@�@�� | �Q�R�U | �| | �Q�R�U | �| | �P | �P�O�O | �@ | �@ | �P | �P�O�O | |
| �Ƃǂ܂� | �R�C�R�P�W | �| | �R�C�R�P�W | �| | �P�R | �P�C�O�O�O | �@ | �@ | �P�R | �P�C�O�O�O | |
| ���@�@�v | �U�C�Q�S�S | �| | �U�C�Q�S�S | �| | �P�S | �P�C�P�O�O | �@ | �@ | �P�S | �P�C�P�O�O | |
| �L�t�� | �₿���� | �P�O | �| | �P�O | �| | �L �V�R�W |
�T�O�C�X�O�O | �L �R�X�V |
�W�W�C�V�T�S | �P�C�P�R�T | �P�R�X�C�U�T�S |
| ���@�@�v | �P�O | �| | �P�O | �| | �V�R�W | �T�O�C�X�O�O | �R�X�V | �W�W�C�V�T�S | �P�C�P�R�T | �P�R�X�C�U�T�S | |
| ���@�@�v | �U�C�Q�T�S | �| | �U�C�Q�T�S | �| | �V�T�Q | �T�Q�C�O�O�O | �R�X�V | �W�W�C�V�T�S | �P�C�P�S�X | �P�S�O�C�V�T�S | |
���i�V�����v�揑�ɂ��j
�@�J���A�J���n�ɂ����Ċe��̗і�A���������Ƃɂ��ẮA��P�߂ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�����Q�P�N�i�P�W�W�W�j���Ɋ肢�o�đ��{�\���̕����������A�A�т��J�n�����̂��_��ɂ�����R�ю��Ƃ̂͂��܂�ł���B���_��̎R�т͑�쑺������i���A���_�ƍ��Z�O�g�n�j�ƕ����̗������ɖ���Z�����A���ׂĐl�H���тŁA�J���}�c�E�}�c�E�X�M�E�q�m�L�Ȃǂ�A���A�����̐���ƂƂ��ɖ؍ނ̔��̗ʂ��N�X�������A���ɑ吳�R�N�ȍ~�͉��B���̉e���ɂ��؍މ��i�̍����ɂ���čD����悵���B�����������Ƃ��h���ɂȂ��āA�吳�U�N���_�ɂ����Ă�����n�����A�{�i�I�ȎR�ьo�c�ɒ��肷��悤�ɂȂ������̂Ǝv����B�������ȑO�ɂ����Ă��A�_����̋}�X�Βn�⍻�ꂫ�n�Ȃǂōk��ɓK���Ȃ��y�n�ɃJ���}�c�Ƃ��X�M���A�����Ă������A���̖ʐς͔�r�I���Ȃ������B
�@�吳�U�N�Ɏ��V�y���i���A����j�ɂ����ĕ���K�O�Y�ق��U�����猴���Z�Z�l���㐤�������A�܂��A���V�N�ɂ͓��n�̐ڑ��n�ɂ����Đ_�J�M���Y�ق��P�����猴�����l���㔽�l�������A����ɂX�N�ɂ͎��������ɂ����Ĉɓ������Y�Ɛ���Ǐ�����ܓꐤ�Z���������̂��͂��߂Ƃ��A�P�O�N�ɂ͉F�V�y���ƃg�����x�c�ɂ����đ�֔_���Z�l�㔽�ꐤ���A���c�_�ꎵ�Z�Z�������Z�������̂ق����������ɂ����ē��l��������O�������A�P�R�N�ɂ͖�c����̏㗬���K���[�i���A����j�ɂ����ĕ����`������R�јZ��l���Z���㐤�Z��������ȂǁA�R�ю��Ƃ��������邽�ߖ��L�n�����A�V�R�X�V�ɂ�鑢�т��v�悳�ꂽ�B
�@�������Ĕ��������_����̖��J�n��r��n�ɑ��т��s���A���a�U�N�i�P�X�R�P�j�ɂ͎R�іʐς����l�l���㔽�l�������ɑ��債�A�_��o�c�̏d�_�͎���ɎR�ю��ƂɏW������Ă������B�@
�@�R�ю��������債�͂��߂��̂͑吳�S�N���납��ŁA�S�_������̃E�G�C�g�ł͑吳�S�N�P�S�p�[�Z���g�A�T�N�Q�W�p�[�Z���g�Ƒ������A�W�N�S�V�p�[�Z���g�A�s�[�N���ɂ͂P�Q�N�̂U�Q�p�[�Z���g�ɂ��B�����B�������_��������˂ɑ����������Ă���ɂ�������炸�A����̎�v�Ȏ������ł��鏬�엿�́A�吳�Q�N���珺�a�V�N�܂ŗ\�Z�����������Ƃ��S�x���Ȃ������Ƃ������A������݂Ă��R�ю����̉ʂ����������͑傫���B����グ�̓�����݂�ƁA�吳�V�N����P�R�N�܂ł͒Y�ނ̃E�G�C�g�������A�؍ޔ��p��̂S�V�p�[�Z���g����X�X�p�[�Z���g���߂Ă����Ƃ����B�吳�P�S�N���珺�a�T�N�܂ł͂܂��ނ�c���オ��̂��Ȃ��Ă����B���ɒ��ڂ��ׂ����Ƃ́A�吳�V�N���납��l�H�эނƎv����J���}�c�E�X�M�E�q�m�L�E�N���}�c�Ȃǂ����̂̒��S�ƂȂ��Ă����B�����̗юY�����͕ʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A����炪�A�ǂ̂悤�ɂ��āA�ǂ��ɔ̔����ꂽ���͖��炩�ł͂Ȃ����̂́A�R�ьo�c���{�i�����Ă������Ƃ������Ă���B�i�u�k�C���_�ь����v��O�㍆�����j
�@�Ȃ��R�ю��Ƃ̖{�i�I�Ȍo�c�ɂ���āA�c���̖ʐς��吳�S�N�ɂ͎O�����ł��������̂��A�V�N�ɂ͎������Ɋg�傳��A�J���}�c��X�M�̂ق��Ƀj�Z�A�J�V���E�N���}�c�Ȃǂ��琬����A�c�̎������s���ق��c��͊�]�҂ɔ��p���ꂽ�B
�@�吳�P�Q�N�X���֓���k�Ђ̔����ɂƂ��Ȃ��؍މ��i���}�������B�����������Ƃ����哿��`�e�́A�R�ю��Ƃ��L�]�ł��邱�Ƃ��d�����A�����R�шȊO�ɐV���ɑ��_��̍r�p�n�����A���_�R�т���і�c���R�т�n�݂����B�����đ吳�P�P�N�ȗ��������K����݂��A����l�ɏ��サ�Ĕ_����̖��J�̌����r��n�ɐA�т������̂ŁA�R�іʐς͔���I�ɑ��債���B�܂��A�c���̖ʐς��R�ъg���ƐA���M�̍��܂�ɂ���Ď���Ɋg�傳�ꂽ�B���ɑ吳�P�S�N�ɂ́A����܂Ŕ��_�n���B��̕c���o�c�҂ł��������_�_���̉�����@�Ƃ��āA�ꋓ�Ɉ꒬�ܔ����Ɋg�債���B
����_��юY��������
| �i�@�@�@�� | �吳�V�N | �W�@�@�N | �P�O�@�N | �P�Q�@�N | ||
| �ۑ��i�{�j | �� | �Q�C�T�W�T | �T�C�V�P�Q | �U�C�S�X�P | �P�V�W | |
| ���@�t�@�� | �X�C�W�S�V | �P�T�C�W�W�U | �T�C�O�U�O | �S�C�T�S�V | ||
| �� | �S�V�X | �Q�C�R�T�P | �Q�C�V�X�Q | �X�X�O | ||
| �O | �P�R�O | �Q�P�Q | �Q�R | �Q | ||
| 舁@�t�@�� | �Q�T�W | �P�R�P | �S | �Q | ||
| ������ | 舗t���p�� | �� �T�Q�S |
�� �P�S�C�Q�X�U |
�� �U�X�S |
�� �V�X�O |
|
| �d | �V�L �P�C�T�P�W |
�U�T�S | �S�C�U�W�O | �T�W�V | ||
| �}�y�юĖ� | �� �T�C�T�Q�V |
�R�C�P�X�Q | �X�U�S | �Q�C�S�Q�T | ||
| �@�@�@�Y | �U �Q�X�C�S�P�V |
�P�S�C�S�X�O | �P�W�C�O�O�O | �Q�S�C�O�O�O | ||
| �c�� | �J���}�c | �{ �T�R�P�C�Q�O�O |
�S�V�T�C�O�O�O | �| | �| | |
| �X�@�@�M | �{ �T�O�C�O�O�O |
�| | �| | |||
(�����@����_�ꓝ�v�ꗗ)
�@�Ȃ��A�R�іʐς̑���ɂƂ��Ȃ��A�����I�Ȍo�c���j���m�����邽�߁A���a�Q�N�V���ɓ���ѐ��j�������Ζ��̗ъw�m�Ɠ��勳���������A���̎w���ē̉��ɑ��_��R�ю{�ƈĂ��쐬�����B�܂��A���N�P�P���ɂ͑哇����_�꒷�̖��ɂ��A�R�ьW�|���M�ׂ��M�B�ؑ]�n���̗ыƎ��@�ɔh������A����ɏ��a�U�N�U���ɂ́A�k�勳���ɂ���Ĕ��_�Ɩ�c���̎R�ю��@�������s��ꂽ�B
�@���̎���ɂ�����_��̗юY���̔����ʂ͕ʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A���a�N��ɓ���Ɣ̔����ʂ͈�ʂɌ����X�����������A����́A�֓���k�Ќ�̕������ނƂ��āA�؍ނ̎��v���}���ɍ��܂�A���i�̍����ɂ���Ĕ��_����і�c���R�т̐����������̂���Ďc�����Ȃ��Ȃ�A���̌��ʁA�p�ނ�d�Y�ނ̐��Y�������������ƂƁA����ɉ����ď��a���Q����ƌĂ��o�ϊE�̕s�������������߂ł���B
�@�������A�R�ю��Ƃ��̂��͍̂����ƂȂ�A����n�o�c�����͂邩�ɗL���Ȃ��̂ł��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ������B
�@�����������Ƃ��瓿��_��ł́A���a�W�N�ȍ~�A�o�c�̏d�_���R�ю��ƂɏW�����邱�ƂƂ��A����n�o�c�ɂ��ẮA����܂ł̕ی��`��p���đQ��������A����l�̎���_����}�邱�ƂɊ�{���j�����߂��B
����_��юY���̔������@�@�i��P�R�`���T�j
| �@�@�N�� �i�� |
�吳�P�R�N | �P�S | �P�T | ���a�Q�N | �R | �T |
| ���@�t�@���i�{�j | �S�C�X�X�V | �V�C�S�P�Q | �S�C�P�R�Q | �S�C�O�O�T | �S�C�R�X�W | �T�C�O�Q�X |
| �� | �P�P | �P�W�R | �X�R | �| | �| | �| |
| �� | �S�C�O�X�R | �Q�C�S�V�T | �P�C�T�O�V | �P�C�Q�W�O | �S�C�V�P�R | �U�C�T�S�T |
| �O | �P�X | �T�U | �U�R | �T�V | �| | �P�O�O |
| 舁@�t�@�� | �| | �U�V | �P�O | �T�O�Q | �U�Q�X | �Q |
| ���@�p�@�ށi�j | �Q�P�W | �R�O�U | �S�U | �V�W | �P�X | �X�O |
| �d�@�@�i�~�j | �Q�V�U | �V�O�R | �W�O�P | �U�V�R | �U�Q�X | �S�S�T |
| �} �y �Ėi���j | �P�C�W�P�T | �P�C�W�U�X | �R�C�U�S�T | �R�C�X�V�T | �S�C�Q�O�Q | �Q�C�X�U�R |
| �@�@�@�Y�i�U�j | �P�T�C�O�O�O | �P�O�C�T�O�O | �R�C�T�V�O | �P�C�R�S�T | �H | �H |
�@���a�W�N�S���ɂ͔_�꒷���哇�b����v�ۓc���H�ɑ���A�R�ю��Ƃ̈�w�̐��i���}���A�R�ђn��Ƃ��Ă̐F�ʂ����������̂ł���B
�@���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�P�O���̔_�n�����́A����Ə��L�̎R�сi�����Q�R�O�O�w�N�^�[���]�j���̑��������āu���_�Y�Ɗ�����Ёv��ݗ����A������В��������{�A���_�o�������哇�����Ŏ��Ƃ��J�n�����B
�@���_�꒷�́A�������`�E�哇�b�E�v�ۓc���H�E�哇�����ł���A���_�Y�Ƈ��͑�������n�ӏC�O���o�ē���`�X�ցA���_�o�������͑哇�i�����j���瑾�c�������o�ė������ƂȂ��Ă���B
�@���a�T�U�N���݂Q�U�U�O�w�N�^�[���̎R�ьo�c���s���A������ѐA�ю��Ƃ����{����ق��A�c���Q�E�T�w�N�^�[����L���Ă���B�܂��A��V����n��ɂ����āA��T�O���̍��ы��̎��玖�Ƃ��s���Ă���B
���L�т̐���
�@���������ɂ����閯�L�т̉��v���ڂ����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����P�X�N�i�P�W�W�U�j�@�u�k�C���y�n�����K���v�ɂ�薢�J�n��ђn�Ƃ��ĕ������������҂��������̂ŁA���ꂪ�����ɑ�������̂ł��낤�Ǝv����B
�@�����R�O�N�i�P�W�V�X�j�Ɂu�k�C�����L���J�n�����@�v�����肳�ꂽ���A���̖@���ł͊J���E�q�{�E�A���Ȃǂ�ړI�Ƃ���y�n�͂����݂��t�����A�N�Ɛ����̂Ƃ��͖����ŕt�^���邱�Ƃ��K�肵�A�܂��A�J����ړI�Ƃ���ݕt�n�ł����Ă��A���̂����P���͖h���т�d�Y�тƂ��ĕۗL���邱�Ƃ��F�߂��Ă����B�����������x�̊��p�ɂ���āA�����R�O�N�ł킸���ꎵ�Z�����ɂ����Ȃ��������L�т��A�Ȍ�͒����������Ă������B�Ȃ��A�����S�P�N�̖@�����ɂ��R�т̔��蕥��������̂����������Ƃ��A���L�т̑����ɔ��Ԃ��������̂ł������B
�@������̊ԁA�R�тɂ����̂̎R�Ύ��Ɍ������邱�Ƃ������A���L�т̌o�c�͕K�����������Ȍo�߂����ǂ����Ƃ͂����Ȃ����A�A����d�Y��ړI�Ƃ���y�n�̎擾�A���邢�́A�q���_�k�n�̖ړI�ő݂��t�����A���̌�N�ƕ��@��ύX���Ė��L�тƂ��Čo�c������̂������A���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�ɂ͂����̖ʐς����_�œ����ɂ��B�����B�������A�����̗ё����T�����Ă݂�ƁA�����ؒn���l�Z�Z�Z����������A�l�H���іʐς͂킸���ɔ��܁Z�����ɂ������A���̑��͓V�R艁i���j�t���ƂȂ��Ă��āA�~�ϐΐ��͎O���ܖ��Ɛ������Ă����B�܂��A�����̏��L�҂͑S�̂̂W�����s�ݒn��ł���A�����������L�`�Ԃ����L�т̐��Y�͂�ቺ������v���ƂȂ��Ă����B
�@���a�P�U�N�ȍ~�ɂȂ�ƁA���ނ��펞�o�ς̊�{�Y�ƂƂ��ďd�v�Ȏg����тт��̂ł��邪�A�؍ގ��v���}�ł�����
���ߗ�����ߔ���������ꂸ�A�ђn�͒������r�p����Ɏ������̂ł���B
�@���A�r�p�����X�т������邽�߂̊e��̎{�u������悤�ɂȂ�ƂƂ��ɁA�_�ƌo�ς̍D�]�ɂ���ĎR�т̔���������ɂȂ�A���ɒn��L�̋����d�Y���ђn�̐ݒ肪�݂���悤�ɂȂ����B
�@���a�Q�Q�N�P�O���ɘh�̑��_�����ǎ��s�g���i�Q�V�N�P�����є_�Ƌ����g���ƂȂ�j���A����Ƃ���R�юO���Z�����]���擾�����̂��͂��߁A�Q�V�N�ɂ͑�V�_�Ƌ����g������l�����w���A�����ĉ��Ó��E�R�z���є_�Ƌ����g�����R�т��擾���ĊǗ�����悤�ɂȂ�A�����̖ʐς͈�Z��Z�����ɂ��y�B�܂��A�_�ƌX�̏��L�R�т́A���ʐςł͂��邪���̍��Y�Ƃ��ď��L����X�������܂�A�s�ݒn��̎肩��݉��҂̎�ւƈڍs�����B
�@�������A���a�S�O�N���납���P�O�N�ɂ킽���đS���I�ɋN������������u�y�n�u�[���v�ɂ��A�㔪�_�E����E�t���E���₻�̑������e���ɂ����āA�J�_�Ւn���܂ޑ�n�ς��s���Y�Ǝ҂ɂ���Ĕ�������A�͂Ȃ͂��������͈̂ꔽ�����x�̍א�̏��ʐςɕ������A��Ƃ��ē��O�݉��҂�ΏۂɌ֑��`�̂������蕥����Ƃ������������̂ł��邪�A���̈ړ��ʐς͂S�O�O�w�N�^�[���Ƃ��T�O�O�w�N�^�[���Ƃ�����ꂽ�B������������̗���̂Ȃ��ŁA�����d�Y���ђn�Ƃ��Ă̖ړI���������l�����є_���i���a�R�Q�E�S�E�P�W���̕ύX�j��R�z���є_�����܂����O�̋Ǝ҂ɏ��L�R�т�n�����̂����̂���ł������B
���L�т̌���
�@���a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�̒����ɂ��ƁA���L�т͑S���X�іʐς̂S�Q�p�[�Z���g�ł���Q���T�U�Q�V�w�N�^�[�����߁A�~�ϗʂ͂P�S�R���P�T�W�U�������[�g���ŁA����̓g�h�}�c�E�X�M�E�J���}�c�������B�����Ă����̗ђn�͂P�U�T�T�˂̗щƂɂ���ď��L����A�ݒ����L�҂P�O�V�S�ˁA�s�ݒ����L�҂T�W�P�˂ł���B�ђn�ۗ̕L�K�͂ł͂O�D�P�`�R�D�O�w�N�^�[���������W�R�S�˂ƂT�Q�D�T�p�[�Z���g���߁A���Ϗ��L�ʐς͂U�D�X�w�N�^�[���Ə��Ȃ��A���K�͗щƂ��������Ƃ������Ă���B
�@�ۗL�`�ԕʐX�іʐς̓���͏�L�̂Ƃ���ł���B
�@��R�߁@�юY�H�Ƃ̐���
�юY�H�Ƃ̂ڂ���
�@�J��̏����ɂ����ẮA���̖̂قƂ�ǂ��J���̎ז����̂Ƃ��ďĂ��̂Ă�ꂽ�̂ł��邪�A�₪�ĊJ����i�݂悤�₭�l�тƂ̐��������������悤�ɂȂ�ƁA���p�E�̔���ړI�Ƃ��锰�ɐi�W���Ă������̂ł���B���������Ȃ��ɂ����āA�����P�U�N�i�P�W�W�R�j����R�i���A����j�ŊJ���̂��ߔ��؍�Ƃ��ڏZ�҂̎�ɂ���čs���A���̍�ƒ��ɔ��̉��ɂȂ�A�ڏZ�N�Q���i���엊���E�C���s���j���]���ƂȂ�Ƃ������̂����������B
�ۗL�`�ԕʐX�іʐϒ��@�@�@(�P�ʁ�ha)
| �@�@�@�@�敪 �ۈ�`�� |
���@�@�@�@�n | ���@���@�@�n | �� �� �� | ���@�@�v | |||
| �l�@�H�@�� | �V�R�� | ���̐Ւn | �����ؒn | ||||
| ���@�L�@�� | �S�C�S�P�O | �Q�V�C�O�O�O | �@ | �P�C�P�R�S | �P�C�U�V�O | �R�S�C�Q�P�S | |
| ���@�L�@�� | �S�S�W | �T�P�Q | �@ | �U�P | �@ | �P�C�O�Q�P | |
| �� �L �� |
�@�@�l | �Q�C�R�R�P | �W�C�U�Q�W | �R | �P�C�O�O�T | �P�P | �P�P�C�X�V�W |
| �Ў��L�� | �R�C�Q�O�O | �W�C�V�X�U | �@ | �P�C�U�R�R | �Q�O | �P�R�C�U�S�X | |
| ���@�@�v | �T�C�T�R�P | �P�V�C�S�Q�S | �R | �Q�C�U�R�W | �R�P | �Q�T�C�U�Q�V | |
| ���@�@�@�v | �P�O�C�R�W�X | �S�S�C�X�R�U | �R | �R�C�W�R�R | �P�C�V�O�P | �U�O�C�W�U�Q | |
(���a51�N�����_�_�Ƃ̊T�v����)
�@�����Q�S�N�i�P�W�X�P�j����ƊJ���n�y��g�c�m��́A���A�҂̓~�����Ə���̂��߁A��������E������E����e����̃h���̖̕��������������A������V�̓��A�Ғ|���`�V�y�����̂������Ƀ}�b�`���ؐ����H��萻�i�����A���Q�T�N�ɂQ�O�����̐��Y���グ�A���ٍ`������Ɛ_�˒n���ɏo�ׂ����B�܂��A���̂���͊e�n�Ń}�b�`���̐���������ł������̂ŁA�h���̖̌��؈ڏo���s��ꂽ���A�܂��Ȃ��o�ς̕ϓ��Ƌ�݂̖\���ɉ��������푈�̉e�����ĐU��킸�A�x�p�Ƃ̂�ނȂ��Ɏ������B
�@�����Q�X�N����ɂ͍����̉ɂƂ��Ȃ����������Y�̎��v���������A���`�_���E�Z���E�i���E�V�R���Ȃǂ̔�������ɂȂ�A�����͒����l�̎���o�ėA�o���ꂽ���A����ɓ��O�̎��v�����ɂ�蔰�؎��Ƃ͔N��ǂ��Ċ����ƂȂ����B�����ĂR�V�A�R�W�N�̓��I�푈��ɂ́A�e��̎��Ƃ������������Ƃɂ���Ď��v�����債���̂ł��邪�A����ɗ����̌X�������݂���悤�ɂȂ����̂ł���B
�@�������������ɑΉ����Ė؍H�ꂪ�o�������̂����̂���ŁA�����S�P�N�i�P�X�O�W�j�ɂ͏d�����Y������Ŗ؊ǁE�����H����������̂��͂��߁A�S�S�N�P�P���ɂ͔��ق̓����Y���A����ɂ������T�O�n�͂̏��C�@�ւ������Ă��Đ��ނ��n�߁A���̌�A�吳�T�N�ɂ͐���Ǐ��E���엲���̗������A�s�X�n�Ɂu���_�؍H��v��݂��Č��z�ނ┠�ނ������B�i���̔��_�؍H��́A���̌��X�̋Ȑ܂��o�ĔM�c���l�Y�̌o�c�Ɉڂ�A���a�P�V�A�W�N����܂ő�����ꂽ�B���C���C���ݕt�߁j
�@�܂����̔N�A�n�Ӌ���Z�C���E�x�c�i���A�㔪�_�j�Ő��Ԃɂ��؍H��������Ăł�Ղ̐������s���A�̂��ɐ��̓^�[�r�����^�����Č��z�ނ�܂���̐������s�����B
�@�吳�N��ɓ���Ɩ؍މ��i�͖\�����A����_��ɂ����Ă͔_��ł̕s������ɒ��ʂ������Ƃ������āA�؍ލD�������_�@�Ƃ��ĎR�ьo�c�ւƓ]�����Ă������B�吳�N��ɂ�����_��̗юY�����͎��\�̂Ƃ���ł��邪�A�_��S�̂̎����ɂ�����R�ю����̃E�G�C�g�͋ɂ߂č������̂ł������B
�@�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j�P�Q���ɓV�H���ޏ����ł��A�P�T�N�V���d�C�@��ɂ���Đ��ނ��s�������A���a�V�N�ɂ�����g�c�O�l�Y�ɏ������B���̂ق��ɓ��c�E�Ȃǂ̐��ޏ����ł��A���a�Q�N�ɂ͓~�쐻�ޏ������Ƃ���ȂǁA�юY�H�Ƃ͎���Ɋ�����悵���B�����ɗv���錴�́A��Ƃ��ċ����n�▯�L�т���̔��o�������A�g�h�}�c�E�Z���E�V�i�E�i���E���`�_���Ȃǂ����������B
����_��юY����
| �@�@�@�N�@�� �i�@�� |
�吳�V�N | �吳�W�N | �吳�P�O�N | �吳�P�P�N | ||
| �����i�{�j | �� | �{ �Q�C�T�W�T |
�T�C�Q�P�V | �U�C�S�X�P | �P�V�W | |
| ���@�t�@�� | �X�C�W�S�V | �P�T�C�W�W�U | �T�C�O�U�O | �S�C�T�S�V | ||
| �� | �S�V�X | �Q�C�R�T�P | �Q�C�V�X�Q | �X�X�O | ||
| �w | �P�R�O | �Q�P�Q | �Q�R | �Q | ||
| 舁@�t�@�� | �Q�T�W | �P�R�P | �S | �Q | ||
| ������ | 舗t���p�� | �� �T�Q�S |
�� �P�S�C�Q�X�X |
�� �U�X�S |
�� �V�X�O |
|
| �d | �V�L �P�C�T�P�W |
�U�T�S | �S�C�U�W�O | �T�W�V | ||
| �}����юĖ� | �� �T�C�T�Q�V |
�R�C�P�X�Q | �X�U�S | �Q�C�S�Q�T | ||
| �@�@�@�@�Y | �U �Q�X�C�S�S�Q |
�P�S�C�S�X�O | �P�W�C�O�O�O | �Q�S�C�O�O�O | ||
| �c�� | �J���}�c | �{ �T�R�P�C�Q�O�O |
�S�V�T�C�O�O�O | �@ | �@ | |
| �X�@�@�M | �{ �T�O�C�O�O�O |
�| | �| | |||
���_�؍H��i�����_�①�~�n�j�i�ʐ^�Q�j

�@�������ɂ����ẮA���a�Q�N�Ɍ���i���A��̓��j�Ŋ�c�����Y�A�Ζ����i���A�h�l�j�Ŋ�c��삪�A���ꂻ��؍H����J�Ƃ��Ă������A�����͂P�Q�A�R�N���둊�����Ŕp�Ƃ����B�܂��A���a�W�N�ɐX����]�������ؑ��K�g���A�������̕t�߂Ŗ؍H����J�Ƃ��A�x�j���P�̐������s���������݂��̂ł��邪�A�����푈���ڂ��������P�Q�N�ɉ����������߁A�P�T�N�Ɏ{�݂����M�̐V�{���s�����̈��ʍH��ɔ��p�����B
�@�܂������A�鍑�Y��������Ёi�В��E�ΐ씎���j�͒��N��{�B�A�k�C���ł͐��c���Ȃǂŋ��R�z�Ƃ��o�c���Ă������A���Ǖ����̎��v�����������ƂƁA�R�p�̖ؐ���s�@�p�P����̘b�����������Ƃ���A���a�P�W�N�R���Ɉ��ʃx�j���H�ꂩ��O�L�̗����H������A�鍑�Y��������З����H��Ƃ����B�������Ē鍑�Y�����͗��S���ɓ���ɐV�H������݂������A�U���ɂ͎��{���P�O�O���~�������ĕʉ�Ђ̒�Y�q����Ђ�n�݂̂����A�O�L�H������̉�Ђ̗����H��Ƃ��A���ʃx�j���H�ꂩ�甃�������H��͉�̂����̂ł������B
�@�V�݂��ꂽ��Ђ̍H�꒷�́A���ݎD�y�s�ݏZ�̌��z�Ɠc��`��ł��������ł������B
�@��АV�݂Ɠ����ɗ����H��͌R�̎w��H��ƂȂ�A�ؐ���s�@�Ɏg�p����q��p�P��������ƂȂ����B�������ď]�ƈ��S�O�O�l��i����܂łɂȂ������A�펞���̐H�Ɠ��ł�����A�u�C�^�E�V�i�C�i���A�ԉY�j�Ŕ_����o�c���A�H�Ƃ�������������Ƃ����Ԑ��ł߂܂ł����̂ł���B
�@���a�Q�O�N�W���I��Ɠ����ɂ��̉�Ђ�����A�鍑�Y��������З����H��Ɩ��̂�ύX�������A�R�̎w��H�ꂾ�������ߓ��N�H�ɂ͐i���R�̗������茟�����s��ꂽ�B�Q�Q�N�ɓ��H��͕�����A�Q�S�N�ɂ͑哯�؍ފ�����Ђ���������邱�ƂƂȂ����B
�ؒY�̐���
�@�����s����悤�ɂȂ�ƁA�����K���i�Ƃ��Ă̖ؒY����������ɂȂ��Ă����B�����P�R�N�i�P�W�W�O�j�̗������˒�����̋L�^�ɂ��ƁA�ؒY�P�Q�O�O�U�S�Q�O�~�̐��Y���グ�Ă���B�܂��A�S�R�N�ɂ͒Y�ċƎ҂U�O�l���A������ҁi���A��̓��j���ʂł��܂ǂU�T���݂��A�R�U���сA�X�O�O�O�~���Y�o�����Ƃ����B
�@���_���ɂ����Ă��Y�Đ�Ǝ҂��邢�͔_�Ƃ̌��ƂƂ����`�Ő��Y���s�����̂������������A�����S�Q�N�ɂ͂R���P�O�O�O�сA�S�S�N�ɂ͂V�O���тY���A���̑����͔��ْn���Ɉڏo����Ă����B���̌�吳�N��ɓ���A��ꎟ���E���ɂ��H�Ɨp�ؒY�̎��v�ɂ���Đ��Y�͂��悢�摝�����A�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�ɂ͂X�O���т�˔j���鐨���ł������B�����Ă��̍D���͏��a�U�A�V�N����܂ő������̂ł��邪�A�X�N����ɂȂ�Ɨ����ɂ���Č��ؕs���������A���Y�ʂ��R�O���ѓ��O�ɗ������݁A���̋���������L�тɈˑ�����悤�ɂȂ����B
�@���������̂��ƂŐ��Y�Ǝ҂͌o�c�̈����}�邽�߁A�ؒY���Ƒg����ݗ����Đ��Y�Ɣ̔���g�D�����A���i�̉��ǂƎ��匟�������{�����̂ł���B���������̑g���̎��匟���͏��a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�S�����c�����ɕ����A�S�S�N�R���܂Ŏ��{���������N�S���A�c�̂̎��匟���Ɉڍs���Ă������B
�@�����푈�ڂ����ȗ��A�����鎑�������R���������A�ؒY�͐H�ƂɎ����R���K�������ƂȂ����B���Ȃ킿�A�āE�p�̈��͂ɂ���ē��{�ɑ���K�\�����̕⋋�H���f���ꂽ���߁A��ނȂ���p�Ƃ��ĖؒY�K�X���g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̂��ߐ��{�́u�z�q�⏕�v�̋K���݂��đ��Y�����シ�锼�ʁA�u�d�Y�z�������K���v�����z���ĖؒY�̎����̐����m�����������u���Ă����B�����ď��a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�ɂ́A���i�͂��ׂĐ��{�����グ�̏d�v�����Ƃ����̂ł���B���Ȃ킿�A���Y�҂͒��ڐ��{�ɔ���n���A���{�͂�����w��z���@�ւɔ���n���ď���҂ɔz������Ƃ������@���Ƃ�ꂽ�̂ł���B
�@�������Đ푈���������Ȃ�ɂ����������Y�ɂ����Y���������ꂽ���ʁA���{������ɐ�s�������Ɠ����ɘJ�͕s���Ƃ��Ȃ����̂ł���B
�@���Ɏ����ẮA���ؕs���ɂ���Ĕp�Ƃ�����̂����o���A���a�R�O�N��ɂ͂قƂ�ǎp���������̂ł������B
���̗юY�H��
�@�����m�푈�I���̂��ƁA�������ނ̐��Y�ɑ����ď��a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j���N�����̉e���ɂ��؍ނ̐V�K���v�ɂ���āA���Y�͊g�傷�����ł������B���������̂���ɂȂ�ƁA�����тɑ����Y����u�u�i�ށv�́A�]���̐d�Y�ނ����]���č��x���p�ɒ��ڂ���A�C���`�ނƂ��Ă̐��Y���n�߂��ď��a�Q�T�N����A�o�����悤�ɂȂ����B�܂��A�u�i�ނ͊����Z�p�̌���ɂ�菰�ށi�t���[�����O�j�Ƃ��Ċ��p�̓����J���A����ɁA����܂���،��̕s����₤���ߗ��p�������Ȃ�A���a�Q�W�N�ɂ͉��H�{�݂Ƃ��Ė�c���ɖ؍ޖh���H�ꂪ�ݒu���ꂽ�B����́A�؍ނ̏W��I�ȗ��p��}�邽�߁A�؍ޖh���@�Ɋ�Â�������Ƌ����g���@�ɂ��H��ŁA����n��̓��Y�u�i�ނ̍��x���p�������A�h���������s���ϗp�N���̉�����}��Ƃ����ړI�ŁA�N�Y�܂���P�T�����A�d���W�O�O�O�A����傤�ނT�O�O�̐��i���A����ʁA�������{�C���[�W�O�n�͂̓d���@�ɂ���ď����������̂ł������B
�@���̂ق��A���_�s�X�n�ɔ��_���ޏ��A�_�Ƌ����g�����ޏ��A��c���ɐX�؍H�ꂪ���Ƃ������A�X�؍H��͂Q�V�N�P�O���ɉЂ̂��ߏĎ����A���̂��Ƃ�؍ފ�����Ђ������p�����Ƃ����̂ł��邪�A����܂��S�Q�N�V���ɎВ��̔���N�j���}���������ߕ����A�_�����ޏ������~����Ɏ������B
�@����������ɂ����ẮA���a�Q�Q�N�T���ɒ鍑�Y�������H�ꂪ������A�Q�S�N�ɑ哯�؍ފ�����Ђ�����������p���ő��Ƃ������Ԃ��Ȃ�����������A�R�U�N�Ó����ɖ{�Ђ�L����r���x�j��������Ђ������H��Ƃ��č��A�t���[�����O�Ȃǂ̐��Y���s���������ɂ߂��B�������A���̌�؍ފE�̕s���ɂ���ĂS�X�N�P�O���ɓ��H�������A�Ó��{�ЂƓ�������̂�ނȂ��Ɏ������B
�n����ɂ�錴�؉^���i�ʐ^�P�j

�@���a�R�W�N�ɂ͎O�����̍��L�n���Ɋ�����Ѓ~�J�h�t���[�����O���쏊�����Ƃ��J�n���A�������Ė{�B���ʂɏo�ׂ��Ă���B
�@����琻�ދƎ҂�����ɂ��̐��������Ă������Ƃɂ��A�R�X�N�ɂ́u���_�n�搻�ދ����g���v��ݗ����A�n���Ǔ��̔��_�E�������ƌ�u�Ǔ��̍������E���s�E���q�̎l���ꑺ�̐��ދƎ҂P�R���ɂ���āA�؍ނ̋������Y�A�����w���Ɣ̔��E���i����Ȃǂ��s�����Ƃ�ړI�Ƃ��Ĕ����A���㗝�����ɂ͒��������̑O�쐭�s���A�C�����B���̌�T�S�N�ɒ芼�ύX���s���Ĕ��_�E�������̖؍ދƎ҂݂̂Ƃ��A�T�U�N���ݔ��_�P�A�������R���ދƎ҂ɂ���č\������Ă���A�������͔��_���̈������v�ł���B
�@�܂��A���a�S�R�N�ɔ��قɖ{�Ђ��������n������Ђ��A�ԉY�̍��������ɂR�Q�V�������[�g���̃`�b�v�H������݂��A�����т���f�ނ��W�ς��ă`�b�v�̐��Y���s���A�N�Ԗ�P���Q�O�O�O�������[�g���̐��i�����q�����ɏo�ׂ��Ă���B
�@�܂��A���a�T�P�N�x����̑�ыƍ\�����P���Ƃ̈�Ƃ��āA�T�T�N�ɔ��_���X�ёg�������Ǝ�̂ƂȂ�A����n��ɏ��a�؏����H��S�R�W�������[�g����V�z���A���ށE�������̂ق��`�b�v���Y���s�����q�����ɏo�ׂ��Ă���B
�@���ޏ��Ƃ��ẮA���_�ɋg�c���ޏ��̌�������p�����O�ؐ��ޏ��ƁA���_���ޏ�������B�܂��A�����ł͗ѐ��ޏ������Ƃ��Ă������A�T�O�N���댚�z�ނ̔̔��ɓ]�Ƃ��A�T�U�N�R���������Ĕp�Ƃ����B
���̎R�i�ʐ^�P�j

�@��S�߁@�ыƍ\�����P����
���x�̂���܂�
�@���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�V���A�ыƂ̔��W�ƗыƏ]���҂̒n�ʂ̌����}��ƂƂ��ɁA�X�ю����̊m�ۂƍ��y�ۑS�������邽�߁u�ыƊ�{�@�v�����肳�ꂽ�B�����Ă��̑�܈���ŁA
�@�u���͏��K�͗ыƌo�c�̋K�͂̊g�傻�̑��ыƌo�c�̊�Ղ̐����y�ъg�[�A�ߑ�I�ȗыƎ{�݂̓������ыƍ\���̉��P�Ɋւ��K�v�Ȏ��Ƃ������I�ɍs����悤�Ɏw���y�я������s�����K�v�Ȏ{����u������̂Ƃ���B�v
�Ɨыƍ\�����P���Ƃ̎��{���K�肵���B����ɂ���č��́A�ыƍ\�����P���Ƒ��i���v�j���߁A�R�X�N�x������̎s�������w�肵�ĔN���I�Ɏ��Ǝ��{�ɑ��鏕���̕��r���u�����B
�@����ɂ��ƁA���ƌv������̎�͎̂s�����Ƃ��A���{��͎̂s�����E�X�ёg���E�_�Ƌ����g���E���̑��X�я��L�҂̋��Ƒ̂Ƃ��ꂽ�B�����āA��n�擖����̕W�����Ɣ���V�O�O�O���~�Ƃ��A��̓I�Ȏ��Ƌ敪���A�i�P�j�o�c�K�͂̏[���A�i�Q�j���Y��Ղ̐����A�i�R�j���{�����̍��x���A�i�S�j�����琬�ыƌo�c�̑��i�A�i�T�j���Ƃ̑��i�A�ƒ�߁A�����ɊY�����鎖�Ƃɑ��āA���͂Q���̂P�i�i�Q�j�Ɓi�R�j�̎��Ƃɑ��Ă͕ʂɓ����T���̂P�j��⏕���A�c��̌o��ɂ��ẮA�_�ы��Ƌ��Z���ɂ̎����̂Ȃ��ɗыƍ\�����P���ƊW�����̘g���݂����邱�ƂƂ��ꂽ�̂ł���B
��ꎟ�ыƑ����P����
�@���͂����������x�Ɋ�Â��A�X�ю����̊J���ƗщƂ̌o�c�����}�邽�߁A���a�S�R�N�x����n��w��̌�����i�߂��B���̌��ʁA
�@�i�P�j�A���L�іʐς̐l�H�ї����ŏI�I�ɂU�U���Ɉ����グ�A���Y���̒Ⴂ�V�R�т△���ؒn����l�H�тɍX�V���Čo�ϐ������߂�B
�@�i�Q�j�A���K�͗щƂ̌o�c�K�͂��g�傷�邽�ߗђn�̗������i���K�͗щƂɒ����������ėђn����������j���͂���B
�@�i�R�j�A�{���ɂ����閯�L�т͍��L�тƎs�X�n�̒��ԂɈʒu����k�ɑ���A�ʐς͍L�͂ɂ킽��A���ݗѓ��͍��L�ѓ�����ŁA�O�ɔ_�������p����Ă���B���L�ѓ��͂킸���ɂO�E�Q�L�����[�g�����J�݂��ꂽ�ɂ������A�ѓ����J�݂��č�ƌ��������߂�B�Ƃ�����{���j�𒌂Ƃ��Ď��Ƃ̎��{���@���߁A���a�S�T�N�x�i�P�X�V�O�j�Ɏw������̂ł������B�����āA�S�U�N�x����̂R���N�v��ɂ����Ď��Ƃ��i�߂�ꂽ���A���Ɣ�U�Q�O�O���~�������āA�ѓ��̊J�݁E�f�ސ��Y�E���сE����юY�{�݂̐ݒu�Ȃǂ���Ȏ��ƂƂ��Čv����I�������B���̎�Ȃ��͎̂��̂Ƃ���ł���B
�P�A�ѓ��̊J��
�@�ѓ��͑����Ɣ�̖�S�W���A�Q�X�T�W���~�𓊂��A��V���P�W�O�O���[�g���Ɠ�����R�O�Q�O���[�g���̓�H���������B
�Q�A�f�ސ��Y�{�݂̐ݒu����
�@���F���Ƃł��郍�O���[�_�[�P��i�Q�S�O���~�j���܂߁A�g���N�^�[�Q��A�`�F���\�[�R��Ȃǂ���������ċ@�B�͂���������A�f�ސ��Y�͑S�ʐX�ёg���ɂ�钼�c�̐����z���ꂽ�B
�R�A���ю{�݂̐ݒu
�@���ސl���A���ԂP��Ɗ����@�R�V��̓����𒆐S�Ƃ���@�B���ɂ���āA���э�Ƃ̌��������߂�ꂽ�B
�S�A����юY�����Y�{�݂̐ݒu
�@����E��̓��E�h�l�̎O�n��ɑ���{�݂ŁA���ꂼ��t���[���P���̂ق��A���E�@�E�`�F���\�[�E������Ȃǂ����A���������̐��Y�g����͂������B
�ыƍ\�����P���Ǝ���
| ���@�� ��@�� |
���@�� ��@�� |
��v �ː� |
���Ɠ��e | ���Ɣ� �i��~�j |
�@���@�@�S�@�@��@�@���@�i��~�j | ||||
| ���@�� ��@�� |
���@�� ��@�� |
�s�@�� ���@�� |
���@�� ���@�� |
���@�� ���@�� |
|||||
| �o�c��Ղ� �[������ |
�ђn���������� | �T | �P�c�n�P�Oha�ʐϑ��� | �U�O | �R�O | �| | �| | �| | �R�O |
| ���@�v | �T | �@ | �U�O | �R�O | �| | �| | �| | �R�O | |
| ���Y��Ղ� �������� |
��V�� | �S�V | �Ј��S�� �����P�C�W�O�O�� |
�P�S�C�O�X�P | �P�V�C�U�O�V | �R�C�O�X�W | �W�C�W�V�S | �| | �| |
| ����� | �R�R | �Ј��S�� �����R�C�O�Q�O�� |
�P�T�C�S�W�W | ||||||
| ���@�v | �W�O | �S�C�W�Q�O | �Q�X�C�T�V�X | �P�V�C�U�O�V | �R�C�O�X�W | �W�C�O�V�S | �| | �| | |
| ���{������ ���x������ |
�f�ސ��Y�{�݂̐ݒu | �R�W�V | �g���N�^�[�@�@�@�Q�� | �P�P�C�V�R�W | �P�X�C�T�X�U | �P�C�P�Q�U | �| | �U�C�O�U�T | �Q�C�W�P�U |
| �g���b�N�@ �@�@�Q�� | �R�C�W�V�X | ||||||||
| �`�F���\�[�@�@�@�R�� | �Q�T�R | ||||||||
| �@�B�ۊǑq�ɂP�T�T�D�R�V�u | �S�C�T�P�O | ||||||||
| ���ю{�݂̐ݒu | �R�W�V | ���ސl���A�����@�P�� | �P�C�U�U�O | ||||||
| �ΘJ�y�ː� �P�� | �Q�U�T | ||||||||
| �� �� �@�@�R�V�� | �Q�C�P�X�S | ||||||||
| �ړ��h���{�݂S�W�D�U�O�u | �T�Q�R | ||||||||
| �\ �m �� | �Q�X�W | ||||||||
| ����юY�����Y �{�݂̐ݒu |
�P�T | �t���[���R���P�V�U�D�V�u | �R�C�T�Q�X | ||||||
| �� �� �@�@ �R�� | �P�R�T | ||||||||
| �� �E �@ �@ �R�� | �S�T | ||||||||
| �l�H�z�_�U�U�R�u | �Q�T�W | ||||||||
| �`�F���\�[ �R�� | �R�P�U | ||||||||
| ���@�v | �@ | �@ | �Q�X�C�U�O�R | �P�X�C�T�X�U | �P�C�P�Q�U | �| | �U�C�O�U�T | �Q�C�W�P�U | |
| ���̑��̎��� | ���Ƃ̐��i | �R�W�V | �g�����V�[�o�[�P�g | �S�Q | �P�C�R�V�X | �| | �| | �X�U�O | �S�P�X |
| �I�[�g�o�C�@�P�� | �P�Q�R | ||||||||
| ���ʊ��@�@�P�� | �U�S | ||||||||
| ���Ǝ������i��Sha | �P�Q�X | ||||||||
| ���F���ƃ��O���[�_�[ �@�@�@�P�� |
�Q�C�S�O�O | ||||||||
| ���@�v | �@ | �@ | �Q�C�V�T�W | �P�C�R�V�X | �| | �| | �X�U�O | �S�P�X | |
| ���@�@�v | �@ | �@ | �U�Q�C�O�O�O | �R�W�C�U�P�Q | �S�C�Q�Q�S | �W�C�W�V�S | �V�C�O�Q�T | �R�C�Q�U�T | |
�����̎��Ƃ��܂Ƃ߂�ƑO�y�[�W�̕\�̂Ƃ���ł���B
��ыƍ\�����P����
�@��э\���Ƃ́A���a�R�W�N�x�i�P�X�V�R�j����n��w�肪�n�߂�ꂽ���A�����ł͂T�O�N�x�Ɏw����A���T�P�N�x����S���N�v��ɂ�鎖�Ƃ̎��{�ƂȂ����B��̗э\���Ƃ́A��n�擖����̕��ς��Q���S�O�O�O���~�Ƃ��ꂽ���A�����̊�{�\�z�Ƃ��ẮA��אX�я��L�҂̋����g��ƐX�ёg���̔��W��}�邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��A�i�P�j�f�ސ��Y�{�݂̐ݒu�A�i�Q�j�`�b�v���Y�{�݂̐ݒu�A�i�R�j���Ɗ������_�{�݂̐ݒu�A�Ȃǂ���Ƃ�����̂ŁA�����Ɣ�Q���T�U�O�O���~�������Čv�悳�ꂽ�B
�@���̌v��Ɋ�Â��đ��N�����T�P�N�x�Ƃ��A��N���A�O�N���A�l�N���i�T�S�N�x�j�ƔN���ʎ��Ǝ��{�v�悪���Ă�ꂽ���A�O�N���A�l�N���ɂ����Ă͎��Ƃ̌v��ύX���s���A�V�K���Ƃ��������ĂT�S�N�x�ɑ�э\���Ƃ͊��������̂ł���B���̎�Ȃ��͎̂��̂Ƃ���ł���B
�P�A�f�ސ��Y�{�݂̐ݒu����
�@�g���N�^�[�Q��A�g���b�N�Q��A�ѓ���ƎԂP������ꂼ�ꓱ�������ق��A���a�T�R�N�x����n��ɎR�����؏�P���T�R�U�R�������[�g����V�݂����B
�Q�A���ю{�݂̐ݒu����
�@�P�T�l���l���A���ԂP��A�Q�X�l���P��A�`�F���\�[�T��������B
�R�A����юY�����Y�{�݂̐ݒu����
�@�h�l�Ƀt���[���P���ƕt�ы@��Ȃǂ�ݔ����A���������̐��Y�g���}�����B
�S�A���Ɗ������_�{�݂̐ݒu����
�@���Ɗ����̉~���Ȑ��i��}�邽�߁A�ыƎ҂̎��Z�P���E�W��E�h���{�݂Ƃ��āA���a�T�Q�N�x�Ɂu�ыƌ��C�Z���^�[�v��ݒu�����B���̎{�݂͓S�R���N���[�g���Q�K���A���ׂT�R�O�������[�g���]�������Ĕ��_�������ٕ~�n���Ɍ��āA���ށE���i�ނȂǂ��܂߂ĂV�S�P�S���~�]��v�����B
�T�A���F����
�R�����؏�i����j�i�ʐ^�P�j

��ыƍ\�����P���ƔN���ʎ��ѕ\
| ���Ƌ敪 | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | �N�@�@�@���@�@�@��@�@�@�� | ���Ɣ� | |||
| �T�P | �T�Q | �T�R | �T�S | ||||
| �o�c����� �[������ |
�@ | �W���ю}�Ł@�@�S�Oha | �@ | �@ | �@ | �P�C�Q�U�O | �P�C�Q�U�O |
| ���{������ ���x������ |
�f�ސ��Y�{�݂̐ݒu | �g���N�^�[�P�Qt�@ �P�� | �X�C�R�U�T | �@ | �@ | �@ | �P�V�C�R�O�V |
| �@�@�V�@�@�@�Vt�@ �P�� | �@ | �@ | �V�C�X�S�Q | �@ | �@ | ||
| �ѓ���Ǝԁ@�@ �@ �P�� | �S�C�X�O�O | �@ | �@ | �@ | �S�C�X�O�O | ||
| �g���b�N�@�P�Qt�@ �P�� | �@ | �V�C�W�W�V | �@ | �@ | �@ | ||
| �@�@�V�@�@�@�Wt�@ �P�� | �@ | �@ | �W�C�P�V�Q | �@ | �P�U�C�O�T�X | ||
| �@�B�ۊǑq�� �@�@�@�@ �P���P�U�V�u |
�@ | �@ | �W�C�W�O�O | �@ | �W�C�W�O�O | ||
| �R�����؏� �P�����P�T�C�R�U�R�u |
�@ | �X�C�X�V�W | �@ | �@ | �X�C�X�V�W | ||
| ���O���[�_�[�@�@ �P�� | �@ | �@ | �@ | �V�C�S�S�O | �V�C�S�S�O | ||
| �N �� �[ ���@�@�@ �P�� | �@ | �@ | �@ | �T�C�P�W�O | �T�C�P�W�O | ||
| ���ю{�݂̐ݒu | �l���A���ԁ@�@�@�@�Q�� | �@�P�T�l�� �P�C�P�U�V |
�@ | �@�Q�X�l�� �Q�C�T�O�S |
�@ | �R�C�U�V�P | |
| �`�F���\�[�@�@�@�@�T�� | �T�V�Q | �@ | �@ | �@ | �T�V�Q | ||
| �g �� �b �N�@�@ �@�P�� | �@ | �@ | �@ | �@�Qt �P�C�V�T�U |
�P�C�V�T�U | ||
| ���ю{�݂̐ݒu | �t���[���O�����@�@�P�� | �@�P�� �S�C�U�O�R |
�@ | �@ | �@ | �S�C�U�O�R | |
| ���Ƃ̐��i���� | ���Ǝ��ƌv��������i���� | �� �� �� �� �v �� �� | �@ | �@ | �S�R�Q | �R�O�O | �V�R�Q |
| �q �� �� �^ �� �� | �@ | �@ | �P�P�O | �@�@ | �P�P�O | ||
| �ʁ@�^�@�i�@�[�@�� | �@�@ | �@�@ | �P�T�W | �@ | �P�T�W | ||
| ���Ɗ������_�{�݂̐ݒu | �W �� �h �� �p �� �� | �@ | �@�P�� �V�O�C�W�O�X |
�@ | �@ | �V�O�C�W�O�X | |
| ���@�@ �ށE���@�@ �i | �@ | �R�C�R�R�Q | �@ | �@ | �R�C�R�R�Q | ||
| ���F���� | ���F���� | ���a�؏����{�݁@�@�P�� | �@ | �@ | �@ | �T�U�C�V�T�W | �T�U�C�V�T�W |
| �Ǘ����P���U�X�C�U�U�u | �@ | �@ | �T�C�R�W�O | �@ | �T�C�R�W�O | ||
| �� �� �� �{ �݁@�@�P�� | �@ | �@ | �U�C�S�U�T | �@ | �U�C�S�U�T | ||
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �Q�O�C�U�O�V | �X�Q�C�O�O�U | �R�V�C�S�T�X | �V�T�C�P�X�W | �Q�Q�T�C�Q�V�O | ||
�i�����@���_���Y�Ɖہj
�@��㑢�т����X�т��Ԕ����ɓ��葽�ʂƂȂ����Ԕ��ނ̕t�����l�����߂邽�ߌv�悳�ꂽ���̂ŁA�����ɐ��������R�����؏�̕~�n���ɂT�R�N�x����{�݁A�Ǘ����E�@�B�ۊnjɂȂǂ����݂����B�Ȃ��A�����Ɠ����Ɍ��ݗ\��̏��a�؏����{�݂͌o�ς̒���A�ƊE�s���Ƃ�����f���ČJ�艄�ׂƂȂ�A�ŏI�N���̂T�S�N�x�Ɏ��{�����B
�@��э\���Ƃ̎��т͑O�y�[�W�̕\�̂Ƃ���ł���B
�@��T�߁@�X�ёg��
�X�ёg���̕ϑJ
�@���a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�R���A�X�і@�̑啝�ȉ����ɂƂ��Ȃ��A���߂Ėk�C���ł��K�p����邱�ƂƂȂ����X�ёg�����x�́A���Ɍ܁Z�����ȏ�̎R�я��L�҂Ŏ���{�ƈĂ�Ґ�������̂������A���̑������̐X�я��L�҂ɑ��A�����I�ȋ����ɂ���Ċe�s������P�ʂƂ���X�ёg����ݗ������A���L�X�тɂ��Ď{�ƈĂ��쐬�����Ă�������s�����悤�Ƃ��鐫�i�̂��̂ł������B
�@���̂��߁A�e�s�����Ƃ��g���̐ݗ����}���ƂȂ����̂ł��邪�A�����ł͏��a�P�W�N�Q���ɓ��ӎ҂Q�T�W���������āu�Ǖ�ӔC���_���X�ёg���v���ݗ�����A����g�����ɒ����F���呾�Y��I�C�����B�������g���́A�펞���̓����̂Ȃ��ŁA�d�Y�̐��Y�m�ۂ�펞�p�ނ̋��o�ȂǍ���̐��s�ɓw�߂邱�ƂɂȂ�A�Ƃ��Ă��{�ƈĂ̕Ґ��ɂ͎���Ȃ��̂܂܂ŏI����}�����B���a�Q�R�N�g�����ɓn�Ӌ���A�C���A�Q�T�N�ɂ͖k�C���X�ёg���A����̋��͂ɂ���Ď{�ƈĂ��Ґ�����A���߂đ����I�ȐX�ьo�c�ɏ��o�����ƂƂȂ����̂ł���B
�@���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�U���ɐX�і@�̑S�ʓI�ȉ������s���A�X�ёg�����x�ɖ���I�ȕϊv�������炳�ꂽ�B���Ȃ킿�A�]���̋���������������E�ނ����R�ƂȂ�A�y�n���S��`���狦���g�������Ɋ�Â��l�I�����̂Ƃ��Ă̑g���ɉ��߂��A�o������ȏ�őg�����X�͕����̌�������Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B
�@�����������v�ɂƂ��Ȃ��A����܂ł̑g���͂Q�V�N�R���܂łɑg�D�ύX�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ����̂ŁA���̔N�P���P�V���u���_���X�ёg���v�Ɖ��߁A�P�Ǝ{�Ǝ҂̉������܂߂đg���������R�V�R���A�����ʐψꖜ�l�Z�Z�����Ɗg�傳�ꂽ�B
�@����A�������ɂ����ẮA���a�P�V�N�V���Ɂu�Ǖ�ӔC�������X�ёg���v��ݗ����A����g�����ɒґ������I�C�������A������܂��Q�V�N�R���R�P���u�������X�ёg���v�i�����g�����E�F��^�O�ܘY�j�Ƒg�D���ύX���ꂽ�B
�@�������A�V�g���ɕύX���ꂽ�Ƃ͂����A���g���Ƃ��o�c�̎��Ԃ͂��قǕς�����Ƃ�����Ȃ��A���їp�c�̂�������③�ю��ƕ⏕���̐\�������ƂȂ�ȂǁA��Ƃ��čs���֘A��������������ɂ����Ȃ������B
�����ɂ��g�D����
�@�g���̌o�c��Ղ̐����g�[��}�邽�߁A���a�S�P�N�i�P�X�U�U�j�U���ɔ��_���X�ёg���Ɨ������X�ёg�����������A�V���́u���_���X�ёg���v�i�g�����E���R�k��j�������A��C�E����z�u���Ă��̏[����}�����B�S�R�N�S���ɓ��~�ꂪ��Αg�����ƂȂ�A�{�i�I�ȑg�����c�̎�ϑ����Ƃ��J�n�A�S�S�N�V���ɂ͓��{��w����ѐX�ь��c�Ƃ̎O�Ҍ_��ɂ�镪�����ю��Ƃ̎��{���_�@�Ƃ��āA�{�i�I�ȋ������Ƃ�W�J����Ƃ���ƂȂ�A�܂��A�S�U�N����͗ыƍ\�����P���ƌv��ɂ���āA�n��ыƂ̐U���Ɨыƌo�c�̈���ɓw�߂��̂ł���B
���_���X�ёg���i�ʐ^�P�j

�@�S�U�N�P�P���ɂ͏o�_���ɂP�S�R�U�������[�g���̕~�n�����A�ؑ��Q�K���������Q�P�W�E�Q�������[�g����V�z�����ق��A�t������@�B�ݔ����������A����܂Ŗ�����ɂ��������������ړ]���ēƗ������̂ł������B���a�T�U�N���݂ŁA�g�����͂W�P�X���ł���B
�@��U�߁@���L��
�䗿�n
�@�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�W���ɗ��������ʐς̂U�O�p�[�Z���g�ɂ�����ꖜ��Z�ꔪ�����]���A�c�����Y���Ȃ킿�䗿�n�ɕғ����ꂽ�B���̓���͗����䗿�n�Z�O�Z�����]�A�t��䗿�n�O��ꔪ�����]�A��c�nj䗿�n�ꔪ�Z�㒬���]�ŁA�w�R�Ƃ̍����̕���������Ƃ����n��ł������B
�@�䗿�n���̎���́A�u�i�T�O�p�[�Z���g�A�C�^���Q�O�p�[�Z���g�A���̑��R�O�p�[�Z���g�̍����тł���A�L�t���Ƃ��āA�z�I�E�n���E�Z���E�V�i�E�J�c���E�j�t���Ƃ��ċt��n��Ƀg�h�}�c�A�]���z�n��ɃS���E�}�c����A�����Ă���B
�@�䗿�n�ɕғ�����Ă���̗��؏����́A�����Q�R�N�ɗp�ޔ��ځY�i�Q�E�V�T�������[�g���j�̕����������������Ƃ����B
�@�����Q�S�N�P�P���ɋ{���Ȍ䗿�ǔ��َx�ǐX���݈����������ݒu����āA���������̌䗿�n���Ǘ����Ă������A�Q�W�N�P���ɂ͓��x�Ǘ������S������ݏ����A������x���O�̓d�X���Ж��l���p�{�݂̏��ɐݒu����A���݈����풓�����B�R�W�N�ɂ͌䗿�тS�O�N�֍ނƎO�Z�Z�����̊J�����v�悳��A�֔��ނ̔��o�A�J���n�ւ̔_���ڏZ�Ȃǂ��s��ꂽ�̂ł���B�S�P�N�P���ɂ͋{���Ȍ䗿�ǂ��鎺�і�ǂɉ��߂�ꂽ�B
�@���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�X���Ɍ䗿�n���̔_�k�K�n���Z�����ɎR�сE����̈ꕔ�������Ď���_��n�݂����B�܂��V�N�ɂ́A�t��䗿�n���Ƀg�h�}�c�O�E�X�P�w�N�^�[����l�H���тƂ��Ă͏��߂ĐA�����A�����łP�O�N�Ƀg�h�}�c�P�E�Q�X�w�N�^�[����A���A�Ȍ�P�W�N�܂Ńg�h�}�c���e�n��ɂP�`�T�w�N�^�[�����x�A�����Ă������A�펞���ɓ���J�͕s�����e�����đ��т͒��~���ꂽ�̂ł������B
�@���a�Q�Q�N�R���鎺�і�ǂ��p�~����Č䗿�n�͍��L�Ɉڂ���A�T���ɂ͗ѐ����v���s���A���L�сE�䗿�т͔_�яȏ��ǂƂȂ�A�{���ɂ͌܉c�ыǂ��ݒu����A���������̌䗿�т͔��ىc�ыǂ̊NJ��ƂȂ����B
�@�c�ыNJNJ��ɂȂ��Ă���́A�ѓ��̑�����l�H���т��ϋɓI�Ɏ��{����A��Ғn��S������������A�]���z�n��S��������������ݒu���ꂽ�ق��A����n��ɕc�ނ��o�c���đ��тɓw�߂Ă���B
���ъĎ�̕ϑJ
�@�����P�P�N�i�P�W�V�W�j�P�O���u�R�ъĎ�l�K���v����߂��A�e�n�ɊĎ�l��z�u���A�R�т̏�����e����E�K���̈ᔽ��������юR�Ζh�~���ɓw�߂邱�Ƃ��K�肳�ꂽ�B����ɂ���ĎR�z���ɂ��P�R�N�P���ɎR�ъė����ݒu����A�������E�R�z���E�����e�����Nj�Ƃ��ĒS�����邱�ƂɂȂ����B
�@�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�P�P���k�C�����B�����і��ېX�h�o�����_�ی������ݏ����ݒu����A����ɂS�P�N�U���ɂ͔��ىc�ы提���ݒu����āA���_�ɓ��c�ы提���_�X�ъĎ璓�ݏ���������A�X�эs���������s��ꂽ�B�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�U���ɔ��ىc�ы提�͎D�y�c�ы提�̊NJ��ɓ����Ĕ��ىc�ы敪���ƂȂ�A���_�͂��̊NJ����ɑ������B���̌�A�吳�V�N�̗ѐ��@�\���v�ɂ���ĐX�ъĎ��p���X�ю厖�ƂȂ�A�X�ъĎ璓�ݏ����X�ѕی������ݏ��Ɖ��߂�ꂽ�B����ɁA���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�D�y�c�ы提�ɑ����Ă������ٕ������A�Ăє��ىc�ы提�ƂȂ�A�����̕ی������ݏ����܂����̊lj��ɑ����邱�ƂɂȂ����B
�@���a�P�O�N�U���ɂ́A�w�R�c�ы提�lj��̐��I�E���E��S�����ىc�ы提�Ɉڊǂ����ȂǁA�������т��̕ϑJ���o�ĊǓ����L�т̊Ǘ����i�߂��Ă����̂ł���B
�c�ы提�̐ݗ�
�@���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�ɓ����́A�X�эs���m���̂��߉c�ы提�̔p�u�������s�����ƂƂ��A���ىc�ы提�̊NJ��ł������R�z�S�E���I�S�E���E�S�����āu���_�c�ы提�v���J�݂���v������āA���N�V�����_���ɑ��A���̌v�����������v���Ƃ��āA
�@�P�A���ɂ͏��a�Q�O�N�x�Ɍ��z�̗\��ł��邪�A����܂Œ��ɂɏ[������������ɂ����Ė������ł��邩�B
�@�Q�A����Œ��ɂ���ъ��ɂ����z���邪�A����ɗv����~�n�̊�t���ł��邩�B
�Ƃ����\�����ꂪ�������B����ɑ����́A����̎�������Ă��ϋɓI�ɋ��͂��邱�Ƃ�����B
�@�������Čv��͏����ɐi�݁A�����_���������w�Z�Z�Ɂi���A���_�������ُ��ݒn�j�������ɂɏ[�����邱�Ƃ���肵�A�V���Q�W���t���������������āA���a�P�W�N�X���P������ݒu����邱�Ƃ������Ɍ��肵���̂ł���B
�@�Ȃ��A�ݒu�����̃n�_�c�ы提�̒S�����́A
�@�i�P�j�A�R�z�S�̂������������Î��̗����������~
�@�i�Q�j�A�����S��������~
�@�i�R�j�A���I�E���E���S�̈�~
�Ƃ���Ă����B
�@���ʂ̏����������A���㏐���ɂ͑O���[�c�э�Ə��������l�Y�����C���A�X���P���������ĊJ�����ꂽ�B
�@�܂��A���ɂ���ъ��ɂ̌��ݗ\��~�n�ɂ��ẮA�ΐ쐴�ꂩ��P�T�U�R���������A���P�X�N�U�����֊�t�����̂ł��邪�A��ǂ̈�����s��Ƃ������Ԃɒ��ʂ��Ē��ɂ̌��z�͗\��ǂ�����{�ł����A���̕~�n�͂��̌㌻�݂̉c�я��E���Z��~�n�ɏ[�����ꂽ�B
�ѐ��@�\�̉���
�@���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�T���ɗѐ��@�\�̉��҂��s���A���L�т̊Ǘ��͔_�яȂɈڂ����ƂƂ��ɁA�����ɂ͎D�y�E����E�k���E�эL�E���ق̌܉c�ыǂ��ݒu����A���̉����@�ւƂ��ĉc�я����u����邱�ƂɂȂ����B����ɂ���Ĕ��_�c�ы提�͔��ىc�ыǂ̊NJ�����Ƃ���ƂȂ�u���_�c�я��v�Ɖ��̂��A���Q�R�N�P�Q�����R�p�~�n���ɖؑ��������ĂW�P���܂�̐V���ɂ����z���Ă���Ɉړ]�����B
�@���N�P�O���ɂ͓����I�c�я����J������A���I�E���E�̓�S�����ǂ��邱�ƂƂȂ����̂ł��������ƂƂ��ɁA���������Î��̗��悪��m���c�я�����ڊǂ���A����ɁA�Q�X�N�V���ɂ͐X�c�я����J������ė����여��ȓ�̒n��͂��̊NJ��ɑ����邱�ƂƂȂ����B
�@�܂��A�O�ɂ��q�ׂ��Ƃ���A�������̌䗿�т͔��ىc�ыǂŊǗ����邱�ƂƂȂ����̂ł���B
���_�c�я��i�ʐ^�P�j

���a�T�R�N�x���݂ɂ����鍑�L�т̗��p�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�ۈ����i�ʐρ@ha�j
| ���� | ���@�@�� ����{�� |
�y�����o �h �� �� |
�y������ �h �� �� |
��@�@�� �h �� �� |
�y�����o �h���ь����n |
| �R�R�C�V�X�P | �O | �R�R�C�V�X�P | �O | �O | �O |
�ݕt�g�p�@�i�ʐρ@ha�j
| ���@�@�@�@�@�� | ���z�� �p�@�n |
�z�@�� �p�@�n |
�d�C�ʐM ���Ɨp�n |
���H���H �p�@�@�n |
���@�� �~�@�n |
���̑� | |
| �� �� | �ʁ@�@�� | ||||||
| �S�W | �P�P�P�D�U�S | �O�D�O�P | �Q�P�D�T�P | �R�U�D�X�P | �T�P�D�T�Q | �O�D�Q�Q | �P�D�S�V |
���Ƃ̊T�v
���E���i�ʂ̎��n�ސ��@�@�@�ސρim3�j
| ���@�E�@�� | �N �x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| �p �d | �p�@�@�� | �d�Y�� | �p�@�@�� | �d�Y�� | �p�@�@�� | �d�Y�� | |
| �� �� | �X�C�T�T�O | �O�@ | �V�C�O�O�S | �O�@ | �T�C�R�S�Q | �O�@ | |
| ���@�@�́@�� | �S�C�X�V�W | �O�@ | �U�C�Q�S�U | �O�@ | �S�C�X�U�Q | �O�@ | |
| ���@�i�@���@�� | �S�C�T�V�Q | �O�@ | �V�T�W | �O�@ | �R�W�O | �O�@ | |
���i�̐��Y�ʂƌo���@�@�ސρim3�j�o��i��~�j
| �� �� | �N �x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| �� �� | ���Y�� | �o�@�@�� | ���Y�� | �o�@�@�� | ���Y�� | �o�@�@�� | |
| �� �v | �U�C�S�R�U | �V�R�C�R�W�O | �Q�C�P�P�Q | �P�P�C�P�O�O | �Q�C�T�U�Q | �P�O�C�T�V�P | |
| �f �� | �� �� | �T�C�V�S�P | �@ | �P�C�W�R�W | �@ | �Q�C�Q�V�X | �@ |
| �� �� | �U�X�T | �@ | �Q�V�S | �@ | �Q�W�R | �@ | |
| ���؎}�� | �@ | �@ | �O | �@ | �O | �@ | |
�o��͑����Y�ʂɑ��鑍�o��ł����B
���E���i�̔̔��ʂƉ��i�@�@�ސρim3�j�o��i��~�j
| �敪 | �N �x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| �� �� | �ސ� | ���z | �ސ� | ���z | �ސ� | ���z | |
| �� �v | �@ | �X�O�C�R�X�W | �@ | �T�P�C�R�S�P | �@ | �S�W�C�T�V�R | |
| ���ؔ̔� | �S�C�T�V�S | �P�V�C�S�T�Q | �U�C�P�T�Q | �Q�R�C�X�X�X | �S�C�W�P�V | �P�U�C�X�O�Q | |
| ���i�̔� | �U�C�P�O�Q | �V�Q�C�X�S�U | �Q�C�R�P�X | �Q�V�C�R�S�Q | �Q�C�R�S�T | �R�P�C�U�V�P | |
���ю��Ɨʂƌo���@�@�ʐρiha�j�o��i��~�j
| ��@�� | �N �x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| �� �� | �ʐ� | ���z | �ʐ� | ���z | �ʐ� | ���z | |
| �� �v | �@ | �P�U�W�C�P�O�U | �@ | �Q�O�T�C�V�W�S | �@ | �P�O�O�C�R�T�X | |
| �X�@�@�@�@�@�V | �Q�T�W | �S�U�C�W�O�O | �P�X�Q | �S�R�C�W�P�Q | �P�X�O | �R�U�C�P�P�P | |
| ��@�@�@�@�@�A | �R�R | �U�W�O | �T�T | �X�T�P | �R�S | �U�X�U | |
| �ہ@�@�@�@�@�� | �Q�C�U�W�U | �S�X�C�T�R�T | �Q�C�W�U�R | �U�O�C�Q�X�T | �Q�C�X�T�V | �R�R�C�P�U�O | |
| ���@�@�́@�@�� | �@ | �V�P�C�O�X�P | �@ | �P�O�O�C�V�Q�U | �@ | �R�O�C�R�X�Q | |
��@�c�@�@���Y���i��{�j�ʐρi�u�j
| �@��@�@�� | �N�@�x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| ���@�� | ���Y�� | �c���ʐ� | ���Y�� | �c���ʐ� | ���Y�� | �c���ʐ� | |
| ���@�v | ��{ �P�C�O�W�X�D�S |
�u �U�P�Q�C�Q�O�T |
�X�O�O�D�S | �T�T�W�C�P�O�U | ��{ �X�U�R�D�Q |
�u �T�T�T�C�W�O�O |
|
| �j�t�� | �X�@�@�@ �M | �O | �@ | �O | �@�@ | �O | �@�@ |
| �g �h �} �c | �P�C�O�S�R�D�S | �@�@ | �W�W�S�D�U | �@�@ | �X�U�R�D�Q | �@�@ | |
| �J �� �} �c | �O | �@ | �O | �@�@�@ | �O | �@�@�@ | |
| ���@�́@�� | �P�D�W | �@ | �O | �@�@ | �O | �@�@ | |
| �L�@�t�@�� | �S�S�D�Q | �@ | �P�T�D�W | �@�@ | �O | �@�@ | |
���@�R�@�@�ʐρiha�j�o��i��~�j
| �@��@�� | �N�@�x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| ���@�� | ���� | �o�� | ���� | �o�� | ���� | �o�� | |
| ���@�v | �@ | �Q�V�C�V�S�W | �@ | �S�S�C�V�W�T | �@ | �T�Q�C�O�X�W | |
| �R�n���R�{�� | m�R �R�Q�V |
�P�Q�C�X�W�V | m�R �S�P�V�D�X |
�P�U�C�O�Q�V | m�R �S�X�R |
�Q�W�C�W�Q�W | |
| �n���ׂ�h�~ | �� �V�O�O |
�P�Q�C�W�P�T | ���މ^���H�� �P�C�Q�X�X |
�Q�T�C�T�V�W | �� �U�P�X |
�Q�P�C�Q�P�R | |
| �C�ݍ��h�n���� | �O | �O | �O | �O | �@ | �@ | |
| �ہ@�@���@�@�� | �P�D�V�R | �P�C�Q�R�R | �P�D�V�R | �P�C�V�R�P | �X�D�O�T �Q�D�P�O |
�X�O�O | |
| ���Ǝ{�݁E���� | �@ | �V�P�R | �@ | �P�C�S�S�X | �@ | �P�C�P�T�V | |
�с@���@�@�����i���j�o��i��~�j
| �@��@�� | �N�@�x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �T�Q�@�@�N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | |||
| ���@�� | ���� | �o�� | ���� | �o�� | ���� | �o�� | |
| ���@�v | �@ | �U�R�C�W�W�V | �@ | �V�Q�C�Q�Q�O | �@ | �T�S�C�V�X�R | |
| �ѓ� | �V�@�@�� | �O | �O | �P�C�R�R�O | �Q�O�C�T�O�X | m �V�V�X �T�R�O |
�Q�V�C�X�O�T �P�C�W�Q�O |
| ���@�@�� | �U�V�O | �P�R�C�S�P�W | �� �P�T�C�O�O�O |
�Q�P�T | �� �T�C�U�O�O |
�P�S | |
| �C�@�@�U | �� �X�S�C�O�O�O |
�T�P�C�S�U�X | �� �X�U�C�W�O�O |
�T�P�C�S�X�U | �� �P�O�T�C�O�O�O |
�Q�T�C�O�T�S | |
| ���؏�i�V����C�j | �O | �O | �O | �O | �O | �O | |
| �Œ莑�Y�E���̑� | �O | �O | �O | �O | �O | �O | |
�i�Ǔ��T�v����j
�c�я����̏��ݒn�A�Ǘ��ʐρA���Ɨ�
| ���@�@�@�@�@�� | ���@�@�݁@�@�n | �Ǘ��ʐρE���Ɨ� | |
| ���@�_�@�c�@�с@�� | ���_�� | �o�_���U�O | ha �R�V�C�V�O�V |
| ��c���S���掖���� | �V | ��c���S�U�U | �V�C�P�W�Q |
| ���_�S���掖���� | �V | �h���@�P�R | �R�C�V�T�V |
| ����S���掖���� | �V | �h���@�P�R | �S�C�V�X�P |
| ���֒S���掖���� | �V | �㔪�_��� | �S�C�Q�T�R |
| �k��֒S���掖���� | �V | �㔪�_��� | �S�C�R�X�W |
| ����S���掖���� | �V | ����P�T�X | �P�C�V�U�W |
| ���D�S���掖���� | �������� | �����D | �S�C�Q�U�W |
| �������S���掖���� | �V | �������� | �R�C�Q�W�S |
| ��ҒS���掖���� | �V | ���o�t | �R�C�X�U�U |
| �k��֑��ю��Ə� | ���_�� | �㔪�_��� | �O |
| ���_��c���Ə� | �V | ��V�U�̂Q | �u �P�U�P�C�R�S�U |
| ��������c���Ə� | �������� | ���x�� | �u �S�T�O�C�W�T�X |
| ��Ґ��i���Ə� | �V | ���o�t | �u �Q�C�R�O�O |
| ��@�ҁ@���@�@�� | �V | ���o�t | �u �O |
�i�P�X�V�X�@�Ǔ��T�v���j
��R�́@���Y��
�@��P�߁@�����O�̋���
��Z���̋���
�@�k�C�����ڈΒn�Ƃ��Ęa�l�ɒm����悤�ɂȂ��������ȑO����A��Z�����ł���A�C�k���A�C�l��݂͊ɃR�^���i�W���j���`�����āA�������s���Ď��������̐������c��ł������Ƃ́A�܂������^���̂Ȃ��Ƃ���ł���A�����_�n�������̗�O�ł͂Ȃ������B�܂��A�u�����v�Ƃ����n�����A�C�k��́u�I�@�e�V���@�y�c�v�i��K�ɋ�⡁i��ȁj�������鏊�̈Ӂj���N���Ƃ��Ă���Ƃ�����悤�ɁA�����̃R�^���͉݂͊�C�l����`������Ă������̂ł���B
�@�������A�A�C�k�ɂ�铖���̋��@�͗c�t�Ȃ��̂ŁA��ɂ�Ȃ������ď���Ă���T�P��߂�����A�ۖ؏M�𑀂��Ă₷�œ˂��A�����Ԃł������Ȃǂ̕��@�Ɍ����Ă����B�܂��A�I�b�g�Z�C���Ȃǂ̂��ߊۖ؏M�ʼn��ɏo��ɂ��Ă��A���܂艓���܂ł͍s�����Ƃ��ł��Ȃ������B���������ɂ߂�ɂ��A���R���ۂ̕ω����画�f�����Ƃ�����B���̈��Ƃ��āA�ӏt�A�������x�̒����ɐႪ�j�V���̂悤�Ȍ`�i������u�w���L�E�E�p�V�v�ƌĂj�Ŏc��A���ꂪ�����Ȃ������̓j�V�����߂��Ƃ����ċ��𑱂��A�܂��A���ɏo������Ƃ��o�i���j�̂悤�Ȋ함�ɏ悹�Ă���𗎂Ƃ��A���̏�Ԃɂ���ċg���������Ƃ����B
����̕ϑJ
�@�A�C�k�̎��R�ȓV�n�ł������ڈΒn�ɁA���X�ɘa�l���ڏZ���͂��߂�悤�ɂȂ����̂ł��邪�A�����A�C�k�Ƙa�l�Ƃ̊Ԃɖ{�i�I�Ȍ����������悤�ɂȂ����̂́A���O�˂̐����Ȍ�ƍl������B���Ȃ킿�A���O�˂��������ĉڈΒn������悤�ɂȂ��Ă���A�Ɛb�ւ̒m�s�Ƃ��ĉڈΒn��K���ɋ�悵�ďꏊ��^���A�m�s�傪���̒n��̃A�C�k�Ƃ̌��Ղɂ���ē����i�������A��A����肳���������������Ď����ɂ���Ƃ����A����ȕ��@���u������悤�ɂȂ��Ă���ł���B
�@���������o�܂̂Ȃ��œ��ڈΒn�ɑ����Ă������n���ɁA��c�Ǐꏊ�ƃ��[���b�v�ꏊ���ݒ肳��A�Ɛb�ւ̒m�s�n�Ƃ��ċ��^���ꂽ�̂ł���B���������āA������c�Ǐꏊ��[���b�v�ꏊ�Ɍ��炸�A�ꏊ�̋��^�ɂ���Č��Ռ����m�s��ƒn���A�C�k�Ƃ̑Γ����Ղ���ڐG���������悤�ɂȂ������A�₪�Đ��͓I�ɂ͒m�s�傪�D�ʂɗ����A����ɁA���l�ɂ��ꏊ��������Ɉڂ�ɂ�āA�a�l���A�C�k���g�����Ē��ڋ��Ƃ��o�c����悤�ɂȂ��Ă������̂ŁA���@���}���ɐi�����A��K�͉�����ȂǗl������ς����̂ł���B
�@�܂��A����ł́A�ꏊ�����l������̗��v�邽�߁A���ځE�ʖڂ����܂�������A�e���ȕi�X��n���ȂǕs���Ȃ��Ƃ������Ȃ�A�A�C�k�͂����̍s�ׂނ悤�ɂȂ��āA�e�n�ŕ������N���錴���Ƃ��Ȃ����B
�@���ɁA��c�Ǐꏊ���܂ޔ��٘Z���ꏊ�́A�a�l���ڏZ���ēy������҂������A�a�l�n�Ɠ��l�ɂȂ��Ă����̂ŁA���{���ڈΒn���������N�̊����P�Q�N�i�P�W�O�O�j�R���ɂ́A�������u�����v�i���Ɠ��i�̈Ӂj�Ɉ������Ƃ����߂ďꏊ��p�~�����B�������āA�����ɘa�l�̋��Z���������悤�ɂȂ��Ă���A�}���ɂ��̕������`�����A���@�̐i������l���̕ω����݂���悤�ɂȂ����̂ł���B
�@���̘Z���ꏊ�����̋L�^�͎��̂Ƃ���ł���B
�@��A���ٍŊ���ڈΒn�V���m�^���C���A���{�l�������j�t����l���\�n�A���ٍ݁X���l�戵��σj�����
�@�E�V�ʎ�v�\��j�t�\��u��ȏ�
�@�i�����\��N�j�\�O��
�@�����@�M�Z��
�@�ΐ썶�ߏ���
�@�H�������q��
�@�����̑[�u�ɂ��A�a�l�n�ƉڈΒn�̋����R�z���Ƃ��A�ڈΒn�֒ʍs����҂̐؎�����߂�֖���T�c���炱���Ɉڂ��ꂽ�̂ł���B
���l���̐���
�@���n���̋��l���ɂ��ċL����Ă�����̂Ƃ��ẮA���\�P�R�N�i�P�V�O�O�j�́u���\�䍑�G�}�v�Ƃ����n�}�̂Ȃ��ŁA�n���ɂ͓삩��u����ׁE���Ƃ����E�̂��ցE�䂤����ӁE����ʂ��v�̏��ŋL������Ă���A�g�䂤������h�ƋL���ꂽ�n��C�ʕ����ɁA�P�Ɂu�K���`�i���Ƃ����j�L�v�ƋL�ڂ���Ă���̂��A���̂Ƃ���ł��Â��L�^�Ƃ݂��Ă���B
�@�܂��A���ۂQ�N�i�P�V�P�V�j�ɖ��{�����g�̏������u���O�ڈL�v�i�ʖ����u���O�ڈΒn�o���v�Ƃ������j�ɂ��A
�@��A�y�Y�V�i�o����
�@��A�K���`
�@�ڈΒn�V���@���Ƃ����ցA�̂��ցA�䂤����ӁA����ʂ��A������A�ւ�ցA��������ցA�����A���Ƃ��A�Ɖ]���ɑ����\�悵
�Ƃ���A���Θp��т͐����Ȃ��I�b�g�Z�C�̎Y�n�Ƃ��Ēm���Ă����悤�ł���B
�@���̑��̎Y���ɂ��ẮA���۔N�ԁi�P�V�P�U�`�P�V�R�T�j�̂��̂Ƃ݂��钘�ҕs���́u�ڈΏ��ɕ����v�̂Ȃ�����E�^����A���ʂ͕s���ł��邪���̂��̂��L�^����Ă���B
�@�~�����A�C�k
�@�b���p�ɕ������鎞�͑����K��̔@�����Q���Α��������ďM�𑆎������ɂ��Âɑ��Ԗ}�E�Ԍv�ɂ����悹�������ȂĐ��l���i�ʐ^�P�j

�@��A���g�V���@���i�V���@��c�I�C���O�����V��c���V���a��a�o��
�@�ʁA���q�A���z�ďo���A�~�n�I�b�g�Z�C������
�@��A�����v
�@�E�̕����V���}���x���o�����f�A�^��O���N�S�\��
�@���̌サ�炭�͓��n���̎Y�z�𖾂炩�ɂ���j������������Ȃ����A���ݐX�����{�������ɂ���u���{���v���A���V�N�i�P�V�T�V�j�Ɍ������ꂽ�̂́A���̓����A���فE�T�c�E�����E���̑��̑��X�ɂ����āA�t�j�V���̑務�������A���������ꕔ�������Ă�������Ȃ��ƂȂ������߁A�����̃j�V����y���ɖ��߂ď������A���Ǝ҈ꓯ�����̗���Ԃ߂邽�߂̂��̂ł������Ɠ`�����Ă��邱�Ƃ���A�������������͂��߃��[���b�v���ʂ܂ő����ʂ̃j�V���������������Ƃ��z�������B
�@�܂��A�u�k�C�����Ǝj�e�v�i�k������ҁj�̂Ȃ��ɁA
�@�����T�N�i�P�W�Q�Q�j���D�����N���ѓc�ƎO��^�܍��q��͓��n������̋��ƉƂł����āA���̔N���������Ђ�������J�A�����̒f�R�����A�C�l�����C���đ�H�����s�������������Q�������B
�Ƃ���A����������̃j�V�����̐�����鎖��Ƃ�����B�������A���̎��Ƃ̐��ʂȂǂɂ��ẮA�n���ɂ����Ă͉������݂܂œ`�����Ă��Ȃ��B
�@�R���u�͑O�f�́u�ڈΏ��ɕ����v�̂Ȃ��ɁA
�@�z�q���G�A�͍��z�g�\�A�t���D�n���ٍ]����E�V���z�ϐ\��
�ƋL����Ă��邪�A���̐��ʂɂ��Ă͊����R�N�i�P�V�X�P�j�́u���ڈΓ������L�v�̂Ȃ��ŁA��c�Ǐꏊ�̃R���u�Z�Z�Z�Z�ʂƋL�^����Ă���̂����߂Ăł��낤�B�R���u�͂T�O������c�Ƃ��A�l�c����ʂƂ��Čv�Z���Ă����B
�@�������A���̂���͂��łɒ���U���i�����ւ̗A�o�i�j�ƍ������v�̑����ɂ���āA�R���u�̐��Y�������̌X�����݂��Ă������A�����͔��D���i�싂�j������𒆐S�Ƃ��ĉ��C�ݒn���ɂ����ẴR���u���i�ʂ��ǂ��Ē��d����A�p���Y�̂��͈̂�i�����̂Ƃ���Ă����̂͌��݂Ɠ����ł������悤�ł���B
�@���n���̏������L�^�u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�ɂ��Éi�V�N�i�P�W�T�S�j�̗l�q���܂Ƃ߂Ă݂�ƁA
�@�������N�V�i�C
�@���M���z�A�ʍs�M���z�A���{�M��\���z�A��n���M�O�z�A�����M�Z�\���z����B���ДN�i�ꔪ�l�j�̎Y���Y�����ɁA�i�����j�b���ʘZ�S���A��̔���S�\�Z�{�A�H�����Z�S�l���A�؎q�l�\�M��B
�@����c�ǁ@���I�C
�@�M�͓��M���z�A���{�\�z�A��M���z����A�Ԃ��ʈ���ԑ�j�뗬�A�ʍ��ԓ�S�O�\���B�i�����j
�@���ДN���̏��̏o�Y���́A�ʂ́Y���Z�甪�S���\�܊іځA��Y���Ȃ��A���N�N�͎O�S�іڂ���B�ʍ��z�떜��S�Z�ʁA�܍��z�Z��ܕS�c�A���肱�\�ҁA�喐��S�\�{�A�H�����Z�S�{�B
�@������
�@�M�͓��M���z�A���{�l�\�z�A��M�\���z����B
�@�Ԃ��ʈ���ԑ召�A�ʍ��ԓ�S�\���B
�@�ДN�o�Y�����ʁY���Z�甪�S���\�܁Y�ځA��Y���͂Ȃ��A���N�N�͐��S�\�Y�ڗL�A�ʍ��z�ꖜ�S���\�Z�ʁA����q�S�ҁA�܍��z�ܐ甪�S�c�A�喐�S�\�{�A�H������S�{�A�����͔���\�܁Y�ڂ��܍����O���ʂƂ��B
�@������
�@�M�͓��]�M���z�A���{�\���z�A�����M�l�z����B
�@�Ԃ��ʈ���j�ꗬ�A�ʍ��Ԕ��\���L�B
�@�ДN�o�Y�����ʁY�����\�O�Y�ځA��Y���Ȃ��A���N�N�͎O�S�Y�o��B�ʍ��z�O��Z�S�\���ʁA�܂���ԓ�玵�S�c�A����q�\�ҁA�喐�S�\�{�A�H�����l�S�{�B
�Ƃ���A�K�������S�e��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����ɂ����邱�̒n���̋��ƊT�v��m���|����ƂȂ�ł��낤�B
�@��Q�߁@�����N��̋���
���Ɛ��x�̉��v
�@�����N��ɓ���A�J��g�ɂ��ꏊ�������x�̔p�~�i�����Q�N�j�A���ꎝ���x�̔p�~�i�����X�N�j�ȂǁA���Ɛ��x�ɉ��v���������Ă��������A���łɓ��n���̎R�z���ꏊ�͌������N�i�P�W�U�S�j�ɑ����ƂȂ�A�ɒB�E�����̐������Ō�ɐ������x���p�~����A����o�c��]�҂ɂ͏o��ɂ���đݕt������̂Ƃ���Ă������A���ꎝ�̉�����Ȃ������̂ŁA�����E�R�z���̗����Ƃ����̐��x�̉��v�ɂ͒��ڂ̂������������̂ł͂Ȃ������B
�@�������A�S���I�ɂ͕����I�ȋ���x�z�̐��͈ꉞ���ł��A���Ƃ͒n���s�������̕z�B�ɂ���ĕی�����܂肪�s���邱�ƂɂȂ����̂ł��邪�A����̐�L���p�Ɋւ���K��͕K���������m�ł͂Ȃ��A�������߂��镴�����₦����������ł������Ƃ����B
�@�����P�O�N��㔼�ɖK�ꂽ�s���́A���Ǝ҂ɓ��ɐ[���ȉe�����y�ڂ����̂ł��邪�A���ٌ��͂P�V�N�T���Ɂu���Ƒg�����v�����z���A���Ƒg����g�D�����ċ��Ǝ҂͂���ɉ���������̂Ƃ��A�g���͐\���K�����߂Đ��Y���̗��l�̖h�~�Ƃ��̉��ǂɓw�߂邱�ƂƂ���ȂǁA���Y�Ƃ̎����܂�ƐU������ɂ��������̂ł���B
�@�������A���ꕴ���͖k�C���Ɍ��炸�S���I�ɂ킽���Ă����̂ŁA���{�͂P�X�N�T���Ɂu���Ƒg�������v�����z���A���Ƃ̌������ꊇ���ċ��Ƒg���ɖƋ����邱�ƂƂ����B�����āA���̋�̓I�ȓ��e�ɂ��Ă͑g�������̎�茈�߂ɔC���邱�Ƃɂ���āA�����̒������ێ����悤�Ƃ�����Ƃ�ꂽ�B
�@�����͓��N�P�P�����̏������Ǔ��ɕz�B�������A���łɋK��̔F�������Ƒg���Ȃǂ́A����K��̉���������Ƃ��ɂ��̏����ɂ��g����g�D���邱�ƂƂ��ꂽ�B�������A�������łɑg�D����Ă����O�g���i�����E�R�z���E���_�j�ɑ��A���̏��������ڂǂ̂悤�ɍ�p�������͖��炩�ł͂Ȃ��B
�@�����P�V�N�i�P�W�W�S�j�T���P�R���t���ٌ��b��\�܍��ɂ�鋙�Ƒg�����͎��̂Ƃ���ł���B
�@���Ƒg�����
�@�����@�{���Ǔ��ɉ��āA�ߋ��A�̑��̋Ƃ��c�ނ��͓̂s�č��������点���ށB
�@�����@���Ƒg���͍����E���E�G���E�L���E�G���i��̋����]�Ӂj�y�̑��̊e��ɋ敪���B
�@��O���@�g���͈꒬�����͐������A�����Ĉ�g�ƂȂ��A����y�������������ߑ����͌S�撷�̎w�肷�鏈�ɏ]�ӂׂ��B
�@��l���@����g�ɉ��Đ\���K�����ߐ��Y���l�̕��Q��\�h���]���̉��ǂ̕����d�邱�Ƃ�ׂނׂ��B
�@����@�\���K���͖��g���̓��{���ݐЋ��������đ��Ă����ߐ�������A���S�撷���o�R���Č����̔F���ׂ��B
�@�A���{�������o�҂̋����͌����̔F������\���K���ɑ��A�X�����ً͈c��q������B
��Z�� ���Ǝ҂͑����Ƃ��Ȃ���Ɨ~���钬���̑g���ɕғ�����������ɕt�����R���q�בg���ɕғ�������Ƃ��čb�����`�̊ӎD�����Ƃ̂Ƃ��͕K���g�т��ׂ��B

�@�掵���@���ƎҌٕv�����O���ɓ������������`�̊ӎD���g�т��ׂ��B
�@�攪���@��������͑g���ɌW��o���g����蒥�������嫂��S�撷�̔F���o�Ď{�s������̂Ƃ��B
�@�����@��������͑g����̏����ɏ]�������Y��̎��ɕt�����̎���ɓ��ӂׂ��B
�@��\���@��������͑��g�����e�����n�̕������̖����Ɏ���V����т��u����v���A�ދ����Ԓ��ٓ����S�A���ԁA�D��̗��o�ɜ�肽�鑹�Q�����������ׂ��B
�@���̏����Ď��̂悤�ɋ��Ƒg���K����߁A���ٌ��ߎ��C�����\�������̂ł���B
�@�������Đ݂���ꂽ���Ƒg���̑�\�҂̌ď̂ł���u����v���A�����P�W�N�T���ɂ́u���Ǝ���l�v�ɁA����ɁA�Q�R�N����́u���Ɠ���v�Ɖ��߂�ꂽ���A�e�g���̗���\�҂͎��̂Ƃ���ł���B
�@���������Ƒg���@���؎��O��E���������Y�E�����Î��Y�E��R��V��
�@�R�z�������Ƒg���@��{�e���E����V�g�E�������g�E��c�Ћg
�@���_�����Ƒg���@���J�v�O�Y�E�������O�Y�E�Ñ��Y
�@�R�z�S��\�O�g�R�z�������Ɛ\���K���Ꭶ����Ύ��̂Ƃ���ł���B
�@�R�z�S��\�O�g�R�z�������Ɛ\���K��
�@���K��n�����\���N�{���b��\�܍��z�B���Ƒg�����j�˂�K��X�����m�j�V�e���g���j�ғ��V���ƃ��c���ҟӃe���K����V��w�X�w�J���X�˃e���ړI���胀�����m�@�V
�@����
�@����
�@�����@�g�������j�e�ߋ��̑��m�ƃ��c�}���g�X�����m�n���Ƒg�����j�˂�g���j�ғ��V���K�m�葱���o�e�c�ƃX�w�V�B
�@�����@���g���j�ғ��X�����m�n�g���e�r���|�g�V�݃j����~���V�������c�ƃ�����X���m�������V�����ɐB�m�_�j���ӃV�e���m�c�ƃ��V�e�v�X�����i�����R�g���׃��w�V�B
�@��O���@�ߋ��̑��j�փX����f�̓n�Ӄe�g������l�A��X�w�V
�@��l���@�e���m�g�p�X���ߋ��̑��j�փX����B�m�����㏞�n�������n�����ȃe����j���e�n���e�꒣�냒���V���ăj�o�^�X�w�V�A�ރ��V���j���������l�j�戵���i�X���m�g�X
�@����@�e��m���ƍ̑��g���I���j�����n�����n�����ăj�L�V����l�j�͏o�w�V
�@��Z���@�e�����l���n���������g���[�����Ӄ����֕U���y�������֏o�Y�l�������L�Z���؎D���{���X�w�V�B
�@�掵���@�ߋ��̑��j�ۃV�s�ǃm���i�������N�n�������ԓ��m�ށj���ȃe���ƍ̑��m�ƃ��i�X�w�J���X�B
�@�攪���@���e���ԃ��ȃe���ƃ��c�����m�n�����n����P�^���ʒu�O�����j�]�X�w�J���X�B�A�q�؊C�ʐ}���g嫃����ԃ������_�ԃ��t���X�w�J���X�B
�@����
�@����
�@�����@�����ԗg�n���������֎l�Z�Z�ԕ���Z�Z�Z�ԁi�Z�ڈ�ԃg�X�j�g�胀�A�A�V�]�O�C�ʔq����P�^�����m�n�����j��X�B
�@���Z���@�����ԃj�p�q�^����i�����}�c�J�C�A�C�J�����j�I�ƒ��`�j�Ӄ��i�N��Еt��g�ԓ��j�K�X�V�Q�Z�T�����v�X�B
�@������@�����ԃn���ԕ��W��m���֓��������T�X�B
�@������@���W�i�L���Ԃ֑����ԃ������Z�����������V�e�����t���R�g�����X�B
�@���O���@�����ԃn�ʖ����ԃj�كi���R�g�i�L���m�g�X�B
�@�ʋ�
�@��O��
�@���l���@�ʌ��ԊԐ��n���������֎O�Z�Z�ԕ��O�Z�Z�ԃg�胀�i�Z�ڈ�ԃg�X�j�A�V�]�O�C�ʔq����P�^�����m�n�����j��X�B
�@�����@�ʌ��ԃj�p�q�^�������m���u���n���Z���m��j�˃��w�V�B
�@���Z���@�ʍ��ԏ�n���ԏꏊ�m�O���x�i�V�g嫃����ԃm�O��}�܁Z�ԃ����茚�ԃm�V�Q�j�i���T���l����X�����m�g�X�B
�@��ꎵ���@�ʍ��ԃ��C�ʂ֓����X���n�K�X���v�ȑO�j�������m�g�X�B�A�V���v�O���g�m�^�������X���s�\�J���m�Q�W�^���g�L�n�{���m�����j��X�B
�@��ꔪ���@�ʌ��ԕ��j���ԃg�����ʃm���҃������R�g�����X�g嫃����ԉc�Ǝ҃n���v�O�j�㗤�X�w�V�A�A�V�{���m�ꍇ�j���e�n�ԃ������X���n�m�g���y��l�֓͏o�w�V�A�ރ����A�ԃn�͏o���j�y�n�X�B
�@�ٖ�
�@��l��
�@������@�ٍ��ԃn�����m�C�ʃj���e�{�s�X���������g嫃��b�m�D�j���e�����^���������m�D�j�e���j�ԃ������V���ƃX�������X�A�A�V�{���m�ꍇ�j���e���L�V�ߎґ��ߖT�m���v�i�D�����]�t�j�O���ȏ㗧��V���J�ۃ��胀�����m�g�X�B�ރ����A�n�ꎵ��A���m��j�����B
�@���Z���@�����ԃn���������֎l�Z�Z�ԕ��܁Z�Z�ԁi�Z�ڈ�ԁj�g�胀�A�A�V�]�O�C�ʔq����P�^�����m�n�����j��X�B
�@������@���g�ԍ��ԃn�����j���e����X�����W�P�i�V�g嫃����m�g�������j���e�Y�ƃX�����m�n���g������m�w������N�x�V�B
�@������@���l�m�ޓ�i�����n�C㊓����]�t�j�ԓ��j�W�Q�Z�T�����v�X�B
�@�̑�
�@���
�@���O���@���z�̎���Ԓ��n�{�D���ݒu�V�̎��m�ۃn���e�{�D�m�w���j�]�t���m�g�X�B
�@���l���@���z�̎�m�ב��m�g���������҃��׃X���m�n���g�����ト���m�Y�˃����Q�X�w�V�B�ލ��z���ꃒ�v�X���g�L�n���x�i�L�l���j���b�X�w�V�B
�@�����@�b�m�g���������m�g�������֗������A���̑��m�ƃ��׃X���m�n�\�e��������֓͏o��������j���e�n���m�g������֒ʒm�V�u�N���m�g�X�B
�@���Z���@�������z�n���l�X���j�����^���z�����l�X�������X�B
�@����@�ߋ��̑��m�����m���j�������l�������胁�������ト���\�e�g�����֕X�w�V�B
�@��A���z�@��A���C�l
�@����@�g������y������l�n�i�ʊ��㓙�j�\�e���ӃX���n�ܘ_���c�����O��E���l�l�j�A�L���n�_���X�w�V�B�A�V�{���m�ꍇ�j���e���l�l�n����l�m�_���������R�g�����X�B
�@������@���N���z�̎�������ƃm�]�Ƀ��ȃe���z�����m�V�Q�������p�V���c�Y�����B�m�׃��C������l�X�����v�X�A�A�V���������҃m���m�n���z���l��{���m��g�V�e�D���z��l�j�t�i��܍Έȉ������j���܁Z�K�����o�X�w�V�B
�@��O�Z���@���C�l���n���i�����m�K�X�ߊl�X�w�V�B
�@���
�@��Z��
�@��O����@���\���K��j��t���m�n���Z�Z�~�ȉ���~�ȏ�m���������o�T�V���w�V�B��V���������o��L�����͎҃n����ȏ㎵���ȓ��m�o�������~���w�V�B
�@��O����@���҃A���g�L�n����j���e�[���R�V���������o�T�V�����m���z���ڎ��V�˒����o�e�S���m�F����P�{�s�X�����m�g�X�B
�@��O�O���@�����y���z�d�B�m�^�������V�^�����z�n��j�˒�����j���~�V�u�L�{���B�Y��m��p�j���c�A�ރ����x�o���v�X���g�L�n�S���m�F���o�����m�g�X�B
�@��v�y����
�@�掵��
�@��O�l���@�{�g����W������p�n�Ӄe��N�m�n���j�����\�Z�����V�S���m�F���o�e�{�s�X�w�V�B�ރ��Y��m�⏕�g�V�e���ƎҌg�уm�ӎD�ꖇ�ɍs���ܑK��������������j���e�V���J�o�[�����ăj�X�w�V�B�A�V���Ɠ�]���X�����m�n��܍Έȏ�j�����s�⑴��ޖ������X�w�V�B
�@��O���@����j���e�g���j�W���������ߌ��V���N����Z�����x�������c�N���g���j�X�w�V�B
�@��O�Z���@��������ֈΘJ�g�ꃖ�N���O�Z�~�x���V���c���Ə�j�t�o���m�߃n�ח���g����j�t���܁Z�K���x���X�w�V�B
�@��O�����@���K��{�s�㍷�z�A���g�L�n���g���m���{�Ћ�������m�㌧���m�F���o�X���X�w�V�B
�@��O�����@��������C���n���N�g�X�A�A�������I�m�߃n�O�C�m���m�đI�X�����W�P�i�V�B
���Ɩ@�̐���Ƒg���̉��g
�@�����R�S�N�i�P�X�O�P�j�S���ɋ��Ɩ@�����z�i���R�T�N�V���P���{�s�j����A���ƌ��E���Ǝ����܂�E���Ƒg���E���Y�g���E���ƌٗp�W�̎����܂�Ɋւ���K�肪�݂���ꂽ�B�������āA���{�ɂ�铝��I�ȋ��Ɛ��x���m�������ƂƂ��ɁA���ƌ��i��u���ƌ��E��拙�ƌ��E���ʋ��ƌ��E��p���ƌ��Ȃǁj�����߂Ė@��������A�������A�����Ƃ��Ė��m�ɋK�肳���ȂNjߑ㉻���}��ꂽ�B�����āA���Ƒg���͉������̂��ߋ������ƌ������L���A�܂��A������s�g���邽�߂̌����`���̎�̂Ƃ��ĔF�߂��邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@����ɗ��R�T�N�T���ɂ͋��Ƒg���K���E���Y�g���K�������z����A�U���ɋ��Ɩ@�{�s�ב��i���߁j�����z�����ȂǁA��A�̊W�@�߂��������ꂽ���A�����V���x�̎{�s�ɂ���ď]���̋��Ƒg�������i�����P�X�N����j�ɂ�鋙�Ƒg���͐��Y�g���Ɖ��̂���邱�ƂɂȂ����B
�@���̓����ɂ����鐅�Y�g���̎�v�Ȏ��Ƃ́A����܂ł̋��Ƒg������Ɠ��l�ł͂��������A���Ƒg�������ƌ��ƌ��т����o�ώ��ƒc�̂̐��i��҂����̂ɑ��A����ΐ��Y�w���Ȃ�тɔɐB�ی�c�̂Ƃ������i��҂��̂ł������Ƃ����B�����������x�ɂ��ڂ����o�߂͕s���ł��邪�A�����R�U�N�Q���P�Q���X���Ɂu�����R�z���Y�g���v���ݗ�����A�R�z�����ɓ����Y�g����P�V�掖�����A���_���ɓ���P�W�掖�������ݒu����Ă���̂ŁA����炩�琄�@����A�������ɂ�����P�U�掖�������݂����Ă������̂ƍl������B
�@�܂��ڍׂɂ��Ă͕s���ł��邪�A�������ł͂��̐V�������Ƒg�����x�ɂ���đg���ݗ��̏�����i�߁A�S�O�N�R���P�X���Ɂu���������Ƒg���v��g�D�����Ɠ`�����Ă���A���S�P�N�S���Q�R���ɂ͔_������b�����p���ƌ���i�R���u�E�i�}�R�E�^�R�E�m���E�M���i���\�E�j�̖Ƌ������Ƃ����L�^���c����Ă���B�Ȃ��A�k�C�����Ǝj�ɂ���Ă������R�U�N�̊�����Ƒg���̐ݗ����삯�Ƃ��āA�S�O�N�܂ł̐V�g���ݗ������u�����v���܂߂Ă킸���Q�S�𐔂���ɂ����Ȃ��̂ŁA���������Ƒg���̐ݗ��͑S���I�Ɍ��Ă��������ł������Ƃ����悤�B
�@�����S�R�N�A���Ɩ@�̑S�ʉ����i���S�S�N�S���P���{�s�j�A���Ƒg���߁i���O�{�s�j�A�S�S�N���Ƒg���o�L�K���i���O�j�Ȃǂ̐���ɂƂ��Ȃ��A���Ƒg���Ɋւ���K��͈�i�Ɛ������ꂽ�B���Ȃ킿�A�������Ɩ@�ɂ����āA
�@���Ƒg���n���ƌ���N�n���������擾�V���n���ƌ��m�ݕt����P�g�����m���ƃj�փX�������m�{�݃��׃X���ړI�g�X�B
�Ƃ��ċ��Ƒg���̖ړI���g�傳�ꂽ�ق��A
�@�P�A���Ɩ@�̋K��ɂ��ݗ��������̂łȂ���A���̂̒��Ɂu���Ƒg���v�Ȃ镶����p���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƁB
�@�Q�A���Ƒg���̐ݗ��͎傽�鎖�����̏��ݒn�œo�L���Ȃ���Α�O�҂ɑ��R�ł��Ȃ����ƁB
�@�R�A�g���̐ݗ��͒n����ɏZ����L���鋙�ƎҌܐl�ȏ�̔��N�ŁA�������Ǝ҂̎O���̓�ȏ�̓��ӂ��K�v�ł��邱�ƁB
�@�S�A�n�搅�ʂ̐�p���ƌ��͑g���ɂ̂ݖƋ����邱�ƁB
�Ȃǂ���߂�ꂽ�B
�@�����������x�̊g�[���āA�S���e�n�ɋ��Ƒg���̐ݗ��@�^���݂�ꂽ���A�����ɂ����Ă͑厚�R�z���������Ƃ���u�R�z�������Ƒg���v���g�����X�X���������đ吳�W�N�i�P�X�P�X�j�T���R�O���ɁA�܂��A�厚���_�������Ƃ���u���_�����Ƒg���v���g�����P�T�T���������ē��N�U���S���ɁA�Ƃ��ɐݗ��̔F�Ă��ꂼ��o�L�����������B
�����āA�e�g���Ƃ��n��C�ʂɂ��Đ�p���ƌ��̖Ƌ�����ȂǁA�ړI�B���Ɍ����ĉ^�c���ꂽ�̂ł���B
�@�������A���̊Ԃɂ����鐅�Y�g���̋��p�ɂ��Ă̎j���͑S���Ȃ��A�ڍׂ͕s���ł���B
���Ƃ̌i��
�@��������̌i���ɂ��Ă͌n���I�ɂ܂Ƃ߂��j�����Ȃ��A�f�ГI�Ȏj���ɂ���Đ��@������x�ɂ����Ȃ����A�����P�P�N�i�P�W�V�W�j�̔��ِV���́u�_���ʐM�v�ɂ��A�������̊T���ɂ��Ď��̂悤�ɕĂ���B
�@�������͌ː���l�Z�ˋ��A�l�����O�Z�]�A���Ƃ͐Αq���ɓ����B�i�����j�C�Y���ʁE�فE���E���E���z�E�I�E�C�l���ɂāA���N�̎��n�͐��ʂ��O�S�Β��A���Y���ܕS�Η]�A�فY���O�\�A���\����Ȃ肵�c�c�B
�@�܂��A�����P�W�N�ɂ̓C���V�̑務�̏ɂ��āA
�@�R�z�S���_�����R��y�э���A�����������|���y�c�������ď\���̈Əo�҂��͋���U���R�O�����ɒ��肵�A�{���i�����j�ꔪ���܂Ŗ}����S�]�Ύ�g�����̓���l�ɂčł�������グ���͓�S�l�\�Η]�Ȃ肵�Ƃ����B�������̖͗l�����ċX������Γy�p�ɓ���Β�߂đ��z�̎��n����ׂ��c�c�B
�ƕA����ɂP�X�N�́u�_���ʐM�v�́A
�@�_�U���R�z�S���_���͘Z���\���������يC�݂Ɋ���A�����\�ܓ�����苙�Ƃɒ��肵�A������\�ܓ����Ɏ���Ă͉��݈�ʂ��ً��ɂ��đ��邱�Ɛ��鐷�Ȃ�B������\�܁A�Z���Ԃ̎��n����ܕS��E����l�돡�덇�ɂ��āA��N�ɔ䂷��ΎO�S�Z�E��ΎO���O��������B�R�z�S�̔@���͖��N䊎�i�z��Z���ܓ�����̏́j�O�����ي�ɁA�{�N�͘Z���\��������钥������o�����Ɉ˂�A�����\�ܓ�����蓊�Ԃɒ��肹���ɋ��Ԃɏ[������B
�Ƃ���A�܂��T�P���ɂ��ẮA
�@�_�U���R�z�S�R�z���E���_�̗����́A�㌎������茚�Ԍ܂����A���ԓ�l����A��[�l�A�]���ғ�Z�O���B
�ƕĂ���B�Ȃ��A�R�z���̃R���u�ɂ��ẮA�@�{�N�͊������̓����D�V�C�����ɂ��Ċ����ł��X���B���z�̎�̂ݎg�p����D�͖��V�A���z�̎撆�g�p����D�͎����y��M���g�p������̂Ȃ�B
�Ƃ����āA�����g�p�������D�́A�����V�A��M�P�V�ŁA�]���҂͂Q�S���ł���A���i�͎�ɓ��c���z�A���؍��z�ȂǂƂ��āA���ْn���̊C�Y���≮�֔̔�����Ă����Ƃ����B
�V�y������̎���
�@�����Q�O�N�i�P�W�W�V�j�P�O���Q�T���̔��ِV���́A�V�y������̎��������̂悤�ɏڂ����`���Ă���B
�@�}���V�y�S�̋���Ɖ]�ӂ͈��ԏꏊ����P���ɂ��āA���͉����ɒB�^�A�����^�̎ꏊ�Ȃ肵���A���v��N�����ԏ�̂Ƃ��ɍۂ��A�����̏Z�l�|���F�g�Ȃ���̔V���p���A�ېV�̌�Ɏ���A���ɓ��l�̏��L�ƈׂ�A�����Z�N�{�q�|���K���i��j�V������A�����N�X�����ɉ����č����Ԃ��ƂƂ����肵���A�����\�Z�N�Ɏ���A��ɔ��ٌ��B�Ɉ˂�ėV�y���͌��C�ʉ��֎O�S�ԁA���ܕS�Ԃ̒��͖��N�O�����Z���܂ŁA�\�����\�܂ŔN���Z�����̊ԁA��؋����ւ����Ă��ȗ��A���ɉ͌��C�ӂɋ�������L����|���K���i��j����A�������Ƃ��c�ނ��Ƃ��B����⑼�̐l����B�����ĖԂ����邱�Ɣ\�͂���ׂ��B�i����V�y����ɖ����\��N���������݂�����ׂȂ�j�B����̊Ď�l�̂ݕ�J�Ƃ��ď\�����\�܂ŎO�����Ԃ͖���T���Ɉ��Â͓��ɉ��Ĉ��Ԃ��ׂ����Ƃ���ɋ����ꋏ��݂̂Ȃ�A��N�܂ł͒N�����ӂɉ��Ĉ��ԁE���ԓ����Ȃċ��l��������̂��炴�肫�B�{�H�Ɏ���|���K���i��j�n�߂ĉ͌��̓��S�ԋ��̊C�݂ɍ����ԏ��q�������A�q�ʼn͖k�ꗢ��̏��ɊJ���n�̍��v�Ԗ^����������q���o�肵������Ȃ�A�V���Ɍ����@�����ق̏��l�^�����N�n�߂Ĉ��Ԃ��ׂ����Ȃǂ͏������`�̖����b�ɂāA�����ԂȂ�r��ɂĉԁX�������l�Ȃ��]�X�͐r�����B�����͒m�炸�B���y�n�ɂĂ͎��Ԃɂ��炴��Έ��Ԃ͎��݂Ȃ炸�Ǝv���B�����v�Ԗ^�̎d���ɂČܓ��̌��Ԃ�����Ȃnj����ǂ��A����ȑ�R�̖Ԃ͉������Ă�ς�ɂ�B�{�N���Ԃ̌���Ɖ]�ӂ́A���ߖT�ɂĂ͎R�z�����F���K�A��������O�A���������|���A���_�����V�y���A�������И��̌܃����ɉ߂����B�����Ė^�����K�͎R�z�����̋����ԁA��O�͒|���K���i��j�A���|���͎R�ˑ����̖ԂɂāA�ߏ�O�c�͑�ԂƏ̂��錚�ԂȂ�B�V�y���͖��|���K���i��j�A���䘻�͍��v�Ԗ^�����J���̍��c�����q�Ƃ��]�ӎ҂Ƒg���ɂČ���Ԃ̓��A�ߏ��c�͑��Ɏ�[�i�Ƃ肨���j�Ə̂����ԎO���̈�T���̈ꋖ�̏��������ԂȂ�B�Ԃ̑召�͎b���[���A���ӛ߂Ɍ��ׂ��]�n�Ȃ��A�ނ̌ܓ��̖Ԃ͉����̊C�ɓ�����ς�ɂ�B�r�������ׂ��炸�B�G��̎����͎��ۂ̎d���Ƒ�ɑ��Ⴙ����̂���Ɉ˂����������߂�ׂ߁A���n��������̎����������邱�ƍ��̔@���B�v�����u�z�c�L�̔@���͉��ł��X����ǂ��A��N�������X���k������ւ���ǂ��A�{�N�͏�������ꂽ�����A�����������������B���ɐ���������Ȃǂ͉����̘b�ɂ�B�ȂĂ̊O�̕����Ȃ�B�v�����͖{�N��������N�ƌ����A�߂Ɍ��Ă�����K�E��O���͒��X���l���肵�R�A�ł͏����A������l�Ɏn�I�[����T������鋎�N�܂ł̗l�Ȍ܌�墂��Ƃ��Ȃ��́A�l�C�ɂ߂ċX���B
�@���̋L���́A�P�O���P�P���̓����Ɍf�ڂ��ꂽ�L���������ɑ��Ⴀ��Ƃ��Ď����������߂邽�߁A���̐��b�l�ؑ��^�����e�������͂ł���B���Ȃ݂ɁA���̌��Ƃ�����L���͎��̂Ƃ���ł���B
�@���V�y���ɂĂ͔��ُ��l�R�{���V���������N�n�߂č����̈��Ԃ������肵���A���ԂȂ�r��ׂ̈߂ɉԁX�~���l�Ȃ��I�ɒ��₵�����肵���A�{�N�͓����J���n���Z���v�Ԗ^���̎d���ɂČ��Ԍܓ����Ȃċ��l�ɒ���̗R�ɕ����B���������z�c�L�L��p��Ǝ��n���A���L�ɐ������邪�A���X�̗Ǖi�Ȃ�A�퐷��ɐ�������Ɖ]���B
�����E�R�z�����E�̊m�F
�@�����Q�P�N�i�P�W�W�W�j�����ł͑S���̋��꒲�������{���A�u�Ύ�E��u�E�n������m�@�L�n���E�G���c��w�T�����ȃe�A����m���A���ʁA���o�Ԑ��������V�A�ϓ_���f�m�������Z���v�Ƃ��Ă��邪�A�����R�z�����Ɨ������Ƃ̋��E�A���ɊC�ʋ��ɂ��ĕ������J��Ԃ���Ă����B���̂��߁A�����Q�V�N�V���T�c�S�O�O�S��������W���̏o�������߁A��������l������̌��ʁA���̋��E���Ċm�F�̂����A���̂悤�Ȑ������o���Ė��𗎒��������B����ɂ��ẮA�������ɂ����Ă�������l�̐������o�������̂Ǝv����B
�@�������g�R�z�����g�m���E�m�F
�@�䐿��
�k�C���n���������S�������y�����_�U���R�z�S�R�z�����g�m���E�m�c�j�t�A�N�X�����������ԋ��ƋG�߃j�n���A���j�V�e�׃��j������s�s���j�t�A�]�e�����V�ʁA���ݒ���\�����m���A�����N������\�ܓ��T�c�O�O�S���L�C�V���ې^�a��o�����n���������A��������l������m���A���m�����j����v��j�t���i�A�����ȃe�䐿�d���B
�@���@�����A�s���E���j�]�O��m��m�ʁA���̖�c�ǐ쒆�����ȃe�X���R�g
�@���@�C�ʃm���n���N�j�V�σm�여�A���`�샍���ȃe�X�����@�ȏ�
�@������\���N�������ܓ�
�@�k�C���_�U���R�z�s�R�z����
�@����l�@��������
�@�A�V�{�l�s�݃j�t����Z�X
�@����
�@����l�@��R�^��
�@�����\�O�g
�@���Ɠ���@����V�g
�@����R�z���O�ꃖ��
�@�˒��@��c�v�O
�@�T�c�S�O�O�S���L
�@�C�V���ې^�a
���������̋���
�@�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�̔��_���̋��l�����݂�ƕʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A����ɂ��A�����̋��Ƃ̓j�V���̖L�E���ɂ���ċ��ƌo�ς����E����Ă����悤�ł���B���Ȃ݂Ƀj�V�������ɂ��Ă݂�ƁA�S�P�N�ɂ͎O���Z�A�S�R�N�ɂ͎O�܁Z�Z�ȂǂƖL���������Ă����B
�@���������̂���A���ō쐬����������̒��ł́A
�u�������Y�Ƃ͔N�𒀂��ċ��l�������A�V�ɉ�����ɓ��Ǝґ����A�����n�炵�A���ǐi����}��̎v�z�ɖR�����A�`�ɋ������V��҂��Ċl������ɉ߂����B�̂ɋ������V�����ɂ���ĖL������������ɂ���B�L�s���Ɏ��R�ɘ߂�̏�Ԃɂ��čX�Ɍ���ׂ��̐��т�F�߂��v�i�����č������j
�ƍ��]����悤�ȏł��������B
�@�������`������Ƃ���ɂ��A������j�V���u�[�����A�����̖��ɑ�s���Ɍ������Ĉȗ������������A�|�Y������̂��o��L�l�ł������Ƃ����B
�����S�O�N���_�����l����
| ��@�� | ���l�� | �Y�@�@�z |
| �j�V�� | �� �P�C�W�X�X |
�~ �Q�S�C�U�P�U |
| �T�@�P | �R�R�W | �X�C�T�S�S |
| �C���V | �Q�X�T | �R�C�U�O�T |
| �T�@�o | �S�O | �R�X�X |
| �J���C | �X�W | �W�V�O |
| ���@�v | �Q�C�U�V�O | �R�X�C�O�R�S |
�@�܂��A�C���V�̋��@�Ƃ��Ă͒�u�ԈȊO�Ɉ����ԁA�����ԂȂǂ��s���Ă����B
�@�����̖����珺�a�̏��߂ɂ����āA���Ƃ̑S��������}���������̔��_���݂̏ɂ��āA���Y���ɍݏZ���ċ��ƌo�c���s���Ă������c�~�g�́A
�@���͐X�������̂Ƃ��Ɉ�ƂƋ��ɔ��_�ɘA����ė����͖̂����O���N�i���Z�l�j�̂��Ƃ������B�������傤�ǓS���̕~�ݍH�������Ă�������ŁA���̂��딪�_�ɂ́A������Z�Z�ˈȏ�̋��Ƃ����荞��ŋ����c��ł����B���Ƃ͈Ⴂ���̓����́A�k�C�����݂̎��鏊�Ńj�V�������Ă����悤�ɁA���Θp�ł��{����̂Ƃ͈���������j�V���������Ɏ��Ă����B���j�V���̒n�����ԂƂƂ��ɁA�T�P�E�}�X�����������ł������B�j�V���͌��ԂŎ��A�����l��N����͑�X���̎����ŁA�O�Z�Z�Έȏ�͐��g������Ă����낤�B���̂���͂��̔��_�Ō��Ԃ͈�Z�������ł��������畽�ς��Ă��O�Z�Z�͎��Ă������ƂɂȂ�B���̂ق��Ƀj�V���̎h���Ԃ�����ŁA��Z�Z�͐��g������Ă����B�����̖�������́A���̌i�C�ł͂ƂĂ��z���̂��Ȃ����̂������ł����āA�����ɓ���ƋƎ҂����D�������肩��R��̕l�ɔԉ������ĂďW�܂�A������Ƃ�������l�ӂɌ��o������u�[���������N���������̂ł������B�Ƃ��낪���̃j�V���͖��N�l�A�܌��Ɏ���̂ŋC���������Đg�����ɏo�����A�S�������ɂ������B���v���ΑS�����������Ȃ��C�����邪�A�����ɂ���������̂Ȃ�����ꂽ�̂�����A�����ɂ����Ĕ엿�ɂ����̂���������ʂ��Ƃ������B
�@�T�P�̒�u�����_�ɂ͘Z�������炢�������Ǝv�������A�ꂩ�����ώO�Z�Z�i��Z�Z�ŘZ�Z�Z�Z���j�͐��g�����Ă����B���̂悤�ɖ����͂Ȃ������B�����������͑N���̂܂ܔ��فE�D�y���ʂ���ѓ��n�̕x�R���ɏo�ׂ��ꂽ�B�T�P�͒�u�������Ȃ��Ǝ҂͕ߊl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B����ł��h���ԂŐ����p�T�P�����A�ۑ��ɉ��̉��ɉB���Ă������̂ŁA�ǂ��̋��Ƃł��������Ă���A�����ɂȂ���̃T�P��䏊�ɋ��{���ׂĉ����A�H�ׂĂ����̂����������v���o�ł���B���ꂪ��̏��a��N����܂ő����Ă����B
�@�z�b�L�L�������̖�������́A�āE�~���킸�����Z�Z�Z�`�O�Z�Z�Z��������B���i�͈�Z�K�œ�܌���l�Z�Ƃ������l�ł��������A����ł���Z�~�͈���ɐ��g������A�ꂩ����Z���ԏo�����Ĉ�Z�Z�~���炢�ɂȂ�������A�����t���y�Ȑ��������Ă����B
�@�j�V����̃��g�C���ꂩ�����ς��Ĉ�ܐl�͂����낤�B�n������łȂ����͒n���ŕ���Ă����B���̃j�V���u�[���������̖��������s���ɂ݂܂��A�|�Y������̂����ɂ������悤���B�吳�ܔN����ɂȂ��čĂуj�V���͗������̒��łȂ��A�|�c���|�c���Ɨ�����x�������B���Θp�̃j�V�������̂���ňꉞ�I�~����ł��ĉ₩�ȃC���V�̎���ɓ���B
�@�C���V�̎�ꂾ�����̂͑吳���N���납��ŁA��V���悭�Ȃ�A�Ǝ҂��ڂ����n�߂������B�Ő����͑吳�������珺�a��ܔN����܂ł͂����務�A�����Ƀ}�O�������͂��߁A�①�D�����܂����̂ł��ė]���A�l�Ɏ̂Ă錻�ۂ����N�����B���a���A���N����͈���Z�Z�сi���܃L���O�����j�������}�O�����A���������~�̑���̂Ƃ����������B�C���V�����̉��i���A���a�Z�N�͈�Z�Z�i�Z�l�l�A��Z�Z�U�j�Ŕ��Z�Z�~�ł������B�C�J�������Ď�ꂽ���A���u�ɍ����Z�іځi�O���E�܃L���O�����j��ܑK���炢�̂������l�ŁA�V�C�̈������͊��Ă�Ƃ������������炢���B���a���N�����l�N�܂ł������ǂ���l�̓C���V�ŕ����Ԃ�A�i�C�̂悢���Ƃ͂��̂������Ȃ������B���ɏ��a���N�A���̔N�͍ō��L�^�̈ꎵ�Z�Z���сi�Z���O���܁Z�g���j�̃C���V�𐅗g������Ƃ�����O�̑務�ŁA�務�̓��łȂ��Ƃ��C�̐F���C���V�ɂ���ĕς���Č������Ƃ������炢������S�������������B���Ƌ����g��������ɂ͂��������A���t�̌i�C���悩���������Ŗ��������R�A�債���K�v���Ȃ������̂��낤�B�������悭�Ȃ����̂́A�đ�E�����g�����Ƃ��ďA�C��������ł������B
�@���̃C���V�̍Ő����̂���́A�암�E�H�c���ʂ���o�҂��ɖ��N��Z�Z�Z�l�̃��g�C�������Ă����낤�B�����ԉ��Ŕ����l�̃����O���S���Ă����B���_�s�X�̐l�������o�ʂɗ��A�n�Ԃ͂�����������ɗ��Ă����B�����@�D�������Ă���ꗬ���ꂪ���_�Ɍ܁Z�ˈȏ�͂���A���A�ԋN�������ς�ŁA���̔����@�D�������ɒ┑���Ă��镗�i�݂͂��ƂȂ��̂ł������B���g�����ꗬ�Ǝ҂ŕ��ς��ē~�͋����������ŏオ��A�����E�G�������Ĉ�Z���~�͏��a���A���N����オ��������A���O�Z�{�Ɍv�Z���Ă���N�ɎO�Z�Z���~�ȏ�̎��������������ƂɂȂ�B
�@���̃C���V���₪�Ă͐��悤�ɂȂ�A���a��O�N����ɂ͑S�����Ȃ��Ȃ�A�E�܂����\�[�����߂�������Ȃ��Ȃ����B
�@�����ɐ������ꂽ���v�����́A���ł��������Ă���B�u���������x�Ɓv�ƁB
�@�������A���̂Ђǂ������̏��Ղ͗]��ɂ����т����A������͊o�߁A��C���B�ɗ͂����A�C�ɐ𓊂�����R���u���̂邱�Ƃ��o�����B
�@���̐��ʂ��ܔN�ڂ̏��a�O��N�ɂ͎O�Z�Z���~�̎��n������A�悤�₭�Č��ɗ����オ�鋙���̎p�������邱�Ƃ��ł���B
�@���a�O�O�N������������Z�O�i�w���_�V��x�L�����j
�Ɖ����̐�����`���Ă���B
�@��R�߁@�吳�ȗ��̋���
�C���V���Ƃ̐���
�@��ꎟ���E���̉e�����A�吳�N��ɓ����ċ��ƌo�ς͍D����悵���B�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�̔��_�n��ɂ����鋙�ƌː��́A��ƂP�T�X�ˁA���ƂU�V�˂̌v�Q�Q�U�˂ł������̂ɑ��A���X�N�ɂ́A��ƂP�V�V�ˁA���ƂT�V�˂̌v�Q�R�S�˂𐔂��Ă���悤�ɁA��Ƌ��Ƃ̑������ڗ������B�����Ă��̂���ɂȂ�ƁA�C���V�̋��l�ɑ����̌X���������A�吳�W�N�ɎO��Z�Z�тł��������̂��A���X�N�ɂ͎O���т��Y���A���̌�A�吳�������珺�a�P�R�A�S�N����܂ł̂��悻�Q�O�N�Ԃ́A�C���V�̑S������Ƃ����銈����悵���̂ł���B
�@���ɂ��̃C���V�́A�吳�����������I�ȑ����������A�吳�P�S�N�ɎO�Z�㖜�ї]�𐔂��Ă��珇���ɐ��ڂ��A���a�W�N�ɂ͎��Ɉ�l�ꎵ���тƗL�j�ȗ��̋��l�����L�^�����B�܂��A����ɂ�ăC���V���Ԑ������a�Q�N�ɓ�O���̂��̂��A���a�W�N�ɂ͌ܓ𐔂��A����ɔ����@�D���吳�����̂T�A�U�ǂɑ��A���̂���ł͂Q�Q�ǂɑ����A�����務�����Ȃт����ďo�����鐷�����������̂ł���B�������Đ��Y���ꂽ�C���V�̑啔���͔엿�p�������Ƃ��Ĕ̔�����A���̕��Y���Ƃ��ċ��������Y���ꂽ�B
�哯���Ɓi���j���_�H��i�ʐ^�P�j

�C���V�̋��l���i�i�ʐ^�Q�j

�@����A�����n��ɂ����Ă͂��łɃ{�^���G�r�̐��Y�n�Ƃ��Ė������Ă���A�C���V�ɑ���ˑ��x�͒Ⴂ���̂����������A�吳�P�R�N�U���ɖΖ����i���A�h�l�j�̋e�n�����Y���A���߂ăC���V���Ԃ��g���čD���т������Ă��玟��ɃC���V���Ƃ�����ɂȂ�A�������ő�d�Ԃ��o�c�����悤�ɂȂ��Ă������B
�@���̃C���V���̍Ő����̂���́A���E�X�E�H�c���ʂ���A���_�łQ�O�O�O�l�A�����łR�O�O�l���܂�̏o�Ґl�i�فE���O�E�_�l�ȂǂƏ̂����j������A�������ł͂W�O�l���̏o�Ґl���ق��A�ԉ��Ə̂��錚���Ɏ��e���ċ����s�����B
�@���������D���f���āA���a�U�N�P�P���ɓ��V�y���i���A���_�����Ƌ����g�����������ݒn�j�ɍ��X�؋��Ɗ�����Ђ��A���V�N�ɂ͖Ζ����ɍ����P���Y���A���ꂼ��C���V�������Ƃ���u�t�C�b�V���E�~�[���v�����H���ݗ�����ȂǁA���a����̕��Θp�͓��{�R��C���V����̈�ɐ������A���_�E�����Ƃ���̋��ƂƂȂ�A���Y�̎�ʂ��߂�Ɏ������B���a�����ɂ������v����̋��l���Ɛ��Y�z�͏�L�̂Ƃ���ł���B
���a�����ɂ�����j�V���E�C���V�E�}�O���̋��l��
| ���� ���ʁE���z �N�x�E�n��� |
�j�@�@�V�@�@�� | �C�@�@���@�@�V | �}�@�@�O�@�@�� | ||||
| ���@�@�� | ���@�@�z | ���@�@�� | ���@�@�z | ���@�@�� | ���@�@�z | ||
| ���a�S | ���@�_ | �U�C�S�O�O | �U�S�O | �R�C�W�R�P�C�O�S�O | �Q�U�W�C�P�V�R | �P�C�P�O�O | �W�W�O |
| ���@�� | �Q�U�C�U�T�O | �R�C�S�U�O | �W�W�X�C�T�T�O | �W�W�C�X�T�O | �R�O�O | �S�T�O | |
| �T | ���@�_ | �P�O�C�O�W�O | �X�O�V | �S�C�W�V�S�C�Q�S�O | �P�X�S�C�X�V�O | �R�P�C�S�U�V | �P�T�C�V�R�S |
| ���@�� | �S�C�X�T�O | �V�X�Q | �T�V�S�C�W�O�O | �R�W�C�V�S�O | �P�Q�C�R�S�O | �R�C�V�O�Q | |
| �U | ���@�_ | �V�C�T�Q�O | �U�O�Q | �S�C�X�V�U�C�O�O�O | �P�S�X�C�Q�W�O | �P�P�C�Q�V�O | �T�C�U�R�T |
| ���@�� | �V�O�C�O�S�O | �S�C�X�O�R | �T�O�S�C�V�O�O | �P�T�C�P�S�P | �X�X�O | �R�X�U | |
| �V | ���@�_ | �R�T�C�R�U�O | �R�C�P�V�Q | �T�C�U�W�X�C�Q�W�O | �P�V�O�C�U�V�W | �S�Q�W | �P�U�R |
| ���@�� | �X�C�T�O�O | �X�T�O | �P�V�X�C�P�O�O | �P�Q�C�T�R�V | �| | �| | |
| �W | ���@�_ | �X�C�S�S�O | �U�U�P | �P�S�C�P�U�W�C�O�O�O | �S�Q�T�C�O�R�O | �W�C�T�P�T | �Q�C�T�T�T |
| ���@�� | �U�C�Q�R�O | �W�P�O | �T�S�O�C�X�O�O�@ | �R�Q�C�S�T�O | �R�O | �P�V | |
�i�P�ʁ@�сE�~�j
�@�������A�������đS�����ւ����C���V�����A�S���I�ȃ}�C���V��V�̌����ɂ��A���a�P�V�A�W�N�����ɂ��ĔN�X�����̈�r�����ǂ�͂��߁A�P�X�N�ɂ͊F���̏�ԂƂȂ����B���Q�P�N�ɂ͎�������������҂������l���݂͂�ꂸ�A���Θp�̃C���V���Ƃ͐��ނ��A����܂ł��܂葽���Ƃ͂����Ȃ������T�o��C�J���A�N�ɂ���Ă͋��l���̎�ʂ��߂�悤�ɂȂ����B�������A�S�̓I�Ȑ��g���͈ˑR�Ƃ��Č����𑱂��A��V�����Ɉˑ����鋙�Ƃ̓]���𔗂���悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B
����J�ԋ��Ƃ̐���
�@�吳�̏����ɂȂ��Ă��甭���@�D�����y�����������A�p���p�ނ̗��l��n���������Ƃ̖��C��h�����߁A�k�C�����͑吳�X�N�i�P�X�Q�O�j�Ɂu�@�D�ɂ�����ԋ��Ǝ���K���v��݂��āA���Θp���ɂ����锭���@�D�ɂ�鑀�Ƃ��֎~�����B���̂��߁A�����@�D�͖����͑D�R�A�S�ǂ̂����q�ɗp����ꂽ�̂����y�̂͂��܂�Ƃ�����B
�@�������A�����푈���瑾���m�푈�ւ����Đ펞�̐�����������A���Ƃɂ����Ă��R���͂������̂��ƁA����������ς����̋������Ƃ��ďd�v�Ȗ����킳������A���a�P�U�A�V�N�ȍ~�ɖK�ꂽ�C���V���Ƃ̐��ނɂƂ��Ȃ��āA�W���Ǝ҂͑��̋��Ƃւ̓]����]�V�Ȃ�����邱�ƂƂȂ�A�J���C�E�X�P�g�E�^����ړI�Ƃ������^�@�D����ԋ��ƁA���Ȃ킿�A����J�ԋ��ƂւƓ]�����i�߂�ꂽ�̂ł���B
�@���̂��Ƃ́A�����̕��Θp������ԋ��Ƌ֎~�̑[�u�Ɗ֘A���đ����̖�肪�������A�u���Θp���ƒ����ψ���v�̐ݒu�ɂ���Ē�����}�����B�������B���̊��������ŏ���J�ԋ��Ƃ̑�����H���~�߂邱�Ƃ��ł����A�����Ƃ����`�ŔN�X�����̌X�������ǂ�u���Θp���Ǝj�e�v�ɂ��A���a�P�U�A�V�N���낷�łɘp���S�̒��Ɛ��P�X�R�ǂ𐔂��A���̂��������S�Q�ǁi�Q�Q�p���Z���g�j�A���_�P�T�ǁi�W�p���Z���g�j�𐔂��Ă����Ƃ����B
�@���������̂����ɂ���ǂ͋}�������A�P�X�N�R���u�@�D��g�ԋ��ƗՎ�����j�փX�����v�i�_�����ȑ��j�Ɋ�Â��A����܂ŋ֎~����Ă�������J�ԋ��Ƃ��A�펞���̐H�Ƒ��Y�Ƃ����ړI�̂��Ƃɒn�������̋����ƂƂ��ď��߂ĔF�߂��铹���J���ꂽ�B����������ɂ́A�u����̉����݂̂Ƀ��Z�����i����g�p�����J�ԋ��Ɓv�Ƃ��������t���ł��������̂́A�����Ȃ�Ɩ��ڂ͕ʂƂ��Ď��ۏ�͑��ƑS�ʂɓ��͂��g�p����A�������A�o�c�s�U�Ɋׂ��Ă�����u���Ǝ҂Ȃǂ́A�����Ă���ɓ������߂��̌o�c�ɓ����Ă������B
�@���������������J�ԋ��Ƃ́A�J���C��X�P�g�E�^�������ł͂Ȃ��A�Ԃɂ����邠���鋛�ނ�ߊl���Ă��܂��Ƃ����ł��������߁A���Θp���̋��Ǝ����S�̂�K�R�I�ɔj�A�Ԃ��Ȃ����l���̎��⋙�l���̌����������A�����Ƃ̐��ނ��v���Ƃ��Ȃ����B�������Ă��̏���J�Ԗ��́A���Θp�������ł͂Ȃ��S��������̍r�p�ɂȂ�����Ƃ��āA�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�̂ł������B
�@���̂��ߓ����Y���ɂ����ẮA���ɏ���J�ԋ��ƑS�p�̕��j��ł��o���A���a�Q�S�N�u����J�ԋ��Ɛ����v�ԁv���߂ė��Q�T�N���猸�D�ɏ��o�����B���R���̐����͉������ɑ傫�Ȕ�����^���A��X�̘_�c�����킳�ꂽ���A����J�ԋ��Ǝ҂��r�p���鋙��̎����F�߂���Ȃ��������߁A����ɉ����ĔN�X���D���d�ˁA�{�^���G�r���Ɋւ���ꕔ�̗�O���F�߂��Ď���Ԃ̉��������������̂́A�R�P�N�܂łɑS�D����������ď���J�ԋ��Ƃ͎p���������ƂɂȂ����B
�g�h�쏜��
�@����J�ԋ��Ƃ��p�������A�p�����Ƃ͎�Ƃ��Ďh���Ԃ⏬��u���ƂւƓ]�����Ă������B���������̂��납��A���̐��͏��Ȃ����̖̂��N�P�P�����痂�N�T���ɂ����āA�k�啽�m�ɐ������Ă��鋐��ȊC�b�g�h���\�����Q���Ȃ��ē쉺���A�p���ɐݒu���Ă���J���C�h���ԁE���ԁE�X�P�g�E�h���ԁE�G�ԂȂǂ̋�����r������A��V����X�P�g�E�^���E�J���C�ށE�^�R�E���̑���������G����H�r���A����Ȕ�Q�������炷�悤�ɂȂ����B���̂��ߕ��Θp���ݔ��s���i�����E�X�E���_�E�������E�L�Y�E���c�E�ɒB�E�����j�ƂP�O���Ƌ����g���i�����E�X�E�����E���_�E�������E�L�Y�E�L��E�ɒB�E���c�E�����j�����c�̌��ʁA���a�R�O�N��Ɂu�����p�g�h�c��v�����������B�����ăg�h��V�̎����ɂ͂��ꂼ��W�s���̃n���^�[�Ɉ˗��̂����A���C�t����U�e�e�������ċ쏜�ɂ�����A����ɗv����o��͊e�s���Ɗe���Ƌ����g�������S���邱�ƂƂ����B
�@���a�T�U�N���݂̋��c����ǂ͎������Ƌ����g���ɂ���A��͓��g�����̖k�R�H�j�ł���B
�����̔敾�ƐU����
�@��O�E�풆�ɂ����铖�n���̋��Ƃ́A�C���V�E�T�o�E�j�V���E�}�O���Ȃǂ̉�V��������̂Ƃ����u���Ƃ𒆐S�Ƃ��Ĕ��W���A�܂��A����Ɉˑ�����Ƃ��낪�傫�������̂ł��邪�A���A����狛���̉�V���������Ē�u���Ƃ̌o�c���s����ƂȂ�A�K�͂̏k���⒅�Ɠ����̌�����]�V�Ȃ��������}�����̂ł���B
�@����ɁA����J�ԋ��Ƃɂ�闐�l�ɂ���čr�p�������Θp������ɂ����鑍���l�����N�X�������A�����̌o�c��Ղ����������s����Ȃ��̂Ƃ��Ă����B�������āA���Y�̒��S�ƂȂ�Ώۂ����������Ǝ҂̖ڂ́A�K�R�I�ɘp���Ɏc���ꂽ�C����L�ނɏW�����A���̋��l���͔N�X��������X�����݂��͂��߂��B
�@�����������̎����́A���Ƃ�艈�ݑS���Ǝ҂̎��v�����قǂ̗ʂ��Ȃ����߁A���Ǝ҂̐����͋ɓx�ɍ���ȏƂȂ�A�����ȊO�ɂ͍��S�̎�l�v�③�ޕv�ȂǂƂ��đ��Y�ƂɏA�Ƃ���҂������Ȃ�ȂǁA�����̔敾�͋Ɍ��ɒB���A���Ƃ̊�@�Ƃ��������ł������B
�@�����������ԂɑΏ����ĊW�@�ւ���̂ƂȂ�A�s����Ȓ�u���ƈˑ�����E���āA�n��C�ʂ̋��c���ǂ��s���A��C���B�̐U���ɂ�苙���̐��������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���a�Q�U�N�ɔ��_�����ƐU���ψ����g�D���u ���_�����ƐU���T���N�v��v�����肵���B
�@���̌v��́A
�@�P�A���Ƌ����g���̍Č������ɂ��ƂÂ��g���g�D�̋����B
�@�Q�A���ƌo�ϊm���̂��߂̒�u���Ƃ̐��������B
�@�R�A��C���B���Ƃɂ�鋛�c�̉��ǁB
�@�S�A�����̔ɐB�ی�Ƌ��l���@�̍������B
�@�T�A���t�т̑����Ȃǂ����q�Ƃ��Ċe�펖�Ƃ����͂Ɏ��{����B
�Ƃ������̂ŁA�����̕��j�ɂ��Q�V�N����n�߂�ꂽ�R���u�ʒz�݁i�吳�R�N�ɃR���u�ʓ��͍s��ꂽ���A���̌㒆�f�j�̂��߂̓��́A����ȗ��p�����Ď��{����A����ɁA�L�ށi�z�b�L�L�j�̕ی쑝�B�̂��ߋ�����ݒ肵���ق��A�z�^�e���B�{�݂�݂��ė{�B�����ɏ��o���ȂǁA�ϋɓI�ȑu����ꂽ�B�܂��A�W�������̗{�B��ڎw���āA�A���E�J���t�g�}�X�E���J�T�M�Ȃǂ̂Ӊ������������s��ꂽ�B
�@����A����J�ԋ��Ƃ������p�~�����ɂƂ��Ȃ��A�J���C�ނȂǂ̒ꐶ���������͂��߁A���̑��̎��������X�ɉ̒������݂��A���ɍ����ΏۂƂ���h���ԁE���ד�Ȃǂɂ�鋙�l�ʂ͂��Ȃ葝�����āA�R�O�N����ɂ͈ꉞ�O�r�ɖ��邢���ʂ���������悤�ɂȂ����B�������āA�����Ƃ͂������ɐ�C���Ƃɏd�_���������悤�ɂȂ�̂ł���B
���c�J�����A�@
�@���A�C���V���Ԃ̐�����G�r��J�Ԃ��s�U�ƂȂ������ʁA�C�O���g�ҁA�����҂���ѓ�A�O�j�̕��ƂȂǂɂ���ċ��Ǝ҂��������A�O�l�ł̃R���u�̎����Ƃ�����x�̋��ƌo�ς́A���a�Q�S�A�T�N����_�Ƃ��āA���̐������ɓx�ɍ���ȏɂ������B
�@���̂悤�ȂƂ��ɂ������č��肳�ꂽ�k�C�������J����ꎟ�T���N�v��̈�Ƃ��āA���Y�H�Ƃ̑��Y�Ƌ����ߏ�l���̒�����}�邽�߁A���K�����ݒn��A�L�x���t�������іy�������ޒn��A�}�K���R�P����щ��W�n��E�Y��������{�n��E�Η����E�g���n��E���P���m���ʒn��̂U�n���I�肵�A�����̓��A���v�悳��Ă����B
�R���u�ʓ��i�ʐ^�P�j

�@�����A�����̋����J�����Ă��̑ŊJ��ɕ��S���Ă����������Ƌ����g�������K���Y�́A�����̈ڏZ�ɂ��ߏ�����ƁA�������_�Ƃ��鑺�������̏o�҂��n���m�ۂ���l���̂��ƂɁA���̋��c�J�����A�ɎQ�����Ăт�����ƂƂ��ɁA�n���x���E�����Ƃ����c���d�˂Č��n�����̌��ʁA���P���̊�n�����ƒ�߂��B
�@���̌�A�����E�c���\�E�����L�u�Ȃǂɂ�錻�n���@�ƒ������o�āA�Q�U�N�S���ɓ��A��]�������s�����Ƃ���A�\���҂͂Q�Q�˂ɂ��B�����̂ł��邪�A���n������Ƌ��c���đI�l�̌��ʁA�X�˂̓��A�����肵�ď�����i�߂����ƁA���N�X���Ɍ��n�֏o���������̂ł���B���̑��w�ƂȂ����̂́A�e�n��Y�E�ؑ����l�Y�E��������E�Ή����E�e�n�����Y�E�����_���Y�E�����s���Y�E���J�P�l�Y�E���R�����Y�̂X�˂ł������B���̂����A�ؑ����l�Y�E���J�P�l�Y�E���R�����Y�̂R�˂́A�ƒ�̎���ȂǂŒ�Z��������߁A���N���X�ɋA�������B
�@���Q�V�N�ɂ�����ɂX�˂����A�����ق��A�D��H�E�����H�E���Y���H�Ȃǂ�ڎw���҂̈ڏZ���s���A���̐��ʂ����҂��ꂽ�̂ł������B���̌�A�������A��̘J���s���ɑ��ė����n�悩��̏o�҂��������ɂȂ�A�܂��A�E�����߂ė��P�֓]�Z������̂��o��Ȃnj𗬂�����ɂȂ����B
�@���w�œ��A�����e�n��Y�́A�̂��ɗ��P���c��c���E���P���������Ȃǂ����߁A���̓��A�҂����ꂼ����肵���������c��ł���A���̓��A�͈ꉞ�����������̂Ƃ݂Ă悢�ł��낤�B
�T�P�E�}�X���ԋ��Ƃւ̏o���@
�@����J�ԋ��Ƃ̐������V�����̕s�U�ɂ��A���Ɋ��H�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ�������u���Ǝ҂̈ꕔ�̗L�u�́A�������Ƃւ̓]������}���ăT�P�}�X���ԋ��Ƃi�o�����B
�@���Ȃ킿�A���a�Q�W�N�T���Ɏ���������\�������o�ċ��H���ʂ𑀋Ƌ��Ƃ��āA�������j���L�̍K�^�ہA�đ�D���L�̐��^�ہA���c�~�g���L�̑���R�ہA�ؑ��O�쏊�L�̐V�h�ہi��������P�O�g�������j�̂S�ǂ��o���������A�D�̂����^�Ȃ̂Ƙp�O�ł̑��Ƃɕs����Ȃ��Ƃ������āA���҂������т������邱�Ƃ��ł����A�P�N����Œ��~���Ă��܂����B
�܂������n��ɂ����Ă������悤�ɁA���Ƌ����g�������E���E��O�K�h�ہi��������Q�O�g�����j�R�ǂD�A�g�����Q�O�����őD�c��g���H���ʂɏo���A�R�O�N�܂łR���N���Ƃ𑱂��A�敾�������ƌo�ςɏ����������炵���̂ł������B
�k�m���Ƃւ̏o�҂�
�@�����Q�X�N�i�P�W�X�U�j���V�A�̃R�i�N��Ђ��f���r�[�ƍ������āA���ق��狙�v�S�U�l���ق�����A�J���`���b�J�ŋ��Ƃɏ]���������̂��A���{�l�̖k�m�i�o�̏��߂Ƃ����邪�A�Ȍ�͋���̊g��ƂƂ��Ɍٗp����������A�ØV�̓`����Ƃ���ł͂��邪�A�����R�R�N���낷�łɗ������̋��v������ɎQ������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ����B
�@�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�ɑn�݂��ꂽ���D���Ɗ�����Ђ́A���̌㐔�Ђ����Ă������ɐ��͂��g�債�A�J���`���b�J�̊ʋl�Ƃ̓�����͂��߁A�k�m���ƓƐ�̊ς�悷��悤�ɂȂ������A�������ł͂��̓��D���ƂɌق���D���𑽂��o�������߁A����ɂƂ��Ȃ����v�̏o�҂��������Ȃ�Ƃ����W���������B�k�m�ւ̏o�҂������ł������N�łP�T�O�l���܂�𐔂������A�T���ɏo�����ĂV�������W�����߂܂łɂ͋A�����A�R���u�̎悪�ł���Ƃ������ƂŁA����Ƃ̈ꕔ�ɑg�ݓ���Ă���҂��������킯�ł���B
�@�������A�����o�҂����v�ɑ���ٗp�_�̎x�x���O�݂���A�����グ���̐��Z�������A�{�l�ւ̒��ڕ���������ł������̂ŁA�Ƃ��ɂ���Ă͈��H��ɏ����Ă��܂��āA�ƌv�Ɉ��e�����y�ڂ�����݂�ꂽ�B���̂��߁A�吳�P�T�N�P�P���Q�T���u�������o�ҋ��v�����g���v���������Ď������𗎕���������ɂ����A�ٗp�_�̍쐬�A�O���̑ݕt�A���Z�����̎x�����A�n�q�葱�����ނ̍쐬�ȂǁA��̎������������Ă��̕��Q�̖h�~�ɓw�߂��̂ł���B���̌�A�g���́u�������o�ҘJ���ҕی�g���v�Ɩ��̂�ύX���A�o�҂��҂ɕK�v�ȕ����̂���������s�����B
�@�������A���v�̏o�҂��n�́A�k�m�Ɍ��炸�����E���сE���G�Ȃǂ̃j�V���ꏊ�����������A���a�V�N�̗������̎��тɂ��A�������S�R�A�������Q�Q�ɑ��ă��V�A�̂��P�P�T�ƈ��|�I�������߂Ă����B
�@���������̌�A�����̃j�V�����ꂪ�s�U�ƂȂ�A���̕��ʂւ̏o�҂��͑S���Ȃ��Ȃ��Ėk�m�ւ̏o�҂��������c���Ă������A����������m�푈�̊g���I���ɂ�����}�b�J�[�T�[���C���̐ݒ�ɂ���āA�S���r�₦��Ƃ����o�߂����ǂ����B
�@���̃}�b�J�[�T�[���C���͕��a���̔����ƂƂ��ɓP�p����A�k�m���Ƃ���D���T�P�E�}�X���Ƃ��ĊJ�����悤�ɂȂ�ƁA�Ăѓ��D���Ɗ�����Ђ̎��ƈ��Ƃ��Ă̏o�҂����������A�����n��𒆐S�Ƃ��Ė��N�����𑗂�o���悤�ɂȂ����B����玖�ƈ��͖k�m�o���̎葱�����~���ɂ��邽�߂ɑg����g�D���Ă������A���a�S�Q�N�W���u�����k�m���ƈ��g���v�Ɖ��߁A�g�����ɒ����̏A�C��v�����ĉ~���ȉ^�c��i�߂Ă���B
�@�������A�k�m���Ƃ͐������l�ʂ̌����ɂ���āA��D�̌��D�Ƃ������������}���A�o�����ƈ����傫���������A�ЂƂ���͂P�Q�O���O��ł��������̂��A�T�R�N�ɂ͂Q�P�����x�ɗ�������ł���B
�@��S�߁@���Ɛ��x�̉��v
���Ɩ@�̉���
�@���a�W�N�i�P�X�R�R�j���Ɩ@�̉����A���X�N�ɋ��Ƒg���߂̉������������ōs���A�g���o�ώ��Ƃ̂�肢�������̋������}��ꂽ�B���̋��Ɩ@�����̗v�_�́A
�P�A���Ƌ����g���̌����\�͂��g�[���A���̂��ƂŐV���ɑg�����̈�ʌo�ς̔��B�ɕK�v�ȋ����{�݂��s�����Ƃ��ł��邱�ƁB
�Q�A�ΊO�I�ȓ���̌o�ώ��Ƃ��s���g���͐ӔC�g�D�ɂ�邱�ƁB
�Ȃǂł������B
�@�����āA�g���͐ӔC�g�D�ɂ����̂ƁA�����łȂ����́A���̐ӔC�g�D�ɂ́A�����E�L���E�ۏ̎O��A����ɁA���̂����g�������o��������̂����Ƌ����g���Ƃ��A�o�����Ȃ����̂����Ƒg���Ƃ��邱�ƂȂǂ���߂�ꂽ�B�������A�ӔC�g�D���̗p���邱�Ƃɂ���āA���Ƒg���͂͂��߂ċߑ�I�Ȍo�ϒc�̂Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�����������x�����ɂƂ��Ȃ��A�e���Ƒg���Ƃ����X�Ɖ��g������i�߁A���_�����Ƒg���͏��a�P�O�N�P�Q���Q�V���Ɂu�����ӔC���_���Ƌ����g���v�Ƃ��āA�R�z�������Ƒg���͗��P�P�N�P���P�W���Ɂu�����ӔC�R�z�����Ƌ����g���v�Ƃ��ꂼ��F���A�V�g���ֈڍs�����B�܂����������Ƒg�����A�������̂P�O�N�W���Q�X���Ɂu�����ӔC���������Ƌ����g���v�ɉ��g�̔F���ĐV�g�D�Ɉڍs���Ă����B
�@�������Ċe�g���́A�g�����̋��Ƃ̔��W����ьo�ϊ����̊g�[�ɗ͂𒍂��A�����̋����E�����̎�舵���Ȃǂ�ʂ��đg�����̒n�ʂ̌���ɓw�߂��B�Ȃ��A���̂悤�Ȋ����̋����ɑΉ����A�������_��������Ɏ������������Ă������_���Ƌ����g���́A���a�P�Q�N�P�Q���ɓ����i���A�J�g���b�N����j�Ɏ�������V�z�����B�܂��A�R�z�����Ƌ����g�����P�S�N�Q���ɎR�z�w�O�Ɏ�������V�z����ȂǁA�g���̋@�\�������[������Ă������B�Ȃ��A���������Ƌ����g�����P�O�N�P�P���ɁA�����\���X����l�ɉ�����r���̍����Ɏ�������V�z�ړ]�����B
�펞���̋��Ɛ��x
�@���a�P�Q�N�i�P�X�R�V�j�����푈�̂ڂ����ȗ��A�����ł͂�����ʂɂ����Đ펞�̐�����������A���ɑ����m�푈�̐i�W�ɂ�ĕ������ɒ[�Ɍ��R���A���ׂĂ̎��ނ͋��͂ȓ������ɂ�������ԂƂȂ����B���������w�i�̂Ȃ��Ő��{�́A���a�P�W�N�X���u���Y�ƒc�̖@�v�����z�i���P�X�N�P���{�s�j���A�]���̋��Ƒg���E���Ƌ����g���E���Y��E���Y�g���Ȃǂɉ��U�𖽂��A���Y�W�c�̂����āA���Ǝ҂͋��Ɖ�A���H�Ǝ҂͐����Ɖ�ɓ��ꂷ�邱�ƂƂ����B
�@����ɂ���ė��P�X�N�Q���Q�P���A
�@�u���Y�ƒc�̖@�攪�\����m�K��j�˃����m�g���m���U�����Y�v
�Ƃ̎w�߂�����A�����F�������ق��g�������̒�����S���ɑ��A
�@�u���_���m��惒�n��g�X�����_���Ɖ�m�ݗ��ψ������Y�B�v
�Ƃ������߂ɂ��A��̓I�ɂ��̐ݗ����w�����ꂽ�̂ł���B���������āA���ǂɑΉ����đ��X�Ə������i�߂��A�R���P���ɐݗ�������֍Â��Ĕ��_���Ɖ��Ȃǂ����A��ɕđ�E��I�ق��A�����T���A�Ď��Q����I�o���Đݗ������肵���B�����āA�����\���A�����F�Ƃ����o�߂ƂƂ��ɁA�đ�E����ɔC�����锭�߂������đ����o�L���������A�펞���̐��Y�Ƃɂ����鍑��ɉ����āu���_���Ɖ�v�͔��������̂ł���B
�@�܂��A�������ɂ����Ă����l�ɂ��̐��x�͓K�p����A�قƂ�Ǔ������Ɂu�������Ɖ�v���ݗ�����ĉ�ɒґ����邪�A�C���A���̌�Q�P�N�Q���ɐ{���G�g���Q���ɏA�C�����̂ł���B
�@�������A�������ċ����I�ɐݗ����ꂽ���Ɖ�́A���̎��ۓI�ȋ@�\�ɂ����āA���ƌ������L���o�ώ��Ƃ��s���_�ɂ��Ă͏]���ƕς��Ƃ���͂Ȃ��������A�푈���s�Ƃ����ړI�̂��߂ɍs��ꂽ�Ƃ��납��A����I�ȋ����g���̓��F�͑S�������A�������Ƃ��s�����̉����@�ււƕς���Ă��������Ƃ͑��̎Y�ƂƓ��l�ł������B
���̋��Ɛ��x
�@���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�����m�푈���s��Ƃ����`�ŏI���������Ƃɂ���āA�펞���ɂ����铝���I�̐��ł������e��g�D�c�̖̂��剻������A����ɁA�Q�P�N�}�b�J�[�T�[�i�ߕ��o���u�����I�o�ϓI�n�ʂɑ���Ǖ��o���K�p�̌��v���X���̖��剻�͑��i����Ă������B
�@���Ɛ��x�ɂ����Ă��Q�S�N�Q���Ɂu���Y�Ƌ����g���@�v���{�s����A�]���̋��Ɖ�͋��Ƌ����g���ɉ��g����邱�ƂɂȂ�A�u���Y�Ƌ����g���@�̎{�s�ɂƂ��Ȃ����Y�ƒc�̐����Ɋւ���@���v�ɂ���āA���_�E�R�z�E�����̊e���Ɖ�́A���ꂼ����U�Ƌ��Ƌ����g���̐ݗ�������i�߂��̂ł���B
�@�������āA����̎葱�����o�ĐV�����g���̐ݗ����}��ꂽ���A�����_���Ɖ�̋������ď��a�Q�S�N�S���R�O���ɑg�����Q�T�P���������Ĕ��_���Ƌ����g���A���N�T���P�S���ɑg�����T�X���������č��⋙�Ƌ����g���̂Q�g�����ݗ����ꂽ�ق��A���N�T���R�P���g�����P�X�O���������ĎR�z�����Ƌ����g�����A�܂��A�X���P�T���ɑg�����S�S�Q���������ė������Ƌ����g�������ꂼ��ݗ����ꂽ�B���̌�A�g���̑g�D�����Ƃ����w���������āA�Q�W�N�S���ɍ��⋙���͔��_�����ɋz���������ꂽ�B
�@�g���͂��̐ݗ��̖ړI���A
�@�u�g�������������āA���̋��Ƃ̐��Y�\�����グ�A�o�Ϗ�Ԃ����P���Љ�I�n�ʂ����߂邱�ƁB�v
�Ƃ��A�g�����ɂ́A
�@�u�n����ɏZ����L���鋙���ŁA��N�̂������Z���ȏ㋙�Ƃ��c�݁A�܂�����ɏ]��������́B�v
�𐳑g�����Ƃ��A
�@�u�g���̒n����ɏZ���܂��͋��Ƃ̍����n��L���鋙�Ɛ��Y�g����A�g���̒n����ɏZ����L���Ȃ������ŁA���̉c�݂܂��͏]�����鋙�Ƃ̍����n���n����ɂ�����́B�v
�����g�����Ƃ��A�g���̍s����Ȏ��Ɓi�����@�����j�Ƃ��āA�M�p���ƁE�w�����ƁE�g�����̋��l�����̑��̐��Y���̉^���E���H�E�ۊǂ܂��͔̔����ƂȂǂƂ���Ă����B
�C�拙�ƒ����ψ���
�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�R���P�S���ɐV���̋��Ɩ@���{�s���ꂽ���A����́A�]���̕����I�ȋ��ꏊ�L���x��p�~���āA������̑S�ʓI�Ȑ������s�����ƂƂ������̂ł������B���Ȃ킿�A�����ƌ��͐V���Ɩ@�{�s��Q���N�ȓ��Ɉ�Ăɏ��ł����ĐV���ƌ���Ƌ����A��O�A�����ɑ����̕��Q�������炵�����ƌ��̎��L����p�~���āA�������݂̋��L����}�낤�Ƃ�����̂ł������B
�@���ƌ��ɂ́A��u���ƌ��E��拙�ƌ�����ы������ƌ��̎O�킪����A���̑̌n���m�����ꂽ�̂ł��邪�A�������ڂ����q�ׂ邱�Ƃ͏ȗ����邪�A������V���Ɩ@�ɂ���āA���ʂ̑����I�ȗ��p�̊m�ۂ�}�邽�߂̖���I�ȋ@�\�Ƃ��Đ݂���ꂽ�̂��u�C�拙�ƒ����ψ���v���x�ł���B�ψ���͋��Ǝ҂���ы��Ə]���҂̑I���ɂ���đI�o���ꂽ�ψ��ƁA�m���̑I�C����ψ��ɂ���č\������A���ƒ�����ɂ����ċ���Ȏw�����������A�V���ƌ��̖Ƌ���Ĕz���ɑ傫�Ȗ����������̂ł������B
�@�������đS���ɂS�X�C�悪�ݒ肳��A�W���Ƃ��āu���_�E�������C�拙�ƒ����ψ���v�Ɓu�����k���C�拙�ƒ����ψ���v���ݗ����ꂽ���A���̍\���͌��I�ψ������ꂼ��P�P���A�m�����I�C����w���o���҂Q���A���v���\����ƔF�߂���҂P���̍��v�P�S���Ƃ���Ă����B����ɂ���ď��a�Q�T�N�W���Ɍ��I�ψ��̑I�����s���A���_�������c�|�O�Y��U�������I�A���̂ق��A�w���o���҂Ƃ��đ���Y�A���v���\����҂Ƃ��đ�ˉK���Y�i�����������j�����ꂼ��I�C���ꂽ�B�܂�������������́A���I�ψ��T���A�w���o���҂P�����I�o����Ĉψ���g�D����A���N�P�O����ˉK���Y����ɌݑI���A������������������ɂ����Ĕ��������B
�@�����k���C��̊W�ł́A����������I�ψ��Ƃ��Ċ��K���Y�A�w���o���҂Ƃ��Đ{���G�g���I�C���ꂽ�B����ɁA�Q�V�N�̑I���Ō��I�ψ��Ƃ��Ċ��K���Y�E�{�Ë���A�w���o���҂Ƃ��ē��s�ނ��I�C���ꂻ�̐E�ɂ��������B
�@���̈ψ���́A�����ȗ��V���Ɛ��x��ψ���̎�|�̕��y�O���}��ƂƂ��ɁA�悭�����̐��Ɏ����X���A�Ƌ��\���҂̓K�i���R���≈�ݑ��B��Ȃǂɓw�߂��B�܂��A���Θp���̊W�C��Ƃ̋��ʖ������c���邽�߁A�אڂ̊����k���E�L�숸�c�E�����̊e�C��ƂƂ��ɏ��a�Q�U�N�R���u���Θp�A���C�拙�ƒ����ψ���v�i�Q�ȏ�̊C����������C��ɐݒu�����j��ݒu���A�L��I�Ȍ��n���狙��v��̎����A�C��Ԃ̒����A����J�ԋ��Ƃ̐����Ȃǂɋ��͂������A�n�ݏ����̍���Ȏ���ɂ�����~���ȉ^�c��}�����B
�@���a�Q�X�N�V���ɊC��̉������s���ď]���̑S���S�X�C�悪�Q�S�C��Ƃ���A�R�z�S�Ɗ����S�̂W�������i�����j�������āu�n���k���C�拙�ƒ����ψ���v�ƂȂ�A�������͐X��������Ɉڂ��ꂽ�B�������A���̍\�������͂���܂łƕς�炸�A�Q�X�N�A�R�P�N�A�R�R�N�A�R�T�N�̊e�I���ł́A���������ɂQ���̈ψ������I���Ă��̐E�ɂ��������B
�@���a�R�V�N�V���ɂ͑S���Q�S�C�悩��킸���P�O�C��ɉ��҂���A���َs���܂ޓn���x���Ǔ���������̉�������C�搧���̗p����āA���̖��̂��u�n���C�拙�ƒ����ψ���v�Ɖ��̂����������n���x�����Ɉڂ��ꂽ�B�R�X�N�W���ɂ͂��̍\�����ύX����A���I�ψ��萔�X���A�w���o���҂���̑I�C�S���A���v��\�҂���̑I�C�Q���ƂȂ�A�C�����S�N�ɉ��������Ȃǂ̕ϑJ�����ǂ��Č��݂Ɏ����Ă���B
�@�n���C��Ƃ�����C�搧�ƂȂ��Ă���́A����������I�ψ��𑗂�o�����Ƃ��ł����A�킸���ɏ��a�R�X�N�W���k�����i�����������j���P���S�N��A���v��\�ψ��Ƃ��đI�C���ꂽ�ɂ����Ȃ������B���̌�A���a�S�V�N�W���ɑ��c���Y�A�T�P�N�W���ɂ͑��c���Y�ƍH�������̂Q�������ꂼ����I�ψ��Ƃ��Ă���ɎQ�悵�Ă���B
�@�C�拙�ƒ����ψ���x�̑n�݈ȗ��A���_������ы�����������I�o���ꂽ�ψ��͎��̂Ƃ���ł���B
�@�����k���C�拙�ƒ����ψ���
�@�J���K���Y�i����l�N�j�E�{����i�����N�j
�@���_�E�������C�拙�ƒ����ψ���
�@��c�|�O�Y�i����l�N�j�E�������Y�i�����N�j�E�n�Y�i����l�N�j�E���c����i���j�E��c�ΗY�i���j�E�����v�V���i���j�E�T�J�F�g�i�����N�j
�@�n���k���C�拙�ƒ����ψ���
�@���c����i�����N�j�E��c�|�O�Y�i���j�E���{���V���i���j�E�X�Α��Y�i����l�N�j�E��c�ΗY�i���j�E���X�ؑ����Y�i�����N�j
�n���C�拙�ƒ����ψ���
�@���c���Y�i������N�ځj�E�H�������i����l�N�ځj
�@��T�߁@���Ɛ��Y�̐���
���̋��Ɛ��Y
�@���ɂ����镬�Θp�C��̋��Ɛ��Y�́A���a�Q�O�N����܂ł̓}�C���V�𒆐S�Ƃ��Ēg���n��V������ΏۂƂ�����u���Ƃ��啔���ŁA���̋��ꉿ�l�͋ɂ߂č����A���{�O��C���V����ɐ�������قǂ̍D����Ə̂���Ă����B
�@�������A�S���I�ȃ}�C���V�����̐��ނƂƂ��ɘp���̋��Ɛ��Y�ʂ��������A�Q�P�N�����̐��Y�ʂ͂P�T�N����̖�R�O�p�[�Z���g���O�ɂ������A�S���̏Ɣ�r���Ē�������ʐ��Y�n�тƂȂ����̂ł���B
�@�������A���Ɛ��Y�ʂ����������Ƃ͂����A�ˑR�Ƃ��Ē�u���Ƃ̐�߂銄���͋ɂ߂đ傫���A�����Y�ʂ̖�U�T�p�[�Z���g�͗����E�X�t�߂𒆐S�Ƃ�����u���ƂŐ�߂�ł������B
�@���������āA�p�����Ǝ҂̑啔���ł��鋙�D���Ǝ҂́A�c��̂R�T�p�[�Z���g���O�ɂ���Čo�c���ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A���̌o�c���e�͔��ɗ�ׂȂ��̂ƂȂ����B���̌��ʁA���o�c�̂̂U�O�p�[�Z���g�����Ə��������ł͉ƌv���ێ����邱�Ƃ��ł����A���ƒ��J���E���S�̎�l�v�E���ސl�v�Ȃǂ̌��Ƃɂ���ĕ���Ă������A�����̌��Ǝ����ɂ���Ă��Ȃ��Ԏ��̂��̂������ł���A�������A���������͑S���̕��ϓI���x�����炩�Ȃ��ʂȏ�Ԃɂ�����Ă����̂ł���B
�@���������̂Ȃ��ŁA���a�R�P�N����J�ԋ��Ƃ̑S�p�ƁA���̌�ɂ������C���{�B���Ƃ̐i�W�ɂ���āA�s�U���������Ă��������Ƃɂ��悤�₭�̒������݂��͂��߂����̂́A�R�O�N��̋��l���ɂ��Ă݂�ƁA�R�Q�A�R�T�A�R�U�A�R�W�N�̂S���N�͂S�O�O�O�g��������鋥���Ɍ������Ă���A�{�i�I�ȉ̏�Ԃł͂Ȃ��A���ƌo�ς���������E�����Ƃ͂����Ȃ������B
�@�������A�O�f�̔N�x�ȊO�͂����ނ˂S�O�O�O�g���ȏ�̐��Y���������A�S�O�N�x�ł̓X�P�g�E�^���̂R�P�V�R�g�����g�b�v�ɑ��ʂU�T�O�O�g���]�𐔂��A�Ȍ�͈��肵�ď�ɂU�O�O�O�g�������鐶�Y���グ�A�S�T�N�ɂ͂P���g����˔j���鐶�Y���������B
�@�����̓���͕ʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A���������ƁA���a�T�O�N�ȑO�ł͋��ނ���ʂ��߁A�����ŊL�ށA�C���ށA���Y�����̏��ƕς�炸�A�������A���ނ������Ă͑����̕ϓ����������A���̂ɐ�߂銄�����Ⴂ���̂�����B
�@�������A�R�U�N�x�ȍ~���ނ̃g�b�v�̍�������Ă����X�P�g�E�^�����T�O�N���琶�Y�ʂ��}���Ɍ������͂��߂�ƁA����ɑ����ė{�B�z�^�e�̐��Y���}���ɑ����������A���Y�z�ł͂T�O�N�x����A���Y�ʂɂ����Ă��T�P�N�x����A�L�ނ���ʂ̍����߂�Ƃ����傫�ȏω����}�����̂ł���B
�@�����ŁA���炭�̊Ԏ�ʂ̍����߂Ă������ނ̕ϑJ�����ǂ��Ă݂�ƁA�R�R�N�ɂP�R�U�P�g���Ƌ��ނ̑����Y�ʂ̂T�W�p�[�Z���g���߂Ă����C���V���́A���R�S�N�ɂ͂S�W�P�g���ƌ������A�Ȍ���N�X�����𑱂��ĂS�O�N�ɂ͑S���݂��Ȃ��ƂȂ����B����́A�S���I�ȃ}�C���V��V�̌����ƂƂ��ɁA���Θp�n�т̃C���V�������ɓx�Ɍ͊��������߂ŁA�����ΏۂƂ��Ă�����u���Ǝ҂̎��Ō��͋ɂ߂Đ[���Ȃ��̂��������B
�@�܂��T�o���ɂ��ẮA�R�S�N�̂P�U�O�T�g���ƁA���̔N�̑����Y�ʂ̂T�S�D�R�p�[�Z���g���������ق��A�R�V�N�̂U�V�T�g��������Ɏ������x�ŁA���̑��F���̔N���܂߂Ċ��҂ł��Ȃ��ƂȂ�A������g���n�����̐��Y�ʂ͔N�X�������A�j�V���Ɏ����Ă͑S�����̋��ƂȂ����̂ł���B
�@�������Ēg���n�����������������A�R�V�N���납�犦���n�����ł���X�P�g�E�^�������������A�S�O�N�Ȍ�ɂ����锪�_�n�扈���l���̑啔�����߂�悤�ɂȂ�A����ɂƂ��Ȃ����Y���H�Ǝ҂̑������݂邱�ƂƂȂ����B�������Ȃ���A�T�O�N�̂Q�A�R���ƂU���ȍ~�A�����m�����H������_�U�E�n�����ɂ����āA�L�͈͂ɂ킽��\�A���D�c�̖��d���Ƃɂ��X�P�g�E�^���A�T�o�̗��l�Ƌ���ւ̔�Q�A����ɁA�T�Q�N�R���\�A�̐�ǐ���Q�O�O�J�C���ݒ�ɂ���Ē��ߏo���ꂽ�؍����D�̕��Θp���ɂ����閳�d���ƂȂǂ̉e�����āA�X�P�g�E�^�����͌������A����܂ł��̋��Ɉˑ����Ă������_�n�扈�����́A�ĂѐV���Ȋ�@�ɒǂ����܂�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@�܂��A���������n�����ł���J���C�ނ́A���Ǝ����̊Ǘ�����ƂƂ��ɁA�R�P�N����n�߂�ꂽ���ʒz�ݎ��ƂȂǂ̌��ʂ�����āA�����ނˈ��肵�����Y�ʂ��グ��܂łɉ��A�S�T�A�U�N�ɂ͂Q�O�O�O�g�����鐶�Y�ʂ������Ɏ����Ă���B
���Y�z�̐����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �敪 �N�x |
���@�@�� | �� | ���Y���� | �� | �L�@�@�� | �� | �C�@���@�� | �� | �����Y�z | �� |
| �R�Q | �T�U�C�R�V�X | �R�S�D�X | �Q�V�C�O�T�U | �P�U�D�W | �P�O�C�X�S�S | �U�D�W | �U�U�C�X�S�P | �S�P�D�T | �P�U�P�C�R�Q�O | �P�O�O |
| �R�R | �U�Q�C�W�Q�V | �T�O�D�X | �X�C�V�R�T | �V�D�X | �P�U�C�U�R�O | �P�R�D�T | �R�S�C�R�T�U | �Q�V�D�V | �P�Q�R�C�T�S�W | �P�O�O |
| �R�S | �U�V�C�U�S�X | �T�W�D�Q | �W�C�Q�P�T | �V�D�O | �Q�Q�C�V�U�X | �P�X�D�U | �P�V�D�V�O�R | �P�T�D�Q | �P�P�U�C�R�R�U | �P�O�O |
| �R�T | �T�R�C�P�O�T | �Q�V�D�Q | �U�C�W�X�W | �R�D�T | �Q�V�C�Q�Q�Q | �P�S�D�O | �P�O�V�C�W�U�U | �T�T�D�R | �P�X�T�C�O�X�P | �P�O�O |
| �R�U | �T�T�C�U�R�V | �R�U�D�W | �P�P�C�O�P�S | �V�D�Q | �R�W�C�V�P�S | �Q�T�D�U | �S�T�C�U�Q�O | �R�O�D�S | �P�T�O�C�X�W�T | �P�O�O |
| �R�V | �W�T�C�R�T�W | �S�S�D�R | �P�S�C�X�U�Q | �V�D�W | �T�W�C�Q�U�P | �R�O�D�Q | �R�S�C�P�Q�T | �P�V�D�V | �P�X�Q�C�V�O�U | �P�O�O |
| �R�W | �X�O�C�R�T�T | �Q�X�D�Q | �P�S�C�X�W�Q | �S�D�W | �T�V�C�P�T�Q | �P�W�D�T | �P�S�V�C�Q�T�S | �S�V�D�T | �R�O�X�C�V�S�R | �P�O�O |
| �R�X | �X�W�C�U�O�T | �R�U�D�P | �Q�Q�C�U�O�X | �W�D�Q | �S�X�C�U�T�V | �P�W�D�Q | �P�O�Q�C�T�T�S | �R�V�D�T | �Q�V�R�C�S�Q�T | �P�O�O |
| �S�O | �P�W�U�C�X�O�P | �T�W�D�P | �Q�Q�C�U�T�W | �V�D�O | �U�O�C�S�O�U | �P�W�D�W | �T�P�C�V�P�W | �P�U�D�P | �R�Q�P�C�U�W�R | �P�O�O |
| �S�P | �P�V�T�C�P�S�W | �T�T�D�W | �Q�X�C�S�V�T | �X�D�S | �T�W�C�S�R�V | �P�W�D�U | �T�O�C�V�S�O | �P�U�D�Q | �R�P�R�C�W�O�O | �P�O�O |
| �S�Q | �P�V�O�C�O�S�T | �S�T�D�T | �R�U�C�T�S�Q | �X�D�W | �T�O�C�U�U�W | �P�R�D�U | �P�P�U�C�P�Q�S | �R�P�D�P | �R�V�R�C�R�V�X | �P�O�O |
| �S�R | �Q�O�S�C�Q�S�W | �T�W�D�Q | �R�R�C�V�O�R | �X�D�U | �T�O�C�Q�W�S | �P�S�D�R | �U�Q�C�V�T�Q | �P�V�D�X | �R�T�O�C�X�W�V | �P�O�O |
| �S�S | �P�U�T�C�X�T�W | �R�V�D�P | �R�Q�C�X�X�S | �V�D�S | �P�O�P�C�V�R�W | �Q�Q�D�V | �P�S�V�C�O�T�R | �R�Q�D�W | �S�S�V�C�V�S�R | �P�O�O |
| �S�T | �Q�W�W�C�U�O�P | �T�O�D�O | �S�T�C�V�O�S | �V�D�X | �P�P�X�C�W�S�O | �Q�O�D�W | �P�Q�R�C�R�T�P | �Q�P�D�R | �T�V�V�C�S�X�U | �P�O�O |
| �S�U | �R�S�P�C�T�R�S | �S�T�D�P | �T�U�C�O�X�S | �V�D�S | �P�R�T�C�T�T�U | �P�V�D�X | �Q�Q�S�C�R�W�T | �Q�X�D�U | �V�T�V�C�T�U�X | �P�O�O |
| �S�V | �R�V�P�C�Q�Q�Q | �S�W�D�X | �T�V�C�S�S�X | �V�D�U | �P�S�T�C�V�V�P | �P�X�C�Q | �P�W�S�C�R�O�X | �Q�S�D�R | �V�T�W�C�V�T�P | �P�O�O |
| �S�W | �S�Q�X�C�V�O�X | �S�U�D�W | �W�O�C�S�U�O | �W�D�W | �Q�P�U�C�X�X�W | �Q�R�C�U | �P�X�O�C�S�T�T | �Q�O�D�W | �X�P�V�C�U�Q�Q | �P�O�O |
| �S�X | �T�R�X�C�Q�S�O | �R�X�D�Q | �W�U�C�X�Q�T | �U�D�R | �S�O�W�C�R�Q�Q | �Q�X�D�U | �R�S�R�C�Q�S�R | �Q�S�D�X | �P�C�R�V�V�C�V�R�O | �P�O�O |
| �T�O | �S�V�Q�C�Q�S�Q | �R�O�D�R | �P�P�O�C�S�O�Q | �V�D�P | �X�Q�W�C�T�S�T | �T�X�D�U | �S�V�C�S�T�O | �R�D�O | �P�C�T�T�W�C�U�R�X | �P�O�O |
| �T�P | �R�X�S�C�S�O�R | �P�S�D�X | �T�U�C�W�O�P | �Q�D�P | �Q�C�O�S�V�C�O�T�R | �V�V�D�R | �P�T�O�C�T�T�O | �T�D�V | �Q�C�U�S�W�C�W�O�V | �P�O�O |
| �T�Q | �W�X�P�C�P�W�W | �P�U�D�R | �S�O�C�T�R�S | �O�D�W | �S�C�S�X�R�C�U�U�U | �W�Q�D�R | �R�R�C�R�U�W | �O�D�U | �T�C�S�T�W�C�V�T�U | �P�O�O |
| �T�R | �U�U�S�C�R�O�V | �P�R�D�R | �R�S�C�O�W�S | �O�D�V | �S�C�P�Q�T�C�R�W�T | �W�Q�D�S | �P�W�R�C�T�X�O | �R�D�U | �T�C�O�O�V�C�R�U�U | �P�O�O |
| �T�S | �V�S�P�C�S�V�P | �R�P�D�W | �P�S�Q�C�R�W�O | �T�D�X | �P�C�Q�W�O�C�W�U�U | �T�R�D�P | �Q�S�T�C�W�O�O | �P�O�D�Q | �Q�C�S�P�O�C�T�P�V | �P�O�O |
| �T�T | �V�U�R�C�V�R�X | �R�T�D�R | �W�O�C�V�R�W | �R�D�V | �U�X�O�C�V�U�R | �R�Q�D�O | �U�Q�U�C�S�O�T | �Q�X�D�O | �Q�C�P�U�P�C�U�S�T | �P�O�O |
| �T�U | �V�X�T�C�Q�S�Q | �Q�X�D�T | �W�P�C�O�W�V | �R�D�O | �P�C�U�T�X�C�R�T�U | �U�P�D�U | �P�T�X�C�S�U�O | �T�D�X | �Q�C�U�X�T�C�P�S�T | �P�O�O |
�i�k�C�����Y�����j
���Y�ʂ̐����@�@�i�P�ʁ@�g���j
| �敪 �N�x |
���@�@�� | �� | ���Y���� | �� | �L�@�@�� | �� | �C���� | �� | �����l�� | �� |
| �R�Q | �P�C�V�S�W | �S�X�D�W | �W�S�R | �Q�S�D�O | �R�P�S | �W�D�X | �U�O�T | �P�V�D�R | �R�C�T�P�O | �P�O�O |
| �R�R | �Q�C�R�S�Q | �T�V�D�P | �P�C�O�X�Q | �Q�U�D�U | �S�P�S | �P�O�D�P | �Q�T�S | �U�D�Q | �S�C�P�O�Q | �P�O�O |
| �R�S | �Q�C�X�X�T | �V�P�D�T | �R�X�Q | �X�D�R | �U�X�R | �P�U�D�T | �P�P�R | �Q�D�V | �S�C�P�X�R | �P�O�O |
| �R�T | �P�C�T�Q�S | �S�U�D�X | �S�S�S | �P�R�D�V | �T�T�V | �P�V�D�Q | �V�Q�Q | �Q�Q�D�Q | �R�C�Q�S�V | �P�O�O |
| �R�U | �P�C�T�Q�X | �T�O�D�Q | �S�W�R | �P�T�D�X | �U�S�V | �Q�P�D�R | �R�W�T | �P�Q�D�U | �R�C�O�S�S | �P�O�O |
| �R�V | �Q�C�W�U�Q | �U�V�D�T | �R�T�V | �W�D�S | �W�P�W | �P�X�D�R | �Q�O�P | �S�D�W | �S�C�Q�R�W | �P�O�O |
| �R�W | �Q�C�O�P�R | �T�U�D�U | �Q�S�S | �U�D�X | �U�Q�W | �P�V�D�V | �U�U�X | �P�W�D�W | �R�C�T�T�S | �P�O�O |
| �R�X | �R�C�X�O�P | �U�W�D�O | �W�U�O | �P�T�D�O | �S�V�V | �W�D�R | �S�X�T | �W�D�U | �T�C�V�R�R | �P�O�O |
| �S�O | �S�C�X�U�O | �V�U�D�O | �W�T�U | �P�R�D�P | �T�U�S | �W�D�U | �P�S�X | �Q�D�R | �U�C�T�Q�X | �P�O�O |
| �S�P | �S�C�R�U�W | �V�S�D�Q | �P�C�O�P�Q | �P�V�D�Q | �R�U�W | �U�D�R | �P�R�V | �Q�D�R | �T�C�W�W�T | �P�O�O |
| �S�Q | �T�C�U�U�X | �W�S�D�Q | �T�Q�W | �V�D�W | �R�R�U | �T�D�O | �P�X�V | �R�D�O | �U�C�V�R�O | �P�O�O |
| �S�R | �W�C�V�W�Q | �X�R�D�T | �P�V�X | �Q�D�O | �Q�T�T | �Q�D�V | �P�V�X | �P�D�X | �X�C�R�X�T | �P�O�O |
| �S�S | �T�C�Q�T�S | �W�T�D�Q | �P�R�O | �Q�D�P | �S�T�V | �V�D�S | �R�Q�U | �T�D�R | �U�C�P�U�V | �P�O�O |
| �S�T | �P�O�C�O�Q�O | �X�Q�D�T | �P�V�V | �P�D�U | �S�U�X | �S�D�R | �P�U�W | �P�D�U | �P�O�C�W�R�S | �P�O�O |
| �S�U | �X�C�R�Q�U | �X�P�D�Q | �Q�Q�W | �Q�D�Q | �S�P�O | �S�D�O | �Q�U�O | �Q�D�U | �P�O�C�Q�Q�S | �P�O�O |
| �S�V | �X�C�X�Q�W | �X�P�D�O | �R�Q�W | �R�D�O | �S�U�T | �S�D�R | �P�W�W | �P�D�V | �P�O�C�X�O�X | �P�O�O |
| �S�W | �W�C�U�O�S | �W�V�D�R | �S�W�X | �T�D�O | �T�X�R | �U�D�O | �P�V�S | �P�D�V | �X�C�W�U�O | �P�O�O |
| �S�X | �P�R�C�R�W�R | �W�T�D�O | �R�X�U | �Q�D�T | �P�C�U�R�W | �P�O�D�S | �R�Q�R | �Q�D�P | �P�T�C�V�S�O | �P�O�O |
| �T�O | �U�C�R�O�P | �T�U�D�V | �T�O�P | �S�D�T | �S�C�Q�U�S | �R�W�D�R | �T�U | �O�D�T | �P�P�C�P�Q�Q | �P�O�O |
| �T�P | �Q�C�O�S�T | �Q�O�D�T | �R�T�O | �R�D�T | �V�C�S�O�W | �V�S�D�S | �P�T�U | �P�D�U | �X�C�X�T�X | �P�O�O |
| �T�Q | �S�C�V�X�R | �Q�P�D�W | �P�P�Q | �O�D�T | �P�V�C�O�Q�X | �V�V�D�S | �U�S | �O�D�R | �Q�P�C�X�X�W | �P�O�O |
| �T�R | �Q�C�S�X�S | �P�Q�D�X | �R�S | �O�D�Q | �P�U�C�T�X�S | �W�U�D�O | �P�V�T | �O�D�X | �P�X�C�Q�X�V | �P�O�O |
| �T�S | �Q�C�S�O�S | �R�P�D�T | �Q�V�W | �R�D�U | �S�C�V�P�R | �U�P�D�W | �Q�R�T | �R�D�P | �V�C�U�R�O | �P�O�O |
| �T�T | �R�C�P�U�O | �T�P�C�T | �Q�O�U | �R�D�R | �Q�C�Q�W�W | �R�V�D�O | �S�W�V | �V�D�X | �U�C�P�S�P | �P�O�O |
| �T�U | �Q�C�S�U�W | �Q�X�D�S | �P�U�R | �P�D�X | �T�C�T�V�W | �U�U�D�R | �Q�O�S | �Q�D�S | �W�C�S�P�R | �P�O�O |
�i�k�C�����Y�����j
�i��j ���ސ��Y�ʂ���ы��l�z�@�@�i�P�ʁ@�g���E��~�j
| �敪 �N�� |
�T�@�@�@�@�P | �C�@���@�V | �T�@�@�@�o | �j�@�V�@�� | �X�P�g�E�^�� | �J�@�@���@�@�C | ���@�@�́@�@�� | ���@�@�@�@�@�v | ||||||||
| �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | |
| 32 | 34.6 | 6,951 | 865.0 | 12,671 | 41.0 | 1,507 | 130.5 | 10,294 | 4.1 | 124 | 310.3 | 12,775 | 362.5 | 12,057 | 1,748.6 | 56,379 |
| 33 | 83.3 | 15,262 | 1,361.1 | 21,025 | 228.2 | 3,692 | 5.5 | 418 | 0.4 | 16 | 383.4 | 11,725 | 279.7 | 10,689 | 2,341.6 | 62,827 |
| 34 | 61.3 | 13,117 | 481.5 | 7,781 | 1,605.1 | 20,633 | 16.4 | 834 | 24.9 | 650 | 333.7 | 11,965 | 472.3 | 12,669 | 2,955.2 | 67,649 |
| 35 | 20.0 | 6,050 | 487.3 | 9,954 | 91.0 | 2,397 | 75.6 | 4,008 | 19.3 | 484 | 419.9 | 16,235 | 410.6 | 13,977 | 1,523.7 | 53,105 |
| 36 | 35.7 | 8,364 | 177.3 | 2,912 | 190.9 | 3,608 | 100.3 | 3,610 | 332.7 | 8,172 | 267.6 | 11,879 | 424.6 | 17,092 | 1,529.1 | 55,637 |
| 37 | 90.0 | 21,683 | 55.8 | 1,641 | 674.7 | 9,422 | 24.6 | 1,538 | 1,041.0 | 16,614 | 165.3 | 7,641 | 810.8 | 26,819 | 2,862.2 | 85,358 |
| 38 | 75.1 | 26,267 | 83.2 | 1,683 | 10.5 | 346 | 64.0 | 5,425 | 1,003.5 | 20,568 | 274.8 | 15,657 | 502.1 | 20,409 | 2,013.2 | 90,355 |
| 39 | 29.8 | 12,493 | 14.1 | 329 | 1.2 | 22 | 7.5 | 437 | 2,853.6 | 44,001 | 342.6 | 16,791 | 651.9 | 24,532 | 3,900.7 | 98,605 |
| 40 | 36.8 | 14,771 | 0.3 | 11 | - | - | 171.8 | 5,921 | 3,172.7 | 92,367 | 497.3 | 25,231 | 1,081.1 | 48,600 | 4,960.2 | 186,901 |
| 41 | 28.0 | 12,792 | 16.3 | 223 | 143.0 | 1,123 | 153.0 | 12,817 | 2,737.9 | 71,749 | 466.3 | 30,733 | 823.3 | 40,711 | 4,367.8 | 175,148 |
| 42 | 25.6 | 11,606 | - | - | 10.0 | 176 | - | - | 4,411.8 | 76,762 | 366.6 | 26,504 | 854.6 | 54,997 | 5,668.6 | 170,045 |
| 43 | 23.0 | 12,561 | 20.0 | 80 | 3.0 | 68 | - | - | 7,387.0 | 93,956 | 652.0 | 43,523 | 697.0 | 54,060 | 8,782.0 | 204,248 |
| 44 | - | - | - | - | 15.0 | 830 | - | - | 4,112.0 | 57,217 | 727.0 | 37,539 | 400.0 | 70,372 | 5,254.0 | 165,958 |
| 45 | - | - | 25.0 | 225 | 342.0 | 4,316 | - | - | 6,847.0 | 109,126 | 2,098.0 | 96,624 | 708.0 | 78,310 | 10,020.0 | 288,601 |
| 46 | 36.0 | 17,943 | - | - | 2.0 | 54 | - | - | 6,226.0 | 129,955 | 2,164.0 | 121,669 | 898.0 | 71,913 | 9,326.0 | 341,534 |
| 47 | 64.0 | 34,701 | 16.0 | 475 | 151,0 | 2,755 | - | - | 8,308.0 | 201,272 | 812.0 | 78,731 | 577.0 | 53,288 | 9,928.0 | 371,222 |
| 48 | 104.0 | 58,135 | - | - | - | - | - | - | 7,220.0 | 190,051 | 833.0 | 116,009 | 447.0 | 65,514 | 8,604.0 | 429,709 |
| 49 | 49.0 | 37,889 | 347.0 | 5,217 | 355.0 | 5,334 | - | - | 10,200.0 | 255,059 | 1,918.0 | 155,976 | 514.0 | 79,765 | 13,383.0 | 539,240 |
| 50 | 85.0 | 68,375 | 12.0 | 298 | 173.0 | 3,761 | - | - | 3,960.0 | 102,652 | 1,212.0 | 199,454 | 859.0 | 97,702 | 6,301.0 | 472,242 |
| 51 | 137.0 | 102,568 | 34.5 | 869 | 188.0 | 5,419 | - | - | 526.0 | 21,003 | 840.0 | 164,104 | 319.0 | 100,440 | 2,045.0 | 394,403 |
| 52 | 443.0 | 377,491 | 5.0 | 198 | 23.0 | 857 | - | - | 3,075.0 | 241,966 | 807.0 | 171,641 | 440.0 | 99,035 | 4,793.0 | 891,188 |
| 53 | 310.0 | 276,306 | 108.0 | 2,176 | 2.0 | 78 | - | - | 1,080.0 | 96,493 | 790.0 | 180,177 | 204.0 | 109,107 | 2,494.0 | 664,307 |
| 54 | 391,0 | 264,683 | - | - | 7.0 | 198 | - | - | 530.0 | 49,125 | 983.0 | 304,441 | 493.0 | 426,972 | 2,404.0 | 741,471 |
| 55 | 412.0 | 241,331 | 32.0 | 1,080 | 8.0 | 194 | - | - | 1,412.0 | 151,260 | 774.0 | 235,518 | 522.0 | 518,426 | 3,160.0 | 763,739 |
| 56 | 1,147.0 | 489,194 | 105,0 | 1,084 | 2.0 | 56 | - | - | 118.0 | 11,483 | 775.0 | 186,857 | 321.0 | 106,622 | 2,468.0 | 795,242 |
�i��j ���Y�������Y�ʂ���ы��l�z�@�@�i�P�ʁ@�g���E��~�j
| �敪 �N�� |
�C�@�@�@�J | �^�@�@�@�R | �i�@�}�@�R | �с@�K�@�j | ���̑��J�j | �E�@�@�@�j | �G�@�@�@�r | ���@�@�́@�@�� | �v | |||||||||
| �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | |
| 32 | 26.0 | 770 | 51.8 | 1,939 | - | - | - | - | 9.5 | 430 | - | - | - | - | 755.5 | 23,917 | 842.8 | 27,056 |
| 33 | 3.6 | 101 | 35.0 | 1,692 | - | - | - | - | 3.0 | 172 | - | - | - | - | 1,050.4 | 7,770 | 1,092.0 | 9,735 |
| 34 | 10.3 | 125 | 57.1 | 3,081 | - | - | - | - | 19.3 | 1,384 | - | - | - | - | 305.7 | 3,625 | 392.4 | 8,215 |
| 35 | 0.2 | 6 | 30.7 | 1,954 | - | - | - | - | 23.2 | 1,103 | - | - | - | - | 389.7 | 3,835 | 443.8 | 6,898 |
| 36 | 15.7 | 378 | 44.5 | 3,286 | - | - | - | - | 23.6 | 950 | - | - | - | - | 399.4 | 6,400 | 483.2 | 11,014 |
| 37 | 27.7 | 863 | 20.3 | 1,655 | - | - | - | - | 9.2 | 455 | - | - | - | - | 299.7 | 11,989 | 356.9 | 14,962 |
| 38 | 23.9 | 368 | 25.1 | 2,396 | - | - | - | - | 17.3 | 923 | - | - | - | - | 178.0 | 11,295 | 244.3 | 14,982 |
| 39 | 5.3 | 318 | 34.7 | 3,941 | 37.9 | 2,102 | 7.6 | 668 | 21.8 | 1,335 | 5.5 | 220 | 16.1 | 5,202 | 731.4 | 8,823 | 860.3 | 22,609 |
| 40 | 1.4 | 58 | 31.8 | 4,135 | 34.9 | 3,021 | 6.6 | 467 | 38.7 | 3,332 | 6.3 | 328 | 6.0 | 2,608 | 730.0 | 8,709 | 855.7 | 22,658 |
| 41 | 5.2 | 172 | 38.6 | 6,019 | 26.2 | 2,453 | 2.5 | 250 | 11.6 | 854 | 8.2 | 453 | 24.2 | 7,151 | 895.2 | 12,123 | 1,011.7 | 29,475 |
| 42 | - | - | 44.5 | 5,651 | 43.9 | 4,232 | 3.4 | 225 | 54.7 | 4,376 | 22.3 | 1,498 | 49.0 | 15,910 | 310.0 | 4,650 | 527.8 | 36,542 |
| 43 | - | - | 33.0 | 4,676 | 54.0 | 6.284 | 2.0 | 182 | 34.0 | 4,939 | 15.0 | 759 | 32.0 | 16,594 | 9.0 | 270 | 179.0 | 33,703 |
| 44 | 6.0 | 434 | 45.0 | 4,587 | 34.0 | 4.284 | - | - | 17.0 | 2,906 | 0 | 2,428 | 28.0 | 18,355 | - | - | 130.0 | 32,994 |
| 45 | 2.0 | 148 | 75.0 | 11,059 | 33.0 | 5.634 | - | - | 28.0 | 1,893 | 0 | 2,678 | 39.0 | 24,292 | - | - | 177.0 | 45,704 |
| 46 | 6.0 | 706 | 73.0 | 15,742 | 13.0 | 1,961 | - | - | 91.0 | 6,710 | 0 | 665 | 45.0 | 30,310 | - | - | 228.0 | 56,094 |
| 47 | 4.0 | 752 | 38.0 | 8,239 | 20.0 | 3,468 | 7.0 | 1,320 | 20.0 | 2,333 | 1.0 | 2,286 | 43.0 | 26,048 | 195.0 | 13,003 | 328.0 | 57,449 |
| 48 | 52.0 | 6,275 | 40.0 | 8,436 | 28.0 | 5,633 | 40.0 | 10,377 | 17.0 | 2,353 | 0 | 2,154 | 21.0 | 26,152 | 291.0 | 19,080 | 489.0 | 80,460 |
| 49 | 77.0 | 23,861 | 23.0 | 6,215 | 9.0 | 2,561 | 15.0 | 2,366 | 73.0 | 9,029 | 1.0 | 677 | 61.0 | 33,955 | 137.0 | 8,261 | 396.0 | 86,925 |
| 50 | 100.0 | 25,806 | 4.0 | 1,106 | 2.0 | 771 | 18.0 | 6,581 | - | - | - | - | 27.0 | 26,083 | 350.0 | 50,055 | 501.0 | 110,402 |
| 51 | 15.0 | 6,089 | 4.0 | 1,518 | 2.5 | 452 | 12.0 | 4,850 | - | - | - | - | 15.0 | 17,191 | 301.0 | 26,701 | 350.0 | 56,801 |
| 52 | 7.0 | 2.526 | 3.0 | 1,459 | 1.0 | 371 | 14.0 | 8,433 | 3.0 | 1,282 | - | - | 8.0 | 18,906 | 76.0 | 7,557 | 112.0 | 40,534 |
| 53 | 6.0 | 4,032 | 0 | 201 | 6.0 | 1,966 | 18.0 | 13,901 | - | - | 0 | 927 | 4.0 | 13,057 | - | - | 34.0 | 34,084 |
| 54 | 183.0 | 86,041 | 23.0 | 13,394 | 10.0 | 3,022 | 27.0 | 17,641 | - | - | - | - | 7.0 | 19,643 | 28.0 | 2,693 | 278.0 | 142,380 |
| 55 | 114.0 | 35,267 | 29.0 | 16,998 | 4.0 | 1,742 | 21.0 | 9,954 | 5.0 | 2,923 | 0 | 922 | 3.0 | 9,361 | 30.0 | 3,571 | 206.0 | 80,738 |
| 56 | 60.0 | 27,499 | 56.0 | 20,540 | �@ | 1,760 | 34.0 | 15,443 | 5.0 | 1,413 | - | - | 4.0 | 14,432 | - | - | 163.0 | 81,087 |
�i�R�j�L�ސ��Y�ʂ���ы��l���@�@�@�i�P�ʁ@�g���E��~�j
| �敪 �N�� |
�z�@�b�@�L�@�L | �z�@�^�@�e�@�L | ���@�@�́@�@�� | �v | ||||
| �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | |
| �R�Q | �R�O�V�D�O | �P�O�C�T�U�Q | �| | �| | �U�D�T | �R�W�Q | �R�P�R�D�T | �P�O�C�X�S�S |
| �R�R | �S�P�Q�D�X | �P�U�C�T�R�U | �| | �| | �P�D�P | �X�S | �S�P�S�D�O | �P�U�C�U�R�O |
| �R�S | �U�W�R�D�U | �Q�Q�C�Q�Q�V | �| | �| | �X�D�W | �T�S�Q | �U�X�R�D�S | �Q�Q�C�V�U�X |
| �R�T | �T�T�S�D�R | �Q�U�C�S�S�P | �| | �| | �Q�D�S | �V�W�P | �T�T�U�D�V | �Q�V�C�Q�Q�Q |
| �R�U | �U�R�R�D�S | �R�V�C�U�U�P | �| | �| | �P�R�D�W | �P�C�O�T�R | �U�S�V�D�Q | �R�W�C�V�P�S |
| �R�V | �V�X�U�D�Q | �T�V�C�O�P�T | �| | �| | �Q�P�D�S | �P�C�Q�S�U | �W�P�V�D�U | �T�W�C�Q�U�P |
| �R�W | �U�O�R�D�O | �T�T�C�Q�X�O | �| | �| | �Q�T�D�S | �P�C�W�U�Q | �U�Q�W�D�S | �T�V�C�P�T�Q |
| �R�X | �S�R�V�D�X | �S�T�C�X�V�P | �S�D�U | �W�T�R | �R�S�D�O | �Q�C�W�R�R | �S�V�U�D�T | �S�X�C�U�T�V |
| �S�O | �T�R�W�D�S | �T�V�C�V�O�S | �P�D�V | �S�O�Q | �Q�R�D�T | �Q�C�R�O�O | �T�U�R�D�U | �U�O�C�S�O�V |
| �S�P | �R�S�O�D�Q | �T�T�C�S�V�S | �P�D�P | �R�P�U | �Q�U�D�S | �Q�C�U�S�V | �R�U�V�D�V | �T�W�C�S�R�V |
| �S�Q | �R�O�O�D�X | �S�T�C�Q�X�U | �T�D�S | �P�C�R�T�W | �R�O�D�O | �S�C�O�P�S | �R�R�U�D�R | �T�O�C�U�U�W |
| �S�R | �Q�R�P�D�O | �S�U�C�X�U�X | �P�S�D�O | �P�C�X�U�P | �P�O�D�O | �P�C�R�T�R | �Q�T�T�D�O | �T�O�C�Q�W�S |
| �S�S | �S�P�T�D�O | �X�R�C�W�P�O | �P�Q�D�O | �R�C�V�U�S | �R�O�D�O | �S�C�P�U�S | �S�T�V�D�O | �P�O�P�C�V�R�W |
| �S�T | �S�R�T�D�O | �P�P�R�C�W�P�W | �P�R�D�O | �R�C�O�R�Q | �Q�P�D�O | �Q�C�X�X�O | �S�U�X�D�O | �P�P�X�C�W�S�O |
| �S�U | �R�X�P�D�O | �P�R�P�C�W�O�W | �W�D�O | �P�C�V�U�T | �P�P�D�O | �P�C�X�W�R | �S�P�O�D�O | �P�R�T�C�T�T�U |
| �S�V | �R�W�X�D�O | �P�Q�W�C�U�T�V | �V�O�D�O | �P�T�C�V�W�Q | �U�D�O | �P�C�R�R�Q | �S�U�T�D�O | �P�S�T�C�V�V�P |
| �S�W | �R�P�Q�D�O | �P�T�R�C�R�X�W | �Q�U�T�D�O | �U�P�C�R�W�W | �P�U�D�O | �Q�C�Q�P�Q | �T�X�R�D�O | �Q�P�U�C�X�X�W |
| �S�X | �P�U�O�D�O | �W�S�C�S�R�O | �P�C�S�U�W�D�O | �R�Q�P�C�O�R�T | �P�O�D�O | �Q�C�W�T�V | �P�C�U�R�W�D�O | �S�O�W�C�R�Q�Q |
| �T�O | �P�O�U�D�Q | �V�U�C�U�P�U | �S�C�P�S�P�D�O | �W�T�O�C�Q�W�S | �P�V�D�O | �P�C�U�S�T | �S�C�Q�U�S�D�Q | �X�Q�W�C�T�S�T |
| �T�P | �V�W�D�O | �U�T�C�S�U�Q | �V�C�Q�T�W�D�O | �P�C�X�U�X�C�X�Q�S | �V�Q�D�O | �P�P�C�U�U�V | �V�C�S�O�W�D�O | �Q�C�O�S�V�C�O�T�R |
| �T�Q | �S�U�D�O | �R�V�C�U�T�O | �P�U�C�W�R�W�D�O | �S�C�S�R�O�C�V�X�S | �P�S�T�D�O | �Q�T�C�Q�Q�Q | �P�V�C�O�Q�X�D�O | �S�C�S�X�R�C�U�U�U |
| �T�R | �Q�T�D�O | �Q�O�C�X�W�W | �P�U�C�R�W�U�D�O | �S�C�O�V�R�C�U�T�S | �P�W�R�D�O | �R�O�C�V�S�R | �P�U�C�T�X�S�D�O | �S�C�P�Q�T�C�R�W�T |
| �T�S | �P�D�O | �P�C�O�O�T | �S�C�U�V�T�D�O | �P�C�Q�U�V�C�X�Q�Q | �R�V�D�O | �P�P�C�X�R�X | �S�C�V�P�R�D�O | �P�C�Q�W�O�C�W�U�U |
| �T�T | �Q�O�D�O | �P�V�C�S�W�R | �Q�C�Q�T�P�D�O | �U�T�X�C�V�P�W | �P�V�D�O | �P�R�C�T�U�Q | �Q�C�Q�W�W�D�O | �U�X�O�C�V�U�R |
| �T�U | �V�R�D�O | �U�O�C�X�W�X | �T�C�S�V�R�D�O | �P�C�T�W�U�C�W�S�O | �R�Q�D�O | �P�P�C�T�Q�V | �T�C�T�V�W�D�O | �P�C�U�T�X�C�R�T�U |
�i�S�j�C���ސ��Y������ѐ��Y�z�@�@�@�i�P�ʁ@�g���E��~�j
| �敪 �N�� |
�R�@�@���@�@�u | ���@�@�J�@�@�� | �m�@�@�@�� | ���@�@�́@�@�� | �v | |||||
| �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | �� | �z | |
| �R�Q | �U�O�T�D�Q | �U�U�C�X�S�P | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �U�O�T�D�Q | �U�U�C�X�S�P |
| �R�R | �Q�T�R�D�X | �R�S�C�R�T�U | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �Q�T�R�D�X | �R�S�C�R�T�U |
| �R�S | �P�P�Q�D�T | �P�V�C�V�O�P | �| | �| | �| | �| | �O�D�R | �Q | �P�P�Q�D�W | �P�V�C�V�O�R |
| �R�T | �V�Q�Q�D�O | �P�O�V�C�W�U�U | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �V�Q�Q�D�O | �P�O�V�C�W�U�U |
| �R�U | �R�W�Q�D�X | �S�T�C�S�R�X | �P�D�Q | �P�S�X | �| | �| | �O�D�V | �R�Q | �R�W�S�D�W | �S�T�C�U�Q�O |
| �R�V | �Q�O�P�D�O | �R�S�C�P�Q�T | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �Q�O�P�D�O | �R�S�C�P�Q�T |
| �R�W | �U�U�W�D�S | �P�S�V�C�P�X�T | �| | �| | �| | �| | �O�D�V | �T�X | �U�U�X�D�P | �P�S�V�C�Q�T�S |
| �R�X | �S�X�T�D�O | �P�O�Q�C�S�S�S | �| | �| | �| | �| | �O�D�Q | �P�P�O | �S�X�T�D�Q | �P�O�Q�C�T�T�S |
| �S�O | �P�S�V�D�O | �T�P�C�P�T�U | �P�D�V | �S�U�P | �| | �| | �O�D�P | �P�O�P | �P�S�W�D�W | �T�P�C�V�P�W |
| �S�P | �P�R�T�D�U | �T�O�C�R�T�T | �P�D�P | �R�R�O | �| | �| | �O�D�P | �T�T | �P�R�U�D�W | �T�O�C�V�S�O |
| �S�Q | �P�X�S�D�O | �P�P�T�C�O�Q�S | �P�D�O | �Q�P�T | �| | �| | �Q�D�R | �W�W�T | �P�X�V�D�R | �P�P�U�C�P�Q�S |
| �S�R | �P�T�R�D�O | �T�V�C�Q�X�O | �U�D�O | �P�C�W�Q�Q | �| | �| | �Q�O�D�O | �R�C�U�S�O | �P�V�X�D�O | �U�Q�C�V�T�Q |
| �S�S | �R�P�Q�D�O | �P�S�Q�C�P�P�O | �S�D�O | �P�C�U�S�O | �O | �X�Q�O | �P�O�D�O | �Q�C�R�W�R | �R�Q�U�D�O | �P�S�V�C�O�T�R |
| �S�T | �P�S�Q�D�O | �P�O�T�C�Q�Q�S | �Q�S�D�O | �V�C�U�P�P | �Q�D�O | �P�O�C�T�P�U | �| | �| | �P�U�W�D�O | �P�Q�R�C�R�T�P |
| �S�U | �Q�T�O�D�O | �Q�P�V�C�U�O�O | �X�D�O | �R�C�Q�V�R | �P�D�O | �R�C�T�P�Q | �| | �| | �Q�U�O�D�O | �Q�Q�S�C�R�W�T |
| �S�V | �P�W�T�D�O | �P�W�Q�C�U�O�O | �R�D�O | �X�Q�T | �O | �V�W�S | �| | �| | �P�W�W�D�O | �P�W�S�C�R�O�X |
| �S�W | �P�U�S�D�O | �P�W�V�C�O�T�O | �P�O�D�O | �R�C�S�O�T | �| | �| | �| | �| | �P�V�S�D�O | �P�X�O�C�S�T�T |
| �S�X | �R�Q�Q�D�O | �R�S�Q�C�O�Q�Q | �O | �W | �| | �| | �P�D�O | �P�C�Q�P�R | �R�Q�R�D�O | �R�S�R�C�Q�S�R |
| �T�O | �T�U�D�O | �S�V�C�S�T�O | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �T�U�D�O | �S�V�C�S�T�O |
| �T�P | �P�T�U�D�O | �P�T�O�C�T�T�O | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �P�T�U�D�O | �P�T�O�C�T�T�O |
| �T�Q | �U�R�D�O | �R�R�C�Q�P�X | �P�D�O | �P�S�X | �| | �| | �| | �| | �U�S�D�O | �R�R�C�R�U�W |
| �T�R | �P�V�T�D�O | �P�W�R�C�T�X�O | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �P�V�T�D�O | �P�W�R�C�T�X�O |
| �T�S | �Q�R�T�D�O | �Q�S�T�C�W�O�O | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �Q�R�T�D�O | �Q�S�T�C�W�O�O |
| �T�T | �S�W�V�D�O | �U�Q�U�C�S�O�R | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �S�W�V�D�O | �U�Q�U�C�S�O�T |
| �T�U | �Q�O�S�D�O | �P�T�X�C�S�U�O | �| | �| | �| | �| | �| | �| | �Q�O�S�D�O | �P�T�X�C�S�U�O |
���D���̐���
�@���Ƃ��o�c���邽�߂ɕK�v�Ȑ��Y��i�Ƃ��ďd�v�ȋ��D�́A���a�R�Q�N�ȍ~�ɂ����锪�_�n��̊K�w�ʐ��ڂ��݂�ƕʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A���ƌ`�Ԃ��p������̂Ƃ��A�������A���ݐ�C���Ƃ����S�ł��邱�Ƃ���A���ׂĂP�O�g�������w�Ɍ����Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��낤�B
�@����̓I�ɂ݂�ƁA�����̑����D���͂R�V�N�i�P�X�U�Q�j�̂X�O�O�ǂ����ɂ��ĔN�X�������͂��߁A�S�S�A�T�N�������ɍĂё����̌X���������A�T�O�N�Ȍ�͂V�O�O�ǂ���������x�Ő��ڂ��Ă���B���������̓�����݂�ƁA���͑D�͑S�̓I�ɔN�X�����̌X���ɂ���̂ɑ��A�����́@�D�͂R�V�N�̂U�W�S�ǂ��s�[�N�ɋ}���Ȍ������݂��A���D���������̗v���́A���ǖ����͑D�̌����ɂ����̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@����A���͑D�̋K�͕ʕω����݂�ƁA�R�g�����������|�I�ɑ����A�Ȃ��ł��P�g���ȏ�R�g�������w�͂R�X�N�ɂ͂R�O�O�ǂ��A����ɁA�T�O�N�ɂ͂T�O�O�ǂ���Ƃ��������������A�����̂V�O�p�[�Z���g�ȏ���߂Ă���B���a�R�Q�N�����̖����͑D�͑����̂V�P�p�[�Z�\�g�ł��������̂��A�S�O�N�ɂ͂R�Q�p�[�Z���g�A�S�U�N�ɂ͂킸���Q�p�[�Z���g�̂P�R�ǂɂȂ��Ă���B���������͑D�Ƃ͂����Ă��A�����̖����͑D�̑D���Ƀ��[�^�[�����t�����A������D�O�@�t���̂��̂������A�������A�R�g�������̂��̂��啔�����߂āA�����Ƃ𒆐S�Ƃ��鏬�K�͌o�c���x�z�I�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ������̂ł���B
�@���a�S�T�N���납��̃X�P�g�E�^���̐����ɂ�āA�P�O�g�������w�̓��͑D������ɑ��������̂ł��邪�A�s�U������}�����T�O�N�ȍ~�͍Ăь������͂��߂Ă���A�S�̂ɐ�߂銄�����ɂ߂ď��Ȃ��B
�@�����������D�����̌��ۂ́A���̂܂ܓ����ɂ����鋙�Ɗ�Ղ̓������ے����A���̓I�ɐ�C���B���ƂɈڍs�������Ƃ������Ă���Ƃ����悤�B
�K�w�ʋ��D���̐���
| �敪 �N�� |
�� ���͑D |
���@�@�@�@�@�@�@�@�́@�@�@�@�@�@�@�@�D | ���@�v | |||||
| �P�g�� ���@�� |
�P�D�O �`�Q�D�X |
�R�D�O �`�S�D�X |
�T�D�O �`�X�D�X |
�P�O�D�O �g���ȏ� |
�v | |||
| ���R�Q | �T�W�P | �P | �W�P | �R�S | �T | �@ | �P�Q�P | �V�O�Q |
| �R�R | �T�V�T | �P | �W�S | �R�U | �T | �@ | �P�Q�U | �V�O�P |
| �R�S | �T�Q�U | �S | �P�P�W | �R�W | �W | �@ | �P�U�W | �U�X�S |
| �R�T | �S�T�O | �P�O | �P�S�P | �S�O | �R�S | �@ | �Q�Q�T | �U�V�T |
| �R�U | �U�Q�T | �P�S | �P�S�W | �S�P | �P�Q | �@ | �Q�P�T | �W�S�O |
| �R�V | �U�W�S | �P�T | �P�S�V | �S�O | �P�S | �@ | �Q�P�U | �X�O�O |
| �R�W | �S�R�T | �Q�Q | �Q�S�R | �S�Q | �P�P | �@ | �R�P�W | �V�T�R |
| �R�X | �Q�U�P | �X�X | �R�R�T | �T�V | �P�T | �@ | �T�O�U | �V�U�V |
| �S�O | �Q�S�S | �P�P�Q | �R�R�X | �U�Q | �S�@ | �@ | �T�P�V | �V�U�P |
| �S�P | �W�W | �P�O�U | �R�R�T | �T�V | �W | �@ | �T�O�U | �T�X�S |
| �S�Q | �X�W | �P�O�T | �R�R�W | �U�P | �W | �P | �T�P�R | �U�P�P |
| �S�R | �T�W | �P�O�P | �R�R�W | �U�S | �P�R | �Q | �T�P�W | �T�V�U |
| �S�S | �Q�S | �V�S | �Q�Q�S | �W | �P�U | �P | �R�Q�R | �R�S�V |
| �S�T | �P�V | �P�O�W | �R�S�T | �T�V | �P�U | �P | �T�Q�V | �T�S�S |
| �S�U | �P�R | �P�O�T | �R�S�S | �T�S | �Q�V | �P | �T�R�P | �T�S�S |
| �S�V | �P�R | �P�O�S | �R�T�W | �S�V | �S�O | �P | �T�T�O | �T�U�R |
| �S�W | �P�R | �P�O�W | �R�W�X | �S�R | �S�V | �Q | �T�W�X | �U�O�Q |
| �S�X | �P�Q | �X�T | �S�R�Q | �S�P | �S�V | �Q | �U�P�V | �U�Q�X |
| �T�O | �P�Q | �W�V | �T�P�T | �T�W | �S�T | �P | �V�O�U | �V�P�W |
| �T�P | �P | �V�P | �T�Q�T | �V�Q | �Q�X | �P | �U�X�W | �U�X�X |
| �T�Q | �P | �U�R | �T�S�Q | �P�O�S | �Q�U | �P | �V�R�U | �V�R�V |
| �T�R | �P | �T�O | �T�O�Q | �P�S�U | �S�U | �@ | �V�S�S | �V�S�T |
| �T�S | �P | �S�W | �S�V�R | �P�S�W | �T�R | �P | �V�Q�R | �V�Q�S |
| �T�T | �P | �R�S | �S�V�V | �P�T�Q | �T�R | �P | �V�P�V | �V�P�W |
| �T�U | �| | �Q�X | �S�V�T | �P�T�T | �T�Q | �P | �V�P�Q | �V�P�Q |
�i�k�C�����Y�����j
��U�߁@���{�B�̐���
�z�b�L�L
�@���ĊL�ނ̐��Y��̂��߂Ă����z�b�L�L�ɂ��Ă͎c�O�Ȃ���Â��j�����Ȃ��A�킸���ɖ����S�R�N�i�P�X�P�O�j�̐��Y�������сi�R�R�Q�U�L���E�Q�Q�Q�~�j�Ƃ����L�^�i�����j���݂�����x�ɂ����Ȃ��B�������ØV�̌��`���ł͂��邪�A�����̖�����͉ē~���킸�P���ɂQ�A�R�O�O�O��������̂ŁA���i���Q�T����S�O�ň�Z�K�Ƃ������l�ł��������A����ł��P���ɂP�O�~���x�̐��g��������A�ꂩ���P�O���o�����Ă��P�O�O�~���炢�ɂȂ����̂ŁA�����t�ł��y�ȕ�炵�����Ă������̂��Ƃ������A����ɑ���ˑ��x�̍����Ɨ��l�Ԃ��������b�ƂȂ��Ă���B
�@��N�̏��a�X�N�i�P�X�R�S�j�k�C�����Y�����ꔟ�َx��ҏS�ɂ��u���Θp�y�����̏����v�ɂ��A
�@�u�k��L�͘p���̎��鏊�̉��݂ɐ������Ă��邪�A��r�I�Z���Ȓn�т͒������A�Î납�甪�_�Ɏ���C��ʼn͐�̒������D���̊C��Ő��[�l�q�T�����q���ł��K������n�тƂ��Đ������Ă���B�v
�Ɠ`���Ă��邤���A�ߔN�̗��l�ɂ��s�U�ɂ��ĐG��A���̑��B���@�Ƃ��āA
�@�u�q�g�f�ދy�їL�����H�����L�ނ̋쏜���͂���A�L�Q�������쏜���ĔɐB���ƍ̎旦�����s��ۂ悤�ɍu�����Ȃ�A���N�̐��������邱�Ƃ͂����č���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�v
�ƗL�]���ɂ��ďq�ׁA���̓����̓��n���ɂ����鋙�l������\�̂悤�ɋL���A�����̐��Y�����������Ƃ������Ă���B
�@�������A���������ˑ��x�̍����z�b�L�L������ی삷�邽�ߔ��_���Ɖ�i���g�j�ł́A���������̎���Ԃ̎���I�ȒZ�k�����̐ݒ�ȂǁA�ϋɓI�ȑ���u�����̂ł������B
�z�b�L�L���l���@�@�@�i�P�ʁ@�сE�~�j
| �N�� �敪 �n�� |
���a�S�N | ���a�T�N | ���a�U�N | ���a�V�N | ���a�W�N | |||||
| ���� | ���z | ���� | ���z | ���� | ���z | ���� | ���z | ���� | ���z | |
| ���@�@�� | �@ | �@ | �Q�O | �P�Q | �P�O�O | �Q�W | �P�T�O | �T�U | �W�O | �P�U |
| ���@�@�_ | �R�O�C�T�O�O | �P�P�C�W�O�O | �T�R�C�R�S�O | �P�R�C�R�R�T | �T�U�C�Q�W�O | �P�P�C�Q�R�U | �T�O�C�S�S�O | �P�O�C�O�S�W | �T�T�C�T�O�O | �Q�T�C�P�O�O |
�i���Θp�y�ѐ����̏����E�k�������x�j
�@���a�Q�U�N�ɂ͕s�U�ɂ��������Ƃ̐U���܂��N�v�悪��������A�����Ɏ��Ƃɒ��肵���̂ł��邪�A���̒��ł��z�b�L�L�ɑ����d�͑傫���A���͊W�����Ƌ������ĊL�̕s�����ӏ��L�i�}���O�����}���K�j�Ə̂���F��̌`���������̂ōk���A�Q�W�A�R�O�̓N�ɂ킽���ėc��L�̈ڐA�����݂��B���̂ق��A���₩����Y���ɂ����ĂT���i��P�U���T�O�O�O�������[�g���j���k�N���Ă��̑��B��}�����B�܂��A�Q�X�N����P�O���N�ɂ킽���ăq�g�f�̎�����サ�A�����グ����ȂǔɐB��Q�̏����ɓw�߂��B���ɂR�S�N�x����S�R�N�x�܂ŘA�����Ēt�L�i�ꍇ�ɂ���Ă͐��L�j���ړ��̂����������A�܂��A�S�V�N�ɂ͂S�R�Q�����̒t�L���ڐA����ȂǁA���̑��B��}�����̂ł���B�������z�b�L�L�̋��l�����݂�ƁA�R�V�N�̂V�X�U�g�����s�[�N�ɂ��āA���̑O��͂��悻�T�O�O�g�����㉺���邱�Ƃ��ێ����Ă������̂́A�S�O�N���납��킸���������������͂��߁A�S�X�N�ɂ͂P�O�O�g����ɗ������݁A�T�P�N�ɂ͂���Ɉ������ĂP�O�O�g�������ƂȂ�A���N�ƑΔ䂵�ē���l�����Ȃ��ƂȂ����B
�@�����������Y�ʂ̌������R�Ƃ��ẮA���R�Ɏ������̂��̂̌������������邪�A�S�X�N���납��͂��߂�ꂽ�u�}���O���v�̓��͎g�p�ɂ�鏝�L�̎��ł�A�C����̈����Ȃǂ������ƂȂ��Ă�����̂Ƃ݂��Ă���A���̂܂ܕ��u����Ή����炸�z�b�L�L��ł̊�@�����͂��ł��邽�߁A���ɂT�R�N�ȗ��S�ʋ��ɂ���āA�����̈ێ��|�{��}�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@���̂悤�ȊW�҂̂���݂Ȃ��w�͂ƕ��s���āA�ʓr�ɐi�߂��Ă����K�͑��B��֔����Ɨ��ݒ玮�h��{�݂ɂ�鐬�ʂƂɂ���āA�Ăщ��N�ɔ��鐶�Y�ʂ��ł���悤���҂���Ă���Ƃ���ł���B
�z�^�e�L
�@�O�f�u���Θp�y�����̏����v�ɂ��A
�@�u�����L�͕��Θp�S��ɐ������Ă��邪�A��r�I�Z���ɐ������Ă���C��́A�����p�����ɒB���H�z�Ɏ���C��ƗL�숸�c���o�Ĕ��_�Ɏ���n��ɐ������Ă��邪�A���_�������đ��͋��ƂƂ��Čo�c�̐������̂��̂ł͂Ȃ��B�v
�Ƃ���Ă���B�܂��A�����Q�U�A�V�N����ɂ͟v���Z�A�����i�Q�O�`�Q�R�Z���`���[�g���j�̑�^�̂��̂��̕߂��Ă����Ƃ����B
�@���������̌�́A�J���C�Ȃǂ̎h���Ԃɂ���������A��c���\�R�z�̋���������ō̎悵����������������A���l���͔��X������̂ł���A���̌����Ƃ��čl�����邱�Ƃ́A�p���͐[���ꎿ�D�y�ł��邽�߁A��c�̒������ƁA�q�g�f�ȂNJQ�G�̔�Q�ɂ��ɐB��Q�ł���Ƃ���Ă����B
�@���a�Q�O�N��ɖK�ꂽ�����Ƃ̖����I�ȋ�����Ƃ��āA����܂ł��܂�d�v������Ȃ������C����L�ނ����ڂ���A��C���B�E�͔|�{�B���Ƃ̊g�[�����������悤�ɂȂ����B�������Ă��̃z�^�e�L�̑��B���Ƃ����ڂ���A���͎R�z���Ƌ����g���ƃ^�C�A�b�v���āA�Q�W�N�T���ɂ��Ԃ�p�����B�{�݂T�O�i��P�U�T�������[�g���j��ݒu�����B���̌��ʁA�t�L�̕t�����ǍD�Ȃ��Ƃ��m�F���ꂽ�̂ŁA����ɗ��N����������{���A�R�O�N�ɂ͒t�L��Z�Z�сi�R�V�T�L���O�����j��l�H�̕c���ĕ�������ȂǁA�z�^�e�L����̑����ɓw�߂��̂ł��邪�A����ɂ��Ă����Y�ʂ̑����܂łɂ͒B�����A�����Ԃ�E���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�z�^�e�L�̗{�B���{�i�I�Ɏn�߂�ꂽ�̂́A���ƍ\�����P���Ƃ����{���ꂽ���a�S�P�N�ȍ~�̂��ƂŁA���̔N�U����{�A�l�o�c�̂P�A�����N���Q���A�̕c�~�A�g�y�t�B�����A���t���̕c�{�݂�p���ēV�R�̕c���s�������ʍD���т����߂��̂ŁA�X���ɒ��Ԉ琬���e���l���P�O�����A�N���T�O�O�O���i���a�S�Q�N�x���Ǖ��y���ƌv��E���_�n�搅�Y���Ǖ��y���j�̎�c�邱�Ƃ��ł����B
�@���ꂪ�z�^�e�L���{�B�̂��������ŁA���ƍ\�����P���ƂƑ��܂��Ĕ��_�E���������Ƌ����g���ɂ�鑝�Y�v�悪���Ă��A�n������̂��߂̋��ꑢ�����Ƃ����{���A�Q�G�ł���q�g�f�쏜�̂��߂̏��ΊD�̎U�z�A�܂��A�N����h�����߂̋�����͂ւ̕ߊl��̐ݒu�Ȃǂ����݂�ƂƂ��ɁA�S�T�N�Ɏ�c�P�T���W�O�O�O����������ĐϋɓI�Ɏ��Ƃ𐄐i�����̂ł���B
�@����ɂS�U�N����̑�Q���\�����P���Ƃ̈�Ƃ��āA�z�^�e�L�̕c����ђ��Ԉ琬�{�݂��A���_���ɂS��A�������ɂX��ݒu���ꂽ�B����́A�Y�����̂T�������ς��ɐ����W�x�`�P�O�x�i�ێ��j�̊C���Ɏ{�݂���ꂽ���ƁA�V�����{�Ɉ��i����j���قǂɐ��������i�K�ŔZ���x�Ȃǂ����A�W�����{�`���{�ɂP�Z���`���[�g���قǂɈ�������̂��A���Ԉ琬�{�݁i�P��P�W�O���[�g���j�Ɉڂ��ւ��ďW�A�R�Z���`���[�g�����x�̒t�L�ɂȂ�P�P��������P�Q������Ɋe�n��ɋ������ĕ���������̂ŁA�z�^�e�t�L�̈��苟����}�����̂ł���B
�@���������ϋɓI�ȑ��{�B���Ƃ̎��{�ƁA�p���̔�悭�Ȑ����Ȃǂɂ��D�K�Ȋ��Ɍb�܂�A���ƊJ�n�ȗ����̐��Y�͔���I�ɑ������A�T�P�N�ɂ͂V�Q�T�W�g���̐��Y�ʁA�P�X���V�O�O�O���~�̐��Y�z���グ�A�L�ޑ����Y�z�̂X�U�E�Q�p�[�Z���g���߂�Ƃ����A���_�n�扈�����ɂƂ��čő�̎������ƂȂ����̂ł���B
�@����A�{�B�{�݂̐ݒu�́A�e���Ƌ����g���ɗ^�����Ă����拙�ƌ��̋��������ɔF�߂��Ă��邽�߁A���_�E�����������ł͎{�݂̑����ɑΉ����邽�߁A��拙�ƌ��̊g����}��ȂNJe��̑i�߂�ꂽ�̂ł���B
�@����ɁA�z�^�e�{�B���Ƃ̐L�W�ɂƂ��Ȃ��A�������狭���v�]�ƂȂ��Ă����{�B��Ɨp�˒炪�T�O�N�h�l�n��Ɍ��݂��ꂽ�B����́A�c�E���R�T�Z���`�̂g�^�|�Q�O�{���C���ɑł����݁A�����U�T���[�g���A���T���[�g���̐^���������������đ���ꂽ���ŁA��t���H�A�h�삳���Ȃǂ��܂߂������Ɣ�͂R�O�P�S���~�ł������B����ɂ���āA�{�B�����̐��|�����ւ��A���ޔ����Ȃǂ̍�Ƃ��e�ՂɂȂ�A���`�������Ȃ��n��̍�ƌ����̃A�b�v�ɑ傫�Ȗ������ʂ������ƂƂȂ����B
���Θp�ق��ċ��ƈ琬���c��
�@���a�S�O�N��㔼�Ɏ��{���ꂽ��Q�������ƍ\�����P���Ƃ̂Ȃ��ŁA���Ǝ҂̂���݂Ȃ������Ɠw�͂ɂ���ċ}���ɐL�������z�^�e�L�{�B���Ƃ́A�����ɂ����鋙�Ɛ��Y�̎�̂ƂȂ���������A�������͓��������ł͂Ȃ��A�L�����Θp�̑S��ɂ����Ĕ��W���A���a�T�O�N�̐��Y�z�͎��ɂU�O���~�ɒB���āA�p�����Ƃ̑啔�����߂�Ɏ������̂ł���B
�@�������A���������}�����𐋂����z�^�e���Ƃ́A���S�ōP�v�I�Ȉ琬���W�ƈ����}�邽�߂ɂ́A���ꗘ�p�E�Ǘ��Z�p�E���ʑ�E���ۑS�ȂǁA�L������ɂ킽���Ė��_���������A�W�@�ւ�c�̂��ϋɓI�Ɍ������c���鋤�ʂ̏��݂���K�v�����Ɋ�����A�T�P�N�S���L�u�̔��N�ɂ��u���Θp�ق��ċ��ƈ琬���c��v���g�D���ꂽ�B���Ȃ킿�A�������͂��ߍ����E�X�E�������̊e���ƁA�_�U�x���Ǔ��̎����s�E�ɒB�s�E�L�Y���E���c���ȂǁA���Θp���݂̊e�s�������⋙���g�����̂ق��A�W�s���@�ցE�c�́E�����@�ւ����ׂĕ�܂����g�D�ł���A���̊����̐��ʂ����҂��ꂽ�̂ł������B�Ȃ��A�����ɂ͐X�����g�����̉������ܘY���I�C���ꂽ�B
�z�^�e�{�B(�ʐ^�P)

�z�^�e�L�Ŗ��
�@���a�S�X�N�i�P�X�V�S�j�ɐX�������p�Ŕ��������{�B�z�^�e��ʂւ����Ɠ��l�̒��A�T�P�N���납�畬�Θp���ɂ�����A���Θp�ق��ċ��ƈ琬���c��ł́A�T�Q�N�Q�����ِ��Y������Ȃǂ̎��������@�ւɗ{�B���e�ʒ������Ϗ����A�����ɏ��o�����B
�@���a�T�R�N�V���P�����Θp�Y�̗{�B�z�^�e�ɁA�v�����N�g���������ƌ�����Ő����܂܂�Ă��邱�Ƃ����q���������̎����Ŕ�������A�U���Q�X���ȍ~�ɏo�ׂ��ꂽ�z�^�e�L�̕ԕi�Ɖ�����ی�����ʂ��Ďw�����ꂽ�B
�@���̓Ő��́A�S�j�����b�N�X���̃v�����N�g���Ő��i�S�j�����b�N�X�E�J�e�l�C���E�t���J�����Ɩ��t����ꂽ�j�ŁA�L���v�����N�g����H�ׂ邱�Ƃɂ���ĊL���ɒ~�ς��A�l�������ێ悷��Ǝ葫�����т���������Ȃǂ̂܂ЏǏ���N�������̂ŁA�ŏ����v���Z�x�͂R�O�O�O�`�R�O�A�O�O�O�l���i�}�E�X�E�l���̓}�E�X���j�b�g�̗��̂ŁA�Ő��̒P�ʁA�P�l���ő̏d�Q�O�O�����̂˂��݂��P�T���ԂŎ��S������j�Ƃ���A���Ȃ蕝�͂��邪�킪���ł͐H�i�q���@�ɂ�鋖�e����Ȃ����߁A�č��̒~�ϊ�l�ł���u�S�l���v�����p���āA�̕߂̋֎~��o�ג�~�̊�Ƃ��Ă����B
�@���q�����������s���Ă���u�͔|���Ɛ������f���Ɓv�Ƃ��āA�z�^�e�L�̓Ő��������s�����Ƃ���A�L�Y�Y�̊L����T���ȍ~���ʂ̓Ő������o����Ă������A�U���Q�V���ɂ͍ō��P�R�E�W�l���A�����B�i����j�i������A�E���j����͂X�V�l���Ƃ��������Z�x�̓Ő������o���ꂽ�B���̂��߁A���q���ɂ����Ęp�������̌��̂ɂ��čĎ������s�������ʁA�ނ��g�����ŁA�L�Y�Y�P�U�E�X�l���A�������X�E�S�X�l���A�X�V�E�W�l���A���c�U�E�T�l���Ƃ������p�~�ϒl������錋�ʂ��o�����߁A�����ɏq�ׂ��悤�Ȏw�����Ȃ��ꂽ�̂ł���B
�@����ɓ��ً͋}���c���J�Â��A���Θp���݂̖L�Y���ł͖����A�܂��A�����E�������E�X�E�����̂S�����ł͂R�������ɁA�Ő��S�l���ȉ��ɂȂ�܂Ōp�����Ē�_�ϑ����s�����ƂƂ����̂ł���B
�@�������āA�}���Ȕ��W�𐋂��A���a�T�Q�N�x�ɂ����Đ��Y�ʁE���Y�z�Ƃ��Ɏ�ʂ̍����߂�Ɏ������{�B�z�^�e���ƂɂƂ��ẮA�܂��ɐV�̂ւ��ꂫ�Ƃ����������ƂȂ�A�������������т₩�����ƂƂȂ����B
�@���̂��ߒ��c��ɂ����Ă��A�T�R�N�Ɂu�z�^�e�c��v���A����ɂT�S�N�ɂ́u�z�^�e�����ʈψ���v��ݒu���A���Y�Ғc�̂ƍs�����Ȃǂ̈ӌ������}�邱�ƂƂ����B�����ċ����̕����ҏ����̊ɘa�╉���������̓����A���q�⋋�Ȃǂ̎{����u���A�o�c�̈��艻�ɓw�߂��̂ł���B
�@���������̌�������s���ɂ��ւ����L�͑����������̂ŁA�����͐��Y�̎���K�����s���A�Ő��l�ɉ����ğv���A�E�������{�C�����H�A�L���̂R�{���Ăŏo�ב̐���g�݁A�����ɂ���ēŐ��l�������������ꍇ�Ɍ��葀�Ƃ��邱�ƂƂ����B���̂��߁A�T�Q�A�T�R�N�ɂ����Ă͂P���U�O�O�O�g���ȏ�̐��Y�ł��������̂��A�T�S�N�ɂ͂S�U�O�O�g���A�T�T�N�ɂ͂Q�Q�O�O�g���Ƌɓx�ɗ������B�����������Ƃ��狙���́A���C����J�Â��ė{�B�����i�ۃJ�S��������������a���j�Ȃǂ��������A����o�c�Ɍ����Č����̓w�͂𑱂��Ă���B
�@���̌��ʁA���X�ɉ̒����������͂��߁A���_�E�����������ɂ����Ă��A����܂ňȏ�ɗ{�B�Z�p��Ǘ��ɗ��ӂ���ƂƂ��ɁA�{�B�z�^�e�����̋K����O�ꂵ�A�L�ł��������鎞�����܂߂����N�o�ב̐��̊m����ڎw���Ă���B
�R���u
�@���Θp�ɂ�����C���ނ̎�̂��Ȃ��R���u�́A���Θp�����ł͂Ȃ��S���e���̉��݂ɂ����ĎY�o���A���̗��j�͌Â��A���łɐ���V�P�T�N�i��T���N�j�Ɂu���z�������v�Ƌ��L�ɂ���A�{���̏d�v�ȊC�Y���ł��������B
�@���ÁA�R���u���̂�̂̓A�C�k�����������̐H���Ƃ��邽�߂̂��̂����ł��������A��i�N�ԁi�P�V�O�S�`�P�V�P�O�j�ɓ��������̋�����������̂�A���ی��N�i�P�V�S�P�j�ɃR���u�P�O�O���҂�U���Ƃ��ėA�o����Ƃ�����������i�u���O�N������o�v�j�A�ƋL����Ă���̂����i�Ƃ��Ă̂͂��߂Ǝv����B���_�n���̉��݂ɂ����Ă��R���u�̎Y�o�͑����A�����U�N�i�P�W�T�X�j�ɗ����Ő܃R���u���o�ׂ��Ă���L�^������A���̂ق���X�̕����ɒf�ГI�ł͂��邪���̐��Y�ʂ��L����Ă��邱�Ƃ́A�����ȑO�̋��Ƃ̐߂ŋL�����Ƃ���ł���B
�@���̂悤�ɃR���u�͘p���̐�C���S��ɂ킽���Đ��炵�A���̐��Y�ʂ͏��a�P�T�N�i�P�X�S�O�j�ɂR�W���тł��������̂��A�R�P�N�ɂ͂U�S���тɂ܂ő������A�������ɂƂ��Ċ��҂ł��鎑���ł���A�ˑ��x�̍������̂ł������B
�@���������āA��㋙�Ǝ���������Ɍ͊����Đ�C���B�̏d�v�����N���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ�ƁA���_�E�����̉��݂ɂ����Ă��A���a�Q�U�N�ȗ��N���Г��ɂ���āA�R���u�ʒz�݂̂��߂̎��R�Γ�����R���N���[�g�u���b�N�̓������ƂȂǂ��ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�̂ł���B
�R���u�̋��l�i�ʐ^�P�j

�@���̌��ʁA���a�R�Q�N�E�R�T�N�E�R�W�N�ȂNj��ނ̐��Y�����Ȃ������N�́A���܂��܃R���u���R�N�����̖L���̔N�ɂ�����A���̔N�̐��Y���̂Q�O�p�[�Z���g���O�̐��Y���グ�A���ƌo�ς̈���ɑ傫�Ȗ������ʂ������̂ł���B
�@�������A�S�O�N�ȍ~�̐��Y�͎�X�̗v���ɂ���ĕK�������R�N�����̖L���ɂ͂Ȃ炸�A�������ł͂��邪�����X���������Ă�����̂́A�ˑR�Ƃ��đ����Y�z�̂Q�O�p�[�Z���g�ȏ���m�ۂ��A���n���̐��Y���Ƃ��Ă͏d�v�Ȉʒu���߂Ă���B
�X�E�����ԊC�ʋ��E�̋���
�@���a�P�X�N�i�P�X�S�S�j�O�l�R���u�̎�ɂ��Ďx�Ⴊ����Ƃ��āA�����E�X���Ɖ�̂Q�ҊԂŎ��̂悤�ȊC�ʋ��E�ɂ��Ă̋��菑�����킳�ꂽ�B
�@�X�E���������Ɖ�E���b�苦�菑
�@�X�E���������Ɖ�C�ʋ��E�n�A�������n�㋫�E����_�g�V��k�j�V�O�ܓx���c�X�������ȃe���E�g�׃X�n���j���a�ܔN�\�ꌎ�Z���_�яȓo�^�σi�����Ζ����쒆�S�����ȃe�n�㋫�E�g�׃X�j�������Ȑ��m�ό`�y�������m�ʒu�փw�����׃i���_�j���e���E����j�x�^�����W���z�̎�����O�j�x�გ���V�^�������W�Ҍ���j����q���E�y�����_�j�փV�b��[�u�g�V�e���m�ʃ�����V���Ə�~����������V�^���B
�@����^
�@�Ζ�����R���N���[�g���������n�_�����W�g�V�K��p�O�ܓx�����X���k���k�m�����ȃe���E�g�V�C�ʃ��уL�Ίݏ��P�R�i���L��R�j�m����j���������V�����ȃe������g�X�B
�@�A�V���z�̎�j�ۃV�e�n���j��ǕN���m�H�k���j�X�m���v�j�����n�p�c�x�L�R�g�j�e���j���E���m���냊�j������E�O�ԊC�ʋ�惒���������X���R�g�A���^���ꍇ�g嫃��̈Ӄi���U�������~����������g�V�וۋ������_���ȃe�P���X�����m�g�X�B
�@�E�m�ʃ��b�苦��X�B
�@���a�\��N�����\����
�@�������Ɖ�@��@�{���G�g
�@�X���Ɖ�@��@���q�����Y
�@�i�ق��ɗ���l�Ƃ��āA�����E����E�厖�̋L�ڂ����邪�A�o�����ɏȗ������B�j
�{�^���G�r
�@���Θp���Y�́u�{�^���G�r�v�́A�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�ɐX���̎R���̐��D���A�������̉����Œn�����Ԃ�p���Ă����߂����̂��ŏ��Ƃ����Ă���B�������̋���������ɂȂ���Ė����S�S�N�P�O���ɃG�r�������݂��Ƃ���A�\�z������鐬�т��グ�����߁A���X�ɂ���ɒ��Ƃ�����̂������Ă������B
�@�G�r���͂P�O�����痂�N�R���܂Ő��D�ŏo�����A�����Q�A�R���̏��őŐ��ԁi��J������j���������@�ł���A�P�ǂ̏�g���͂S�A�T�l��v�������A�����Ԃ̕������Ȃǂ͗������ł��b�܂�Ă����̂ŁA�₪�Đ�i�n�����̂��A�{�^���G�r�͗������Y�̊ς�悷��悤�ɂȂ����B
�@��g���͕����_�������Ƃ��Č����Ƃɐ��Z������@���Ƃ��A���l���z���珔�o����T���������̂�z������̂ł��邪�A�D��́u�D���v�Ə̂��ċ��Ԃ⋙��̎g�p�㏞�ɂQ�l�������A�c�����g���ɔz������Ƃ������̂ł������B��g���́u��q�v�Ə̂��A�e���H�Ƃ����Q���Ď���瓭���ɏo�����A���̉҂����͖��������Ō��V�A�W�O�~�A�吳�N�Ԃł͂Q�O�O�~�O��A���a�P�Q�N����Ŏ��P�O�O�~���炢�ɂȂ�A���̋����Ԃ͑����̌i�C�����C�ɂ��ӂ�A����������H�X���傢�ɂɂ���������̂ł���Ƃ����B
�@�吳�P�Q�A�R�N����ɂ͋T�c�E�����S��������D�������ē��҂�������̂��R�O�O�]���ƂȂ�A�����������n�Ƃ���D�����P�O�O�]�ǂɂ��B����ȂǁA���������������Ƃ��������B�܂��A�p���ł̔����@�D�ɂ�鑀�Ƃ��֎~����Ă����ɂ�������炸�A���c���ʂ��痎�������ɂ��Ĕ����@�D�ŃG�r��������Ƃ�������̂��o��悤�ɂȂ������߁A�n���x���ł͂��т��ъĎ��D���o�������Čx�����A���߂ɓw�߁A�Ƃ��ɂ͊C��ŒǐՂ��邱�Ƃ��������Ȃ������Ƃ����B
�@���a�P�O�N�i�P�X�R�T�j�ɂ̓G�r���������ƂƂȂ�A�]���̏o���D�W�O�ǂ��܂肪�U�O�ǂɐ�������A�Ǔ��̋��������s�����Ɍ��肳�ꂽ�B�������A�אڂ��钬�ł��G�r�����̗v�]�������������߁A�P�R�N�X���ɂ͊W���Ƒg���̋��c�ɂ���āA����Ƃ̖��ڂɂ��X���P�T�ǁA���_���V�ǂ����F���ꂽ�B
�@�{�^���G�r�͂���߂Đ����������A�������͂��ߖ{�B�e�s�s����łȂ��A�D�y�⓹����v�s�s�֏o�ׂ���Ă������A���a�P�P�N�X���ɓV�c�É������R���ʑ剉�K�䓝�ĂȂ�тɒn���s�K�̂��ߗ������ꂽ����ɂ́A�X���Q�V������P�O���V���܂ł̂����̂V���ԁA�P�P�T�O�����䗿�i�Ƃ��Č��シ��Ƃ������h�ɗ������̂ł���B
�@�G�r���́A�n���Ǔ��ł͗������A�_�U�Ǔ��ł͖L�Y���̐�p���Ƃ̊ς����������A�P�T�N�W���ɉ��݂P�Q�̋��������c�������ʁA���R����ƂɕύX�����B�����Đ��D�W�T�ǂ��Q�Q�O�ǂɑ������A���D�T�Ljȏ�̈����D�Ƃ��Ĕ����@�D���g�p�ł��邱�Ƃɋ��肳�ꂽ�B
�@�������A����܂ŋ����ƂƂ��ċ��D�𐧌����Ă܂ŕی삵�Ă������̂��A���̂悤�ȋ�����������Ƃɂ���Č��ǂ͗��l�̌����ƂȂ�A���R�̂悤�Ɏ������͊�����Ƃ������}�����̂ł���B
�@���̂悤�Ȏ�J�ԋ��Ƃɂ�鎑���̗��l�́A���Θp����ł͂Ȃ��S�����݂ɋy���߁A�����ł͂Q�S�N�ɏ���J�ԋ��ƑS�p�̕��j���߁A�Q�U�N�܂łɐ������s�����̂ł���B
�����{�^���G�r�ƃC���V���i�ʐ^�P�j

�@�G�r���Ɉˑ�����Ƃ��낪�傫�������������̋����͎������Ƃ��Ē�ɒ���d�ˁA�悤�₭�S�ʓI�Ȍ��D�͕ۗ��ƂȂ��ĂQ�U�N�ɂR�O�ǂ������ꂽ���A���̌�Q�V�N�ɂS�ǁA�Q�W�N�ɂT�ǂ����D����A�R�P�N�ɂ͑S�D�̋����ł���ƂȂ����̂ł���B
�@�Y�z�͔N�ɂ���đ����͂��邪�A�吳�V�N�ɂR�Q�O�сA�吳�����R�V���сA���a�P�P�N�V���сi�W���S�O�O�O�~�j�A���P�Q�N�U���T�O�O�O�сi�X���P�O�O�O�~�j�Ȃǂ̋L�^������B
�@���ł���ƂȂ��Ă�����G�r���ɑ��闎�������̎����͋����A���̂��ߖ�������҂����o���A�u�C�̃M�����O�v�Ƃ��u�M�����O�����閧���D�c�v�ȂǂƐV���_�l�ɂȂ邱�Ƃ���������A�R�Q�N�܂ł͂��̂悤�ȏ�Ԃ��������̂ł���B
�@�܂����̓����A�����ɂ�鋙�@�����݂����̂������Ă悢���т��グ���悤�ł��邪�A����ɐ���ɂȂ��Ă����X�P�g�E�^���̋����Əd�Ȃ邽�߁A���ƂƂ���ɂ͎���Ȃ������B
�m���E���J���̗{�B
�@�풆����ʂ��Ēg���n��V�����̌����ɂƂ��Ȃ��A���Θp���Ƃ͐�C���{�B�ւƓ]�����Ă������̂ł��邪�A�����ɂ��������m���E���J�����̗{�B���Ƃ́A���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�ɏ��߂Ē��肵���̂ł���B
�@�������A��������ɒ��Ƃ�����̂͋ɂ߂ď��Ȃ��A���͈ϑ����ƂƂ��ĂR�W�N����m���E���J���̗{�B�������J�n�����B����͓���ƒ���������Ď�̌o�c�̂Ɏ����������ϑ��������̂ł������B���_�����Ƌ����g���ɂ����Ă��A�N�w���i�n�ł���L��ɔh�����āA�{�B���H�Z�p�̏K���ɂ����点���̂ł������B���̌��ʁA�ǍD�Ȑ��т����߂���̂��o�Ă���A����ɒ��Ƃ�����̂������悤�ɂȂ��Ė{�i�����A�R�W�N�ɕ������P�O������A�����ĂP�T��A�Q�U��A�Q�S��ƘA�N�V�K�{�݂݂��đ��Y�̐����z����Ă������̂ł���B
�@����A�R�W�N�Ƀm�����H���ꎮ�����_�E�����������ɓ�������Đ��Y�ɑΉ����A����ɁA�S�P�N�ɂ͔���Ǘ���Q�������Ȃǒ��X��������Ă������B
�@���������m���E���J���{�B��Ɖ��̏���ɉ����āA�S�P�N�x����J�n���ꂽ�\�����Ƃ̒��S���{�B���Ƃɂ������Ƃ��납��A���_�E�����������ł͂S�R�N�x���牫���{�B�ۑS�{�ݎ��Ƃ���ы��ꑢ�����ǎ��Ƃ����{�����B����ɂ����̎��ƂɊ֘A���āA�S�S�N�ɔ��_�����������Ǝ�̂ƂȂ��āu�̂�E�����������{�݁v�P����ݒu�����ق��A���N�ɂ́u�̂��c�|�{�{�݁v�P���A�u�����{�݁v�P����ݒu����ȂǁA���c�̊m�ۂƍ͔|���̉����A�������H�ɂ��i���̌���Ɛ��i�̋ψꉻ��}�����̂Ŏ��Ƃ͏����ɐ��ڂ����B�������ĂS�T�N�x�ɂ͊��m���T�S�����i�P�O�T�Q���~�j�A���J���Q�S�g���i�V�U�O���~�j�̐��Y���グ���B����ɗ{�B�Z�p����H�Z�p�̕��y��}�邽�߁A�Z�p�E����z�u���Č������d�˂����ʁA���Y�R�����̐��Y���グ��܂łɂȂ�A�{�B���Ƃ̒��S�Ƃ��Ċ��҂��ꂽ�̂ł���B
�@���������H�����̕s����ƁA�V�K���Ƃł��邽�ߎ�X�̏�Q�������A����ɉ����ĂS�V�N�P���̌������쓌���ɂ��債���ɂ���āA�e�o�c�͉̂�œI�ȑŌ����A�ċN�s�\�ȏ�ԂɂȂ����̂ł���B���̂��߁A�悤�₭�O���ɏ�肾�����m���E���J���{�B���Ƃ́A�����ɂ����čs���l�܂�A����ɑ����ė{�B�z�^�e�w�̓]�������コ�ꂽ���Ƃ���A�s�U�̂����ɏI�~����ł��ʂƂȂ����B
���J�T�M
�@���a�Q�W�N�i�P�X�T�R�j�S���ɒ��͗V�y��������ی싦�͉�̋��͂ɂ��A�ԑ����烏�J�T�M���Q���T�O�O�O�������ړ����ĂӉ����������Ƃ���A���ʂ̋��l���݂邱�Ƃ��ł����B����ɗ͂Ĉ��������Q�X�A�R�O�N�ƘA�����ĕ������A�܂��A�R�P�N����R�R�N�ɂ����Ēn���̗��ɂ��Ӊ����������݂�ꂽ���A���҂������ʂ͓����Ȃ������B
�J���t�g�}�X
�@���a�Q�U�N�i���Ǝ�́E���O�j�ɂP�O�O�����A�Q�V�N�ɂX�O�������Ӊ��������A�Q�W�N�ɂ͗V�y����łQ�O�O�O���A���݂Ő���Q�O�O�O�������l�����Ƃ����L�^�����邪�A���̌�͌p���������f�̏�Ԃł���B
�N���}�G�r
�@���a�S�P�N�i�P�X�U�U�j�ɔ��_�������ƒ����^�C�A�b�v���A�R�����H�䂩��N���}�G�r�̗c�̂T�O�������ړ��̂����A���_�`�����ɕ������Ă��̐���Ɋ��҂����B���̌�A���Y������A�n���x�����Y�ۂȂǂ̎x���ĂQ��ɂ킽��̕ߎ������s�����̂ł��邪�A�P�����̕߂ł������s�ɏI������B
�A���r
�@���a�R�T�A�U�N�x�ƂS�Q�N�x�ɂ����āA���_�n�搅�Y���Ǖ��y�����A���r�t�L���ڐA���ċ��ꑢ����}�����̂ł��邪�A�Ȍ㒆�f���đ傫�Ȑ��ʂ����҂ł���ɂ͎���Ȃ������B
�A��
�@�V�y����ɂ�����A���̑��B��ڎw���A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�Ɏ鑾��i���s�S�j����A�����P�O�O�������ړ������̂��͂��߁A�Q�V�N�R�O�O�����A�Q�W�N�T�O�O�����i�n���̗��P�O�O�����j�A�Q�X�N�V�T�O�����i���R�O�O�����j�ȂǑ������ŕ������āA������x�̐��ʂ��グ���̂ł��邪���̌�͂��炭���f�ƂȂ��Ă����B
�@�������A�͐���̕ی�ƗV���҂ɑ��鎑�����B�̂��߁A�S�W�N�ɂ͍ĂїV�y������A���̏���ɂ��悤�Ƃ������Ƃ��v�悳�ꂽ�B�����āA���_�������̏��g�����ɂȂ��Ă���ނ蓯�D�҂̑g�D�ł���u�V�y���숼���B���͉�v�Ɉϑ����A���i����ړ������t�A���T��������������̂��͂��߁A�Ȍ���A�N�������Ă��邪�A���݂̂Ƃ���ꕔ�̒ނ舤�D�҂��y���܂�����x�ɂ������A�K�������ǍD�Ȑ��т�������Ɏ����Ă��Ȃ��̂�����ł���B
���Y����
�@���Θp���ɂ����鐅�Y�����̎�Ȃ��̂Ƃ��ẮA�G�r�E�^�R�E�C�J�E�J�j�̗ނ�����B���_�n��ɂ����Ă͂����̂����A�C���V�̕s���ɑ����ď��a�P�U�N���납��Q�W�N�ɂ����ăC�J���l�������p�������A�Q�O�N�ɂW�T���R�O�O�O�сi��R�Q�O�O�g���j�ƁA���̔N�̋��l���̎�ʂ��߂�ȂǖL���̔N���������̂ł���
���A�Q�W�N�ȍ~�͌��������ǂ�͂��߁A���N�̂悤�ȋ��l�͊��҂ł��Ȃ��Ȃ�A�킸���ɂ��̖ʉe���c�������ƂȂ����B
�@�^�R���ɂ��Ă͋��l�����N�ɂ���ĕs���ŁA���܂葽���͂Ȃ����A�R�Q�N�ȍ~�ł͂R�O�g������T�O�g�����O�̐��g���ƂȂ��Ă���B
�@���Θp�̓��Y���Ƃ��Ė������������̃{�^���G�r�ɂ��ẮA��ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A����J�ԋ��Ƃ̑S�p�Ȍ�͒��f�̊ς�����A�N�X�킸���ɐ��g���̐��g���ɂƂǂ܂��Ă������̂́A�S�O�N��ɓ����Ă��炠����x�̒����������A���悻�R�O�g����O�シ�鋙�l���������悤�ɂȂ����B
�@�܂��A���Ȃ�Â����痎���̉��݂ō̕߂���Ă����Ƃ����i�}�R�́A���l���Ƃ��Ă͂��܂葽���͂Ȃ��������A���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�ɒ��茧�o�g�̐���d�삪�������ɋ��Z���������肱���̐������n�߂Ă��琷��ɂȂ�A�����P�g���قǂ̕ߊl���������Ƃ����B�������A�P�Q�N�V���ɓ����푈���ڂ������Ă���́A�����ւ̗A�o���r�₵�����߁A���̃i�}�R�����ԋ��Ƃ͒��f�����Ƃ����o�܂��������B���{�i�I�ł͂Ȃ��ɂ��Ă����X�ɋ��l���������A�Q�W�N�̂S�V�g���]�A�Q�X�N�̂U�T�g���Ƃ������g�����������B
�G��
�@�ȏ�̂悤�Ȏ�v���l���̂ق��ɁA���_����ї����n�扈�݂ɂ͎�X�̋��ނ������I�ɉ�V���Ă���B���l�ʂ������Ȃ�������ȋ��ƂƂ��āA�Y�����ł���T������U���ɂ����ăV���E�I���h���Ԃ�����Ԃɂ���ĕߊl����A�������Ƃ��ē����s�s���ɏo�ׂ���Ă���B�܂��A�U�A�V���ɂ̓C�T�_�̋��l���݂��A���N�͔엿�Ƃ��ė��p����Ă������A�������ʂŃn�}�`�̗{�B������ɂȂ�Ƃ��̎����Ƃ��ďo�ׂ����悤�ɂȂ�A���i���ǍD�Ȃ��ߋ��ƌo�ςɏ����������炵�Ă���B����ɂP�P������P�Q���ɂ����ĎY���̂��߉��݂Ɋ���Ă���n�^�n�^���s��ɏo�ׂ���Ă���B���̂ق��A�N�Ԃ�ʂ��ă`�J�̋����݂��A���N�܂��͉��H�p�Ƃ��ďo�ׂ���Ă��邪�A��������ʓI�ɂ͏��Ȃ��B
���C���̑��B
�@���C���t���̃A�p�[�g�Ƃ����鋛�ʐݒu���Ƃ́A���a�R�P�N�i�P�X�T�U�j�ɔ��_�����Ƌ����g�����R�P�O�𓊓������̂��͂��߂Ƃ��A�Ȍ�͂S�S�N�x�܂Ōp�����đ�����Q���𓊓������B�܂��������Ƌ����g���ł��R�Q�N�x�ɂQ�T�T�𓊓������サ�炭���f���Ă������A�S�P�N�x����ĊJ�̂����S�T�N�x�܂łɖ�R�R�O�O�𓊓����A���C�����̔ɐB�ɑ傫�Ȍ��ʂ��グ���̂ł���B
�C���ۂ̓���
�@��Ă鋙�Ƃւ̔���I�ȐU����}�邽�߁A���͏��a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�ɗ{�B�Ǘ��w���D�������B���̎w���D�́A�m���E���J���E�R�\�u�E�z�^�e�Ȃǂ̗{�B���Ƃ̒ǐՒ�����e�X�g�{�B�Ȃǂ��s�����߂̂��̂ŁA�Q�W�O���~�������Č����̂����S�V�N�R���Q�W���Ɋ�n�ƂȂ闎���`�ɓ��`���A�S���Q�P�����_�`�Ői�������s���A�k�������͂�����u�C���ہv�Ɩ��������B
�@�D�̂͂Q�E�S�g���łe�q�o���A���͂̓f�B�[�[���G���W���ł��邪���ʂ̃X�N�����[���i�ł͂Ȃ��A�D���ɓ��������n�C�h���W�F�b�g�Ő��i���鏬���̂������̂ł������B
�@���͂��̊C���ۂ𗎕����Ƌ����g���ɊǗ��ϑ��̂������Y���Ǖ��y���⋙���ȂǂƋ��p���A�����@�̂ق��e��v��ނȂǂ����ĉ��݈�т̒����𑱂����̂ł��邪�A�T�T�N�R���������Ĕp�D�Ƃ����B
�@��V�߁@�T�P�̂Ӊ����B����
�����O�̃T�P��
�@�T�P�͌Â�����S���̉��݂ŕߊl����Ă����̂ł��邪�A�����Ǔ��ɂ������̓I�ȋL�^�Ƃ��ẮA�����Q�N�i�P�W�O�T�j�́u���O���ڈΒn�I�s�v�i�R�蔼�����j�ɁA
�@���[���b�v�ΉƏ\��A����L�A�����o���B������o�鋛�@�攽���݁A�@�Ȃ苛�Ə����B�����@�Ȃ�T�P���̋L�^������A�������N�i�P�W�T�S�j��ؒ��k���́u�ڈΕ��Y���v�ɂ́A
�@���ڈΒn���E���b�v��֍����N�o���A���E���b�v���g�e���Y�i���B����w�H���m���I�������o�J���m���m�{��������X�P�g�]�t�A��X�P��w�������n�������������g�]
�ƋL����Ă���A�����֒�������ɂ��Ă��V�y����̃T�P�͂��łɐ��ɒm���Ă����悤�ł���B
�@�܂����̔N�A�����N�V�i�C�ΔԂ̐����E�q���V���A�T�P�̖n�G��z�K�_�Ђɕ�[���đ務�F����s���A���݃T�P���ւ̔M�ӂ������Ă���A�C�Y���Ƃ��Ă����Ȃ萷��ł������悤�ł���B����ɁA�����S�N�̏��Y���l�Y���u���ڈΞH���v�̈�߂ɁA
�@�Βn�ɂ͑��Ԃɍ�������ĉ�Ɏ��s��B���O�����͌����A��Ԃ͉����A�O�Ԃ͉����ƌܔԈʂ܂ōb���ĖJ�����o����B
�ƃT�P�̋��l����̈�[�Ƃ�����������L�q������A�܂��Ǔ��e�n�̉��݂ŃT�P���̂��������Ƃ́A�����U�N�́u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�Ȃǂɂ��Љ��Ă���B
�@���������̎���̃T�P���́A����͂��ꂽ���̂̑��B�ی�̑�͂قƂ�ǂƂ��Ă��Ȃ������B����́A�������������������̂ɑ��ċ��Ƃ����Ȃ��A�܂��A���@���c�t�ŁA�T�P��߂�s�����Ƃ������ƂȂǂ͑S���l�����Ȃ��������߂Ǝv���邪�A���N�J��Ԃ����Y���O�̐e����ߊl���邱�Ƃɂ���āA�����ɂȂ��Ă���͎���ɔ����̒����������͂��߁A���̂܂܂ɕ��u����₪�č��₷�鋰�ꂳ���łĂ����̂ł���B
����ƊJ��������ƃT�P
�@����������J�������J��g���َx���ł́A���y��l�ɃT�P�̋��l���ē����ēV�R�Ӊ��̕ی�����サ���̂ł��邪�A�Z���͗e�Ղɏ]�����ƂȂ��A�ˑR�Ƃ��ė��l��������ꂽ�̂ł������B
�@���̂��ߓ��x���ł͖����P�R�N�i�P�W�W�O�j�X���A����ƊJ��������ɃT�P�V�R���ɐB�̎��Ƃ��Ϗ������B���������������ł́A���̎��Ƃ͂����ꑺ�̗��v�ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A���ɍ��ƓI�Ȃ��̂ł�����A����ƊJ��N�Ƃ̎�|�ɉ������̂ł���Ƃ��āA�J���ڏZ�l�Q�R���������Ă��̎��Ƃ��s�����ƂƂ����B�����Ă��̎��Ƃ́A�z�㍑�O�ʐ�ɂ�����V�R�Ӊ��̕��@�ɂȂ炢�A����ɗv�����̌o��͎����ꂪ���S���邱�ƂƂ��A�P�V�N�܂ł̂T�N�Ԃ��������Ԃƒ�߂Ē��肵���̂ł���B
�@�Ȃ��A����ƕ��s���Ĕ��ٌ��͂P�U�N�R���ɕz�B���o���A�V�y����̉͌��C�ʂ̉��֎O�Z�Z�ԁA���܁Z�Z�ԓ��ɂ����Ă͌��ԋ��Ƃ�S�ʓI�ɋ֎~����ƂƂ��ɁA���N�P�O������P�Q���܂łƂR������U���܂ł́A�����ԋ��Ƃ��֎~����Ȃǂ̕ی�[�u���u���Ă����B
�@���̌��ʗV�y����ɂ�����T�P�̕ߊl���́A�P�R�N�̂P�U�U�S���ɑ��A�P�U�N�ɂ͂W�T�P�Q���ƂT�{�ȏ�̍D���т��グ�邱�Ƃ��ł����B
�����P�R�N�ی�ȍ~�T�P���l��
| �N�@�� | �����P�R | �P�S | �P�T | �P�U | �P�V | �P�W | �P�X | �Q�O |
| ���l�� | �� �P�C�U�U�S |
�P�C�S�R�V | �U�C�S�O�S | �W�C�T�P�Q | �R�C�R�P�O | �R�C�X�U�V | �R�C�W�W�X | �P�O�C�Q�V�R |
�i����_�ꉈ�v�j���j
��������̐ݒu�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���݂ɂ��V�R��玖�Ƃ̎������Ԃ��I�����閾���P�W�N�A����܂ł̂悤�ɊJ���ڏZ�l�����Ɍ��炸�A�L���������c�̂����u��������ݒu�T���v���߁A���ٌ��߂ɑ��u��������ݒu��v���o���ĂP�O���ɋ����A�L�u�̋����ɂ���Ď��Ƃ��p�����邱�ƂƂ����B
�@�����̏�m��j���Ƃ��Đ\���W���ނ����Ɍf���邪�A���̓V�R�Ӊ����Ƃ́A���̌�R�O���N�ɂ킽���đ������D���т��グ���̂ł���B
�@�Ȃ��u�ݒu�K���v�ɂ��ẮA��������c�ǐ�ɂ��Ă����悻���l�Ȃ��̂ł������B
�@��������ݒu��
�@�R�z�S���_���V�y�V�y���쉗�����\�O�N�������\���N���܃P�N�Ԉ����������ꊯ�ݑ��������\���N�I�������������e�n���N�����������c�V�㓯�쉗�e����ݒu�v�x���i�T�����Y�֘A�����ȃe�����
�@������
�@�i�c�@��
�@���Ǝ���{������l
�@���J�@�v�O�Y
�@�{������l
�@�Óc�@�m��
�@�R�c�@�P�g
�@��@�d�M
�@���ٌ��߁@���C��a
�掵�l�Z��
�@�O���V�ʊ�o�j����m��i�B���
�@�R�z�S���_���O�ꃖ��
�@�˒��@�O��v���Y�㗝
�@�M���@�g��r���q
����ܘZ�ꍆ
�@��V��͌�
�@���ٌ��߁@���C�@��
�@��������ݒu�T��
���@���ʗV�y����j�ݒu�V�^����������m��Ӄn�����Y���m�ɐB���}���V�����m���v���d�����m�g�X�̃j�Y�쎚�r���j���������������������E�������ȃe��������g�胀
�@���@�����ʃm�[�u�n���_���m���S�g�X
�@��O�@���ꃒ���N�m�����j���e�o���Z���g�X���҃n�������m�i���j�˃������㋙�Ǝ���l�����c�m�㐥�����ۃX�������������^�����m�n�����l���m�܊������i�A�V���Ń��������^����j���J���T���m���������������p�g�V�e���o���m�g�X
�@��l�@�O���m���������^�����m�w�n�o���ӎD���t�^�X�����m�g�X
�@��܁@����n�������V�e�����撆�j�ؗ��Z�V�����V�e����Ԗ��j�ؗ��Z�V�V���m�~���ߊl�X�����m�g�X
�@��Z�@����ݒu�m���߃n���N�\���\�������\��\�ܓ����g�X
�@�掵�@������`�����C�ʒ������E�֕S�E�Ԉ������ܕS�Ԉȓ��j���e����������ߒ��n���ԍ��Ԉ��ԃ������X�������X
�@�攪�@����ݒu���n�Y��ٗv�m�ꏊ�j�Ԓ����z�u�V�����Ԏ�����n�ܘ_�샍�������Z�V���W�Q�Җ������R�g���\�h�X�����m�g�X
�@�A����l�n���X�j�����m��Ŏ�l�m�ΑӋy�q�Y��m�@���j�A�e�n�Ď@�X�w�V
�@���@�����z���m�㋛?�m�C���j�V���X���}�e�n�������Ӄ��׃V�ی샒���t�w�V
�@��\�@�������㒆�n�����݃j���Ӄ��׃V���j�m�O�n�m���ȃe���l�X���R�g�����X���߃q���ԃg嫃��钆�n�s����˃e�����\��N�\�ꌎ�J��g�j�������ɐB�ی�m�׃��䔭�s������O�\�����V�m��Ӄj���ᔽ�҃i�J�����R�g���Ď��X���R�g�A���n���V�}���c�v���j�e�������ߊl�X�����m���]�t
�@��\��@�掵���\���j���V�^���K�ƃZ�V�҃n�N�ԗV�y����y�Y��j�����X���x��j���e���������l�X���������X�������O�~�������J���X���~�������J���T�����������o�X���m�g�X
�@��\��@�Ō쒆��\���y�q�ߊl�m���j�ۃV�������B���V�^���҃n�������Y��j�t�e�����y�q�͖n�����g�X���V�e�����N�n�ܘ_���m���N�����O���N�ԊY��j���e�o���X���R�g�����X���ĔƃV�^�����m�n�V�j���t���j�����g�V�e���~�������J���X�\�~�������J���T�����������o�X���m�g�X
�@��\�O�@����ݒu�\���o�c���n�����ꓯ�o�e���\�����j�͖��V�ʃV�e�Y����j�e�ߊl�Z�V�V���n���ň��������J��j���^�X�����m�g�X
���]�A���g�L�n���уV�u�L�e�������c�m�㑺���m����j�x�p�X�����m�g�X
�@��\�l�@�������m�i���ڍ撲���A�����j�V���S�����w�͏o�����m�g�X
�@�܂��A������ɂ����Ă��V�y����̎��т��݂āA�������ޒ��p�J����E��唐�؊����E����R�ˋv�O�Y�炪�������\���āu������玎���v�ٌ��߂Ɋ肢�o�āA�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�Q���ɋ����B����ɁA�����E�R�z�̌S�E�𗬂���c�ǐ�ɂ����Ă��A���������c���č�������ݒu����o���A�P�X�N�P�������Ď��Ƃ����{�����B
�@�������A��c�ǐ�̓V�R�Ӊ��͐��т����܂�ǂ��Ȃ��������߁A�Q�R�N�̌p���o�肪�p�����ꂽ�Ƃ����A������ɂ��Ă͌p���o�肳�ꂽ���ǂ����A���̌�̋L�^���Ȃ��s���ł���B������ɂ��Ă����̌�̌o�߂���݂āA���͐�Ƃ��T���N�Ԃ����Œ��f���ꂽ���̂Ǝv����B
�V�y��������אB�g��
�@�����R�S�N�i�P�X�O�P�j�ɂ͂���Ɏ����̈ێ������}�邽�߁A����܂ł̓V�R�Ӊ��ɉ����Đl�H�Ӊ����K�v�ł���Ƃ����L�u�ꓯ�́A�������W���āu�V�y��������אB�g���v��g�D���A�V�R�E�l�H�̗��ʂ���Ӊ����B���Ƃ��s�����ƂƂ����B
�@�g���͂��̔N�X���A�������Y�ۋZ�t�ɓK�n��{�݂Ɋւ��钲�����Ϗ��������ʁA�͌������U�L�����[�g���㗬�̌���i���A����j�ɁA�T�O�O�����̏����\�͂����Ӊ��{�݂����݂��A�܂��A�͌�����P�E�R�L�����[�g���قǏ㗬�̃�����̐��𗘗p���A�̗����ݒu���Ď��Ƃ��J�n�����B���������̐l�H�Ӊ��{�݂́A�p���̉��x���Ⴍ�����������o�Đ��ѕs�ǂƂȂ������߁A���R�T�N�ɖ��É�������Ƃ������Č@�蔲����˂��@�����̂ł��邪�A������n�Ղ��d���ĕs�����ɏI������B���̂��߁A�K�n�����߂ĒT�������Ƃ���A�㔪�_�Z�C���E�x�c��x���̑�ɗǎ��̂킫���������邱�Ƃ��A�C�k�ɂ���Ēm�炳��A�R�U�N�P���Ԃ̊ȈՂӉ��{�݂�݂��Ď����������ʁA�\�z�ȏ�̐��т��グ�邱�Ƃ��ł����B����ɂ���āA�R�V�N�Ɍ���̂Ӊ�������̒n�Ɉړ]�������A�T�O�O�����̂Ӊ��{�݂�ݒu�����B���ꂪ�A�����_���Ə�ݒu�̒[���ƂȂ����̂ł���B
�@�K�����̒n�́A�����E�����E���ʂƂ��ɃT�P�̂Ӊ��ɍD�K�ň����������т��ǂ������̂ŁA�S�O�N�ɂ͂W�O�O�����A�S�P�N�ɂ͂P�O�O�O�����A����ɁA�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�ɂ͂P�Q�O�O�����Ƃ����悤�ɁA���X�Ǝ{�݂��g�����������B
����Ӊ���@�i�ʐ^�P�j

�Z�C���E�x�c�Ӊ���@�i�ʐ^�Q�j

�@�������ĂӉ����Ƃ�����ɂȂ�ɂ�ĕߊl�����N�X�����̌X�����݂��A�����R�X�N�ɂ͎j���R�ʂƂ�����R���U�O�X�W�����L�^�����̂��͂��߁A���������Ɏ���܂ő�P����������ƌĂ��D���т��c�����̂ł������B������Ɖv�����������A�����S�O�N�ɂ͔��_�����꒡�Ɍ��ݎ����ɂP�Q�O�O�~�i���z�\�Z�P�Q�Q�Q�~�j���S�P�N�ɂ͔��_���w�Z�����̑��ꌚ�ݎ����ɂT�O�O�~����t����ȂǁA�������Ƃɂ��傫���ь������B
�@���������g���̓w�͂Ǝ��т��F�߂��A�����R�X�N�̖k�C�����Y���i��ɂ����ē��v�����̂��͂��߁A�S�Q�N�̖k�C�����Y���i��ł͖��_��v�A���S�R�N�̔��O�{�B�i�]��ł͖ؔu��g�A����ɁA�吳���N�ɓ����ŊJ�Â��ꂽ��B������ł͋�u����ȂǁA���X�̉h�_�ɋP�����̂ł������B
�@���̂悤�ɑg�����Ƃ͒��X�ƌp������A�D���т��c���Ă����̂ł��邪�A���a�X�N�i�P�X�R�S�j�R������������āA���c�Ӊ����Ƃ���Ăɓ����Ɉڊǂ���邱�ƂɂȂ������߁A�i���P�������g���̗��j�ɏI�~�����ł��ꂽ�̂ł������B
���E���c�ւ̈ڊ�
�@���a�X�N�S���A�V�y��������אB�g���̎{�݂͓����Ɉڊǂ���u�k�C��������z����t���V�y�����Ə�v�Ɩ��̂�ύX���Ĕ����������A���N�U���ɂ͖k�C�������z����̌��n�Ɂu�k�C�������z����n���x��v���n�݂̑n�݂ɂ���Ė{��̒������Ə�ƂȂ�A����ɁA�P�Q�N�X���ɏ㔪�_���ꂽ���Ƃɂ��A���̎x��ɕ��݂̗V�y�����Ə��ƂȂ�ȂǁA�ڂ܂��邵���ϑJ�����B���̓n���x��́A�n���E�w�R�x���Ǔ��̂Ӊ�������邱�ƂɂȂ������A�P�U�N�ɂ́u�k�C�������Y�Ӊ���n���x��v�Ɖ��̂��A�P�W�N�X���V�y���͔Ȃ̕ߊl�̗��ꐮ���ɂƂ��Ȃ��A���̗̍���Ɏx�ꎖ�������ڂ����B
�T�P�Ӊ����Ɨp���i�ʐ^�P�j
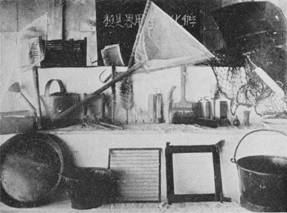
�@�Q�P�N�Ɏx��͊NJ���悪�g������A����܂Ŗ{��̏��ǂł�������u�x���Ǔ����Ə����������悤�ɂȂ�A���Q�Q�N�ɂ͋��R�p�����R�U�i��P�P�X�������[�g���j�����NJ����̂����������āA�x�ꎖ�������̗��ꂩ��{�����̌��ݒn�Ɉړ]�����B�Ȃ�����Ɠ��������ɁA�������O�ʂ̍��L�n�P���T�O�O�O�i��S�X�E�T�w�N�^�[���j�����NJ������A����ɂS�O�O�i��P�R�Q�O�������[�g���j�̗{���r�P�P�ʂ����āA��c�{��E�j�W�}�X�̐��Y���J�n�������A��X�̈��������d�Ȃ��Đ��ʂ��オ�炸�A�Ԃ��Ȃ����̎��Ƃ͒��~���ꂽ�B
�@�Q�V�N�ɃT�P�E�}�X�Ӊ����Ƃ͂��̏d�v�����獑�c���ƂƂ��Ď��グ���A�u���Y���k�C�������E�܂��Ӊ���n���x�x��v���n�݂����Ɠ����ɁA�㔪�_�̗V�y�����Ə�́u���_���Ə�v�Ɖ��̂��ē��x�ꏊ���ɉ��߂��A��苭�͂ȂӉ����Ƃ��W�J����邱�ƂƂȂ����B�������A���݂̖k�C�������Y�Ӊ���n���x��́A���̂܂c���Ă���Ɠ�������`�ƂȂ�A���Y���̈ϑ����ăT�P�e���̕ߊl���Ƃ��s�����ƂɂȂ��đ����������A���̌�S�S�N�R������ł��̎��Ƃ����������p���A�ߊl��������܂ł���т��č��̎��ƂƂ��čs���邱�ƂɂȂ����̂ŁA���̖k�C�������Y�Ӊ���n���x��́A���̗��j�ɖ������낵���̂ł������B
�@�Ȃ��A�Q�V�N�ɉ�����̒����A�ʏ́u���̑�v�ɂT�O�O�����̂Ӊ��{�݂����݂��āu�V�y�����Ə�v�Ɩ��t���A���_���Ə�̂P�T�O�O�����i�Q�U�N�Ɋg�[�j�ƍ��킹�ĂQ�O�O�O�����K�͂̂Ӊ��\�͂�����A���̔��W�����҂��ꂽ�̂ł��邪�A�p���Ɍb�܂ꂸ�����̐��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�J�݂P�O�N��̂R�U�N�Ɏ��Ƃ𒆎~���A�R�W�N�����ɔp��ƂȂ����B
�������Y�Ӊ���n���x��i�ʐ^�P�j

�T�P�̉͌��ʉߊϑ�����
�@���a�R�V�N�ɗV�y�����ΏۂƂ��āA�����ŏ��߂ĉ͌��ʉߊϑ����Ƃ����{���ꂽ�B����ɂ���āA�t���̌��Ֆh�~������K���𖾒����Ȃǂ��S�V�N�܂ő�����ꂽ�ق��A�S�O�N�ɂ͕��Θp�����E�܂��g��Đ��Y�v�悪���Ă���A
�@�P�A�V�y����̂����E�܂��̐��Y����
�@�Q�A���ݐ��撲��
�@�R�A����ӂƂ܂��̐��Ԓ���
�@�S�A�����̒萔����
�@�T�A�e��W������
�Ȃǂ̒��������{���ꂽ�B
�@����ɁA�S�Q�N�ɂ͕����ȓ��茤���̈�Ƃ��āA�u���������Q�W�̐��Y�͂Ɋւ��錤���v���T���N�v��Ői�߂��A�܂��A�S�W�N�ɂ͖k�Ă���M���U�P�X�������ړ����ĂӉ���������ȂǁA�V�y�����ΏۂƂ��čs���Ă���ϋɓI�Ȓ���������Ӊ����B���Ƃ́A���܂�L�����ڂ��W�߂Ă���Ƃ���ł���B
�n���x�ꔪ�_���Ə�i�ʐ^�j

�@�V�y����Ɣ��_���Ə�́A
�@�P�A���B�̗��j���������ƁB
�@�Q�A�ݏֈȐ��C��̖��[�����͐�ŁA���ƐU���カ��߂ďd�v�Ȓn�ʂɂ��邱�ƁB
�@�R�A�n���x��ɕ��݂���ċZ�p�w���Z���^�[�̖������ʂ����Ă��邱�ƁB
�@�S�A���Y�����c�ŕߊl�̗����s���Ă���S���B��̉͐�ł��邱�ƁB
�@�T�A���ۃ��x���ŃT�P�E�}�X�Ɋւ���͐쐶�Y�͒��������{���ꂽ�����B��̉͐�ł��邱�ƁB
�ȂǁA�T�P�E�}�X���B���ƂɊւ����͐�Ƃ��āA�܂��A���ۓI�Ȏ����͐�Ƃ��Ă��A�L���F�߂���Ɏ������̂ł���B
�@���������āA�����̎��тɂӂ��킵���{�݂̑S�ʓI�Ȑ������A�v�����]�܂�Ă����̂ł��邪�A���a�T�Q�N�U���ɗ{���r�Ƃ��̏�Ƃ���ю���r�̐V�݂Ɗ֘A�H���ɒ��肵�A�ꉭ�~�]�̔�p�𓊂��ĂP�Q���ɂ�������������B�������Đ������ꂽ���_���Ə�́A�Ӊ����ݔ��P�S�S�O�����A�{���r�ݔ��Q�T�O�O�����A����r�ݔ��P�W�O�O������
�����K�͂�i���A�Z�p�w���Z���^�[�I�Ȗ������ʂ����A�n�搅�Y�Ƃ̔��W�ɑ傫����^������̂Ɗ��҂���Ă���B
�T�P�̕ߊl���i

�V�y����T�P���̐���
�@�����P�R�N�i�P�W�W�O�j�Ɏ����I�ɃT�P�̓V�R��玖�Ƃ��֎n���Ĉȗ��A�����N��ɂ����Ă͂Q�O�O�O���䂪�R���N�A�R�O�O�O���䂪�R���N�Ƃ����悤�ɁA��r�I�D���ɐ��ڂ����B�������A�����R�X�N�̂R���U�O�X�W���i�j���O�ʁj��M���ɁA�P���������N���P�Q���N�ɂ��B����Ƃ����ŁA���ɖ��������ɂ����Ă͑�����������Ƃ�������D����悵���B
�@�������A�吳�N��ɓ���Ƌ}�ɐ��ނ��͂��߁A��O�I�ȖL���̔N�����������̂́A�吳�V�N�i�P�X�P�W�j�̂P�O�V�S�����Œ�ɁA�P�O�O�O���䂪�l���N�A�Q�O�O�O���䂪�l���N�Ƃ����s�U������}�����B����́A�㗬��͔Ȃɂ�����ł�Ղ��̉e����A����㗬�̃}���K���z�̍̌@�Ȃǂɂ��͐���̈����������ł���Ƃ݂�ꂽ�̂ł������B
�@�吳�W�N�ɑ�ꎟ���E��킪�I������Ƃł�Ղi���}���ɖ\�����A���̐������قƂ�ǔp�Ƃ���ĉ͐��������ɉ������Ƃ������āA�吳��������ĂэD�]���͂��߁A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�ɂP���R�O�P�P���A�P�O�N�ɂ͂Q���Q�V�Q�O���𐔂��A���̂ق��̔N�������ނ˂T�O�O�O�����O��ߊl����Ƃ����D�������a�Q�T�N�܂ő����A�ꉞ�A������������ƌĂ��D�������}�����B
�@�������A�Q�U�N�̂Q�Q�X�U���A�Q�V�N�̂P�R�X�Q���Ȃǂ̂悤�ɁA����ɉ����������ǂ��đ����s�U����ɓ���A�R�T�N�ɂ͕ߊl�����킸���ɂS�S�S���Ƃ����A�V�y����ɂ�����T�P���B���Ƃ̊J�n�ȗ��A�j��ň��̕s�����L�^���A���̌���R�V�N�������S�R�N�܂ł́A�ߊl���P�O�O�O���ȉ��Ƃ����P��I�ȕs���Ɍ������Ă����B
�@�S�S�N�ɂP�O�O�O����ɏ���Ă���悤�₭�D�]���A�S�W�N�̂U�O�S�T���Ȃǂ��o�āA�T�U�N�ɂ͎��ɂT���V�R�S�U���Ƃ����j��ō��̕ߊl���L�^���āA���S�ɑ����s�U�����E�����ς�����A�Ӊ��{�݂̐����[���ƂƂ��ɍ���̐����Ɋ��҂����Ă���B
�@�R�Q�N�ȍ~�ɂ�����V�y����ɂ�����T�P�̕ߊl�E�̗��E�����̏͏�\�̂Ƃ���ł���B
�N�x�ʍ��ߊl��
| �敪 �N�x |
�߁@�@�l �� |
�́@�@�� ���� |
���@�@�� ���� |
| ���R�Q | �U�Q�W | �P�P�U | �P�C�W�T�X |
| �R�R | �Q�C�O�R�U | �S�T�P | �P�C�T�T�P |
| �R�S | �P�C�Q�P�X | �Q�X�O | �T�U�O |
| �R�T | �S�S�S | �V�P | �V�O |
| �R�U | �U�T�Q | �V�V | �W�Q�W |
| �R�V | �P�C�V�V�T | �Q�V�W | �P�V�P |
| �R�W | �W�S�T | �Q�O�O | �U�P |
| �R�X | �T�V�P | �P�P�R | �P�S�X |
| �S�O | �V�S�U | �P�Q�U | �T�V�U |
| �S�P | �U�S�V | �P�O�Q | �Q�O�P |
| �S�Q | �T�W�S | �P�P�P | �S�V�S |
| �S�R | �W�S�P | �P�S�W | �S�P�O |
| �S�S | �P�C�O�P�X | �P�S�S | �T�O�O |
| �S�T | �Q�C�Q�S�X | �R�R�U | �W�V�X |
| �S�U | �P�C�W�T�U | �Q�U�P | �V�X�X |
| �S�V | �R�C�X�R�X | �T�S�T | �U�X�V |
| �S�W | �U�C�O�S�T | �P�C�O�Q�S | �T�V�S |
| �S�X | �Q�C�S�X�V | �R�X�V | �R�S�O |
| �T�O | �R�C�T�S�U | �S�P�O | �V�W�O |
| �T�P | �W�C�O�W�W | �P�C�P�X�U | �S�Q�T |
| �T�Q | �R�W�C�R�V�W | �R�C�T�Q�V | �P�C�P�X�T |
| �T�R | �P�R�C�P�R�S | �Q�C�O�V�V | �W�C�U�U�S |
| �T�S | �X�C�V�W�S | �W�C�X�T�Q | �X�C�S�R�W |
| �T�T | �P�R�C�P�R�O | �P�R�C�Q�V�S | �P�P�C�X�Q�S |
| �T�U | �T�V�C�T�S�U | �S�R�C�X�U�X | �P�R�C�V�O�O |
�i���_���Əꎑ���j
�����E��c�ǐ�̃T�P�̑��B
�@���̐́A��������R�z�����̉��݁A��������c�ǐ�ɂ����Ă��e�Ղɕߊl����Ă����T�P���A���������ɂ͔��_���Ɠ��l�Ɏ���ɎY�z����������X���ɂ���A���̂܂ܕ��u����Έ���������Ȃ��Ȃ�Ƃ����ɂ������B���̂��߁A���ꂻ���玎�����s�����̂ł��邪�A���܂萬�т��ǍD�łȂ��������ߒ��f���Ă��܂������Ƃ́A��ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@���̌�A���͐�ɂ����鑝�B���Ƃ͂��炭�s���Ȃ������̂ł��邪�A���̏��a�Q�R�N�ɂ͗��������Ƌ����g����������ŕߊl�E�̗��E�����̎��Ƃ��J�n���ĂR�R�N�܂Ōp�����{�����B�������A�������������N�łQ�R�N�̂V�S�����A�R�R�N�̂S�R�����Ƃ����悤�ɁA�ʓI�ɏ��Ȃ������������Ă��A�ߊl�������������Ƃ�������͂��ɂ݂��Ȃ������B
�@������͓�����Q�̉͐�Ƃ��āA�����̑��B�ی�ɓw�߂�K�v�����邽�߁A�����������k�C�������E�܂����B���Ƌ��͉��ϑ����A���a�T�P�N�i�P�X�V�U�j����Ăѐe���̕ߊl���Ƃ��n�߂Ă���B�����āA�̗��E�Ӊ��E�����͔��_���Əꂪ�S�����A�ŗǂ̎����ɗ�����ɒt�����^��ŕ�������Ƃ������@���Ƃ��Ă��邪�A���̐��т͏�\�̂Ƃ���ł���A���ʂɑ傫�Ȋ��҂����Ă���B
�@�Ȃ��߂������ɂ����āA��c�ǐ�ł̎��Ǝ��{���v�悳��Ă���B
������̎��Ə�
| �敪 �N�x |
�߁@�l �� |
�́@�� ���� |
���@�� ���� |
| ���S�V | �| | �| | �Q�O |
| �S�W | �| | �| | �T�O |
| �S�X | �| | �| | �T�O |
| �T�O | �| | �| | �P�W�O |
| �T�P | �S�X�O | �R�W | �X�Q |
| �T�Q | �T�P�S | �V�R | �P�V�O |
| �T�R | �U�O�W | �V�V | �P�V�O |
| �T�S | �W�T�U | �P�C�O�R�Q | �P�U�O |
| �T�T | �P�C�X�O�V | �P�C�W�Q�S | �P�T�O |
| �T�U | �S�C�U�Q�T | �S�C�O�T�O | �Q�Q�O |
�ی싦��
�@���a�X�N�i�P�X�R�S�j�S���A�����ȗ����Ƃ𑱂��Ă��������אB�g���̎{�݂����Ɉڊǂ��ꂽ��́A�����h�~�g�����������ėV�y����̖����h�~�ɒ��������͂��Ă����B�܂��A�I���̍������ɂ́u���_�������z�����Ƌ��͉�v��ݗ����āA�����h�~��t���̕ی�ȂǂɐϋɓI�ɋ��͂����B����ɏ��a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j�ɂ͑S���I�ȉ^���ɍL����A���̉�́u�V�y��������ی싦�͉�v�Ɖ��߂ĐV�������A�S���g�D�Ƃ��Ėk�C�������ی싦�͉�A����ݗ�����A���̎��Ƃɑ��鋦�͑Ԑ���������ꂽ�B�����łQ�T�N�ɂ͊e�x�ꂲ�ƂɘA����̎x�����݂����A�n���x�����ɂ͔��_�������I�C����Č��݂Ɏ����Ă���B
�u�V�y��������אB�Ǝ��v�̏����ɁA
�@����N�m�����V�y����m���������Y�A�ɗ��ԗm���B�X���A�����J�A�q�����p�M�����z�ƃm�o�c�j�w�����j��U���o�����]�\�N�i���j���v���v���R�g���������b�N�o�������j��O�m�ח��j�f�n�Y�A���S���x���אB���ƃm���W�����V���c�m��ƃ��V�e�{�X���P�A���V�����R�g���A
�ƗV�y��������אB�g���̗����߂����엲�����q�ׂĂ���A����������l�̊肢�́A�����̕ϑJ���o�Ȃ����������v���͂̂��ƂɈ����p����A�����h�~��t���ی�̂��߂ɗ͂�������Ă���B
�T�P�����h�~�̊Ď������i�ʐ^�j

�@��W�߁@���`
���_���`
�@�����Ƃ̔��W�ƂƂ��ɔ����@�D���������A���т��є�������C��̂�h�~���邽�߂ɂ��A�܂��A�o�������̑��������҂��邤���ł��A�W�҂̊Ԃɋ@�D���{�݂̐ݒu�v�]�����܂�A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�ɓ��������z�`�������ɂ���āA���_�����݂ɂ��ďڍׂȒ��������{���ꂽ�B���̌��ʁA�V�y���n����ɋ��`�̒z�ݐv���Ȃ��ꂽ���A���H��͑����H���W�P���~�]�A�����H���P�Q���~�]�ƎZ�o����A�����Ƃ��Ă͂��܂�ɂ����z�ȍH����ƂȂ������߁A��X�̏������ɋ�̉����݂�Ɏ���Ȃ������B
�@���̌��������u�V�y���͌��ɓK���Ȏ{�݂�z�݂��Ĕ����@�D�̔���e�ՂȂ炵�߂�悤�v�Ƃ����������ꂽ�B����ɑ����a�P�S�N�X���ɔ��ٓy�؎��������̎��@�A����ɁA�����`�p�ے��̎��@�Ȃǂ��o�āA���P�T�N�ɂ͂��悢��V�y���͌������C���đD���Ԃ�z�݂���Ƃ����v��̂��Ƃɒ����v���i�߂�ꂽ�B�����čH������R�T���~���x�ƎZ�o����A���������̍������̂ɂȂ����̂ł��邪�A�͌����p�̑D���Ԃ͉ߋ��̎��Ⴉ��݂Ă��Z�p��ɖ�肪����Ƃ��ꂽ�����A�₪�đ����m�푈�ւ̓˓��Ƃ����d��ȏ�̕ω��ɑ������āA�Ăю������݂�Ɏ���Ȃ������̂ł���B
�@�I���A���Ƃ̉���I�ȐU���Ɉӂ������ꂽ���Ƃ���A�k�C�������J���ψ���Y��啔�ψ��ɂ���Đi�߂�ꂽ�A���`�E�D���Ԃ̐V�݂Ɗg�[�̂��߂̒����̌����A�Q�Q�N�R�����_�D���Ԃ̐V�݂��k�C���J���T���N�v��ɐ��荞�܂�邱�ƂƂȂ����B���̓���ɐڂ����n���Ƃ��ẮA�����Ɂu���_�D�����ݒu����������v�i��E�^�쒬���j��g�D���A���̎����Ɍ����ċ��͂ȉ^����W�J���邱�Ƃɂ����B
���_���` �i�ʐ^P1�j

�掵�����`���������v�攪�_���`�C�z���ƌv�敽�ʐ} �i�ʐ^P1�j
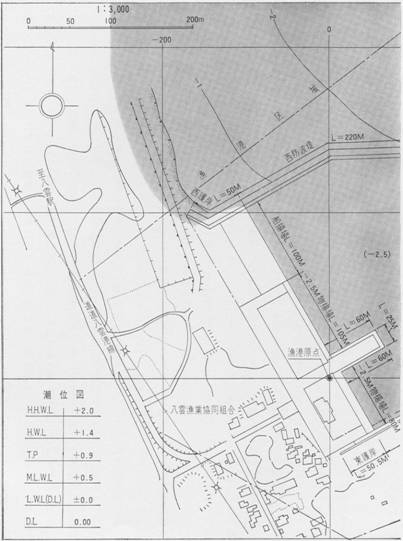

�@�Q�R�N�V���ɂ́A�z�ݗ\��n��V�y���n���i�t�B�b�V���~�[���H��ȓ�j�Ƃ��A����P���i��R���R�O�O�O�������[�g���j�A�C�ʂQ���ɂ��Ē�������A�v���i�߂�ꂽ�̂ł��邪�A�Q�T�N�T���ɐV���Ɏ{�s���ꂽ���`�@�ɂ���āA���`�͔_�ё�b�����`�R�c��̋c���o�������ŁA�W�m���̈ӌ����Ďw�肷�邱�ƂƂȂ�A���_���`�͂Q�U�N�U���Q�X���_�яȍ�����Q�S�R���������đ��틙�`�Ƃ��Ďw�肳��A�悤�₭���̒z�݂����m�ɂ��ꂽ�̂ł���B���̑��틙�`�Ƃ́A�S��ނ̂����u���p�͈͂����틙�`�i�n���̋��Ƃ���Ƃ�����́j���L���A��O�틙�`�i�S���I�Ȃ��́j��苷�����́v���������̂ł���B�@�������āA���N�̌��Ăɖ��邢���ʂ�������ꂽ�킯�ł���A���Q�V�N�ɂ͒��H��O��Ƃ���{�i�I�Ȓ������s���ċ��`�ʒu������A���悢���ꎟ���`�����v��̒��łQ�W�N�x�̎��ƒ��肪�m�肵�A���N�P�Q���P�S���Ɍ��n�Ő���ȋN�H�����s���A���_���`�������Ƃ̉���I�ȃX�^�[�g������̂ł���B�����������`�����v��̘g�g�݂ƁA����ɑ��鍑��\�Z�̔z���Ƃ��������̒��ŁA�i�s�͒x�X������̂ɂȂ������A�������т��̌v��ύX���o�Ȃ�����A�T�Q�N�x����̑�Z�����`�����v��̒��ŁA���H�ȗ����ɂQ�V�N�̍Ό��Ƌ���𓊓��������_���`�́A���ɂT�S�N�x�������Ċ������A���_�����̖������Ȃ���ꂽ�̂ł������B
�������`
�@�×��A�������̉��݈�т͈ꌩ����Ɣg�Â��ȂƂ���ł��邪�A�ЂƂ��ѓ����������A��]���Č��Q�̐�����Ƃ���ł���B���������āA�o�����̋��D���������̕ω��ɂ���ċ}����A�҂���ꍇ�ɂ��A���{�݂��Ȃ����߁A�݂�ڑO�ɂ��Ȃ��瑘��A�����l���������Ƃ������̂������Δ��������B�܂��A�����@�D�͋����ɂȂ�Ɗ݂���R�T�O���[�g���قǂ̊C��ɂȂ����܂܂ł������߁A����������C�݂ɑł��グ���Ĕj�D����Ȃǂ̑������傫���A���`�i�D���ԁj�̒z�݂͋����ɂƂ��đ��N�̌��Ăł������B
�@����������w�i�Ƃ��đ�����ꂽ�v���ɑΏ����A���a�X�N�i�P�X�R�S�j�W���ɂ͓����ɂ���Ď�����v�̍�Ƃ��i�߂�ꂽ���Ƃ�����A�����������]�܂ꂽ�̂ł��邪�A�₪�Đ푈�ւ̓˓��Ƃ�������̉��ł́A�����������i�~�ɂ͎���Ȃ������̂ł���B
�@�I��ア�������A�������M�S�ɌJ��Ԃ��ꂽ����ɂ���āA���a�Q�P�N�V���Ɂu�������j�D�����z�݃m���i����j�v������ō̑�����A�܂��A�Q�Q�N�R���ɂ͔��_���`�Ɠ��l�ɖk�C�������J���ψ���Y��啔�ψ��ɂ����n�����̌��ʁA�T���N�v��ɕғ������ȂǁA�O�r�ɖ��邢���ʂ��������������B�������A�ˑR�Ƃ��Ē��肳��邱�ƂȂ����N���o�߂������A�Q�U�N�U���Q�X���_�яȍ�����Q�S�R���������đ��틙�`�Ƃ��Ďw�肳��A���Q�V�N�W���T���ɋN�H�����s��ꂽ�B
�@�������āA�Q�V�N�ɑ�ꎟ���`�����v��C�z���ƂƂ��čH���ɒ���A�R�R�N�������Ĉꉞ�����Ƃ������ƂŃX�^�[�g�����̂ł��邪�A���̋��`�͒��H�����u������ѐ����h�g��v���v�悳��Ă����̂ɑ��A�H�����ɂ����āu�����h�g��v���폜����Ƃ����ύX������A���`�Ƃ��Ă͂���߂ĕs�\���ȋK�͂ƂȂ����B���̂��߁A���ǂɑ��Ē�Ȃǂ̋��͂ȉ^����W�J�������ʁA���������S�V�N�x�̑�l�������v��܂ł͏C�z�`�Ƃ��āA��������v��ł͉��C�`�ɑg�ݓ�����A����ɁA��Z���̂T�Q�N�x�ȍ~�ł͍Ăъg���v����܂߂��C�z�`�ɕғ�����āA�H�����i�߂��Ă���ł���B
�������` �i�ʐ^P1�j

�掵�����`���������v�旎�����`�C�z���ƌv�敽�ʐ} �i�ʐ^P1�j


�V�K���`�̎w��v���^��
�@�����E���_�̗����`�́A���a�T�O�N��ɓ����Ē��H�ȗ��Q�O���N���o�߂��A��Z�����`�����v��̂Ȃ��Ŕ��_���`�͂悤�₭�����Ɏ���A�������`�͊g�������肵�Ă���ɏC�z�������i�߂���ȂǁA�����ɂƂ��Ė��邢���ʂ�����������B
�@����A���a�S�O�N��㔼�ɓ����Ă���̉����Ƃ́A�z�^�e�L�̑��{�B�𒆐S�Ƃ��鋙�Ƃւ̓]�����}���ɐi�߂��A���Y�z�̑唼���߂�悤�ɂȂ����B�����������͔��_�E���������`����n�Ƃ��đ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A�T�O�N��ɓ����ĊԂ��Ȃ����`���痣�ꂽ�n��̋�������A��Ƃ̌������Ƃ����S�ȑ��Ƃ��m�ۂ��悤�Ƃ��邤���Ŋe�n��ɋ��`���݊�����a�����A�D���܂�I�ȋ��Ɗ�n�̐����ɑ���v�]�����܂��Ă����B
�@���������v�]�ɑΉ����āA���Ɨ����E���_�����Ƌ����g���͋��c���d�ˁA�����E���_���`�𒆊j���`�Ƃ��đ���������}��ƂƂ��ɁA���`�̕⊮�I�Ȏ{�݂Ƃ��ė{�B���Ɗ�n�����̌������Ɖ��ɂ��ėv����i�߂邱�ƂƂ����B���������ʂ͐��x��������ȏ�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ������߁A�����`�̐����Ɉ��e����^���Ȃ����Ƃ���{�Ƃ��āA�掵�����`�����v��i���a�T�V�N�x�[�U�Q�N�x�j�̂Ȃ��ŐV�K���`�̎w�肪����悤�^�����N�������Ƃňӌ��̈�v���݂��̂ł���B���������āA�T�Q�N�ƂT�R�N�ɂ����ė������𒆐S�ɐV�K���`�ݒu��]�ӏ��̒����ɓ������̂ł��邪�A���������NJ����ɂ����Ă͓���n��P�n��ɂ܂Ƃ܂������̂́A���_�����Ǔ��ł͖�c���E�R��E����̂R�n��ƂȂ�A���ǂ͂S�n�悩�狭���v�]���o����A������P�n��ɍi�邱�Ƃ͕s�\�ȏ�ԂƂȂ����B���̂��ߒ��Ƃ��ẮA�����Ă�����W�邱�ƂȂ��A�e�n��ɂ����鋙�Ƃ̈��S�ƐU����}�闧�ꂩ�狙���̗v�]�𗦒��Ɏ���A�T�R�N�P�O���ɒ����E�c��c������ї������g�����̘A���������āA�����S�n�拙�`�̐V�K�w��Ƒ������H�ɂ��ĊW���ǂɒ��Ɏ������B
�@�����A�n���Ǔ����ݒ����ɂ����ẮA���{�B���Ƃ̐L�W�ɂƂ��Ȃ����`�ݒu�̗v�]�������A���̎w��ɂ��Ă͊e�����Ƃ�����������W�J���Ă����B
�@�����������w�i�Ƃ��Ē��ɂ����ẮA�T�S�N�i�P�X�V�X�j�P���ɋ��`�w��\���ɕK�v�Ȋ�b�����A���Ȃ킿�C��[�ʂ◤�挻�����ʂȂǂ̈ϑ����W�O�O���~�̗\�Z���v�サ�A�c��̋c�����o�Ē��������{����ƂƂ��ɁA�y�،��Ə��̋Z�p�I�Ȏw�����Ȃ��琬�č���i�߁A�T�U�N�U�����m�����Ăɑ掵�����`�����v��̂Ȃ��ɂ��̂S�n�悪���荞�܂��悤�w��\�������o�����̂ł���B
�@���̌�A�����E�c���\����ї����E���_�������g������ƂƂ��ɐ��Y����J�����Ȃǂ̊W�@�ւɑ����͂Ȓ�𑱂����B���̌��ʁA���a�T�V�N�T���J�Â̑�P�Q�O�`�R�c��̋c�����o�Ĕ_�ѐ��Y��b�̍̑�����Ƃ���ƂȂ�A�T�V�N�P�O���W�����̂悤�ɍ������ꂽ�B
�_�̐��Y�o�������ܕS�l�\�l���@�i�ʐ^P1�j
�_�ѐ��Y�ȍ������ܕS�l�\�Z�� �i�ʐ^P2�j

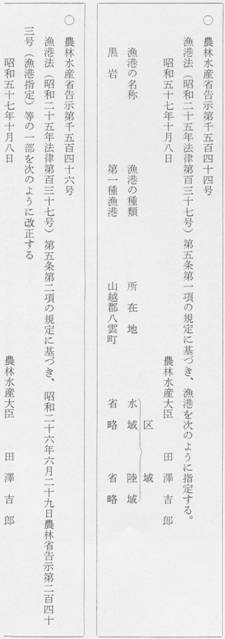
�@����ɂ��A���₪���틙�`�P�ƍ`�Ƃ��āA�܂����_���`����Ƃ��ĎR��A�������`����Ƃ��ē���n��ɁA����
���ꋙ�ƍ����n�ƂȂ�{�݂����݂���邱�ƂƂȂ����B���ۂ̍`�̌��݂͑掵�����`�����v��̂Ȃ��ōs���邱�Ƃ�
�Ȃ邪�A������ɂ��Ă������Ƃ̈��S���ƂƐU���̂��߁A�W�n��̋����͂��̊����ɑ傫�Ȋ��҂��Ă���Ƃ�
��ł���B
�@��X�߁@���ƍ\�����P����
���ƍ\�����P����
�@���a�R�O�N��ɂ�����킪���́A���x�o�ϐ��������i����A�H�Ƃ𒆐S�Ƃ���Y�Ƃ̐��Y�̐L���ɂƂ��Ȃ��āA�����̏]���҂̏�����������͒�����������݂��A����ɑ��đ�ꎟ�Y�Ƃł��鐶�Y�͂̒Ⴂ�����Ə]���҂̏����͐L�т��A���҂̏����i���͂܂��܂����傷��X���ɂ������B
�@���̂��߁A�����o�ς̍��x�����Ɖ����Ƃ̌���ɑ������A���Y�ƂƏ\���Ȋ֘A���������Ȃ���A���̐i�����W�Ƌߑ㉻�𑣐i���A�����ĉ����Ƃ���ƓI�Ȍo�c�ɂ܂ň琬���邽�߂̊e��{��𐄐i���āA���Y�Ə]���҂Ƃ̏����i�������A���̐��������ƒn�ʂ̌����}��K�v�ɔ���ꂽ�B
�@�����������w�i�Ƃ��Đ��{�́A�����Ƃ̐��Y��Ղ̐�������ъJ���A�ߑ㉻�̂��߂̎{�݂̓����Ȃǂ����Ƃ��A�\�����P�Ɋւ���K�v�Ȏ��Ƃ��A�n��̓������������I�������I�ɍs����悤�w������������j���߁A�S���̉��݂��S�Q�n��ɕ����āA���a�R�V�N�x���版���ƍ\�����P���Ƃ����{�����̂ł���B����ɁA���R�W�N�W���ɂ͗v�j�������i�߂āu�����Ɠ��U���@�v��������z����A�@���I�ɂ����m�ȍ����������ꂽ�̂ł������B
�@���̂Ȃ��Ŗk�C���ɂ����鋙�ƍ\�����P���Ƃ́A���{�C�k���E���{�C�암�E���쑾���m�E�����̂S�n��ɕ����Đi�߂��A�R�V�N���{�C�k���n��A�R�W�N���{�C�암�n��A�R�X�N���쑾���m�n��i�n���k���E�_�U�E�����̒n��j�A�S�O�N�����n��Ə����w����A�{���S���݂̎w�肪�I������B�Ȃ��A���̍\�����P���Ƃ́A�w���Q���N�̒����Ɗ�{�v������̊��Ԃ��o�Ď��Ƃ����{�������̂ŁA���Ƃ̓��e��v��Ύ��̂S�_�𒌂Ƃ�����̂ł������B
�@�P�A���Y��Ղ̐����̂��߂̎���
�@���ɂ��z�����E�R���N���[�g�u���b�N�̖���ɂ�鋛�ʁE�m�����ꑢ�����ƁE�m���l�H�̕c�{�݂̐ݒu�ȂǑ��{�B�{�݂̑����𒆐S�Ƃ��鋙����ǎ���
�@�P�A�o�c�ߑ㉻���i�̂��߂̎���
�@��Ƃ��đg�������S�ƂȂ��ĉq���I�ȉJ���܂��͋��l���ۑ��̂��߂̐��X�①�{�݂Ȃǂ̋������p�{�݂����݂���ƂƂ��ɁA���~�{�B�{�݂Ȃlj����Ƃ̐��Y�������߂鎖�ƁA���Ɨp�ʐM�{�݂ȂNj��D���Ƃ̔\�����i�⑀�Ƃ̈��S���͂��鑕���̋ߑ㉻�Ɋւ��鎖��
�@�R�A���Y���̗��ʂ���щ��H���P�Ɋւ��鎖��
�@���H�{�݁E�̂肩���������{�݂��邢�͐��g�J�{�݂Ȃǂ̐ݒu�ɂ�艿�i�̈������͂��邽�߂̎���
�@�S�A�Z������
�@���Ǝ҂Ȃǂ����̌o�c���g�債�A�@�B�������邱�Ƃɂ��A�ߑ�I�Ȍo�c�ɂ܂Ői�߂悤�Ƃ�����̂ɑ��Ĕ_�ы��Ƌ��Z���ɂ��Z�����s���B
���̑�ꎟ�\�����P����
�@���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�ɓ������܂ޓ��쑾���m�n�悪�A�\�����P���Ƃ̑Ώےn��Ɏw�肳�ꂽ���Ƃɂ��A���͓��N�V���n���x���ق��W�s���@�ցE�c�̂̎Q���āu���Y�U����c�v���J�Â��A�����ɂ����鋙�Ƃ̎���ɂ��ĕ��͌������������B�����āA���E�c���\�E���Y�W�s���@�ւ���є��_�E���������������E�N�����E�w�l�����Ȃǂɂ���č\������u���_�������ƍ\�����P���i���c��v�i��E�c���F��j��g�D���A�e�n�悲�ƂɌv�撲���ǂ�݂��āA���Ƃ��Ƃ�܂��Љ�����������{�����̂ł���B
�@�������������͂������ʁA�����̋��Ƃ��u�ߔN�̊C���ω��ɂƂ��Ȃ������̉�V���Ȃ��A��u���Ƃ��ɓx�̕s�U�Ɋׂ�A�ډ��̂Ƃ���ꕔ���͑D�ɂ��C���ށA�L�ޓ��̐�C���ƂɈˑ����Ă��鋙�Ƃ���������ł��邱�ƁB���̂����A�����ʂɑ��ċ��Ə]���Ґ����������߁A��˓�����̐��Y�ʂ��ɂ߂ď��Ȃ��A�o�҂��E���ق��E�����ƒ{�̎���Ȃǂ̕��Ƃɂ���āA���v���ێ����Ă��鋙�Ƃ����������ɂ��邱�ƁB�v�Ȃǂɒ��ڂ��A���̂悤�Ȍ����Ŕj���邱�Ƃ�ڎw���āA�����ނˎ��̖ڕW��ݒ�̂������ƍ\���̉��P��}�邱�ƂƂ����B
�@�P�A�ߏ�A�Ƃ̊ɘa
�@���Y�Ƃւ̓]�������サ�Đ�ƌo�c�̐��̊m����}��B
�@�Q�A���ƍ����n�̐���
�@�����`�E���_�`�C�z���Ƃ𑣐i���ċ��ƍ����n�����A���͑D�ɂ��p�������Ƃւ̓]���𑣐i����B
�@�R�A���c�̒z��
�@���ƍ\�����P���Ƃɂ�鍩�z�ʁE���ʁE��^���ʂ̒z�݂�ϋɓI�ɍs���A�����̑��B��}��ƂƂ��Ɏ��ƌ��ʂ̊m�F�������s���B
�@�S�A�����̔|�{
�@���E�킩�����ނ̐l�H�Ӊ��̂ق��A�L�ނ̈ڐB�A�C���ނ̐l�H���B���Ƃ��s���ق��A����̐ݒ蓙�ɂ�莑���̔|�{��}��B
�@�T�A�����̒���
�@�k��L���̎����������s���A���l�K���[�u���u���Ď����̈ێ��|�{��}��B
�@�U�A���Ƃ̋ߑ㉻
�@���D�̑�^���A���Q�T�m�@�A���D�����@�̑������ߑ㉻����ق��A����E���@�����ƋZ�p�̉��P�𐄐i���A���Y�̑�����}��B
�@�V�A���H�����̉��P
�@���̑̐��̊m���A�W�{�݂���ї①�Ɏ{�݂̐����A�W�ב̐��̉��P�ɂ��̔��̍��������s���A�ɂ���E���������E�k��L���̉��H�{�݂̊g�[�ƋZ�p�̌���ɂ���Đ��i�K�i�ꂷ��B
�@�W�A���Ƃ̏���
�@�E�ɂ�Ƃ蓙�����ƒ{�̑����H��������サ�A���ƊO�����̑�����}��B
�@�X�A�o�c�Z�p���狭��
�@���Y���Ǖ��y���ɂ��o�c�Z�p���P��}��ق��A���ƌ��C��E�N�w���E�N���E�w�������C��ɂ��o�c�Z�p�̌����}��B
�@�P�O�A���̐���
�@���Y���H�̐����A�Z��̉��P�𑣐i�����邢������������B
�@�P�P�A���ƒc�̂̋���
�@���_�E���������Ƌ����g���̌o�c������}��A�������p�{�݂̐����𑣐i����B
�@�P�Q�A���ƊQ�G�̋쏜
�@�g�h�쏜��̋����𑣐i���A���l������ы���̊m�ۂƌ��Y��h�~����B�܂��Y���C�K�j�E���c��E�J�V�p�����̕ߊl�����サ�A�����ђt�L���̔�Q������}��B
��ꎟ�\�����P���Ƃ̎���
�@�ȏ�̖ڕW�ɉ����ď��a�S�P�N�x����S�T�N�x�܂łɂ����đ�ꎟ�\�����P���Ƃ����{����A�ʕ\�Ɍf����悤�Ȏ��т��グ���̂ł���B���̎�Ȃ��̂��W�Ă݂�ƁA���ꑢ�����ƂƂ��ẮA���_�E�����������ŕ��^���ʂT�U�O�T�̒��݁A���_�������ŃR���N���[�g�u���b�N�W�P�T�O�̓����A���_�E���������Ŏ��R�Q�S�W�O�������[�g���̓������s��ꂽ�B
�@�܂��A�o�c�ߑ㉻���ƂƂ��ẮA�������ɂ�鉫���{�B�ۑS�{�݂R�U�O��̐ݒu�A���������ɂ�鋙�Ɨp�ʐM�{�݂U��A���g�ׂ����{�݁i���������������t�j��A���_�������ɂ��̂�E�����������{�݈�̌��݂�����A����ɗZ���P�Ǝ��ƂƂ��ẮA���D�����P�V�ǁA�w���P�ǁA���D�@��w���V��������A�T���N�̑����Ɣ�P���Q�R�Q�X���~�ŁA����́A���E����⏕���T�O�V�V���~�A�������S���Q�S�X�T���~�A�ؓ����Q�Q�Q�V���~�A���Ȏ����P�U�S�O���~�Ȃǂ̂ق��A����W�X�O���~�ł������B
�@�Ȃ��A����獑�ɕ⏕���Ƃ̂ق��A���E����P�Ǝ��Ƃ��ϋɓI�ɍs���A�������ɂ�邩�~�{�B�{�݁A���_�������ɂ��̂�{�B�Z���^�[�A�⑫�������ƂƂ��Ă̎�c�|�{�{�݁A�����{�݊e��̌��݂Ȃǂ��s��ꂽ�B
��P�������ƍ\�����P����
���Ǝ�ڕʎ��Ǝ��ђ��i41�`45�j
�⏕�����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�@�Ɓ@�@���@�@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�@�@�@�l |
| ������Ǒ������� | ���_���� | ����ԏʒz�� ���R�Γ����@�S�S�Om3 |
�P�C�S�S�P | �@ |
| �R���N���[�g�u���b�N���� �W�C�P�T�O�@ |
�T�C�W�S�W | �@ | ||
| ���^���ʓ��� �Q�C�T�R�T�@ |
�W�C�O�S�W | �@ | ||
| �������� | ����ԏʒz�� ���R�Γ����Q�C�O�S�Om3�@ |
�T�C�X�U�X | �@ | |
| ���^���ʓ��� �R�C�O�V�O�@ |
�P�O�C�R�O�Q | �@ | ||
| �����{�B�ۑS�{�ݐݒu���� | ���_���� | �R���N���[�g�u���b�N �Q�W�O�@ |
�W�C�U�P�V | ���W���P�O���܂ށC����E�R��E�l���E�R�z�n�� |
| �������� | �R���N���[�g�u���b�N �W�O�@ |
�Q�C�S�V�P | ���W���S���܂ށC�����n�� | |
| ���Ɨp�ʐM�{�ݐݒu���� | ���_���� | �Q�V�l�b�|�c�r�a�|�v �U��@ |
�V�X�W | �@ |
| ���g�J�{�ݐݒu���� | �������� | �S�R���N���[�g �Q�K���ĂP�� �W�O�Q�D�R�U�u �@�①�{�݁@�Q�O�� |
�Q�X�C�R�P�S | �@ |
| �̂�C�����������{�ݐݒu���� | ���_���� | �ؑ��������� �R�X�U�D�U�P�u�@ |
�P�P�C�W�P�W | �@�B�h�M�d�C�����ꎮ���܂� |
| �v | �@ | �@ | �W�S�C�U�Q�U | �@ |
�Z���P�Ǝ����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �N�x | ���@�Ɓ@�� | �Z�@���@�z | ���@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�l | ||
| �S�P | �V�C�R�O�U | �S�C�X�R�O | �U | ���D�V���U�@ | ||
| �S�Q | �P�O�C�R�P�V | �U�C�S�X�V | �P�Q | �@�@�@�V�@ �T�C���D�@��@�@�V | ||
| �S�R | �W�C�W�Q�T | �S�C�U�T�O | �T | �@�@�@�V�@ �R�C �V ���D�@�@�P | ||
| �S�S | �V�C�S�R�X | �R�C�Q�O�O | �Q | �@�@�@�V�@ �Q�@ | ||
| �S�T | �S�C�V�W�O | �R�C�O�O�O | �P | �@�@�@�V�@ �P�@ | ||
| �v | �R�W�C�U�U�V | �Q�Q�C�Q�V�V | �Q�U | �@ | ||
��\�����P����
�@�����i���̐����A��ƓI�o�c�̈琬�A��鋙�Ƃ����Ă鋙�Ƃւ̓]���Ȃǂ�ڕW�Ƃ��Ďn�߂�ꂽ��ꎟ�\�����P���Ƃ̐��i�ƁA���̔��Ȃ̂����ɗ����A�u�����Ɛ��Y�̊g��A���Y���̌��エ��ьo�c�̋ߑ㉻�𑣐i���A�����ĉ����Ə]���҂̐��������̌����}��B�v���Ƃ�ړI�Ƃ��āA����������\�����P���Ƃ����{����邱�ƂɂȂ����B
�@���̑�\�����P���Ƃ́A�S���P�O�W�n��A�S���P�W�n��ɋ敪����A�������܂ޒn��́u���Θp�n��v�Ƃ��ĂS�T�N�x�Ɏw�肳��A���S�U�N�x�㔼���玖�Ǝ��{�ƂȂ����̂ł���B���{�ɂ������ē����Ƃ��ẮA���̂悤�ȍ\�z�����ƂɁA�ϋɓI�Ȏ��Ƃ̓W�J��}�邱�Ƃɂ����B
�@����E����P�Ǝ����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| ���@�Ɓ@��@�� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | �� �� �� | ���@�@�@�l |
| ���Ɨp�C�ǎ{�� | ���_���� | �P�� | �T�O�O | �@ |
| �������� | �P�� | �S�T�Q | �@ | |
| ���Ɨp�ʐM�{�� | ���_���� | �R�P�� | �R�C�U�Q�V | �@ |
| �������� | �S�T�� | �T�C�O�W�T | �@ | |
| ���H�p�����{�� | ���_���� | �S�� | �S�Q�W | �@ |
| �������� | �V�V�� | �V�C�P�V�Q | �@ | |
| ����ю�c�ڐA | �������� | �P�T�C�O�O�O�� | �R�R�U | �@ |
| �ق�����c�ڐA | ���_���� | �S�O�O�s | �S�S�U | �@ |
| ���{�{�{�� | ���_���� | �U�O���Q�O�Q�� | �T�C�U�Q�W | ���ꎮ |
| �P�Q�O���X�O�V | �U�C�Q�R�P | |||
| �������� | �P�T�O���W�O�V | �S�C�W�U�P | ���ꎮ | |
| �P�Q�O���S�O�V | �R�C�O�Q�O | |||
| �͔|���Ǝ��K����{�� | ���_���� | �R�O�� | �U�Q�O | ����T��@�����T�䐅���Q���P�O��@�����P�O�� |
| �D �� �g �{ �� | �������� | �P�� | �U�O�W | �@ |
| �̂�{�B�Z���^�[�⑥���� | ���_���� | �����Q���@�B�P�� | �S�C�R�Q�O | �����P���S�T�D�S�S�u |
| �ق��ĊL��c���� | ���_���� | �t�L�U�W�O�痱 | �P�C�O�Q�O | �@ |
| �v | �S�S�C�R�T�S | �@ | ||
�@
���Ȃ킿�A�����͕��Θp�̍ʼn����Ɉʒu���A�͔|���Ƃ�U�����邤���ł̎��R�����Ɍb�܂�Ă���A�������A�ߔN�����T�����̐����ƂƂ��ɁA�����𒆐S�Ƃ����w�R�Ǔ��ւ̓��H�Ԃ���������A�k���n���̋��_�n��Ƃ��Ă̗��n���������p���邽�߁A���_�������J���v�����ɁA�����̋ύt���锭�W�Ɉӂ�p���Ȃ���A���邭�L���ŏZ�݂悢�����̌��݂Ɍ����ĔZ���ȍ͔|���ƒn��̌`���ɓw�߂邱�Ƃ���{�Ƃ��A��̓I�ȏd�_�ڕW�����̂悤�ɒ�߂��B
�@�P�A���Ɛ��Y��Ղ̐���
�@���Ɛ��Y�̑�����}�邽�ߒn��o�ό��̒��S�ƂȂ鋙�`�̐����𑣐i����ƂƂ��ɁA����@�\�{�݂̊g�[��}��B
�@�Q�A�͔|���Ƃ̐U��
�@�]�O�Ɉ�������������Ǒ������Ƃ����{���A�n���I�����A����̓������������L���ށi�b�����ނ��܂��j�̉��ݐ������̑��{�B��ϋɓI�ɑ��i���A���݂ɂ����鎑���g���̍��x���ƌv��I�Ȑ��Y�g��̐��i��}��B
�@�R�A�����Ƃ̋ߑ㉻
�@�����Ƃ̑̎������P���邽�߂̏�����u���Ȃ��狙�Ƃ̌o�c�w�������͂ɐ��i����ق��A���`�A���H�A�Z��Ȃǂ̊֘A���ݎ��Ƃ̗L�@�I�ȑ��i��}��B
�@�S�A���ƌo�c�̍�����
�@�����o�ς̍������𑣐i���邽�߁A���Ƌ����g�����������A���킹�ċ��ƌo�c�̈����}�邽�ߍ���ɂ�����o�ς���ы��Ɠ����ɑΉ��ł���o�c��Ղ̋�����}��B
�@�T�A���Y���̗��ʍ������Ɛ��Y���H�Ƃ̐U�����i
�@�����H�����̎��I�ω��A����ҕ�������ɑ���Љ�I�v���ɑ������A���Y��������I�ɋ�������ƂƂ��ɁA���Y���̕t�����l�����߂ċ��ƌo�ς̈����}�邽�߁A���Y�̑����Ƃ��킹�ė��ʂ̉~�����A�������H�����̐��̐����g�[��}��ƂƂ��ɁA���Y�Ғc�̂��L�������n�①�ɂ̊��p��}��A�Y�n����n�Ԃ̒����̐��̊m�����i�A�A���͂̑����A�Y�n�W�o�ב̐��̐����Ȃǂ𑣐i���A���Y�����ʂ̉~������}��B
�@�U�A���Y���Z�̏[��
�@���Ƃ���ѐ��Y���H�Ƃ̐U���������邽�߁A�o�c�̍������A�{�ݐݔ��̋ߑ㉻�A�Z�p�J���Ȃǂ�ϋɓI�ɐ��i���Čo�c��Ղ̑����m����}��ƂƂ��ɁA�o�c�ߑ㉻�̂��߂̋��Ƌߑ㉻�����Ȃǂ̏[���Ƃ��̓�����}��B
�@�V�A���ƌ�p�҂̗{���m��
�@���Ƃ̍P�v�I���W��}�邽�ߎ����̗D�ꂽ���ƌ�p�҂�{���m�ۂ���K�v����A�W�@�ւƖ��ڂȘA�g��}��A�w�Z�E�ƒ�ɂ����鋙�ƏA�Ǝw������������ƂƂ��ɁA���ƌ��C�����͂��ߊe��̌��C�E�u�K�Ȃǂ��[�����A���N�̋��ƏA�ƈӗ~�̍V�g��}��B
�@�W�A���ƒ����̈ێ��ƊC��h�~�̐��̊m����}��B
�@�X�A���������h�~�̐��i��}��B
�@�P�O�A���̑��֘A����𐄐i���A���ƌo�ς̈����}��B
��\�����P���Ƃ̎���
�@�������āA��Ɉ����p���ꂽ�\�����P���Ƃ́A���a�S�U�N�x����S�X�N�x�܂ł̂S���N�����ԁi�Z�����Ƃɂ����Ă͂T�Q�N�x�܂Łj�Ƃ��Ď��{���ꂽ�̂ł��邪�A���̎��т͂����ނ˕ʕ\�̂Ƃ���ł������B
��Q�������ƍ\�����P���Ɓ@���Ǝ�ڕʎ��Ǝ��ѕ\�i�S�U�`�S�X�j
�⏕�����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | �� �� �� | ���@�@�@�l |
| ������Ǒ������� | ���_������ | ����ԏʒz�� ���Ύ��R���P�C�Q�Q�Om3 |
�T�C�U�P�W | �R��E�l���E��c���n�� |
| �̕c�琬�{���P�� | �Q�C�R�T�R | �R�z�n�� | ||
| �������� | ����ԏʒz�� ���Ύ��R���Q�C�T�P�Sm3 |
�W�C�V�S�U | �����n�� | |
| �̕c�琬�{���Q�� | �S�C�T�R�U | �����n�� | ||
| ���{�B�U������ | ���_������ | �~�{�B�{�݁i����ԁj�P�W�O�� | �P�P�C�V�R�S | �R�z�n�� |
| �~�{�B�{�݁i�ق��āj �u���b�N�P�U�Q��U�Z�b�g |
�P�P�C�T�S�O | �R�z�E�R��n�� | ||
| �������� | �~�{�{�݁i����ԁj�Q�S�O�� | �P�T�C�R�U�P | �����n�� | |
| �~�{�{�݁i�ق��āj�P�W�Z�b�g | �P�R�C�P�W�W | |||
| �o�c�ߑ㉻���i�� | ���_������ | ������ƕۊǎ{�� �S���Q�K���ĂP���U�T�T�D�Q�u |
�P�W�C�T�U�O | ���Y�� |
| �������� | ������ƕۊǎ{�� �S���������ĂP���S�R�Q�u |
�Q�P�C�T�O�O | ���� | |
| �v | �@ | �P�P�R�C�P�R�U | �@ | |
����⏕�����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�@�@�l |
| ���{�B�U������ | ���_������ | �ق��ĊL�̕c�y�� ���Ԉ����{���@�@�S�� |
�P�C�O�X�R | �R�z�n�� |
| �ق��ė{�B�{�� �R���N���[�g�u���b�N�Q�V�� ���������Q�O�{ |
�R�C�U�V�S | ����n�� | ||
| �������� | �ق��ĊL�̕c�y�� �����琬�{�݁@�@�X�� |
�Q�C�S�T�X | �����n�� | |
| �ق��ė{�B�{�� �R���N���[�g�u���b�N�W�Q�� |
�V�C�Q�S�O | �����n�� | ||
| �C��~���ݔ��ݒu���� | ���_�����_�~� | �C��~���ݔ��ݒu �@�~�������ˊ��P�� �@�~���S���{�[�g�P�� �@�r���|���v�P�� |
�V�V�T | ���_���~� �����@�@�@�V |
| �v | �@ | �P�T�C�Q�S�P | �@ | |
����⏕�����@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�@�Ɓ@�@���@�@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�@�S�@�@��@�@�� | |
| ���@�@�� | �� �� �� �� | ||||
| �̂�{�B�Z���^�[�i�⑫�����j | ���_������ | �����H���@�P�� �@�B���@�P�� |
�R�C�T�W�X | �P�C�V�X�S | �P�C�V�X�T |
| ���Ɨp�ʐM�{�ݐݒu���� | ���@�T�@�s�c�b�T�V�R�@�@�P�� | �R�W�T | �P�X�Q | �P�X�R | |
| �Q�V�l�g�y�@�n�r�a�P�v�P�Q�u�@�P�U�� | �Q�C�O�S�W | �S�W�O | �P�C�T�U�W | ||
| �� �� �@�@�Q�� | �Q�C�T�W�O | �U�O�O | �P�C�X�W�O | ||
| ���@�@ �T�@�P�� | �S�U�S | �Q�O�O | �Q�U�S | ||
| �������� | �Q�V�l�g�y�@�P�X�� | �V�C�R�P�T | �R�C�U�T�V | �R�C�U�T�W | |
| ���@�@ �T�@�T�� | �Q�C�O�O�O | �P�C�O�O�O | �P�C�O�O�O | ||
| ���z�����{�ݐݒu���� | ���z�����{���@�Q�W�� | �Q�C�P�X�P | �T�U�O | �P�C�U�R�P | |
| �L�ދ���Q�G�쏜�� | ���_�E���������� | �q�g�f���T�O�� | �P�C�O�O�O | �T�O�O | �T�O�O |
| ���Y���H�g���琬���� | ���_�n�搅�Y���H�� | �^�c��ꕔ���� | �Q�C�P�T�R | �V�P�S | �P�C�S�R�X |
| ���D��g���{�� | �������� | ���^�D�����c�m�{���u�K�� | �R�O�O | �P�T�O | �P�T�O |
| �t���ڐA���� | ���_�������B���͉� | ���i�ΎY�t������ �W�O�C�O�O�O�`�W�P�C�O�O�O�� |
�U�Q�P | �Q�O�O | �S�Q�P |
| �ق��āE�ق������B������ | ���_�E���������� | ���꒲�� | �W�P�X | �S�O�O | �S�P�X |
| �����e���r�w�� | �n���k�������P���c�� | �����e���r�P�� | �P�C�T�O�O | �P�U�O | �P�C�R�S�O |
| �ق����L��c�ڐB���� | ���_������ | �t�L�@�i�S�C�O�R�Q�C�O�O�O���j �Q�C�O�P�U�j |
�R�C�U�T�U | �P�C�W�P�S | �P�C�W�S�T |
| �������� | �t�L�@�i�Q�W�W�C�O�O�O���j �P�S�S�j |
�Q�U�P | �P�Q�X | �P�R�Q | |
| �C��~��^�c�ݔ����� | ���_�~� | �X�q�P�O�O�@�@�Ŕ� | �P�P�S | �T�O | �U�S |
| ���D�C��h�~�� | �������� | �W����]���Q�� | �Q�P�P | �T�O | �P�U�P |
| �v | �R�P�C�Q�P�O | �P�Q�C�U�T�O | �P�W�C�T�U�O | ||
�U���R���_�ы��Ɠ��ʊJ�����Ɓi�T�Q�j�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | �� �� �� | ���@�l |
| �o�c�ߑ㉻�{�ݐ��� | ���_������ | �{�B�p�ۊǍ�Ǝ{�� �����P���@�P�O�R�D�U�W�u �����ݔ��P�� |
�T�C�O�T�Q | �R�� |
| �������� | �{�B�p�ۊǍ�Ǝ{�� �����P���@�P�O�R�D�U�W�u �����ݔ��P�� |
�T�C�O�T�R | �h�l | |
| �v | �@ | �@ | �P�O�C�P�O�S | �@ |
����P�Ǝ��Ɓi�S�V�`�S�X�j�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | �� �� �� | ���@�@�l |
| �ق��ĊL�|���@�����ݕt | ���_�� | �Q�� | �T�W�S | �@ |
| �{�B��Ɠ˒璲�� | �V | �{�B��Ɨp�˒�{�ݓK�n���� | �S�V�O | �h�l |
| ���Ƌߑ㉻�������q�⋋ | �V | ���Ƌߑ㉻�������q�⋋�� | �P�C�P�P�P | �@ |
| �v | �@ | �@ | �Q�C�P�U�T | �@ |
�\�����P�⑫���������i�T�P�`�T�R�j�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| ���Ǝ�� | ���Ǝ�� | ���Ɠ��e | ���Ɣ� | ���l |
| �{�B�ۊǍ�Ǝ{�ݐ������� | ���_������ | �����i�S�R���N���[�g�j�P�O�D�P�S�u�@�Q�� �@�B���z���ǐݔ� |
�P�Q�C�V�U�W | ���� |
| �������� | �P�Q�C�S�W�W | ���� | ||
| ���_������ | ����1���i�S�R���N���[�g�|���v���P�O�D�P�S�u�j ���r���ݔ� |
�P�U�C�P�T�O | �R�� | |
| �������� | ����1���i���R���N���[�g�u���b�N�ؑ������P�Q�X�C�U�u�j �@�C�����g�{�݂P�� |
�X�C�S�R�V | ���� | |
| ������Ǒ����i�z�������Ɓj | ���_������ | ���i���R�j�P�C�P�U�Om3 | �V�C�V�O�X | �R�z�E�l���n�� |
| �������� | ���i���R�j�Q�C�P�S�Om3 | �P�Q�C�O�R�T | ���� | |
| ���Y���ׂ����{�ݐݒu���� | ���_������ | �����P���@�@�@�W�O�S�D�V�T�u �g���b�N�X�P�[���@�@�@�S�O�� ���ؐݔ��@�@�@�@�@�@�@�P�� |
�V�T�C�V�R�O | ���Y�� |
| �v | �@ | �@ | �P�S�U�C�R�P�V | �@ |
����⏕�����i�T�O�`�T�R�j�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�@�Ɓ@�@���@�@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�l |
| ������Ǒ������� | ���_������ | ���R�O�`�T�O�j�@�Q�S�Om3 | �P�C�T�W�P | �R�ǒn�� |
| �������� | ���R�O�`�T�O�j�@�R�V�Om3 | �P�C�X�V�V | �����n�� | |
| �ق��ė{�B�{�ݐݒu���� | ���_������ | ���������@�W�S�{ �T���^�R���N���[�g�u���b�N�@�W�S�� |
�V�C�S�S�Q | ����E�ԉY���Y�E�l�� |
| �������� | ���������@�P�O�S�� �T���^�R���N���[�g�u���b�N�@�U�W�� |
�U�C�O�P�U | �h�l�n�� | |
| �{�B��Ɨp�˒�z�ݎ��� | �������� | �{�B��Ɨp�V�� �@�@�g�^�|�ō� �@�@�S���V�T���@���T�� |
�Q�S�C�X�O�O | �h�l |
| �v | �@ | �@ | �S�P�C�X�P�U | �@ |
���P����i�T�O�`�T�R�j�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �� �� �� �� | ���Ǝ�� | ���@�Ɓ@���@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�@�l |
| ���Ƌߑ㉻�������q�⋋���� | �@ | ���Ƌߑ㉻�������q�⋋�� | �P�R�C�P�P�W | �@ |
| �k�C�����ƐM�p�������� | ���v�o���z�@�R�C�S�O�O | �P�C�V�O�O | �@ | |
| ���Y���H�J���������� | ���H�i�J�������P�� | �V�U�U | �@ | |
| �z�^�e�{�B���ƌ��C��� | ���C�� | �Q�O�X | �@ | |
| �v | �@ | �@ | �P�T�C�V�X�R | �@ |
����⏕���Ɓi�T�O�`�T�R�j�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| ���@�Ɓ@��@�� | ���Ǝ�� | ���@�@�Ɓ@�@���@�@�e | ���@�Ɓ@�� | ���@�S�@��@�� | |
| ���@�� | ���Ǝ�� | ||||
| �{�B��Ɠ˒�z�� | �������� | �˒�V�����ю��� ��t���H�P�S���ЂT�� |
�T�C�Q�S�O | �S�C�P�P�U | �P�C�P�Q�S |
| ���D�C��h�~�� | �W��������є��˔� �S�S�Z�b�g |
�X�T�X | �P�O�O | �W�T�X | |
| �����w�l���������\��� | �����w�l���������� | �Q�O�X | �U�X | �P�S�O | |
| �����E����ߊl���� | ������ߊl�{�݁@�@�@�@ �P�� | �P�C�U�W�V | �W�O�O | �W�W�V | |
| ����ѐ������� | �����@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�� | �Q�C�W�X�W | �X�O�O | �P�C�X�X�W | |
| �ȈՈړ����D��ݒu���� | ��ˑD��@�@�@�@ �@�@�@�P�� | �U�C�W�O�O | �Q�C�Q�U�U | �S�C�T�R�S | |
| �ق��āE�ق����L���B������ | ���_������ | �������� �����e���r�����@�@�@ �@�P�� |
�P�C�V�U�O | �W�T�O | �X�P�O |
| �D�g��ݔ� | �D�g��@�@�Q���� �R�S�D�O���~�P�V�D�O�� �R�R�D�O�@�~�P�V�D�O�@ |
�W�C�S�O�O | �S�C�Q�O�O | �S�C�Q�O�O | |
| �ق��ċ��ꑢ�� | �t�L�����@�@�@ �V�C�O�W�O�� | �P�Q�C�V�S�S | �R�C�P�W�U | �X�C�T�T�W | |
| �t���ڐA���� | �т�ΎY�t���ڐA �W�O�C�O�O�O���@�@�Q�O�O�s |
�V�P�O | �R�O�O | �S�P�O | |
| ���Ɨp�ʐM�{�ݐݒu | ���Ɨp���D�ǂQ�Q�� �t���j�c�q�P�P�U�^�c�r �P�R�P�v |
�R�C�W�T�O | �U�U�O | �R�C�P�X�O | |
| �C�����������{�ݐݒu | �����P�� �@�i�S�R���N���[�g�|���v���R�D�Q�S�u�j �@���r���ݔ� |
�R�C�R�W�O | �P�C�P�Q�U | �Q�C�Q�T�S | |
| ���Y���H���琬���� | ���_�n�搅���H�� | �^�c��ꕔ���� | �S�C�S�O�O | �P�C�U�T�O | �Q�C�V�T�O |
| �ق��ĊL���H���� | �ق��ĊL�E���L�����i�J������ | �R�O�S | �P�T�O | �P�T�S | |
| ���Y���H���Q�h�~�� | ���b���@�@�@�P�R�D�U���|�U�� �@�@�@�@�@�@�P�O�D�Q���|�P�� �@�@�@�@�@�@�@�@ �U�D�W���|�P�� |
�S�C�U�O�O | �V�Q�O | �R�C�W�W�O | |
| ���f���{�B�������� | ���_���E���������� | ���������@�@�@�@�@�@�@ �P�� | �Q�C�Q�T�R | �Q�W�O | �P�C�X�V�R |
| �v | �@ | �@ | �U�O�C�P�X�S | �Q�P�C�R�V�R | �R�W�C�W�Q�P |
�i�����@�@���_���̐��Y�T���@�@�T�R���S���j
�@��P�O�߁@��K�͑��B��J������
���ݐ��Y�����J�����̎w��
�@���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�T���Ɍ��z���ꂽ�u�C�m���Y�����J�����i�@�v��T���̋K��ɂ�鉈�ݐ��Y�����J�����Ƃ��āA�S�W�N�P�Q���Q�P���k�C��������Q�U���������āu���Θp���ݐ��Y�������v���w�肳�ꂽ�B����́A���̋����̊C��̗��p����݂āA���Y���A���̑��{�B�𐄐i���邱�Ƃɂ���āA���Ɛ��Y�̑��傪���҂������ɂ��Ďw�肳�����̂ŁA���Θp���݂̍���������ɒB�s�Ɏ���P�s�U���̒n��C������ƒ�߂Ă����B
�@���ɂ����Ă͂��̎w��Ɋ�Â������̌��ʁA���̐ϋɓI�ȋ��͂������āA���̐���ɂ����Ă͖k�C���̓��Y�I�Ȑ����ł���A���n�扈���Ƃ̎�v�Ώې����ŋ��ƈˑ��x�̍����u�z�b�L�L�v�����̑��B��}�邱�Ƃ��K���ł���ƔF�߂��B�����Ĕ��_���n�搅������Ɏw�肵�A�������ِ��Y������A�k�吅�Y�w������ђ����Y�ۂɂ���āA�S�W�N����R���N�ɂ킽���b���������{���ꂽ�B���̌��ʃz�b�L�L�̑��B�ɂ́A�t�L���C�݂ɑł��グ����̂�h�~���邱�Ƃ��ł��L���ł���Ƃ̌��_���B
�@�������������Ɋ�Â��ăz�b�L�L���B�̂��߂̋�̓I�Ȍv�悪���Ă��A�������Ƃ����Ƒ����ɏ��߂ē������ꂽ����I�Ȃ��̂Ƃ��������K�͑��B��J�����Ƃ��A���a�T�P�N������{���ꂽ�̂ł���B
�v��̊T�v�Ǝ���
�@�����̉��݉����ł͌Â�����R���u�����s���Ă��Ă���ق��A���a�S�O�N�ɂT�Q�E�T�L���O�����A�S�R�N�ɂS�O�O�L���O�����̃z�b�L�L��c���������ȂǁA���̑��B��}���Ă����B����ɂ�������炸�z�b�L�L�̐��Y�́A�S�T�N�����ɔN�X���������ǂ�͂��߂��B�����������Ƃ���A�t�L���g�ɂ���ĊC�݂ɑł��グ����Ƃ�����Q��h�~���A���̌����̌�������u����K�v�����Ɋ�����Ă����B���̂��߁A�g�ɂ���Ĉړ�����t�L���A�W�g���u���b�N�Œz�݂��闣�ݒ�̔w��ɏW�߁A�˒�ɂ���ĎU�킷��̂�h���A���Ղ̋ɂ߂đ傫���ꐶ�����̐����������߂邽�߂́A��K�͂ȑ��B��������悤�Ƃ����v�悪�����ꂽ�̂ł���B
�@����ɂ���Ă��̎��Ƃ́A�u���_�n���K�͑��B��J�����Ɓv�Ƃ��āA���a�T�P�N�x����T�T�N�x�܂ł̂T���N�ԂɁA����i�a��j�ƎR��i�`��j�n��̐��[�S���[�g���C��Q�����ɁA�P�P�O�O���[�g���̗��ݒ�ƂS�O�O���[�g���̓˒��z�݂��悤�Ƃ������̂ŁA�����Ɣ�Q�R���~�Ƃ�������I�ȑ厖�ƂƂȂ����B
��P�\�@��K�͑��B��J�����Ɓi���ݒ�j�i�ʐ^�P�j

�S�̌v��N���ʓ���
| �N�@�@�x | �T�P�@�@�N�@�@�x | �@ | �T�Q�@�@�N�@�@�x | ||||||||
| ��@�@�� | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�z | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�@�z | |
| ���@�Ɓ@�� | �� �� �� | �V �[ �� �{�P�D�O�� �i�Q���f���j |
�S�V�� | �~ �@�P�C�S�R�U�C�P�O�O |
��~ �V�Q�C�R�O�O |
�� �� �� | �V �[ �� �{�R�D�T�� �T�P�N �i�Q��f �ʕ��܁j |
�Q�X�U�� | �~ �P�C�S�O�T�C�W�O�O |
��~ �S�S�T�C�T�S�O |
|
| ���@���@�� | �S�C�W�O�O | �Q�R�C�S�Q�O | |||||||||
| �{ �H �� �� | �U�V�C�T�O�O | �S�P�U�C�P�Q�O | |||||||||
| ���ʂ���ю����� | �@ | �@ | |||||||||
| �D������ы@�B��� | �@ | �[�� | �@ | �P�O�Oha | �@ | �U�C�O�O�O | |||||
| �@ | �@ | �@ | |||||||||
| �N�@�@�x | �T�R�@�@�N�@�@�x | �@ | �T�S�@�@�N�@�@�x | ||||||||
| ��@�@�� | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�z | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�@�z | |
| ���@�Ɓ@�� | �� �� �� | �V �[ �� �{�R�D�T�� |
�Q�S�R�� |
�~ �P�C�V�P�T�C�U�O�O |
��~ �S�S�T�C�T�S�O |
�� �� �� | �V �[ �� �{�R�D�T�� �Q�{ |
�Q�X�O�� |
�~ �P�C�W�O�P�C�S�O�O |
��~ �U�U�W�C�R�P�O |
|
| ���@���@�� | �Q�R�C�S�Q�O | �R�Q�C�R�R�O | |||||||||
| �{ �H �� �� | �S�P�U�C�P�Q�O | �T�Q�R�C�P�Q�O | |||||||||
| ���ʂ���ю����� | �@ | �ˁ@�� | �Q�O�O�� | �T�O�S�C�R�O�O | �P�O�O�C�W�U�O | ||||||
| �D������ы@�B��� | �[�� | �P�O�Oha | �U�C�O�O�O | �[�� | �Q�O�Oha | �@ | �P�Q�C�O�O�O | ||||
| �@ | �@ | �@ | |||||||||
| �N�@�@�x | �T�T�@�@�N�@�@�x | �@ | �v | ||||||||
| ��@�@�� | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�z | �H�@�� | �i�@�� �`�@�� |
���@�� | �P�@�@�@�� | ���@�@�@�z | |
| ���@�Ɓ@�� | �� �� �� | �V �[ �� �{�R�D�T�� �Q�{ |
�Q�V�P�� |
�~ �P�C�W�X�P�C�T�O�O |
��~ �U�U�W�C�R�P�O |
�� �� �� | �V �[ �� �{�R�D�T�� �S�{ |
�P�C�P�O�O�� |
�~ �P�V�T�C�X�O�O |
��~ �Q�C�R�O�O�C�O�O�O |
|
| ���@���@�� | �R�Q�C�R�R�O | �P�P�U�C�R�O�O | |||||||||
| �{ �H �� �� | �ˁ@�� | �Q�O�O�� | �T�Q�X�C�T�O�O | �T�P�Q�C�O�W�O �P�O�T�C�X�O�O |
�ˁ@�� | �S�O�O�� | �T�P�U�C�X�O�O | �P�C�X�R�S�C�X�S�O �Q�O�U�C�V�U�O |
|||
| ���ʂ���ю����� | �[�� | �Q�O�Oha | �@ | �P�Q�C�O�O�O | �[�� | �Q�O�Oha | �@ | �R�U�C�O�O�O | |||
| �D������ы@�B��� | ���W�ݒu | �S�� | �P�C�T�O�O | �U�C�O�O�O | ���W�ݒu | �S�� | �P�C�T�O�O | �U�C�O�O�O | |||
�i�����@���S�̌v�揑�j
�@���̎��Ƃ̊����ɂ���āA���{�O�̐��Y�ʂV�X�g�����Y�z�V�O�Q�T���S�O�O�O�~�i�T�P�N�x�j�ɑ��A���Y�ʂ����悻�V�E�X�{�̂U�Q�R�g���A���Y�z�T���T�R�W�S���V�O�O�O�~�ɖڕW��u�������̂ŁA���Ǝ�͖̂k�C���ł���B���Ɣ�̕��S�敪�́A����U�O�p�[�Z���g�A����R�O�p�[�Z���g�A����P�O�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă���A������̎{�݂͒��ɊǗ��ϑ�����A�����͒��Ɣ��_�����Ƌ����g���̊W�҂őg�D����u��K�͑��B��Ǘ��^�c�ψ���v�̈ӌ����ĊǗ��K�����߁A�K���Ō����I�ȗ��p��}�邱�ƂƂ��ꂽ�B
�@�H���͏��N�x�i�T�P�N�x�j�b��I�ɎR��n��i�`��j�ɂ����ĂW�g���^�ٌ`�u���b�N�ɂ�闣�ݒ�S�V���[�g���̒z�݂��s��ꂽ���A�T�Q�N�x�ȍ~�͍��ُ̋k�����̉e���ƁA���ƌ��ʂ̊m�F������ł���Ȃǂ̗��R�ŁA�S�̌v��̂Ȃ��œ˒�S�O�O���[�g���̒z�݂����~�߂�ȂǁA�v��ύX���Ȃ��ꂽ�����łT�T�N�ɎR��n��̍H�����I�������̂ł���B
�@�Ȃ��A����n��i�a��j�ɂ��Ă͎R��n��̎��ƌ��ʂ̒������s�����߁A�ꎞ�x�~�Ƃ����[�u������Ă��邪����̎��{�����҂���Ă���B
�@�T�T�N�x�܂łɂ�����S�̌v��ɑ��鎖�Ǝ��т͏�\�̂Ƃ���ł���B
�@��P�P�߁@���Y�c�̂̕ϑJ
�������Ƌ����g��
�@��S�ߋ��Ɛ��x�̉��v�ŏq�ׂ��Ƃ���A�����ɂ�����e���Ƌ����g���́A�����ȗ������ނ˓����悤�Ȍo�܂ɂ���Č��݂Ɏ����Ă���B�������Ƌ����g���́A���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j���������ɂ���Ĕ��_���̍s�����ƂȂ������A�g�����NJ�������ɂ��Ă͏]���ƑS���ς��͂Ȃ��B�Ȃ��A���������̖����ƒ������������̖����͎��̂Ƃ���ł������B
�@���a�Q�S�N�X�����������i����͑g���������j
�@�����@�����K���Y�E�{�Ë���E�ؑ��m���Y�E���ؖΒj�E���c�����Y�E�e�n�[�Y�E�V�쓿���E���J�K���Y�E��c�e���E���q��s
�Ď��@�����E�˂̍�T��E�����O�O�Y
���a�R�Q�N�������������i���O�j
�����@�����K���Y�E�e�n�g���E�˂̍�T��E����v�E�{�Ë���E���X�ؑ����Y�E��ؐΑ��Y
�Ď��@���c�ےj�E��R���x�E�����s�j
�g���������̐���
�@���a�P�O�N�i�P�X�R�T�j�P�P���ɋ�����������̎ߌ������ɂ��������������A�����W�U�Ԓn�i�����\���X����l�։���r���̍����j�ɐV�z�ړ]���Ă���A���Ɖ�A�V���Ƌ����g�����o�ĉ^�c�𑱂��Ă������������́A�������̘V�����ƂƂ��ɗ������`�C�z�H���̐i�W�ɂƂ��Ȃ��A���a�S�R�N���`�w�ʂ̌��ݒn�i�����T�X�Q�Ԓn�j�ɐV�z�ړ]�����B
�@���Ȃ킿�A�Ɩ��̉~���ȉ^�c�������邽�߁A��ꎟ���ƍ\�����P���Ƃ̈�Ƃ��āA�������`�Ɋ֘A����u���g�J�{�ݐݒu���Ɓv�����{���A�����T�X�Q�Ԓn�ɓS�R���N���[�g�Q�K���ĂW�O�Q�E�R�U�������[�g�����H��Q�X�R�P���]�~�������Č��݂��A�Q�K��g���������ɂ��ĂĂ���Ɉړ]���A���̐��̊�b���������̂ł���B
�@�Ȃ��A���a�S�P�N�x���疳���ǂ̉^�c���J�n���A���Ƌ��D�Ƃ̘A���𖧂ɂ��Ȃ���C��h�~��}��A�C�ǂȂ�тɑD���Ǖ����T�m�@��ݒu���ċ@�\�̊g�[�ɓw�߂Ă���B
���Ǝ����@�@�@�i�P�ʁ@��~�j
| �N�x ���� |
�S�̌v�� | �T�P | �T�Q | �T�R | �T�S | �T�T | �݁@�@�@�v | |
| ���@�Ɓ@�� | ��~ �Q�C�R�O�O�C�O�O�O |
�V�Q�C�R�O�O | �Q�P�W�C�S�R�O | �R�R�O�C�O�O�O | �S�O�O�C�O�O�O | �P�V�S�C�W�X�O | �P�C�P�X�T�C�U�Q�O | |
| �S�̌v��Ɋւ��闦 | �P�O�O�� | �R�D�O�� | �X�D�T�� | �P�S�D�R�� | �P�V�D�S�� | �V�D�U�� | �T�Q�D�O�� | |
| �N���ʌv��ɑ��闦 | �@ | �P�O�O�� | �S�X�D�O�� | �V�S�D�O�� | �T�X�D�X�� | �Q�U�D�Q�� | �T�Q�D�O�� | |
| ���Ɨ� | ���ݒ� | �P�C�P�O�O�� | �i�b��S�V�j | �P�Q�O�� | �P�V�O�� | �P�W�R�� | �P�Q�V�� | �U�O�O�� |
| �ˁ@ �� | �S�O�O�� | �| | �| | �| | �| | �| | �| | |
�@�i�����Y�ێ����j
�������Ƌ����g���i�ʐ^�P�j

�@�������āA�g���{���̎��Ƃł���̔��E�w���E�M�p���Ƃ���Ƃ��āA���p���ƁE�����ƁE�ɐB�ی쎖�ƁE���ƊǗ����ƁE�c�Ǝw�����ƁE�C��h�~���ƁE���ώ��ƁE������Ǒ������ƁE���{�B���ƂȂǁA����ɂ킽�鎖�Ƃ����{���A�g�����̐����̌���ƌo�c�̈����}���Ă���B
�@����ɁA�g���N����w�l���̈琬�ɓw�߁A���ɕw�l���͏��a�R�O�N�ɔ����ȗ��A�������P��V�����^���̐��i�ȂǂɊ����Ȋ����𑱂��A�T�P�N�̑�R��S�������w�l���������є��\���ɂ����đS����Q�ʂ̉h�_���l�����A�܂��A���Y�Ɣ��W�ɐs���������J�ɂ��A�T�P�N�x�k�C���Y�ƍv���܂������Ƃ��ď��߂ē������M�p�����̗�ؔ~�q�ɑ���ꂽ�B
�@�Ȃ��g���́A����Ɖh�l�̗��n��Ɏx����ݒu���A�n�拙���̗��ւ�}���Ă���B
�@�����S�O�N�R�����Ɩ@�ɂ�闎�������Ƒg���ɉ��g�ȗ��̗��g�����i��j�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�����Î��Y�E��R��V��E�X�䔼���F��E�{��c�g�E�����O���Y�E���J���n�E�{��玟�Y�E�ґ�����E�{���G�g�E���K���Y�E�e�n�g���E���X�ؑ����Y�E�e�n�L�E�q��E���c���Y
�R�z�����Ƌ����g��
�@�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�P���R�z�����ɔ��ٌ��R�z�S��\�O�g�R�z�������Ƒg�����g�D���ꂽ���Ƃɂ͂��܂�A���̌�u�R�z�������Ƒg���v�A�u�����ӔC�R�z�����Ƌ����g���v�ƕϑJ�����ǂ�A���a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�Q���ɔ��ٖ{���R�z�w�O�Ɏ�������V�z���A�g�����̒n�ʂ̌���Ƒg���Ɩ��̉^�c������}�����B
�@�����A�����푈�����Ȃ�ł������킪���́A���a�P�V�N���꒬���ɂ���Q�ȏ�̋��Ƌ����g�������Ă��̋K�͂��g�債�A�e��{�݂̐ϋɓI���~���ȉ^�c��}�邽�߁A���_�E�R�z�����g���̍����ɂ��Ă��̋���v�������B���̍��ƓI�ȗv���ɑΉ����āA���g���͏I�n�~���̂����ɋ��c��i�߁A�킸���Q��̉�������č������邱�ƂɌ��肵���B�����ė��g���͓��N�P�O���Q�S���ɑ�����J�Â��A�����v���������c�A���g�����A���ɂ��\���̌��ʁA���P�W�N�P���Q�O���������ĔF���ꂽ�̂ł���B�������A���̍����͋z�������ł������̂ŁA�R�z�����Ƌ����g���͂Q���S���ɉ��U�o�L�̂����������_���Ƌ����g���Ɉ�̎��������p�������������B
�R�z���Ɖ�̕���
�@���a�P�W�N�ɐ��Y�ƒc�̖@�̐���ɂ��A�����ӔC���_���Ƌ����g���͉��U���A�P�X�N�R���P�����_���Ɖ�Ƃ��Ĕ��������̂ł���B���̂Q�P�N�P�O���V���A�����ɍ���̗v���ɂ���Ĕ��_���Ɖ�ɍ��������������ӔC�R�z�����Ƌ����g���n����̋����P�Q�R���͘A�����āA����̈��]�����ɂ�����R�z���Ɖ�̓Ɨ���ؖ]����̂ŁA���₩�ɑ�������W���Ăق����Ƃ����������ɒ�o�����B
�@���������v���Ɋ�Â����_���Ɖ�ł́A���Q�Q�N�R���W�����番����O��Ƃ��ċ��c��i�߁A����ɂƂ��Ȃ����Ɖ�̋��E���ƌ��̏����E�s���Y���̑����Y�̏������@�Ȃǂ̕��j�����肵�A���N�T���Q�O���ɗՎ�������J���ĉ��ύX�i�u���_���m���j�˃��v���u���_�� �厚���_���y�厚�R�z��������O�m���j�˃��v�Ɖ��߁j���A�\���̂������N�V���P�O���ɔF�����B����A�R�z�ł͋��Ɖ�ݗ��̏�����i�߁A�Q�Q�N�R���T���ɑ�����J�Â��u�R�z���Ɖ�v�̐ݗ������c����ƂƂ��ɁA���c�|�O�Y�̂ق�������I�o���ĔF��\�������B����ɂ���ĂV���Q�R���F�ƂȂ�A�W���U���ɓo�L���������ĎR�z���Ɖ���������̂ł���B
���_�E�R�z�������Ƌ����g���̍���
�@���a�R�Q�N�ɗ������Ƃ̒��������ɂ���āA�����ɂ����鋙�ƒc�͔̂��_�E�R�z���E�����̎O�����ƂȂ�A���ꂼ�ꂪ�Ɨ����ĐM�p�E�̔��E�w���̎��Ƃ����{���Ă����̂ł���B�������A���Ƃ̐��ނ͂�����Ƃ����������A�e�g���Ƃ����z�̕�������A�����̌Œ艻�ƌ������̗ݑ��̂��߁A�o�c�ɍs���l�܂�𗈂��Ă����B
�@���̂悤�ȓ�����w�i�Ƃ��āA��苭�͂Ȍo�c��Ղɗ��g���̈琬��}�邽�߁A�R�T�N�S���ɐ��肳�ꂽ�u���Ƌ����g���������i�@�v�ɂ���āA�����I�Ɏア��Ԃɂ��鋙���̍�����肪��N���ꂽ�̂ł���B
�@���Ȃ킿�A���Ƌ����g���͂��̌o�ώ��Ƃ�ʂ��đg�����̗��v��i�삷�������S���Ă�����̂ł��邪�A�g�������̋@�\�����x�ɔ������邽�߂ɂ́A���������Ƃ��đ��p�I�Ȍo�c���ɂ��o�ϑ̐��̊m���������ƂƂ��ɁA����Ɍo�c�̓K���K�͂��m�ۂ��Čo�c�\���̌����}��K�v�����v������A�܂��A�����ƐU���̒S����Ƃ��Ă��d�v�Ȗ����������A���ƌ��Ǘ��A����C�z���͂��ߍ��E������ђ��ȂǂƖ��ڂȊW�������Ă���Ƃ��납��A�g���̒n��ƍs�����Ƃ̊W���l������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������̂ł������B
�@������̂ق��ɂ������ɂ�郁���b�g�͐�����������ꂽ���A���������̎O�������O�q�̂悤�ɍ����I�Ȉ��������ɂ������Ƃ��������A�S�g���̍����������ۑ�Ƃ���A���͂ȑg���̐��̊m�������҂��ꂽ�̂ł������B
�@�����������Ƃ���R�U�N�P�O���A�O������\�҂ɂ�鍧�k��J�Â��ꂽ�̂���ɁA���P�P���P�T���ɂ��̐\�����킹�Ɋ�Â��āA���E���c���\�Ȃ�тɎO�����������W�܂�A�����Y���Ɠn���x���̌W�����獇���̕��j��K�v���ɂ��Đ��������B���̂��ƍ����̐i�ߕ��ɂ��ċ��c���s�������ʁA�Ƃ肠�������_�E�R�z����������ΏۂƂ��鍇�����i���c���ݒu���邱�ƂƂ��A�c����������ɁA������ђ��c���\�P�Q���A���_�E�R�z����������\���ꂼ��P�S������Ȃ�u���_�����Ƌ����g���������i���c��v���������B�����ĂP�Q���P����P�c����֍Â��A�����ɂ��Ă̌�����������і��_�̔c���E��|�̕��y�E���ƌv��Ȃǂ̋��c���n�߂�ꂽ�̂ł��邪�A�P�Q���Q�V���ɂ͒m�����痼�����ɑ��A�����̕s�U�𗝗R�Ƃ��č�������������t���ꂽ���Ƃ������āA���悢���̓I�Ȍ����ɓ������B�������A�������������ɂ͂����̂̍��������������č�Ƃ͓�q�������A�W�҂̔M�ӂƓw�͂ɂ�藂�R�V�N�R���ɂ͘b���������悤�₭�܂Ƃ܂�A�T�����ꂼ��̑g������ɂ����đI�o���ꂽ�ݗ������ψ��ɂ���āA�V�g���ݗ��̏������i�߂�ꂽ�B
�@�������ė��҂̋��c���������A���_���w�Z�̈�قɂ����ĐV�g���̐ݗ�������J���A�R�V�N�W���P���������āu���_�����Ƌ����g���v���������邱�ƂɂȂ����̂ł���B�g�����͐��g�����S�R�R���A�y�g�����R�U���ł���A�V�g�����ɂ͑O���_�����g�����̖ؑ��O�삪�A�C���A�R�z�ɂ͓����̊ԓ������R�z�x����u���A�n�拙���̗��ւ�}�����B
�@�吳�W�N�T���ɎR�z�������Ƒg���Ƃ��Ĕ����ȗ��A���x�̖��̕ύX���o�����Ɛ펞���Ɉꎞ���f�������̂́A����ɕ������ĎR�z�����Ƌ����g���ƂȂ����̂ł��邪�A���̍����ɂ���ď��ł���Ƃ����o�߂����ǂ����̂ł���B���̊Ԃɂ�������g�����i��j�͎��̂Ƃ���ł���B
�@��쐷���E�|���C���Y�E���J�h��E��R�[���E�|���C���Y�i�āj�E��{�L���Y�E������O�Y�E��c�|�O�Y�E�������v�E��c�|�O�Y�i�āj�E�������v�i�āj�E�X�Α��Y�E�|�쏲�E�l�c�씪�E�V�앐�Y
���_�����Ƌ����g��
�@���_�������̉��v�ɂ��ẮA�ꕔ�f�ГI�Ȃ���u���Ɛ��x�̉��v�v�̐߂ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�����P�V�N�T�����ٌ��̕z�B�ɂ���ċ��Ƒg����Ⴊ���肳��A�P�W�N�P���u���ٌ��R�z�S���_����\�l�g���Ƒg���v�Ƃ��č�������킹�đg�D���ꂽ���Ƃɂ͂��܂�B���̌�A�����ɂ킽�鋙�Ɩ@�̉��p����Ɋ�Â��u���_�����Ƒg���v�E�u�����ӔC���_���Ƌ����g���v�E�u���_���Ɖ�v�E�u���_���Ƌ����g���v�ȂǂƁA���̂�g�D�̕ύX���s���Ă������A�����I�ȓ��e��@�\�ɂ͒������ω��͂Ȃ������B���a�R�V�N�W���P���ɎR�z���Ƌ����g���ƍ������u���_�����Ƌ����g���v�Ƃ��ĐV���������������Ƃ͑O���ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@�����ӔC���_���Ƌ����g�������A�܂菺�a�P�O�N�i�P�X�R�T�j����͒�������Ɏ������������Ă������A�P�Q�N�P�Q�������i���݂̓����J�g���b�N����j�ɂV�U�i��Q�T�P�������[�g���j�̎�������V�z�ړ]���đg���^�c�̋�����}�����B���̌�A�P�W�N�ɎR�z�����Ƌ����g���ƍ����A���N���肳�ꂽ���Y�c�̖@�ɂ���ĂP�X�N�Q���ɉ��U�𖽂����A�R���ɂ͔��_���Ɖ�Ƃ��āA�펞���̍���ɑ������鐅�Y�c�̂Ƃ��Ĕ��������B
�@���a�Q�O�N�A�����m�푈�̏I���ƂƂ��ɐV���Ɩ@�����肳��A�V���ȋ��Ɛ��x�ɂ���āA�Q�S�N���Y�Ƌ����g���@�Ɋ�Â��u���_���Ƌ����g���v�N�S���R�O���ɑg�����Q�T�P���������Đݗ����A�g�����ɕđ�E���A�C�����̂ł���B
�@�g�����đ�E�́A�����K�͂ȋ��Ƃ��o�c���A���̊ԋ��J�E�����Ɛ������̎{�݂̉��P���s���A���ɋ����ɂ�����g�������𐄐i���A���a�P�O�N�����ӔC���_���Ƌ����g�����Ƃ��ďA�C�ȗ��P�V�N�]�A���̊ԑg������̈�̋��^�����ނ��āA�����o�ς̍Č��Ƌ��������̈���̂��ߐ�O���Â����̂ł������B
�@�Q�S�N�U���ɂ͖k�C�����Ƌ����g���A����̉�ɑI�C����A�����A�̌��Ē����ɂĂ��g���̂Q�U�N�P�Q���A�a�̂��߂ɋ}�������̂ł��邪�A���̌��т͉i�������̂�������Ƃ���ł���B
�����������̐V�z
�@���_�����ł͎������𓌒��ɁA�N���ׂ�������{���i���A���h�{���~�n�j�ɒu���ċƖ����^�c���Ă������߁A���ɕs�ւ��������Ă������A���a�R�U�N�ɖ��꒡�ɂ��V�z���ꂽ�̂��@��ɋ����Ɍ���������A�ׂ������̓������������Ɍ��݂��Đ��Y��قƖ��t���A���N�P�Q���Ɏ��������ړ]���Ĉ�̓I�ȊǗ��^�c��}�����B
���_�����Ƌ����g���i�ʐ^�P�j

�@�������A�S�P�N�ɂ͒��ɂ����ď��h�{�����ɂ̌��݂��v�悳��A�܂�����A�g���ł́A���_���`�����̎��_�ɂ����Ď���������ѕt�����������`�t�߂Ɉړ]����K�v���ɔ����Ă����Ƃ��ł����������߁A���҂̋��c�ɂ�萅�Y��قƉׂ������̑S�~�n�ɏ��n���邱�ƂɌ��肵�A���N�P�O���ɐ��Y��قَ̕����s���A���_�w�O�̓��{�ʉ^���_�x�X�̂Q�K����ĉ��������ɂ��Ă��̂ł���B
�@���a�S�Q�N�T�����Y���̌��ʒu�ɁA�S�R���N���[�g�Q�K���Ă̎��������͂��߁A�ׂ������E�q�ɁE���X�ɂȂǂ̌��z�ɒ��肵�A�P�O���P�T���ɗ����j�����s���Ď�����������Ɉړ]�����B���̌�����X�Ƌߑ㉻�ݔ��𐮂��Ȃ��猻�݂Ɏ����Ă���B
�@�吳�W�N�U���ɔ��_�����Ƒg���Ƃ��Ĕ����ȗ��̗��g�����i��j�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�Ñ��E����K�O�Y�E�đ�E�E���{���V���E���c����E���J���L�E�ؑ��O��
���Y���H�����g��
�@���a�R�O�N��㔼����ɂ킩�ɋ��l�����������͂��߂������n�����h�X�P�g�E�^���h�Ɋ֘A�������H�Ƃ��c�ނ��̂�����ɑ������Ă����B�������A�������H�Ǝ҂͎��R�����I�Ȃ��̂ŁA���ޗ��̎d����A���i�̔̔��A���Z����Q��蓙�X�A���Y���H�Ƃ̓��ʂ�����ɂ��ẮA�e�����ꂼ��ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���Ԃł������B������������ɂ�����H�Ǝ҂��A����狤�ʂ̏����ɂ��ċٖ��ȘA�g��ۂ��Ȃ���A���݂̗͂����W���đΏ����A���̐U����𑣐i���邽�߂̑̐��Â��肪���}�ɕK�v�ɂȂ��Ă����B
�@���̂��߁A���a�S�V�N�T���R�O���u���_�n�搅�Y���H�U�����c��v���������A�����ǂ����i���Y�ہj���ɐݒu���ċ����̐����ێ����Ȃ���A���̋�̉��ɂ��Č�����i�߂��̂ł���B���̌��ʁA�g�����̑��ݕ}���̐��_�Ɋ�Â��K�v�ȋ������Ƃ��s���A���̌o�ϓI�n�ʂ̌����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�S�W�N�P�P���U���u���_�n�搅�Y���H�����g���v��ݗ�����Ɏ������B���̑g���͒�����Ɩ@�Ɋ�Â����Ƒg���ŁA�X�P�g�E�^���E�z�^�e�L�E�C�J�Ȃǂ̐������H�𒆐S�Ƃ��鋤�����Ƃ̎��{��ڎw���A�����̉����Ґ��P�Q���A����g�����ɏ��؏����Y��I�C���Ĕ��������B
�@�����܂��g���̌��S�Ȕ��W�����҂��āA�S�W�N�x����T�R�N�x�܂ł̌܂��N�ɂ킽��A���N�x�g���^�c��̂��悻�Q���̂P��⏕���ĉ~���ȉ^�c�̏����ɓw�߂��B�������T�O�N��ɓ����Ă���A�吻�i�����ł���X�P�g�E�^���̋��l���A�؍����D�̕��Θp�����d���Ƃ̉e�����ċ}���Ɍ������͂��߁A���H�Ǝ҂ɒ��ڑ傫�ȑŌ���^���A�g�������T�R�N���łW���Ɍ������ĕK�����������̐��ʂ�������Ɏ���Ȃ������Ƃ����邪�A�₪�đg�����̑��ݕ}���Ɠw�͂ɂ��A���Y���H�Ƃ̐U���Ɋ��H�����o���A���S�Ȕ��W�Ɖ^�c��}���邱�Ƃ����҂���Ă���B
�@���g�����͂T�Q�N�U���ɏA�C�̍��X�ؗ⎟�Y�i���ځj�ł���B
���̑��̐��Y�Ƒg��
�@�ȏ�̎O�����̂ق��ɏ��a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�R���ɔ��_�����̋����ɂ������u���Ǝ҂̂����Q�V�����A���ߑ��Y��g�����Ƃ��āu���_�������Ƌ����g���v��ݗ������̂��͂��߁A�S���ɂ͍������v��g�����Ƃ���u�R�z�����Ɛ��Y�g���v�A���Q�U�N�U���ɂ͍�c�|�O�Y��g�����Ƃ���u�k�m���Ɛ��Y�g���v���ݗ����ꂽ�B
�@�܂��A���H�Ǝ҂̑g���Ƃ��Ă��Q�S�N�V���ɑ��c��Y��g�����Ƃ���u�R�z���Y���H�Ƌ����g���v���ݗ����ꂽ�̂ł��邪�A�����̑g���͂�����������Ƃ̐��ނƂ��������̂��߁A���Ɍ���ׂ����т��Ȃ��܂ܒZ���Ԃɏ��ł��Ă������B
��S�́@����
�@��P�߁@�����ȑO�̏���
�ꏊ����̌���
�@�����ȑO�ɍs��ꂽ���s�ׂƂ����A���O�˂���m�s�n�Ƃ��ďꏊ�����^���ꂽ�ˎm���A���̏ꏊ���̃A�C�k��ΏۂƂ��čs�������ՁA���Ȃ킿�A�m�s�傪�u����v�Ə̂��ăA�C�k�̗~��������E�����Ȃǂ�A���̓���Ƃ��Ă��܂̔�E�R���u�E�����ȂǁA�ڈΒn�̎Y����Ԃ����@�ɂ��n�܂����B�������A�����������m�̏��@�͍]�˒����ȍ~�ɍs���l�܂���������A�₪�Ēm�s�傪��������l�ɐ������킹�A�����h�^����h��[�߂����Ďx�z�m�s�n�Ɋւ��錠���`���̈���ϑ�����Ƃ����u�ꏊ�������x�v�̔����ƂȂ����̂ł���B���������āA����珤�l���ꏊ�����l�A���l����̒��������^����A�����Č��Ղ̏ꏊ���^�㉮�Ə̂����B���̉^�㉮�́A�m�_�I�C�E���E���b�v�E���}�R�V�i�C�E���i�V�x�Ɍ��Ă��Ă����L�^������A���̂���̉^�㉮�ɂ͏�Z������̂��A�܂��A�A�C�k�ِ̌l���Ȃ��A���Ղ��ςނƃR�^���̒��ɂ�����a���ċA�������Ƃ����Ă���B
�@�������A�ꏊ�����l�͗�����Nj����邠�܂�A�A�C�k�ɑ��Č��Օi�̂͂���ڂ⏡�ڂ����܂�������A�e���i�����Ȃǂ̈����������A����ɂ����̕s�]���āA�ڈΒn�����̑O�r�ɂ��s����������悤�ɂȂ����B
���{�̒��J��
�@�����P�P�N�i�P�V�X�X�j���當���X�N�i�P�W�P�Q�j�Ɏ����O���N�A���{�͂����̈������������A�A�C�k�̕��i�ԁj��Ɩk�ӌx�����������邽�߁A���ڈΒn�����A����������������p���Ē��J���Ƃ����B���������āA�Ԃ��Ȃ������ƂȂ����������i�̂����R�ǁj�܂ł͕ʂƂ��āA�R�z���ȓ��ɂ�����ڈΒn�̏��s�ׂ͂��ׂĊ��c�ōs���邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A���{���ڈΒn�ɕK�v�ȕāE�݂��E���̑��̏��i������A������n�̉�ɗA�����ăA�C�k��o�Ґl�ɋ������A�ڈΒn�̎Y���͖��{����������Ď����A��A���قȂǂŔ��肳�����B
�@���̂������{�́A�A�C�k�̕������`�Ƃ������߁A���Օi�̑���͏]���̊��K�ɏ]�������̂́A�͂���E���ڂ𐳊m�ɂ��A�e���i��r�˂��邱�Ƃɓw�߂��B����ɁA����܂ł̕��X�����̕��Q�����߂邽�߁A�����P�P�N�ɑK�ꖜ�ѕ����]�˂�����Ēʗp�������B���̂��Ƃ́A�ڈΒn�ɂ�����ݕ��ʗp�̎n�܂�ł���Ɠ����ɁA������肪���m�ɂȂ�A�����ăA�C�k�ɋΌ����~�̋C����{�������Ɠ`�����Ă���B
�R�z���ꏊ�̌i��
�@�]�O�́u���E���b�v�ꏊ�v�́A���{������Ɂu�R�z���ꏊ�v�Ɖ��̂����ƂƂ��ɁA�R�z���ɉ���݂����A�ʍs�l�̎�`���ߏ�������֏����u���ꂽ�B
�@�܂��A���̏ꏊ�̎Y���͎�Ƃ��ĊC�Y���ł����āA�����S�N�i�P�W�T�V�j�́u�ڈΎ��n���l�^�v�ɂ��A
�@�@��̓�ɓy��\�o�V��Ɨ��o����n����A�t�����X�ߔN����ɋ���X
�Əq�ׂĂ���ق��A���D�������������Ƃ��L����Ă���A�N�X�ɐ������������Ƃ��m����B���������āA���̂���͋��Ƃ�����ɂȂ�ɂ�Ęa�l�̉����������Ȃ�A�R�ǂ���R�z����ɂ����āA�����̐l�X���h��������h�����ł��A���X�������Ă��������̂Ǝv����B���̂��Ƃ́A���������S�N�̏��Y���l�Y���u���ڈΓ����v�ɂ��A�����֒��C���Ƃ��v���邪�A
�@�R�z����
�@�L�����̐��k���l��̖��t�̍��i�����k�݁l��_�{�����Օ��j�Ɛ`���ہi�n�^�m�A���L�j�����ꂵ���A���͌����̂����ߖ��܂Œ��X�i�`�����j�E���Ɂi�n�^�S���j�E�]�ˑO�Ƃ���@�����H��i�j�E�����j�����сA�z�Ƃ��ւ�y���i���V�����j�����͔w繡�i�c�d���j�@�̎h���i���W���j�Ɉ����ցA�������k�ȁl�ɉ����̋q�������A����ɏ��̒n�ƂȂ�A���ɏ����̌��̌��������ꂯ��B
�Ƃ����āA�����̏�i�������c���Ă���B
�������̌i��
�@�������̑O�g�ł����c�Ǐꏊ�̖��m�ȉ��v�ɂ��Ēm���|����͂Ȃ����A�ꏊ�̊J�݈Ȍ�A�������̏ꏊ�����l�̎���o�Ȃ��狙�Ƃ𒆐S�Ƃ��Ĕɉh���A�R���u�͂ЂƂ��뒷��U���Ƃ��ċߍ]���l�̎�ɂ���ėA�o���ꂽ���Ƃ�����قǂŁA�a�l�̏o�Ғ�Z�҂����R�ɑ����Ȃ�A���O�n������a�l�n�ƍ��ق��Ȃ��قǂ܂łɔ��W���Ă����B
�@�����P�T�N�Q���P�W���t���ِV���́u���g�ȑO�����S�e�����v�i���E�������v�Ƃ��āA�������N�X�ڏZ�l�������߈��i�T�N�i�P�V�V�U�j���c�̏���߂ė�������{���Ƃ���c�����x���Ƃ��B�ڏZ�l�̑����͐m�O�E�F���苙�Ǝ������؎�邽�ߎ��n���i�͉ߔ����l�ɔC���B
�ƕ��Ă���A�������ŏ��̈ڏZ�҂ł��鑊�ؐm�O�E�F��́A���i�N�Ԃ��łɑ�������̎��͎҂ƂȂ�d���e���ƂȂ��Ă����B
�@�����P�P�N�i�P�V�X�X�j�ɖ��{�����ڈΒn�����Ē��J���̐�����Ƃ����Ƃ����A�ˈ�̏��������c�ǁi�R�ǁj�܂ł٘Z���ꏊ�Ƃ��A���X�N�̋��a���N�i�P�W�O�P�j�ɂ͏ꏊ���x��p�~���đ����Ƃ��Ď�舵���A�R�z���ꏊ�ȓ��Ƃ͑S���قȂ��舵�����邱�ƂƂȂ�ƂƂ��ɁA������l���������A���ł����ۂ���邱�ƂɂȂ����B
�@�܂��A�������͋��a�R�N�ɖ��{����߂��s���ɂ���āA�h�̖ƎR�z���̏h���n�_�̒��Ԓn�_�Ƃ��Ē��x���E�n�p���Ɏw�肳��Ă����̂ŁA����ɂƂ��Ȃ����c�̈��H�X���͂��ߗ��ɂ⏤�X�Ȃǂ��A���R�ɊJ�Ƃ����悤�ɂȂ������̂Ɛ��@�����B
�@�O���Q�N�i�P�W�S�T�j�̏��Y���l�Y���u�ڈΓ����v�ɂ́A
�@�������@�]�h�ؑ��O���Ƃ��ւ�B�l�ƌ\���v�B���ΐl�\���l�A�����l�܁A�Z���A���ĉ�����B�������L�B���҂̂ݖ�B�����̑O�}���D�����������B�����͖�c�Ǒ��̉�������ɂ����ď����x�z����Ȃ�B�ꏊ�ΔԂ̏O��艺��Ƃ��ɍ����ɂĒ��т��B�F����h�܂ő���z����B�n�p����B�����ɉY���D�L�B�c�c�����c�c
�@�������Ɉ��̋W����B�����Ёi�J�}�n�o�L�j�Ɖ]��B�����y�Ĕ��ٕӂ��o�҂ɗ����B�c�c�㗪�c�c
�ƋL���Ă���B
�@�܂��A������������S�N�i�P�W�T�V�j�́u�ڈΎ��n���l�^�v�Ɓu㥗L���L�v�ɂ���Č���ƁA
�@�����͍L艂ɂ��ė��y��B���Ɛ��Ȃ�B�̂ɋt������B�������������B�i���O�ҁj
�@���I�C���Ɛ��O�\���A�������Ȃ��x��������������A���w�����֒u���悵�Ȃ�B�@�k�H���͉ԑ���A�t�ďo�Ґl�ɑ��ɂ͈ꕪ���Ȃ�Ƃ��ӁB�g���̌X��ɓ����@���Ȃ�B�v�i����ҁj
�Ƃ���A�x���̗R�Ǖ��ʂ܂Řa�l���������荞�݁A�������Ȃ��Ă������Ƃ�����������B
�@�Ȃ��A���X�̋�̗�Ƃ��ẮA�����U�N�ɔ��ق̏��l�{�엘�O�Y�̎��j��g���A�����ɓX�܂�݂��C�Y�≮���c�ޖT��A���l������Ώۂɖ{�i�I�ȓ��p�i�G�݂�n�߂��̂��A���̒n���ɂ����鏤�X�̏��߂ł���Ƃ����`�����Ă���B
�@��Q�߁@����ƊJ���n�̏���
���𒆐S�Ƃ���w�̑̐�
�@�����P�P�N�i�P�W�V�W�j�ɊJ�ꂵ������ƊJ��������́A�ڏZ�҂̐����Ɖc�Ƃ̗��ւ�}�邽�߁A���P�Q�N�T���ɂQ�T�U�~�̔�p�𓊓����āu���v�P���i�R�Q�j��V�z�i������O�ɂQ�K���Ă�V�z�j���A�ڏZ�҈ꓯ�̋��L�Ƃ��Ė��������B������̔��͒P�Ȃ�q�ɂł͂Ȃ��A�ڏZ�҂������K�v�Ȑ����E���Y���ނ̋����Ɛ��Y���̔̔���ړI�Ƃ���w�̎{�݂ŁA������������A�Ɛg�̈ڏZ�N���������Z���Ă��̎����ɏ]�����Ă����B�����āA���̔��Ŏ�舵���Ă����_�@����c�Ȃǂ̐��Y���ނ��͂��߁A�āE�݂��E���傤��E���Ȃǂ̐����K���i�₻�̑��̓��p�i�́A�J���n�ψ����d���ꑊ���^���̎����Ȃǂ̗v�����������āA�K���Ȏ����Ɉ��ɔ�������Ă����A�ڏZ�҂̊�]�ɉ����ĕ����������̂ł���B�܂��A�����E�����i�܂���j�i�����Ƃ��炭���Ō�D�����z�j�E�������̑��̔̔����ɂ��ẮA�ψ������قⓌ���Ȃǂ̑���ׂĔ̔��ɓK���Ȏ���������߂đ��o�������B����ɁA���p�Ƃ��ĕK�v�Ȃ��̂͂Ƃ߂Ĕ����グ���Ă��炤�ȂǁA���ׂĔ��ɏW�ג������A�L���ȋ����̔��ɓw�߂��̂ł������B
�@���̂悤�ɁA���͓����̊J���n�ɂ�����B��̕������ʋ@�ւƂ��āA�������Ƃ̂ł��Ȃ��������ʂ������̂ł���B
�@�Ȃ��A�������������̔������̌��p�����߂邽�߁A���ŏ��Ƃ��c��ł����������ˎm�̒��쏯���ɑ��A�����P�Q�N�T���ɓ���ƉƗߏ����V���Y���玟�̂悤�ȏ���𑗂�A���_�ɈڏZ�����l�X�̂��߂ɔ��قɈڂ��āA���ւ̕����̔[����Y���̔̔��ɗ͂�݂��Ă����悤�A���Ɉ˗�����Ȃǂ̎�i���u���Ă����B
�@���ʖk�C���V����?�n��艺���J���䎎���V�ׁA���m���m���L�u�V�Ҍ�ڂ��V���Ɍ�t���͈ڏZ�m���։v�V�ׁA�䎩���S�C�X���X�V�`���قֈ��ځA�{�ƔV�]�ɂ��ȂėA�o���֔̕ۓ��J��������S�C�V�҂Ƒ��v��l�Ƃ̌䎖�Ɍ�B
�@�˂Ă͍�n��㕕��s�͎���ړX��v�P�ύׂ͋g�c�m�s���\�q���B
�@�܌���\���
�@�����V���Y
�@���쏯���a
�@���̖��������쏯��́A���X�ɑ��̏��X�����������Ĕ��قɈړ]���A���Ƃ��c�ނ��������ւ̕����[���A���Y���̔̔��Ȃǂɓw�߁A�J��������̉^�c�ɋ��͂����̂ł���B�Ȃ��A���̒��쏯���������ɑ��������M�̂Ȃ��ŁA���ق��܂߂ē����̏�`������߂����ɏЉ�邪�A�Ƃ�������𒇉�Ƃ���`���Ȃ���A���ꂪ�J���n�ɂ�����{�i�I�ȏ��Ƃ̎n�܂�ł������B
�@�����O�Z�Z�{�l�蔃���\��A��\��K�ܗЁA�����K���ЂÂɌ����A�������ׂ̏�ׂ͖���ςɌ����A���`���p��͑������͂��Ȃ荂�l�Ɍ����A���ƂĂނ�݂Ǝ�����Ă͖����̎�ɂ͍s���s�\�A���������͒��X�����������Z�P�~���Ɍ����A�����E�l�Ƃɉ��Ă͊Ԉ�Ȃ��H�Ђ̂ݏ�͏o������A���l�ƂȂ�Α����̐S�z�L�V��Ȃ�B
�@�Ȃ��A���쏯���͔��ٍ`���甪�_�̕l�܂Łu�_���ہv�Ƃ������O�D�ʼn^���ɓ��������̂ł��邪�A�J��������ł͖����P�S�N�V���ɁA�P�W�V�R�~�P�T�K�̔�p�������Đ��m�^���D�i�R�T�g���j��V�����A�u���_�ہv�Ɩ��t���ĕ����A���̐�p�D�Ƃ��ĕ։v���͂������B
�@�������A�������������I�ȉ^�c�̔��ʁA�J��������ł͈ڏZ�҂ɑ��Ă��т��������������A���̔��͈ڏZ�҂̕K���i�������̂ł���ƂƂ��ɁA���Y���ɂ��Ă��K������ʂ��Ĕ̔����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă����̂ŁA�t�ɂ����A��������ł͔��ȊO�̗��ʋ@�\���萶����]�n�́A�قƂ�ǂȂ������̂ł���B���Ȃ킿�A������ɂ����ẮA�c�ƁE�ݎE�ړ��E�J���E�i�s�Ȃǂɂ��đ����̐������������A�ᔽ�҂́u���_���J���\�������v�ɂ���ď��������Ƃ������̂ł������B�܂��c�Ƃɂ��Ắu�e�����Ӊc�ƃ����T�Y�B�K�Y�_�ƃg�{�\�g���ȃe�P�Y�v���ׂ����̂Ƃ��������A�u�ψ��m���i�N���j���H�ƃ��׃V�{��m��`���ڃ~�U�����m�n�����O���ԃj���V�Ĕƃj�y�x�o�ޏ�j���v�����̂Ƃ��Ă����B�����Ă���Ɂu���n���i�������y�r�������׃X�҃n�����ܓ��ԃj���V�Y�㉿�����w���[�V�����߃��˖��j�ӃZ�V����O�ƃj�y�x�o�ޏ�j���v����ꂽ�B���̂悤�Ɍ��d�ɐ���Ă������߁A�J���̏��ƂƂ��đ��Ɍ���ׂ����̂͑S���Ȃ��A�����B��̍w�̋@�\�Ƃ��Ă̑��݂������킯�ł���B
���_��������ւ̈ڍs
�@�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�ɓ���ƊJ���n�ł́A�ڏZ�҂̓Ɨ����c�̊�b���ł߂邽�߂ɁA�����x�����v���ĈڏZ�l�ɑ�����O�̒��ڕی��p�~���邱�ƂƂ��A����܂Ŕ��ōs���Ă����w�̐��x���p�~�����B�����Ă���ɑウ�A�����ɂ��u���_��������v��ݗ������A����ɕ⏕��^���ĉc�Ƃ����邱�ƂƂ����B
�@���̏���̉c�Ɠ��e�́A�u�_�Ɠ���m���p�i���̔��V�A�y�r�_�ƃj�Y�o�X�����m�������i���傤���j�i�����肤��j�X������Ɓv�Ƃ������A�ق��Ɏ萔��������Ĉϑ��̔�������A�����ɉ����Ĕ���������s���A�܂��A�_�Y����S�ۂƂ��ĂU�����ȓ��̒Z�������݂̑��t�����s�����B
�@�������A����Ƃ͏���ɑ��āu�n�������Z���N���v���m�z���ʁA��P�N����j���^�U���g�L�n�����j�V���閘�m�s���z���⋋�v���邱�ƂƂ�������łȂ��A���فE���_�Ԃ̍q�C��ɑ��Ă��u�n�ƃ����O�P�N�Ԉ�P�N�ܕS�~�d�c�⏕�v��^���邱�ƂƂ��Ă����B�܂��A�_�Y�����������݂̑��t���A������я����D�Ȃǂ݂̑��t����ی���s���Ă����B
�@����̓���ɂ͊p�c�O�Ƃ������������A����Ƃ̕ی�ɑ��ď���Ƃ��Ă��A�u�ꃉ�J���n�m�։v���}���K�׃��j�J�݃X�����m�i���o�Ɩ��戵�葱�L�n�J���n�ēg���c�v�̂������肷����̂Ƃ��A�u�J���n�ē������ЋƖ��m�i�����q�l�A�y�r����m���{�������v��ꂽ�ꍇ�͒����ɂ���ɉ����A�܂��u���v�v�Z�n���P�N���j�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă����B�����āA�����芼����ыƖ��戵�葱����A�����̋`���Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ́A����Ƃ̕ی�𒆎~���܂��͔p�~����Ƃ�����߂ɂȂ��Ă����B
���_�������Аݗ��V�`�j�t��i�ʐ^�P�j
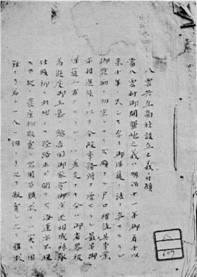
�@�������Đݗ����ꂽ����́A���ɑ����ĕ������ʂ̋@�ւƂ��ĈڏZ�҂̗��ւ�}��������łȂ��A���Y���̔̔�����p�i�̍w����ʂ��āA�ڏZ�҂̌o�ώv�z�����シ��������ʂ������̂ł���B�Ⴆ�Δ��ɂ����镨�i���������̏ꍇ�ƈقȂ�A�u���Ѓm�̔����i�n�s�e�������փj�V�e�v�ƋK�肵�A�݂��t���͋�����Ȃ������B�܂��A�����x�̔p�~�ɂƂ��Ȃ��A�����s��̎��ł��]���̂悤�ɕ��i�̕���������݂��t�����Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B���̂��߁A�ڏZ�҂̑��ݕ}���̑g�D�Ƃ��āA����܂ł̐ϗ����x�̂ق��ɁA�V���Ɉ�˓�����唞�P�U�A�ꂢ����Q�U�i�ꂢ����͂P�U�P�T�K�̊��Ŋ��Z�j��ςݗ��Ă����Ĕ��r���~�Ƃ��A�s���̍ЊQ�ɔ������̂ł���B
������Д��_����ւ̔��W
�@���_��������́A�����Q�P�N�i�P�W�W�W�j�@�P�Q���Ɋ���g�c�m��A���엊��̔��c�ɂ���ĂT�O�ӏ�����Ȃ�芼���쐬����A�V���Ɂu�L����Д��_��������v�Ɖ��g���ꂽ�B���̏���͌o�c�̊m����}�邽�߁A�J���n���┪�_�����Ɍ��炸�A�Q�T�N���납�痎���Ⓑ�����ɂ��̘H���g�����ė��v��}�������A�Q�U�N����͏���ɑ��铿��Ƃ̕⏕���ł���ƂȂ������߁A�V���ȑΉ��𔗂��邱�ƂƂȂ����B
������Д��_����芼�i�ʐ^�P�j

������Д��_����o������i�ʐ^�Q�j

�@���̂��߁A�L�u�̓w�͂ɂ�薾���Q�V�N�u������Д��_����v���T�����x�U�T�Ԓn�i���{�����P�Q�W�Ԓn�A���_�Y�Ǝ������t�߁j�ɐݗ������B�����Ė�c���ɂ��x�X�������A�_�Y���̔�����ϑ��̔�����ѕāE���E�݂��E���傤��E�엿�E�����E�����E����E�����E�_��E���p�i�Ȃǂ���L���̔����A��������̎��Ƃ��p���A����ɐϋɓI�Ȋg�����}��ꂽ�B�������Ƃ̕⏕�ł���Ɠ����ɁA����ɂƂ��Ȃ���X�̐�������������A�u�ꃉ�J���n�m�։v���}���K�׃��j�J�݁v����Ă������̂���A�����̗��v��}�邽�߂̑g�D�ɉ��߂��Ă�������ł���B
�@�������A�����̓���ƊJ���n���ŁA���H�X�E�����ƁE���l�h�E���̑������Ɋւ���Ƃ��c�ޏꍇ�́A�J���n�c��̋c����K�v�Ƃ��A�_�ƈȊO�̉c�Ƃ𐧌����镗�������������߁A���R�̂悤�ɊJ���n���̏��Ƃ͑傫���L�W���邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���B
�@��R�߁@���Ƃ̈ڂ�ς��
��������̏���
�@�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�ɐX�E�������Ԃ̍������S�ʊJ�ʂ������Ƃɂ���āA����܂ŗV�y���l�i���Y�����j�ɂ������R���̏h���i�V��c�E�����E�|���j���V�����̕��Ɉړ]���A���������ɑ������P���̂܂イ�����ł����Ƃ����B�܂��A����ƑO�サ�āA��炶�₽����X�Ȃǂ��ł��Ă��������A�Q�W�N���납��e�n�ɔ_�ꂪ�J�݂���A�悤�₭�ږ��̑�����������悤�ɂȂ�A�����̗����ɂ��V�����Ƃ����Ă��͂��߂��B���̂���͂��߂āu�����v�̂̂�����������A�Ԃ�����ǂ���邵���u�������v���ł��Ă����Ƃ����B�܂��A����ɑ����āu�䗿���v�Ə��������悤������邵���|�҉����ł�����A��ʏ��X�����X�ɂ��̐��𑝂��A�R�U�N�̓S���J�ʌ�͋}���ɔ��W�������A���̎���̏��X�̓����Ƃ��ẮA������u�Ȃ�ł����v�Ƃ�����`�̏��X�����������̂ł���B
�@���̂���ɔɐ��������_�s�X�̏��X��T���Ă݂�ƁA�܂��i�����P�j��c���X���������邪�A�����X�͓���Ƃ̎m���ږ��Ƃ��Ĕ��_�ɈڏZ������c���V�傪�^���Ƃ��c�݁A�ږ��ɕāA�݂��A���̑����p�i���������邽�߁A�Z�����ő�K�͂ȕč��G�ݏ����J�Ƃ��A����ɂS�S�N�{���Ɏx�X���o���Č��������X���o�c���Ă����B
�@�����Q�R�N�ɔ��_��������̎x�z�l�Ƃ��ĈڏZ���Ă������쏕���Y���A�R�O�N����V�y�����̂����ƂŎ��̏������n�߁A�u�V�y�쐳�@�v�u���_��v�Ȃǂ̖������o���Ďs��ɐ��������߁A�N�N���Ƃ��g�����Ă������B�܂��A�R�R�N�ɂ͔~�����\�Y���{���ʂ�ʼnَq�����Ƃ��n�߁A�R�S�N�ɂ͎������J�ƁA����ɁA�R�T�N�ɂ͌��������Èߏ����n�߂��B
�@�����̂ق��ɁA�R�P�N�ɂ́i�����R�j����K�O�Y���X���J�X���āA�āE�݂��E�G�݂Ȃǂ���舵���A�R�Q�N�ɂ́i�����S�j��֏��X���J�ƁA�R�R�N�ɂ͍��v�ԏȈꂪ���A�R�S�N�ɂ͗�؉i�g���~���Ǝq�X�̂��Ƃ��ĊJ�Ƃ��A�R�T�N�ɂ͉͍��⎟�Y�������Ƃ��n�߁A�R�U�N�ɂ͏�������X���J�Ƃ���ȂǁA�������ŏ��X���J�Ƃ���Ă������B
![]() ��c���X�i�Z�����j�i�ʐ^�P�j
��c���X�i�Z�����j�i�ʐ^�P�j

![]() ���쏤�X
���쏤�X

�~�������i���A��������X�j

![]() ��֏��X
��֏��X

����![]() ���ђ�
���ђ�

�@�������Ď���ɏ��X�X���`������Ă��������A���ɑ�֏��X�A��c���X�A���쏤�X�́A���_�̎O�古�X�Ƃ��Ă������A�����L���łɂ���������Ƃɑ��āA�d���݂��s�����̂�����قǂł������B
�@����ɁA�S�����J�ʂ����R�U�N�Ȍ�́A���X�͖ڊo�܂������W���Ƃ��A���]���E���_���Ȃǂ̌�����ł��A�|���E�k�J�E���c�E�V��c�E��{�E�F�J�E���쉮�i���݂̔��_�فj�E�|���E����Ȃǂ̗��ق��J�Ƃ����قǎs�X�n�͊�����悵�A�O��E�Ί_�E�n�ӁE��i���낪�ˁj�Ȃǂ̗����X���J�Ƃ��ꂽ�B�������Ĕ��W�𑱂��������̂ł��邪�A���̊Ԃ̂R�V�N�U���A�����ɉЂ��������ĂQ�X�˂��Ď����A�ێR���X�E��؉َq�X�E�����X�E��؈��H�X�E�V�����E�Ί_�����X�E�R�{�G�ݓX�ȂǑ����̏��X����Ђ���Ƃ����Ɏ�����̂ł������B
�@���_�̏��X�X�́A�ŏ��A�V�y�����t�߂̌������ʂ��甭�W�����̂ł��邪�A�S�����J�ʂ��Ă���͒��S�X������ɉw�̕��Ɉڍs�������̂ŁA���ݔɉ؊X�ƂȂ��Ă���{���ʂ�������͇��V�����ƌĂ�A���n�тʼn�����т��������ł������Ƃ����B�������āA�S���̊J�ʂƊe�_��̔��W�Ȃǂɂ���āA���Y���̎������A�����K���i�̍w���Ȃǂ������ɂȂ�A�X�܂��J�����̂����������B���܂����ŁA�����̏��X�����ׂċ����邱�Ƃ͂ނ����������A�َq�X����]��������؋����X�E�É͎G�ݓX�E����Ƌ�X�E�������X�������E������S�X�i�̂��Ɏ��]�ԓX�����Ɓj�E�a�����X�E�|�����X�E���J������X�E�x�䏤�X�E�ΐ엚���X�E���َq�X�E����S�H��Ȃǂ��A������������吳�����ɂ����ĊJ�Ƃ��ꂽ�B
�吳���̏���
�@������������吳�����ɂ����āA�ꂢ����ł�Ղ�̍D���������A�܂��A���Ƃɂ����Ă��j�V����C���V�̖L���Ɍb�܂�A�吳�Q�N�̋���������A���̌o�ς������ނˈ��肵�Ă����B���ɗ��R�N��ꎟ���E��킪�ڂ�������ƁA������̉e�����ĕ������������锼�ʁA�T�N�ɂ͂ł�Ղi���\�����āA��Y�n�ł��锪�_�͒�����������悵���B���������D���̉e�����āA���Ƃ��܂��}���ȐL�W�����������A���̂Ȃ��ő�c���O�Y���吳�S�N�i�P�X�P�T�j�ɏZ�����ł��傤�䐻���̔����J�n�A�܂��A���T�N�ɂ͔~�����\�Y�Ƌ����Łu������Д��_�q�Ɂv��ݗ����A�����K����q�ɂQ�������݂��đq�ɋƂ��J�n�����̂��ڗ������B���̑q�ɂ́A���̌�W�N�ɔ��_�M�p�w�����Y�g�����������Ĕ_�Ƒq�ɂƂ������̂ŁA���̂����̂P���������Ȃ����_���_�Ƌ����g���̑q�ɂƂ��Ėʉe���Ƃǂ߂Ă���B
�������X�i���A��ǁj����w���ʁi�ʐ^�P�j

�@����A�吳�U�N�Q���ɐݗ����ꂽ�u�L����Д��_�M�p�w���g���v�̍w�����Ƃ��g�������ɂƂ��Ȃ��A�_�Ƃ̍w���͂��g���ɏW�\���A�s�X�n�̏��X�X�͑傫�ȑŌ����邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A���V�N�ɔ~�����\�Y��L�u�̔��N�ɂ���āu���_���H�g���v��ݗ����A�Ǝ҂̋����ɂ��o�c���P�Ɗ�Ղ̋�����}�����̂ł���B�������A��ꎟ���E��킪�I������ƁA�ł�Ղi�̖\���ɂ݂���悤�Ɍo�ϊE�͋ɓx�̕s���Ɍ������A���������̑Ō������S�ɉ��Ȃ������ɁA�P�Q�N�X���ɂ͊֓���k�ЂɏP���A���炭�s�����オ�����A�₪�ď��a�����̋��Z���Q������}����̂ł��邪�A���H�g���͂悭�ƊE�̌o�c���P�A�g�����̗Z�a�����ɓw�߂�ȂǁA���̈������ɐs�������̂ł���B
�@���a�W�N�i�P�X�R�R�j�����̏��X�X�̗l�q�́A���̐}�T�悤�ł������B
���_���H�g�����i���吳�P�P�N�\�����a�P�Q�N�V���j�����Ă�����؉i�g�ØV�̘b�ɂ��ƁA
�@�u������O�N�i�P�W�X�O�j�Ƒ��ƂƂ��ɖ�c���ɔ_�ƊJ��҂̎��˂̓�j�Ƃ��ĈڏZ���Ă����B��c���̏ꏊ�͉w�O�̈������X�̏��ŁA���̂Ƃ������ȌK�̖����������A���ł͂��̌K�̖����܂��ڗ]�ɂȂ��Ă���B�_�Ƃ̓�j�V�Ƃ��Ẳi�g���S�����匙���Őe�����ł��锪�_�̔~���Ƃ����̖{�����ʏ��X�̏��ɂ���A�َq�����Ƃ�����Ă����W�ŁA�����𗊂�ɏ��l�ɂȂ����i�g�́A�������쏤�X����V�y������̏��ʼnَq�����c��ł������A�����O���N�Z�������̂��Ղ�̔ӂł������B���x�����̉Ƃ̗��ɂ������u�ۖ��v�Ƃ���������o���́A�̉�肪�����C�������Ƃ��ɂ́A���������̉Ƃɂ��R���ڂ��Ă��܂��Ă����B���h�c�ɓ����Ă����W�Ŏ����̉Ƃ݂̂�����邱�Ƃ��ł������h�ɑ������B���̂Ƃ��̉Ђɂ��Q�X�˂��Ď������B����͓����̔��_�s�X�̒��S�ŊJ���ȗ��̑�Ƃ����A���_�ɂƂ��āA�ŏ��ɂ��čŌ�̑�ƂȂ����̂ł������B���̑�͖k�J���ق��y������ł��������߂ɁA���̖҉�H���~�߂邱�Ƃ��ł������A���̓y�����Ȃ���Ύs�X�n�̑S�Ă��l����ꂽ�قǂŁA�Q�X�˂Ƃ����A�����̒��̖����Ă��Ă��܂������ƂɂȂ�B
�@���̐́A���_�̔��W�ƂƂ��ɂł������X�̂Ȃ��ŁA�{���ʂ�ɂ͌܌��̓X�����������Ȃ��ł���֏��X�͑�X�I�Ȃ��̂Ō��݂̑��O�ɂ������B�����\���M�Ԃ̉����ɂ͖������炢�̂��̂ŁA�Ȃ��ł����̓X�Ŕ���o�������_�Y�̂������蕲�͗L���ł������B���ł��{�B���ʂő܂����u���_�ЌI���v�Ƃ��Ĕ����Ă���Ⴊ����قǑS���I�ɂ��̖����͂��点�Ă������̂��B�������_�ɂ͎O�古�X�Ƃ����āA����K�O�Y�i�G�݁E�_�Y���j�E��c���O�Y�i�G�݁j�E���J��Ў��Y�i��֏��X�j���ɐ����Ă����B
���_�s�X�̔��˒n�i�����j�i�ʐ^�P�j

�@���_�������͔_�Y�����萶�Y�����B��̑��ɉ߂��Ȃ������̂ŁA���X���_�Ƃɕ��i��̔�����̂́A�t����Ăɂ����Ă̑ݔ��肪�قƂ�ǂŏH�ɐ��Z�����_�Y���̑���������Ďn�߂ĉ������Ƃ����������@�ł������B���̂��ߕs��ŋ����Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��N������A��J�͑��������B�_�Ƃŋ����������l�́A���X�ɋ���݂��ċ����Ƃ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă����l�̂����̂������Ȃ�ł͌����Ȃ��ł������B���͑�R���邪�엿������č앨���Ƃ�̂ł͂Ȃ��A�J���傾����������n�͌��݂̔������炢�ŁA�n�����҂����������B���ʋ��t�̕��͌i�C���悭�č��̔��̏�Ԃ������Ă����B�j�V����Ƃ��ėL���ȕl�����ɑ務�̂Ƃ��́A�q���̂Ƃ������������b�R�������ăj�V�����E���ɍs���̂��y���݂ł������B
���_���s�X�} �i����{�E�ƕʖ��א}���j�`���a�W�N�P�Q���` �i�ʐ^�P�j
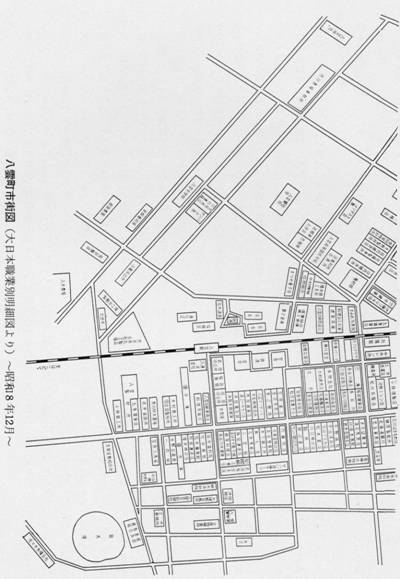

�@�Ύ��œX���Ă��Ă��܂����������A�Ăщَq�������A�����ł��X���璷�����܂ł̋������������A�V�Q�҂ł������W���炩�����X�ł͒��X�Ƃ��Ă��ꂸ�����ɋ��������V��S������ʂ��V�̗Ⴆ�𒉎��Ɏ��s�A���̓w�͂����Ȃ����A�������璷�����܂ł�Ɛ�ʼn������̔̔��Ԃ��g���邱�Ƃ��ł��A���ꂪ�P�O�N�Ԃ��炢�͑������ł��낤�B���̂���A�悤�₭�S���̕~�ݍH�����n�܂����B�����X�ɂȂ������@�͐��c�������X�i���A�X�lj����ԏ�j������A���قŎ��Ƃ��J�n����Ƃ������Ƃň��z���čs�����̂ŁA���̌�̌����������Ă��炢�َq���ƂƂ��ɂ�邱�ƂɂȂ������u��e��ǂ����̈�e���������B�v�ʼnَq�͂�߂ċ������ɓ]�����A�_��̐��쏊���Ȃ������̂ōH��������]�����悭�A���ѕt�߂�����������E���������̂������B�S�����J�ʂ����̂������R�U�N�i�P�X�O�R�j�ʼnw���s�X�n���痣��Ă��āA����Ȃ��Ƃł͂ƌ��O���ꂽ���A����s�X�����тĂ����ĕs�ւ͊������Ȃ��悤�ɂȂ����B�s�X��т����n�ō��̌������s�X�̒��S�n�ł���������A�A�V�̔ɂ�����ɉw���������͉̂��Ƃ����Ă��₵���C���������B
�@���J������X���ŏ��͌R���̕������i����ɔ̔����Ă����X�ŋ��H����R��ɗ����l�ŁA�����эL���P���̉Ƃ��Ȃ���������ŁA���łɔ��_�͑����̐l��������A���̔ɉh�Ԃ肪���̂��Ƃ������̂��B�s�X�n�̒��S���������R�T�N����ł́A�����ŕ��쏤�X������A�����Č��݂̗�؋����X�A���ł͏�������X�̂�����ƈڂ��Ă������̂��w���X�͂���ɂ���������ł��낤�B���_�̏��X�����łɂP�O���A�S�����~�݂��ꂽ����͐l�����}���ɑ����ĂQ�O�����炢�ɂȂ����B
�@����E�x�@�E�X�ǂ����̗X�ǂ̑O�ɂ������̂����������C������B
�@���ł͓��H���悭�Ȃ�X�������Ė��邢�ܑ����ꂽ���H�ɂȂ��Ă��邪�A���̂���̊X�̒��͓��H�͈����A��ݖ�ɂ͕����Ȃ������B�X�������X�̗ǂ����ł���̂��ւ̎R�ŁA������u���L�ō��Ζ������ĂƂ����悤�ȗL�l�ŁA��̊X�̂Ȃ��͐^���Âł������B
�@�钆�ɕ��C�ɍs���̂ɂ��傤��������čs�����̂��A�����̔��_�̎s�X��z������̂��������Ȃ����炢�ɍ��͂悭�Ȃ��Ă���B
�@�d�C����������ŗL�u���ォ���������T���b�g���炢�ňÂ������B������ɂ��捡�ɔ�ׂ�ƌ��ƃX�b�|���̈Ⴊ����B�v
�Əq�ׂĂ���A�����̔��_�s�X�n�̗l���������������Ƃ��ł���B
�@�i���a�R�R�N�W���P�������_�V����j�����V�R��
�����n��̏���
�@�����n��̏��Ƃ́A�����ɏq�ׂ��悤�Ɉ����U�N�i�P�W�T�X�j�ɋ{���g���A���p�i�G�ݓX���J�Ƃ����̂��͂��܂�Ƃ���Ă��邪�A����͂����܂ł��{�i�I�ȏ��X�o�c�̂͂��܂�ł����āA�����镶���x�ɏo���ꂽ�������̋I�s���ɂ��ƁA�Ζ����E�����E��c�ǂȂǂɏ��X�A���l�h���������悤�ɋL�^����Ă͂�����̂́A���̋�̓I�ȏɂ��Ă͑S���s���ł���B
�@�܂��A�����X�N�i�P�W�V�U�j�T���̌ːЌ���ɂ��ƁA���ƂƂ��ĖΖ����P���A�����T���ƋL�^����Ă��邪�A���ꂪ�ǂ̂悤�ȏ��Ƃ��c��ł������͕s���ł���B
�@�����S�N�i�P�W�V�P�j�W���Ɂu�U���E���߁v�����z����A���̌�A������g�т����E�l���X�����痈�āA�˕ʂɎU����]��q�˕������Ƃ����B
�@�˒����꒲�ׂ̖����P�S�N�������E�ƕ\�ɔ����i�j�j�P�l�̋L�ڂ�����A��������P���͒j�ł������炵���B�������A�����͎����̔��͎����Ō����̂������̂����Ȃ݂Ƃ��ꂽ����ł���A�������Ƃ̂��鎞�͑f�l�Ŕ������̏��Ȏ҂Ɉ˗�����Ƃ������K�ł������Ƃ����B�R�W�N�ɓc��C�O�Y�������ŏ��߂ė����X���J�Ƃ��A���l���p�Ƃ�����͐�����㑾�Y���A����ɂ��̌�A���c����Y���J�Ƃ����B���݂͗����s�X�n�����łT���̗����X���c�Ƃ��Ă���B
�@�����Q�R�N�ɐX�E�������Ԃ̍������S�ʊJ�ʂ��A�R�U�N�ɂ͓S�����J�ʂ����̂ł��邪�A�����w�͂S�S�N�W���܂ŊJ�݂���Ȃ������B���̗��R�́A�����͒��p���x�e�E���h�̏ꏊ�Ƃ��Ĕ��W���Ă����̂ŁA�w���J�݂���邱�Ƃɂ���ė��l���f�ʂ肵�Ă��܂��Ƃ��āA�������җ�Ȕ��Ή^�����������߂ł���Ɠ`�����Ă���B�����������Ƃ���A�������Ȃ�̏��X�◷�l�h���������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����邪�A�ڍׂȋL�^�͎c����Ă��Ȃ��B�����A�������鏤�X����T���Ă݂�ƁA�����S�S�N�T���ɉ��c鉡����ށE�����E���E�āE�H���G�ݓX���A�U���ɉ��c�S���Y�����ށE�H���i�X���J�ƁA���̌�吳�U�N�ɉ������g�������ǂ�̐����̔��ɉ����Ď�ށE�َq�ނ��A���a�R�N�ɂ͓��c�����Y���m�َq�̐����̔��A���K���Y���H���i�E�G�ݓX�A�U�N�ɍ�{�������吳�P�R�N�ȗ��c�Ƃ��Ă��������g�~�̓��h�����X�ؗэ�ɏ��n���ĕĉ��ɓ]�ƁA���a�P�P�N�����������]�ԓX�A�����Ďēc�C���Y�A�ɓ��ƗY�炪�����S�����i�������j�����ɊJ�X���ĉc�Ƃ��n�߂��B�Ȃ��A�����̓����Ƃ��Ă͈ꕔ�̐��X�������āA�قƂ�ǂ̏��X���u�Ȃ�ł����v�u��낸���v�ƌĂ��悤�ɁA�����鏤�i���c�ƕi�ڂƂ��Ď�舵���Ă����̂ł���B
�@���A�q��B���A�������v�A�J�����t���X�Ȃǂ̐V�����X�܂������A���a�Q�U�N�����ɂ͏��ƌː��͂S�R�˂ɂ܂ő��������B
�@�܂��A�����̌�y�@�ւƂ��āA�n�����Ƃ̉f�悪�����Ŏn�߂���悤�ɂȂ����̂͑吳�W�N����ŁA�����̌�y�Ƃ����A���X���Ă��錶�����Q�Ȃł���A�l�ʂ�ɂ������i�����P�j�p�J���قōs����̂��ʗ�ł������B
�����s�X�i�ʐ^�P�j

�@�吳�V�N�R���ɗ��َ�p�J�G���Y���p�Ƃ��A�������֓]�������̂ŗ��W�N�Ɉ���F���Y�������\���X�ɗ��l�h���J�Ƃ��A���̂��납�珄�Ɖf�悪��f���ꂽ�Ƃ����B�q���̏�q��ӂ��܂����O���čL�Ԃɂ��A�����ނ͊e���������ӂ낵���ɕ��œ����ďオ�����̂ł���B�吳�P�R�N�ɂ͕���ÔV���Y�����̗��l�h������A���������f���Q�ȂȂǂ̏��s���s��ꂽ�B
�@���a�V�N�ɓ��l�͗��l�h�̗אڒn�ɕ������V�z���āA�ŋ��E���w�E�Q�ȁE�f��Ȃǂ̋��s���s�����B�Q�U�N�ɂ͋K�͂��g�債�u��������v�Ƃ��đ��������A�R�Q�A�R�N���납���ʉƒ�ɋ}���ɕ��y���͂��߂��e���r�̉e�����A����ɑ����^�Ԃ��̂����R�ɏ��Ȃ��Ȃ�A���ɂS�R�N�X���������ĕق����̂ł���B
�펞���̏���
�@���a�P�Q�N�i�P�X�R�V�j�V���ɓ����푈���ڂ����A�₪�Đ���͋}�ς��Đ펞�o�ϓ����̐��ւƌJ������ꂽ���߁A��ʍ����ɂƂ��Ă͂������̂��ƁA���ƌo�c�҂ɂƂ��Ă͂܂������Í�����Ƃ������鎞���ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A���N�W���ɂ͑��������{���ł��o�����g���̋������j�ɑ������A���H�Ǝ҂͂���܂ł̏��H�g�������U�A���̔N�X���Ɂu���_���H��v�ɉ��g��������Ƃ�����Ԃł������B���P�R�N�ɂ͍��Ƒ������@�̐���ɂ���āA���Z�E�Y�Ɩʂ����ʍ��������Ɏ���܂Ő펞�̐����ɂ�����A����ɂP�S�N�ɂ͍������p�߂����z����Ă�����u�������W�v�����s�����ȂǁA�����̘J���͂͌R���Y�Ƃ̐��Y�Ɍ������A���a�I�Y�Ƃ͗}������ē��p�����͂����܂��s�����������A�o�ϓ����͂��₪�����ɂ��������ꏤ�H�Ǝ҂����̉e����������łȂ��A�Љ���̂��ׂĂ��傫���]�������̂ł������B
�@���������āA���{�̕��j�ɂ��ݗ��������H��ł͂��������A���ǂ̋ٔ����ɂ�Ă��̂����炻�̊����͐���A�L�������̏�ԂɊׂ����B���������a�P�S�N�X������A�����X�A���H�X�Ȃǂ͋x�Ƃ������A�܂��A�����P�X���ɂ͈�ʂ̕�������ђn��ƒ��Ȃǂ�O���̐����ɓ�������Ƃ����A������u��E�ꔪ���������߁v�������Č��艿�i����߂�ꂽ�B����ɁA�����̓�����ړI�Ƃ��āA���{����p�̖Ȑ��i�E�Ζ��E�����E�ߗ��E�S���E�āE�ؒY�E�����H�i�Ȃǂ̍ɒ������s����ƂƂ��ɁA�����ɑ��������u���_���Ƒg���v���ݗ����ꂽ�B
�@���a�P�T�N�i�P�X�S�O�j�ɂ͂��ɕK���i�̓����z������������A�č��ɂ��Ă͂T���R�O������ؕ����ƂȂ�A�W���P������ʒ��ɉ��߂�ꂽ�̂���n�߂ɁA�����E�}�b�`�̐ؕ����ւ̈ڍs�ȂǁA���������͒��������̘g���L�����Ă������B�P�U�N�ɂ͎�H�̂Ȃ��ɂł�Ղ�ⓤ�ނ�������ꂽ�ق��A���E�َq�E�H�p���E�����i�E�|�E�����߂��炩�����蕲�̉ʂĂ܂ł��z�����ƂȂ�A����ɂP�V�N�ɂ́A�݂��E���傤������R�ɔ����Ȃ��Ȃ�ƂƂ��ɁA�@�ې��i���Q������_�����E�ؕ����Ɉڍs����Ɏ����āA���R�ɔ�������̂͂قƂ�ǂȂ��Ȃ����̂ł���B�������ď��Ǝ҂́A�P�ɍ��Ƃ̌v�悷��z���@�\�ɏ]������@�ւɂ����Ȃ����̂ɕς����Ă������̂ł���B
�@���̂悤�ȏ�̂Ȃ��ŁA���{�͂���ɋ��͂ȓ����o�ϑ̐��ւ̓]����}�邽�߁A���X��z���@�ւƂ��Ă̕K�v���x�ɂƂǂ߂邱�ƂƂ����B���a�P�V�N�Q���u�H�ƊǗ��@�v�����z���A�H�Ƃ̊��S�Ȕz���ꌳ����}���������A�z���@�\�Ƃ��Ėk�C���H�Ɖc�c���ݗ�����A�e�s�����ɂ��ꂼ��o�����������ꂽ�̂ł������B����ɁA�T���Ɍ��z�����u��Ɛ����߁v�ɂ��A�č��̔��ƎҁA���ًƎ҂̐��������A����я����Ǝ҂̐����]�p�Ƃ��f�s�����Ɏ������B
�@���̂��ߓ����ł́A���P�W�N�Ɂu���_�������Ɠ]�p��ψ���v��ݒu���A�����Ǝ҂̐��������Ȃǂɂ��ĐT�d�Ȍ����𑱂������ʁA�X���ɂ͂T�V���̏��X��p�Ƃ�������ɏ��������̂ł������B�c�Ƃ𑱂��邱�ƂƂȂ������X�ł��A�������z���Ɩ����ׁX�Ƒ����Ă��邾���ŁA�펞�X���J���Ă���Ƃ�����Ȃ����肩�A�₪�Ĕz���̑啔���́A�בg��ʂ��ăN�W�����Ŋ��蓖�Ă�悤�ɂȂ������߁A���ƌo�ς͋ɓx�ɋ������Ă������̂ł���B
�@���̂悤�ɂ��ē��������s�����Ȃ��ŁA��肢���������̎��������߂邽�߁A���a�P�X�N�V���ɔ��_���Ƒg���͉��U���u���_�z�������g���v�ɉ��g�������A���悢��{�i�I�ȕ����̔z���@�\�Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă������B
�w�O�䓛���X����{�ʂ��]�ށi�ʐ^�P�j

���̏���
�@���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�W�������m�푈�͏I�������̂ł��邪�A���̍����͕����̌��R�A�����̍����Ƃ�����Ԃ����������߁A�����o�ς͒����ɉ�������邱�ƂȂ��A���E�����Ȃǂ͂�������K���i�Ɏ���܂ŁA�ˑR�Ƃ��Ĕz�����x���������ꂽ�B�������A�I��̔N�͋���ɂ�����A�����̐����͔s��Ƃ������_�I�ȒɎ�ƁA�����̌��R�Ƃ�����d��킳�ꂽ�̂ł������B���̂������{�͏��a�Q�P�N�P���ɁA�Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��C���t���[�V�����̎��E��Ƃ��āu���Z�ً}�[�u�߁v���{�s����Ɠ����ɁA�����������{�s���ĐV�����̌n������A�o�ς̍Č���}�����B���Ȃ킿�A���~��a���Ƃ��ĕ������A�����̈����o�������z�A�������ю�R�O�O�~�A���ш��P�l������P�O�O�~�A�����P�l������T�O�O�~�ɐ������A������ꂩ���T�O�O�~���������v���ꂽ�̂ł������B
���̂��߁A�l�X�͂��Ƃ��a���������Ă����R�Ɏg�����Ƃ��ł����A�H�Ƃ����߂Ē��ڐ��Y�҂�K��Ă��A���͂���K�ł͓��邱�Ƃ��ł����A�莝���̈ߗ��i�Ȃǂƌ�������Ƃ����g�|�̎q�����h�����炭�������B���������āA��ʏ��i�̐������ĊJ���ꂽ�Ƃ͂����A�}���ɏ��X����������Ƃ����]�n�́A�قƂ�ǂȂ������̂ł���B
�@�������A�����������ڂ����ǂ����Ȃ��ŁA�āE�\�����̑Η������Ƃ������ۏ��w�i�Ƃ��āA�č������{�ɑ����̐����ύX���A���a�Q�S�N���납��o�ς̈����������������ɓ]�����}��ꂽ�B����ɂ���č����̐��Y�Ԑ������݂��͂��߁A�悤�₭�������o���n�߂�悤�ɂȂ��Ă����B���̂��߁A���N�S���ɖ�A�T���ɐ����E�����i�A�X���ɐΒY�Ƃ����悤�ɁA�������œ������O����A����ɁA���Q�T�N�R���ɖؒY�E�܂��ȂǁA�S���Ɏ��E�����̔z�������P�p����A�Q�U�N�V���ɂ͑S�@�ې��i�����R�̔��ƂȂ�ȂǁA��H�ȊO�̕����͋}���Ɏ��R�̔��̐��ւƐi�݁A���Ƃ͓����푈���n�܂��Ĉȗ����ɂP�T�N�Ԃ�ɕ��������̂ł���B
�@���̂悤�ɁA���Y�⏤�i���ʂ̉Ƃ�����̕ω��ƕ��s���āA���i����݂łł��s���ɏo���͂��߂�ƁA�s�X�n�ł������ł��A����܂łقƂ�Ǖ���Ԃ������X�܂����X�ɊJ�X����悤�ɂȂ�A�܂��A��݂ł��������V�����X�������ȂǁA�悤�₭���ƍĊJ�̒����������͂��߁A���a�Q�T�N�ɂ͂V�X���i�����_���j�̏��X�𐔂����Ƃ����B���Q�U�N�U���ɂ́A��������Ƒ�ꂪ�V�݂����ƂƂ��ɁA�]���̔��_���͑�ꌀ��Ɖ��̂���Ĕ��_�s�X�n�ɂR���̏�݉f��ق��ł���ȂǁA���͂悤�₭������悷��悤�ɂȂ����B
�Ǝ�ʏ��ƌː��i���a�Q�X�N�j�@�@���_�n��
| �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� |
| �H���i�X | �R�X | ���Y�X | �S | ����X | �Q | �����X | �R |
| �ʏ� | �R | ������ | �U | ���� | �T | ���� | �R |
| �����X | �S | �N���X | �P�Q | �d�Y�� | �S | ���ϕi�X | �P |
| ����X | �V | �Ƌ�X | �Q | �������� | �R | �ʐ^�� | �U |
| ���]�ԋ� | �S | ���ٓX | �T | �d�C�X | �S | ���� | �S |
| �����X | �S | �^����X | �Q | ���H�X | �P�V | �ԉ� | �Q |
| ���v�X | �T | �y��X | �P | �����X | �P�T | �f��� | �R |
| ���X | �Q | ���̔��� | �R | �ю��X | �P | �����ԋ� | �P |
| ���˓X | �Q | �C�X | �S | ������ | �T | ���� | �S |
| ���X | �R | �َq�X | �W | ���[��X | �R | �@ | �@ |
| ����� | �Q | �� | �T | �V�Z�� | �Q | �@ | �@ |
| �����X | �P�O | ���e�� | �V | ���� | �R | �@ | �@ |
| �F�͓X | �R | ���˕��X | �P | �m���d���� | �V | �v | �Q�S�U |
�Ǝ�ʏ��ƌː��i���a�Q�U�N�j�@�@�����n��
| �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� | �Ɓ@��@�� | �ː� |
| �H���i�����X | �Q�O | �����X | �P | �����G�ݓX | �P | ���e�X | �S |
| �ߗ��i�X | �S | ���Е���X | �P | �V���̔��X | �P | ���� | �S |
| �č��X | �R | �َq�����X | �Q | �ߕ��ٖD�C���X | �Q | �v | �S�R |
�i�u�����������v���v�j
�@�܂��A���a�Q�T�N������{���ꂽ�s�s�v��X�H���Ƃɂ���āA�{���ʂ�̐������i�߂��A����ɂQ�W�N�ɂ͒�����ƒ��̕��j�Ɋ�Â������̌v��ɂ��u�k�C�����X�X���f���n��v�Ƃ��āA���E�����ƂƂ��Ɏw����A���N�U��������ƒ�����h�����ꂽ�����s���H�w�����̎w�����ɂ���āA�܂��{�����X�X�̐f�f�ɂ���{�I�ȕ��͎w�����s��ꂽ�B�����ĂQ�X�N�ɂ́A���X�X�́u�����I�̔��͍\���v�̗v�f�ł��闧�n�����i�����͈́j�Ǝ���Ԑ��i�O�q���ꏤ�X�X�̏j�Ȃǂɂ��Ă̒�������ьo�c���e�̐f�f�ɂ���āA���S�ȋL���ɂ�鍇���I�o�c�̎w�����Ȃ��ꂽ�B�܂�����A���H�W�Ҏ�������@�c��Ґ����đ��̎w��n������w������A�X�܂̐����E���i�̒�E�Ɩ��ݔ��̉��P�Ɉӂ�p����ȂǁA���Ԃ̈�V�ɓw�߂��B�Ȃ��A�ᏼ���ʂ�i�{���U��j�ł́A�Q�X�N�Ɂu�ᏼ���U����v���g�D����A�g��������h�Ɩ��t�����X�H����ݒu���A�U�����납��P�O������܂Ŗ��T�y�E���j���ɖ�X���o���āA���X�X�̐U���ɂ��Ď��݂��Ă����B
�@���̎���̏��H�c�̂Ƃ��ẮA���a�Q�Q�N�ɐݗ����ꂽ���Ƌ����g��������A�Q�W�N�ɂ͂���ɑ����Đݗ����ꂽ�`�̔��_���H��Ɉڍs���A���_�n��������Ƒ��k���ƂƂ��ɏ��H�Ƃ̐U���ɑΏ����Ă����B
�@�܂��A���a�P�V�N�ɑg�D���ꂽ�H�Ɖc�c�́A�Q�R�N�Q���ɐH�Ɣz�����c�ւƉ��g����A�Q�U�N�S�����c�̔p�~�ƂƂ��ɁA�č��ɂ��Ă͔��ْn���H�Ƌ����g���Ƃ��Ĕ����c�I�Ȍo�c�ƂȂ������A�R�O�N�ɂ͉��U���Ĕ��ٕč�������ЂɈڍs���A���݂Ɏ����Ă���B
����������̏���
�@�����̐l���͏��a�R�O�N�����ɂ��āA�킸���Ȃ��猸���X�����݂��͂��߂Ă������A�R�Q�N�S���ɗ������ƍ������ꋓ�ɂQ���U�V�R�W�l�ƂȂ�A�V�����_���Ƃ��Ĕ��������̂ł���B
�@�����������̏Ƃ��ẮA�������͂��߂Ƃ���e�퓹�H�͖����ǂł���A���S�̗A�������݂̂悤�ɔ��W���钛�����݂�ꂸ�A���̂��߁A�k�C���̒��S�s�s�ł���D�y����Q�O�O�L�����[�g���A���ق���W�O�L�����[�g���̒n�_�Ɉʒu���Ă��铖���̌o�ς́A�ʏ�̏ꍇ������s�s���璼�ډe�����邱�Ƃ����Ȃ��A����ΓƗ������������ێ����Ă����B�������A�w�R�n��e�����ɒʂ��铹���R�H���̊�_�Ƃ��āA�n�������k���ɂ������ʏ�̋��_�ƂȂ�A�����E�o�ς̒��j�I������S���Ƃ���ƂȂ����̂ł���B
�@�Ƃ͂������̂́A�V�����a����������Ƃ����Ē����ɏ��ƌ`�Ԃ��傫���ω����邱�Ƃ͂Ȃ��A���_�s�X�n����̏W���n��Ƃ���A�����s�X�n�����̏W���n��ƂȂ�A�����n��ɂ����Ă͏]���̊��K�������āA���i�w���̂��ߐX���s�X�n�ɏo�����X�����݂��A��������̓I�ȊW�ƂȂ�ɂ́A�Ȃ������̎��ԓI�o�߂�K�v�Ƃ����B�������A�₪�č����̊��S�ܑ����������A�����Ԃ̕��y�ɂƂ��Ȃ��ċ����I�E���ԓI�����������A����ɏ��H��̊����Ƒ��܂��Ĉ�̉��͗\�z�ȏ�̃X�s�[�h�Ŏ������邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�@�܂��A����܂œ����ɂ́A�����_�z�R�̉���ȊO�ɂ݂�ׂ����̂��Ȃ��������A�����ɂ���ď�̓���������邱�ƂƂȂ�A��������p�����ό��J�����傫�ȉۑ�Ƃ��Ĉ��N���[�Y�A�b�v�����Ƃ���ƂȂ����B
�@���a�R�O�N��㔼�ɂ����ẮA���x�o�ϐ�������̉e�����A��ʏ���҂̍w���͂��㏸����ƂƂ��ɁA���X�̑�^�����ڗ����͂��߁A�s�X�n�̊O�������i�ނɂ��������A�V�����X�������ɂ݂���悤�ɂȂ����̂��A���̂���̓����̈�ł������B�Ȃ��A���a�R�Q�A�R�N���납�珙�X�ɕ��y���͂��߂Ă����e���r���A���N�������ĂقƂ�ǂ̉ƒ�ɕ��y���A����܂Ō�y�̒��S�ł������f��قɑ����^�Ԃ��̂����R�ɏ��Ȃ��Ȃ�A��݂R�f��ق͂S�O�N��O��ɑ������Ŏp���������B�����ɂ����Ă��A���a�V�N������Ƃ��ĊJ�݂��A���̌�g�����ĉc�Ƃ𑱂��Ă����������ꂪ�ق����̂��S�R�N�X���ł������B
�����n�揤�X�X�i�ʐ^�P�j

�@���_�s�X�n�ɂ����ẮA���a�R�O�N��ɓ��������납�玟��ɌÂ��X�܂̉����ɒ���A�܂��A�����ʐς̊g���ɏ��o�����̂�����A�ߑ�I���o�������ꂽ���i�̒��Ɩ��Ȃǂɔz�ӂ����悤�ɂȂ��Ă����B�����āA���ꂪ�{�i�I�ɂȂ����̂͂S�V�A�W�N���납��ł���A���܂⒆�S���X�X�ɂ����ẮA�̓��̖ʉe���Ƃǂ߂���̂̂ق������Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��悢�ł���B�������A�����������ƌo�c�҂������A���ɂQ��ڂƂ�����l���唼�𐔂������łȂ��A�����I�ɂ͂R��ڂɂ���Čo�c����Ă���ł���B
�@���ł��A���̂悤�ȏ��X�X�ĊJ���̓����ɑΏ����āA����������Ǝ҂̓X�܂̉��P�𑣐i���A���X�X�̋ߑ㉻�ƌo�c�̍�������}�邽�߁A���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�S������u���_�����q�⋋���{�v�́v���߁A����ɂT�O�N�S���ɂ́u���_��������ƓX�܉��P���q�⋋�K���v���{�s���āA���̐��i�����������B���̗v�̂��邢�͋K���ɂ��u������Ǝҁv�Ƃ́A�l�܂��͖@�l�ŁA���{���P�O�O�O���~�ȉ��A�]�ƈ��P�O�O�l�ȉ��i���ƁE�T�[�r�X�Ƃɂ����Ă͂T�O�l�ȉ��j�̂����ꂩ����̏���������Ɓi���Z�ƁE�ی��ƁE���@�I���Ƃ���шꕔ�̗V����y�Ȃǂ������j�ƒ�`�������̂ŁA���܂��͏��H��̎w���ɂ���ċ��Z�@�ւ̗Z�����A�X�܂̉��P�����钆����Ǝ҂ɑ��ė��q��⋋���A���S���ɘa����Ƃ������̂ł������B�������A�ؓ��z�Q�O�O���~����Q�O�O�O���~�܂ł����x�Ƃ��A�������A�����T�p�[�Z���g���镔���łR�p�[�Z���g�ȓ��ŁA���̗��q�⋋���Ԃ��Q�N�ԂƂ������߁A�K���������p�҂���������Ƃ������̂ł͂Ȃ��������A���ꂪ�X�܉��z�̑傫�Ȃ��������ɂȂ������Ƃ������ł���A�S�W�N�x����T�R�N�x�܂ł̘Z���N�ŁA�����S�O����ΏۂƂ��鐬�ʂ����߂Ă���B
�@����ɁA�����Ԃ̋}���ȕ��y�ɂ���āA���Y��������l������ς��������A�]���̉הn�Ԃ�n���肪�p�������A��^�_�Ƌ@�B�̕��y�ɂ��n�̎��炻�̂��̂������������߁A����܂ŕs���ł������n�����Ǝ҂��A�Ƃ��ɐ��ƈێ��s�\�ƂȂ��ĂS�O�N��ɂقƂ�Ǔ]�p�Ƃ����B�܂������ɁA�n�ԁE�n����E�n�k�v���E�E���̑��̔_�@����𒆐S�ɉc�Ƃ������������A�]�p�Ƃ������̂������A���̈ڂ�ς����������ʂł���B�������������w�i�Ƃ��āA�ߔN�����ȏ��̂���u���̒b�艮�v���p���������̂����R�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�܂��A�ߔN���ƊE�̕ω����������̂̈�ɁA���a�S�O�N�ɓ����ĊԂ��Ȃ��o�������g�X�g�A�h�`���ɂ��V���@�̕��y������B�Ƃ��ɁA�S�Q�N�P�P�����_���_�Ƌ����g���̃}�[�P�b�g�����̕����������ꂽ�̂��͂��߁A�S�T�N�ɓ��w�O�}�[�P�b�g�̐i�o�A���S�U�N�}���X�C�X�g�A�A����ɑ����ă}���~�X�g�A�A�����Ȃǂ��o�ć����j�[�N�V���b�v���܂̐i�o�A�e�[�I�[���}���A�������d��Ȃǂ����̂�������Č������̔�������J��L���A���̂��߁A�ꋫ�ɗ��������X�g�A���o�����łȂ��A��ʏ��X�ւ̉e�������Ȃ��Ȃ��̂�����ł��낤�B���̂��ߊe���X�ł��`�F�[���g�D�ɂ���āA�̔��̊g����ڋq�U�v�ɐ^���ȑ���u���Ă���B�����������Ƃ���A���H�������g�D�ł���u���_�����X�X�U���ψ���v�̊����Ɋ�����҂́A�܂��܂��傫���Ȃ��Ă���B
�@�Ȃ������ɂ́A�������̏o��@�ւ����Ƃ̎x�X�E�o�����E���H��Ȃǂ������A����������炪�A�n���k����w�R�̈ꕔ�̎��Ӓ������NJ�������̂��������߁A���^�����҂����R�����A���̏����z���S�U�N�x�Œ��ɂ����鑍�����z�̂W�P�p�[�Z���g���߂�ȂǁA�傫�ȍw���͂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����F�̈�ł���B
�����Ԋ֘A��ƂƃX�[�p�[�̐i�o
�@���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�ɒr�c���t�������{���v��\���A���x�o�ϐ��������i���ꂽ���Ƃɂ���āA���Ԃ̐ݔ������ƋZ�p�v�V�Ɋ�Â��V���i��V�Y�Ƃ̑䓪�ɂ��A�킪���̌o�ς͒����������������A�R�U�N�ɂ͍��������Y�́A�A�����J�E�\�A�Ɏ����Ő��E��R�ʂ��߁A���������̏�ɂ��������ω��������炵���B�Ƃ�킯���[�^���[�[�V�����ُ̈�Ȃقǂ̔��B�́A���ɂ����u�ԎЉ�v���������A���������̌���Ƒ��܂��č����̍s�����a�͊g�債�āA�����Ԃ𒆐S�ɐl�тƂ̐����l���͂������A�A���̌n�ɂ��傫�ȕω����y�ڂ����B
�@�������������Ԃ̕��y�ɂ���ČJ��L����ꂽ�������̔������w�i�ɁA���فE�����ȂǓs�s���̒��ԂɈʒu���铖���́A�L���~�n�����������ɂ��邱�Ƃ���A�k�n����w�R�n���ւ̔̔��V�F�A�̊g���}����f�B���[�̒��ڂ���Ƃ���ƂȂ�A���̋��_�Ƃ��Đ����H���t�������̔��X�̐V�݂������������B�܂��S�O�N�ɃN���E���n�g���^�A�R���i�n�̃g���y�b�g�����ԗ��T�[�r�X�H�ꂪ�i�o�����̂���ɁA�S�Q�N�ɂ͓��Y�v�����X�n�̃A�T�q����A�T�[�r�X�H��E�c�Ə��E�K�\�����X�^���h���Z�b�g�ŐV�݁A�S�R�N�ɂ̓g���^�p�u���J���ق��������T�[�r�X�G��Ɖc�Ə���V�݂��A����ɁA���Y�T�j�[�A���ك}�c�_�A�O�H�n�̃T�[�r�X�H����i�o���āA�L�̓��[�J�[�n��̊�Ƃ����������ɏo���낢�A����ɍ��킹�ăK�\�����X�^���h���V�݂��ꂽ�B���̂��ߊ����̒n�������H��͂��̉e�����A���ÎԂ̔��h���Ȃǂɓ]�Ƃ������̂�����A������ƂɂƂ��Ă͂��т����������炵���̂ł������B
���_�����X�X�i�ʐ^�P�j

�@����A����玩���Ԋ֘A��Ƃ̐i�o�ƂƂ��ɁA�w���͂̑�ʋz�����˂�����X�[�p�[�����ɂ��V���@���ڗ������߂����A���_���_�Ƌ����g�����S�Q�N�P�P���ɐV�z�������ɕ��݂̃}�[�P�b�g���J�݂��A����ɑO�q�����悤�ɍ��S�𗘗p����g�����ւ̃T�[�r�X��ړI�ɁA���_�w�O�̑q�ɂ��������ĉw�O�}�[�P�b�g���J�݂��邱�ƂƂ����B����ɑ��ď��H��ł́A��ʏ��X�̔��e�����l���_���ɐV���v��̍Č�����\�������Ɠ����ɁA���c��H�J���ψ���ɂ��X�܂̑��ݔ��Β���o����ȂǁA�j�~�^���𑱂����̂ł��邪�A�@�I�ɂ͂���𐧖邱�Ƃ͕s�\�ł���Ƃ��āA���N�U���w�O�}�[�P�b�g�͊J�X�����̂ł������B�������A�T�R�N�ɂ͓������_�`���̊g���H���ɂ��A�~�n�̈ꕔ����������邱�ƂƂȂ������}�[�P�b�g�́A�����T���������ɓy�n�����߁A�T�V�N�P�Q���w�O�X�܂�V�݂����B
�@����ɁA�T�Q�N�ɂ͔��َ��{�̑�^�X���j�[�N�V���b�v���܂��i�o����ȂǁA�n�����H�ƊE�ɂƂ��Ė��͑傫���A���H��ł͒��������Ǝ҂̓K���Ȏ��Ɗ������m�ۂ��邽�߁A�T�P�N�ɔ����������u���_�����X�X�U���ψ���v�𒆐S�ɁA��^�X�⒬�O���{�̐i�o���ɂ��Đ^���Ɏ��g�݁A���̑�����������B���̌��ʁA�����̐i�o�X�[�p�[�ɑ��A�X�ܖʐς̐����A�]�ƈ��̈������֎~�A�J�������A�c�Ǝ��ԁA�x�X���A�֑��`�A�����̎��l�A�e�i���g�����A�d����A���K���A���@���̏���Ȃǂ̋��菑�����킵�āA�n���ƊE�Ƃ̋����̐��̈ێ��ɓw�߂��̂ł���B
�@��S�߁@�L�揤�Ɛf�f
�L�揤�Ɛf�f�̎��{
�@���a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j�T���A�n�������k���n��̒��j�s�s��ڎw���������A���̒n��̒��S���Ɠs�s�ƂȂ邽�߂̕�����T�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���Ə��H��̋��͂̂��ƂɁA�k�C������іk�C�����H�w���Z���^�[�ɂ��L�揤�Ɛf�f�̎��{�����߁A���_�E���������X�X�𒆐S�Ƃ���f�f���s�����ƂƂ����B
�@���̍L��f�f�́A�����H�w���Z���^�[�������P�T�O���̏��X�A�S�O�O���̏���҂�Ώۂɂ��Ē������s���A���̓I�Ȕ��f�̎����Ƃ��悤�Ƃ�����̂ŁA�܂����N�U���ɗ\���������s���Đf�f�ɕK�v�Ȓ������ڂ�����A�V������W���ɂ����ė\���f�f�A�X������P�P���ɂ����Ė{�f�f�Ƃ����菇�Ői�߂��A�����e�w�Ƃ̏���ҍ��k����͂��߁A���H������E���N���E�o�c�҂ȂǂƂ̍��k���ʂ��Đi�߂�ꂽ�B�������ē����ɂ����鏤�ƊE�̓����E�Ǝ҂̌o�c�ӎ��E���H�Ƃ̒����W�]�E�ό��J���̖��_�Ȃǂɂ��Ď�X�������d�˂��A���̒������ʂ���b�Ƃ��ĕ��͂��f�f�������̂ŁA���S�W�N�R���u���_���L�揤�Ɛf�f���v�������Ă܂Ƃ߂�ꂽ�̂ł���B
�@���́A�����ҁE����ҁE�����҂̂R�҂���Ȃ�A�a�T���P�S�P�y�[�W�̍��q�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă��邪�A�����̔��_�����H�Ƃ̊j�S�ɂӂ��M�d�Ȏ����Ƃ��āA�Ȍ�͏��H�ƐU���̎w�j�Ƃ��Ċ��p�������B
�@���̕��̂�������A�����ɓ����Ɗ����̊T�v�ɂ��Ď��ɓE�^������̂Ƃ���B
�����E�����Ƃɂ����铮��
�@���̕��̎����҂̂Ȃ��łӂꂽ���a�S�W�N��O���ɂ�����u���������Ƃ̓����v�͈ꗗ����Εʕ\�̂Ƃ���ł��邪�A�����̔��z�͏����ɐ��ڂ��A�n�������k���W���i���_�E�������E�X�E�����E�k�w�R�E���I�E�听�E�F�j�̏����̔����ɐ�߂�苒���i�̔��V�F�A�j�́A�Q�T�p�[�Z���g�Ƃ�⍂�����A������ԂɂƂǂ܂��Ă���B����A�����̔����͂S�T�N�x�łQ�T���V�Q�X�R���~�ƂW���̂Ȃ��ł��ł������A�������̔����̃V�F�A�͂S�Q�E�W�p�[�Z���g�ŗD�ʂɗ����Ă���Ƃ��Ă��邪�A���̂����ł͐H���E�����̔̔������X���T�S�T�O���~�ň�ԍ����A�����Ԃ��܂ދ@�B������Ɏ����łV���T�Q�X�S���~�ƂȂ��Ă���B
���Ɠ����̐��ځi�����Ɓj
| ��@���@�Ɓ@�� | ���@�@�X�@�@�� | �]�@�@�Ɓ@�@���@�@�� | �́@�@�@�@���@�@�@�@�z�@�i�@���@�~�@�j | |||||||||
| �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | |
| �_ �{ �� �Y �� �� �� �� | �S | �V | �T | �W | �P�X | �P�Q | �P�W | �Q�W | �P�Q�C�O�V�U | �T�C�P�U�O | �Q�S�C�U�R�O | �S�X�C�R�U�U |
| �H �� �i�@�V | �T | �U | �X | �U | �R�Q | �R�Q | �S�S | �S�V | �T�U�C�R�U�X | �V�W�C�Q�W�V | �W�Q�C�S�V�X | �X�T�C�S�T�O |
| �z �� �� �� �� ���@�V | �T | �S | �| | �| | �U�T | �P�X | �| | �| | �P�U�C�X�R�R | �P�R�C�U�V�S | �| �i�R�P�C�S�R�T�j |
�| �i�Q�X�C�Q�Q�X�j |
| �@�B���@�V | �Q | �U | �P | �Q | �Q�S | �Q�O | �X | �U | �T�Q�O | �P�R�C�R�V�O | �V�C�O�Q�O �i�Q�X�C�V�Q�Q�j |
�Q�R�C�V�P�O �i�V�T�C�Q�X�S�j |
| ���z�ޗ��@�V | �P | �| | �| | �P | �P | �| | �| | �U | �V�O�O | �| | �| | �S�C�W�O�O |
| �������@�V | �R | �W | �V | �Q | �P�O | �P�T | �P�R | �P�O | �X�C�R�W�X | �Q�C�S�X�W | �R�C�O�R�V | �R�C�P�T�S |
| �� �� ���@�V | �P | �Q | �Q | �| | �S | �S | �T | �| | �U�C�S�Q�R | �Q�U�C�X�R�V | �X�R�O | �| |
| �� �� �� �� �� �� | �R | �T | �S | �| | �R | �U | �V | �| | �U�Q | �S�R�T | �| | �| |
| ���@�@�@�@�v | �Q�S | �R�W | �Q�W �i�R�W�j |
�P�X �i�R�R�j |
�P�T�W | �P�O�W | �X�U �i�P�X�Q�j |
�X�V �i�Q�O�U�j |
�P�O�Q�C�S�V�Q | �P�S�O�C�R�U�P | �P�P�W�C�O�X�U �i�P�V�Q�C�Q�W�R�j |
�P�V�U�C�S�W�O �i�Q�T�V�C�Q�X�R�j |
���Ɠ����̐��ځi�����Ɓj
| ��@���@�Ɓ@�� | ���@�@�X�@�@�� | �]�@�@�Ɓ@�@���@�@�� | �́@�@�@�@���@�@�@�@�z�@�i�@���@�~�@�j | |||||||||
| �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | �R�X | �S�P | �S�R | �S�T | |
| �e�폤�i������ | �P | �| | �| | �U | �S | �| | �| | �P�W | �T�P�W | �| | �| | �U�C�S�W�Q |
| �D���ߕ��g�̂܂��i | �R�V | �R�T | �R�T | �R�R | �P�Q�X | �P�Q�X | �P�R�S | �P�Q�V | �Q�W�C�X�X�X | �R�S�C�Q�S�T | �R�V�C�U�P�O | �S�Q�C�P�V�U |
| �� �H �� �i �� �� �� | �P�S�Q | �P�V�O | �P�U�O | �P�R�V | �R�Q�P | �R�X�O | �R�W�U | �R�R�X | �U�O�C�V�S�Q | �W�R�C�S�V�X | �P�O�S�C�T�T�X | �P�Q�Q�C�O�U�P |
| �����ԉԁ@�V | �V | �W | �P�P �i�V�j |
�P�S �i�T�j |
�Q�O | �Q�W | �S�W �i�Q�O�j |
�W�W �i�P�S�j |
�Q�C�X�Q�V | �S�C�T�O�R | �Q�U�C�O�S�V �i�R�C�Q�X�T�j |
�T�S�C�S�S�X �i�Q�C�W�U�T�j |
| �Ƌ� �E ���� �E �Y��@�V | �P�X | �Q�W | �R�R | �R�Q | �P�O�W | �P�P�U | �P�Q�U | �P�R�U | �P�V�C�S�U�V | �P�W�C�Q�S�W | �R�S�C�P�V�X | �R�X�C�U�T�O |
| �� �� ���@�V | �T�T | �U�R | �U�X �i�U�R�j |
�U�X �i�U�S�j |
�P�V�P | �Q�Q�Q | �Q�W�T �i�Q�P�V�j |
�Q�W�X �i�Q�T�S�j |
�Q�V�C�S�R�X | �S�U�C�X�O�R | �W�P�C�R�Q�V �i�S�X�C�W�X�Q�j |
�P�U�U�C�U�X�R �i�P�R�V�C�S�U�S�j |
| ���@�@�@�@�@�@�v | �Q�U�P | �R�O�S | �R�O�W �i�Q�X�W�j |
�Q�X�P �i�Q�V�V�j |
�V�T�R | �W�W�T | �X�V�X �i�W�W�R�j |
�X�X�V �i�W�W�W�j |
�P�R�W�C�O�X�Q | �P�W�V�C�R�V�W | �Q�W�R�C�V�Q�Q �i�Q�Q�X�C�T�R�T�j |
�S�R�P�C�T�P�P �i�R�T�O�C�V�R�W�j |
| ���@�@�@�@�H�@�@�@�@�X | �S�V | �S�X | �U�O | �U�S | �P�S�W | �P�V�T | �Q�R�X | �Q�O�W | �P�O�C�R�R�S | �P�R�C�W�S�S | �P�S�C�Q�Q�O | �P�X�C�T�W�T |
| ���@�@�@�@�@�@�v | �R�R�Q | �R�X�P | �R�X�U | �R�V�S | �P�C�O�T�X | �P�C�P�U�W | �P�C�R�P�S | �P�C�R�O�Q | �Q�T�O�C�W�X�W | �R�S�P�C�T�W�R | �S�P�U�C�O�R�W | �U�Q�V�C�T�V�U |
�i���Ɠ��v�j
�n�������k�����̔̔����V�F�A�̐����@�@�@�i�P�ʁ@���j
| ��@�@�� | �����̔����v | �D���ߕ��g�̂܂��i | ���@���@�� | ���@�H�@�X | ||||
| �S�P | �S�T | �S�P | �S�T | �S�P | �S�T | �S�P | �S�T | |
| �� �_ �� | �Q�T�D�Q | �Q�S�D�X | �Q�V�D�X | �Q�Q�D�Q | �S�T�D�O | �S�Q�D�W | �Q�V�D�R | �P�X�D�U |
| �������� | �Q�Q�D�Q | �P�T�D�O | �P�X�D�V | �P�X�D�W | �P�S�D�T | �P�S�D�Q | �R�P�D�T | �Q�U�D�V |
| �X�@�@�� | �P�V�D�T | �Q�P�D�S | �P�S�D�Q | �Q�T�D�S | �P�U�D�W | �P�W�D�Q | �P�T�D�P | �Q�S�D�W |
| �� �� �� | �P�R�D�T | �P�T�D�T | �P�R�D�W | �P�S�D�U | �S�D�S | �P�O�D�T | �P�Q�D�O | �P�Q�D�P |
�n�������k���ɂ����鏤�Ɨ͂̔�r�@�@�i�P�ʁ@���~�j
| ��@�@�@�@�� | ���@�@�_�@�@�� | ���@���@���@�� | �X�@�@�@�� | ���@�@���@�@�� | �k�@�w�@�R�@�� | |||||
| ���@�@�z | ���� | ���@�@�z | ���� | ���@�@�z | ���� | ���@�@�z | ���� | ���@�@�z | ���� | |
| �l���S�T�N�@ �i�l�j | �Q�O�C�R�S�T | �P | �P�R�C�Q�W�S | �R | �P�U�C�X�S�T | �Q | �P�O�C�Q�U�U | �S | �X�C�P�Q�T | �T |
| �l���P�C�O�O�O�l�����菬���X�ܐ��i�X�j | �P�R�D�U | �Q | �P�S�D�O | �S | �P�T�D�P | �T | �P�R�D�T | �P | �P�R�D�X | �R |
| ���@�Ɓ@�́@���@�� | �U�Q�V�C�U�P�U | �P | �R�Q�P�C�T�P�T | �R | �S�R�S�C�Q�P�V | �Q | �Q�X�P�C�W�S�U | �S | �P�W�V�C�V�P�X | �T |
| �� �@�́@ ���@ �� | �Q�T�V�C�Q�X�R | �P | �W�T�C�O�W�V | �R | �P�O�X�C�R�W�O | �Q | �U�Q�C�X�Q�W | �S | �S�S�C�P�R�O | �T |
| ���@���@�́@���@�� | �R�T�O�C�V�R�W | �P | �Q�O�X�C�V�U�X | �S | �R�O�O�C�O�T�P | �Q | �Q�P�U�C�W�R�Q | �R | �P�R�T�C�R�P�T | �T |
| �� �H �X �� �� �� | �P�X�C�T�W�T | �R | �Q�U�C�U�T�X | �P | �Q�S�C�V�W�U | �Q | �P�Q�C�O�W�U | �S | �W�C�Q�V�O | �T |
| �́@ �� �@�� �@�� | �P�V�D�Q | �R | �P�T�D�W | �S | �P�V�D�V | �Q | �Q�P�D�P | �P | �P�S�D�W | �T |
| �́@ ���@ �K�@ �� | �P�C�Q�U�U | �Q | �P�C�O�T�W | �T | �P�C�P�V�Q | �R | �P�C�T�V�P | �P | �P�C�O�U�U | �S |
| �J�@���@���@�Y�@�� | �R�X�T | �R | �R�Q�X | �T | �R�V�U | �S | �S�R�R | �P | �S�O�O | �Q |
�i�����̔����͂S�T�N�Ŏ����ԁE�Ζ��ނ������j
�@�������A�����E�H���i�i���E�č��������j�̎d���n�͔��َs�ւ̈ˑ��x�������ĂV�O�E�U�p�[�Z���g���߁A���ɖ�E�ʕ��̂X�W�E�R�p�[�Z���g�͑S�ʓI�Ɉˑ����Ă���悤�ȏ�ԂŁA�N���ł��U�U�E�V�p�[�Z���g���߂Ă������ł���ƕ��͂��Ă���B
�@����ɑ��A����҂̏��i�ʔ����ꏊ�̈ˑ��x���݂�ƁA����ґS�̂̂X�P�E�Q�p�[�Z���g�͒����̏��X�Ɉˑ����A���O�ւ̈ˑ��x�͂킸���W�E�W�p�[�Z���g�ƒႢ���A�ߕ��E�g�̂܂��i�ɑ��钬�O�ˑ��x�͂Q�O�E�S�p�[�Z���g�ƍ����A���̂������َs�ւ̈ˑ��x���P�T�E�U�p�[�Z���g���߂�ȂǁA����ғs�s�u��������������B���̑��Ƌ�E�Y�i���イ�j��ނ̂P�Q�E�W�p�[�Z���g�A�����i�̂P�O�E�T�p�[�Z���g�Ƃ������O�ˑ��x�͂��Ⴂ�Ƃ����邪�A���̂Ȃ��ł͔��َs�ւ̈ˑ��x����ԍ����A���O�ˑ��̂Ȃ��ł��s���o���̔�����Q�ʂ��߂Ă���ƕ��͂��Ă���B
�����̊T�v
�@�����������͂̂ق��A�������̍ו��ɂ킽�钲�����������ƂɁA���������̒n���̒��S���Ɠs�s�ƂȂ邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ́A���Ɍf����悤�Ȏ����������P�ɔᔻ���ďI��邱�ƂȂ��A����҂̂��߁A�����̂��߂ɁA���P�E���s����s���͂ł���Ƃ��Ă���B���̂����A���{������e�ɂ��ẮA�X�܂��ʂ̐ӔC�Ŏ��{������́A���X�X�������Ŏ��{���ׂ����́A�S���I���͂Ŏ��{������̂��悭����߁A���ꂼ��̕���œw�͂���ƂƂ��ɁA���s���E�w���@�ցE�W�@�ւȂǂ̋��͂ƁA�����̗������͂����߂āA�����̑厖�ƂɎ��g�ނ��Ƃ��K�v�ł���Ƃ��Ă���B
�@�����̂P�@���_�����Ƃ̓����Ɩ��_���@�����́A�n�������k���W���̂Ȃ��ł́A���Ɣ̔����E�����̔����E�����̔����Ƃ���P�ʂ��߂Ă��邪�A�����Ƃł́A�̔��K�́i���P�X������̔����j�A�̔������i���l���P�l�����菬���̔����j�A�J�����Y���i���]�ƈ��P�l�����菬���̔����j�Ȃǂɂ��Ă͂Q�A�R�ʂɂƂǂ܂��Ă���B�������A�S�P�N�x�ƂS�T�N�x���r�����̔����V�F�A�̐��ڂł́A�����ƁA�����Ƃ̂���������ቺ���A���̂Ȃ��ł��A�D���E�ߕ��E�g�̂܂��i����ш��H�X�ł͑啝�Ȓቺ�������Ă���B���̂����A���_���w���͂̂��������ւ̗��o�z�́A�T���W�U�T�T���~�i���_���w���͂̂P�T�p�[�Z���g�j�Ƒ��z�ł���̂ɑ��A�z���z�͂P���V�U�S�P���~�i���S�E�T�p�[�Z���g�j�ƒႢ�ɂ���̂ŁA���o�w���͂̋z������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝw�E���Ă���B
�@�����̂Q�@�o�c�ӎ��̍��V���@���_���̔̔����V�F�A�̐L�єY�݂̗v���́A����҂��n�����X�ɑ��閞���x���Ⴂ�̂ɑ��A�o�c�҂͏��i�E�ڋq�T�[�r�X�E�X�܂ȂǁA�̔��ɖ��ڂȊW���������ɂ��āA���ȕ]���������Ƃ����ӎ������w�E���A�e�o�c�҂͏���҂��u������o�c�ɉ��P���邽�߂̓w�͂��K�v�ł���Ƌ������Ă���B�������A���_���̏��Ƃ�n�������k���n��ɂ����钆�j�I�n�ʂɍ��߂悤�Ƃ���ӗ~���ア�悤�ł���A�����E���Ǝ҂��Ƃ��ɘA�ъ��ƐӔC�������߂�悤�A�L�����������߂Ă����K�v������Ƃ��Ă���B
�l���P�l������̔����@�@�i�P�ʁ@���~�j
| ��@�� | �����ƌv | �D���ߕ� �g�̂܂��i |
�Ƌ�� ���イ�� |
�� �H �X |
| �� �_ �� | �P�V�D�Q | �Q�D�P | �Q�D�O | �O�D�X |
| �������� | �P�T�D�W | �Q�D�W | �Q�D�R | �Q�D�O |
| �X�@�@�� | �P�V�D�V | �Q�D�W | �R�D�V | �P�D�T |
| �� �� �� | �Q�P�D�P | �Q�D�V | �Q�D�W | �P�D�Q |
| �k�w�R�� | �P�S�D�W | �P�D�X | �O�D�W | �O�D�X |
���_���̍w���͂Ə����̔����̍\��

�@�����̂R�@�{���ʂ菤�X�X�̖����ƍĊJ�����@���_�������̔����̂S�V�E�Q�p�[�Z���g�Ɩ��߂����߁A���S���X�X�̋@�\��S�����Ă���{���ʂ菤�X�X�ł͂��邪�A�����Ƃ��ɒ��S���X�X�@�\���ʂ������߂ɂ́A�v��A
�@�i�P�j�@�X�܉����E���X�X�̋ߑ㉻�E�������Ƃ̐��i�Ȃǂɓw�߁A���͂��鏤�X�X�Â�����s���B
�@�i�Q�j�@�L����������ڋq���z�����A���o�w���͂�n���ɉ�A�����邽�߂ɂ͊j�ƂȂ�X�܂Â��肪�K�v�ł���A���̋K�͂Ƃ��Ă͔���ʐςP�R�O�O�������[�g���O��A�N���S�A�T���~���x�̂��̂��K�v�ł���B
�@�i�R�j�@�����Ԍ�ʂ̑����ɑΉ����A�����ʐς̒��ԏ�m�ۂɓw�߂�ƂƂ��ɁA�w�O�n��̍ĊJ�����s���B
�@�i�S�j�@�ʌo�c�̋ߑ㉻��}��A����Ҏu���^�̌o�c�ɓ]�����邽�߁A�����X�܁A���i����̉��P�ɔz�ӂ���B
���ƂȂǂ������A���̐��i�Ǝ����ɓw�͂��邱�Ƃ��K�v�ł���Ɗ������Ă���B
�@�����̂S�@�������X�X�̐U�����@�������X�X�̌o�c�҂́A���Ȃ̏��X�X�ɑ��ĔߊϓI�Ȍ����������A�o�c�ӗ~������߂ĒႢ�Ǝw�E���A���̂��߁A���X�X�����S�ƂȂ��Ď��{���ׂ����ʂ̑�Ƃ��āA
�@�i�P�j�@�n��Z���̐H���i�E���p�i�E���̑��̐����K���i�ƃT�[�r�X�����ӔC�����o���A���ꂼ�ꂪ���X�̌o�c�ڕW���������A�ڕW�B���̂��ߌo�c�ӗ~�̍��V���g��}�邱�ƁB
�@�i�Q�j�@�X�܂̉����E���i�̒�Ȃǂɔz�ӁA�ߑ㉻��}�邱�ƁB
�@�i�R�j�@���͂��鏤�X�X�Â�����߂����ƂƂ��ɁA�������Ĕ̔����i�̐��Â���ɂƂ߁A�ӗ~�Ǝ��͂̂���ꍇ�͔��_�s�X�n�Ȃǐl�������n��ɏo�X�����Čo�c�̊g���}�邱�ƁB
�@�i�S�j�@�������X�X�Ŕ��W�̊��҂���Ȃ��Ǝ�ɂ����Ă͑��̋Ǝ�ɂ��i�o���A�o�c�̑��p����}�邱�ƁB
�Ȃǂ������A����ɒ�����Ƃ��āA�s���I�ɂ��Y�Ɗ�Ղ̐����ɓw�߁A���������̌����}�邱�Ƃ��]�܂��Ƃ��A����n�̊J���A�V�l�z�[���̌��݁A�X�ю����̊J���ȂǂɊ��҂����Ƃ��Ă���B
�@�����̂T�@�����Ƃ̐������@���_���́A���َs�E�D�y�s�̉����Ƃ̏����ɑ����Ă��邪�A���̂����ŐH���i�X�ɂ����锟�َs�Ɉˑ�����x�����͂���߂č����A�d����Ɋւ��镉�S�����ɏd����ԂƂȂ��Ă���B���_���͂��̒n��ɂ����铹�H��ʖԏ�̒��S�ƂȂ��Ă��闘�_�����A�n�������k���S��𗘗p�͈͂Ƃ���H���i�E���p�i���S�̉����Z���^�[�̐ݒu���]�܂����Ƒi���Ă���B
�@�����̂U�@�s�s��Ր����ւ̋������@���_���͓n�������k���n��ł͍ł��l���̑����s�s�ł͂��邪�A�K���������͂̂���s�s�Ƃ��Ă̐������\���ł���Ƃ͂����Ȃ��B���㔪�_�������̒n��̒��j�I���Ɠs�s�Ƃ��Ĕ��W���邽�߂ɂ́A�s�s�{�݂̐����ɑ��鏤�Ǝ҂̑S�ʓI�ȋ��͂��K�v�ł���Ƌ������Ă���B
�@�����̂V�@���X�X�ĊJ���^���̓W�J���@���X�X�J���͌X�̊�Ƃ�ꕔ�̋Ǝ҂����Ő��i�ł�����̂ł͂Ȃ��A��������������邽�߂ɂ́A���X�X�̘g�������čL�������ɌĂт����A�s���S���ҁA�W�@�ւ̗����A�\���ȋ��͂����߂�K�v������̂ŁA�[���^���𐄐i���A���Ƃ̌v������A�J�����Ƃ̐��i��}��g�D��݂��āA���Ƃ̐��i��}�邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ��Ă���B
�@��T�߁@���X�X�J�����i�ψ���
�ψ���̐ݒu�Ɗ���
�@�O�߁u���_���L�揤�Ɛf�f�v�̊����������_���H��́A����ϋɓI�ȋ�̍���������邽�߁A���a�S�X�N�i�P�X�V�S�j�X���Ɉψ���ݒu�̂��߂̏��ψ��������ď����ɒ���A�P�O���ɓ����g�D�Ƃ��āu���X�X�J�����i�ψ���v���������A�ψ����Ɉ䓛�[���I�C�A�����ɂ����鏤�X�X�J���̕��r�ɂ��Ď��₵���B
�@��������ψ���́A�ו������̂��߁A�i�P�j���X�X�ߑ㉻����i����E���엲��j�A�i�Q�j�������Z���^�[����i���E�L�����F�j�A�i�R�j�L�揤�ƌ��J������i���E��엘�i�j�̂R������\�����A�ϋɓI�ɏ��X�X�̋ߑ㉻�ƍĊJ���̕���ɂ��Č�����i�߂邱�ƂƂ����̂ł���B�����Ĉψ�����ъe����́A���ꂼ��ړI�ʂɐ�i�n�����@���Ă��̌��ʂɌ����������A�܂��A���_�������J���v��A���_���L�揤�Ɛf�f���Ȃǂ��Q�Ƃ��Ȃ��璲����i�߁A�T�P�N�P�P���S���ɓ��\�����o�����B
���\���̊T�v
�@�ψ���̒��������̂����悻���܂Ƃ߂Ă݂�ƁA���̂T�_�𒌂ɏ��X�X�̐U�������Ă���B
�@���_���́A�n�������k���ɂ������ʂ̗v�Ղɂ���A���j�s�s�����Ƃ��邽�߂ɁA�����̗����Ƌ��͂����߁A���H�Ǝ҂̉ʂ������������o���A�w���́E���H�͂����������s�g�D�ɂ��A�s���Ƃ��ĉ������ׂ������A���X�X���̂Ŏ��{���ׂ��敪�m�ɂ��Ȃ���A���i�̐��Ƃ��āA�i���́j���X�X�U���ψ�����������A���̉��P��Ɏ��g�ނׂ��ł���B
�@�i�P�j�@�{�����X�X�̍ĊJ���́A�����T�����̃o�C�p�X���������ɍ��킹�āA�ϋɓI�ɐi�߂�ׂ��ł���B
�@�i�Q�j�@�V�����w�Ɩk�C���c�ѓ��H�̌��݂����҂��A�V�������X�X�`�����s���ׂ��ł���B
�@�i�R�j�@���_�E�F�ΐ��A���_�E�������̑��������𑣐i���A�������ʂ̒��S�����Ƃ��Ă̖������ʂ������߁A���ʋ@�\�̐������P���s���ׂ��ł���B
�@�i�S�j�@���X�X�̉����́A���X�X�݂̂ɂƂǂ܂炸�A���Ɣw�i�̐����Ɠs�s�v��̒��a��}��A���S�̂̋ߑ㉻���s���ׂ��ł���B
�@�i�T�j�@�ߔN��ƗU�v�⎩�q���̒��Ƃ�ɂ��l���̑����Ə���o�ς̐��������҂����ɂ��������āA�n������o�ό��ɊO�������^�X�̐i�o���z�肳���̂ŁA���Ǝ҂̘A�шӎ������߁A���}�ɏ��X�X�̋ߑ㉻��i�߂�ƂƂ��ɁA�O�����{�̐i�o�ɑΏ����邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@����ɁA�e����̕����݂�ƁA���X�X�ߑ㉻����ł́A�i�P�j�������T�����ɖʂ���{�����X�X�̍ĊJ���A�i�Q�j�V�����w�Ə��X�X�A�i�R�j���y�c�ѓ��H�ƃC���^�[�`�F���W�A�i�S�j���q�����Ƃ�Ə��X�X�A�i�T�j���_�F�ΐ��A���_�������̐����A�i�U�j��ƗU�v�Ə��X�X�̂�����A�̂U�_�ɂ��ďq�ׁA�����𐄐i���邽�߂ɂ́A������݂̃v���W�F�N�g�`�[����Ґ����ď��X�X���̂̎��Ǝ��{�c�̂������A�P�����������ƒ��肪�K�v�ł��낤�Ƃ��Ă���B�����āA�s�����ɑ��鑁�������v�]�����ƁA���X�X���̂Ŏ��{���ׂ������ނ��ċ�̓I�ɋ����A���ꂼ�ꑣ�i����������̂Ƃ��Ă����B
�@�܂��A�������Z���^�[����ł́A���_���ɂ͗��ʂ̍�������ړr�Ƃ������c�̉����s�ꂪ�Ȃ��A���v�x�̍������N�H���i����p�i�ɂ��ẮA���̑啔���قɈˑ����Ă��錻��݂āA���ʃZ���^�[���K�v�ł��邪�A���_�������̐l���ł͐������Ȃ��ƍl������̂ŁA�w��n�̐l�������z�����邽�߁A�k���w�R�Ⓑ�������ȂǏ���̊g�傪�K�v�ł���Əq�ׂĂ���B�����āA���̗��ʃZ���^�[��ݒu���邽�߂ɂ́A��^�①�ɂƒ艷�q�ɂ��K�v�ł��邪�A���z�̎����Ɨp�n�̊m�ۂȂǁA����Ȗ�肪���݂���̂ŁA���ʂ͔��ٗ��ʃZ���^�[�̃T�u�Z���^�[�ݒu����n�߂邱�Ƃ��]�܂����ƕ����B
�@�Ō�ɍL�揤�ƌ��J������ł́A���_�����Ƃ̓����̕��͂Ɩ��_�̉𖾂ɓw�߁A�����̉����E���P��}�邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ��������A���_�����Ƃ̔w�i�����Ƃ��āA�i�P�j�Z���̋����A�i�Q�j�Љ�{�̏[���A�i�R�j��ʗ��ւ̌���A�i�S�j�_�Ǝ҂̏�������A�i�T�j�������̑��o��@�ւ̏[���g��A�̂T���ڂ������Ă���B�����āA���H�Ǝ҂ɍĊJ���̈ӗ~���N��������ƂƂ��ɁA�w���@�ւƎ��{��̂Ƃ��Ă̑g�D���m�����A�����̗͂ɂ���ĐϋɓI�Ȏ��g�݂��K�v�ł���Ƌ������Ă����B
�@�Ȃ��A�ψ���͂��������A�u���X�X�ĊJ���̒���āv�Ƃ��āA�w���́A���H�͂������c���g�D���ē����҂��������₷���g���g�D����i�߁A�X�̑g���P�ʂʼn��P������āA���P�ɒ��肷�鐄�i��̂ƂȂ�A�����Ȑςݏグ�����ł������s���A���̂�����p�m�����W���p���w�͂��Ă����ׂ��ł���ƒ����B
�@�����������\�������H��ł́A���a�T�P�N�i�P�X�V�U�j�P�P���P�P���Ɂu���_�����X�X�U���ψ���v��g�D���A���̖��ɐ^�����ʂ�����g�ޑ̐���z���Ă���A���̊����Ɛ��ʂɊ��҂����Ă���B
�@��U�߁@���ƒc�̂̐���
���H�g���̐ݗ�
�@�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�P�P���ɓS�����J�ʂ��A�ڏZ�҂���������ɂ�ď��X�X�̌`�����}���ɐi�B����ɁA�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�ɂڂ���������ꎟ���E���̓����ɂ��A���炭�D�����オ���������߁A���X�X��������悷��悤�ɂȂ����B�������A�U�N�Q���Ɂu�L���ӔC���_�M�p�w���g���v���ݗ�����čw�����Ƃ��g�������ɂƂ��Ȃ��A�_�Ƃ̍w���͂͑g���ɏW�����͂��߂����߁A�s�X�n�̈�ʏ��X�ւ̉e���͏��Ȃ��Ȃ������B�����������Ԃ�ŊJ���邽�߁A�吳�V�N�ɏ��X�X�L�u�̋��c�ɂ���āu���_���H�g���v��ݗ��A����g�����ɔ~�����\�Y��I�C���A���X�̌o�c�w���Ɗ�Ղ̋����ɓw�߂��̂ł���B�P�P�N�ɂ͗�؉i�g���Q��g�����Ƃ��Ă�����p���A�g���͑��I����ɂ�����o�ϋ��Q���ォ�珺�a�����̕s������ɂ����āA���H�ƐU���̂��߂ɐs�������̂ł���B
���_���H���z�������g���܂�
�@���a�P�Q�N�i�P�X�R�V�j�V���ɓ����푈���ڂ����A�����̏���K���A���i�̌��艿�i�̐ݒ�ȂǁA���ƌ`�Ԃ͐펞�̐��ւƋ}���ɓ]�����Ă������B�܂��A����ƑO�サ�Đ��{�̑ł��o�����g���������j�ɉ����A�]���̏��H�g�������U����ƂƂ��ɁA���N�W���ɂS�X���̓��ӏ��������ď��H��K���i���a�S�N�k�C�����߁j�ɂ��u���_���H��v�̐ݗ��ɂ��ē��������̔F���A�X���Q�O��������s���A��ɂ͗�؉i�g���A�C���A���߂Ă̌��F���H�c�̂Ƃ��Ċ������J�n�����̂ł���B
�@�������A�����푈���������̗l����悷��ɂ�Čo�ϓ����͂܂��܂���������A���̉e�����܂Ƃ��Ɏ����H�Ǝ҂́A�������i���̑��������̌��R��ꕔ�����̐ؕ����̎��{�ɂ���ĉc�Ƃ̋x�~�A�p�Ƃ܂��͏k����]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł���B���̂��߁A�펞�̐����ɂ�镨���̎��������̉~�����Ɣz�����������ɑ������āA���a�P�S�N�S���ɗ�؉i�g�E���J��r�V���E�n�ꖖ�O�Y�E����l�Y�E�����`���E�쑺�^��E�͖앐��E�Ԓ˗^���E���J��y�O�Y�E�M���r�O�Y�E��������P�P�������N�l�ƂȂ�A���ɔz���ɊW�̐[����ʏ��H�Ǝ҂ɌĂт����āu���_���Ƒg���v�̐ݗ����͂���A���N�X���Q�W���F���ĂP�O���S���ɓo�L�������A�������͒������g���猚���R��������ď[�����A�P�O���Q�Q����؉i�g�𗝎����Ƃ��Ĕ��������̂ł���B
�@�Ȃ�����Ɠ����ɁA�����ɐݗ����ꂽ���_���H��͎��ǂ̋ٔ����ɂ���Ċ����𐧖�A���H��Ƃ��Ă̋@�\������Ɏ����ėL�������ƂȂ�A���x�I�ɂ͏��a�P�W�N�i�P�X�R�S�j�U���A���H��K�����p�~���ꂽ���Ƃɂ�莩�R���ł����B
�@���̂悤�Ȍo�܂ɂ���Đݗ����ꂽ���Ƒg���́A�M�p�]��ψ��E�c�Ɠ����ψ��̐��x��݂��Đ펞�����o�ω��ɂ����鎖�Ƃ̉^�c�ɓ����������A�P�T�N�ɗ�ؗ����������C���ď���l�Y��������p���A�͖앐�ꂪ�햱�����ɏA�C�����B���a�P�U�N�ɑ����m�푈���ڂ������Đ�����g�傳���ɂƂ��Ȃ��A�푈���s�A���������̂��߂Ɋ�Ɛ������i�߂��A�P�X�N�V���ɂ͂���܂ł̏��Ƒg�������U���A���悢��펞�F�Z���ȁu���_�z�������g���v�ɉ��g����A�g���͕����ǂ��蕨���̔z���Ɠ����o�ς̎{�s�@�ւƂ��Ĉʒu�t�����Ă������̂ł���B
���_���Ƌ����g��
�@���a�Q�O�N�W���I����}�����킪���́A�ɒ[�ȕ����̌��R���������A���̂��߈ُ�ȃC���t���[�V�����ƂȂ�A��㐔�N�Ԃ��g����蕨�h�̎��オ�������B����������ł́A�����Ǝ҂̕����ɂ���Ĉ�ʏ��i���o���悤�ɂȂ�ƁA���ƌo�c������ɉ��A�펞�������Ă������X�̍ĊJ���݂��͂��߂Ă����B���̂悤�Ȏ��@�̂Q�Q�N�P���A�u���H�����g���@�v�����z�{�s����A�z�������g���̉��U�ƐV���ȏ��Ƌ����g���̐ݗ����������ꂽ�̂ł���B���̂��߁A�Q��̔��N�l����o�ē��N�Q���P�T���u���_���Ƌ����g���v�̐ݗ������߁A�������ɏ���l�Y�A�햱�����ɏ��쉳����I�C�A�g�����W�W���ɂ���Ĕ��������̂ł���B���̌�A�Q�S�N�U�����z�́u������Ɠ������g���@�v�̎{�s�ɂ���āA���Q�T�N�ɏ]���̑g�������g���ĐV���ȏ��Ƌ����g���ƂȂ����B�������g���̉^�c�́A���H�Ǝ҂��ׂĂ�g�����Ƃ��������g�������ɓO���邱�Ƃ��ł����A���G����ɂ킽�钆���Ǝ҂̗v���ɑΉ��������̂Ƃ́A�K�����������Ȃ��̂����Ԃł������B���̂��ߑg���̎��̂́A�₪�đg�D������q�̏��H��ֈڍs����Ƃ���ƂȂ�A���R���ł̌`�ƂȂ����̂ł���B
�@�Ȃ��A���a�Q�T�N�V���ɂ́A������Ǝ҂ɂƂ��đ傫�Ȗ��ł������Ŗ��E�o���E����E�J���E�@�K�E�o�c�E���Z�ȂǁA��X�̕���ɂ킽���Ė������k�ɉ����A�����o�c�҂̌[���@�ւƂ��āu���_������Ƒ��k���v�i���㏊���E����l�Y�j���A���Ƌ����g�����i�̂����H��Ɉڍs�j�ɊJ������Ă����B
���_���H��
�@���P�O�N���o�����a�R�O�N�����Ƃ��āA�킪���̌o�ς͂悤�₭�������ɓ���A��Y�Ƃ̈琬�ɏd�_��������A������ƂɂƂ��Ă͈ꕔ�d���w�H�Ɗ֘A����������A��ʓI�ɂ͘J���͂̋z���⎑���J��̍���Ȃǂɉe������č������A�ߑ㉻���W�����A���ƂƂ̊Ԃ̐��Y��������i���͂܂��܂��g�傷��X���������悤�ɂȂ����B
�@���̂��߁A�������H�Ǝ҂őg�D���鏤�Ƌ����g���̎��Ԃ��A���̗v���ɑΉ��������̂Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ������̂ŁA�e�n��̏��H�Ǝ҂͎���̐����Ɗ�Ƃ�h�q���邽�߁A�Q�S�N����Q�U�N�ɂ����āA�e�n�ɔC�ӂ̏��H�c�̂�ݗ�����@�^���݂�ꂽ�B�����ɂ����Ă��������������ɑ������^�c�����������āA�L�����H�Ǝ҂̌o�c�Ɛ����̈����}�邽�߁A���a�Q�W�N�i�P�X�T�R�j�U���P�P���ɔC�Ӓc�̂ł͂��邪����Q�P�O���������āu���_���H��v��ݗ������B�����āA��ɏ���юl�Y�A����ɕ��������A���J�썎�����A�C�A�Q�X�N�P�O���ɂ͋����Ƌ����g�����玖����������ĊJ�݂��A���悢�揤�H�ƊE���W�̊�Ղ��z���ꂽ�̂ł������B
�@���̌�͎����ɑ����������ɐ��ʂ��グ�A���a�R�R�N�S���u�Вc�@�l���_���H��v�Ɖ��g�������A�R�T�N�P�P���u���H��̑g�D���Ɋւ���@���v���{�s����A���R�U�N�X������Ɋ�Â��V�g�D�ł���u���_���H��v�̐ݗ�������J�Â����B�����āA��A����͏]�O�ǂ���I�C���邱�ƂɌ��߁A�m���F�̂��ƂP�P���S���ɓo�L���������Đ����ɔ��������̂ł������B���g�����̏��H�Ǝ҂V�V�U���ɑ��A������͂R�V�R���ŁA�\�Z�K�͂͂R�O�O���~�ł������B
�@�������ď��H��́A���H��c���ƕ��ԓ���@�l�ƂȂ�A�n��I�ȑ����o�ϒc�̂Ƃ��ď��H�ƊE�̌��S�Ȕ��W���߂����A�o�c��������𒆐S�Ɍ����Ȋ�Ռ`���ƁA�����҂̕����������Ƃ𐄐i����ق��A�o�c�w�����ɂ��X�̑��k�A���邢�͏��k�A���H�ƐU���ɑ���u�K��̊J�ÁA���Z��������ȂǁA��苭�͂Ȋ�����W�J���邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�����_���H��i�ʐ^�P�j

�@�������A���̂悤�ɑ̐����������ꂽ���H��ł͂��邪�A�����������玖�����ɓ��ĂĂ����������V��������ƂƂ��ɋ����Ȃ��Ă������߁A�ߑ�I�ȏ��H��قւ̉��z��]�ސ������܂�A���a�S�R�N�i�P�X�U�W�j�T���̑���ɂ����āA�S�T�N�x���{��ڕW�Ƃ����ٌ��ݕ��j���m�F���ꂽ�B���̌�����Ɉψ����݂��A�ʒu��K�͂Ȃǂɂ��Č����������A���ʒu�ɉ��z���邱�ƂɌ��肵�A�ꕔ�S�R���N���[�g�Q�K���āA���זʐςS�O�Q�������[�g���]�A���H��Q�O�W�O���~�������ĂS�T�N�T���ɒ��H�A�W���Q�O�����������B���ł͏��H��̊����Ɋ��҂��āA���z��ɑ��U�T�O���~��⏕�����̂ł���B
�@�Ȃ��A�����ƕ��s���ď��H������������邽�߂̉����@�\�Ƃ��āA���a�R�W�N�ɐN���A�S�V�N�ɕw�l����݂����ق��A�S�O�N�ɂ͉�̊����Ɩ��ڂȊW�����u���_�ό�����v�̐ݗ���̂ƂȂ�ȂǁA�����ɂ����鏤�H�Ƃ̒����@�ւƂ��Ă̋@�\���ʂ����Ă���B
�@���a�T�T�N�x�ɂ����������͂T�Q�T���i����ʕ\�j�𐔂��A�S���H�ƎҐ��̂V�O�p�[�Z���g�A���K�͎��ƎҐ��̂V�T�E�T�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă���B
�@�܂��A���a�T�T�N�T���̖������I�ɂ���Đ��������ւ��A��ɕ��������A����ɒ��J��M�Y�ƎR�����F���I�C����A�ق��ɗ����P�T���A�Ď��Q���̖����ƁA���R�v�����ǒ��ȉ��W���̐E���ɂ���ĉ^�c����Ă���B
���_���H��i�ʐ^�P�j

�Ǝ�ʉ���i�T�U�N�R���R�P���j
| �敪 �Ǝ�� |
���H�� �ҁ@�� |
���K�� ���ƎҐ��@ |
����� |
| ���@���@�� | �U�V | �U�Q | �T�X |
| ���@�݁@�� | �W�S | �W�O | �V�W |
| ���@���@�� | �Q�V | �P�W | �P�W |
| ���@���@�� | �Q�V�V | �Q�V�O | �P�W�R |
| ���@�H�@�� | �X�P | �W�X | �V�V |
| ���Z�ی��� | �P�U | �S | �R |
| �s �� �Y�� | �S | �R | �P |
| �^�A�ʐM�� | �P�U | �X | �S |
| �T�[�r�X�� | �P�R�W | �P�R�Q | �W�P |
| ���@�́@�� | �R�Q | �Q�W | �Q�P |
| �v | �V�T�Q | �U�X�T | �T�Q�T |
�i�����@���a�T�U�N�x�ʏ푍���c�āj
����̏͑O�y�[�W�̂Ƃ���ł���B
�����ɂ����鏤�H�c�̂̐���
�@���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�P�P���ɉ��c�@�g�E���c�����Y�E�����P��E���J��M�`�̂S�������N�l�ƂȂ��āu�������H�g���v�̐ݗ����v�悳��A���R�N�R���g�����Q�O���������Ĕ����A����g�����ɉ��c�g���A�C���A�g�������݂̐e�r�����ƌo�c�̉��P����ɏ��o�����̂��A�����ɂ����鏤�H�g�D�̎n�܂�ł������B
�@���������̌�A�����푈�̂ڂ����ɂ���ċ������ꂽ�o�ϓ����̉e�����A�]���̂悤�Ȋ������ł��Ȃ���ԂɂȂ������Ƃ́A���_���̏ꍇ�Ɠ��l�ł������B���̂��߁A����ɑ��������V�g�D�̕K�v����F�߂��L�u�̔��N�ɂ��A���a�P�S�N�P���u���������Ƒg���v���n�݂���A�g�����ɐ����P�ꂪ�A�C���ĐV���Ȋ����ɓ������̂ł���B
�@����ɁA�����m�푈���ٔ��̓x���������P�W�N�W���u�������z�������g���v�ɉ��g�������A�펞�������ɂ����镨���z���̎{�s�@�ւƈڍs���Ă������̂ł���B
�@���A���a�Q�Q�N�P���ɏ��H�����g���@�̎{�s�ɂ��A���N�Q���ɂ���܂ł̔z�������g�������U���āu���������Ƌ����g���v���g�D����A�g�����Ɋ��K���Y���A�C���Ĕ��������̂ł������B���N�T���g��������ւ��ē��c���Y���A�C�A���̌�A������Ɠ������g���@�ɂ��葱�����o�Ĉȗ��A��т��Ă�����ێ��p�����A�ꕔ�H���i�̋����d����A�����@�\�Ƃ��Ă̖������ʂ����g�����̕։v��}���Ă����̂ł���B
�������Ƌ����g���i�ʐ^�P�j

�@���a�R�Q�N�ɒ���������A���̍s�����͈�{�����ꂽ�̂ł��邪�A�g�����̂��̂͗����n�揤�H�Ǝ҂�ΏۂɂȂ��p�������B�������A����̐i�W�ɂ���ď��i�d����̂�����ɕω��������炵�A�g�������ɑ���ˑ��x�����X�ɏ��Ȃ��Ȃ�A�������A���_���H��ւ̉������������ꂽ���Ƃ������āA���c�g�����͂��̑g���̉��U�����ӂ��A�g�����Q�V�����ӂ̂��Ƃɏ��a�T�R�N�P���������Ē������j�ɖ������낵���̂ł���B�������ė����n��̈�ʏ��H�Ǝ҂́A�������_���H��ɉ������A�L���n��o�ς̔��W��ڎw���Ċ����𑱂��Ă���B
�@��V�߁@���Z�@��
�k�C����B��s���_�x�X
�@�����ɂ�������Z�@�ւ́A�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�P�O���ɐ݂����k�C����s���_�h�o�����͂��܂�ł���A���㏊���ɏ���ЎO�Y�����C���ĊJ�Ƃ����B�����ĂP�Q�N�P���Q�W���ɂ͑������o�����ɏ��i�A����ɁA���Ƃ̐i�W�ɂƂ��Ȃ��P�T�N�W���Ɏx�X�ɏ��i���A���a�T�N�i�P�X�R�O�j�X���ɂ͌��{���Q�T�P�Ԓn�ɓX�܂�V�z���ċƖ����g�������B
�@���a�P�X�N�X���ɖk�C����s���k�C����B��s�֍����������߁u�k�C����B��s���_�x�X�v�Ɖ��̂��A����ɁA�Q�T�N�P�O���ɂ͒������o������ғ����ċƖ��͈͂��g�������B���a�Q�W�N�P�P���{���Q�U�T�Ԓn�Ɍ��Q�V�O�������[�g���]�̓X�܂�V�z�ړ]���A�Ɩ������̐��̍��V��}����݂Ɏ����Ă���B
�k�C����B��s���_�x�X�i�ʐ^�P�j

�k�m����s���_�x�X
�@���a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�X���ɁA���ٖ��s������Д��_�o�����Ƃ��Č����L���P�T�Q�Ԓn�ɊJ�݁A���㏊�����엘���������ĊJ�Ƃ����̂����̑O�g�Ƃ���B���̌�A�P�X�N�R���ɑ�B�E���M�E�k���{�Ȃǂ̊e�Ђƍ������k�m���s������Д��_�o�����ƂȂ����B���a�Q�U�N����s�@�̎{�s�ɂ��A���N�P�O���k�m����s���_�x�X�Ɖ��̂����B�Q�W�N�W���ɂ͖{���Q�Q�R�Ԓn�ɓX�܂�V�z�ړ]���A�Ɩ��̊g���ɔ������݂Ɏ����Ă���B
�k�m����s���_�x�X�i�ʐ^�P�j

�n���M�p���ɔ��_�x�X
�@���a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j�P�Q���ɓn���M�p�g�����_�x���Ƃ��āA���㏊�����쒉�Y�������ĊJ�Ƃ����̂��n�܂�Ƃ���B�Q�U�N�P�O���M�p���ɖ@�̎{�s�ɂ���ēn���M�p���ɔ��_�x�X�ƂȂ�ƂƂ��ɁA�������Z���ɁE������Ƌ��Z���ɁE�Z����Z���ɂȂǂ̑㗝�Ɩ�����舵���Ă���B
�@�Q�V�N�P�O���{���P�P�Q�Ԓn�ɓX�܂�V�z�������A���̌�T�Q�N�ɂ͖{���Q�O�X�Ԓn�ɋߑ�I�ȓX�܂�V�z�ړ]���A���݂Ɏ����Ă���B
�n���M�p���ɔ��_�x�X�i�ʐ^�Q�j

��T�́@�H��
�@
�@��P�߁@����ƊJ���n�ƍH��
���ƂƂ��Ă̐��ԁE����
�@����ƊJ��������̑n�ƈȑO�ɂ�����H�ƂƂ��ẮA�킸���ɒP���Ȑ��Y���H�炵�����̂��c�܂�Ă������x�ŁA���Ɏ��グ��悤�Ȃ��̂͂Ȃ������B�J��������ɂ����đ�P��̎m���ڏZ�҂ɑ���_�Պ����Ə���̂��߁A�V�c�w���q�𒆐S�ɐ��Ԃ��s�킹���̂��A�����ɂ�����H�Ƃ̏��߂Ƃ������Ƃ��ł��悤�B���Ȃ킿�A�ڏZ���X�̂P�P���A��������ɉ����ԏ���ݒu���A�J��g�ɋ��t�P���̔h����v�����ċZ�p�̏K���ɂƂ߂������̂ł������B���������ɂ����ẮA���ƂƂ͂����A����Ɂu���ԋK���v��݂��A�K�i��i�P���Ȃǂm�ɒ�߂ďA�Ƃ������̂ł���B�����Đ��i�́A
�@�c�O���ځ@���\�ڊ|�@�ڂɕt�@�����l�K
�@�\�߁@���\�ڊ|�@���f�ɕt�@�����ܑK
�@���@���S�ڊ|�@���f�ɕt�@�����\�K
�ƒ�߂Ċe�˂����Ԃ������̂��W�߁A����ɁA
�@�בO�J�ԁi�c�O���ډ��\�ځj��\�܊�
�@���@�ܖԁi�c�ꐡ�ډ��\�ځj�l�\��
�@���܂������ԁi�c�\�߉��S�ځj��\�܊�
�Ƃ����K�i�̖ԂƂ��Ē����Ɏg�p�ł���悤�ɍ��ꂽ�B���i�͊J��g���َx�����Ɖۂ̍�����A�ꔽ������j�V���O�J�ԂłV�~�R�V�K�R�ЁA���ܖԂłP�Q�~�V�V�K�A���܂������ԂłP�R�~�U�T�K�S�ЂƂ���Ă����B�������āA�P�T�N�ɂ̓j�V���Ԃ̐����͓�Z�ܘZ�Ԃ𐔂��A�O���ɏ��������̂ł��邪�A���ǂ͂��ꂪ�ō��ŁA���̌�_�Ɗ�Ղ��m�������ɂ��������Đ��ԔM������Ɍ��ނ��A�P�W�N�ȍ~�͑S���݂��Ȃ��Ȃ����B
�@�܂��A����Ɠ����Ɏn�߂�ꂽ���̂ɐ���������B�����P�Q�N�W���ɊJ��g���琻�����t�P���̔h�����Ă�����K�����y���������A���P�R�N�ɂ͖Ԏ��юl�Z�Z����Y���A�O�r�Ɋ�]���݂�ꂽ�B�����Ŏ�����ł́A���P�S�N�ɖ���������ݒu����ȂǗ͂𒍂��A�P�T�N�ɂ͎O�O�O�шꎵ�O����̖Ԏ����������ꂽ�̂ł��������A��������ԓ��l�ɁA�_�Ɗ�Ղ̏[���ɂ��������Đ������A�P�W�N�ȍ~�͑S���p���������̂ł���B
�������̋�
�@�����A���̍�t��������ɍs���Ă������߁A�J���n�������̒��c�ɂ�薾���P�V�N���琻���̋Ƃ��n�߂��Đ��Y�����X�ɏオ��A�Q�R�N�ɂ��g蒅�i�������j�h�ꔪ�Z�Z�т��Y�����B���������傤�ǂ��̂���A�h�C�c���牻�w�������A�����ꂾ���Ď��v�����ނ������Ƃ�����A�Q�S�N�ɂ͈��Z�Z�тɌ��Y���A�������Q�T�N�ȍ~�͂قƂ�njڂ݂��Ȃ���ԂƂȂ����B
�@�Ȃ��A�����P�T�N�ɒґ���������������ł�Ղ��@����ꂽ���ƁA�P�V�N�ɊJ���n�����������c�ōs�����ł�Ղ�̐��������邪�A����ɂ��Ă͔_�Ƃ̍��ŏڂ����q�ׂ��B�܂��A�P�V�N�P���ɂ͓������J���n�������̒��c�ɂ���āA�݂��E���傤��̐������n�߂����A����ɂ��Ă͎��߂ł��炽�߂ďq�ׂ邱�ƂƂ���B
�n�b�J�̐���
�@�ڂ����L�^�͂Ȃ����A�����Q�O�N��ɓ���ƊJ���n�Ŕ��ׁi�n�b�J�j�͔̍|�����コ��A�Q�P�N�Ɏl�E�������̍�t��������A�������s��ꂽ�Ƃ���Ă��邪�A�C�ۏ������K���Ȃ��������Ƃ������Ă��܂�L�W�����A�Q�T�N�ɂ͑S���p�~�����Ƃ����B
�@�����n�b�J��������Ƃ��Ďg�p���ꂽ�Ƃ�������i���ԂƂȂׁj�i�ꖼ�������r�L�Ƃ����j���A�����y�����قɕۑ�����Ă���B���̊���ɂ��Ĕ��ق̍l�Êw�Ҕn��@�����������u�y��̌����v�̒����g���{�k���n��y�ѕ��ߊO�n�o�y�́u�����y��v�ɂ����h�Ƃ��Ď��̂悤�ɏڏq���Ă���̂ŁA�����̃n�b�J�����̎�����m���|����Ƃ��Ă����ɗg����B
�@�R�`�����u���S�̊���i�ꖼ�����r�L�j
�@�k�C���_�U�����_���̓���`�e�̌o�c���铿��q��̒ɕۑ�����Ă���l�����̓����̉~���^�̓�ł����āA�{�i�͔��_���̌ØV�p�c�ǁi�}�}�j�F�i��F�̂��ƂƎv����j���̐����ɂ��ƁA�������N�t�A�R�`�����u���S�{��������^���Ȃ�l�̐��E�ɂāA�����t�g�Ȃ�l�������̍ێ��Q�������̂ŁA�p�c���̋L���ł͈ꖇ�����������ŁA����͒ʏ̊���ƌĂ�Ă�����̂ŁA�������ׂ��̂����ۂ̗�p���u�̈�Ƃ��Ďg�p�������̂œ璆�ɗ␅��X������ė�p���Ĕ��ב��̏��C���~���^�̓��ɐG���Ɛ��H�ƂȂ��ĉ����̗e��ɓH���l�ɂȂ��Ă����Ƃ������ł���B��̒��a�͓�ړܕ��A�[���͋㐡�ܕ�����A�ꕔ�͉~���^���Ȃ��A��̎��͂ɂ͕��ꐡ���̉���L���A���͑��Γ��A�����l�����̂��̂ŁA�㉏��菭���������ɕ�����Ă���B���Ǝ��̋����͎O���������āA�����̂��̂͑O�q�̓����S��̕��̗l�ɎO�p�̓�ӂ��Ȃ��l�ɕ�����A��[�Ɖ��[�̋����͈ꐡ�A�����͎������ł���B
�@��Q�߁@������
��
�@�����ɂ�����̗��j�͌Â��A�����P�P�N�i�P�V�X�X�j���{�ɂ�铌�ڈΒn�̒�����A�A�C�k�̕��i�ԁj��ɕK�v�Ȏ��̌��n���������݁A�R�z���̎�����͔̉ȂɊ��c�̎���݂����̂������Ă͂��܂�Ƃ���B
�@�����U�N�i�P�W�O�X�j�����́u�R�z���ꏊ���Ӓ��v�̒����g���h�Ɋւ���L�^�ɂ��A����������i�V�T�j�A�𑠁i�V�T�j�A���i�R�U�j�A���ԏ����i��Z�ԁj���e�P�������Ă�ꂽ�����K�͂̂��̂ŁA�|�葍���P�Q�l�ŁA�암�唨����o�����z�N���Ă����Ƃ���Ă���B�܂��A���N�́u�ڈΓn�C�L�v�ɂ��A�@�u�댬�@���Ԏj�p�v
�Ƃ���A����ɁA���V�N�́u�ڈΒn���X���ʐ}�v�ɂ��A
�@�u�ƈꌬ�@���ԉ��ꌬ�@���n�j�p���v
�ȂǂƂ��̌������L�^�������̂����邪�A��������������ɂ��Ă͋L�^���Ă��Ȃ��B
�@�������A�����T�N�i�P�W�T�W�j�́u�ڈΎ��n���l�^�v�̒��̈�߂ɁA
�@�u���萼�k�ܒ��A������͐̓��z���@�����A��̓��ɔ������L���̖̂���B��b�P�����B�v
�Ƃ���A���̂���͎��͔p�~����Ă����悤�ł���B
���������Ёi�ʐ^�P�j

�@���̌サ�炭���̏����݂͂��Ȃ��������A�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�ɏ��쏕���Y���A�V�y�����̂����ƂŐ������n�߁A���̔N�������Δ��l�����A���傤���イ�Z�l�O���l���������A�����R�R�N�ɂ͖����g�j���h�g���_���h�ȂǂƖ��t���Ďs��ɏo�����B����ȗ��A���N��Z�Z�Έȏ���������āA�吳�T�N�i�P�X�P�U�j�̑�O��k�C����ޕi�]��œ��v���l�����A�i���D�G�Ƃ��Đ��������߂��B����ɁA�吳�W�N�ɂ��g�V�y���h�̏��W�o�^���čL���e���܂�A���a�R�O�N����ɂ͔N�Y���Z�Z�قǂ̏����𑱂��Ă������A�₪�Čo�c��Ɋׂ������ߏ��a�R�T�N�Ɂu���H�v�i�{�Ћ�m�Ǔ��V�\�Ð쒬�j�ƒ�g���āA�������u���H�v�Ɖ��߁A�N�ԂQ�R�O�L�����b�g���Y���ē���s����J���̂ł������B���̊ԁA�S����ޕi�]��ɂ����āA�����ΗD�Ǐ܂����ق��A���a�S�O�N�̑S�������ӕ]��ł͓����ł�����_�����I����ȂǁA�i���̗D�G���͍L���F�߂��Ă����B�������A�S�O�N�ȍ~�ƊE�̋��������ɂƂ��Ȃ��o�c��Ջ����̂��߁A���H�Ƃ̊֘A�ɂ����ē����ł̐��Y�𒆎~�����ނȂ��Ɏ������B�����Ă���܂ł̐��Y�g�Q�R�R�L�����b�g���́A�����i�{�Г����j����H��ƒ߃���i�{�А_�ˁj�Ɉϑ��������邱�ƂƂ��āA���a�S�Q�N�i�P�X�U�V�j�ɂ́A�n�ƈȗ��U�V�N�̗��j�ɏI�~����ł����̂ł���B
�@�Ȃ��A����Ƃ͕ʂɖ����R�P�N�i�P�W�X�W�j�ɍ匴�����A�ł�Ղ���Ƃ����낱���������Ƃ��āA�A���R�[���̐��������݂����A�L�C���������܂��ł����A�܂��A�ŋ��������������ߐ������Ȃ������Ƃ������������Ƃ����B
�݂��E���悤��̏���
�@�݂��E���傤��̏����́A�����P�V�N�i�P�W�W�S�j�P���ɓ���ƊJ��������̌o�c�ɂ��A����̎��v�ɉ����Ď������邽�ߊJ�n���ꂽ�̂��͂��܂�ł���B�������A����͂����܂ł��������x�ɂƂǂ܂���̂ŁA���ƂƂ��Ĕ��W���邱�Ƃ��Ȃ��A�ǂ̂��炢�p�����Ă����������炩�ł͂Ȃ��B
�@�吳�S�N�i�P�X�P�T�j�ɑ�c���O�Y���݂��i������j�A���傤��i�T�b�����j�̏������J�n���A�吳�X�N�ɂ݂͂��܁Z�Z�сA�R�T�O�~�A���傤���ܘZ�A�V�O�Q�O�~�Y����قǂɔ��W�����Ă����B
�������X�ݖ������i���j�i�ʐ^�P�j

�@�����ő吳�P�Q�N�Ɂi�����P�j�������X醬�����������A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�ɂ́i�����Q�j�������X醬�������̔������A����ɁA�T�N�ɂ́i�����R�j���얡�X醬�������������ꂼ��J�Ƃ��A����̗v���ɉ����Đ����o�ׂ��Ă����̂ł��邪�A���a�R�O�N��O�サ�Ē����������̌o�c������Ȏ�����}���A���̑��������R�ɔp�Ƃ����̂ł������B���ݑ��Ƃ𑱂��Ă���̂́A�i�����P�j�����̌�g�ł���i�����Q�j�������X醬������������Ёi�i�����Q�j�̏��W�́A�������J�n�������a�Q�N�ɓ���Ƃ��牺�����ꂽ�Ƃ����j�̂�����Ђł���B���Ђ͏��a�W�N�ɍH����Ď��i���A��s����j�����̂ł��邪�A�悭������Č����A�����R��s��̌��݂ɂ���Č��ݒn�ɍH������݈ړ]�������ƁA�Q�V�N�ɂ͖@�l�g�D�ƂȂ����B�R�O�N�S������В��������j�̐Ղ��p���Ō��В������������A�C�A���R�P�N�R�K���Ă̗��̍H��⌤������݂��A���������̋@�B���E�������ȂNJ�Ƃ̍�������}��A�����i���ˁj�E�D�y�E���قɉc�Ə���u���Ĕ̘H�̊g���ɓw�߂Ă���B�]�ƈ����펞�T�O�l�O���i����n����ƂƂ��ċƐт����߁A�i�����Q�j�I�[�P�[�݂��E�i�����Q�j���悤��̂ق��A�W���M�X�J���̂����߂�ނ̂�Ȃǂɂ��Ɩ����g���������o�ׂ��Ă���B
�@��R�߁@�q��
���_��
�@�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�𑊑O�シ�邱��A�n�V�m�X�׃c��̍��ݑ�V�n��i��V��n�����P�O�O���[�g������̒n�_�j�ŁA�u���_�āv�ƌĂ�铩��̐������s���Ă������Ƃ́A�������铩���ØV�̘b�Ȃǂ�������炩�ł���A�{���̏Ă����j�̂Ȃ��ł��M�d�Ȓn�ʂ��߂���̂Ƃ���Ă���B
�@������ψ���ł́A���́u���_�āv�ƌĂ�铩��ɂ��Ď��Ԃ��������邽�߁A���a�T�Q�N�i�P�X�V�V�j�W���k�C���J��L�O�قɒ������̔h����v������ƂƂ��ɁA�n�����_�����w�Z�̋��y�j������������ы���ψ���E���Ȃǂɂ���ėq���̔��@���������{���A���̌��ʂ��u���_���\�q���̒����Ɖ���\�v�ɂ܂Ƃ߂ĕ����B���ꂪ���_�ĂɊւ���ŐV�̒����ł���A�܂��A�n���I�ɐ������ꂽ���̂ł���̂ŁA�����v�Ă��̊T�v�ɂӂ�Ă݂�Ǝ��̂Ƃ���ł���B
�@���_�Ă̍��ꂽ�N��ɂ��ẮA���Ɏ����ׂ����͎̂c����Ă��Ȃ����A��i�̒��̉Ԃт�̖��Ɂu��\�ē����_�ԋŁv�Ƃ��邱�ƂƁA�ØV�̘b�Ȃǂ��琄�@����ƁA�����炭�����S�O�N����i��\�͖����S�P�N�ɂ�����j���璷���Ă����N�̊Ԃƍl�����Ă���B
�@����ɁA���_�Ă���������H�́A��i�ł���Ԃт�̖��Ɂu�S�i������j�@�ԋŁi�����悤�j���v�Ƃ���A�S�͖����A�ԋł͍��ł��������̂ƍl�����邪�A���̌o���ɂ��Ă͎c�O�Ȃ���S���𖾂���Ă��Ȃ��B�����A���_�Ă̏�蕨�i���傤�Ă��́j����D�⎇�D�n���̓y���Ă����߂����̂ł���A��D�����ɗނ��镂���Z�p�������p�����Ă���_�A�܂��A���_�ɂ͋�����_��𒆐S�Ƃ��鈤�m���o�g�҂������A�q������_����ɂ��������ƂȂǂ��画�f����ƁA���̌S�ԋł͈��m���o�g�҂ŁA��D�̒��S�n�ł������튊�œ��Ƃ��K���������̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳���B�������A�����ς��͂��ߒ������ɂ�錻�n�Ɖ�ɂ�������炸�A�S���s���ł����č��̂Ƃ����g���̓��H�h�Ƃ���Ă���B
�@���_�Ă̐��i�́A���݂܂ł̂Ƃ��딪�_�����Ɍ����邾���ŁA
���_�āi�ʐ^�P�A�Q�j


���̐��͏��a�T�P�N�i�P�X�V�U�j�ɒ����ς��J�Â������ʓW�g�₭���₫�h�̎����ɂ��Ɩ�R�O�_�ł���B���̂����A��蕨�ƎG�킪���ꂼ�ꔼ�����߂Ă���A��蕨�ɂ͓���̉Ԃт�E���イ���E�����E�����܂��E�����Γ���Ȃǂ�����A�قƂ�ǂɖ����{����Ă���B���͉Ԃт�̗�ł͓B�i�����j�����ɂ�蓩�H�����L���A����ɔ��_�Ƃ����ł����݂�����Ă���B�܂��A���イ���E�����E�����܂��̗�ł́A�����ȔS�y���āA���̂����ɔ��_�Ƃ����ł����݂�������̂��ʗ�ł���B�Ȃ��A��蕨�͊�{�I�ɂ͒P�ɓy���Ă����߂����̂ŁA��D�n�i�Ԃт�j�Ǝ��D�n�i���イ���E�����E�����܂��j�ɑ�ʂ���邪�A�����ⓒ���܂��̂悤�ɓ��ʂɂ̂ݎ{�ցi���䂤�j�i���킮������{���j���ꂽ���̂�A�Ԃт�ɂ݂���悤�ȂԂǂ��̎���~�̉ԂȂLjꕔ���{�ւ�����̂������A�S�ʓI�ɂ͕����i�܂��͍����j�̋Z�p�������p�����Ă���B
�@�܂��G��ɂ́A�����߁E���E���ǂ����E���т�E������E�Ќ��E���M�E�����ڂ��ȂǁA���Ȃ葽��ނ̂��̂�����A������Ȃǂ͂��Ȃ�ʎY���ꂽ�Ǝv����̂ŁA����ɂ����Ă��܂������������Z�������Ƃ���Ă���B�������A�G��ɂ͏�蕨�̂悤�ɖ����{����Ă��Ȃ����߁A���ʂɂ͂�قǏڍׂȌ������K�v�ł��낤�Ƃ��Ă���B�܂��O�L��蕨�Ă͎��s�������߁A���̐Ղ͌o�c�҂������ĎG����Ă��A�ڏZ�҂̕w�l���G��ސ����Ɍٗp����Ă����Ƃ����B�Ȃ��p�y�͗q�̓�����R�O�O���[�g���̔M�c�n��̋u�̒�������Ƃ����Ƃ����Ă���B
�@�k�C���̏Ă����Ɋւ�����j�́A�{�B�ɔ�r����Ƃ���߂ĐA�������_�܂łɖ�P�Q�O�N���炢�����o�߂��Ă��Ȃ��̂ɁA���̒Z�����j�̂Ȃ��Ŗ�R�O�قǂ̗q���p�q�ƂȂ��Ă��āA�����̌������������Ƃ���Ă���B�����āA���̂R�O�قǂ̗q�̂Ȃ��ŁA�����ɑ��Ƃ��ꂽ�̂����ُĂ�����ł���A�����Ŗ����N��ɑ��Ƃ��ꂽ�̂��A�y��āi���M�j�E�D�y�āE�V�\�Ð�āE�ڕ��āi�D�y�j�E���_�ĂȂǂ̐��q�����Ȃ��A���Ƃ݂͂ȑ吳���珺�a���ɑ��Ƃ��ꂽ���̂ł���B���������āA�k�C���̏Ă����j�̂Ȃ��ŁA���_�Ă̂悤�ɖ������ɍ��ꂽ�Ă����͂����ւ�M�d�Ȃ��̂ł���A�������q���Ƃ��Ďc���Ă����͂���߂ď��Ȃ��A�{���̏Ă����̗q�������Ƃ��Ă͂��ꂪ�ŏ��̂��̂ł���Ƃ��Ă���B
�y�Ǔ��̐���
�@�����m�푈�̂ڂ����ɂ��H�Ƒ��Y���������ꂽ�_�Ƃ́A��肢���������Y�����߂邽�߁A�D�Y�n�⎼�n�т̓y�n���ǂ��v������A����ɂƂ��Ȃ��Ë��p�̓y�ǂ̎��v���}���ɑ��������B������������I�w�i�̂��ƂɁA���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�k�C�����_���Д��_�y�ǍH�ꂪ�������Ɍ��݂���A�����������n��V��R�i���A��V�j����Y�o����S�y�������Ƃ��ēy�ǐ������n�߂�ꂽ�B�����āA���N�̐������͂R�T���{�i������ځA���a��`�l���j�𐔂��A��ɒn�����_���͂��ߑ��E���ѕ��ʂɏo�ׂ��ꂽ�B
�@���A�Ɛ�֎~�@�ɂ���Ėk�C�����_���Ђ���̂��ꂽ���߁A����܂œ��Ђ̔_�n���ɏ������Ă����y�ǐ�������́A�Q�R�N�T���ɓƗ����Ėk�C���_�ލH�Ɗ�����Ђ̌o�c����Ƃ���ƂȂ�A���_�y�ǍH����K�R�I�ɓ��Ђ̔��_�H��ƂȂ����B
�@���̌�A���a�Q�S�N����܂ł͏����Ȑ��Y�������Ă������A���̒n���̓y�n���ǎ��Ƃ���i������悤�ɂȂ�Ɛ��Y�ʂ����X�ɉ��~�������ǂ�n�߁A���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�P�P���ɋx�ƁA�̂����R�p�Ƃ̂�ނȂ��Ɏ������B�Ȃ��A�x�Ƃ���܂ł̐������́A�y�ǂłT�O�O���{�A�����K�łP�O�O���ɋy�B
�k�C�����_���Д��_�y�ǍH��i�ʐ^�j

�@��S�߁@������
�ł�Ղ߂̐���
�@��ꎟ���E���ɂ��A�I�����_�E�h�C�c�Ȃǂ���̂ł�Ղ�A���̓����r�₦���C�M���X�A�t�����X�̎s��́A���̎��v����{�ɋ��߂����߁A�ł�Ղ�̎����͂���������A������ł�Ղ�i�C�Ƃ����ُ�Ȍo�Ϗ�Ԃ��������̂ł���B�������A�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�푈�I���ɂ���āA�I�����_�A�h�C�c�̂ł�Ղ��B�s��ɕ�������悤�ɂȂ�Ɖ��i�͈ꋓ�ɖ\�����A�s����������ł�Ղ�͑؉݂̎R�Ɖ����ƂȂ����B
�@���������o�Ϗ��w�i�Ƃ��āA�ꂢ����ł�Ղ�������Ƃ������߂̐����ɒ��ڂ�����̂����ꂽ�B���_�n���ɂ�����ł�Ղߐ����̌o�߂ɂ��ẮA�k�C���������o�ό������ҁu�k�C���_�Ɣ��B�j�U�v�Ɉ��p����Ă���吳�W�N�u�B������v��P�O�O���A�������j�u���_�n���ɂ����鈹�����ƒ����v�ɏڂ����q�ׂĂ���̂Ŏ��Ɍf����B
�@�u���_�n���ɂ�����b�����̐����͍ŋ߁i��ꎟ���E��풼��j�̑n�ƂɌW��]���Ă��̐��@�̔@���c�t�̈��E�����ډ������ɒ��肹����͔̂��_�����h���b�������Ǝҍ匴���Ɂi�����j�A�����s�X�n�G���b���戵���n�c���l�Y�̓�̂݁A���������ݔ����蒆�̂��̐X�сA��X���X���薔�b�����Ƒg��������Ǐ��𒆐S�Ƃ��ď\�ܔn�͏��C�@�ւɂ�萻������Ƃ���v�撆�̂��̂�����ȏ㐻�����蒆�̂��̂̓��M�c���X�̌o�c�ɌW����̂͑��ݔ��c�X�����������\�ܑ܂������ւ������c�c�匴���Ɍo�c�̂��̂͑��ݔ������ĕs���S�ɂ��Ĉ���͂ɎO�\�ѓ��O�c�c�B
�@���_�n���ɉ�����_�Ǝ��z�b���͈ꖜ�ܐ�܂Ə̂����A��c�Ǖ��ʂɉ�����b�������Ǝ҂͑��Ɨp�����������n�鏒�Ɠb���Ƃ�s�˂���c�q�����O�L�̈���Y�H�����肽��Ɖ]�Ӂv
�@���̂悤�ɂ��Ĕ��_�n���ɂ�����ł�Ղߐ����̋@�^���萶�����������A�吳�X�N�{�i�I�ɊJ�Ƃ����M�c�����H��̓����̐��@�́A�ł�Ղ��œ������č��e���ł������B�ݔ��͏��C���܂P�E�d���^���N�R��E�ϋl�ȂׂV���E��������@�P�E��ʐ�܂P�E���[�^�[�P�Ȃǂł���A���i�͊ʋl�Ƃ��ē��ʂU�O�ʁi�Q�T�E�T�L���O��������j���x�����A�k�C���P�~�Ɠ��k�n�����s��Ƃ��ďo�ׂ��Ă����B����ɁA�吳�P�P�N�W�����琻�ٍH��݂��A�L�����f�B�E��o�����߁E�悤����E�����Ȃǂ���������������Ă������A�₪�Ăł�Ղ�̒l�オ��Ƃ��炵���߂̎s��i�o�Ȃǂ������ċƐт��U��킸�A�吳�P�S�N�������Ĕp�Ƃ����B
���_�o�^�[����
�@�吳�T�N�i�P�X�P�U�j�ɘh�̑��i���A����j�̍匴�����A�ł�Ղ�������Ƃ��鐅���߂̐����ɒ��肵���̂ł��邪�A�O�q�̂悤�ɐ��@���c�t�Ȃ��ߋƐт�������Ă����B���̌�A�吳�P�P�N�ɖx��w�������̌㉇�č匴�����H����J�݁A���炵���߁E�������߂̐������n�߁A���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�{���ɓX�܂�݂���ƂƂ��ɉ����߂̐����̔����J�n���ċƖ����g�������B
�@���������o�c�̂�����琻�@�̌����𑱂��A���a�U�N���g�o�^�[�����h�̐��@�����A���_�̓��Y�i�Ƃ��ĉw������J�n�����B���̃o�^�[���߂͏��a�P�P�N�ɐ��@�������擾���A�����錳�c�Ƃ��Ă̒n����z�����̂ł���B�����ē��N�{���ōs��ꂽ���ʑ剉�K�ɍۂ��A�u���_�o�^�[���v��V���ɋ����邱�ƂƂȂ�A���ɍH���V�z���ċސ�����Ƃ������h�ɗ������B���Y���͏��a�P�S�A�T�N���낪�ō��ŁA���Y�P���L���O�������x���Y���đS���ɖ��������B
�@���ݗ���̍H��ɂ����ẮA�Q��ڍ匴���j�ɂ���Ď��Ƃ��p������A�D�]�̂����ɎD�y�E���ق��̑��ɏo�ׂ���Ă���B
�@��T�߁@���D��
���D���i���傤�j�̐ݒu
�@�����P�P�N�i�P�V�X�X�j�ɓ��ڈΒn�����{���̂ƂȂ�A���ڊC�^����舵�����ƂƂȂ������߁A����ɕK�v�Ȋ��D�̑��D����ݒu���邱�ƂɂȂ����B
�@���̂��ߔ��ٕ�s���́A�������N�i�P�W�O�S�j�ɔ��ْn�����̊C�ʖ��ߗ��Ă��s���A�Q�P�V�Q�i��V�P�U�W�������[�g���j�̒z����A�����ɑ��D����ݒu���Ċ��D�̐V����C�����J�n���A�܂��A�����N�Ԃɂ͖��Ԃٍ̕��D�ȏ�̑D�������ނ́A�Z���ꏊ�̗ё��������̂������̂��������B�����n��ɂ͗ǎ��̑D�ނ��o�邽�߁A���قƎ��������Ċ��c�̑��D�����ݒu���ꂽ�B�u�x�����L�v��e���̓�ɁA
�@��p�D�V��
�@�ڈΒn���o�Y���ϓ���⍑��O���^���V��D�Ȃ��ăn���ӂׂ��炸�ƂāA�D�X�����܂����点���B�Ƃ���A�l���A��c�ǂȂǂɂ����D��������ꂽ�B
�@�����̊��D�̂����A�S�S�D�ɂ��đ��D�A�j�D�A���������ȂǂƓ����ɋL�ڂ���Ă��邪�A���n���̊W�ł́A
�@�c���ہ@���S�Z�\��
�@�E�n���ٔV�ݖ�c�Ǔ��鏈��B�������N�A���V�N���c���Õ��q�萿�ɂȂ�B
�Ƃ���A���ق̉�D�≮���c���Õ��q�̏��D�Ƃ��Ċ������Ƃ����������B�܂��A���D�ɂ��ĕ����Q�N�x�����L�t�^���̏\��Ɂu��p�D�ҏo���v�Ƃ��āA�@�@�@������S�Z�\�㗼�i�S��\�����Z��
�@����D
�@�c����
�����D�Ƒ�������A����p�D�j���A�����������O�j�����B
�Ƃ��̉҂������L���Ă���B
�@����ɑ��D���̂��Ƃɂ��ẮA�����N�Ԃɖ����s��\�Y���������u�ڈΎ��n���l�^�v�ɁA
�@����
�@��
�@���n����̑��B����E�����E�N����Ƃ����B���D�������O�\�ԑ��O�C�[�E�ԃj�e�ځA�O�E�ԃj�e���A�E�ԃj�e����ځA��O�C�S�ԃj�e��q���B�O�S�ԃj�e�Z�q��B�i�ȉ����j
�@���c�����D�����O�\�ԑ��ʐ[�\�ԃj�e���ځA�O�\�ԃj�e����ځA�\�ԃj�e���l�ږ�B
�@�i�ȉ����j
�Ƃ���A���̈ʒu�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���c�̑��D�����ݒu����Ă������Ƃ��L����Ă���B
���D�Ƃ̐���
�@�����̎�������ՂƂȂ�A�܂��A�D�̗p�ނƂȂ�J�c���␙�Ȃǂ��L�x�������̂ŁA�����n��͓���L���̑��D�n�Ƃ��Đ��Ƃ��ɂ߂��B
�@�����P�R�N�i�P�W�W�O�j�̗��������Y�\�ɂ��ƁA���N�V������P�Q���܂ł̑��D���́A���D�P�z�i�����j�A�O���D�P�R�z�A�z�b�`�D�W�X�z�A��D�X�T�z�Ƃ���A�����͒n�������ł͂Ȃ������E�����E�슝���ւ��������Ă����Ƃ����B�܂��D�̗p�ނƂ��Č䗿�т����o�������́A������𗘗p���ĉ͌��܂ŗ��������Ƃ����Ă���B
�@�����P�S�N�i�P�W�W�P�j�u���������ꏑ�ށv�̐E�ƕ\�ɂ́A�D��H�P�T�N�i�j�ȏ�P�l�A�U�O�N�i�j�ȏ�P�l�A�v�Q�l�ƋL����Ă��邪�A���̎����ɂ��Ă͕s���ł���B���̌�A�����P�W�N����ɍ��c�����Y���X���őD��H�Ƃ��Ă̋Z�p���K�����āA�����ɗ��đ��D�Ƃ��J�n�����B�܂��A�Q�O�N�ɂ͑��ދƂ��c��ł�����R��V�傪��R���D�����J�݂��A�����E�吳�Ɛ��Ƃ��ɂ߁A�Ƃ��ɑO�L�슝�����ʂ�������������������Ƃ����B
�@���̌�A���c���D���͋e���Y�E����ƁA��R���D���͋��E���x�ƈ����p���A���ꂼ��o�c�𑱂����B����������������Θp���Ƃ̐��i����A���^�ؑ����D�̐����ƏC���ł���A���a�R�O�N�ォ��͋��D�\���̕ω��ɂ���ĖؑD����|�D���ւ̌X���������A����ɂP�O�g�������̈�D�͂e�q�o�D�ւƕω������B���̂��ߋƎ҂��A���̎{�݂�]�ƈ��̓]����]�V�Ȃ�����Ă������B���̂ق��吳�����ɂ́A�����ő�R�������o�c���鑢�D�������������A���a�P�O�N��Ɏ��莞��̐��ڂƂƂ��ɔp�Ƃ����B
�@����A���_�n��ɂ����Ă������������x���Ƌg�c�F���Y���A���Y���ɂ����Ă��ꂼ�ꑢ�D�����J�݂��Ă������A���둢�D���͏��a�T�O�N�ɔp�Ƃ��A�T�V�N���݂ł͋g�c���D�����������Ƃ��Ă���B
�@��U�߁@���Y���H�Ɠ�
�t�B�b�V���~�[���̐���
�@���Ƃ̐���ł����������������珺�a�̏����ɂ����ẮA�������E�ϊ����E�����Ȃǂ̐����Ǝ҂͑����������̂́A�����͒P���ȑ�ꎟ���H�ɑ�������̂ł������̂ł����ŏq�ׂ邱�Ƃ͏ȗ����邪�A�����ɂ�����{�i�I�Ȑ��Y���H�Ƃ̎n�܂�Ƃ��ċ�������̂́A�t�B�b�V���~�[���̐����ł��낤�B
�@���a�U�N�i�P�X�R�P�j�P�P���ɔ��َs�ݏZ�̍��X�������Y���L�x�Ȏ����ɒ��ڂ��A���Y���i���A���_�������~�n�j�Ɂu���X�؋��Ɗ�����Ёv��n���A�H����J�݂����̂�����ł���B���̍H��́A�~�n�Q�T�O�O�A�H�ꌚ�R�T�O�̋K�͂�L���A�@�B�^���́u���m�ڎ�����b�g�X�����X�؎��v�ƌĂ����̂ŁA�C�݂ɋ��D���ăE�C���`�ł��Ɋ����g���A�g���b�R�Ō�����ɉ^���A�o�P�b�g�G���x�[�^�[�̋���E�֗���������Ɠ����ɐ��������ƁA�Ϗn�E����E���ӁE�����E����ɂ�����x���ӂƂ����H�����o�Đ��i�Ƃ�����̂ŁA�����̎������݂��琻�i���܂łP���ԂQ�O���Ƃ����X�s�[�h�ł������B
�@�Ȃ��A���i�̐����́A�����W�`�X�p�[�Z���g���O�A���f�P�O�p�[�Z���g�ȏ�A�����_�S�`�T�p�[�Z���g�ȏ�A�e���b�P�O�p�[�Z���g�ȉ��A�����P�O�p�[�Z���g�ȉ��A�V�����b�_�P�p�[�Z���g�ȓ��A���y�P�O�p�[�Z���g�ȉ��Ƃ������̂ł���A�t�B�b�V���~�[���g���̗A�o�����ł��G�L�X�g���[�ɍ��i�Ƃ����ǎ��̂��̂ł������B�d�オ�������i�́A�H�ƁE�엿�E�����ʂɖ��܂ɋl�߂��A�A�����J�����̂��̂͂P�O�O�|���h�l�߁A���[���b�p�����̂��̂͂T�O�|���h�l�߂̂Q��ɋ敪����A��Ƃ��ăA�����J�A�h�C�c�ɗA�o���ꂽ�B�������āA�n�Ƃ̗��V�N����X�N����ɂ����ẮA���������ō��ŔN�ԂQ�O�O�O�g�����O���Y�����̂ł��邪�A���a�P�O�N�S���Q�O���ɂ͑哯���Ɗ�����Ђɏ��n���ꂽ�B���̌�Ԃ��Ȃ��펞�̐����ɓ���A�A�o���r�₵�����ߍ����ŏ���ꂽ���A���l�������X�Ɍ�������ɂ�Čo�c�s�U�ƂȂ�A���ɏ��a�Q�S�N�P�Q���������čH���������̂ł������B
�@�܂��A�����̖Ζ����i���A�h�l�j�n��ɂ����Ă��A���a�V�N�ɔ��َs�̍����P���Y���t�B�b�V���~�[���H������݂��A���i���h�C�c�A�I�[�X�g�����A�ȂǂɗA�o���Ă������A���ۏ�̈����ɂ��A�o�s�U�̂��߁A�Q�A�R�N�ő��Ƃ��x�~�����Ƃ���������������B
�ʋl�̐���
�@�吳�̖����A�x�R���̍��c�����Y������Łu�^�P���v�̊ʋl�̐������s�����̂��ŏ��ł��邪�A���ƌ�킸���T�A�U�N�Ŕp�Ƃ����B���a�ɓ����Ă���ł́A�V�N�i�P�X�R�Q�j�ɔ��ق̏o���������A�o�����X�R�z㣋l�H���ݗ����A�u�т��Ɋʁv�����ē��N�P�������o�ׂ������A�������ɂ���ĊԂ��Ȃ��o�c�s�U�Ɋׂ�A�X�N����͓�������㣋l������ЂɌo�c���ڂ��āu�g�}�g�T�[�W���v�Ɓu���Ίʁv���������A������܂����N���������ɔp�Ƃ����B
�@����ɁA���a�W�N�ɂ͒n���̏��c����ɂ���Ė{���Ɂu���_㣋l�H��v���ݗ�����A�u�т��Ɂv�u���^�P�v�̊ʋl��N�ԂT�O�O�����O���������B������������o�c�s�U�̂��߂P�O�N�X���ɓ�������㣋l������ЂɌ�n���ꂽ���ƁA�܂��Ȃ��p�Ƃ����B�܂��������a�W�N�A�R��ɒ|���^�g�̌o�c����ʋl�H�ꂪ�ݗ�����A�N�ԂQ�O�O�����O�́u�т��Ɋʁv���������A�킸���P�N���܂�̑��ƂŁA���X�N�ɂ͔p�Ƃ����B
�@�����̂ق��ɂ��ʋl���������݂���̂����������A����������ƂɎ��炸�A�i���������݂̂͂��Ȃ������B
�Ⓚ�E�①��
�@���a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�U���ɔ��_�①�L����Ђ��{���P�T�Q�Ԓn�ɐݗ�����A�Q�P�N�T�����{���ܘY���В��Ƃ��Ď��Ƃ��J�n�����B���̌㏼�{�����Y��������p�����A���X�A���N�H���i�̗Ⓚ�①�ۑ���e�퐅�Y���H�i�Y���Ă����̂ł��邪�A�T�Q�N�ɂ͂����������B
�@���̂ق��A��H�ƂƂ��āA�i���j���������B�Ⓚ�E�①�ƂƂ��āi�L�j���}�L�e�n���X�B���Y���H�ƂƂ��āi�����P�j���X�ؐ��Y�A���{���Y�A���J�쐅�Y�A���䐅�Y�A�i�����Q�j���X�ؐ��Y�A��{���Y�A�{�ԏ��X�A��؏��X�A�i�L�j�}�����X�������Y�Ȃǂ�����A�X�P�g�E�^����z�^�e�̉��H���s���Ă��邪�A�z�^�e�L�łɍЂ�����Đ��i�����U��킸�A�~���Ԃ̃X�P�g�E�^���ɂ��Ă��L�єY�݂̏�Ԃł���B
���_�①�L����Ёi�ʐ^�P�j

�@��V�߁@�{�Y�H�Ƃ̕ϑJ
�@�����ɂ�������Ɖ�Ђ̕ϑJ�ɂ��ẮA���łɑ�P�͔_�{�Y�ƁA��V�߁u���_�Ƃ̐i�W�v�̍��ŏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�吳�P�P�N�U���ɉ��H���ݒu���đ��Ƃ��J�n�������Ɖ�Ђ��A�����̕ϑJ���o�Ȃ���U�O�N�ԂƂ��������ԁA�P�����x�Ƃ��邱�ƂȂ����_���_�̐��Y���������������Ă����̂ł��邪�A���a�T�U�N�R������������ĕ����邱�ƂƂȂ����̂ł���B���̎���͎�X����Ǝv���邪�A����͂��Ă����A���Ɖ�Ђ̕ϑJ�ɂ��Ă��Ȃ�d�����镔�������邪�A�n�Ƃ�����Ɏ���܂ł̌o�܂��L�����ƂƂ���B
���Ɖ�Ђ̗U�v
�@�吳�W�N�i�P�X�P�X�j��ꎟ���E���I����A���_�̔_�Ƃ͂���܂ł̍����キ�Ώd�_�Ƃ���L�{�����_�Ƃւ̓]�����A��o�҂ɂ���Ē���A�e�n�ɒ{���g������������ē����̓������i�߂���悤�ɂȂ�A���{���������N��������ƂƂ��ɋ������Y�ʂ��������Ă������B�������������̏����ɂ��ẮA���łɖ����̖�������R��̐ΐ�_��ɂ����ăo�^�[��������A����̍����_��ŋ�����������w�����ăo�^�[��{�B���ʂ֔���o���ȂǁA�l�o�c�̐��������ł��Ă����̂ł���B
�@�����ɂ����Ă��A�����̈琬�Ɨ��_�̏���̂��߁A�吳�P�S�N�Ɂu�k�C�����_����K���v���߁A�W�����̎{�ݔ�⋍��������̍w����ɑ��č����ȕ⏕������t����ȂǁA����������i�s��̐����ɓw�߂Ă����B
�@����A�k�C���ɂ�������Ɖ�Ђ́A�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�D�y�ɖk�C������������Ёi�ꖱ�E���{����j���ݗ����ꂽ�̂���ƂƂ��Ă̍ŏ��̂��̂ł���A������Ђł͕��H���ݒu��������Ƃ��āA������S�O�O���ȏ�ɒB���Ȃ���̎Z�x�[�X�ɂȂ�Ȃ��Ƃ���Ă����B
�@���̂��߁A�����ɂ����ẮA�O�q�̂悤�ɒ��N��������Y���ʂɑΉ����āA���̏����H��̑����ݒu��Ɋ����A�P�O�N�ؑ��������͂��ߒ���c����L�u��́A���łɁA�o�^�[�̐������s���Ă����ΐ�E�������_��ɑ��A�����o�ׂ̋��͂�v������ȂǁA�W�҈�v���͂̑̐�������A�k�C������������Ђ̕��H��U�v�ɓw�߂��̂ł���B���̌��ʁA���_�_���̔M�S�Ȉӗ~�Ə������ɂ���ĉ�Б������H��i�o������A�Ƃ肠�����P�P�N�U�����甪�_�Y�Ƒg���̂ł�Ղ��H����������āA�����̎�����J�n���邱�ƂƂȂ����̂ł���B���ꂪ�����ɂ�������Ɖ�Б��Ƃ̂͂��܂�ł������B
�@���P�Q�N�V���ɂ͔��_�H������݂��Ė{�i�I�ȗ����̐������J�n���A�n�������ł͂Ȃ������E���������ʂ̋������D�ԗA���ɂ���ďW�������B���������i�̒��S�i�ڂ͗����ł���A�����Z�p�ɂ��Ď����������i�߂��i���̌��オ�}��ꂽ�ق��@�B�̌������s���A���_�H��ł͗����p�^�܂����������ȂǁA���������̌o�ϐ������i���ꂽ�̂ł������B
����{�����i��������_�H��
�@�吳�P�P�N�U�����H��Ȃ��瓖���ɕ��H���ݒu���đ��Ƃ��J�n�����k�C������������Д��_�H��́A���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�Ɂu����{�����i������Д��_�H��v�i�H�꒷�E�{���d���Y�j�Ɖ��́A�{�݂̋K�͔͂N��ǂ��Ċg�[����Ă������̂ł���B���������̂���̓����i�̎s���͈������A�����̏��u�����Ǝj�v�́A�@�@�u���a��N���̓����i�s���́A�O���i�̓��M�ɂ�������炸�A�����̂��߂̔��}���ō��Y�i�����Ƃ�����ۂ�悵���B�O�N�̏t��ɂ͂�����C�����݂������A�l�A�܌��̐��ٗp���v���ɂ͂���ƁA���C���T���ۑ��Ȃǂ̊W�������āA�s��͂ӂ����є��}���C���ƂȂ�A�ُ�ȉ��i�̉������������B���Ƃ��o�^�[�ꕕ�x�̕��ω������i�͓�N�̖��~�ꎵ�K�ɑ��A�O�N�ɂ͖��~�l�K���x�ƂȂ����B�����i�̒l���肪�������čK�����A�ꎞ�I�ɐ��ٕ��ʂ̎��v�����N�����̂ŁA�s���D�]�Ɋ�]���Ȃ������̂́A���i�̉܂łɂ͂��ڂ��Ȃ��c�c�v�@�@�@�@�@�@�Əq�ׂĂ���A���ƊE�̕s���������A���̕s���ɒ[���Đ��Y�҂Ɖ�Б��̕������������A������u���������v�ɂ܂Ŕ��W�����̂ł���B���a�V�N�P���ɗ��A�Ɖ�Б��o���ɂ���āu���������Ɠ����i�Ƃ̓����������v�\������������}��A���A�͔��_�ɏo������݂��A���Q���u�k�C�������̔��g���A����_�����H��v�i�H�꒷�E�����c�O�Y�j�����݂��A���݂̑�������i������Ђł͗����i�~���N�j���A�V�݂̗��A�ł͐����i�o�^�[�j�����ꂼ�ꐻ�����A�����̊��S������}��Ƃ������Ɠ����������Ƃ�ꂽ�̂ł������B
�������ي�����Д��_�H��
�@�����k�C���ɂ�������ƊE�́A����{�����i������ЁA�ɓ�����������ЁA�X�i���ي�����Ђ̎O���Ђɂ���Ďx�z����A���̐��͂��Η����������������W�J����Ă����B�������A�吳�������珺�a�����ɂ����Ă̕s������ɓ���ƁA�����̊e�Ђ͂Ƃ��Ɍo�c���k�̕�����Ƃ�͂��߂����A��ƂƂ��Ă̐����g�[���}���A���a�W�N�i�P�X�R�R�j����{�����i������Ђ͖������ي�����Ђɔ�������A���_�H��́u�������ي�����Д��_�H��v�i�H�꒷�E�����c�O�Y�j�ƂȂ����̂ł���B
�@�������A�펞�o�ω��ɓ����ď�������������A���ƊE���܂���ƍ����Ƃ����V���ȋǖʂ��}�����̂ł���B�P�T�N�i�P�X�S�O�j�ɂ͓��ƊW�҂̊ԂŐT�d�Ȍ������J��Ԃ��ꂽ���ʁA����������Ƃ�����ƈ�Ђɓ������邱�ƂƂȂ�A���a�P�U�N�R���u�L����Жk�C�����_���Ёv�̐ݗ����݁A���N�U��������Ђɑg�D�ύX���āA��\�I�ȍ����ЂƂ��Ĕ������邱�ƂƂȂ����̂ł���B���̂��߁A�����Ɨ��A�̔��_�H��͂Ƃ��ɂ��̎P���ɓ����č��̂��A�����Ђ̔��_�H��ƂȂ����̂ł���B
������Жk�C�����_���Д��_�H��
�@���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j��ƍ����ɂ��u������Жk�C�����_���Д��_�H��v�i�H�꒷�E�����c�O�Y�j�Ƃ��Čo�c����A�����E�����E�o�^�[�E�J�[�C���E�����Ȃǂ̐��Y���s�����̂ł��邪�A�P�V�N�ɂȂ�ƌR���D��E�H�Ƒ��Y�̍���ɂ����āA�J�[�C���i�q��@�p�j�E�����E�玙�p�����E�����̐��Y�ɏd�_���ڂ�A�o�^�[�͕��Y���I�Ȃ��̂ƂȂ����B
�@�������A��ア����펞�o�ς̉����ł��鏔�����̐��ɂ����ꂽ���_���Ђ́A�����R�ɂ�銔�����剻�̎w�߂Ɨ��_�Ƃ̋����v���ɂ���āA�g�D�ύX�Ɍ�����������ꂽ���ʁA���a�Q�Q�N�P������u�k�C�����_����������Ёi�k���Ёj���_�H��v�i�H�꒷�E�{�@�u�ǁj�Ɖ��߂��ĐV���������̂ł���B
�k�C�����_������������_�H��
�@�������Ĕ��������k�C�����_����������Ђ́A�����Ɠ����Ɋ����̍ĕҐ����}���A�_�����{�̉�ЂƂ��ĉ^�c��}��A�������剻�Ɉꉞ�̐��ʂ��グ���̂ł������B
�@�������A�I���R�N�ڂ��}�������a�Q�Q�N�̍�����́A�Љ�o�ς��̑�������ʂɂ킽���č��Ƃ��Ԃ������A�C���t���͍��i���A�����̐�Ηʕs���͊ɘa����邱�Ƃ��Ȃ������B���̂��ߐ��{�͓��N�S���u���I�Ɛ�̋֎~�y�ь�������̊m�ۂɊւ���@���v�i�Ƌ֖@�j�����z�{�s����ƂƂ��ɁA���Q�R�N�R���ɂ́u�ߓx�o�ϗ͏W���r���@�v���{�s���A�k���Ђ͂����̖@���̓K�p���邱�ƂƂȂ����̂ł���B����ɑΉ����Ėk���Ђ́A�Q�R�N�P������Q�T�N�T���ɂ����āA�w������^���ɑS�͂��������̂ł��邪���̂������Ȃ��A�Q�T�N�P���ɏo���ꂽ�u�ĕҐ��Ɋւ��錈��w�߁v�ɂ���āA�u�k�C���o�^�[������Ёv�Ɓu�����Ɗ�����Ёv�ɕ�������A���_�H��͓��N�U������u�����Ɗ�����Д��_�H��v�i�H�꒷�E�{�@�u�ǁj�Ƃ��ĐV�������邱�ƂƂȂ����B
�@�������Ėk�C���̓��ƊE�́A���{���P���Q�O�O�O���~�̖k�C���o�^�[�E�A�R���U�O�O�O���~�̐����ƁA�Q�R�U�T���~�̖������ƍ����H��A�Q�R�W�T���~�̐X�i���Ɖ��y�H��̎l����ƃ��[�J�[�̑��D�ɂ䂾�˂��A�̔����������]���Ď��R��������ɓ˓����Ă������̂ł���B
�����Ɗ�����Д��_�H��
�@�̔��������玩�R��������ɓ��������ƊE�̕ϊv���ɐV�������������Ɗ�����Ђ́A���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�U���D�y�ɖ{�Ђ������A�����e�n�ɂP�V�̎�ǍH����������ق��A���ԍH��E����������E�W�����Ȃǂ�ݒu���Ċ�Ƒ̐������A���R�����ɑΉ������̂ł������B���_�H��͂P�V�̎�ǍH��̈�Ƃ��āA�����ہE�����ہE���_�ۂ̎O�ۑ̐��̂��ƂɁA�lj��̒��ԍH��Ɏ둾�E��m���E�������E�������E��c���E�����I�̂U�H���i���A�����̐����E���_�̕⓱�Ɩ��E���{�̎��Âƌo�c�⓱����Ƃ��Ď��Ƃ�i�߂��̂ł���B���̂��������I�H��͓��ʂ��������A�H��Ƃ��Ă̏d�v�x�����債�����߁A���N�X���ɔ��_�H�ꂩ�番�����Ď�ǍH��ɏ��i���A�lj��W�����I�E�O�H�E���E�ᏼ�E�����̌܂����Ƃ����̂ł������B
�@�������Ĕ����������_�H��́A�����Ƃ̉��H�����i�����H��Ƃ��āA���N�H��̑����z��ݔ��̋ߑ㉻��}��A���̍Ő����Ƃ������鏺�a�S�V�N����́A�]�ƈ��Q�P�P����i���A�����ɂ������H��Ƃ��Ē蒅�����̂ł������B
�@�������A���x�o�ϐ������ォ��ᐬ������ɓ��������a�T�O�N��ɂ����āA���_�E�ɉ��������E�I�ȗ��_����́A�����ɂ���������ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��A�T�R�N�x����S�N�A�������̐��u���i�L��������W�W�~�����K�j�A���������i�Ɍ����̂��߂̋�������g��^���A�_�ƌX�ɑ��鐶�Y�ʊ����z�����A���т������������B
�@������������Ȃ��ɂ����Ă������͑��B����A�������Y�����тĂ���ɂ�������炸�A�A�������i�͔N�X�������A���Y�Ə���̎����W�̃o�����X�͍D�]�����A���ƊE�ɂƂ��Ă͋ɂ߂Đ[���ȏ���}�����̂ł���B
�����Ɓi���j���_�H��i�ʐ^�P�j

�@���������̂��Ƃɂ����āA�����Ƃ̏��a�T�T�N�x�̓����ɂ���������i�H��Ƃ��ẮA�D�y�E����E�����E����E���H�E�镪���E�����E����E���_�E���فE�k���E�ԑ��E�����E�y���E�ڕʁE���W�ÁE�v���ʁE�ʊC�E����̂P�X�H�ꂪ���Ƃ��Ă���A�����Ő��Y���ꂽ�����̂�����P�O�O���g�����������Ă����B���_�H��ł͒����Ő��Y����鐶���Q���W�O�O�O�g���̂�����U�V�p�[�Z���g�̂P���X�O�O�O�g���̂ق��lj��W��������̋��������킹�A���H�����i�H��Ƃ��đS���������Ă����B�������A�O�q�̂悤�ȓ��ƊE�̏��w�i�Ƃ��āA��Ђ͐����̔�������𐧌����A���a�T�S�N�ɖ���E���ڕʁE�эL�̂R�H����A�T�T�N�ɂ͏@�J�Ǔ��ڕʍH��A�����Ǔ��v���ʍH��������ȂNJ�Ƃ̍�������}��A�W�����Y�̐����Ƃ��ăR�X�g�_�E����}�����̂ł��邪�A�啝�Ȍ������v���L�^�����̂ł������B���̂��߉�Ђ́A�����P�V�H��̂��������K�͂̏��������_�H���s�̎Z�H��Ƃ��Đ������A���Y��������ړI�Ƃ��ď��a�T�U�N�R������������ĕ�������j�����肵�A�P���P�R���ɖk�C���x�В����m�햱��������A���̎|�ɒʍ������̂ł������B
�@�������āA�H��̑��Ƃ͂Q�����������đS�ʓI�ɏI�����A�]�ƈ��V�P���͑ސE�҂P�U���������S���e�n�̓��ЍH���x�X�Ȃǂɔz�u�]���ƂȂ�A�����Ɗ�����Д��_�H��́A�����ɂU�O�N�ɂ킽����j������̂ł���B
�@���̂��߁A�����Ő��Y�������H�������͔��ق̖k�C�����Ɗ�����ЂɁA�s���������͔��ٗ��_���Ђɏo�ׂ���邱�ƂƂȂ����B
�@���a�Q�T�N�����Ɗ�����Д��_�H��Ƃ��Ĕ������Ĉȗ��A�T�U�N���� ����܂ł̓��H��̌o�߂͎��\�̂Ƃ���ł���B
�����Ɓi���j�㔪�_�W�����i�ʐ^�P�j

�����Ɓi���j���_�H��o�ߕ\
| �N�@�@���@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�� | �]�ƈ��� |
| ���Q�T�E�@�U�E�P�O | �����Ɣ��_�H��Ƃ��ĐV���� | �@ |
| �@ �V �E�@�X�E�Q�P | �P�������I�H�ꂪ�������āA��ǍH��ƂȂ�B | �@ |
| �@�Q�U�E�@�U�E�@�T | �r�^�~���N���J�n | �@ |
| �@�Q�X�E�@�W�E�R�P | ��d���p�^��Z�k���u��ݒu�A�f���}�[�N����u��A�����������@�v���A �Z�p�҂R���������Đݒu���瑀��܂ł̎w������ |
�@ |
| �@ �V �E�P�P�E�Q�X | �H����z�ݔ��ߑ㉻�����H������ | �@ |
| �@�R�O�E�@�R�E�@�P | �����s�����w�Z�Ŕ��_�H�ꐻ�̒E�������ɂ��W�c�������� | �@ |
| �@ �V �E�@�X�E�P�R | �P�O�O�O�|���h�\�͂̑�^�o�^�[�`���[�����݁A�����H������ | �@ |
| �@ �V�@�@ �| | �lj���c���E�������H��ɗ�p���u��݂��A�N�[���[�X�e�[�V�����Ƃ��� | �@ |
| �@�R�R�E�@�W�E�@�| | �G�R�o�b�N�E������ʏ[�U�@��ݔ����A�C���X�^���g�X�L���~���N�����J�n | �@ |
| �@�R�W�E�@�X�E�@�P | ���D㣎�����́A�V���ɖؑ������^������o�^�[��������V�z���A�U�R�O�O���b�g���A ���^���`���[������ |
�@ |
| �@�R�X�E�@�R�E�@�P | �W�����E���H�Ԃ̐����ɂƂ��Ȃ��n�ЁE��ʁE�M缁E��J�E���m��W������ | �@ |
| �@ �V �E�@�T�E�Q�X | �S�����^���d�㕲�����V�z�A�����ݔ��P���C�����ݐ����J�n | �@ |
| �@ �V �E�@�T�E�R�P | ���D�E��֏W������ | �P�Q�O |
| �@ �V �E�@�U�E�P�V | �������H��W�����ƂȂ� | �@ |
| �@ �V �E�@�V�E�@�P | ���_���ۂ�ݒu�A�����I�H��lj��_�H��̏��ǂƂ� | �@ |
| �@�S�O�E�@�T�E�@�P | �ᏼ�E�O�H�W������ | �@ |
| �@ �V �E�@�T�E�@�| | �U�R�O�O���b�g�����^���`���[���j��Ƃ��A�o�^�[�̐����\�͂��� | �@ |
| �@ �V �E�@�U�E�@�P | ��c���W���H��� | �@ |
| �@ �V �E�@�W�E�@�P | �둾�W���H����j�Z�R�H��Ɖ��� | �@ |
| �@ �V �E�P�O�E�@�| | �畲���Ƃ̐L���v��ɂ��ƂÂ��v���ʍH��̐�����p�~���Ĕ��_�H��ɐݒu�A �H��Q���O�U�R�X���~�œS���X�R���N���[�g���蕽���ꕔ��K���� ���x�P�P�X�T�������[�g���̍H���ݒu�� |
�@ |
| �@�S�P�E�@�U�E�@�P | �эL�H��ƂƂ��Ƀl�I�~���N�o�e�A�l�I�~���N�o�V�̐����J�n | �@ |
| �@ �V �E�@�U�E�@�U | �V���������ؑ������^���������ĂP�X�T�������[�g���A ���i�q�ɓS���X���[�g�������Q�O�X�������[�g����V���z |
�@ |
| �@�S�R�E�@�U�E�@�| | ���������̏d�������V�X�e�����G�A�[�q�[�^�[�V�X�e���ɐ芷���� | �@ |
| �@ �V �E�@�X�E�@�| | �Ɛg���S�R���N���[�g�j�K���ĉ��ׂR�U�S�������[�g����V�z | �P�U�T |
| �@�S�S�E�@�X�E�@�| | �玙�p�����ʂ̊ʌ^�̕ύX�ɂƂ��Ȃ��āA�[�U���C���R���x���̍X�V���s�� | �P�U�P |
| �@�S�T�E�@�T�E�@�| | �Ⓚ�@���݂��ĎO��Ƃ��� | �@ |
| �@ �V �E�P�Q�E�@�| | �玙�p�����Q�O�O�O�����ʂ̋�ʃN���[�i�[���݂� | �P�X�U |
| �@�S�V�E�@�Q�E�Q�X | ���ݐΒY�{�C���[��p�~���āu�悵�݂ˏd���{�C���[�v��ݒu�� | �Q�P�P |
| �@�S�X�E�@�Q�E�Q�W | ����E�֏��V�z | �@ |
| �@ �V �E�@�R�E�R�P | �h�����ݔ����� | �@ |
| �@ �V �E�@�R�E�@�| | ���Q�ݔ��Ƃ��ĒP�����C�@�ɂ��{�݂�V�݂� | �P�U�R |
| �@�T�O�E�@�W�E�@�P | �o�^�[���тɍ��������畲�o�V�̐������~ | �P�R�U |
| �@ �V �E�@�X�E�R�O | �lj������I�H�ꍇ�����ɂ��_���ֈڊ� | �@ |
| �@ �V �E�P�P�E�P�V | �Б�O���V�z | �@ |
| �@�T�Q�E�@�R�E�R�P | �������W���H�ꍇ�����ɂ��p�~ | �P�Q�V |
| �@ �V �E�@�T�E�Q�P | ���^���`���[���������H��֔z�]�i���j | �@ |
| �@ �V �E�@�W�E�Q�V | ��������^���N�ԑ����V�z | �@ |
| �@�T�T�E�@�P�E�R�P | �畲�����p�~ | �@ |
| �@ �V �E�@�P�E�@�| | �����O���C�t�����i�k�k�����j���Y�J�n�̂��߂Q���P�O�O�O���~�𓊂��u�����g�ݒu | �V�S |
| �@ �V �E�@�U�E�@�P | �����O���C�t�����J�n | �@ |
| �@�T�U�E�@�P�E�P�R | �k�C���x�В����m�햱����_�H�����ʍ� | �V�P |
| �@ �V �E�@�Q�E�� | ���ƕ� | �@ |
| �@ �V �E�@�R�E�� | �]�ƈ��V�P���̂����P�U���̑ސE�҂������A���ЍH��x�X�֔z�u�]���I�� | �@ |
���̑��̓����i�H��
�@�����Ɗ�����Д��_�H�ꂪ�V�����������a�Q�T�N�t�A���َs�́u�c�����Ɗ�����Ёv��������c���ɐi�o���A���Q�U�N�W������ݒu���đ��Ƃ��J�n�����B�Q�W�N�ɂ́u�k�C�����Ɗ�����Ёv�i�В��E�c���v�O�j�Ɖ��̂��A�x�m�����ɂ����ė����������s���Ă������A�₪�Čo�c�s�U�Ɋׂ������߁A���Q�X�N�H��������Ɏ������B
�@�������A����܂Ŗk�C�����Ƃɋ������o�ׂ��Ă������Y�҂́A���̂܂ܐ����ƂƎ��������邱�Ƃ�]�܂��A�V���ɖ������Ƃ̐i�o��v�������B����ɉ����Ė������Ƃ́A���N���ʐ��ɂ̈ꕔ����ďW�����J�n���A�������������ɑ������̂ł���B���̌㓯�Ђ́A�R�T�N�O�����ɏW������V�z�ړ]���ċƖ����p�����Ă������A��ƍ������̕��j�ɂ���ĂT�O�N�X���R�O���ɂ��������A�����H��ƍ��������̂ł������B
�@�Ȃ��A���̐Ւn�͓y�n�E�����̈���������A�����̗L�����p�ɔ������B
������{�n��������Ё@
�@���a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�W���Ɂu������{�n��������Ёv���A����R�T�U�Ԓn�ɐݗ�����đ��Ƃ��J�n�����B���̉�Ђ̐ݗ��ɂ������Ă͎�X�̌o�܂����邪�A���̊T�v���L���ƁA���a�S�O�N�ɒ����Ə�̉��z���K�v�ƂȂ�������A���܂��ܔ_�яȂł͐H���̎����g��ɑΉ����A���ʂ̍������Ǝ������̋ߑ㉻�𐄐i���邽�߁A�u�H�����ʎ{�ݐݒu���Ǝ��{�v�́v���߁A��v�e�n�ɐH���Z���^�[�̐ݒu�𐄐i������j��ł��o�����B
�@�����Œ��Ƃ��Ă͂��̋@������A���삷�Ȃ킿�n���E�w�R�̑S��ƌ�u�E�_�U�̈ꕔ���܂߂����Y�n�т̒��S�Ɉʒu����K�n�Ƃ��Ė������グ���̂ł���B����ɂ�肱�̒n���̐H�����ʂ̈���ƒ{�Y�U���Ɋ�^����Ƃ����ϓ_����A���̃Z���^�[�̐ݒu��̂ƂȂ邱�Ƃ̑I����A�ߑ�I�Ȏ{�݂̌v��ɒ��肵���B�܂��A�v����������邽�߂̋��͍H��U�v�ɂ��ẮA�k�C�����ƌ��Ђ𑋌��Ƃ��Č��𑱂����Ƃ���A�����ЂƑ�m���Ɗ�����Ђ���ђ��̎O�҂ɂ��o���́u�k�C���H�����Ёv��ݗ����邱�ƂɌ��肵�A�{���Z���^�[�ɕ��݂��ăn���A�\�[�Z�[�W�A�x�[�R���Ȃǂ̉��H�H��ƕt�ю{�݂����݂̂����A�����~��̘H�ɉ����������Ƃ����̐������邱�Ƃɐ��������B
�@�����ݒu����u����{���Z���^�[�v�́A�N�ԂQ���T�O�O�O���̂ƎE��̏������\�ŁA�������\���I�ʼnq���I�ȐH������������ߑ�I�Ȏ{�݂��v�悳��A���a�S�O�A�S�P�N�̓N�������Ď{�s���ꂽ�B
�@�ƒ{�ꕔ��͂S�O�N�x����g�p�ł��邱�ƂƂȂ�A���N�P�Q���S���ɐݒu���̎w�߂����B���̃Z���^�[�͖k�C���H�����Ђ��o�c������H�H��ƈ�т���������}�邽�߁A�g�p�J�n�Ɠ����ɑS�ʓI�ɓ��ЂɋƖ����ϑ����ĉ^�c�ɓ������̂ł���B
�@�Ȃ��A���̒{���Z���^�[�̌��ݎ��Ɣ�́A�����⏕�ƋN�ɂ���Ċm�ۂ����������[�p����ق��́A���ׂĐH�����Ђ����B����Ƃ�����茈�߂ōs���A�������N�̏��҂Ɍ������z�Ђ����N���S���A���ꂪ�����������_�ŃZ���^�[�̏��L���ЂɈڏ�����Ƃ����������킳��Ă����B
�@�������ē���{���Z���^�[�͐H�����ЂɋƖ����ϑ�����A����Ɍ��Ђ��ݒu�������H����A���a�S�P�N�i�P�X�U�U�j�T������]�ƈ��V�U���������đ��Ƃ��J�n�����B�������A�����̗\�z�ɔ����Č��Ђ̋Ɛт͐U��킸�A�₪�đ��z�̗ݐϐԎ�������Čo�c����Ɋׂ����B���̂��ߌ��Ђ́A�o�c�̍Č���ڎw���ĂS�U�N�Q���ɐV��Ёu�k�C���{�Y������Ёv��ݗ����A�K�͂̏k���ƍ�������}�邱�ƂƂ����̂ŁA���͂R���P������{���Z���^�[�̋Ɩ���V��ЂɈϑ����邱�ƂƂ����B
�@�������V��ЂƂ͂Ȃ������̂́A���Ɍo�c��Ղ��������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�ˑR�Ƃ��Đ��i�̘̔H�J����i�܂ʂ܂܊Ԃ��Ȃ��s���l�܂���������A�T�O�N�Q���ɂ͂��ɔ��_�H��̕������\���ꂽ�̂ł���B
������{�n���i���j�i�ʐ^�P�j

�@���̍H����́A�P�ɒ{�Y�̐U����n��Y�Ƃ̈琬�Ƃ����悤�Ȗ�����ł͂Ȃ��A�]�ƈ��S�T���̏A�J���A����ɂ�����{���Z���^�[�̉^�c�ȂǁA�h�������肪�������Ƃ��Ă��d��Ȃ��Ƃł������B���������Ă��������������̂��߁A���͋c��ƘA���������Ȃ���k�C���{�Y�ƂƂ��Ɏ��s���������ʁA�K���ɂ����{�n��������Ёi�{�ЁE���j�̐i�o�����肵�A�y�n�E���H�H�ꂻ�̑��t�ю{�݂��̂������Ƃ��邱�ƂɂȂ����B�������ĂT�O�N�W���Ɍ��n�@�l�Ƃ��āu������{�n��������Ёv���ݗ�����A�X���P�����瑀�Ƃ��J�n���ꂽ�̂ŁA���͓�������{���Z���^�[�̋Ɩ��ЂɈϑ������̂ł���B
�@���̌㓯�Ђ͒{���Z���^�[�̔�������]�����̂ŁA���͋N�����ґ����z�ł���Q�S�T�T���]�~�������Ď{�݈��n�����ƂɌ��߁A�T�P�N�P���R�P���ɂ��ׂĂ̕����������n���A��������Łu����{���Z���^�[�v��p�~�����B
�@��W�߁@�́E�Ӑ�
�́E�Ӑ�
�@�����ɂ�����n��H�ƂƂ��č̐E�ӐƂ�����B
�@�����ɂ́A�V�y���E��c�ǁE�����Ȃǂ̑傫�Ȑ삪����A�����̖{����x���Ō��Ƃ̎��ނƂȂ鍻���̎��A�����n�扺�̏�̐ΎR�ł͍̐��Â�����s���Ă���B���ɐ풆����ʂ��āA���_��s��̌��݂⍑�S���ٖ{���̘H�Օ⋭�p�Ƃ��Ă̎��v�ɉ����A��ʂ̍����̎悪�s���Ă����B
�@�܂��A���a�R�O�N��㔼�ɑł��o���ꂽ���̍��x�o�ϐ�������ɂ��A�H�Ƃ⌚�Ƃ̒������L�W�ɂƂ��Ȃ��A���ނƂ��Ẳ͐썻���̎��v�͑傫���Ȃ����B
�@�����������Ƃ���A���a�S�O�N�i�P�X�U�T�j�S���ɂ́A���َs�E�n���E�w�R�x���Ǔ��̍����̎�Ǝ҂����̑̐����m�����邽�߁A���ٍ����H�Ƌ����g����ݗ������B�����ɂ͐X�E�����E���_�̎O�����NJ����Ƃ��锪�_�������u����A�������ɂ͉͈��Y�����������B
�@���̌�A�����̎�Ƃ͂S�R�N�W���ɁA�ӐƂ͂S�U�N�P�O���ɁA�ƊE�̍ЊQ�h�~�ƌ��S���W��ړI�Ƃ��ēo�^���ƂȂ�A�T�S�N�ɑO�L�����g���́u���_�E�X�E�����n�捻���Ӑ���v��ݗ����A�T�U�N���݉��������������������˂ċ���߂Ă���B
�@�������ē������{����Ă��������T�����ܑ̕��H����e�퓹�H�̘H�Օ�C�H���ȂǁA�������Ƃ̎�v���ނƂ��ċ������ꂽ�B
�@����A���x�o�ϐ�������̐L�W�ɂƂ��Ȃ��A���R�̂悤�Ɋe����Q��肪�������A���a�S�U�N�ɂ͐��������h�~�@�̎{�s�ɂ���āA�����r�������߂�ꂽ�B�����̎�ɂ��Ă͐������������Ɛ��Y�ɉe���������炷���Ƃ���A�T�O�N�R���ɔ��_�������ӐΌ��Q�h�~���͉�i�V�Ёj���������A������є��_�E���������Ƌ����g���ƌ��Q�h�~���������̂������ۑS�ɓw�߂��̂ł���B
�@�������������̂S�W�N���ɔ��������I�C���V���b�N�ɂ���āA�ݔ������̗}����������Ƃ̏k���ɂƂ��Ȃ����ތ��v�̌��ʂƁA�͐썻���̌����ɂ��ē����̋K�����������Ȃ����B����ɍ̎�ʂ��͐삨��ъ���ۑS�̋��e�͈͓��Ɍ��肳���悤�ɂȂ�A���̗ʂ͑Q�����A�Ő����̂S�U�A�V�N����ɂ͖�T�O���������[�g�����������̂��A�T�T�N�ɂ͂��̖�R�O�p�[�Z���g�ɗ������B�܂��A�͐썻���̌͊��ɂ��̎�͕s�\�ƂȂ������߁A�������̍̌@�ւƈڍs���A�T�T�N����͖��L�n�ƌ_��̂����@�B�@����s���Ă���B
�@�T�U�N���݂̍̐Ǝ҂́A�|�썻���A�i�L�j�s���A�i�L�j�ؑ������H�ƁA�i�L�j���_�O���ӐA�i���j�͈�H�ƁA�i���j�_�n�g�A�k�M�ӐH�Ɓi���j�̂V�Ђ�����A�����H���Ȃǂ̌��ɂ���čӐ̎��v�����������߁A�k�M�ӐH�ƈȊO�̊e�Ђ͓y�؍H���Ƃ����˂ĉc�Ƃ𑱂��Ă���B
�@��X�߁@�H�Ɖ��̑��i
�H��U�v�ւ̒���
�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�ɂڂ����������N�푈�̉e���ɂ���āA�킪���̍z�H�Ɛ��Y�͈ꋓ�ɉ���ƂƂ��ɁA���ێ��x���悤�₭���P�����Ɏ������B����܂ł̐H�Ƒ��Y��{���̍���́A�H�Ɛ��i��A�o���A���ޗ���_�Y����A����������ւƐ����]�����i�߂�ꂽ�̂ł���B���ɂR�O�N��ɂ�����{�i�I�ȍ��x�o�ϐ�������ɂ���āA���������E�L���̏d���w�H�ƍ��ƂȂ����̂ł���B���������̔��ʁA�Y�Ƃ�l���̓s�s�W�������i�݁A������ߑa�E�ߖ��̕��Q�݁A�H�ƒn��Ɣ�H�ƒn��̏����i�������傷��X�����ڗ��悤�ɂȂ����B
�@���������f���āA�����ɂ����Ă��l���̗��o���ۂ��݂��͂��߂����߁A�����̎��~�߂ƌٗp�̋@����g�傷�邽�߂̕��ł��o���ꂽ�B���Ȃ킿�A�V���ɒ����ɍH���ݒu������̂ɑ��A�������t�̓����J���čH�Ƃ̗��n�𑣐i���A�n��Y�Ƃ̊J����}��ړI�������ď��a�R�T�N�U���u���_���H��U�v���v�𐧒���z���A���P�Ƃ̎{����u�����̂ł���B���̏��ł́A�����Œ莑�Y�z�T�O�O���~�ȏ�������āA���̐����܂��͉��H�������͏C���̍�Ƃ��s�����Ə���V�݂������̂ŁA�Y�Ƃ̊J���U���Ɋ�^����ƔF�߂����̂ɑ��A���ݔN������O���N������A���N���ŌŒ莑�Y�Ŋz�̂P�O�O�p�[�Z���g�ȉ��V�O�p�[�Z���g�A�T�O�p�[�Z���g�ƑQ����������������ď������邱�ƂƂ����̂ł���B
�@���̏��̎{�s�ɂ���ēK�p�����̂́A�R�U�N�x�̒r���x�j��������З����H����͂��߂Ƃ��A��q�̒�H�@�K�p�ݔ��ȉ��̂��̂Ƃ��āA�R�X�N�̓n�Ӑ��ޏ��̐��ލH��A�S�O�N�x�̓����u���b�N������Ж�c�ǍH��̂ق��A�ԗ������H��łS�P�N�x�̔��كg���^�A�S�S�N�x�̃c�o���H�ƂƔ��ٓ��Y�A�S�T�N�x�̔��_���_���ԗ������H��Ȃǂ��������B
�@�Ȃ��A�{����H�@�ɂ��d�œ��ʑ[�u�@�̓K�p������̂ɂ��ẮA�H��U�v���̓K�p�����O������̂Ƃ��Ă������A�T�R�N�V���ɊW�����������āA�J���n��ɂ�����d�œ��ʑ[�u�@�̓K�p�ݔ��ȊO�̂��̂ł����Ă��A����ɕt�т���ݔ��ł��鎖������Βn�тȂǂɂ��ẮA�T�R�N�x��������ɍH��U�v����K�p���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��A�H�ꗧ�n�̗v������肢�������ɘa�����̂ł��邪�A���̓K�p��P���̓��}�n�k�C������������Ђł������B
��H�@�K�p�ɂ��H�Ɖ�
�@�������A�����������̒P�Ǝ{�A���̑傫�Ȗ������{�I�ɉ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��͓̂��R�ł����āA���ɂ����Ă����̒��ォ��H�Ƃ̕��U��}��n��J�������W�J�����̂ł���B
�@���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�U���ɁA��i�n��ւ̍H�Ɣz�u��ϋɓI�ɍl�������u�H�ƓK���z�u�\�z�v�̍�����͂��߂Ƃ��āA���N�P�P��������z�́u��J���n��H�ƊJ�����i�@�v�i��H�@�j�Ȃǂɂ���āA�����m�x���g�n�сi�����E���E���É��y�т��̎��Ӓn��j�ɏW�����Ă���H��U�z�u���A�������J���̋��_�Ƃ��ėL�@�I�ɑ��݂ɉe��������Ɠ����ɁA�A�������I�ɒn��̔��W��}�낤�Ƃ����̂ł���B
�@��H�@�́A�������g��J���n���h�́u�H�Ƃ̊J���𑣐i���邱�Ƃɂ���Čٗp�̑���Ɋ�^���A�H�ƒn��Ɣ�H�ƒn��̏����i���̏k�����͂���A�����o�ς̋ύt���锭�W��ړI�Ƃ���v���̂ŁA�Y�Ƃ̊J�����x���Ⴍ�A�o�ς̔��W
�����u���b�N�i���j��c�ǍH��i�ʐ^�P�j

�̒���Ă���n��̂����A�H�Ƃ̔��B���邱�Ƃɂ���Ēn����̍H�ƊJ���𑣐i����ƔF�߂���n��i���J���n��j���w�肷��B�����Ă��̊J���n����̍H�ƗU�v���i�̂��߂̗U�v��Ƃɑ��ẮA���̊�ɂ�荑�łőd�œ��ʑ[�u�@�ɂ����ʏ��p�i�R���̂P�j���F�߂���ق��A���łŕs���Y�擾�ŁE���ƐŁE���łŌŒ莑�Y�ł̌��Ƃ��u�����邱�Ƃ�F�߁A����Ɏ{�݂̐����ɂ��ē��ʂ̔z�����������邱�ƂƂ��Ă����B
�@���������u��J���n��H�ƊJ���n��v�̎w��́A���a�R�V�N�X������J�n����A�S���łP�O�T�n��A�k�C���łP�P�n�悪�w�肳�ꂽ���A�����͂R�W�N�P�O���Ɂu�X�E���_�E�������n��v�Ƃ��Ďw������B���͂���ɑΉ����邽�߁A�S�O�N�P���Ɂu���_����J���n��H�Ƒ��i�̂��߂̌Œ莑�Y�ł̖Ə��Ɋւ�����v�𐧒肵�A��H�@�Ɋ�Â������̎��Ƃ̗p�ɋ�����ݔ���V�݂��܂��͑��݂������̂ɂ��āA�O���N�x���̌Œ莑�Y�ł�Ə����邱�Ƃ����߁A�R�X�N�x����K�p���邱�ƂƂ����̂ł���B�����Ă��̏��́A�d�œ��ʑ[�u�@�̒�߂�Ƃ���ɂ��ېŖƏ��̓K�p�N�����J���n��Ƃ��Ďw�����������P�U�N�ȓ��Ƃ������A���̌㐔��̖@�����ɏ������Ē����������A�T�U�N�X���̎��_�œK�p�N�����Q�O�N�܂ʼn����i���a�T�W�N�x�j����A�H��U�v�ɑ傫�Ȍ��ʂ��グ�Ă���B
�@���a�S�V�N�x�ȍ~�A��H�@�Ɋ�Â��Œ莑�Y�ŖƏ��̓K�p�������Ə��͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B
��H�@�ɂ��Œ莑�Y�ŖƏ����
| ���@�@�Ɓ@�@���@�@�� | �Ɓ@���@���@�� |
| ������Ѓ~�J�h�t���[�����O���쏊 | ���R�X�`�S�P |
| �V�S�V�`�S�X | |
| �������X�ݖ������������ | ���S�W�`�T�O |
| ���T�Q�`�T�S | |
| �T���n�C�u�H�Ɗ������ | ���S�X�`�T�P |
| ���샌�~�R��������� | ���S�X�`�T�P |
| ������Ё@倁@�� | ���S�X�`�T�P |
| �n�����R���N���[�g������� | ���S�X�`�T�P |
| �L����Ё@���}�L�e�n���X | ���T�O�`�T�Q |
| ������{�n��������� | ���T�Q�`�T�S |
| ���}�n�k�C������������� | ���T�R�`�T�T |
| �L����Б����d�C�����ԍH�Ə� | ���T�S�`�T�U |
| ������Ѓ~�J�h�t���[�����O���쏊 | ���T�P�`�T�R |
| ���كg���y�b�g������Д��_�c�Ə� | ���T�T�`�T�V |
| ���_���X�ёg�� | ���T�T�`�T�V |
| �V�T�U�`�T�W�i�lj��j |
�i�����E�������ہj
�_�H�@�ɂ��H�Ƃ̓���
�@����������J���n��̍H�ƊJ�����i�𒌂Ƃ���ϋɓI�Ȏ{��̐��i�ɂ�������炸�A�ЂƂ��є��������ߑa�E�ߖ��̕��Q��A�s�s�Ɣ_���Ƃ̏����i������̌��ۂ�}�~���邱�Ƃ͗e�Ղȏ�Ԃł͂Ȃ������B���̂��ߍ��́A���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�U������Ɂu�_���n��H�Ɠ������i�@�v�i�_�H�@�j�𐧒�A�ߑa�����ۂ��������Ă���_���n��ɍH�Ƃ�ϋɓI�A�v��I�ɓ������Ĕ_�Ə]���҂��A�E�����邱�Ƃɂ���āA�_�ƍ\���̉��P��_�ƂƍH�Ƃ̏����i��������}�邱�ƂƂ������̂ł���B�������A����܂ł̒�H�@�����_���Ǔ��S���ΏۂƂ��Ă����̂ɑ��A�_�H�@���K�p�����n��͓��ɒ����H�Ɠ����n��ƒ�߂��n��Ɍ����A����ɐi�o�����Ƃ◣�_�҂ɑ���Ő��܂��͋��Z��̗D���[�u���u����ق��A�s�����ɑ��Ă͒n���ł̌��ƂɂƂ��Ȃ�������[�u�Ƃ��āA��t�łɂ���ĕ�Ă���u���邱�ƂƂ����̂ł���B
�@���āA���̔_�H�@�̐���ȑO�ł���A�������H�ꗧ�n�Ɋւ���ŏ��̖@���Ƃ������ׂ��u�H�ꗧ�n�̒������Ɋւ���@���v�i���a�S�W�N�P�O�������Łu�H�ꗧ�n�@�v�Ɖ��́j�����a�R�S�N�S���Ɏ{�s����Ă����B���̖@���́A�H�ꗧ�n�����̕ۑS��}��Ȃ���K���ɍs����悤�ɂ��邽�߁A�H��K�n�̒����A�H�ꗧ�n�̓��������A�����čH�ꗧ�n�ɂƂ��Ȃ����Q�̖h�~�Ɋւ��钲���Ȃǂ��s���A���炩���ߒʏ��Y�ƏȂɂ����āu�H�ꗧ�n������v���쐬���A�H��܂��͎��Ə��ݒu���悤�Ƃ���҂Ȃǂ̉{���ɋ����ė��ւ�}��ƂƂ��ɁA�Z�������ƒ��a�̂Ƃꂽ�H��܂��͎��Ə�̐ݒu��}�낤�Ƃ����|�Œ�߂�ꂽ���̂ł���B
�@���ł͏��a�R�X�N�R���A���̖@���ɂ��H��K�n�̑I����s���A�O�����c�n�Ɨ���c�n�̂Q�n��ɂ��āA�O�L�u�H�ꗧ�n������v�ɓo�^�����悤�葱�����o�Ă������A�_�H�@�̎{�s�Ɋ�Â��_���H�Ɠ����n��Ƃ��āA�O�L�Q�n��̂ق��A�V���ɖ�c���c�n�R���X�P�X�Q�������[�g����lj����ĂR�c�n��I��A�S�W�N�P���Ɏ��{�v��̌��\�����̂ł������B�������A�k�������̍H��U�v�ɑ���ϋɓI�Ȏp���Ə��ʂ̏�ω��ɂ��A���{�I�Ȍ������𔗂���Ƃ���ƂȂ����̂ŁA�S�X�N�x�̍H��K�n�����납��O�����A����̂Q�c�n���͂����Ė�c���c�n�����Ƃ����B����ɁA�T�P�N�R���ɂ͊W���ǂƋ��c���d�ˁA�_���H�Ɠ����n����c���c�n�̈�{���ĂɕύX���A�܂��A�n��ʐς����łɔ_�ƐU���n��̎w����Ă���_�p�n���ɂ��g�債�ĂT�R���U�R�P�X�������[�g���ɕύX�̎葱�����Ƃ����̂ł���B�������āA��c���n��̔_���H�Ɠ����n��̐ݒ���݁A�u���}�n�����H��v�U�v�����̑f�n�������ƂƂ��ɁA�V�K��ƗU�v�ɔ����ėp�n�̊m�ۂ��}��ꂽ�̂ł������B
�H�ƍĔz�u���i�@
�@������������̓W�J�ɂ�������炸�A��ǓI���n����݂Ă��A�ߑa�E�ߖ��̕��Q�����������ɂ����܂�ڌ����݂��Ȃ��������߁A���͒n��J���̎哱�͂ł���H�Ƃ��ߑa�n��ɕ��U�����đS���I�ȍH�Ƃ̍Ĕz�u���s���A�ߑa�E�ߖ��̖��������ɉ����������Ƃ��āA���a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j�ɐ���{�s�����̂��u�H�ƍĔz�u���i�@�v�ł���B
�@���̖@���ł́A�ߓx�ɍH�Ƃ��W�ς��Ă���n����u�ړ]���i�n��v�Ƃ��A�H�ƏW�ϓx�̒Ⴂ�n����u�U���n��v�ƒ�߁A�k�C���ł͎D�y�s�Ǝ����s�������S�n�悪�U���n��Ƃ��ꂽ�B
�@����́A�ړ]���i�n�悩��U���n��ɍH�ꂪ�ړ]����ꍇ�A���͈ړ]����H��ƗU�v��̎s�����ɑ��A�ړ]��H��̏��ʐψꕽ�����[�g�������肻�ꂼ��T�O�O�O�~�̕⏕������t���邱�ƁA�܂��A���͈̔͂̍H��̐V�E���݂ɑ��čH�ꏰ�ʐψꕽ�����[�g��������T�O�O�O�~�������n���s�����Ɍ�t���邱�ƂȂǂ��߁A�������ꌏ������̕⏕���x�z�͈ꉭ�~�ƒ�߂��Ă����B�����ĕ⏕���́A�Βn�сE�����E��n�E�r�E�r���H�Ȃǂ̊��ۑS�{�݁A�^����E�̈�فE�v�[���E�������Ȃǂ̕����{�݂̌��ݔ�Ɍ��肵�A���ۑS����ьٗp�̈�����\���l�����āA�����o�ς̔��W�ƕ��������}��Ƃ������̂ł������B�Ȃ��A���̂ق��ړ]����H��ɑ��Ă��A�������Ő���̗D���[�u���u����ꂽ�ق��A���̓y�n�J�����Ђ����炩���ߎ擾��������H�ƒc�n�ɌW���ؓ����c���ɑ��A���N�P�E�V�p�[�Z���g�̗��q�⋋���s����Ȃǂ̉��T���t�^����Ă����B
�@�Ȃ��A�����������x�ɂ���ď��a�T�Q�N�x�ɐi�o�������}�n�k�C������������Ђ�ΏۂƂ��āA���Ɍ�t���ꂽ�⏕���͂R�S�P�P���T�O�O�O�~�ŁA����͋��y�����ٌ��݂̍����Ƃ��Ďg�p���ꂽ�̂ł���B
�@��P�O�߁@�U�v��Ƃ̊T�v
��ƗU�v�̓W�J
�@���̉ߑa���h�~�ƘJ���s��J��̂��߁A��ƗU�v�����s�̏d�_�{��Ɍf�����k�������́A���a�S�U�N�A�C���X���̖��Ɏ��g�݁A���������Y�ƂƋύt�̂Ƃꂽ��ƗU�v��}�邽�߁A�S�U�N�U���ɐV���ɏ��H�ۂ�ݒu���ď��H�U������ɒS�������A�S�V�N�R���ɂ́u�H��K�n�ē��v���쐬���A���̎w���@�ւ⒆���̌o�ϒc�́A���̏o��@�ւȂǂ�ʂ��A�����Ȋ�ƗU�v�^����W�J�����̂ł������B
�@�܂��A��ƗU�v�̊�{�ƂȂ�H�Ɨp�n�ɂ��ẮA�������E���v��ȏ�ԂƂȂ炸�A�������I�m�ȋ@�\��������c�n�̊m�ۑ������߂������̂ł���B���̂��߁A�k�C���J���R���T���^���g�Ɉ˗����āu�H�ƒc�n��{�v��v���쐬�A�p�n�E�p���E�J���́E�d�́E��ʎ���Ȃǂ��ڍׂɒ������͂���ƂƂ��ɁA��Ɍ��Q�������ƂȂ�Ȃ���ƂŁA�n��̓����ɔz�����������Y�Ƃł���A���g�y���ʂ̍����K���Ǝ�ł��邱�ƂȂǂɗ��ӂ��A����ɘJ���͂̊m�ۂɂ��Ă��\�������������A�u�I��I�U�v�v��}�邱�Ƃɓw�߂悤�Ƃ���z�����Ȃ��ꂽ�̂ł���B
�@���a�S�W�N�T���ɂ́u���L�n�g��̐��i�Ɋւ���@���v�Ɋ�Â��u���_���y�n�J�����Ёv�i�������E����s��v�j��ݗ����A�����p�n�E���p�n�Ȃǂ̎擾��Ǘ���e�Ղɂ��鐧�x��̓����J�����B�܂�����ł́A���̒ɂ���ĊW�s���@�ցE�c�̂Ȃǂőg�D����u���_���J���͊m�ۑ��A�����c��v��ݒu���A�n��Y�ƂƗU�v��ƂƂ̊Ԃɂ����āA�ߓx�̂���J���͂̊m�ۂɓw�߂邱�ƂƂ���ȂǁA����Ԑ��������B�܂��A�S�W�N�R�������Ɂu��ƗU�v���݈��v�i�����_�z�Ə������ː��������a�T�Q�N�܂Łj��u���A����ɁA�����Łu���_���J�����k��v���J�Â���ȂǁA�ƊE���̎��W���ƗU�v�������s�����̂ł���B
�@�����������̐ϋɓI�Ȋ�ƗU�v�ɑ���p��������t���A���a�S�U�N���H�Ɖۂ�����i�C�����H�Ƃ̖k�C���i�o���͂��߁A�H�ꗧ�n�Ɋւ������X�Ɗ��A���Ƃ��Ă����̗U�v�Ɋ����ȉ^����W�J�����̂ł������B�������A���N�W���A�����J�̃j�N�\���哝�̂ɂ��h���h�q����̔��\�A�S�W�N�̒����푈�ڂ����ɂ���ꎟ�I�C���V���b�N�ȂǁA���яd�Ȃ鈫�����������ĐV�K��Ƃ̗U�v�͍��������߁A���i�C�����H�Ƃ̐i�o�͂��Ɏ������Ȃ��������̂́A�S�W�N�Q�����Ƃ̃T���n�C�u�H�Ƃ��͂��߁A���Ɍf����H�ꗧ�n�̎����������̂ł���B
�@���T���n�C�u�H�Ɗ�����Ё��@�T���n�C�u�H�Ɗ�����Ђ́A�{�Ђ𓌋��ɂ������쌧���{�s�ɍH��������g�����H��Z�b�g�h�̒������[�J�[�ł���B�ߋ��\���N�ɂ킽���ē����т��猴�ޗ��ƂȂ�u�i�ނ��d����Ă����Ƃ����W����A���n���ɂƂ��Ă����̂̐[����Ђł�����B���������W�ɂ��铯�Ђ��A���˂Ă��璼�ږk�C���ɐi�o���A�H������݂���v�悪����Ƃ����������ł́A���������U�v�̖������グ�A�ϋɓI�ɂ͂��炫�������̂ł������B���̌��ʁA���a�S�V�N�S���ɖ�c����K�n�ƔF�߁A�����H��Z�b�g�̂���������H���V�݂��邱�ƂɌ��肵�A�ߑa���U�v��Ƃ̑�P���ƂȂ����̂ł���B
�T���n�C�u�H�Ɓi���j�i�ʐ^�P�j

�@���Ђ́A��c���W�Q�Ԓn�ɖ�S���������[�g���̕~�n�����A���N�X���ɖǂ�H��E�؍H��E������E�q�ɁE�������Ȃǂ̌��݂ɒ���A�@�B�ݔ����܂߂đ��z�R���Q�O�O�O���~�������Ď{�݂��������A�S�W�N�Q���P���{�i�I�ɑ��Ƃ��J�n�����B
�@���H��́A����̖L�x�ȃu�i���ޗ��Ƃ��āA�H�삢�������A�����Ɠ��k�n�����s��Ƃ��ďo�ׂ������A�u�i�ނ����������ĉƋ�p�̕��i�����A�S���̖؍ޓX��؍H��ɔ���o���ȂǏ��X�ɋƐт�L���A���a�T�O�N�ɂ͏]�ƈ��W�T���A�N�Ԑ��Y���ł����P�V���r�A�S���R�O�O�O���~���グ��ȂǏ����Ɍo�߂��Ă����B�������A���Ђ̌o�c�g��ɂƂ��Ȃ����H��̑�^�ݔ������Ȃǂ���A�����J��ɍs���l�܂���������A�T�R�N�P�P���Q�X���ɂ͓����n�قɑ��ĉ�ЍX���@�̓K�p��\���A�ٔ����̒�߂��Ǎ��l����ъW�l�W��ɂ��X���v��Ă������A�F�Ď��ƌo�c�A���Y�Ǘ����s���A��ЍČ��̂��߂ɓw�͂������A�؍ފE�̍\���s���ɂ��v��B��������ƂȂ�A���a�T�V�N�T���P�P�����Y������O��Ƃ��ĉc�Ƌx�~���\�����s���A�S�E�������ق���ɂ��������B
�@���������倗����@�������倗��͓����ɖ{�Ёi�В��E���c���Y�����{���S�S�O�O���~�j�������A�S���Ɍ܂̍H��������m�a�n��̃��C�V���c���[�J�[�ł��������A���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�k�C���ɑ�Z�H��̌��݂�\�肵�A���n���������Ƃ̏��ĐϋɓI�ȗU�v�^����W�J�������ʁA���̗v��������A���N�T�����n�������s���Љ���Z���^�[�O�ɍH�ꌚ�݂�����A�{�i�I�ɑ��Ƃ��J�n�����̂͂P�P���W���ł���A���ꂪ�U�v��Ƒ�Q���ł������B
�@���Ђ͔��_���y�n�J�����Ђ�ʂ��A�H��~�n�V�O�T�P�������[�g���]���A�H�ꌚ�݂ɒ��肷�����A�n���o�g�҂W�O�������̗p���A�O�����̐E�ƌP���Z�����H��Ƃ��āA�V������D���P�����J�n�����B�H�ꂨ��я]�ƈ��h�ɂ͓y�n�擾����܂ߖ�X�O�O�O���~�������ė����A���ƊJ�n�Ƃ��������Ȍo�܂����ǂ����B���H��́A�������̌S�R�H��ƂƂ��ɁA���i�̑啔������Ҍ����̑��ߗ��i����g���@���W���P�b�g�h�ɔ[�����A�o�����N�ԂQ���W�O�O�O�_�[�X�A��Q���~�ŁA�]�ƈ�����ɂP�O�O���ȏ��i���钬�����w�̍H��Ƃ��Đ��Y�����𑱂����B�������A�T�R�N�S���ɐ��i�[���悪�A�@�ۋƊE�s���̂�������ē|�Y����Ƃ����s���̎��Ԃ����������B���̂��ߓ��H��́A���ƌp�����s�\�ƂȂ�A���N�T���Q�O���������ĕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ����̂ł������B
�@��������Г��샌�~�R�����@���a�S�W�N�T������c�Z�����g�n��ɑ����銔����Г��샌�~�R���i�В��E����@�������{���Q�O�O�O���~�j���A�l���̍��������ɓ��Y�P���������[�g���O��̋K�͂�L���鐶�R���N���[�g�����H��̌��݂����肵�A���N�W���ɑ��Ƃ��J�n�����B
�@���H��̐i�o�́A�������_�E�F�ΐ��A���_�E�������̉��Ǖܑ��┪�_�E�����̉��ǒ����ȂǁA�y�؊֘A���Ƃɂ���Đ��R���N���[�g�̎��v�������Ȃ��Ă��邤���A�����k�C���V�����̕~�݂�c�ю����ԓ��̐V�݁A����ɁA���_�Ⓑ�����ɂ����鍑���o�C�p�X�Ȃǂɂ����v�̑��������҂���A�s��J���̗]�n���߂����Ă̐i�o�ł������B�������A�T�O�N�x�̏o���łP���U�O�O�O�������[�g���A�P���S�O�O�O���~�Ƃ��܈���L�єY�݁A�K�����������̐��ʂ��グ�Ă���Ƃ͂������A����Ɋ��҂���Ă���Ƃ���ł���B
�i���j���샌�~�R���i�ʐ^�P�j

�@�����}�n�k�C������������Ё��@�����ƂɎg�p���鏬�^���D�́A�D�O�@���������ɂ�铮�͉������y����ɂ��������A�؍ޕs���Ɖ��i�̍�����D��H�̋��l��ȂƂ���A�V����̑D�ނƂ��Ăe�q�o�i�K���X�@�ۋ����v���X�`�b�N�j���A�ϋv���A�y�ʐ����̑��ۑS�Ǘ��̗e�Ղ��Ƃ����_�ŋ����̒��ڂ��W�߂�Ƃ���ƂȂ�A���a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j���납��}���Ɏ��v���������Ă��Ă����B�����������Ƃ���A���}�n�����@��D�n�H��i��茧�j�Ő��������e�q�o�D���A�������Ď��v�ɂ������Ă����̂ł���B
�@����A�k�C�����Ƌ����g���A����Ȃǂł����Ђɑ��āA�k�C���̋���ɓK����D�`�J���Ɛ����H��̐i�o��v�]���A���Ђɂ����Ă����H�E���f�E�ɒB�E���_�Ȃǂ����n�ɋ����A�H�ꗧ�n�ɂ��Č����������Ă����B
�@�������������@�m�������ł́A���������ϋɓI�ȗU�v�ɏ��o���A�S�W�N�R������Ƃ�������ɂ킽�铯�Ђɂ�錻�n�����Ȃǂ̌��ʁA���N�U���̖{�Ж�����ɂ����ē��ЂƂ��Ă͂V�ԖځA�����ł͍ŏ��̂e�q�o�D�����H����A��c���n��H�ƒc�n�ɐi�o���邱�ƂƂ����̂ł���B���̂��ߒ��ł́A�y�n�J�����Ђ�ʂ��ėp�n����������ƂƂ��ɁA���Ǝ��̘J���͊m�ۂɂ��Ă��ϋɓI�ȋ��͑Ԑ��������ėՂނ��ƂƂ����B
���}�n�k�C�������i���j�i�ʐ^�P�j

�@��Ђ��玦���ꂽ�v��ɂ��ƁA�S�z���}�n�����@�o���ɂ�錻�n�@�l�ŁA�������͂S�X�N�ɒ��H���ĂT�O�N�t�̑��ƊJ�n�ŁA�������͂T�P�N�ɒ��H���ĂT�Q�N�Ɋ��������A�P�O�g�������̂e�q�o���͋��D�Ƙa�D�����邱�ƂƂ��Ă����B�������S�W�N�̃I�C���V���b�N�ɂ���āA���ނ̕s���Ƒ����v�}����ɂ��A���Ԃ̐ݔ��������}����ꂽ���߁A�V�K���H�͑啝�ɒx��邱�ƂƂȂ����B���̊ԁA���a�T�O�N�ɔ��_�����Ƌ����g���������Ă��鋤�����ƌ��̊֘A����A�C�ʎg�p�ɂ��Ă̋��c��������A��Б��͋��ƐU�����͋��P�V�O�O���~���x�������ƂƂ����B���̌㒅�X�������i�߂��A�T�Q�N�t�H���ɒ��肵�A���`�g���H����͂��ߎ������E�g�[�@���E���͎��ȂNJ֘A�{�݂����݁A���N�P�O���P�Q���ɗ��������s�������ɑ��Ƃ��J�n�����̂ł���B
�@���a�T�V�N���݂ł͏]�ƈ����W�U���A�N�ԏo�z�͂P�O���U�O�O�O���~�ɋy��ł���B
�@���L����Д��_�d�q���@���a�T�R�N�i�P�X�V�W�j�T���ɕ������������倗��̎{�݂ɂ��Ē��͓��ЂƋ��c�̌��ʁA�y�n�E�����Ƃ��ɖ�V�O�O�O���~�Ŕ������A�����̐V�K��Ɛi�o�̂��߂ɔ������̂ł������B
�@���ł͂��̎{�݂����p�ł����Ƃ̐i�o�ɂ��ď��̎��W�ɓw�߂��Ƃ���A�������쏊���o�����Đݗ����錻�n�@�l�ŁA�����̂k�r�h�̑I�ʍ�Ƃ��s���H��Ƃ��āu�L����Д��_�d�q�v�i�В��E��ljx�j�̐i�o�����肳��A���̎{�݂����ē����������s���A�T�R�N�P�Q�����瑀�Ƃ��J�n�����B
�@���Ђł́A�����������瑗���Ă��锼���̂k�r�h�̗ǔۂ�I�ʂ̂����Ăѓ��������ɑ���Ԃ����̂ŁA���ԂP�O�O�����I�ʂ���A��Ƃ��Ď��v�E���W�I�E�e���r�E�d�q�v�Z�@�E�R���s���[�^�[�W�Ɏg�p�����B�Q�S���ԑ��Ƃ��s���Ă���A���ƈȗ��N�X�Ɛт�L���A�n����ƂƂ��Ă܂��܂����W�����҂���Ă���B
��U�́@�z��
�@��P�߁@���������܂ł̒n������
�V�y�����R
�@�����ɂ�����n�������Ɋւ���ł��Â��L�^�Ƃ��ẮA�O���O�ˎ���i�P�T�X�O�`�P�V�X�X�j���璅�ڂ���̌@���s���Ă����u�V�y�����R�������B����ɂ��Ắu�V�k�C���j�v�i��ʐ���)�ɁA
�@�V�y�����R�@���ɏ��������o�������A��ʕs�ւ̂��ߒ��~���ꂽ�B�̂��ݓc�s�O�Y�����a�l�N����\�N�ԁA�Y�o�z�\���̈�̉^��������č̌@�ɏ]���������A���v���Ȃ��̂ŕ��������B
�Ƃ���A�܂��u�k�C���Y�ƔN�\�j�v�ɂ́A
�@�����N�i�P�U�V�S�j�V�y���z�R�̍̍z�ɒ��肵�A��E���E�����Y�����B
�Ƃ�����A���̂ق��ɋ��A����Y�o�����悤�ł���B����͍�����R�O�O�N�ȏ���O�̂��Ƃł���A�^�U�̂قǂ͂��܂��Ɋm�F����Ă��Ȃ����A���y�����ق̐������A���̂�����I����̂Ɏg�p�������̂ł���Ɠ`�����Ă���B
�@�܂��A���̌�̂��Ƃɂ��ĐG�ꂽ�j���Ƃ��ẮA�����R�N�i�P�W�T�U�j���Y���l�Y�́u���ڈΓ����v�ɁA
�@���i�N�ԁi���P�V�V�Q�`�P�V�W�O�j�����@�肵�ɎR����Ď��l�����B�̑���p�B�ƂȂ肵�R�B�R��ɋg���^�J�B���v�������ꍡ�͐��ɏo��悵�B
�ƋL���Ă��邪�A�R�N��̈����U�N�ɂ͖��{�����c�ōĊJ���Ă���Ƃ�����݂�ƁA���̋g���@�^�Ȃ�҂��Ԃ��Ȃ���߂Ă��܂����悤�ł���B
�@�����N�Ԃɓ���Ɣ��ٕ�s�͒n�������̊J���ɗ͂𒍂��A�Q�N�V���ɉڈΒn�J��G�������z�����Ƃ����A���E��E���E�S�E���E�R�Ԍ@�V�V�A�������p���Ȃđ����x������̂́A�N�G������A��Ƌ��i���j�L�i���j�V��B���@�o��z�ނ͒����Ɍ䔃��i���j�L�i���j�V���B
�Ƃ������j�������čz�ƊJ�������シ�����A���{��������悵�Ă��̊J���ɓ��������B���Ȃ킿�A���R�N�ɔ��ٕ�s�́A���ْn���̋��E�⥓��E�S�E���̏��z�R����������ƂƂ��ɁA���ɓ암�˂ɖ����čz�R�ɏn���������̂�h�������A�z�R�̗ǔۂ��Ӓ肳����ȂǐϋɓI�ł������B
�@�����������j�ɂ���āA�����U�N�ɂ͎����I�ł͂��邪�V�y�����R�����c�ō̌@�����炵���A
�@���ڈΒn���[���b�v���R�V�V�A���N�i�������U�N�j�����@��|�A�i�ʏo���X�A�����ҕ��v���A�c�c�i�ȉ��ȗ��j�c�i�V��k�C���j��܊��j����j
�ƗǍD�ł��邱�Ƃ���Ă��邪�A��ɂ��̂Ƃ��̎Y����d�������R�z�̋��Ƃ̂ӂ��������肩�甭������A���̎����𗠕t�����̂ł���B
�܂��A���̍z�R����̂�鉔�́A�u�i�����j�̖ډ��v�ƌĂ�A�㎿�̂��̂ł������Ɠ`�����Ă���B���̊��c���R�̋K�͂͂܂т炩�ł͂Ȃ����A�����_�z�R��n�ɕ��v���N�i�P�W�U�P�j����Ŏ��S�����Ɠ`������l�����̕悪�������邱�Ƃ���݂Ă��A���Ȃ�̋K�͂������̂ł͂Ȃ����Ƒz������Ă���B�Ȃ��A�����̎��S�҂́A���k�n���i�H�c�����p�S�j�̏o�g�҂ł��������Ƃ��������Ă���B
����N�ԗV�y���z�R�ŋ��I����̂Ɏg�p�����Ɠ`����������i�ʐ^�P�j

�@���v���N�ɖ��{�́A�ڈΒn�̍z�R���J�����邽�߁A�A�����J����n�����z�R�w�t�ł���u���[�L�ƃp���y���[�̂Q�������������B���̗��҂͗��Q�N�X���ɗV�y�����R�����A�Ζ���g���Ċ��j�ӂ�����@���w���������A����͂킪���ɂ�����ŏ��̎��݂ł������Ƃ����Ă���B���̂Ƃ��̏́u�u���[�L�E�v�v�Ɏ��̂悤�ɋL�^����Ă���B
�@�E���v�z�B
�@���B�n��m�n�m�B�g����j�V�e�A���͋ƃm�͗l���������^���B���m�u�u���[�L�v�n�Aৃj�甪�S�Z�\��N�㌎�Z���j�����Z�V�j�A���i���^�j�P�ǃg���G�^���B���B����ƃ��c���n�A���j�S�\�N�T����S�N�O�����m���j�V�e�A�����z�V�j�]���X�����m�A���B�R���g���A����ৃj�ƃ��N�Z�V���m�n�N�^�����m���\�n�Y�B���B�j�n�A�d���^�������O���A���B�ӃV�L�R���j�V�����`�A�����R�m�\�ʃj�B�Z���B�������ԃj��l�����A���e�A�������F���X�j�s�ăi�������A���A�ȃe�݃j���ʃY�x�V�B���B���m�d�i���������n�r�_�Ȑ܃Z�������m��H�j�V�e�A���j�R���e�n�ʍs�w�h����i���B��m���S�i�����j���e�n�A�ʘH�m���T�̓j�ڕ��O�ڃj�߃M�Y�B�A���J�w�n�A�S�ƁA���y�r�ߚ{�m�~���p�q�V�i���B���m�u�u���[�L�v�m�n���e�Ζp�q�e������X���m�@���{�Z�V�n�����B�j�V�e�A���n�j�A�e�B�v�j���p�@�����w�V�j�A��j���{�m�Ӄj�K�q�A���ʃm������^���B
�@���̌�A�����U�N�i�P�W�V�R�j�P�Q���ɁA�n�����z�R�t�����C�}�����J��g�������c�����ɕ����u�n�����ʏ����v�ɂ��ƁA
�@�]�A�R�z�������H�R���g���j�E���v�m�����z�j���A�u�������[�v����s�������j���e�׃X�x�L���ʃm���j�t�A���V�N���׃m�w�������P�i�A�A�����N���z���n�����j�V�e�J�̃X���j�����U���x�V�B�\�N�O�V�����p���Z���n�����i���g�m�_�j�������J�j
�ƋL����Ă��邪�A���̕ǂ���P�O�N�Ƃ��ċt�Z����Ε��v�R�N����̂��ƂƂȂ�A�u���[�L���Ζ�̎g�p���@���w���������N����ɂ́A���̗V�y�����R�͔p�B����Ă������ƂɂȂ�킯�ł���B
�Ζ�
�@�u���[�L�͗V�y�����z�̂ق��A�R�z���̐Ζ��ɂ��Ă��������s�����o���Ă��邪�A����ɂ��ƁA�@�Ζ�
�@���Θp�ȃm�R�z���j�Z���i���Ζ��m���o�X�����A���B���Z���i�����F�g�n����吧嗎���m�@�V�B�R���g���i�ʑ�R�i���Y�B���V���@���e�[�L�j�������A��w���o�������X�@�L�����i�����l�i�V�B���n���j���e�n�A��������ފ��_���p�g�i�V�A���n�ȃe���n�m�������������B�c�c
�Əq�ׂĂ���A�Ƃ��Ă����҂����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@���̌�A�����W�N�i�P�W�V�T�j�S���A����ɂ��Ē����������C�}���ɂ��u�k�C���R�z���Ζ��n�������v�̂Ȃ��ł��A
�@��l�i�Ζ��j����˃n�A���ƃm����}��S�ڎ��@�i���~�Z���j�m�O�}�\�����m���j�A���B�甪�S���\��N���A�i�������T�N�j�|�{���m�w�}�j�˃e�A���e�����m�i���B�L�ۏ\�ځA�[�T���ڃj���i�V�e�j�A�j�e�A���̓j���N�؞y���������B�c�c
�ƋL���A�����T�N�ɉ|�{���g���Ζ������@�������ƁA�܂��A�ꏊ��K�͂ɂ��Ă����炩�ɂ��Ă���B�����Ă���ɁA��T�i�Ζ��J�w�j�̍��̂Ȃ��Ō��_�Ƃ��āA
�@�V���T�_�X���j�A�Y���j�䃒�w�c�����i�V�B��j�A�r�_�[�䃒���c���i�V�g�X�B�R���g���A�u���m�I�ʃj���q��䃒���c�n�e�Ճi���B�ȃe�A���m�L���������x�V�B�Y���j���e�n�A�I�ʃ����n�j�[�N���������ʃ������m�]�A���i�V�B�Ń����m�x�������n�A�����N����ˁA�y�r�H�T�m������j�ߐڃX�x�V�B
�Əq�ׁA�����č̖�����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��邵�A���������ɂ��Ė{�i�I�ɍ̖������`�Ղ��L�^���c����Ă��Ȃ��B
���S
�@���̃��C�}���́A�����Ɍf�����u�n�����ʏ����v�ŁA����ɂ��̒n���̍��i���j�S�ɂ��ĐG��A
�@�E���v���������A⍃j�������y�r���i���������ԃm�C�l�j�݃����S�m�d�w�����Z�X���j�A���T�}�\�\�p���i�l���j�A���`�ꖜ����Z�S���i���甪�S�ԁj�j�V�e�A�L�T������i�\�ԁj�A���T���c�ܐ��A���B�s�e�ܖ�����Z�S�Z�\���������i�����O�S�O�\�O�ԗ����j�^���B���z�n�e�����j�r�_�x�����B�R���g���A��ʃj��m���g���[���B��V���ϕS���������m�z���\�����܃��g�X���o�A���z�}�\�\�ԃi���x�N�A�����S����������ԃ��ܗL�X�x�V�B�A�A���z���j�n�A��m�u�`�^�j�����v���܃��g���G�A���Ó��m�œS�F�j���e�V�������Z�V�j�r�_���V�B�̃j�A�Õ���m���S���������a�V�e��������J�i���V���^���B
�Ƒ��ʂɂ��āA�������ǎ��ł���ƕ��Ă���B
�@���̂悤�ɁA���n���͂�����Θp��т́A�킪���L���̍��S�n�тƂ��Ēm���A�ڍׂɂ��Ă͕s���ł��邪�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�Ɉ��p�ܘY���l���ō��S�̎掖�Ƃ��o�肷��ɂ�����A���L�n����̍̌@�ɓ��ӂ��鑺��c���̗�ɂ�������悤�ɁA��������ɂ������ō��S�̍̌@���s��ꂽ���̂Ǝv����B
�œS�F
�@���Ó��i���A�l���j�̑œS�F�̂��Ƃɂ��ẮA�����T�N�i�P�W�V�Q�j�J��g�����́u�A���e�Z�������S�m�V�����ʁv�i�u�V�k�C���j�v�掵���j����j�ɏڂ������A���̊T�v��`������̂ɁA�O�f���C�}���̕�����̂Ŏ��Ɍf����B
�@�C�݃��������p���R�z�������A��p�����i�ꗢ�j�i�����Ó��m���œS�F�n�A�}�\�\�N�O�n���e���z�V�A�N�ԍ�ƃV�e�ꃖ�N������V�A�X�j�l�A�ܔN�ԍ�ƃV�A���j�O�N�O�j�p�Ѓg�i�����B�������j��m�u�t���[�}���[�A�z���W�v�F�m���A���e�A���Ԏd�|�m���䃒���w�^���B���ċG���A�O�z�F�j��ƃX���l�v�n�A���X���l����j�j���`�e���X�i��j�j�l�l�d�R�j�B���V�e�A�O���ԃj�ܐ甪�S���i���S�іځj�A���`����j���S�O�\�O���i�����N���X�@�����j�A���U���x�V�j�����^���V�R�����P���B����X�ؒY�m�ʃn�A���o�X���S�m�ڕ�������{���i���g�]�t�B�����A�����n�����j�t��K�m�l���m��ܖсi�Z�іڃj�e�\��K���j�i���g���A�O���n�V���������V�N�����i���V�g�B
�@���̕����炨�悻�P�O�N�O�Ƃ���A���v�R�N�i�P�W�U�R�j��O�シ�鎞���Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̕���͏ڍׂ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�Ȃ��A���̌o�c�҂͍����@�^�Ƃ����A�痼����ς�ł��̎��Ƃ��s�����Ɠ`�����Ă��邪�A���ۂɎ��Ƃ��s�����̂͂��悻�U�A�V�N�ɂ������A�K�������ǍD�Ȑ��ʂ����߂��Ƃ͂����Ȃ��悤�ł���B
�@�C�݂ɂ���L�x�ȍ��S�������Ƃ��A���Ó���㗬����a���@���Đ��������A���Ԃ��đ傫�ȁu�t�C�S�v�ŕ��𑗂�A�����đ��ʂ̖ؒY��R���Ƃ��āu�������v���������̂ƌ����邱�̐��S���Ղ́A���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�t�A���_�������������ψ��ɂ���āA�S�R�u�˂̓�����[�ӂ��Ƃɋ߂��X�Βn�i���A�l���S�R�X�Ԓn�j�ł��������Ƃ��m�F����Ă���B
�@��Q�߁@���_�z�R
�V�y���z�R
�@���a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�T���ɕR�������_�z�R�̗��j�͌Â��A�����̕ϑJ�͂��������A�����ɏq�ׂ��u�V�y���z�R�v�ɂ��̒[���Ă����̂ł���B
�@�V�y�����R�́A�����N�Ԃɂ����Ă������̐l�X�ɂ���Ď��@���J��Ԃ��ꂽ���A���̋Ɛт͌���ׂ����̂��Ȃ������B�������A�����̒�����Ǝv����V�y���z�R�̂��Ƃ��u���̑n�Ɓv�i�s�z�ȎO���j�ɋ�R�Ƃ��Ĕɉh���Ă����l�q��������Ă���̂Ŏ��Ɍf����B
�@�����ו��������n�������������������Ēʂ����B���̔n�̏�ւ͊��l���l�̏���čs�����Ƃ��������B�����đ����̍H�v���R�֏������A�R���牺�����肵���B���ɓX���o���Ă��҂́A�R�֎x�X��������B���X�̂Ȃ����̂�雞�i�{�J�j�◑��A���A����R�֔���ɍs�����B�R����͋₪�o���B���_���͈ꎞ��R�ׂ̈߂ɔɏ������āA��̖k�C���̖�ɂ������Ă���Y���҂̌Q�͖����Ă����_���֏W���ė����B���ɂ͑��ɓX���o���҂�����A���S�����~�߂āA��R�֕���ɍs���҂��������B�����ĉׂ������n�͖����A���̕��ɉs�����̂₤���ނ����R�̘[�ցA���ʂ�A����ʂ�A���n��A�R���z���A�J���z���āA���낼��ƒʂ����B
�@����Ȏ�����A��N�����Ă���A��ɋ�R���j��Ɖ]�Ӊ\���g�܂��ė����B�����ĎR�ł͋Z�t����Ȃ��Ȃ����B�����ōH�v�����l���ו���Z�߂ĎR���������B��R�͈ꎞ���~����Ɖ]�ӂ��Ƃł������B�������̌�\�N�o���Ă��A��\�N�o���Ă��A�R�͖ق��ĕ����������Ȃ���A���ĂюR�֍H�v���Z�t���o��Ȃ������B���̎��R���������Z�t�͎����̌����݂ɑ��Ⴕ�āA�@���Ă��@���Ă���̂悢�z���ɓ���Ȃ������̂ŁA�ނ͕��������ɂ��ĎR���瓦���A�����̂��Ƃ��c�c�㗪�c�c
�@���̂悤�ȏ킵�Ă��邪�A������I�ł�����Ǝv���A�^�U�̂قǂ��m���߂�j�����Ȃ��͎̂c�O�Ȃ��Ƃł���B
���z�Ə�
�@���炭�x�~��Ԃ̑����Ă������̍z�R�ō̍z���Ƃ��n�߂��̂́u������Б��z�Ə��v�ł������B���z�Ə���������u�V�y���z�R�v�Ə̂��A�}���K������Ƃ����̌@�����߂��̂́A�吳�V�N�i�P�X�P�W�j�̂��Ƃł���B�����Ă��̔N�́A�O�ꖜ�l�Z�Z�Z�т��Y�o���A���肩��̑�ꎟ���E���ɂ����v�̑���ɂƂ��Ȃ��ďd�v�z�R�Ɏw�肳��A��������������������̂Ǝv��ꂽ�̂ł��邪�A�W�N�ɑ�킪�I������ƈ�C�Ɏ��v���������A���N�͂킸���ɎO���т��Y�o���������ŁA�������x�R�̂�ނȂ��Ɏ������B
�@�������Ă��炭�x�R�𑱂��Ă������A���̌�o�ς����Ă����̂ŁA���z�Ə��͉���z�R�Ɖ��̂��A�吳�P�T�N�i�P�X�Q�U�j�X������̌@���ĊJ���A�����a�Q�N�ɂ̓}���K���O�㖜�т��̌@�����B�����̏́u�k�C���z�Ǝ��v�i���a�R�N�X�����s�j�ɏڂ���������Ă���̂Ŏ��ɏЉ��B
�@����z�R
�@�ʒu�@�_�U���R�z�S���_��������
�@�z��@�̌@�o�^����@�ʐώO�Z�܁A����ܒ�
�@�z��@���E��E���E���E�����E����
�@�z�Y�z�@�������z�O��Z�A���܋�с@���z�l��A�㎵���~
�@���v�@��ܔN�O�ɗV�y���z�R�Ə̂��ꎞ�ҍs�������Ƃ���A����i�炭�x�~���邪�\�ܔN�㌎���Ăђ���̏����𐮂ցA�\��������苌�̌@�̒��z���čz������̌@���p�����B
�@�n���@���_�w�̐��k���Z���̒n�ɍ݂�A���_������ܗ��̊Ԃ͎Ԕn��ʂ��A������R�����̉^���͔n�w�ɂ��B���ߎO���̊Ԃ͖w�ǐl�ƂȂ��͂��Ɉꌬ�̉��쉷��h�Ɖw��������݂̂Ȃ�B
�@�n���y�ѓS���@���߈�тɈ��R�┭�B���A�z���͔V����ق����㟏[塡�z���ɂ��čz���̎�v�Ȃ���̓�{�ɂ��ĉ���������ڔT�����ڂɂ��āA�������S���H�����z�ɂ��đ����֍ۂɋ߂������z�̎ȏ�ɉ�݂��������B�R��ǂ������z�Ƃ��Ă͎��ɔ��w�ɂđ��݂�����ȂāA�@�B�I�z�ɂ�炴��Ύ�I�݂̂ɂĂ͖����z�ƕ�������\�͂�����ȂĈ����z�͔p�ƂȂ�����B���m�z���̉����������Z�Z�ړ��O�z�̕i�ʖ����Ƃ��ĎO�܁����O�̂��̂Ȃ�B
�@�i�ʋy�їp�r�@�����{�z�R�Y�o�z�͎�Ƃ��ĕH�����Ȃ邪�V�ɏčz���ɂďĂ��Ď_�������ߍd�����z�Ƃ�����̂ɂ��āA�čd�����i�Ƃ��Đ��|��Г��ɔ��z���B�e�z�i�ʎO�܁����O�A���i�ܓȂ�B
�@�B���@�ҍs����B���\�O���A�\�l���B�Ȃ�B
�@�̍z�@�@����K�i�@�ɂč̍z���B
�@�r���@�@���R�r��
�@�ʋC�@�@���R�ʕ�
�@�^���@�@�B�����艟�ɂĐ��B�ꖘ�^�ԁB
�@�I�z�y�ѐ��B�@�@�čz���͓��a�l�ڍ������ڂ̒G�F���ɂ��čz��d�Ƌ��ɑ������ꒋ�鑀�Ƃ��ĒY�_���������������ɕω������߁A�������ܗL�i�ʂ����ނ���̂Ƃ��B�O�܁��ʂ̂��̂��l�܁��ȏ�ɍ��ނ���̂Ȃ�B
�@���Q���@���L���ׂ����ƂȂ��B
�@�B���Ɩ��@�A�Z�`���������g�p���B
�@�z�v�@�����@�j�l��@�v�l��
�@�������ĉ���z�R�́A���z�Ə��ɂ���č̌@���Ƃ�������ꂽ���A���a�U�N�i�P�X�R�P�j�U���ɂ͔��_�z�Ɗ�����Ђ̌o�c�Ɉڂ����B
���_�z�R
�@���_�z�Ɗ�����Ђ̌o�c�Ɉڂ�������z�R�́A�u����z�R�v�Ɖ��̂������}���K���z�͎���̋r���𗁂тĎ��v�����債�A�{�݂������g�[�����ɂ�ĎY�o�ʂ�����ɑ��������B���a�W�N�ɂ͋����}���K���P�Q�Q�W�g���i�Q���P�X�U�U�~�j���Y���A�X�N�ɂ͏]�ƈ����B���v�S�Q���A�B�O�v�j�P�T���A���Q�P���A�E���T���̌v�W�R���𐔂���悤�ɂȂ�A�����̎q������炷�邽�߂̓��ʋ����ꂪ�ݒu���ꂽ�B
�@�܂��A�z�̉^�����@���A�n�̔w�𗊂�Ƃ��Ă����R������w���̊ԂɁA�ȈՋO���i�P���j��~�݂��A�P�g���ύz�ԂQ���Ȃ����R����n�ň�������A�w������s�X�n�܂ł͉_�Γ��H�̉��C�ɂ���ăg���b�N�𗘗p���邱�ƂƂ��Ĕ\������}�����B
���O�z�Ɗ�����Ђɂ��g�[
�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�U���A���_�z�Ɗ�����Ђ͒��O�z�Ɗ�����Ђƍ������A���̂����O�z�Ɗ�����Д��_�z�Ə��Ɖ��߂��A�{�i�I�ȍ̌@�ɏ��o�����̂ł������B�������A���P�Q�N�ɓ����푈���ڂ����������Ƃɂ���Ď��v�͑��債�A�}���K���͏d�v�����Ƃ��đ��Y���v�����ꂽ���߁A�N�X���Ƃ��g�������
�ʕt�n�ɂ��}���K���z�̉^���i�ʐ^�P�j

�ȈՋO���ɂ��z�Ή^���Ƒ�؍B�i�ʐ^�Q�j

����ƂȂ�A����ɂƂ��Ȃ��ď]�ƈ����}���ȑ������݂��̂ł���B����ɁA�����m�푈�ւ̓˓��ɂ��ΘJ������؍��l�J���҂̋����A�J�Ȃǂɂ���đ������R���A���Y�ɔ��Ԃ�������ꂽ�B���ɗA���͂̑�����}�邽�߁A�R�����甪�_�s�X�n�܂ł̊ԂɁu�ʑ����P�����[�z�������v�̌��݂��v�悵���B�����ĂP�P�N�ɑ����H���Ƃ��ċ����w�Z�t�߂Ɍ��������A�㉔��ɒ��z����ݒu�A���̊Ԗ�U�L�����[�g���̍��������݂��A����i�U���̂P�g���j�ɂ������A�����s���A�㉔�삩��s�X�n�܂ł̓g���b�N�A���Ƃ����B����ɁA�P�V�N�ɎR���̑I�z�ꂩ�猴�����܂ł̑����H���A���P�W�N�P�O���ɂ͏㉔�삩�甪�_�w�܂ł̑�O���H�����������������A���܂��܁A���_�R�p��s��̌��݂ɂ���Ĉꕔ�H���̕ύX���s���A�P�P�������P�V�L�����[�g���ɋy�ԍ������������A�z�⎑�ނ̗A���Ɉ��З͂������̂ł������B�܂��A�z���ݎԐς݂��邽�߁A�P�W�N�T�����_�w�����ɍ��������������˂ĂS�O�O�g�������e����Q�K���Ď����z�ɂP�S�S�i��S�V�T�E�Q�������[�g���j�����݂��A��p�S�������P�R�O���[�g����~�݂��ė��ւ�}�����B
���R�����������ƎБ�̈ꕔ�i�ʐ^�P�j

���ĘF�i�ʐ^�Q�j

�@���̂悤�ɁA���ݔ������P�������A�̍z���@��I�z���@�̉��P���͂��ߐV�z���̒T�z�ɂ��͂𒍂��Ő��Y�ɔ����A�d�v�z�R�Ƃ��Đ����𑱂����̂ł������B�������A�Q�O�N�W���I��ƂƂ��Ƀ}���K���̎��v�͌������A�����Đ펞���̍̍z�Ɏ�͂��������Ԑ����琶�����ۈ����u�̕s���ɂ��댯�̑���A�؍��l�J���҂̖{���A�ҁA�s��ɂ�鐶�Y�ӗ~�̌��ނȂǂɂ���āA���̔N�̎Y�o�ʂ͂W���܂łɂU�X�O�O�g���Ɨ������̂ł���B�������A�Q�P�N�܂ł͍B���̕ۈ������ɏd�_�������č̍z�͑S���s���Ȃ��������߁A���ẲԌ`�z�R�͊Ԃ��Ȃ����������悤�ɂȂ����B
���̔��_�z�R
�@��Ђ͂���������������Z���Đ��Y�ݔ��𐮂��A�z���܂����a�Y�Ƃ̕������ނƂ��ď��X�Ɏ��v�����܂�A���̐��Y���ĊJ�����̂͏��a�Q�Q�N�̂��Ƃł������B�����Ă���ɍ̌@�B���̊J���i�߂čz����g������ƂƂ��ɁA�����ɔ����ĒT�z���p�������B
�@�Ƃ�킯�͂���ꂽ�̂́A���z��̕s�����Ȃ����邽�߁A�z�̕i�ʂ����߁A�P���W�O�g���������ł��镂�V�I�z������݂��邱�Ƃł���A�Q�V�N�P�O���ɒ��H���A���Q�W�N�P�P���ɂ�������������B���̕��V�I�z��̌��݂ɂ���āA���E�����E�}���K���Ȃǂ̊e�z�����A���ꂼ��i�ʂ̍������̂Ƃ��邱�Ƃ��ł��A�^���≿�i�̖ʂł��L���ɂ��邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�@�������A���a�Q�X�N�X���Q�U���S�����P�����P�T���䕗�ɂ��A�A���@�ւł�������x���P�U�Q��̂����V�W��|�A���ɂ��̋@�\���~���Ă��܂����B���̂��߁A�P�O���ȍ~�͑S�ʓI�Ƀg���b�N�A���ɐ�ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B�܂��A���̑䕗�ɂ��z�R�̔�Q�͑傫���A�Z��̏Ď��P�O���S�S���сA�|��V���S�U���сA����S���P�W���т��͂��ߊe�{�݂���Q���A���d���̒f���ɂ���d�̂��ߍB���g���|���v����~���A���čB�͂P�S�O���[�g���܂ŐZ���������ߍ̍z�s�\�ƂȂ�A���̔�Q�z�͍z�R�{�݂����łQ�P�U�P���~�ɋy�B
���z���Y�ʒ�
�i���E�����E�}���K���j
| �N�x | �Y�@�o�@�� |
| ���a�P�P�N | �� �Q�C�Q�P�V |
| �P�Q | �T�C�S�X�P |
| �P�R | �U�C�X�W�U |
| �P�S | �W�C�U�T�X |
| �P�T | �V�C�P�X�P |
| �P�U | �X�C�R�X�O |
| �P�V | �P�P�C�X�X�U |
| �P�W | �P�P�C�V�O�V |
| �P�X | �P�W�C�W�X�T |
| �Q�O | �U�C�X�O�O |
| �Q�P | �| |
�@�Ȃ��A�z�R�ɒʂ��钬���㉔�쉷����́A���R�O�N�V���̐��Q�ɂ���āA���̗����A���H�̌���ȂǍĂё�ЊQ���A��ʓr��Ƃ�����ԂɂȂ����̂ł��邪�A���q���{�ݕ����̏o���ċً}�����H�����Ȃ��ꂽ�̂ł������B
�@�������čz�Ə��́A���ĂȂ���ЊQ�����Ŏ��ɂ�������炸�A���̕����ɑS�͂�s�������̂ŁA���قǎY�o�ʂ�������Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�{�݂��[�����]�ƈ�������ɑ������āA���a�R�O�N��ɓ���������ɂ̓}���K���z�R�Ƃ��đS���P�O���̂Ȃ��ɓ���قǂł������B���̂���ɂ͏]�ƈ����R�O�O�l���A�f�Ï��E�����z�����E����E�N���u�Ȃǂ��ݒu����A�܂��A���I�@�ւƂ��ẮA���E���w�Z��ȈX�ǂ��ݒu����Ă��������A�s�X�n�Ƃ̊Ԃɒ���o�X���^�s����Ȃǂ̏[���Ԃ�ł������B
�@���P�O�N�Ԃɂ����鐶�Y���͏�\�̂Ƃ���ł���B
�@�B�I�z��ƃg���b�N�ɂ��z�Ή^���i�ʐ^�P�j

���z�Y�o�ʒ�
�i���E�����E�}���K���j
| �N�@�@�� | �Y�@�o�@�� |
| ���a�Q�Q�N | �� �P�C�Q�W�P |
| �Q�R | �P�C�X�Q�V |
| �Q�S | �T�C�O�V�T |
| �Q�T | �S�C�S�T�Q |
| �Q�U | �U�C�X�Q�P |
| �Q�V | �V�C�O�X�R |
| �Q�W | �W�C�S�T�R |
| �Q�X | �W�C�V�S�U |
| �R�O | �W�C�V�V�S |
| �R�P | �P�O�C�P�S�X |
���ɕR
�@�������Ĉ��肵���o�c�𑱂��Ă������_�z�R���A���a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�Ƀ}���K���z���͂��߂Ƃ���z�̗A�������R�����ꂽ���ƁA�܂��A���̌�ɂƂ�ꂽ���Z�����ߍ�ɂ���ēO��I�ȍ������𔗂�ꂽ���ƂȂǂ̊O�I�ȗv���ƁA�z�����̂��̂ɂ����E�������͂��߁A�V�z�J���̂��߂̎������B���܂܂ɂȂ炸�A�������ň��������d�Ȃ����̂ł������B
�@���������z�ƊE�̏�w�i�ɁA���O�z�Ɩ{�Ђɂ����Ă���Ƃ̍�������ĕ҂𔗂��A�R�V�N�ɑ�K�͂ȏk���ɂ��z�u�]�����s�����̂��͂��߁A���̌�̌o�c�������ɂ���āu���_�z�Ɗ�����Ёv�i�В��E���ː����j��ݗ����A�o�c�̌p����}�����B�������A���Y�ʂ̌����ɂ��s�̎Z�A�T�z�����̌͊��A����o�X�̉^�s���~�ȂǁA�܂��܂����������d�Ȃ��Čp������ƂȂ����̂ŁA���ɏ��a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�S������������č̍z�𒆎~���邱�Ƃ����肵���B�����ď]�ƈ��͓������E�É����E�w�R�Ǔ���m�����̒��O�z�ƌn�z�R�ɂ��ꂼ��z�u�]�����s���ȂNjƖ������A���_�z�R�̗��j�ɏI�~�����ł��ꂽ�̂ł������B
���z�Y�o�ʒ��i���E�����E�}���K���j
| �N�@�@�� | �Y�@�o�@�� |
| ���a�R�V�N | �� �V�C�S�S�R |
| �R�W | �W�C�V�V�Q |
| �R�X | �P�O�C�U�R�U |
| �S�O | �P�Q�C�Q�W�V |
| �S�P | �V�C�U�W�T |
| �S�Q | �V�C�Q�V�O |
| �S�R | �T�C�V�W�Q |
| �S�S | �Q�O�O |
�@�Ȃ��A���a�R�V�N�ȍ~�R�Ɏ���܂ł̐��Y�ʂ̐��ڂ͉E�\�̂Ƃ���ł���B
�@��R�߁@���S
���S�̍̎�
�@���S���������܂߂ĕ��Θp��тɑ��ʂɖ������Ă��邱�Ƃ́A�����ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�{�i�I�ɍ̌@���ꂾ�����̂͏��a�P�T�N����̂��Ƃł���B����́A�����푈�̂ڂ����ɂ��S�̎��v�x�����܂����̂ɑ��āA�O������̓S�z�̗A�����������𑝂��A���S�Ɉˑ�������Ȃ��Ȃ�������ł������B
�@�܂��A�������{�|�ǂ̎Ј��ł������V���Y�Ɨ����@�^�́A�V�y���̕l�ƎR��̕l�ō��S�̌@�̎��Ƃ��v�悵���Ƃ��悤�Ƃ������A���̎��Ƃɑ��ċ����́A�C�l�̍r�p��J�����č̌@���̑ԓx���Ƃ����B�������A���̔��_���Ƒg�����đ�@�E�́A�n�������̊J�������lj��ٗv�Ȏ��Ƃł���Ƃ��Ĕ������̐����ɓw�߁A�悤�₭����ɓ��ӂ�^���Ď��ƒ�����\�ɂ������̂ł������B����ɂ���ēV���́A���S���_�z�R�V��z�Ə���ݗ����āA�V�y���ƎR��̊C�l�ō̍z���J�n�������A�����̍̌@���@�͌��z���܂ʼn^�����A��Ő����I�z����Ƃ������n�I�Ȃ��̂ł������B���̌㓯�Ђ̖L�쓿���́A�C���𗘗p���Ă̔�i�Ƃ��j�����I�z�A������u�L�����v�Ƃ������@���l�Ă��A�̍z�\�������߂ďo�z�ʂ��������B�Ȃ��A�����̍��S�͑啔�������{�|�lj��k�H��ɑ����Ă����B
�@���a�Q�O�N�W�������m�푈�̏I���ƂƂ��ɍ��S���Ƃ͋x�~�̏�ԂƂȂ����̂ł��邪�A���̕������ނƂ��ēS�ނ̎��v�����܂�ɂ�A�Ăыr���𗁂т�悤�ɂȂ����B
�@���S���_�z�R�V��z�Ə��ł͂Q�S�N�U���ɍ̌@���ĊJ�i�Q�U�N�V��z�Ə��Ɩ��̕ύX�j�����Ƃ𑱂����B���܂��܂Q�T�N�̒��N�����ڂ����̉e�����A���S�̎�Ƃ��Ő������}���A�c�ƎҐ������R�ɑ����������A���肩�版���Ƃ̕s�U�ɂ����������ɂƂ��āA���������铭���ꏊ�ɂȂ����͔̂���Ȍ��ۂł��������B
�@�������č��S�̍̌@�͉��݈�тɋy�сA�Ǝ҂����S�z�ƁE�k���{���S�E�������|�E�˖{���ƂȂǁA�P�O���Ђɂ��B�����B�I�z���@�B������A���������ݎ��ΑI�z�@���玼�C�����ΑI�z�@�ւƐi�ݍ̍z�\�͂��傫�����サ���B�����Ă����̍��S�́A�������S��x�m�S�����Ȃǂɑ����A����������߂��̂ł������B
���S�I�z�@�i�ʐ^�P�j

�@�������A�₪�Č��z�̌͊������邱�ƂȂ���A�C�O����̓S�z�ΗA���̉e�����ĉ��~�������ǂ�A���a�S�O�N��㔼�ɂ͂킸���ɂQ�A�R�̋Ǝ҂����Ƃ𑱂���Ƃ����ł������B���������Ȃ��ŁA�T�P�N�P���ɖk�C���H�Ɗ�����Ђ�����Œ��Ƃ��A���S�z�����@�ɂ��̌@���s���A�V���S�����Ƀg���b�N�A�����s�������A����܂����T�Q�N�U���������Ĕp�~���A���݂ł͍��S�̎掖�Ƃ͑S���s���Ă��Ȃ��B
�@��S�߁@���̑��̍z�R
�����z�R
�@�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�R���X���t�̔��ِV���́A�����z�R�i���E��E���E�����E�A�����j�E���j�̂��Ƃɂ��āA
�@�n���������S�������z�ƌ��ғn�ӑ����Y�A�吳�T�N�T�����Ƃɒ��肵�A�z�v�\�������g�p���ĘI�V�@���Ȃ��A���̂������̍z�ɓw�߂��錋�ʁA�ǍD�Ȃ�I�������čB�����@�������Ė�S�l�ɒB��������\���Ɏ���z��������������ȂĂ��ɉҍs�𒆎~����Ɏ����B�i�ȉ����j
�ƕĂ��邪�A���̂ق��ڂ����L�^���Ȃ��̂ŁA�c�O�Ȃ��疾�炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
����ҋ��R
�@���a�T�N�i�P�X�R�O�j�ɉ���҂̍��g�@�����A����t�߂̑�i�ʏ̖{����j�ōz��������͂������ʁA�ܗL�ʂP�����̂P�Ȃ����P�O�O�O���̂P�̋��z�Ɣ��������B���̂��߁A�W�N�T���ɑ���{�z�Ɗ�����Ђ����@���ĉ���ҋ��R�Ə̂��A�B�v�P�R�����g�p���č̍z���s���A�z�͏H�c�s�̏���B���ɑ����Ă������A�z���������ł��������߁A�T�N�Ԃ̍̍z�ʂ͂킸���ɂS�E�W�g���ɂ����Ȃ������Ƃ����B���a�P�Q�N�T���ɐX��������̓��Ћ��R�̍̍z�J�n�ƂƂ��ɁA�z�v���]�o���Ă��̂܂ܔp�B�ɂȂ��Ă��܂����B
�ΎR
�@���̓��ɂ������㓡�_��̗��R�͊�ΎR�ŁA�����R�V�N�i�P�X�O�S�j�V���Ɍ㓡�����Y�ɔ���n�����O�͍��L�n�ł��������A���̓�������S���ɂ����v������A�����̑��؍����Y���������ĐH�����č̐��A���z�����Y�����o�ɓ������Ă����Ƃ�����B
�@���a�P�U�N�̑����m�푈�ڂ����ɂ���āA�����A���͑����̂��ߓS���̌X�Ȃǂ����ǂ���H�����e���Ŏ��{����A����ɂ��̐̎��v�������������߁A���S�{�ݕ��ł͐ΎR�̈ꕔ���グ�A�����w�܂ł̊ԂɈ�������~�݂��Ĕ��o�����̂ł������B�������A���Ԃ��Ȃ����S�ɂ��̐͒�~����āA�㓡�����Y�̌�p�҂ł���㓡���Y�ɕ����������A�~�݂������������P�����ꂽ���A���݂͖k�M�ӐH�Ɗ�����Ђ��̐��s���Ă���B
�@��T�߁@���̑��̒n������
�n�M�J��
�@�l�ނ��������Ă���n���ɂ́A���܂��ɉ𖾂���Ȃ������̂Ȃ�����߂��Ă���A�������𖾂��邽�߂ɁA�n���Ɋւ��邠���镪��ɂ����Đ��I�Ȍ������i�߂��Ă��邱�Ƃ͎��m�̎����ł���A���X�����܂��Ȃ��Ƃ���ł���B
�@���̈ꕪ��ł���n�������w��A�n�\����n���[���������ɂ�ĉ��x�������Ȃ邱�Ƃ́A���ۂ̑���Ƃ����̂ق��̕��@�ɂ���ė�����Ă���A���ɒn���̓����͐���x�̍����ɂ���Ɛ��肳��Ă���B���ۂɉΎR�̕��̂Ƃ��ɗ��o����n��̉��x�́A�ێ��P�O�O�O�x�ȏ�ɒB���A���̂��Ƃ��؋����ĂĂ���B
�@���������n���[���̔M�G�l���M�[�͌��Ƃ��ė��p���A�n�M���d�Ȃǂ��낢��Ȏ��Ƃ��J������Ă���A�܂��A�����������i�߂��Ă���B
�@���a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�ɂ͐Ζ��J�����c���o�����ĐΖ������J��������Ёi�{�ЁE�����j��ݗ����A�Ζ��E�K�X�����̒T���ȂNJe��̊J�����Ƃ��s�����ƂƂȂ����B�܂��A����d�͉�Ђ̈ϑ����đS���̒n�M�����ɂ����o���A�����̒n�M�L�]�n�_�ɂ����Ē������J�n����A�����S��ɂ��Ă��T�R�N�ƂT�S�N�ɂ��̗\���������s��ꂽ�B�T�R�N�ɂ͊�b�����Ƃ��Ĕ��_�S��̏d�͒����E�n�\�����E�n���������E�ʐ^�n������єM�ԊO���f�������Ȃǂ��s���A�T�S�N�ɂ͉���n��̏d�͒����A�R��E����n��̒n�k�T���i�n���w�����̈��j�E�ʐ^�n������єM�ԊO���f�����������{���ꂽ�B���̌��ʁA����n��Ɨ����n��̏�̓��E����n�悪�N���[�Y�A�b�v����A�T�T�A�T�U�N�̂Q�N�ԂŒn�\����R�O�`�T�O���[�g�����̒n���𑪒肷��d���T�����A����łR�O�_�A�����n��łV�O�_�s���A���ꂼ��f�[�^���ςݏd�˂�ꂽ�B
�@�������ĂT�V�N�ɂ͗L�͒n�_�Ƃ��āA��̓��Ɖ���n��̋��z�R�t�߂ŁA����ɏڂ����n���𑪒肷�邽�߂̃{�[�����O���A��̓��Œn���Q�O�O���[�g���T�E�A����łT�O�O���[�g���Q�E�����{���ꂽ�B
�@���̌��_�ɂ��ẮA���݂̂Ƃ��땪�͌��ʑ҂��̏�Ԃł��邪�A�T�W�N�ȍ~�����������������i�߂��A���̒n�������J���ɐ[���S�����Ă���Ƃ���ł���B
��V�́@�ό�
�@��P�߁@�ό�
�ό�����
�@�����ɂ�����ό������́A��Ƃ��ď�̓��E����E����n��̉���n�сA�Y�g�x�E���c�琬�q��E����̊��Ȃǂ̎��R�I�Ȏ����̂ق��A�N�ԍP��s���Ƃ��Ē蒅���Ă����ό�����Ȃǂ̎�Âɂ����܂�E�q��܂�E���[���b�v�쉺��E�~�܂�Ȃǂ�����B
�@����������n�т������ẮA������������̃��N���G�[�V������e���̏�Ƃ��ė��p����Ă�����x�ŁA���O����̊ό��q���]�葽���͂Ȃ��B�����A����n�Ƃ��Ă̏�̓��n��ɂ́A���ϘA�w��̗��ق������Ē����O����K���ό��q�������A�����ɂ����Ă������Ȋό��n�ł���B
�@�܂��A���a�S�X�N�i�P�X�V�S�j�ɂ͒��c���쉷��i���ڂ����j���J�����ꂽ���Ƃɂ��A�K���q���N�X�������Ă���B����ɞw�R�Ǔ��F�Β��Ƃ̖��ڂȘA�g�̂��ƂɁA�b�R���Y���C�������_�F�ΐ��i���A�����Q�V�V�����j��ʂ��ē��{�C�Ǖ��\�[�������C���ɘA�������A����E���s�E���c���Ȃǂ̉���ƁA�r���R���̌i�ς��Љ�悤�Ƃ���_�X�J�C���C���i���a�T�T�N�P�O���j��ݒ肵�A�������̈��ό����[�g�̑ł��o���A�L���ɓw�߂Ă���B
�@�Ȃ��A�T�P�N�i�P�X�V�U�j�ɂ͉���n�悪�і쒡�̃��N���G�[�V�����̐X�Ƃ��Ďw��������Ƃ���A���n��̊ό��J�����ƂƂ��āA���E���Ԃ���ьٗp���i���ƒc�Ȃǂɂ��J�����i�ɏ��������҂���Ă���B
�ό�����̐ݗ�
�@���a�S�O�N�i�P�X�U�T�j�V���A���͔��_���H��ƂƂ��Ɋό�����ݗ��ɂ��ď�����i�߂Ă������A�����Q�V�����H��ɂ����āA�������فE�^�A�ƎҁE�H��E�Y�ƒc�́E���X�E�y�،��z�ƎҁE�W�҂Ȃǂ�ԗ������u���_�ό�����v�̐ݗ�������֍Â��A��ɏ���юl�Y��I�C�����B
�@�������Ĕ��������ό�����́A�ό��q�̗U�v�Љ����Ɏ��グ�A���̕���Ƃ��āA�ԉΑ���X�|�[�c���Ȃǂ̊J�ÁA�܂��A�ό��p���t��G�͂������쐬���ē������`���悤�Ƃ�����̂ŁA���ԖڂƂ��ē��H�����̕ی�J���E�ό����̂��߂̏����E�������Ղ̕\���E�ό��n�̊J���Ȃǂ��v��A����ɁA�ό��v�z�̌[���E�����̔����^���E�ό��q�̈��S�m�ہE���q�@�ւ̃T�[�r�X����̂��߂̌�����Ȃǂ��s�����ƂƂ����B
�@���̊ό�����́A�����ǂ_���H����ɒu���A�N�ԍP��s���Ƃ��Ėq��܂�E�ԉΑ��E���[���b�v�쉺��Ȃǂ����{���Ă���A����͍�������ł���B
�b�R���Y���C��
�@�����ɂ�����L��ό����[�g�Ƃ��āu�b�R���Y���C���v������B
�@���̊ό����[�g�́A�Ǖ��\�[�������C���i���َs�E���O�C�݂��o�R���ē��{�C�����ɏ��M�Ɏ��鉄���S�W�X�L�����[�g���j�Ɏ����œ���̊ό��n���Љ�悤�Ƃ�����̂ŁA���فE�ˈ�E�K�ݓ��E�̖@�E�슝���E�����E�����E�X�E���_�E�������̂P�O�s�����ɂ܂����鑍�����P�W�P�E�T�L�����[�g���ɂ킽����̂ł���B���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�T���ɊW�҂����_���Љ���Z���^�[�ɏW�܂�A�b�R�������R�������o�ē��Y�p�����ɒʂ邱�Ƃ���A�u�b�R���Y���C���v�Ɩ��������̂ł������B
�@���̃��[�g�̌o�ߒn�ɂ́A���E�R�x�E�q��E����E��ނ�E�k�J�ȂǂƂ����悤�ɁA�ω��ɕx�i�����_�݂��A���H�����ƕ����Ď��R�����p�����ό��̐U����i�߂悤�Ƃ�����̂ł���B
�@�����ɂ́A�R�^������E����z�e�����F�A�s�X�n�ɓ����āA���_�����E����̊����o�Ē��������ɒʂ��Ă���B�܂��A�����𗬂�闎����E��c�ǐ�E�V�y����͌k���ނ�A�C�݂͈�ނ�̖����Ƃ��Ă��m���Ă���A�K���l�������B
�@��Q�߁@����
�Ǔ�����̗R��
�@�����Ǔ��̎R�ԕ��ɂ́A��̓��E���̓����͂��߂Ƃ��āA����E����Ȃǂɉ��_�݂��A�܂��A�C�ݕ��ɂ͕l���̂ق��R�z�����c���ւ����ĉ���n���_�݂��Ă���B
�@����́A�E�E���̑��̊ϓ_����A�l�X�ɕ��ނ���Ă���B�Ⴆ�A���̕����`�Ԃɂ���Ė����Ƒw���Ƃɕ��ނ���A�܂��A���w�����ƔM�̋N���ɂ���ĉΎR����Ɣ�ΎR����Ƃɕ��ނ����B�����ɋ������R�ԕ��̉���͉ΎR���ŁA�������ɑ����A�C�ݕ��̉���͔�ΎR���ŁA�w���ɑ�������̂Ƃ݂��Ă���B
�@�����̉���́A�Â����瓒����Ƃ��ė��p����Ă����̂ł��邪�A������A����ɂ���Ĕ������ꂽ���͂܂т炩�łȂ��B
�@�O���N�ԁi�P�W�S�S�`�P�W�S�V�j�Ɉɐ��̐l���Y���l�Y���A�ڈΒn��T�����đ����̋I�s����n�}���c�������A���̒��̒����u�ڈΓ����v�̈�߂ɁA�������̉���ɂ��Ď��̂悤�ȋL�q������B
�@�u�c�c���R�ɉ���L�Ĕ��ٕӂ�蓒���l�s���Ɩ�B���a�Ɍ��\�����ƕ�����B�]�����ē����l���������Ă�ɍs�����A��h���ċA��ʁB�����ĎR�[�����Ȃ���ǂ��r���҂������Ȃ�B�������Ƃ��ӂ��{�̉������ɂč��ɂĉ������ӂ�����B���������ɂ��ċ��炭�͋ʋC��萶������̂��Ƃ������B�c�c�B�v
�@�܂��A�����N�ԁi�P�W�T�S�`�P�W�T�X�j�̖����s��\�Y�̎��@�L�u�ڈΎ��n���l�^�v�ɂ��ƁA�����������̍��ɁA
�@�u�c�c�R���ւ͗����������앝���O�Ԗ�B�l���}�O���ɂ��Đ��ɉ���L�B��������Ƃ����B���ӂ���Q���k�։�薔���ɓ]���ĉ����蔼���ɂ��Ċ��鏊�c�c�c�B�v
�Ƃ���A�����͂��������̓��n��̉�����w�������̂Ǝv���邪�A���̏ꏊ�͔��R�Ƃ��Ȃ��B
�@�����S�N�i�P�W�T�V�j�W���Q�P���̓��L�ɏ��Y���l�Y�́A
�@�u�c�c�g�����x�c�i�E��ЌܘZ�ԁj�g�����͉���̎���B�����ɉ���L�̍����c�c�c�B�v
�ƋL���Ă���B
����ɁA�A�����J�̒n���w�҂ŁA�����U�N�i�P�W�V�R�j�ɊJ��g�̉��Ŗk�C���̒n�������ɂ����������C�}���̕��ɂ́A�����Ǔ��̉����ɂ��Ď��̂Ƃ�����Ă���B
���C�}���̕�
| �n�� | �� | �M�x�Z���`�K���[�h | �� | �� | �n�@�@�@�� | �L |
| ���u�N�X���v | �� | �l�\�ܓx�� | �����g�S�j�V�e���z���܃� | �A�������E���[�� | ��u�N�X���v���������m���֓�S�� | ��\�������j�A�� |
| �� | �� | |||||
| �O | �� | |||||
| ��u�N�X���v | �� | �O�\�x | �������f���z���㏸�X | �́@�@�@�� | �]�h�X�����������O�� | �� |
| �m�@�^�@�t | �� | �� | �������f | �́@�@�@�� | ���������]�h�m���֓� | �� |
| �E�@���@�v | �� | �O�\��x | �S�i���z�i�V�j | �A�������E�� | �����j�߃V | ���n�c�� ���n���i�� |
| �� | �O�\�ܓx | |||||
| �|�@�@�@�� | �� | �O�\�O�x | �S�i�Y�_�X���J�j���z���܃� | �A�������E�� | ���������]�h�m���ֈꗢ | �� |
| �� | ��\���x |
�@�����P�T�N�i�P�W�W�Q�j�U���Q�X���t���ِV���Ɂu���ٌ��Ǔ��e����i���v�̕�������A�������̉���ɂ��āA
�@�u�v���i�O���Ŋ����S�h��ӑ����w���Ă���j�{�[������Ɏ���B�{��͊����S������������ꗢ���{�[���Ə̂��闎����݂̊ɂ�����k���Ď��鈟�������i�A���J���j��Ȃ�B
�@���x��\�O�x�A�����Y�_���z���ʁA�Y�_���Ĉ��z�i�o�c�^�A�X�j���ʁA������������i�J���V�E���j����A�������Օ�i�\�V�E���j�c���ʁA���_�����������i�A�N�l�V�E�A�j���ʁA���_��������
�@�֔�ǁA�����C�����z�i���E�}�`�X�j�A�ᜁi���C���L�j�A�����ɓ��Ɍ�����B
�@���s���ɂ��Ď��N�X���i�C����ɒ����B�{��͊�����������������O���]�A�N�X���i�C�ɂ���A���ٓ�A���������S��Ȃ�A�_�A���c���Y���L�n�ɂ���A����������J�݂����A
�@���x�S�O�\�x�A�����Y�_���z���ʁA�_���S���ʁA�Y�_���Ĉ��z���ʁA�������������c���ʁA�������Օꏭ�ʁA����C�����z�A�n���ǁA����A�q�{���\�a�A�����畆�a�A�ᜓ��Ɍ�����B
�Ɠo�ڂ���Ă���B
�@�����̂ق��A�O�����N�i�P�W�S�S�j�ɗ����̍��c�Õ��q����������A�e���ł͂��邪������݂����̂����ɂ����g���c�����h�̎n�܂�Ƃ������Ă��邪�A���ꂪ�����Ƃ���A�O�q�������Y���l�Y�́u�ڈΓ����v�ɏЉ��Ă���̂��A���̉�����w���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��l������B�������A����ɂ��Ă��������ǂ����͕s���ł���A���݂͎��Ɨp�����ň�ʂɗ��p����Ă͂��Ȃ��B
�@������ɂ��Ă������쉈���ɂ́A�Â����牷�킫�o�Ă������Ƃ́A�����̕����ɂ���Ă��ؖ������B
�⍥������
�@�����P�S�N�i�P�X�Q�T�j�T���P�O���A�T�c�S���ё��̐�������Y���A�T�z���ɗ�����̒��B�ɉ��킫�o�Ă���̂������B���܂��܂��̓����吳�V�c�̋⍥���ł��������߁A���̉�����u�⍥���v�Ɩ��t�����Ƃ����Ă���B
�@���ٖ{�������w����P�P�L�����[�g���A������㗬�̎R���ɂ���A�̓N���[����������ŁA���x�͐ێ��U�O�`�X��x�A�ݒ��E�̑������Ɍ��\������B�����͗�����̐����Ƃ�������������ɕ�܂�A�t�߂ɂ́A�ԑ�E�����̑�E�J�ʋ��J�Ȃǂ̌k�����ǂ�����A�V�A�g�t�̎����ɂ̓n�C�L���O��ނ�ȂǂŐe���܂�Ă���B
�@���̉���͕�C�̖��i�P�W�U�W�`�U�X�j�̍ہA�|�{���g�������҂̓����ɗ��p�����Ƃ������Ă���B
�@���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�ɐ���g�l������h���J�Ƃ������A�S�N�̋�x�啬�ł䂤�o�ʂ��ɓx�Ɍ��������߁A���炽�߂ĕt�߂��{�[�����O�����̂��������A���̌㌚���̑����z��뉀�̐������s���A����ɂ����钘���ȉ���Ƃ��Ċό��̈ꗃ��S���Ă���B
�@���݂͐�������������p���Ōo�c�̂����A�q�̑��}�p�o�X���^�s����ȂǁA���ϘA�w��̗��قł���B
�⍥������i���a�����j�i�ʐ^�P�j

�⍥������i�ʐ^�Q�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̓�����
�@��̓��̊O�R�e�����A����t�߂̐��c�ɉ��킫�o�Ă���̂����A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�V���Ɍ@�킵�ē��ʂ��m�ۂ̂����A���N�X���ɉ��ق����ĂĊJ�Ƃ����̂��n�܂�ł���B
�@���̌�A���a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�P�Q���ɔ��_�J��������Ђ���������ė��N�Q������c�Ƃ��n�߁A�⍥���ƂƂ��Ɋό��̈ꗃ��S���Ă��鉷��ł���B
��̓�����i�ʐ^�R�j

���쉷��F�䑑
�@���ٖ{����c���w����P�T�L�����[�g���A��c�ǐ�㗬�̖�c�nj䗿�n�ɁA���c��l�Y��������Ƃ��Čo�c���Ă����g���c�����h�ƌĂ�鉷�������B�������ꂽ�̂͋ɂ߂ČÂ��A�A�C�k�̌ØV�L���^�i�̐l�j�̌��Ƃ���ɂ��A���̑c���̎���A���ɍ]���≳�����ʂ̃A�C�k���A�������������A�c�V�i�@�ۂŐD�����ߕ��j�̌������̂�ɏW�܂����Ƃ���ł���Ƃ����Ă���B�܂��A�F�䉷��Ƃ��̂���A����`�e��݂������̓r�������A���������܂����̉���Ŏ����������Ƃ�����Ƃ����b���āA���t�����Ƃ������Ă���B
�@���a�T�N�i�P�X�R�O�j�ɉ��c��l�Y�����̉������@�肵�A�Z��p�̗����݂��Ĉ�ʂɂ����p�����Ă������A�R���̂��Ƃł�����t�߂̔_�Ƃ����p������x�ŁA���ʂ����Ȃ��ቷ�̂��߁A����Ƃ��Ă͒n���ȑ��݂ł������B
�@���̉��{�i�I�ȉ���Ƃ��Ē��ڂ���͂��߂��̂́A���a�S�P�N�i�P�X�U�U�j�V���ɓ����̓y�n���L�҂ł������D�y�̋{�с@���A�Ǝ҂Ɉ˗����ă{�[�����O���s�����Ƃ���A�n���R�O���[�g���̒n�_�Őێ��U�O�x�̉��A�����P�U�O���b�g�����o�i���S�Q�E�W�E�P���V�j�������Ƃ���A�����ɏZ���������āA�_��فi�D�y�E����E���o�c�j�Ɩ��t���ĉ��ق��o�c�������Ƃɂ͂��܂�B
�F�䑑�i�ʐ^�P�j

�@�������_��ق͊Ԃ��Ȃ��p�Ƃ��A���̌ケ�̉���͂S�V�N�ɔ��_�J��������ЁA�S�W�N�ɎR�{�q�v�i���j�A���N������В錚�i���j�ւƏ��L�����ڂ�A���N�錚������ɂ�����{�̐��{�[�����O�����B
�@����A�y�n�ɂ��ẮA���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�P�Q���ɖ�c�nj䗿�n�������̍ہA�����ݏZ�̌Óc�C�ꂪ���������������A���a�S�O�N�P���ɂ��̈ꕔ����c���̉��c�y�v�ɁA����ɂP�Q���ɂ͉��c�������V��ւƈڂ����B���S�P�N�Ɏ���͒錚���牷�p���̕�������ƂƂ��ɗ��ق����āA�u�F�䑑�v�Ɩ��t���ĉc�Ƃ��J�n�����B
�@�͐H����ŁA���x�͐ێ��T�U�x�A�䂤�o�ʂ͖����T�O���b�g���ŁA�菝�E�₯�ǁE�ݒ��a�E�w�l�a�E�畆�a�ȂǂɌ��\������A���p�q���ߔN����ɑ������Ă���B
�����쉷��
�@�����ɗV�y���z�R�̍��ň��p�����u���̑n�Ɓv�̋�R�̈�߂ɁA
�u�c�c�c�����͎~�ނʂ����̒���k���āA�����̐����܂ŋt������B�Â���R�̐Ղɂ͋�����������A�O�{�A䊁X�Ƃ��Đ��������̒��ɗ����Ă�B�����������ɂ͑ۂ������Đ�̒��ɓ]�����Ă�B����������������킫�o�鉷��͈��āA���̒��֗���Ă�B�F���̒�����^���Ȍ����J�����Â��z�B�ɂ́A�y�����ꗎ���āA�Â���m��ʍB�̒��ɂ͐��̗����鉹�������̂₤�ɉ��������Ă�B�����͉���̑��ɉ��āA��c�̏����������B�c�c�c�v
�����쉷��i�ʐ^�P�j

�Ƃ���A��������ɂ͊��ɗV�y���z�R�ɑ����ʂ̉��킫�o�Ă������Ƃ�������Ă���B
�@�Ȃ��A����͌�N�s���J�x�c�w���̊Ǘ��l�ł����������đ��Y���A��������ĂĊǗ����A�����g���������h�ƌĂ�Ă������A���a�̏��߂ɒ��O�z�Ƃ����̒n��i�o���邱�ƂɂȂ����̂ł��̌��������n����A�E���̕����{�݂Ƃ��ė��p�����悤�ɂȂ����B���������̉���̉��x�́A��������ĊJ������܂ł͂R�U�x���x�ł����Ȃ������B
�@�܂��A����Ƃ͕ʂɂ���ɏ㗬�P�L�����[�g���̒n�_�ɁA�n�Ӄ����̌o�c���鉷��h�������ĉ��쉷��ƌĂ�A�����[�}�`�E�_�o�ɁE�n���ǁE�]�����E�w�l�a�E�畆�a�ȂǂɌ��\������Ƃ������ƂŁA���܂肪���Ŏ������Ȃ��瓒��������q�����������B���������̉�����A���O�z�Ƃ��������ĐE���̓����p�ɗ��p���Ă������A���a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�̕R�ɂ���Ă���������ł����̂ł������B
���c���_����
�@���a�S�U�N�k���@���������ɏA�C���Ă���A�Y�ƐU���̈�Ƃ��Ċό������J���ɐϋɓI�ɏ��o���A���ɗ����쉈���̉��̓��n��A�܂�����n��Ȃǂ̒�����k�C���n�������������Ɉϑ������B���̌��ʁA���a�S�X�N�i�P�X�V�S�j�X���Ɍ��n�̒��ōł��L�]�Ǝv���鉔��n��ɏœ_�āA�������_�F�ΐ��i��ɍ����Q�V�V�����ƂȂ�j���_�s�X�n�����P�X�L�����[�g���A���Ȃ킿���_�E�F�Η����̂�⒆�Ԃ��番���������X�O�O���[�g���̒n�_�A�����鍂������ƌĂ�Ă����n�_�̌@����s�����B����ɂ��A�n���S�X�E�V���[�g���̉ӏ�����ێ��S�V�E�W�x�̓��������S�T�O���b�g�����o���A����Ɍ@�艺�����Ƃ���A�X�V�E�R�`�P�O�O���[�g���̉ӏ��łU�S�x�A�����S�O�O���b�g�������o���A�㕔�������킹�ĂT�S�x�V�O�O���b�g���́A�ǎ��ŖL�x�ȓ��ʂ邱�Ƃ��ł����B
�@�����Œ��́A���̉���̗��p�ɂ��Č����������A�������C�y�ɗ��p�ł�����O��������݂��邱�ƂƂ��A���T�O�N�P�O���P�T���Ɂu���c���_����v�Ɩ��t���ăI�[�v�������̂ł���B
�@���̉���́A�ؑ��������ĂP�V�R�������[�g���̎R�������̑���ŁA�����͒j�����ꂼ��U�O�������[�g���A���̂ق��ɂT�O�������[�g���̋x�e����݂������̂ł������B����̉^�c�ɂ��ẮA�P�O���̋c��ʼn�����𐧒肵�āA����������l�P�O�O�~�A���l�T�O�~�A���l�R�O�~�Ƃ��A�c�Ǝ��Ԃ͖����i�Ηj���������j�ߑO�P�O������ߌ�U���܂łƂ����B
�@�������ĊJ�݂��ꂽ���_����́A�Ǘ��l�Ɉϑ����ĉc�Ƃ��������A�X�ђn�тɕ�܂ꂽ�B�R���̉���Ƃ������ƂŁA�J�ݓ����͓d�C���d�b���Ȃ��Ƃ����s�ւ��ɂ�������炸�A���p�q�͎���ɑ����ĂT�T�N�P�O���܂ʼn��ׂT���Q�V�P�S�l�ɋy�B
�@�����������Ƃ��璬�́A���_�E�F�Γ��H�𒆐S�Ƃ����L��ό��J���𐄐i����ƂƂ��ɁA����ό����ɂ����邻�̖������ʂ������߂ɂ��A���{�݂̐����ɂ��Č����������A�T�T�N�U���ɓd�C���A�V���ɂ͓d�b�������B����ɁA�N�����p�ł���������Ԃ����p�\�Ȏ{�݂��v�悵�A��S�T�R�Q���~�𓊂��A�ؑ������^���A�J���[�g�^���Ԃ��Q�K���āA���ׂU�P�U�E�S�������[�g���̎{�݂��������A����܂ł̎{�݂Ɠn��L���łȂ��A�P�P���P������c�Ƃ��J�n�����̂ł���B���̎{�݂́A����̉��ɂ��т����W���X�X�X�E�R���[�g���̗Y�g�x�ɂ��Ȃ݁A�u���ڂ����v�Ɩ��t����ꂽ�B
�@���ܕ\�͕ʎ��̂Ƃ���ł���B
���c���_���ڂ����i�ʐ^�P�j

���͏�
| �@�T�O�@�q���ϑ�Q�W�W���S�W�S�� | |||||||||||||||||||
| �\�@�@�@���@�@�@���k�C���R�z�S���_���Z�����P�R�W�Ԓn�@�@�@�@���_�����@�@�k�@�@���@�@�@�@�@�� | |||||||||||||||||||
| ���@�@�@�_�@�@�@���@�@�@��@�@�@�@�@�i���@��@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j | |||||||||||||||||||
| �@1�D�@�N�o�n | �R�z�S���_���@�@����@�@�@�@���L�є��_���Ƌ�@�@�Q�O�O�єǁ@�ɏ��� | ||||||||||||||||||
| �@1�D�̎���� | ���a�T�O�N�U���P�W���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@ �V�@��@�J�@�@�@�C�@���@�@�@�@�P�U�� | ||||||||||||||||||
| �@1�D����� | �@�����i�Q�O�T�D�T���j�ɂ�鎩���� | ||||||||||||||||||
| �@1�D���� | �ہ@���@�@�T�R�D�S�x�@�@�@�@ �P�D�@�N�@�@�@�o�@�@�@�ʁ@�@�@�@�P���ԁ@�@�@�R�S�T�� | ||||||||||||||||||
| �@1�D���� | ���F�����̂������C���c���C�L�Ȃ� | ||||||||||||||||||
| �@1�D���f�C�I���Z�x | �o�g�@�@�U�D�T�i��F�@�j�@�@ �P�D�@��@�@�@�@�@�@�@ �d�@�@�@�@�P�D�O�O�P�P�i�Q�O���^�S���j | ||||||||||||||||||
| �@1�D���˔\ | ��@�@�@�@�@�@�@�@�� | ||||||||||||||||||
| �@1�D�����c�����i�P�C���j | �R�D�T�U�W�O���� | ||||||||||||||||||
| �@1�D�ܗL�����y�т��̕��ʁi�P�C���ɊܗL���镪�ʁj | |||||||||||||||||||
| �J�`�I�� | �~���O���� | �~���o�[�� | �~���o�[���� | �A�j�I�� | �~���O���� | �~���o�[�� | �~���o�[���� | ||||||||||||
| ���f�C�I�� | �g�E | ��@�� | �E | �E | �N���[���C�I�� | �b�h�f | �P�P�U�S�E | �R�Q�E�W�S | �T�O�E�R�V | ||||||||||
| �J���E���C�I�� | �j�E | �V�X�E�O | �Q�E�O�Q�O | �@�R�E�P�O | �q�h�����_�C�I�� | �g�r�n�S�f | ��@�� | �E | �E | ||||||||||
| �i�g���E���C�I�� | �m���E | �P�O�U�O�E | �S�U��P�P | �V�O�E�V�Q | ���_�C�I�� | �r�n�S�h | �R�R�W�E�S | �V�E�O�S�U | �P�O�E�W�P | ||||||||||
| �A�����j�E���C�I�� | �m�g��S | ��@�� | �E | �E | �q�h���ӎ_�C�I�� | �g�o�n�S�h | �O�E�O�X�R | �O�E�O�O�Q | �@�O�E�O�O | ||||||||||
| �J���V�E���C�I�� | �b���d | �Q�T�O�E�P�@�@ | �P�Q�E�S�W | �P�X�E�P�S | �q�h����_�C�I�� | �g�`�r�n�S�h | �O�E�O�O�T | �O�E�O�O�O | �@�O�E�O�O | ||||||||||
| �}�O�l�V�E���C�I�� | �l���d | �R�X�E�W�R | �R�E�Q�V�T | �@�T�E�O�Q | �q�h���Y�_�C�I�� | �g�b�n�R�f | �P�T�S�Q� | �Q�T�E�Q�W | �R�W�E�V�V | ||||||||||
| �����C�I�� | �y���d | �ȁ@�� | �E | �E | �Y�_�C�I�� | �b�n�R�h | ��@�� | �E | �E | ||||||||||
| �t�G���C�I�� | �e���d | �@�O�E�X�U�V | �O�E�O�R�T | �@�O�E�O�T | ���_�C�I�� | �n�g�f | ��@�� | �E | �E | ||||||||||
| �t�G���C�I�� | �e���c | ��@�� | �E | �E | �����C�I�� | �g�r�f | ��@�� | �E | �E | ||||||||||
| ���C�I�� | �b���d | �ȁ@�� | �E | �E | ���f�C�I�� | �e�f | �O�E�U�O�O | �O�E�O�R�Q | �@�O�E�O�T | ||||||||||
| �}���K���C�I�� | �l���d | �@�P�E�P�X�T | �O�E�O�S�S | �@�O�E�O�V | �@ | �@ | �E | �E | �E | ||||||||||
| �A���~�j�j�E���C�I�� | �`���c | �P�P�E�P�Q | �P�E�Q�R�V | �@�P�E�X�O | �@ | �@ | �E | �E | �E | ||||||||||
| ���C�I�� | �o���d | �ȁ@�� | �E | �E | �@ | �@ | �E | �E | �E | ||||||||||
| �v | �P�S�S�Q�E | �U�T�E�Q�O | �P�O�O�E�O�O | �@ | �@ | �R�O�S�T �E�@ | �U�T�E�Q�O | �P�O�O�E�O�O�@ | |||||||||||
| �ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�v | �S�S�W�V�@�@�~���O���� | ||||||||||||||||||
| ��d���� | �~���O���� | �~�������@ | �@ | ||||||||||||||||
| ���^�]�_ | �g�Q�r�����R | �P�P�P�E�T | �@�@�P�E�S�Q�W | �@ | |||||||||||||||
| ���^��_ | �g�a�n�Q | �@�Q�V�E�U�O | �@�@�O�E�U�R�O | �@ | |||||||||||||||
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�v | �S�U�Q�U�~���O���� | ||||||||||||||||||
| �V���Y�_ | �b�n�Q | �S�U�Q�E�P | �@�P�O�E�T�O | �@ | |||||||||||||||
| �V���������f | �g�Q�r | �@�@�O�E�U�S�U | �@�@�O�E�O�P�X | �@ | |||||||||||||||
| ���@�@�@�@�@�@�@�@�v | �T�O�W�X�@�@�~���O���� | ||||||||||||||||||
| �� �@�� �@�� | �@ | ||||||||||||||||||
| �P�D���@�@�@�@�@�@�@ �@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ܓy�ށ|�H����i�ɘa���ᒣ������j�@�@�@�@�@�@�@�i�����͖@�ɂ��j | |||||||||||||||||||
| ���a�T�O�N�U���Q�T���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͎ҁ@�k�C���Z�p�����@���@�m�@�q�@�Y�@�@�@ �k�C�����q���������@�@�@ |
|||||||||||||||||||
| �P�D�K���Njy�ы֊��� | |||||||||||||||||||
| ���p | �K���� | ���E�}�`�������C�^�����Q�C�n���C�������]����ъp���ǁC���㎙���C�X�N����Q�C�������햝������ �C�����@�\�s�S�ǁC�q�{����s�S�ǂ���ь��o��Q |
|||||||||||||||||
| �֊��� | ���ׂĂ̋}��������ɔM�������C�i�s�����j�C������ᇁC�d���S���a�C�o���������C���x�̕n�� ���̑���ʂɕa���i�s���̎����C�D�P���i���ɏ����Ɩ����j�B �܂����x�̓����d���ǁC�������NJ��҂̍������i�S�Q���ȏ�j�͌����Ƃ��ċ֊��Ƃ���B |
||||||||||||||||||
| ���p | �K���� | ���������펾���C�����֔�C�ɕ�����єA�_�f���C�A�����M�[������ | |||||||||||||||||
| �֊��� | ���C�l�t���[�[�C�������ǁ@���̑���ʂɐ���X���ɂ������ | ||||||||||||||||||
| �P�D�����̕��@�y�ђ��� | �@ | ||||||||||||||||||
| �P�D���p�̕��@�y�ђ��� | �@ | ||||||||||||||||||
| �@�@�@�@�@���a�T�O�N�U���Q�T���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ҁ@�@�k�C���q������ |
|||||||||||||||||||
�R�^������
�@���ٖ{���R�z�w�����P�L�����[�g�����_���A�����T���������̎R���ɃR�^��������B
�@���̉���́A�����n�������̊J���Ɩ��Ԋ�Ƃ̈琬��ڎw���ĉ���̊J�����v�悵�A���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�j�P�Q���ɉ���@��p�n�ɏ[�Ă邽�߁A�l���T�V�Ԓn�e�n�ЗY���L�̔��O��������O���i��R�V�O�U�������[�g���j���A�n�������������ɒ������˗������Ƃ���A���@�L�]�Ƃ������ʂ��̂ł������B
�@�����Œ��́A�W�@�ւƋ��c���d�˂����ʁA��]�҂�����Ή���J���Ƃ��̌�̌o�c�̂��ׂĂc�ɔC���ׂ�����낵���낤�Ƃ̌��_�ɂȂ�A��]�҂��L�����߂��Ƃ���A���a�R�S�N�ɂȂ��ĕx�m�����̌��ƎҊ֏�@������@��̐\���o���������B���̂��ߒ��͐ێ��S�O�x�ȏ�̉��䂤�o�����ꍇ�͓y�n�����n����Ƃ�����������A���l�ɂ���Ė{�i�I�ȃ{�[�����O���J�n���ꂽ�̂ł���B�����邱�̒n�т́A���_�w�Ƃ������ΎR���̑w���̂��߃{�[�����O�͓�q�����̂ł��邪�A�R�T�N�U�����ɂȂ��Ēn���R�T�V���[�g���ɒB�����Ƃ���ŁA�ێ��S�P�E�U�x�A�䂤�o�ʖ����X�T���b�g���̉��䂤�o�����̂ł������B
�@���͓��N�V���̋c��ɂ������A�����̏����ǂ���y�n�P�P�Q�R�i��R�V�O�U�������[�g���A��n���l���P�S�S�̂Q�A�P�S�T�̂Q�A�P�S�U�j�����n���邱�Ƃɂ��ċc��̏��F�A�֏�@���ɏ��n�����̂ł���B
�@����ɂ�蓯�l�́A�R�T�N�P�Q���ɉ��ق����āA�g�R�^�������h�Ɩ��t���Čo�c���J�n�����݂Ɏ����Ă���B
�R�^������i�ʐ^�P�j

�@�Ȃ��A�͖��F���������A�ێ��S�P�E�T�x�A�䂤�o�ʖ����X�T���b�g���ŐH����ł���B
����z�e�����F
�@�R�^�������Q�O�O���[�g�����_���̒n�_�A�����T���������ɉ���z�e�����F������B
�@���̉���́A���a�S�V�N�i�P�X�V�Q�j�R���ɖ��J�N�Y�����ă{�[�����O���s���A�ێ��Q�S�E�T�x�A�����P�T�O���b�g���̗����@�肠�āA�����Ɂu�z�e���l���v�����ĂČo�c�������Ƃɂ͂��܂�B�́A�P���d����Ŗ��F�A�菝�E�₯�ǁE�畆�a�E�p���ǁE���������펾���E���A�a�Ɍ��\������B
�@���a�T�S�N�i�P�X�V�X�j�S������n�������̌o�c�ƂȂ�A���̂��u����z�e�����F�v�Ɖ��߁A���p�q�ɑ��đ��}�o�X���^�s���ĕւ�}���Ă���B�܂��A���ϘA�̎w��Ƃ��Ȃ��Ă���B
�R�z����
�@���S���ٖ{���R�z�w�����R�O�O���[�g����c�����A�����T���������̎R���ɎR�z���������B
�@���̉���́A�Â��Éi�N�ԁi�P�W�S�W�`�P�W�T�R�j�ɔ������ꂽ�Ƃ����A�����N�Ԃ́u�ڈΎ��n���l�^�v�R�z���̍��ɁA
�@���͐V�z�A�ʍs���̓�A�H��ɗN�o��
�Ƃ���A�܂��A���a�̏��߂ɔ��s���ꂽ�Ǝv���铹��̉�����Љ�����̂ɁA�R�z�z��Ƃ��āA
�@�Éi�N�Ԃ��̒n�ɉ��ޗ������A�������N�V�J�̏h��F�������q�V�����M��ʂɓ��������߂����A�吳��N���L�u����v������Ă�������N�o�����A�]�O�ʂ���M����Ƃ��Čo�c���c�c�c�ƋL����Ă���B
����z�e�����F�i�ʐ^�P�j

�@���̉���́A�z��n�Ƃ��ď㔪�_�̒��{�Z�Y�����L���Ă������A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�ɔ��ق̍����@�����A�R�z�X�ǂ̓���ɂQ�K���Ẳ��ق����Ăĉc�Ƃ����Ƃ���A�����͉��݂̖L���������Đ������ɂ߂��Ƃ������A���̌�͎���ɕs�������������ߗ��p�q���}���Ɍ���A�P�T�N����ɂ͔p�Ƃ��Ă��܂����Ƃ����B
�@�Ȃ��A���̍z��n�́A���{�Z�Y���珺�a�X�N�ɍ����@���Ɉڂ�A���݂͓����s�̒��J��g�V�̏��L�ƂȂ��Ă���B
�v�ۓc����
�@���ٖ{���R�z�w�����P�L�����[�g����c�����A����̉����ɗ�킫�o�Ă���B
�@�吳�����ɎR�z���֓��A�����v�ۓc�Ď����A�吳�P�S�N�i�P�X�Q�T�j�ɂ��̗��𗘗p���ĉ��ق��o�c���A���̌�v�ۓc���`�������p���A�R�z����ƂƂ��ɐ������ɂ߂��B���ɔ畆�a�Ɍ��\������Ƃ������ƂŁA�����q�̗��p�����������B
�@�����o�c���������Ă������A�����Ƃ̕s�U��A�Љ��̕ω��������ė��p�q������͂��߁A���a�Q�U�N�ɂ͔p�Ƃ����̂ł������B
���̑��̉���
�@���܂܂ŏq�ׂ��ق��ɁA�������̓��Ɂu�]�H����v�A�u����������v���������B
�@�]�H����́A�����R�Q�N�i�P�W�X�X�j�ɗ����̑��؍����Y���A��������݂��ē����ł���悤�ɂ������A���M���Ȃ���Η��p�ł����A�]�藘�p����Ȃ������Ƃ����B
�@����������́A�]�H�������i��n�̗�����݂ɋ߂����ɂ���A�[�����Y���o�c���Ă����Ƃ������A���l���p�Ɠ]���������߁A�J�p�N���ڂȂǂ͑S���s���ł���B
�y�㊪�E��S�ҁ@���z