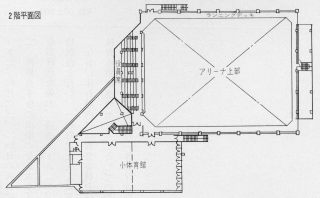第8編 教育
第1章 教育制度の変遷
第1節 教育制度の概要
教育制度のれい明
徳川幕府崩壊のあとを受けて誕生した明治新政府時代に入ってから、わが国の教育制度はにわかに整えられ始めた。すなわち、明治4年(1871)の太政官(明治政府の最高官庁)制改革にともない文部省が創設され、翌5年壬申7月に太政官は、学事奨励に関する「被仰出書」を公布して「人たるものは学ばずんばあらず」と述べ、さらに「自今以後一般の人民必らず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめんことを期す」と施政の決意にふれるとともに「一般の人民他事を抛ち自ら奮て必らず学に従事せしむべき様心得べき」と、国民皆学を目指すことを明らかにした。
次いで8月「学制」を発布し、9月には「小学校則」を定め、原則として義務教育制を採用するに至り、いよいよ近代的な学校教育制度整備のれい明期を迎えたのである。
しかし、開発の遅れていた北海道では、時期尚早ということで、直ちにこれに拘束されることなく、土地の状況に適合した独自の方式が採られることになった。したがって北海道の教育は、この学制と直接のかかわりはなく、郷塾あるいは郷学などと称して、いわゆる寺子屋式教育が続けられたわけである。
6年9月に至って北海道開拓使は、これらを文部省令に準拠して「教育所」と改称させることにし、しかも各郡に教育所を設置するよう勧奨したため、特に道南地方に多かった寺子屋も逐次公費による教育所に改められていったという。
こうした社会背景のなかで、比較的早くから開けていた山越内では、開拓使山越内出張所詰使掌山本質の尽力によって、6年11月に旧会所建物を利用して「山越内教育所」を開設した。これがまさしく当町における教育施設の初めである。
一方、落部村においても総代相木慶太郎らの主唱によって、7年3月東流寺に「開成私塾」を設けて子弟教育に乗り出したのである。なお、このころ落部管内に属していた由追にも、医師松沢 某がこの地方の子弟を集めて教育していたという言い伝えもあるが、その詳細については全く不明である。
ちなみに学制による教育費は、生徒が受業料(明治19年3月まではこう称していた)を負担するという受益者負担の原則に立ち、その不足するところを学区が区内集金や寄付金などで補充し、さらに不足する場合には国が補助するという考え方に立つものであった。
村落小学教則下の教育
明治8年3月に函館支庁では「学制」を順次施行する方針を立て、函館小学校教則を定めるとともに奨学告諭を出し、併せて教育費の人民負担を求める布達を出したが、これは事実上勧告にとどまったようである。そして、教育制度が公式に地方山村に及ぶことになったのは、明治11年1月に函館小学教則を改正して、別に「村落小学教則」が定められてからである。
この村落小学教則は、上等五級(2年半)、下等五級(2年半)の計5年で卒業する課程とされ、(正則)小学教則の上下とも八級(4年)の計8年の課程とされているのに比べると、かなり簡易化されたものであった。これは、学制の中の
「村落小学ハ僻遠ノ村落農民ノミアリテ教化素ヨリ開ケサルノ地ニ於テ其教則ヲ少シク省略シテ教ルモノナリ」という規程に準拠したものであるという。
この教則制定によって、教育施設の多くは「学校」と公称することになり、明治11年2月に山越内教育所は「公立山越内学校」と改称された。一方、この年遊楽部原野に入植した徳川家の旧臣たちが、11月には早くも開墾地内に私塾を開いて子弟教育に着手し、翌12年に学校設立の許可を受けて、8月に「八雲学校」を創設するに至った。
なお、落部村においてもこの村落小学教則に基づき、周辺の村々で学校設立の機運が高まることによって、地元への学校設立の声も上がり、有志の発意によって村民の資金協力を得て12年9月には校舎を建築し、翌13年2月「公立落部学校」を開設したのである。しかし、これらの学校はいずれも下等五級(2年半)だけを修学するという、程度の低いものであった。
この当時、開発途上にあって所得水準の低い開拓移民にとって、学校施設の開設維持に関する費用の工面については大きな負担であり、しかも子弟の教育に対してはおおむね関心がうすい状況にあった。函館支庁では「民力の贍(タ)ルヲ待ツ」という方針のもとに、12年7月公立学校の教員月俸は特に官費をもって支給することとし、学校設置を推進したのであるが、翌13年6月限りで早くも官費支給を廃し、「小学補助金配布及支払概則」を定め、文部省補助金の例ならい、補助制度に切り替えるという状況であった。ちなみに13年度の補助金額は、学童一人当たり五〇銭という割合であった。
変則小学への移行
明治12年9月に新しい制度である「教育令」が公布され、学制が廃止された。この教育令の概要は、公立学校の修業年限を八か年とし、地方の実情によっては四か年まで短縮でき、さらに、学校に入らなくても別な方法で普通教育を受けることのできる者は、これを就学とみなすというものであった。次いで13年1月文部省達により、小学校で読書・習字・算術・地理・歴史・修身の6科を具備しないものは「変則小学校」とするという規程が設けられた。
こうした新制度の志向するものは、間もなく北海道にも導入され、13年3月に函館支庁が定めた「小学教則」と「変則教則」によって、さきに制定された村落小学教則はわずか二か年で改変されたのであった。
この変則小学教則には、就学について「此ノ教則ハ父兄ノ営業ヲ助ケ永ク学問ニ従事スル能ハサル者ノ為ニ設、務テ日用切近ノ学科ヲ教授シ、満四ヵ年ヲ以卒業期トス」とあり、課程を八級に分けてそれぞれ六か月の修学期間とし、学科内容も地理・地誌・理科などが欠け、算術の代わりに専ら珠算を採用するものであった。さらに10月には一部が改正され、変則学校を卒業してもなお就学しようとする者のために、修学期間を上中下三級の一か年半とする「余科」の課程を設けることができるものとされた。
これらの措置は、地方村落における移民の乏しい経済力と、教育要求程度の低さに対応するものであったといわれ、この施行地を定めるに当たっては、関係の茅部・山越郡下の学校はすべて変則学校とされたが、修学年限が四か年に延長されたわけである。なお、当町管内においては余科を設ける学校はついになかった。
変則小学の発展
明治13年2月教育令が大幅に改正され、全体に中央集権的色彩が濃厚になり、就学督促や学校設置に関する監督権限が強化された。さらに翌14年5月初等教育の方向を示す「小学校教則綱領」が布達された。
しかし、これらの法令による北海道内の制度改革は、三県時代に入ってからのことであった。函館県は明治16年3月新たに「函館県小学校教則」および「函館県小学校校則」を定めて管下に布達したことにより、それまでの変則小学校教則など諸規程は、わずか3年で再び制度が改正されたのである。
この新制度は、小学校を初等科・中等科(各六級3年)・高等科(四緑2年)の三段階制8年とし、その履修科目にもそれぞれ差異を設けるものであり、16年4月から実施されたのである。
しかし実情として、この正規の三科をすべて設置する学校は、市街地を形成する比較的豊かなところという、ごく少数に限られ、その他の地域ではそれぞれの状況に応じて初等・中等の2科、または初等科だけを設置するという情勢であった。
この改革によって、当町管内三か村の学校は結果的にすべて初等科だけとなり、修学年限はこれまでより1年短縮されて3年となったが、このときから各学校は現代風に「○○小学校」と呼称されるようになった。
なお、これよりさきの13年7月、函館支庁では「公立学校分校及巡回学級設置手続」を定め、独立の小学校を設置できない村(地方)における便宜的な方法として、分校の設置方法を定めていたが、就学督励が強化されるにつれて、辺地で比較的児童の多い地域での教育が当然問題となってきていた。こうしたことを背景として、16年2月落部村野田追に「落部学校野田追分校」が開設され、翌17年1月八雲村黒岩に「八雲小学校黒岩分校」が開設されるなど、分校の設置が進められるようになった。
貧民子女学資の給与
住民個々のなかには、貧困のため子弟を就学させることのできないものもあった。こうしたことから、明治14年4月に函館支庁では「貧民子女学資給与規則」を定め、貧困の程度によって受業料を免除する「無謝修学」と、その他学用品のいっさいを交付する「給資修学」に区分して、その適用により子弟の就学率を高めるよう配慮した。
明治15年遊楽部川沿いの海浜地帯に居住していたアイヌ集落の子女を教育することにより、併せてその父兄をも感化しようという方針のもとに設立された「遊楽部学校」は、この給与規則を活用したものであったという。
学校林の無償下付
このころの学校経費は、町村協議費、受業料、補助金、篤志寄付などのほか、当地方の特殊なものとして、遊楽部川・野田追川・落部川などの渡舟賃収入を当てていたが、全般的に戸口が少なく財政基盤の弱い村々にとっては、経営費用の調達は容易なことではなかった。
こうした状況を憂慮した函館県をはじめ三県令らは、明治15年3月に政府の許可を受けて、学校維持のための基本財産を造成させるとともに、農業現術教育の場を与えることをねらいとして、公立学校に対し一校当たり50万坪(約167ヘクタール)を限度に土地を無償付与する道を開いた。
これによって八雲村では、字サランベ(音名川と砂蘭部川の中間地帯)の土地50万坪を予定して無償下付の出願をし、17年に実測のうえ46万3350坪の下付を受けて八雲学校の付属学林に充てた。しかし、山越内村では適当な土地がなかったものか、山越内学校の学林が下付された形跡がない。なお、落部村においては学校林地として、字入沢から辰五郎沢口にかけて相当地積の下付を受けていた。
小学簡易科時代
明治19年4月に「小学校令」が公布され、5月に文部省令「小学校ノ学科及其程度」および同訓令「小学簡易科要領」が布達され、尋常・高等小学へ移行の素地がつくられた。すなわち、小学校を尋常科と高等科の二段階に分けて修学年限を各四か年とし、このうち尋常科は義務教育とするという制度的内容のものであり、土地の状況によって簡易教育の道を開くというものであった。
これらの制度改正を踏まえて、道庁ではその改革を検討し、翌20年4月に「小学校規則及小学簡易科教則」を制定公布した。前者の小学校規則によれば、尋常小学校では修学年限を4年とし、卒業後六か月以上1年以内の温習科をおくことができるものとしたほか、復習科目や一週の授業時数など一定の標準を定めていた。これに対して後者の小学簡易科は、修学年限が3年で一日の授業時数を3時間とし、卒業後修学しようとする者のために同じく六か月以上1年以内の期間で、温習科を設けることができることとした。また、教科目についても普通小学校に比べて、修身と体操を除き読書・習字・算術のほか特に作文と実業演習(年長女子は裁縫)が加えられていた。さらに事情によって学級を分けるときは午前もしくは午後、または夜間にも授業ができること、生業繁忙期には50日以内の休暇を設けることができるとしたなど、村落の実情を配慮したものであった。
道庁ではこれらの実施にあたり、公立学校の等科指定を行っているが、この時点で全道260校のうち尋常科・高等科の併置校は、札幌・函館・松前の3枚、尋常小学校もわずか7校に限られ、他の250校はすべて小学簡易科の課程という状況であった。したがって管内小学校は、実体としては名称や修学年限とも従前のままであったが「小学簡易科」の学校となり、教科目と授業時教において変化がみられたのである。
しかし、22年8月に「小学簡易科教則」を改正し、授業時教を3時限から5時限まで延長できること、4時限以上の授業を行う場合は修身や体操を加えることができることなどを定めたので、実質的には尋常科とほとんど内容を同じくする道が聞かれた。
この改正は修学年限を延長せず、さらに経費も増加させずに、教育内容の高度化を図るためにとられた措置であったというが、当時、管内の学校にどのように作用したかは知ることができない。
尋常小学校の誕生
明治21年(1888)4月に市制・町村制が公布され、さらに23年5月には府県制令郡制が公布されるなど、地方自治制度が整備されたことにともない、これと教育行政との関連を明らかにして、国民教育の拡充を図るための必要な措置がとられた。すなわち、明治23年10月に小学校令が改正公布され、小学簡易科廃止の方向が打ち出されたのである。しかしこの規程は、市制・町村制を施行している府県に適用するというもので、直ちに北海道に適用されるには至らなかった。
25年4月に「市町村制施行セサル地方ノ小学規程」が発布され、市町村制を施行していない地方でも、小学校の設置などの基本的な事項を除いて、小学校令の規程により難いときは、長官(北海道の場合)が文部大臣の許可を受けて特別の定めをすることができることとされた。
これらの規程に基づいて道庁が新制度を布達したのは明治28年3月で、「小学校則」および「小学校修業年限指定標準」の制定により、4月からこれまでの小学簡易科教則が廃止され、各学校の名称が一様に「○○尋常小学校」と改称されることになったのである。
しかし、このときの改正では尋常小学校を二類に区分し、第一類は修業年限を3年または4年とし、第二類は特殊な地方で、2年または3年として教科内容も低く、授業時教も短縮されたものとなっており、その設定は町村の規模や態様に応じた一定の指定標準が定められた。なお、この指定標準の中で「小学簡易科ヲ尋常小学校ト改メ其修業年限ハ三箇年トス(以下略)」と明示されていたので、管内の小学校はこれに該当することになり、修業年限は三か年で、第一類校の教科目では修身・読書・作文・習字・算術・実業・裁縫(女子)・体操と一定したほか、土地の状況によって唱歌を加えることができるとされたのであるが、3年制の学校に限って日本地理と歴史は加えられないことになっていた。
その後、八雲尋常小学校については、33年8月とくに認可を受け、他に先駆けて尋常科4年制を採用するとともに2年制の高等科を併置して「八雲尋常高等小学校」と改めたのは特異なことであった。しかもこのころになると、大規模地積貸付けによる農場が各地に興隆し、小作移民の増加によって学校を必要とする地域が増え、八雲村では八雲尋常高等小学校の付属として、32年10月に上砂蘭部分校と久留米分校が、翌33年5月に大関分校が開設(以上3枚は、さきに設匠の黒岩分校とともに34年4月に独立技となる)され、また、34年6月には落部小学校の付属として蕨野分教室が開設されるなど、学校設立が相次いで行われた。
明治33年小学校令改正
明治33年8月小学校令が改正されるとともに、文部省令で新たに「小学校令施行規則」が制定された。この改正の要点は、時代の進展に応じて義務教育に属する尋常科の修業年限を4年に延長し、授業料の徴収を原則として廃止するとともに、教科目が整理統合されるというものであった。しかも修了または卒業の認定については平素の学業成績を重視し、従前から引き続いて行われていた試験制度を廃止した。なお、高等科については二か年、三か年または四か年と、状況により採用されるものとした。
しかし、これもまた市町村制施行地に適用すると定められていたので、直ちに適用されるものではなかったが、この改正令は同時に布達された文部省訓令によって、北海道も同様に心得べきものとされた。これによって28年3月の小学校教則は廃止され、33年8月を期して尋常小学校はすべて4年制の学校となったのである。
簡易教育規程による教育所
地域の開拓が進み移住者が増加するにつれて、学齢児童数も増加したが、成立間もない町村などは経済的に学校施設を整える資力がなかったので、就学率はきわめて低い状態であった。道庁ではこのような特殊事情を考慮して、明治31年2月に「簡易教育規程」を制定した。しかしこの規程では、「町村」を単位とするものであったので、当地方においては実効がなかった。町村の内部においても同様に条件が整わず、就学困難な状況にある地区の多い実態にかんがみ、道庁は明治34年4月にこれを大幅に改正し、町村内の一部でも移住後5年以内、戸数100戸未満などで「尋常小学校設置ニ関スル費用ノ負担に堪ヘサルモノハ此ノ規程ニ依リ簡易教育所ヲ設ケテ尋常小学校ニ代フルコトヲ得」とし、教科目・修業年限・教則・学年・休業目などについては尋常小学校の規程を準用するものとして、就学率の向上を図ることとしたのである。
この規程をうけて八雲村が二級町村制施行直後の35年11月、常丹・奥津内の地帯を通学区とする「常津内簡易教育所」、野田生・柏木・大木平を通学区とする「大柏野簡易教育所」を開設し、それまでの山越内尋常小学校への遠距離通学の解消を図った。
その後、常津内教育所はなお通学区域が広く、不便が多いという事情から、38年6月に奥津内・鉄山・向野の地帯を通学区とする「奥津内簡易教育所」を設置して「常津内簡易教育所」と分離した。さらに同じ理由で、久留米尋常小学校の通学区から山崎の地帯を分離して、「山崎簡易教育所」を設置したのは同年8月であった。
明治40年の小学校令改正
明治40年3月に再び小学校令が改正された。この改正は、尋常小学校の修業年限をこれまでの四か年から六か年に延長し、これを義務教育とするとともに、高等小学校の修業年限を二か年(場合によっては三か年)とするということを中心とし、この実施は翌41年4月からというものであった。
これによって41年4月から、すべて尋常小学校の修業年限が6年に延長され、高等小学校は2年となった。この制度の基本は、その後昭和16年4月「国民学校令」が公布されるまで長く続いたのである。
特別教育規程による特別教授場
明治16年12月に北海道庁令で「特別教育規程」が定められた。これは当時特殊な条件下にある児童の就学対策として定められたもので、主として10歳以上になって就学する児童の、特別教育について規定したものであった。また同時に、新開地の児童や、季節によって一時的に出稼ぎする者の児童にも準用できるという性質のものであった。
この規程の要点は、教授の場所を「小学校又ハ簡易教育所建物ノ内外若シクハ児童ノ便宜ナル所ヲ選ビ、適宜之ニ充ツヘシ」とし、便宜な場所を設けてするものは「其最寄ノ尋常小学校又ハ簡易教育所ノ所属トシテ取扱う」としたこと、「教授ノ日及時間ハ児童ノ出席ニ便宜ナルトキヲ選ビ」学校長が適宜定めることなどとし、建物・施設などもいたずらに形式にこだわらず、児童の通学の便に重点をおいたものである。
しかし、この規程の趣旨は、40年3月の小学校令および小学校施行令の改正に合わせてその改正要旨を加味し、さらに従前の簡易教育規程と前記の特別教育規程を統合した形で、41年3月庁令をもって新たに定められた「特別教育規程」に引き継がれたのである。
したがって、従前の簡易教育規程の趣旨を折り込んで、「町村ニシテ尋常小学校設置ニ関スル費用ノ負担ニ堪ヘサルトキハ教育所ヲ設ケテ尋常小学校ニ代フルコトヲ得」という規程と、従前の特別教育規程による新開地域の児童などを対象とする特別の教授について「特別教授ノ場所ハ管理者ニ於テ児童ノ便宜ヲ図り適宜之ヲ設クルコトヲ得」という規程を同一規程内にまとめられたのであったが、山間地における新開地域が多くなっていたときでもあり、通学の便を考慮した特別教授場の新設という形で十分に適用された。
すなわち、大関尋常小学校付属としてサックルペシベ特別教授場(38年4月)、鉛川特別教授場(40年4月、のちに八雲校の付属となる)、トワルベツ特別教授場(41年12月)、ペンケルペシベ特別教授場(43年8月)の4校、大柏野簡易教育所付属として大木平特別教授場(39年6月)と野田生原特別教授場(43年8月)の2校が相次いで開設された。
さらに大正年代に入って、八雲尋常高等小学校付属として上鉛川特別教授場(3年4月)と大新特別教授場(5年6月)が、黒岩尋常小学校付属として富岩特別教授場(9年5月)と続き、昭和年代に入って八雲校に付属する八雲鉱山特別教授場(9年5月)が設立されていった。
一方、落部村でも明治42年4月に栄浜小学校の前身である恵海特別教授場と下の湯に白滝特別教授場、大正2年4月上の場特別教授場などが、それぞれ落部小学校の付属として開設されていた。
特別教育規程による尋常小学校
大正5年12月に庁令をもって再び「特別教育規程」が改正された。これによって従来の教育所という名称を廃して尋常小学校と改め、町村が尋常小学校の設置費用の負担に堪えないときは、この規程による尋常小学校を設置できることとなった。これは、同じ義務教育機関でありながら、尋常小学校と教育所に分けて二様に呼ぶことは、児童や保護者に心理的な影響を及ぼし、就学の普及発達を阻害するおそれがあるため、名称だけは統一しようとする趣旨であった。
したがって、この規程による尋常小学校は、小学校令による尋常小学校とは性格を異にし、原則として単級であり、設置後六か年間を限って存続を認めるもので、特別の事情がある場合は、道庁長官の許可を受けてその期間を延長することができるものとされていた。
教育所という名称の廃止にともない、大正6年4月蕨野教育所が自動的に尋常小学校となったが、この特別教育規程の趣旨によって大正8年4月恵海特別教授場が茂無部尋常小学校となり、さらに9年3月、鉛川・八線・赤笹の3特別教授場も独立し、それぞれ尋常小学校となった。
なお、蕨野・茂無部両校の経過については不明であるが、鉛川・八線・赤笹の3校は地域の事情によって、大正15年と昭和7年の2回にわたって規程の適用延長の許可を受けている。さらに昭和9年4月に野田生原特別教授場を尋常小学校に昇格させたが、翌10年4月からこれら4校を一斉に小学校令による尋常小学校としている。
高等科の増設
明治32年8月八雲尋常小学校に高等科が併置されてから、30数年間にわたってその設置を望まれながらも容易に実現せず、尋常科を卒業してからさらに高い教育を求める生徒は、遠く野田生・黒岩・大関・その他各地から汽車あるいは徒歩で、八雲までの通学を強いられてきた。このことは、生徒にとって大きな苦痛であり、また経済的負担もともない、各地区の小学校に高等科の併置を望む声が高まりつつあった。すなわち、昭和10年に公布された「青年学校令」によって、尋常小学校を卒業した者が進む普通科が各校に設置されるようになったが、地域の保護者は、働きながら学ぶという青年学校よりも、普通学科に重点をおく高等科を併置して進学させようとする機運が盛り上がってきたのである。
こうした社会的な要請が一段と高まりを見せたことから、町は昭和12年4月に野田生校へ設置したのをぱじめ、14年4月に大関校、15年4月に黒岩校と八雲鉱山校、16年4月に山越内校、20年4月に山崎校と、それぞれ地域的に主要な学校に高等科を併置して要請にこたえるとともに、教育効果の向上を配慮したのである。
一方、落部村においては、落部校に高等科を併設したのは大正11年4月であり、一校体制を維持してきたのであるが、同様な要請によって昭和17年4月に野田追・上の湯の2校にそれぞれ高等科を併置した。
教育費負担の地方費移管
大正7年に「市町村義務教育費国庫負担法」が公布され、小学校の正教員と准教員の俸給の一部を補肋する道が講じられた・そして徐々に補肋額の増額がみられるようになったものの、教員俸給費の負担は市町村にとって大きな財政負担となっていた。
しかし、昭和15年税制の画期的な改正が行われ、「義務教育費国庫負担法」として改正公布され、教員の俸給費の負担を市町村から道府県に移管されることとなり、相当の負担が緩和された。さらに18年の全面改正では、俸給に限らず、教員に係る負担のすべてが道府県に移管されることになり、初めて現行のような制度の素地が作られたのである。
国民学校の誕生
昭和6年(1931)に満洲事変がぼっ発して以来、戦局は急を告げ、小学校においても「忠君愛国」の精神かん養を中心とする教育が進められつつあった。こうしたことから、16年に小学校令が「国民学校令」に改正公布され、「皇国民」の錬成を目的に具体的に示されるに至った。「国民学校令」はその目的に「皇国ノ道ニ則リテ初等教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為ス」と唱え、時代に即応した初等教育の展開を期したのである。
これは、初等科6年と高等科を2年に編成し、19年度からは高等科も義務教育にしようとするものであったが、高等科の義務化は決戦態勢突入のため施行が延期されたまま終戦を迎え、ついに実現しなかった。
しかもこの国民学校令は、各小学校を「国民学校」とその名称を改めるとともに、初等教育を制度的に一本化するものであり、これまで北海道に適用されてきた各種の特例がすべて廃止されることになった。このため「特別教育規程」などが廃止され、特別教授場はすべて国民学校の「分校」とみなされることになったのである。
学校教育法の制定
昭和20年(1945)に太平洋戦争が終息し、敗戦の混乱のなかで、諸制度の民主的な改革が進められていた。教育に関しては、22年3月31日法律第二五号をもって「教育基本法」が公布され、「人格の完成をめざし、平和的な国家および社会の形成者として真理を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と教育の理念を提唱するとともに、教育権の独立についても明示されるなど、これまでに比べて根本的に変革されたのであった。
さらに同日「学校教育法」が公布となり4月1日から施行され、この法律によって学校が、小学校・中学校・高等学校・大学のほか、盲学校・聾学校・養護学校および幼稚園に区分され、さらに学校教育に類する教育を行うものとして各種学校が定義された。そして小学校を6年、中学校を3年としてこれを義務教育としたことにより、いわゆる63制へ移行することになったのである。
したがって、これまでの国民学校(初等科・高等科)は廃止されて単に「小学校」となり、別に新制の「中学校」が設置されることになったである。
新制中学校の設置
学校教育法の施行により中学校を設置することになったのであるが、これに当てるべき校舎がなく、施設設備は貧困な町財政にとって至難なことであった。町としては、従前の高等科併置校にそれぞれ独立の中学校の設置を理想としたのではあるが、各校の施設や校下の情勢などによって、昭和22年5月16日に町議会の議決を経て、本校として「八雲中学校」を設置し、野田生・山越内・山崎・黒岩・大関・八雲鉱山の6校に「分校」を設置することとし、5月20日を期して一斉に開校式を挙行したのである。
しかし十分な施設はなく、各分校は地元小学校の既存施設を、八雲本校は八雲小学校と高等女学校の校舎をそれぞれ間借りして充当し、二部授業という変則的な方法で急場をしのぐ有様であったため、町としてもこの施設整備については、緊急の要務であった。
こうしたことから町は、関係校下父兄と協議を重ねた結果、それぞれの所要施設の増設を寄付金で賄う方針を立てて協力を要請し、関係住民もまたこれに応じて積極的に取り組んだため、殊の外早期に整備を進めることができた。特に八雲中学校は、旧軍用建物を借りて模様替えしたことにより、翌23年3月には独立校舎を整えることができたのである。
なお、落部村でも22年5月落部小学校に併置する「落部中学校」を1校だけ設け、また同年12月には、生徒の通学の不便を解消するため野田追に分校を設けた。
戦後の学校増設
終戦後、戦災による集団疎開入植者をはじめ、緊急開拓者が山間の辺地に入植するにつれて、児童の通学についての緩和対策が必然的に問題となってきた。
こうした状況に対応して町は、24年4月に熊嶺分校(八雲小付属)を開設したのをはじめ、31年に富咲分校(大関小付属)を増設した。落部村でも32年1月に二股分校(上の湯小付属)を増設するとともに、いわゆる道川御料地区の児童については、森町との協議によって三岱小学校に委託入学させるという措置をとっていた。
学事取締・学務委員
明治5年(1872)8月に学制か公布され、北海道にも徐々に新教育制度の普及が進められつつあったが、明治11年1月に学務奨励委員(同年3月に学事取締と改称)を置くなど、教育行政組織もしだいに整備されてきた。その後、明治12年9月に教育令が発布され、町村内の学校事務を処理させるために学務委員を町村民に選挙させることになった。さらに13年12月に教育令が改定され、学務委員も定数の2、3倍を選挙し、その中から県令等で任命するように改められた。
しかし、当地方で山越内村戸長三井計次郎、落部村戸長柏木幾一郎に対し「学事取締兼務申付候事」という辞令が交付されたのは、明治13年5月11日のことであった。また、函館支庁が「学務委員撰挙規則」を布達し、「学務委員ハ毎町村ニ一名又ハ数名ヲ置者トシ、町村ニ於テハ其定数ノ三倍ニ当ル人員ヲ撰挙スルモノトス」と定め、さらにこれと同時に「学務委員事務章程」を定めてその任務権限を明らかにしていたが、実際上は戸長が選挙されて任命されたものらしく、落部村の柏木戸長が14年5月2日、山越内、八雲二か村の三井戸長が15年2月16日、それぞれ「学務委員兼務申付候事」との辞令を受けている。
学務委員は学区を管理し、就学督励・学校巡視・学校経費予算を作り、戸長と協議して議案を作製し、郡町村総代人に議定させるなど、いわば学事に関する事務の一切を管掌するものであった。
その後、明治18年6月教育令の改正によって学務委員が廃止されたので、函館県でも同年8月に廃止し、従来学務委員の行った教育事務は、すべて戸長に処理させることになった。
明治23年10月の「地方学事通則」により、これまでの学務委員とは性格が異なる新たな学務委員制度が施行されることになったが、これが北海道で適用されることになったのは28年5月のことであった。すなわち、庁令をもって「学務委員規則」を定め、「区町村立小学校設置区域内ニ学務委員ヲ置クベシ」とされ、その人員および任期は町村総代人会で評決し、戸長が定め、戸長は郡長の許可を受けるというものであった。しかしこの制度が、当町でどのように作用したかを知る史料は、残念ながら残されていない。
さらに、明治33年12月には新たな「学務委員規則」が公布され、学務委員は町村長・戸長を補佐し、または、その諮問に応じて意見を述べるものとされた。この制度により、明治35年以降の八雲村では、学務委員は村(町)会議員のうちから3名、村(町)会議員の選挙権を有する者のうちから3名、さらに学校の男子教員のうちから4名の計10名を定員とし、前二者については村(町)会で選挙するものであった。この学務委員は、長い間教育行政に参画する機関として存続していた。
教育委員会=公選
戦後、教育の民主化・地方分権・一般行政からの独立などをねらいとして、昭和23年7月15日に教育委員会法が公布された。そしてまず都道府県と五大市に教育委員会を設置することとされ、同年10月に選挙が行われた。市町村における教育委員会は、当初は25年までに設置するものとされたが、その後の法政正によって2年間設置期限が延長され、さらに再延長が考えられていたが、その法案が国会で廃案となったため、早急にこれを設置しなければならないこととなった。
こうしたことから、「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意によって地方の実情に即した教育行政」の展開を期する教育委員会委員の選挙は、昭和27年10月5日に実施された。選挙は、公選委員定数4名に対して6名の立候補者があり、激しく争われた結果、北島光雄・館英太郎・長谷川克巳・関口恭平が当選した。また、議会議員の中からは坂本堅太郎が選出され、委員長には互選により関口恭平が就任した。初代教育長は町助役大塚卯次郎が兼任することとし、11月1日を期して八雲町教育委員会が発足したのである。
これにより、それまで町長の事務部局の機構であった「教育課」が廃止され、その機能は教育委員会事務局に移された。翌28年4月16日には、専任教育長に森町立森中学校長であった加藤慎一が任命され、教育行政全般の処理体制が整った。
また、このときの規定としては、最初の公選委員は半数改選を前提とし、得票教の少なかった2名が29年に任期2年で退任となるものとされていたが、法の政正によって任期が延長され、半数改選は行われないことになった。なお、北島委員は昭和30年4月の町議会議員選挙に立候補したため自然失職となった。
教育委員が任命制に
昭和31年6月「地方教育行政の組織および運営に関する法律」が公布され、(1)教育委員の公選制を廃止し、首長が議会の同意を得て任命すること、(2)教育長の任命について道教育委員会の承認を得ること、などが規定され、10月1日から施行された。
これにより、委員の定数は教育長を含めて5名で、任期は4年とされたが、初めての任命に限り2名が4年、その他の委員はそれぞれ、3年、2年、1年とし、その後は通常4年、中途退任者の後任委員は前任者の残任期間とすることなども規定された。したがって、毎年1名は更新される仕組みとなった。
こうした新法の適用によって、同年10月1日に町は議会の同意を得て、大島勝世・松本初次郎・古河四郎・池浦秦宜・加藤慎一の5名を任命した。そして互選により委員長に大島勝世、教育長に加藤慎一を選び、新教育制度の執行に当たることとなった。
落部村の教育委員会委員は、公選により、伊藤淳一・橋本直也・千葉 登・加我喜三郎の4名が当選、議会議員の中から徳田又雄が選挙され、教育長は村助役の奥田保男が兼務して新体制に対応した。そして、委員長には互選により伊藤淳一が就任したが、29年には加我喜三郎、30年には千葉 登とそれぞれ更迭している。なお、30年4月には伊藤淳一が村長選挙に立候補当選して欠員となり、また、議会選出の委員は、徳田又雄から吉崎芳造、大山勝悦へと交代するという経緯があった。
さらに、昭和31年10月の任命制による新教育委員会は、加我喜三郎(委員長)・愛山一二・皆川繁雄・牧野貞一・辻村美矩(助役で教育長を兼任)の体制で発足したが、翌32年4月1日の町村合併により3月限りで自然解消となった。
任命制以後の教育委員は次のとおりである。
古河四郎(31・10・1〜42・9・30) 伊藤慶三郎(47・10・2〜現在) 新明幸一郎(44・12・20〜46・10・31)
大島勝世(31・10・1〜36・9・30) 古沢房次郎(47・11・17〜54・3・17) 菅野きみ江(46・10・1〜47・7・31)
加藤慎一(31・10・1〜38・12・15) 坂田武則(54・5・4〜現在) 須田久助(47・10・2〜56・6・30)
白鳥 郁(34・6・16〜37・9・30) 池浦泰宜(31・10・1〜32・9・26) 馬場春江(47・10・2〜現在)
森 佐富(37・10・1〜41・9・30) 松木初次郎(31・10・1〜34・5・27) 阿部 悟(54・7・1〜現在)
與座梅子(41・10・1〜46・7・17) 徳田又雄(32・10・1〜43・9・30) 松崎忠行(56・7・1〜58・6・30)
鶴見清春(43・10・1〜47・9・30) 加藤孝光(36・11・4〜44・9・30) 水野 渉(58・7・1〜現在)
鈴木善治(46・10・1〜47・10・21) 石垣寿典(38・12・21〜47・9・30)
都築重雄(46・11・27〜54・6・30) 鈴木 優(42・10・1〜46・9・30)
なお、歴代委員長は、大島勝世・徳田又雄・加藤孝光・新明幸一郎・都築重雄・伊藤慶三郎であり、教育長は、加藤慎一・石垣寿典・須田久助・松崎忠行・水野 渉が任命され、現在にいたっている。
ひまわり学級の開設とその経過
昭和28年(1953)4月「国立八雲病院」が、結核患者の施療を主体とし、入院病床300を有する療養所に転換して「国立八雲療養所」と改称された。したがって、入院患者の中には多くの学齢児童生徒も含まれ、これら入院中の児童生徒は学業の道を絶たれることとなり、そのため休学となったり、場合によっては長く留年しなければならないという者も少なくなかった。
このような不幸な子供たちに対し、入院中にもできる限り所定の教育を行い、休学や留年という弊害を排除しようとして考えられたのが、特殊学級の開設であった。すなわち、32年6月にこの療養所内に八雲小・中学校の特殊学級「ひまわり学級」を設置し、療養所の第3病棟の3室を教室に当て、学齢児童生徒(当時児童37名、生徒9名)を八雲小・中学校へ転入の手続きをとらせて、それぞれの学校の児童生徒として授業を実施するというシステムによるものであった。
こうしてしばらく運営経過をみたあと、認可を得て38年12月に八雲小学校ひまわり分校および八雲中学校ひまわり分校と名付け、分校として正式に運営することになったのである。
しかし、40年4月に国立療養所がこれまでの結核療養施設から「進行性筋ジストロフィー症児」および「重症心身障害児(者)」を収容する医療機関へと性格転換が進められた。こうしたことから、その対象児童生徒もさらに広がって全道各地にまたがるとともに、児童数も急速に増加するようになった。このため町は、町立学校として維持することは適当でないという判断のもとに、道立移管について運動を続けた結果、翌45年4月に「道立八雲養護学校」として開校されることになったのである。これによって、町立の「ひまわり分校」は3月限りをもって発展的に廃校となったわけである。
学校給食センターの開設
従来各学校ごとに実施されていた学校給食事業を、センター方式としてこれを集中するとともに、八雲町内小中学校の児童生徒に対する完全給食を目指す「学校給食センター」の設置は、町教育行政にとって多年にわたる懸案事項であった。
このため町は、種々の調査を行った結果、昭和39年度に施行することに決定し、八雲中学校に隣接する用地482坪(約1590・6平方メートル)を買収して9月30日に工事入札を執行、腰高ブロック木造モルタル仕上げ230・18平方メートルの建物に、ボイラーほか厨(ちゅう)房用機械器具一式を備え、1日3000食を目途とする施設を12月に完成した。そして同月24日に、試験的に八雲中学校生徒991名を対象に、給食事業を開始した。さらに翌年1月25日第3学期から八雲小学校1429名に給食を実施し、本格的な事業を開始したのである。 こうして逐次体制を整備しつつ40年度中に浜松小・山崎小中・大新小・春日小の各校、41年度に山越小・同中・大関小中の各校に実施した。また、43年度には施設を拡大して給食範囲を広め、野田生小・同中・東野小・落部小・同中・栄浜小の各校、44年度に熱田小などと順次実施し、現在では全町の小中学校のすべてを対象に3200食を実施している。
学校寄宿舎の建設
広大な面積を擁する当町には小学校の数も多く、42年度には23校を数えていた。これらの小学校のうち辺地の児童は、中学校に進学するようになると通学距離が非常に遠くなり、特に冬期積雪のため通学不能となる場合もしばしばで、下宿生活を強いられる生徒もあった。
町では昭和42年度において、これら辺地の中学生の不便を解消して教育効果の向上を図るため、八雲・大関の両校へ通学する生徒を対象に寄宿舎を建設したのである。
八雲中学校寄宿舎は、32名を収容定員とするブロック造り平家建て400・63平方メートルで、校舎の西側に建てられ「恵雲寮」と名付けられ、大関中学校寄宿舎は、6名を収容定員とする木造平屋建て85・95平方メートルで「清心寮」と名付けられた。
さらに、44年度には野田生中学校生徒を対象に、15名を収容定員とする木造平屋建て133平方メートルの寄宿舎が、野田生小学校前に建てられ「雄峰寮」と名付けられた。
なお、これらの寄宿舎に入寮する生徒に対しては、特に居住費用については町が助成し、父母負担の軽減を図って利用を容易にするよう配慮してきたのであるが、設置当時に比べて学校周辺をとりまく集落の様相もしだいに変化し、各年度によっても異なるが、昭和52年度では恵雲寮19名、雄峰寮10名、清心寮2名の計31名が寮生活を送った。
昭和40年以降の学校統廃合
戦後、緊急開拓による入植者の増加のため、学校の新設も数校に及んだが、昭和30年代における高度経済成長政策の影響は、立地条件の悪い開拓地をはじめ既存農村地帯をも直撃した。つまり、離農者の激増、戸口の都市流出による過疎化現象をきたしたのである。このため、各学校の児童生徒の減少傾向が目立ちはじめ、極度の小規模校がにわかに多くなってきた。
また、道路交通事情の伸展をはじめとする一般社会情勢の変化も激しく、こうした背景のなかで教育関係者の間では、教育内容の充実・教育条件の格差解消・教育施設の充実整備という観点から、適正規模化をめざす学校統合が問題として取り上げられるに至った。
こうしたことから町教育委員会は、39年8月にその諮問機関として、町議会・校長・PTA関係者などによる「学校統合推進協議会」を組織し、積極的な調査研究を重ねた結果、統合第1号として学校改築の要に迫られていた久留米小学校を対象に関係者が協議のうえ、スクールバスによる送迎などを条件として40年3月限りで廃校とし、4月から八雲小学校に統合したのであった。さらにこれと並行して、児童生徒の激減という状況にあった上鉛川小・中学校についても話し合いが進められ、同じく4月から八雲小学校と八雲中学校への統合が実現した。なお、42年3月には鉛川小学校と上の湯小学校二股分校が廃校になった。
また、農村地帯からの離農が相次ぎ、47年3月に富咲小学校、同年11月に熊嶺小・中学校、48年1月に八線小学校と桜野小学校が廃校となり、さらに51年3月には熱田小学校、大関小学校夏路分校、野田生中学校桜野分校の3校が廃校となったほか、落部中学校統合校舎が建築されたことによって上の湯中学校もこれに統合されたのであった。
なお、これらと事情を異にするが、八雲鉱業株式会社の閉山によって44年7月に八雲鉱山小・中学校が廃校となり、また、翌45年3月に八雲小・中両校のひまわり分校が発展的に解消したのを合わせると、40年以降小学校9、同分校3、中学校4、同分校2、計18校が姿を消したのであった。
第2章 実業補習と青少年教育
第1節 概説
実業補習教育の創始
実業に従事しようとする生徒の教育に関する思想は、既に明治5年(1872)発布の学制の中に組み込まれていたが、制度的には容易に整わず、明治26年11月の文部省令「実業補習学校規程」の発布によってようやくその緒につき、さらに本格的な制度として見られたのは、明治32年2月に「実業学校令」が公布され、実業教育の分野における基本的な規程として整備されるに至ってからであるという。
これにより実業補習学校が実業学校の一種として定義されたのであるが、この種の学校設立は全国的にも全道的にもあまり進展を見ることがなかったため、文部省では35年1月に実業補習学校規程を改正整備するとともに、その趣旨を説明する訓令を発するに及び、道庁においても同年9月に「実業補習学校規程実施方法」を定め、その設置奨励に乗り出したのである。
それによれば、「各種の実業に従事し、または従事しようとする者に対して簡易な方法で、その職業に必要な知識技能を授けると同時に、普通教育の補習をする」という目的のもので、教科は「普通教育の補習、徳育、実業の科目」とし、教授時間について「小学校の教授時間外で生徒の修学にもっとも便利な時期を選ぶ」とすることなどを骨子とするものであった。
こうした勧奨を受けた村当局では、小学校の卒業生や学齢超過者が20名以上となる通学区を選んで設置する方針を立て、37年2月に村会の議決を経て、5月から山越内と大関の2実業補習学校をそれぞれ小学校に併設することとした。しかしその校則によれば、実業科目は農業とし、修業年限は3年とするものであったが、一週の授業時数は修身、国語、算術が各2時間、これに対し農業がわずか1時間という程度のものであった。兼務教員の報酬やその他の費用は原則として授業料(一人月15銭)で賄うこととされ、文字どおり簡易なものにすぎなかった。そのうえ39年11月には大関実業補習学校については校則を修正して修業年限を二か年に短縮(山越内実業補習学校については不明)するという状況であった。
その後途中の経過は不明であるが、他の地域においては青年会(団)の夜学会が行われつつあったものの、公式に実業補習学校への進展もなく、大関・山越内の両校も、ときの理事者に「実質ハ単ナル夜学機関ニ道ギズ」と言わせるほど低調であった。大関では実際には大正9年以来休校状態にあったので、高等国民学校開設直後の13年1月の町会において両校の廃止を決議したのである。
落部村においては、明治38年11月落部小学校に補習科を廃して「落部実業補習学校」を開設し、夜間の勉学とともに農業実習も併せて行い、大正11年4月開校に高等科が設置されるまで続けられていたが、詳細については不明である。
実業補習教育の展開
大正9年(1920)12月に実業補習学校の性格を時勢に適応させることを目的に「実業補習学校規程」が改正された。すなわち、実業補習教育の本旨について「小学校ノ教科ヲ卒へ職業ニ従事スルモノニ対シ職業ニ関スル知識技能ヲ授クルト共ニ国民生活に須要ナル教育ヲ為ス」と明確にし、併せて女子に関する規程が設けられる一万、同年8月には「実業補習教育費国庫補助要項」も定められて、その振興が要請されるようになったが、依然として不振であった。
こうした状況のなかで道は、大正11年9月に高等国民学校の設置を提唱したのである。これは「実業補習学校の本旨に照らして本道のようにこれに該当する青年が多数に上り、しかも積雪期の長い地方においては、その必要性を認め、冬期間の農閑期を利用して約四か月にわたる季節教育を施す高等国民学校の設置を促進し、その実現に努力してほしい」と訴えるもので、同月「高等国民学校準則」を布達した。12月には「実業補習学校補助規程」を定め、この準則による学校に対し基本的には設立者負担額の5割以内を補助することとしたのである。
高等国民学校の設置
本村町長は、この高等国民学校こそ八雲の実情に適合する教育施設であることを認め、道庁と調査打ち合わせを進めて同年11月7日の町会協議会で施設要領や経費予算関係を説明協議し、同月16日の町会でこの設置案件を満場一致で議決したのであった。
(議案第四号)
八雲高等国民学校設置ノ件
大正九年文部省令第三十二号実業補習学校規程ニ依リ、大字八雲村字砂蘭部ニ八雲高等国民学校ヲ設立シ大正十一年十二月一日ヨリ開校ス
この議決に基づく設置申請に対し、12月19日付けで宮尾長官から認可された。校舎は、元八雲片栗粉同業組合事務所(現、公民館敷地内)2階建て46・5坪(約153平方メートル)の建物を当て、初代校長は木村町長が兼務し、教員には伊藤直太郎(元、八雲小学校長)、内田文三郎(郡農会技師)を嘱託した。こうして、生徒数本科27名、初等科14名で発足し、12年1月6日に開校式を挙行した。このときの木村町長の式辞は次のとおりであった。
八雲高等国民学校(写真1)

式辞
町立八雲高等国民学校ノ設置成リ本日ヲ卜シテ開校ノ式典ヲ挙ク、抑々本校ハ実業補習教育機関ニ属シ、実業ニ従事スル青年者ヲ教養シテ確固タル国家観念ヲ与フルト共ニ実業上ノ智識ヲ得シメ依テ以テ常識品位ニ富ム中堅的人物ノ養成ヲ目的トシ当局ノ奨励補助ノ下ニ設置ヲ見ルニ至レルモノニシテ之ヲ一般実業学校ニ対比シ其ノ施設敢テ形式ニ累セラルコトナク極メテ実際的ニシテ特ニ小学校卒業後直ニ実業ニ従事シツツアル青年ヲシテ其ノ業務ヲ廃スルコトナク比較的容易ニ一層充実セル修養ヲ可能ナラシムル特質ハ本町現下ノ実清ニ稽へ最モ適応セル教育機関タルヲ信ス。惟フニ、全欧ノ情勢ハ千歳稀ニ見ルノ危局ヲ経テ今ヤ文化ノ戦ハ年ト共ニ活躍壮観ヲ極メ、列強競フテ之ガ籌画ニ汲々タリ、即チ義務教育年限ノ延長、補習教育義務制度ノ実施等、苟クモ人後ニ落チサランコトヲ期シ殊ニ公民教育ノ振興ニ至リテハ彼ノ丁抹国ノ如キ斯種教育ノ普及ハ為メニ著シキ農業ノ進展ヲ招致シ其ノ国富頓ニ増進シテ将ニ戦前ノ独逸ヲ凌駕スト伝ヘラル、此ノ秋ニ当リ如上列国ノ大勢ニ対応シテ倍々国運ノ伸長ヲ企画セントスルモノ就中青年ノ補習教育ヲ充実シ以テ人格完成ニ寄与スル施設ノ如キ洵ニ刻下ノ急務タルヲ認メスンハアラス、惟フテ茲ニ到レハ本校ノ使命ヤ重且大ナリト云フヘシ。況ヤ本道最初ノ試ミニ属シ而カモ渡島半島ニ於ケル設置ノ嚆矢タルニ於テヲヤ、望ムラクハ生徒諸士須ラク深遠完美ナル国体ノ渕源ヲ尋ネ常ニ本道開拓ノ聖旨ヲ奉体シ拮据勉励以テ本校設置ノ目的ヲ顕揚セラレン事ヲ之ヲ式辞トス
大正十二年一月六日
八雲町長 従七位勲八等 木村定五郎
こうして設けられた学校の実業科目は、八雲の実情や教員の関係から「農業」とし、初等科2年、本科2年に区分するもので、初等科は小学校尋常科卒業者で、実業に従事する13歳以上の者、本校には初等科を修了した者、高等小学校卒業者もしくは実業経験を有する15歳以上の者を入学させるものであった。第1学期(4月から11月まで)は実習と実地研究を行い、第2学期(12月から3月まで)は学校に集合させて学科を教授したのである。
しかしこの学校も、所期の目的どおり生徒を確保することができず、翌12年度の在籍者も総数で27名と振るわなかったので、14年1月の町会には早くも議員の建議案をもって「八雲高等国民学校ヲ町財政ニ鑑ミ大正十三年度限リ廃止セントス」という提案がなされ、これは否決されたものの、波乱含みの運営状況であった。
この間、大正12年9月に平山豊三が専任校長となり14年3月まで在職、そのあと11月に山本清道を迎えたが、昭和4年3月限りで専任校長制を廃止し、12月からは侯爵徳川義親(高等官四等待遇)を校長に委嘱した。また、専任1名、兼任1名の教員を配したほか、町内学識経験者およそ20名を講師に委嘱して運営した。なお、徳川校長の俸給は月額100円と定められていたが、その在職中は全額町に寄付されていた。
本校の教育方針は、学則で示されていたように、
「実業補習学校規程ニ依リ設立シ、実業ニ従事スル青年ヲ教養シテ確固タル国家観念ヲ与フルト共ニ、実業ニ関スル知識ヲ得シメ、兼テ常識品位アル中堅人物タラシムルヲ目的トス」
とするものであった。したがって、教育目的が実業に関する知識の習得にあることはもちろんのこと、青年の人格形成、徳性のかん養に力を注いだもので、当町の農村社会において、幾多の有為な人材養成に寄与するところは大きかった。
大正15年4月に「青年訓練所令」が公布されて、本校にも「青年訓練所」が併設という形で運営されたが、さらに昭和10年4月に実業補習学校と青年訓練所を統合する「青年学校令」が公布された。このため本校が、
(1) 全町から生徒を募集するものであること。
(2) 実業科目を農業に限定していること。
(3) 冬期四か月の農閑期利用の集合教育制であること。
(4) 初等科・本科を各2年とするものであること。
などの特異性から、青年学校となじまない点があったので、この措置について道当局と慎重に打ち合わせた結果、一般の青年学校と競合しない「専修科」だけをおくこととした。そして同年9月28日に町会の議決を経て、冬期四か月の農業科専修を行う「公立青年学校八雲高等国民学校」と改称し、ようやく命脈を保ったのである。
しかし、戦局が急を告げた18年4月には、青年学校の整備統合によってついに廃止されたのであった。
青年訓練所の設置
青年に対する教育施設として実業補習学校があり、一方では青年の修養団体として青年団の設置が奨励されつつあったが、大正15年(1926)4月に「青年訓練所令」が公布されて、青少年の教育機関として青年訓練所が並立されることになった。この青年訓練所は「青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムル」ことを目的とし、おおむね16歳から20歳までの男子を対象に4年間を教育期間とするものであった。しかしこの訓練所は、学校に兵式訓練を取り入れる意図から出発したものであるといわれ、科目は教練のほかに修身・公民科・普通科・職業科などに分け、しかも、ここで教練を修了した者には在官期間を約半年間短縮するというものであった。そのうえ、補習学校よりも簡易であり、教授時間も少なくという考え方に立っていた。
道庁においては、15年5月に「青年訓練所準則」や「青年訓練所規程施行規則」などを定め、その設置方を市町村に勧告した。したがって当町においてもこれに呼応し、町会の議決を経て八雲・山越内・黒岩・大関・上砂蘭部・久留米・山埼・野田生・常丹・奥津内・八線・赤笹の12訓練所を、それぞれの小学校に併設することを定め、7月1日を期して一斉に開設したのである。
落部村においては、落部小学校に併設する落部青年訓練所のほか、各小学校に併設されたと思われるが、詳細については不明である。
当時八雲町としては、「此事タル青年教育ニ対スル一新国策ニシテ我国文政史上画時代的意義ヲ有シ、其効果ハ一面ニ於テ国防ノ充実ニ寄与スルノミナラズ、国家産業ノ発展ト民力ノ充実ニ資スルトコロ甚大ナルベシ」(大正15年事務報告)と礼賛しており、その世相をしのばせるものがある。
なお、八雲町ではこの後昭和9年(1934)4月に鉛川青年訓練所が増設されているが、その運営内容については不明である。
青年学校への発展
実業補習学校と青年訓練所の二本立ての教育制度は、対象となる青年が二つの学校に在学する矛盾と、そのための教育内容上の重複調整など難点を解消し、さらに強力な青年教育を推進するため、昭和10年4月にこれらを統合した「青年学校令」が公布された。これは文部省と陸軍省の協力によってなったものであるという。
青年学校令は「男女青年ニ対シ其ノ心身ヲ鍛錬シ徳性ヲ涵養スルト共ニ職業及実際生活ニ須要ナル知識技能ヲ授ケ以テ国民タルノ資質ヲ向上セシムルコト」を目的とするもので、普通科(2年)・本科(男子5年・女子3年、土地の情況により男子4年・女子2年)を根幹とし、さらに研究科(1年以上)と専修科を配していた。学科は普通科男子では修身および公民科・普通学科・職業科・体操科、女子には男子の学科のほかに家事および裁縫科を課することとし、本科では、女子は普通科と同じであったものの、男子は体操科を教練科とする仕組みであった。
これらに基づく関係省令や訓令などが公布されたことにより、道庁では同年6月「青年学校令施行細則」や「青年学校学則標準」などを定めて市町村に令達した。
このような制度の改正によって、同年4月1日にこれまでの公立青年訓練所と公立実業補習学校は、この青年学校令により設置した青年学校とみなされることとなったが、その名称は一定期間中に変更しなければならないとされた。
このため町は、7月27日「青年学校名称学則変更ノ件」を町会に付議し、名称や学則を変更して8月1日付けをもって道庁長官の認可を受け、従来の青年訓練所をそれぞれ「八雲町立○○青年学校」と改称した。また同時に、実業補習学校規程によって設立した家政女学校も「公立青年学校八雲家政女学校」と改称され、また、変更を保留していた高等国民学校も、9月28日に町会の議決を経て「公立青年学校八雲高等国民学校」と改めたのである。
青年学校の義務教育化
昭和14年(1939)4月に「青年学校令」が改正されて、満12歳から満19歳までの男子に義務教育制が実施されることになり、14年度に普通科に入学するものから逐次義務教育とし、20年度で本科5年までのすべてが義務制となった。
このため道庁では、同年10月に「青年学校令施行細則」を定めるとともに、施行上の注意事項を訓達したことによって、当町においても青年学校の義務教育化か進められるようになり、義務就学者を就学させるべき青年学校として、従前の青年学校をこれに充てることにした。また、就学の便を考慮して、15年4月に八雲鉱山と野田生原に独立の青年学校を設置したほか、16年4月に上鉛川、17年8月には大新に八雲青年学校の分教場を設置した。
しかし、戦争の激化という時局を反映して、青年学校の場は強じんな体力の錬磨、勤労精神の高揚による積極的な生産活動および軍事教練の強化という方向に進んでおり、働きながら学ぶ青少年にとっては大きな負担であった。
昭和18年戦局がいよいよ決戦段階を迎えるに至り、これら青少年の訓育内容を一層充実させるという面から、全道的に青年学校の整理統合が断行されることになり、八雲町では4月6日町会に諮問し次のように5校に統合した。(落部村での対応は不詳)
八雲青年学校 八雲・常丹・大新・上砂蘭部・奥津内・久留米および高等国民学校を統合 黒岩青年学校 黒岩・山崎を統合
大関青年学校 大関・八線を統合
八雲鉱山青年学校 八雲鉱山・上鉛川を統合
野田生青年学校 野田生・山越内・赤笹・野田生原を統合、ただし、野田生原に分教場を設置
この青年学校は、軍事教練一本やりと言っても過言でないほどの教練に終始することになっていくが、終戦によって有名無実となり、自然消滅の形となって、制度的にも昭和23年3月をもって廃止された。
第3章 小中学校の沿革
第1節 栄浜小学校
恵海特別教授場の創設
江戸幕府が東蝦夷地を直轄することになった直後の享和年間(1801〜1803)には、既に5、6戸の和人が茂無部(現、栄浜)に定住し、漁業を営んでいたという。しかし、漁業の不振もあって戸口はあまり増加せず、明治20年(1887)ころになっても20戸足らずという状況であった。しかも、本村である落部に比較的近いということから、住民の間には地元に教育施設を設置しようとする積極的な姿勢はみられず、落部学校の設立以後およそ30年の長い間、学齢児童をこれに通学させていたのである。したがって、児童にとって大きな負担となったばかりでなく、出席率はおろか就学状況もきわめて悪かった。当校沿革誌によると、明治40年ごろの状況は
「通学距離近クモ三十余町ヲ越エ、暴風雨ノ日ハ大人尚歩行ニ苫シム。况ヤ七、八歳ノ児童ニ於テオヤ。到底通学シ能ハズ、欠席多ク停級ニノミ、空シク学齢ヲ超過シ、義務教育終ラザルモノ多ク」と記している。
このため「父兄之ヲ憂歎シ、特別教授場設置ノ念甚切ナリ」(同)とあるように、ようやく学校設立の機運が盛り上がり、40年10月地元に特別教授場を設立しようとする協議がまとまったのである。こうして時の落部小学校長兜伝五郎をはじめ、菊地松太郎・宮古善古・柳谷忠五郎の三評議、有志菊地松助らが、戸長岩間勝従に対し再三にわたって要請を続けた結果、運営経費の一切を地域住民が負担することを条件として、42年3月に村費から教員俸給の支出承認を得るに至り、翌4月1日を期して特別教育規程による「落部尋常小学校付属恵海特別教授場」を開設することになったのである。
しかし、ようやく開設したものの、校舎や備品の調達については容易なことではなかった。そこで住民が協議のうえ、取りあえず民家を借りて15坪(49・5平方メートル)の教授場に改造し、児童を入学させるときは保護者が机や腰掛けなどを負担するという苦労を重ねて、開設にこぎつけたという。当時の児童数は26名であった。この施設は粗末なうえ狭かったので、その年8月に他の民家を二か年の期限で借り受け、17・5坪(57・75平方メートル)の教授場に改造してこれに移転した。
2年後にはさらに校舎の移転を迫られることとなり、適地を選んで150坪(495・0平方メートル)の敷地を買い受け、資金には共有林の売却とにしん漁場貸付金などを充てたほか寄付金を集め、44年12月に24・5坪(80・9平方メートル)の新校舎を完成させたのである。この特別教授場は、当初は4年生までの児童を収容し、5、6年生の児童はこれまでどおり落部小学校に通学するという変則的なものであったが、大正5年度に5年生を、翌6年度に6年生をこれに移し、初めて全児童(当時53名)を収容する体制となった。
尋常小学校への独立とその後
金児童の収容体制となり、これまでの教授揚が必然的に狭くなったため、部落民はさらに協議のうえ、大正7年(1918)7月に敷地30坪を買収し、14・5坪を増築するなどの整備を進め8月に工事を完成した。こうして一応の体制が整った時点でこれらの施設を村に寄付することとして村当局と折衝の結果、翌8年2月の村会で採納議決を経てその経営管理いっさいを引き継ぐこととなった。そして同年4月に昇格して「公立茂無部尋常小学校」と改称されて独立し、6月に住民喜びのうちに開校式を挙行したのである。当時の児童教は66名であった。
その後、昭和に入って校舎移転新築の議が持ち上がり、昭和4年(1929)2月に長谷川信義から三反歩、宮古善吉から一反歩の寄付を受けて村有財産とし、同年5月に位置変更(現、「かもめ保育園」の場所)、改築認可を受けて工事着手、同年9月に1教室・教員住宅付設の新校舎(53坪余)を完成した。この当時の児童数は70名であった。その後児童数はしだいに増え、9年から12年までは80名を超えたことから教室は狭くなり、5、6年の高学年は落部小学校に編入して通学させた。
昭和16年4月に「茂無部国民学校」と改称され、児童数は105名に達したが依然として1教室体制で、わずかに教員住宅を切り離して職員室4・5坪を増築するにとどまる状況であった。
教育環境の改善向上
昭和22年(1947)4月学校教育法の施行にともない「落部村立茂無部小学校」と改称されたが、校舎は依然として1教室のままであった。
このため25年度(児童敬100名)1教室を増築して初めて2教室となった。そして32年4月の町村合併によって「八雲町立」と変更になったのである。
37年8月に地域住民は新校舎建築期成会を結成し、老朽校舎の早期改築を要望し続けるだけではなく、39年には校地一反歩を購入して町に寄付するなど、その建設に備えたのである。これに対応した町では、39年度において建築工事に着手し、その年10月に完成した。新校舎は、4教室に図書室・給食室などを設備した363・2平方メートルとなった。しかしこの当時で、児童数は60名に減少していた。
栄浜小学校(写真1)

その後、45年4月の字名改正により「栄浜小学校」と改称した。また、52年9月に開催された「全道へき地複式教育研究大会」の第11分科会場となったのを契機として、体育館(243平方メートル)の建設計画が進められ、52年4月に着工して同年8月に完成し、教育環境が一段と整備されて現在に至っている。一方、この時点で児童数は30名、56年には32名(4学級・教員7名)という激減ぶりを示している。
第2節 落部小学校
開成私塾の創始
明治6年9月に開拓使が各郡に教育所の設置を勧奨したころ、いち早く時勢を察知した総代相木慶太郎や地主代表宮川大吉らがその設置を提唱し、ときの村用係相本幾一郎と協議して東流寺留守居の直脇順教を教師に選び、明治7年(1874)3月東流寺に「開成私塾」と名付けて教育所を開設した。もとより私塾なので寺子屋式であり、漢籍の素読と習字を教える簡易なものであったが、これが落部村における教育機関の芽生えであった。
当時は順教のほかに相木幾一郎・相木慶太郎・相木七五三作・川上腎輔らを助教に当てたが、同年7月には順教が函館に転出し、後任を住職の藤 探道に依頼したものの、本務多忙のためその職を十分に果たせず、11月には金沢逢太郎と代わるなど変転が激しかった。また生徒も、開設当初は16名を数えたのであるが、翌年から10名以下となり、12年には6、7名を数えるのみとなるなど、草創期における教育普及の難しさを物語っている。
落部学校の設立
明治11年に簡易な教育をねらいとする「村落小学」の制度が施行されたことによって、各地に学校設立の動きが生まれ、同年3月隣村森村に学校が設立されたことに刺激を受け、「村民は森学校の設立を羨み本年中に此の村に於いても私立学校を立てんと頻りに希望の由……。」(函館新聞8月10日付)と報じているように、村内有志の間でにわかに学校設立の機運が高まり、校舎建築に向けて動き出しだのは翌12年2月であった。
相木幾一郎・相木慶太郎・宮川大吉・相木七五三作・星野順一郎ら有志が、本村の落部はもちろん野田追・茂無部の住民に対し、教育の必要性を説いて回った。また、時の第18大区戸長(当時森村にあった)菊地忠兵衛の助力を得て寄付金332円六〇銭を集めて建築計画を進め、敷地199坪(657平方メートル、大山造船所の西寄り地先海成り地)を求めて7月に着工、31坪(102・3平方メートル)の校舎を9月に完成させたのである。そして同年12月に福山の人准訓導三浦健次郎が「落部学校在勤申付侯事」と函館支庁学務係から辞令を受け、初の教員として赴任した。翌13年2月5日に多数の来賓や村民を集めて落成式と開校式を行い「公立落部学校」と名付けて児童28名を収容し公式に発足したのである。発足当初の学校の性格は「村落小学」に属し、上・下等5年のうち下等の5級2年半を修業課程とするものであったが、その直後の4月からは制度が改正されて「変則小学」と変わり、4年制となった。
学校の経営費用については、設立計画の進行と並行して12年4月に落部・野田追両河川の渡舟賃の収益から200円を充用する許可を受けて運営を図ったが、15年ごろには早くもこれでは足りなくなり、教育費に係る戸数割を課していた。すなわち、同年の戸数割では資力に応じて7等に区分し、一戸平均七銭二厘の割で100円を、ほかに受業料も3等に区分して一人平均十銭の割で36円を徴収し、渡舟収益の200円を合わせて336円として運営していた。
なお、本校の初の付属として野田追分校が設けられたのは、明治16年(1883)2月であった。
小学校への移行
明治16年4月「変則小学教則」の一部改正により、性格としては変則小学で変わりはなかったが、当校では初等・中等・高等のうち、初等科だけ6級3年を修学する学校となり、従来より修学期間が一か年短縮されると同時に「落部小学校」と公称するようになった。なお、校舎は同年12月の暴風雨によって全壊したため、臨時に相木慶太郎宅や八幡社を教授場に充てて急場をしのぎ、翌17年10月に旧漁業協同組合事務所の裏側に再建して供用を開始した。しかし残念ながらこのときの規模などについて、明らかにする史料は残されていない。
明治20年4月に教則の改正と学校の等科指定により、その性格は更に変わって「小学簡易科」となった。これは修学年限は同じく3年制ながら、授業時数や教科目の簡易化が図られたのである。
明治22年に国道が開通し、落部・野田追の両河川にも橋が架けられたため、学校運営費の重要な財源としていた渡舟収益金がなくなったので、翌23年から村の賦課金をこれに充当して運営するようになった。また、村の財政がその負担に堪えないという理由で、野田追分校を閉鎖(26年6月まで)して本校に通学させたこともあった。
尋常小学校時代
明治28年4月から「小学簡易科」が廃止され、小学校の課程が尋常科と高等科の2種に区分されるとともに、尋常科は一類と二類に分け、しかも、同類の中でも修業年限に差異を設ける制度になったのである。その結果、特に記録はないのであるが、東野小学校の沿革誌によって類推すると、当校は第二類に属し、修業年限を3年とする学校に指定されたようである。
なお、制度的にはこのときから「落部尋常小学校」と呼ばれることになった。
明治33年(1900)8月改正による義務教育年限の一率4年制への移行にともなって修業年限を改め、翌34年4月に訓導小山熊治が初代校長の発令を受け、教育機能の充実が図られた。なお、同年9月には2年制の補習科が設けられ、38年11月の落部実業補習学校(3年制)の併設まで存続した。
このころになると、各地域の開発も進み戸口も増加したので、明治34年には蕨野分教場の設置をはじめ、42年白滝、恵海特別教授場、大正2年上の湯特別教授場などと開設の素地が作られつつあった。こうした情勢を背景として当校においても、明治35年度の2学級87名に対し、38年度には154名、39年度には186名に達したのである。このため、39年に校舎建築の認可を受けて増改築に着手し、場所を現在の関口商店付近に選定し、1413坪(約4663平方メートル)を求めて同年12月に143坪(約472平方メートル)の新校舎を完成させ、3学級編成として移転したのである。
しかし、41年4月には尋常科の修業年限が六か年に延長されるとともに、移住者の増加や就学率の向上などの要因が重なって児童教も増え続け、大正5年には250名に達したので、翌6年4月から4学級とし10月に1教室を増築した。
高等科の併置から国民学校まで
大正11年(1922)4月に実業補習学校を廃して2年制の高等科を併置して「落部尋常高等小学校」と改称し、教育体制が一段と強化された。15年6月には生徒数の増加(尋常科270名、高等科45名)にともない、1教室を増築してこれに対応した。
しかし、昭和3年(1928)4月には、尋常科で300名(6学級)を超え、高等科で80名(1学級)を数えて、これまでの校舎では収容しきれない見通しとなったため、同年2月開会の村会において移転増改築について議決された。そして、校地(現在地)一町五反歩(約1万4850平方メートル)を買収、6月下旬に起工し、8月に旧校舎326坪余(約1076平方メートル)を移設したあと、9月30日には増築分を含めて完成したのである。新校舎は木造平屋建て8教室と屋内体操場などを擁し、412・8坪余(約1362平方メートル)というものであった。その後、普通教室・裁縫室など必要に応じて随時増築され、設備も整えられていった。
昭和16年2月9日午前6時10分、前日行われた料理講習後における火鉢の残り火から、校舎が全焼するという災禍に見舞われた。このため、役場の議事堂とその付属建物や落部漁業組合の事務所を仮教室に充て、8学級編制により二部授業を行って応急の措置をとったのである。この直後の4月には「落部国民学校」と改称されたが、校舎の復旧は村を挙げての念願であり、そのため基礎工事前の校地整理・土盛り・地ならしなどの作業は、全村民の労力奉仕をもって行われた。工事は同年9月に着工して翌17年7月に完成の運びとなり、その月から全児童をこれに移して授業を開始した。新校舎は11万8978円余を費やし、総面積555坪(約1832平方メートル)で10教室、120坪(約396平方メートル)の体育館を備えた堂々たるものであった。この当時の児童数は初等科で431名(6学級)、高等科で104名(4学級)を数えていた。
現体制に至るあらまし
昭和22年(1947)4月に「落部村立落部小学校」(464名・10学級)となると同時に高等科を廃し、5月から落部中学校を併置した。そのため体育館の半分を仕切って4教室を造っただけではなく、下級学年で二部授業を行うなど不便が続いた。25年6月に中学校が独立校舎へ移転し、27年に体育館の間仕切りが解消されるとともに、2教室と東西の玄関が増築された。
32年4月の町村合併により「八雲町立」となり、その後も幾多の変遷を経て、37年10月に体育館の改修とステージや用具室など26坪(約86平方メートル)の増築、41年12月に音楽・理科の特別教室96坪(約317平方メートル)の増築、49年に東側便所の新設などを主なものとし、特に51年7月には学校プール(アルミ製・長さ25メートル・幅10メートル)が工費3355万円をもって新設された。
さらに、本校舎は資材調達に不自由な時代に建築されたもので、既に40年を経過し、老朽化を来し危険度も増加してきたため、昭和55年には本校舎改築の議が持ちあがり、9月の第3回定例会において、落部小学校校舎改築事業費が議決され、10月21日起工式が行われた。
焼失した落部尋常高等小学校(写真1)

改築工事は55、56年の二か年の継続事業で本校舎鉄筋コンクリート2階建て2236平方メートルを完成し、引き続き57年度で体育館を建築する計画で進められ、56年10月一、二期工事、総額4億1315万6000円をもって教室・図書室・理科教室・スタジオ・放送室・音楽室・特別活動室・職員室・水飲場・便所などが建設され、引越しを完了したのである。
第三期工事として57年度に体育館(760平方メートル)の建設が進められ、11月完成をみるに至った。
当校は、一時600名前後の児童を数えたのであったが次第に減少傾向をたどり、41年422名、45年313名、50年289名というように推移し、56年現在では265名(7学級・教員10名)という状況である。
旧落部小学校(写真1)

落部小学校(写真2)

第3節 落部中学校
新制度下の対応
昭和22年(1947)3月31日法律第二六号で公布された「学校教育法」は、即日施行され、いわゆる6・3制教育が義務化されたのである。
このため各市町村とも新たな中学校を設置することとなったのであるが、当時の国内情勢としては戦後の混乱虚脱と経済危機の中で、財政は極度にひっ迫し、資材欠乏高騰の最悪の条件下におかれていた町村にとって、校舎の新築は全く不可能な状態であった。
しかし新学制の実施により、22年5月1日落部小学校3教室を仮校舎とし、初代校長に落部小学校長小林吉郎兵衛が兼務発令され、落部・茂無部・上の湯・野田追を通学区域とし、生徒数172名(1、2学年のみ)3学級編成で発足、新憲法実施記念日の5月3日小学校において開校式を行ったのである。
こうして新校舎の建築に迫られながらも、財政事情が許さず、とりあえず小学校体育館に間仕切り4教室を設け、4学級編成(60坪=198平方メートル、工費50万円、内村民寄付45万円)をもって11月30日、仮教室に移転して授業が続けられたのであった。
独立校舎と分校の設置
昭和22年11月30日、落部小学校体育館に仮教室を設置すると同時に、遠距離通学生(野田追地区方面)の通学難緩和のため野田追小学校に分校を併設し、生徒数32名をもって「落部中学校野田追分校」を設けた。翌23年4月初代専任校長として蛯子幸三が就任し、24年4月上の湯小学校に「落部中学校上の湯分校」を併設、生徒数27名をもって開校したのである。
その後、海外からの引揚者などの関連もあり生徒数も次第に増加の傾向を示し、応急的に設置した仮教室も狭くなり、新校舎の設置は急を要する重要課題となり、昭和24年から29年にわたる四次六か年をもって、独立校舎を新築することとした。
第一期工事は4教室・玄関・便所など120坪(396平方メートル)を工費113万円で24年12月完成、小学校仮教室から1学級を残して4学級が新校舎に移転、翌25年6月には第二期工事、3教室・職員室・宿直室・玄関・教具室など158・25坪(523平方メートル)が工費148万余円で完成、全学級新校舎に移転完了、26年11月には第三期工事として屋内体育館83坪(274平方メートル)を工費179万円で、29年には第四期工事として2教室・家庭科教室71・75坪(237平方メートル)を工費197万余円をもって完成し、総坪数433坪(1429平方メートル)の独立新校舎が完成したのである。
校勢の推移
独立新校舎完成の昭和29年4月には、生徒数302名、9学級編制の中学校となり、その後、給水施設、グラウンド整地・放送設備など環境整備が進められ、32年4月落部村と八雲町の合併により「八雲町立落部中学校」と校名を変更し7学級編制となった。
35年ころから生徒数は漸増傾向を示し、36年には8学級編制、生徒数316名、38年には348名の在籍生徒を数えるに至った。39年には技術科教室および付属廊下63坪(208平方メートル)が工費295万円をもって新築され、自転車小屋・更衣室などの建築が進められ環境整備が行われ、42年11月には開校20周年記念式を挙行、43年11月からセンター方式による学校給食が開始され、12月には理科特別教室が落成するなど教育効果の向上が図られたのである。
こうして、年々校舎の整備および改修工事が進められてきたのであるが、本校舎建築以来20年余を経過し、しかも資材の入手困難な時代に建築された関係もあり、要改修箇所も増加するばかりの状態となった。
またこの間、41年には教員住宅3戸、翌42年には1棟2戸が新築されるなど教員に対する住宅難の緩和が図られたのである。
校舎の改築
本校校舎は前述のとおり、戦後間もない昭和24年資材不足の混乱時代に建設された木造建築で、時代を経るごとに老朽化したため、昭和46年11月に落部中学校建設促進期成分が設立され、校舎の改築
について調査研究が進められた。また上の湯中学校の落部中学校への統合問題も併せて検討され、51年度統合が決定されたことにより、校舎の改築問題が急速にとりあげられることになった。
このため北口町長は昭和49年第1回定例会の町政執行方針の中で、落部中学校校舎を八雲南中学校(仮称)として改築に着手したい考えのもとに、当初予算に設計調査費を計上する旨を述べ、7月開会の臨時会において49年から二か年の継続事業として建設工事に着手することを提案、議決を経て8月第一期改築工事に着工、翌50年12月第二期工事を完成したのである。
工事は株式会社松原組ほか2社によって行われ、第一期工事として本校舎、鉄筋コンクリート造り2階建て、建築面積1080平方メートルを、第二期工事で校舎の半分969平方メートル、鉄骨造体育館989平方メートルを総工費3億7000余万円をもって完成させたもので、新校舎は全校内電気暖房装置を施工して生徒の健康管理面を配慮するとともに、理科室・音楽室・金工木工室・調理室・美術室・図書室などの特別教室や放送設備など近代的な教育設備を有する町内有数の学校として完成したのである。
落部中学校(写真1)

こうして昭和51年4月から、中学校再編成計画に基づく落部、上の湯両中学校が統合し、新生「落部中学校」として発足することとなった。56年5月現在の生徒数は135名、4学級編制である。
第4節 上の湯小(中)学校
特別教授場の設置
上の湯地区は落部市街から落部川上流に10キロから15キロメートル離れ、この沿線の平野地を開拓して古くから入植者があった。大正元年(1912)には戸数21戸となり、これら入植者の子弟に対する教育機関設置は、住民共通の大きな念願であった。このため大正元年10月に住民は、学校敷地として犬主32番他の一反五畝(約1485平方メートル・佐々木幸七所有)を村に寄付することとし、戸長岩間勝従に対し学校設置の陳情を続けたのである。その結果、村の評議会において落部尋常小学校付属上の湯特別教授場として設置されることとなり、翌2年4月に15坪(49・5平方メートル)の、掘立・草ぶきの校舎を、住民の労力奉仕によって建築した。そして同月25日に代用教員北村文一が任命され、5月1日から授業を開始した。開設当時の児童数は、男12、女4の16名であった。しかし当時は、学校設備が皆無であり、児童が入学する際は、各自が使用する机や腰掛け類を必ず持参しなければならないという状況で、こうしたことは大正11年まで続いたのである。
このように地域住民の奉仕によって建設された教授場は、大正10年には児童数が40名に達し、校舎も狭くなると同時に腐朽度もはなはだしく、改築の必要に迫られた。このため12年に村会の議決を経て、木造まさぶき平屋建て40坪(132平方メートル)の校舎を建築し、その後昭和8年に改築というように、教育環境の改善が図られていった。
小学校時代
昭和12年(1937)4月に「落部村立上の湯尋常小学校」に昇格し、同年6月には青年学校令による青年学校を併置した。また同時に、隣接地に三反八歩(約2996平方メートル)の学校敷地と実習地の寄付(高木福所有地)などもあり、校地は六反四畝二四歩(約6415平方メートル)となった。
昭和16年小学校令の改正により「上の湯国民学校」と名称を変更し、翌17年4月からは高等科が設置され、児童生徒数は61名を数えるに至った。
戦後の状況
戦後、6・3制が施行されたことは前に述べたとおりであるが、当時直ちに中学校に充当できる設備はなかったので、昭和22年5月に落部中学校で開校式を行い、この上の湯地区も落部中学校の通学区域に編入されたのである。しかし通学距離が遠いため、翌23年4月からは上の湯小学校の中高学年の教室で授業を行うこととなり、24年3月に「落部中学校上の湯分校」として認可された。この間、中学校の授業を小学校教諭が担当するという、不規則な状態であった。
昭和24年4月には分校で入学式を行い、この時点で生徒数は28名で、校舎は村有建物(集乳所)を仮校舎として使用することとなった。25年10月には校舎60坪(198平方メートル)が新築されて移転した。これと同時に「上の湯中学校」として独立認可となり、小学校長佐藤富雄が中学校講師に兼務発令され、27年10月校長に就任した。
昭和32年4月の町村合併により「八雲町立上の湯中学校」となり、以後中学教育の場として電化・水道・TV学習・学校給食・校長住宅などと、逐年環境整備が進められてきたのである。
上の湯小学校(写真1)

しかし時代の推移とともに過疎化の影響を受け、開拓農家ばかりでなく既存農家も離農が相次ぎ、生徒数も次第に減少しはじめ、46年には16名となった。こうしたことから、当時進められていた学校統合問題が取り上げられ、町教委・学校・PTAにおいて検討が重ねられた結果、49年1月に統合特別委員会が発足し、積極的な調査研究がなされたのである。これにより51年4月から落部中学校と統合することが決定され、生徒は町が配置するスクールバスによって通学することとなり、同年3月をもって「八雲町立上の湯中学校」を廃校したので小学校だけとなり、教員3名、児童数7名という小規模校になったのである。
第5節 蕨野小学校
寺子屋教育の創設
明治25年(1892)に愛知県東春日井郡松河戸村の人長谷川円右エ門が、野田追(通称市岡地区)の奥地にあたる奥蕨野一帯の適地を調査し、矢野喜三郎、長谷川桑次郎、長谷川義次郎らと共同して土地の払い下げを出願するとともに、その年直ちに現地に入植し、畑八反歩(約80アール)の開墾を行った。これがこの地方の開発の端緒であり、記念すべき年となった。払い下げが実現したかれらは、翌26年4月にはいち早く小作人を募って猪子作次郎、生田時次郎ら10戸(あるいは8戸ともいわれている)を入植させたのをはじめ、27年にはさらに5戸を入れて開拓の基礎を作っていった。
中学校統合記念碑(上の湯)(写真1)
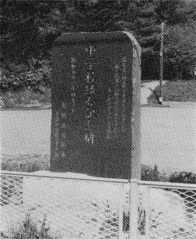
こうしたことから当然のように入植者たちの子弟の教育が問題となってきた。この地帯は既に設立されていた野田追分校の通学区とされていたが、あまりにも遠距離でありそのうえ未開地でのこともあって、児童の通学は困難と危険をともなった。そこで住民は協議のうえ、移住人のひとりである加藤文次郎を教師とし、27年11月に長谷川円右エ門宅を教場に寺子尾式でしかも夜学の私塾を開いたのが、この地方における教育のはじまりである。
また、翌28年4月には養鶏を営んでいた下山清吉が、私有の甘蔗(かんしょ)製造小屋を改造して教場をここに移し、自ら教師を引き受けて私塾を開いた。しかし下山は養鶏のかたわらでもあり、生徒ひとりにつきわずか黍(きび)二升の月謝という約束のもとで、苦しい教育が続けられたという。
そのためであったか、または当然村が果たすべき教育機関設置の機が熟さなかったための特別な援助措置であったかは不明であるが、明治30年4月から年60円の補助金が戸長役場から交付されていたという。33年5月に下山が野田追分校の雇教員を拝命し、月俸8円を支給されたこととなっているが、当時はこの私塾が正式に分教場として認可になる以前のことであり、発令のあとであっても私塾にそのまま在勤するという形式は到底考えられないことであり、のちの記録と関連させて推察してみても、この時期で一応私塾が閉鎖され、児童は野田追に通うようになっていたのではないかと考えられる。
公設分教場の開設
寺子屋教育を開始してから7年を経過した明治34年(1901)2月20日、落部尋常小学校付属蕨野分教場となり、正式な教育機関として公認されるに至った。そして分教場主任には当時すでに昇格していた野田追尋常小学校の代用教員菊地 登が当てられ(兼務か)、受持教員に下山清吉が配されるという体制であった。
しかし、落部小学校を本校とするはずのこの分教場の運営経緯については、むしろ東野小学校の沿革誌に詳しく記されており、34年2月の項に「通学不便ノ為メ冬期間蕨野分教場ヲ設置ス」となっている。また、下山(34年7月転出)の後を継いだとみられる同校一教員の履歴の一項に「冬期間蕨野ニ在勤セリ」とあるところから推察すれば、実質的には当時野田追尋常小学校に直属し、しかも季節的な分教場であり、その他の期間は開校に通学させていたものと思われる。しかし、これらの事情を解明する史料は残されていない。
分教場の建物は依然として旧来のものを充当していたので腐朽が激しく、使用に堪えられなくなったため、36年6月に住民から寄付を募って民家を買収し、一教室12坪(約40平方メートル)に住宅を併設する校舎に改造した。
簡易教育所から小学校へ
校舎改築直後の明治36年7月、簡易教育規程による「蕨野簡易教育所」となり、ようやく通年制の教育機関となった。しかし専任の校長は置かれず、野田追やときには落部の校長が兼務していた。
通年制の独立校となり児童も増加したので、大正5年(1916)9月に現位置の村有地1200坪(約3960平方メートル)を校地に定め、62坪(約205平方メートル)の校舎を新築して機能の充実を図った。校舎は一教室20坪(約66平方メートル)に所要施設を設けるとともに、12坪の教員住宅を併設したもので、これまでに比べると相当の拡充であった。なお、この建築に当たっては、当地の武農場からの用材と住民から400円の寄付があり、このほか労力奉仕が寄せられたのであった。
その後、改正特別教育規程により簡易教育所という名称が廃止され、これらが尋常小学校と改められることになったことにより、大正6年4月に「蕨野尋常小学校」と改称された。当時の児童教は67名に達していた。なお、このときも校長は兼務であり、専任校長が発令されたのは昭和7年4月になってからであった。
小学校独立から現在まで
大正6年に小学校として独立したのであるが、このころになると下二股地区へ造材夫として移住するものも多くなり、これらの子弟の入学もあって児童数は70名を超えた。
さらに、昭和6年(1931)には94名に達したので教室を増築した。そして翌7年に専任校長として伊藤祐美が就任した。しかし、その後は次第に児童数が減りはじめた。
8年には野田追青年訓練所蕨野支所が独立して「蕨野青年訓練所」となり、小学校に併置された。
16年4月の学制改革で「蕨野国民学校」と改称し、さらに戦後の22年4月「蕨野小学校」と改められた。
29年には教員住宅を新築し、翌30年創立50周年記念式典を挙行したのである。32年4月の町村合併によって「八雲町立蕨野小学校」となった。
38年9月には校舎も建築以来46年を経過したため、老朽校舎として認定され、76・75坪(約253・27平方メートル)の校舎を開場建設(株)の請け負いにより、工費370万円(付帯工事として石炭庫兼物置の移転改築を含む)をもって、わらび野139番地に新築、さらに教員住宅2棟も併せて完成し、10月移転したのである。
また、辺地校の教育活動として、39年に旧校舎の廃材を利用した鶏舎を造り、児童に飼育させてその収益を修学旅行の費用に充てたり、42年からはミルク給食を自給自足による完全給食にするなど、ユニークな活動が続けられたのである。しかしこの給食は、52年4月には町給食センターから受けることとなり、自校給食10年の歴史を閉じたのである。
児童数の推移をみると、大正年代では60名前後が続き、昭和6年には94名を数え、11年までは再び60名前後を維持してきたのであるが、12年以降はしだいに減少をたどり、20年代に入ると20名前後になり、町村合併時点の32年は29名であった。その後は再び増加を示したものの39年から漸減し、43年には一けたとなり、56年にはついに1名という超ミニ校となって、校長と担任教師の2人によるマンツーマン教育が行われている。
蕨野小学校(写真1)

このため、遠足・運動会・学芸会などの学校行事は、隣接の赤笹小学校と合同で実施しているほか、集合学習などを行っている。
第6節 東野小(野田追中)学校
分校の創設
かつて野田追場所と呼ばれ、あるいは野田追村と呼ばれるなど、旧落部村の総称名とされるほど中心集落としての存在を誇った野田追ではあったが、ここに近代開発の手が差し伸べられたのは、明治14年(1881)に徳川農場の野田生牧牛舎設立による乳肉兼用牛の飼育が開始されたことなどによって、入植開拓が逐次進められるようになってからである。
したがってこの地域は、明治13年に落部学校の創設に当たっては地域住民も寄付金を拠出し、これに子弟を通学させるという方途を講ずるにすぎなかった。しかし、戸口の増加にともなって児童の遠距離通学が問題となり、地元に学校設立を望む声が自然に高まった。こうしたことから村内協議に持ち込まれた結果、民家の借り上げによる仮教場ながら「落部学校野田追分校」が設置され、この地で初めて授業開始の道が開かれたのは、明治16年2月のことであった。こうして翌17年寄付金を集めて12月に野田追2番地に22・5坪(約74平方メートル)の校舎を建築し、児童20名を収容して軌道に乗せたのである。
閉鎖と再開
分校の運営費は、野田追川の渡舟賃の収益の中から130円を充当し、このほか不足分は戸賦金で賄うこととしていた。しかし、明治22年末に国道が開通して渡舟事業が廃止され、翌年度からは落部学校
とともにその収入が全くとだえることとなったので、分校の運営は苦境に立たされることになった。こうした情勢の変化は、戸口の少ない地区はもちろん、財政事情の苦しい落部村にとっては大きな打撃であり、村内協議の結果23年から野田追分校を閉鎖し、再び児童を落部本校に通学させることとしたのである。
しかし徳川家開墾地では、明治21年の士族移住を最後に小作経営に切り換え、積極的に小作人の受け入れを進めたことにより、25年に24戸の入植者があり戸口は再び増加してきた。このため、子弟の教育問題が再度協議され、翌26年6月からあらためて分校を再開することになった。なお、この当時の児童教は既に45名に達しており、一部は対岸の野田生からも通学していたという。
昇格独立の前後
明治28年4月に本校である落部小学校が尋常小学校と改められたことから、当校も自動的に「落部尋常小学校野田追分校」と改められ、第二類、3年の履修校に指定された。さらに33年8月の制度改正によって分類が廃止され、修業年限がすべて4年制になるなど変遷が続いたが、この間児童教の増加も著しく同年12月に昇格して「野田追尋常小学校」となったのである。
また、この昇格独立を前後する時期に、児童の増加と通学区域の拡大によって校舎の移転改築について協議されていたが、徳川農場から牧牛舎跡の建物と土地1500坪(約4950平方メートル)の寄付を受けることとなった。これにより計画は順調に進み、現校地内に2教室と当時としては珍しい体育館35坪(約116平方メートル)を配した合計113坪(約373平方メートル)の校舎を新築落成したのは34年9月のことであった。新校舎の移転と同時に2学級編制(児童数96名)に拡充され、併せて補習科も設けられたようであるが、その詳細については記録に乏しく不明である。
校勢の拡充期
明治41年4月に修業年限が六か年に延長され、戸数増もあって児童数の増加が進み、44年度に106名に達し、さらに大正5年度(1916)には122名を数えるに至った。こうした傾向はなおも続いたので1教室を増築し、9年4月に3学級編制としたのであった。しかし、この直後に訪れた農業恐慌によって多数の離長者が続出し、戸口の減少を招いたことにより児童数も120名前後に落ち込み、12年4月から再び2学級編制に縮小されたが、それ以後はしばらく現状維持を続けていた。一方、校舎も老朽化して修繕を要する状態となっていたため使用上の便宜を考慮し、昭和4年(1929)9月に同じ校地内に移転のうえ改修工事を行った。
昭和16年4月に「野田追国民学校」と改称、初等科6年の履修校とされたが、翌17年4月から2年制の高等科を併置して1学級を増設し、学校機能の拡充を図った。
戦後の拡充期
昭和22年(1947)4月の新教育制度施行によって「野田追小学校」と改称し、11月「落部中学校野田追分校」が併置され、これまで落部中学校へ通学していた生徒が分校へ通うことになった。しかも23年6月には小学校で3学級編制となり、中学校も正常化するにつれて教室の不足を末したりである。そこで翌24年11月に住民から寄付を集める応急措置により、中学校校舎として2教室など57坪(約188平方メートル)を増築し、翌25年4月に「野田追中学校」として独立のうえ、2学級を編制した。
しかし旧来の小学校校舎は、老朽化して早急に改築の必要に迫られていたので、村で31年度から、二か年の継続事業をもってこの改築事業に着手し、32年2月に普通教室3、特別教室1など合わせて109・75坪(約362平方メートル)の第一期工事を完了した。たまたまこの年4月に村は八雲町と合併したため、これを引き継いだ新生八雲町は、残りの工事である職員室や図書室などの付帯施設57・5坪(約190平方メートル)と体育館60坪(約198平方メートル)の建築を第二期工事として施行し、33年2月に全工事が完成した。
東野小学校(写真1)

昭和33年には在籍児童教が170名を記録したのを頂点として、その後は減少傾向をたどり始めるが、翌34年4月の学級編制基準改正によって4学級編制(在籍165名)となり、質的向上が図られることとなった。翌5月には併置の中学校が野田生中学校と統合したため再び単独校となり、さらに38年4月には、児童教は137名と減少しながらも、5学級編制、配置教員7名となったのである。
校勢の現況
昭和30年代後半に顕著となった過疎化現象は、児童数の急激な減少を招き、40年には97名となり、さらに42年に76名、44年に61名という状況であった。しかしそれ以後は、小規模ではあるが安定した校勢を維持しながらも、47年4月からは3学級編制となった。
45年4月に旧落部村地内の字名地番改正によって「東野小学校」と改称し、通学区域も東野全区と旭丘の一部に整理され、学校所在地も東野471番地となった。昭和56年における児童数は55名(4学級、教員8名)である。
第7節 野田生小学校
簡易教育所の開設
野田生地区には徳川家の所有地が多く、明治12年(1879)徳川家開墾試験場では、この土地を利用するため経営に着手した。当時愛知県からの移住者が多く年々増加し、25年ごろは戸数も2、30戸を数えた。開墾試験場では25年に有限責任八雲共立商社野田生支店(現在の長屋宅付近)を設置し、住民に米穀や雑貨などを供給していた。
こうした移住民の子弟たちは、開墾試験場の杉立正義を会長とする青年会に集まってお互いに学習をし合ったり、野田生の龍穏寺(当時は現野田生2区にあった)住職昼間魯宗のもとに通って教育を受けていた。
こうした不便な教育状況を憂慮した村会議員河原友二は、教育所の設置を主唱し、明治35年(1902)の第1回村会に建議した結果、同意を得て簡易教育所を設立することとなったのである。これにより、大木平・柏木・野田生の3地区の頭文字を取って「大柏野簡易教育所」と命名し、校舎は共立商社野田生支店の倉庫を模様替えのうえ、同年11月3日に開校式を行ったのである。この校舎の位置は長屋宅のそば(旧野田生劇場)で、その後小学校に昇格したとき廃止された。これが野田生小学校の創始であり、ときの教員は菅常次郎であった。
小学校時代
教育所を設立した翌年鉄道が開通し、入植者も増加して児童数も増えたため、39年7月大木平に「大柏野簡易教育所付属大木平特別教授場」を設置して通学区域を分離した。
41年には簡易教育所が教育所に改められ、次いで43年8月には「付属野田生原特別教授場」を設置して分離した。また校舎も狭くなったため同年12月に現位置(野田生462番地)を選定し、土地所有者である徳川家から学校敷地として903坪(2980平方メートル)を永久無償の借用(大正4年全地の寄付を受ける)を受け、翌44年に60・5坪(約200平方メートル)の校舎と22坪(72・6平方メートル)の教員住宅を新築、1月「野田生尋常小学校」と改称して移転した。初代校長には山本雄八郎が任命されて7月に赴任した。児童教は229名で、本校2学級、付属特別教授場2という体制であった。
その後児童教が増加したため、大正3年(1914)に教室と廊下を増築して3学級編制とし、昭和10年(1935)には249・5坪(823・35平方メートル)に及ぶ大規模な増改築を、工費8972円80銭(うち地区負担750円)を投じて施行し、青年学校も併置した。
しかし当時の父兄の間には、働きながら学ぶという青年学校よりも、普通学科に重点をおく高等科に進学させようとする機運が強く、小学校を卒業した児童のなかには八雲の高等科まで通うものもあった。このため、11年には高等科の併設を町に願い出たが、町会は財源の困難を理由に、賛成11、反対12をもって否決したという経緯もあった。
こうしたことを経ながらも、住民は野田生教育後援会を組織してさらに強く町に陳情を繰り返した結果、翌12年に高等科が併置されることとなり、野田生小学校の校舎40・75坪(約134・5平方メートル)を増築し、高等科の在籍54名を収容して野田生尋常高等小学校と改称、教育効果の向上が図られたのである。
昭和16年小学校令の改正により「野田生国民学校」と改称すると同時に青年学校は廃止され、初等科6年、高等科2年の編制となった。
戦後の状況
昭和22年3月に教育基本法および学校教育法が制定され、いわゆる6・3割となり、国民学校を廃して小学校とし、別に新制の中学校が設置されるようになったことは、教育制度の変遷で述べたとおりである。
これにより小学校は「野田生小学校」、中学校は「八雲中学校野田生分校」として新たな制度に対応したのであった。翌23年に分校は独立して「野田生中学校」となって小学校に併置され、校長は小学校長高本正一が兼任発令された。24年には小学校の北側に中学校の新校舎が建設されて独立移転した。
小学校は、その後36年8月に増改築工事が行われ、37年に体育館・廊下・職員玄関など348平方メートルが完成した。そして11月の開校60周年記念式典に併せて落成式を行った。
野田生小学校(写真1)

さらに、42年には特別教室として、音楽家・理科室・準備室・廊下など312平方メートルが新築された。
昭和56年5月現在の児童数は91名で、6学級編制である。
第8節 野田生中学校
新制度下の中学校
昭和22年の新制度により、八雲中学校野田生分校として発足した当校は、前述のとおり23年4月「野田生中学校」となり、24年に校舎を新築した。
統合へのあゆみ
昭和28年10月に町村合併促進法が施行され、翌29年から八雲・落部両町村の合併について調査検討が進められたのであるが、将来この合併が実現した場合、野田追川を隔てて隣接する落部村立野田追中学校との統合問題が取り上げられた。
このため、30年1月には野田生小中学校PTAの主唱により新中学校敷地候補地の選定について協議が重ねられた結果、敷地問題特別委員会を組織することとなり、野田生地区(市街地・市街隣接の地域・ガンビ岱・大木平・赤笹・沼尻・柏木)から13名の委員が選出され、会長には河原寿太郎が就任し、校地の取得について交渉を重ねたのであった。
一方、町村合併問題は種々の経緯をたどりながら協議が続けられたのであるが、時限立法である昭和31年9月30日の「町村合併促進法の失効」を前にして、9月20日物別れとなり、「町村合併促進協議会」は解散することとなった。これにより、続いて公布された「新市町村建設促進法」へと移行して行くのであるが(行政編・町村合併参照)、昭和32年4月に八雲町と落部村の合併が実現し、この時点において作成された「新町建設計画」の中で、落部村立野田追中学校(生徒数61名)と八雲町立野出生中学校(生徒数124名)の統合整備が挙げられており、両地区の住民も早期実現を強く望んでいたのであった。
このため、両地区住民による野田生・野田追中学校建設期成会(会長・岡島宗弘)を組織し、32年12月の議会に「野田生野田追統合中学校建設に関する請願書」を提出した。議会はこの請願を総務常任委員会に付託し、継続審査とすることとなったのである。その結果、33年1月の臨時会において委員長西亦治信から、統合中学校建設が適切な措置であるとの報告があり、請願は採択されることとなった。
こうした経過をたどって町は、統合中学校建設の実現に向けて努力を傾けた結果、33年12月に起債の見通しを得たので、同月5日第4回定例会に提案して議決を得た。
これにより二か年の継続事業として、第一期(33年度)木造レヂノ鉄板ぶぎ平屋建て校舎201・32坪(664・35平方メートル)、6教室と職員室を工費595万円をもって着工、翌34年に第二期工事として、校長室・宿直室・衛生室など82坪(270・6平方メートル)を工費268万5000円をもって、江差町の田畑組が請負、同年4月全工事を完成した。
なお、学校敷地として、33年12月に統合中学校建設期成会から二町一反六畝二歩(約2・2ヘクタール)が寄付されたが、この上地は野田生土地改良区の造田計画に予定されており、その事業費分担金である昭和33年度から51年度までの48万6952円40銭を、町が負担するという条件が付けられていた。野田追川から126メートル八雲寄りで、国道から180メートル山側に位置しており、34年5月に仮称野田生中学校北仮校舎(旧野田生中学校)と同南仮校舎(旧野田追中学校)から移転し、新生「八雲町立野田生中学校」として、7月4日開校式を行った。これが当町における最初の統合中学校である。
野田生中学校(写真1)

その後、36年に体育館、40年に特別教室が新築されるなど環境の整備が行われてきたが、44年には遠距離通学生の冬期間における通学難を緩和するため、寄宿舎「雄峰寮」を野田生市街地に新築、8〜10キロメートルの範囲の通学生9名を収容し、教育効果の向上を図った。
昭和50年には桜野中学校を廃して野田生中学校桜野分校としたが、この分校も生徒の減少によって51年3月に廃校となった。
56年5月現在の生徒数は71名で、3学級編制である。
第9節 赤笹小学校
大木平特別教授場
明治35年(1902)11月に大柏野簡易教育所が創設されたことにより、その通学区に属していた野田追川上流地帯にも次第に開拓者が入り、大木平から瀬棚渕方面と大木平の高台地にある東ガンビ岱地区にも多数の入植者がみられるようになった。
すなわち、39年5月の村会議案にも、
「字大木平附近ハ戸数五十戸、人口二百有余、学齢児童モ亦二十有余ヲ超へ……。」
と明記されるような状況となっていた。
したがって、これら入植者の子弟を通学させるうえで不便を訴える声が高まってきた。また一方、通学先の大柏野簡易教育所においても、時勢の進展につれて児童数も急激に増加し、早急に増築を追られている状況であった。このため村では地区の要請にこたえ、大木平地区に教授場を新設して増加する児童をこれに入学させることが、双方の問題を一挙に解決させるという判断のもとに、前記の村会に諮って6月からこれを設置することとした。この決定に基づき地区側では、大木平(現、野田生5区)の現舟橋宅前付近に校地四反歩(40アール)を選定し、かやぶきの教員住宅を併設した校舎24坪(約79平方メートル)を建築し、7月1日から授業を開始したのであるが、このときの収容児童数については残念ながら記録が残されていない。なおこの教授場は、大木平に設置されたので村当局を含めて一般に「大木平特別教授場」と呼ばれていたが、これは開設報告の際事務的に誤ったものと思われ、正式には「大柏野簡易教育所付属大柏野特別教授場」と届けられていたことが、のちの焼失後における一連の照復文書によって指摘され、それが確認されるという事実が秘められていた。
その後、本校である簡易教育所が明治41年(1908)4月に単に教育所と改められ、さらに44年1月に尋常小学校と改称されているので、当然この教授場に付する冠称もその都度自動的に変わるという経過をたどった。しかしこの教授場は、大正2年(1913)1月24日に火災のため焼失してしまったのである。
赤笹特別教授場への変更
前述の教授場開設後も、なお引き続き奥地へ開拓入植するものが多くなったため、村でも「未開地ノ解除ト共ニ通学区域拡張セラレ、最遠距離二里(約7・9キロメートル)ニ及ビ将来通学不便ト思ハル」(大正元年状況調書)と記録するような状況を迎えていた。こうした状況のなかで起きた分教場の焼失は、その復旧をめぐって紛議をかもし出すことになった。すなわち、火災から4日後の1月27日、当時ガロー沢下一帯の開拓経営に乗り出し、既に15戸の入植者を入れていた服部伝次は、「さらに2、30戸の入植を計画しているおりから、これを再建するときは当地児童の通学の便を考えて、少しでも奥地に移転するよう。」と嘆願したのを皮切りとして、現状維持を主張する大木平派と、赤笹への移転を主張する赤笹派の二派に分かれる対立を生み出したのであった。
当時、現状維持を便利とする側に大木平の26戸のほか、東ガンビ岱13戸、上50万11戸の計50戸に対し、赤笹移転を便利とする側に下手から野田追川上流に向かって、下50万11戸、瀬棚渕・赤笹12戸、ワサビ沢(安藤山)8戸、ガロー沢下(服部山)15戸などと延び、さらに山地に向かって岩磐農場7戸、境川上(函館山)6戸の計59戸という状況であり、赤笹派では現在の校地の位置を予定し、ここから一歩も譲らないとする勢いであった。
これに対して調査収拾に当たった村当局では、大木平やガンビ岱は野田生の本校に通学するとしても一里前後にすぎず、他校の通学区域と比較しても大差がないということで、奥地に重点を置くことに結論を出し、赤笹(現校地)に移設することと決定した。これを受けた赤笹関係の住民はこぞって協力し合い、校地100坪(約330平方メートル)を選定し、15・5坪(約51平方メートル)の校舎を建築して体制を整えたのであった。こうして従前の教授場の変更という形をもって、大正2年(1913)4月1日「野田生尋常小学校付属赤笹特別教授場」と称し、児章23人を対象に授業を開始したのである。
これにより、大木平・ガンビ岱方面の児童は再び通学区を変更し、野田生校へ通学することとなった。
小学校昇格の前後
児童数が徐々に増加し、既設の12坪(約40平方メートル)の教室では狭くなり、大正8年5月に一部模様替えと10坪(約33平方メートル)の増築により、教室を18坪としてこれに対応したのであった。
翌9年4月には校舎や設備も整ったため、町では特別教育規程の適用(六か年の期限付認可)ながら、これを昇格して「赤笹小学校」と改めた。しかし、当時の児童数が42名であったのに対し、認可満了時の15年にも51名を数えるにすぎず、炭焼として移住していた戸口も木炭が出なくなるとしだいに減少し、したがって児童数も減じ昭和7年(1932)には43名という状況であったため、二度にわたって特別教育規程の適用期間の延長認可を受けるという状態であった。
昭和8年9月には校舎の老朽化に対処して、1教室を主体とする新校舎36・49坪(約120平方メートル)を建築し、さらに教育普及の向上を図るという方針のもとに10年4月特別教育規程の適用を廃し、小学校令による小学校に組織変えした。しかし、このときの児童歌は既に32名と滅少し、15年には29名となるなど校勢の衰退傾向が続いていた。
その後、16年4月に「赤笹国民学校」、22年4月に「赤笹小学校」と改称されていったのは、他校と同様である。
戦後の校勢
既に児童数が20名台に落ち込んでいたのではあるが、教員配置基準の改正によって24年1月から2教員制、さらに41年4月から3教員制がとられるなど教育内容の充実が図られ、同年11月に普通教室2を主とする校舎228平方メートルが新築された。
しかしその後は児童数の減少が著しく、42年度では10名台となり、50年度以降はついに一けた台に落ち込み、56年度現在では教師3名に対して在校生9名(2学級)の小規模校となっている。
旧赤笹小学校(写真1)

赤笹小学校(写真2)

第10節 山越小学校
教育所の開設
山越小学校は、明治6年(1873)11月1日に山越内教育所として開設された当町管内で一番古い学校である。これが開設されたきっかけは、同年9月に開拓使が、前年発布した学制の精神に基づいて教育所の設立を勧奨したことにもよるが、ときの開拓使山越内出張所詰使掌山本 賢が、山越内村民に対していち早く教育の必要性を訴え、その設立を説いたことが直接の動機となったのである。
当初、村民の経済事情からすれば、教育費の負担や子弟の通学などの問題があって難色を示したのであるが、山本の熱心な説得に応じて村民協議の結果、寄付金を募って教育所の設立に動き出し、旧会所跡の建物を充当して開設することとなったのであるが、当校沿革誌によるその時の状況は、
村民設立ノ協議ヲ尺シ、四拾余円ヲ寄附シ以テ会所ト唱フ建物ヲ折半シ、一ツハ駅場トシ一ツハ山越内教育所トシテ(坪数五十坪)其ノ筋へ経伺ヲ遂ゲ、本村移住三井計次郎ヲ教員ニ雇ヒ、月俸其ノ他需要品費悉ク皆村費ヲ以テ支弁シ、同年十月中校舎落成、十一月一日開校式ヲ行フ、生徒男女合セテ惣数四十余名
とある。
しかし、設立したものの設備など十分ではなく、寺子屋式の教授方法がとられ、また、教科書が不足で授業にも支障をきたす状態であった。このため、明治9年には教員の三井計次郎が自費で函館支庁に出向き、生徒心得3部、地理初歩2部、小学読本2部、日本地誌略2部、日本略史2部、算術書2部、地名字引1部などを借り受け、これを教科書に使用したという。
また、明治7年に入学した村上忠八は「商売往来、実語経、論語、大学などを学び、教授方法は座って習い寺子屋式であった」と語っていたと伝えられており、当時の教育内容の一端を知ることができる。
山越内学校時代
時が移り児童歌が増加するにともなって施設が狭くなり、また一方、村民の教育費負担も増加して学校の維持が困難になってきた。そこで公立学校とすることについて出願して許可を受け、営繕工事費若干と書籍や器械の下付を受けた。そして、「村落小学教則」が公布された直後の明治11年2月13日、その名を「公立山越内学校」と改称した。
こうして村落下等5級(2年半)を履修する学校となったのであるが、13年3月には「変則小学教則」により、これまでの村落小学から変則小学に変わり、その修業年限も8級4年制となった。
山越内小学校時代
明治16年(1883)4月「函館県小学教則」により「山越内小学校」と改称された。しかしこの教則では初等科3年・中等科3年、高等科2年の三段階とされたのであるが、当校は初等科3年だけを履修する課程を採用したので、変則小学よりは1年後退したものとなった。
さらに、20年4月「小学簡易科教則」が公布されると修業年限は3年で実質的に変わらなかったが、性格的には「小学簡易科」となった。
しかしこのころの山越内村には、学校と病院という二つの公的な施設があり、その経営に対する村民の負担が大きかった。そこで、村総代をはじめ有志らは、24年3月限りで学校を閉鎖してほしいと嘆願する有様であったが、戸長の説得により小学校を存置し、病院を廃止して八雲の病院に合併させるということで、当校の命脈を保ったという経緯があったという。
尋常小学校時代
明治28年(18九5)3月に公布の「小学校教則」により、小学簡易科が尋常小学校と改められたが、第一類で修業期間は依然として3年とする学校であることに変わりはなかった。この教則は4月から施行されたものであったが、当校沿革誌によると、準備期間があったかどうかははっきりしないが、実際に「山越内尋常小学校」と改称したのは、その年8月からであったという。その後村民は、三か年の修業期間では短く、学力程度も低すぎるという理由で、翌29年5月に認可を受けて修業期間二か年の温習科を設置したのであるが、これに進学するものはごく少数にすぎなかったようである。なお、初代校長として山県光麓が発令されたのは、明治31年になってからであった。
こうしたうちにも校舎の老朽化が問題となり、認可を受けて建築費900円余(うち寄付金160円余)を投じ、32年11月に校舎を新築したのであるが、児童数約40名に対し12坪(約40平方メートル)の教室1のほか、狭い裁縫室や事務室など総面積32坪(約106平方メートル)程度にすぎず、当時における村の財政事情の一端を伺い知ることができる。
明治33年に義務教育年限が4年制に延長されたことによって児童数も増加し、新築校舎も狭くなり、36年度には二部授業(午前・午後の各3時間)を行わざるを得なくなった。このため、翌37年春に教員室・廊下など8坪(約26平方メートル)を増築するとともに、内部の模様替工事を行って38年4月から二部授業を解消し、2学級編制(児童数84名)となった。
これより先の明治35年(1902)4月に八雲村と合併するまでは、山越内全村を通じて唯一の学校であり、したがって通学距離も遠くて不便だったため、不就学児童も非常に多かった。しかし、11月に「大柏野」と「常津内」の簡易教育所が開設されて通学距離の縮小が図られ、これまでの不便も解消して就学率も向上の傾向を示すようになった。
明治41年4月から義務教育年限が6年に延長されたが、そのころ進められていた岩磐農場や宮村農場の開発にともなって児童数は急激に増加し、42年度、45年度と相次いで教室の増改築を行い、これに対応したのであった。しかし、その後は児童数も横ばい状態で、教室の増築なども行われなかったが、昭和8年(1933)に3学級編制となったあと、11年に昇降口7・5坪(約25平方ノートル)を増築して内部の模様替えによる応急措置を行った。
国民学校から小学校へ
昭和16年4月に「山越内国民学校」と名称が変わると同時に高等科が併置されたが、戦時体制下のため校舎の増築も困難をきたし、17年以後には特に認可を受けて初等科200名で3学級、高等科31名で一学級というすし詰め教育が行われた。
16年には坂田竹三郎から学校に電話が寄付されたが、この寄付採納についての議案を審議する議会において一議員から、
「電話ハ余り必要ナカルベシ。学校ノ風紀上ヨリスルモ悪シト聞クガ調査セシヤ」
「学校位置ノ使否ヨリ考察スルニ電話ハ必要ナシト認ム」
などと、現在では笑い話のような質問や意見がまじめに論議されており、当時における社会風潮の一端をかいま見ることができる。
戦後、新教育制度の実施により昭和22年4月に「山越内小学校」となり、5月から「八雲中学校山越内分校」を併置した。
昭和28年6月に山越内小学校PTAは、校舎建築敷地84坪余(約277平方メートル)を諏訪神社から買収して町に寄付し、これを受けた町では2階建て318坪(約1050平方メートル)で、普通教室6、特別教室1の校舎を建築することに決定した。そして6月23日に入札を執行、534万円800円で松原組に落札し、10月に完成した。なおこの工事には、財務局から買収した木造2階建て1棟317坪の建物や、旧校舎の便所と付属廊下木造平屋建て2棟12坪が充当され、床はフローリング張りとされた。
昭和31年5月の字名改正の際「山越小学校」と改称した。その後、44年には総工費928万円をもって306平方メートルの体育館が完成し、11月1日に盛大な落成祝賀会が開催された。
また、48年11月1目には開校100年を迎えるとあって、前年の47年早々に開校100年記念協賛会(会長・酒田貴志)を組織して記念事業について検討を加えた。こうしたことによって、住民から多額の寄付金が寄せられ、校門横に黒御影石の100周年記念碑が建立されたほか、記念誌の発行や全教室(6学級)にカラーテレビと放送施設が備えつけられるとともに、盛大な記念式典を挙行した。
56年5月現在の学級数は4で、児童数は64名である。
山越小学校(写真1)

山越小学校開校100年記念碑(写真2)

第11節 山越中学校
分校から独立校舎へ
昭和22年(1947)5月に学校教育法が施行されたことによって「八雲中学校山越内分校」として、山越内小学校に併設したのが当校のはじまりである。
当初はもちろん専用教室もなく、2部授業によったのであるが、のちに倉庫を改造した増築教室と諏訪神社社務所に応急的に設けられた教場を利用して授業が続けられ、これが解消されたのは23年1月であった。
23年4月からは併置のままで独立校として認可され「山越内中学校」となったが、旧来の山越内小学校は敷地が狭いため教室を増築する余裕がなかった。このため早急にその対応に迫られた町では、適地を選定するとともに24年から2か年をもって独立校舎120坪(約396平方メートル)を新築し、翌25年8月から供用を開始するに至った。こうして当校は、町内最初の新築校舎を持つことになったのであるが、独立後もしばらくの間は校長を小学校長が兼任するという体制であったが、28年6月専任校長に小泉武夫が発令され、名実ともに独立校となった。
31年4月の字名改正により「山越中学校」と改称し、その後38年の特別教室増築に見られるように、時代の変遷を経てきたのであるが、現存する町内の中学校校舎としては最も古い校舎となっている。
生徒数は、独立校舎に移った25年が125名、37年には135名を数えたが、以後はこれを頂点に徐々に減少傾向を示し、56年では42名(3学級、教員9名)にまで減少している。
山越中学校(写真1)

第12節 浜松小学校
開拓草創期の教育事情
明治3年(1870)に斗南藩か山越郡下を分領支配することとなり、翌4年に旧藩士と思われる7戸の移住者が「尾古津内」に入植したが、在住10年余りの間に開墾したのはわずかに七町余(約7ヘクタール)であり、しかも、明治15、6年ごろにはいずこともなく離散してしまったといわれ、少なくともこの地方開拓の創始といえるようなものではなかった。
したがって、古来「奥津内」と呼ばれた当校下の本格的な開拓は、明治18年(1885)に未開地三〇三町歩(303ヘクタール)の貸し下げを受けた竹内幸輔が「竹内農場」を創設し、以後25戸の小作人を入れて経営を行ったのを創始とし、その後農場外の地帯への個々の入植も含めて漸次戸口の増加がみられるようになったのである。
これら入植者たちの子弟教育については、もともとこの地区が山越内村に属し、既設の山越内校に近いという事情もあって、地元に直接施設を設けることなく山越内校に通学させるのを常としていた。しかし明治30年前後において、同じ山越内村に属していた常丹地区の開拓が盛んになったので、必然的にこれら子弟の通学について不便が訴えられ、学校の設立を望む声が高まってきた。このような地区住民の要望に対応して、明治35年8月に奥津内と常丹の同地区を通学区域とする「常津内簡易教育所」の設立認可を受け、校舎も整備されて11月5日から通学できるようになり、同地区内児童の通学事情が緩和されることとなった。(この項、野田生校・熟田校参照)
奥津内簡易教育所
明治36年(1903)にブユベ川と酒屋川に挟まれた地区、すなわち向野と呼ばれた地域41八町歩(418ヘクタール)の貸付を受けた札幌の人宮村朔三が「宮村農場」を創設し、小作人28戸を入植させた。このため、これら入植者たちの子弟教育について、前年常丹寄りの西の沢に設置された教育所では通学が不便となり、その分離設置を望む声が一気に高まった。
こうした情勢を背景として、37年2月の村会では議員(氏名不詳)の建議案をもって、奥津内・鉄山・向野を通学区とする「簡易教育所新設の件」が議題とされ、37年度に開設要望の趣旨をもって可決された。
これを受けた三井村長は4月招集の村会に対し、「時局ニ照シ経費節減ノ折柄ニ付本年度ハ之レガ新設ヲ見合ハセントスル所以ナリ」として新設延期の議案を提出したのであるが、村会ではこと教育にかかわることとしてこれを認めず否決した。
このため村長は、議決に基づいて認可の申請を行ったものと思われるが、時あたかも日露戦争ぼっ発直後のことでもあり、支庁としても町村に対して経費節減を求めていたこともあって、これに難色を示したものかどうかその理由ははっきりしないが、「奥津内簡易教育所」として公設が認可されたのは翌38年5月4日であった。これにより地域内で協議した結果、校地に竹内農場から595坪(約1964平方メートル)の提供を受け、住宅併設の校舎42坪(約139平方メートル)を農場主と住民の負担で建設し、6月12日から授業を開始した。これが当校の創設であり、当時すでに児童は45名を数え、初の教員には尾形石吉が任ぜられていた。
明治41年4月法令の改正により、自動的に「奥津内教育所」と改称された。また、同時に義務教育年限の延長が施行されたのであるが、当教育所はこれまでのとおり4年生までの収容にとどめ、5、6年生は山越内校に通学させるという措置がとられていたが、大正2年4月からは全児童を収容することとなり、独立校としての体裁が整えられていった。
小学校昇格と校舎改築
年ごとに校勢は伸展して大正5年には児童数も68名に達した。村では教育所の組織変更を決定し、5月13日に認可を受けて「奥津内尋常小学校」と改称、初代校長に三浦十郎を迎えた。なお、教育所という組織は、当校を最後に姿を消すことになったのである。
大正7年には児童数74名を数え、明治43年に一部増築したにもかかわらず狭さは極限状態となったので、地域内で協議した結果、住民一致協力して寄付を集めるとともに、用材の伐採と運搬から校地の整備に至るまで出役奉仕を行うと同時に、役場に対して全面改築を申し入れたのであった。町では翌8年町会に諮ってその実施を決め、5月に認可を受けて工事に着手し、9月に完成させた。新校舎は、2教室を主体とする67坪(約221平方メートル)のもので、総工費は3180円(町費1180円、地区寄付2000円)であった。改築落成式は9月8日に行われた。こうして整備されたことによってその月2学級編制が認可となり、さらに翌年4月から2教員制となって教育環境はしだいに整えられていったのである。
学制改革から現在まで
大正15年7月小学校に青年訓練所を併設し、昭和10年青年学校令により青年学校と改められた。小学校は16年4月国民学校令によって「奥津内国民学校」と改称するなどの変遷によって戦時中を経過したのである。
奥津内尋常小学校(写真1)

戦後、22年の学制改革(63制)によって「町立奥津内小学校」と改称し、さらに31年5月の字名改正により「町立浜松小学校」と名称を変更して現在に至っている。この間、31年11月に校舎改築工事に着手し、翌32年4月に105・75坪(約349平方メートル)、総工費360万円をもって完成した。39年4月に児童数が62名となって3学級編制となり、その後児童数は減少傾向を示しはじめ、44年には児童数39名で2学級編制となった。56年現在では3学級編制で児童30名である。
また、昭和50年11月には開校70周年記念式典を行い、さらに51年8月に体育館新築工事が着工され、工費2149万5000円をもって、鉄骨造り延べ面積259平方メートルの近代的な施設が11月に完成した。
第13節 八雲小学校
創始時代
明治11年(1878)に遊楽部原野の開拓を志して移住した旧尾張藩士が、その居所も暖まらぬうちに「人類ノ集ル、必ス教養ノ設ナカル可カラス」(当校沿革誌)と教育の必要性をとなえ、移住者に同行してきていた植松稔を教師に選び、その居留先である角田弟彦宅を教場に当て、寺子屋式ではあるが子弟に勉学をさせたのはその年11月のことであった。しかも徳川家開墾試験場では、翌12年第2回移住者を迎えるに先立ち、いち早く公立学校の設立を計画し、その筋に出願して許可を受け、校舎40坪(約132平方メlドル)を新築した。この学校用地は試験場内の土地(現、出雲町斉藤一郎宅付近)3500坪(約1万1550平方メートル)を当て、建築費も全額徳川家の拠出によるものであり、このほか移住者の労力奉仕もあって7月26日に完成したのである。
浜松小学校(写真1)

次いで8月初めに第2回移住者を迎え、校名を「八雲学校」と名付け教師には引き続き植松稔を当て、児童30名を収容して8月18日から授業を開始した。しかし、開校式は農閑期を待って行うこととし、翌13年2月7日盛大に挙行したのであった。なお、この学校設立の出願に際し、既に校名を「八雲」とすることを予定しており、八雲村誕生の2年前から「八雲」の文字が公式に用いられていたことは、村名の由来とともに興味深いところである。
明治13年3月に試験場外の児童を就学させるため、学校維持費として村民の賦課金と遊楽部川渡舟賃収益の一部を充当することとし、なお不足する分は徳川家から援助を仰ぐということにしたので、これにより文字どおり公立学校としての体裁が整っていった。
設立当初の学校としての性格は、当時の制規によって「村落小学」であり、修業年限は下等5級(2年半)という程度の低いものであったが、翌13年4月から「変則小学」の修業年限4年と変わり、さらに16年4月から同じく変則小学ながら初等科3年を履修する学校へと後退したが、このときの改正をもって「八雲小学校」と称することになった。さらに20年4月からは、実質的には変わりないが「小学簡易科」3年制の学校となった。
八雲学校(写真1)

なお、このときの改正教則によって1か年の温習科をおくことができるようになり、当校にもこれが設けられたのであるが、これに関する史料がないので、設置状況を明らかにすることができない。28年3月に小学簡易科卒業生9名、32年補修科卒業生16名を送り出しだのが最後となっているので、このとき廃止されたものと思われる。
明治14年6月に植松教員は辞任して帰郷したので、移民の中から内堀竜眼を仮教員にあて、生徒長伊藤直太郎を補助として復習をみさせた。そして翌7月に桜井武醅を後任者とし、同年12月函館師範学校で受験して正式に準訓導となった。
その後、明治19年6月に卒業生伊藤直太郎が、資格を得て3代校長として赴任し、大正4年まで28年8か月にわたってその職にあった。
尋常小学校時代と遊楽部学校統合
明治28年4月に小学簡易科が廃止されて「八雲尋常小学校」と改められたが、学校の分類としては第一類ながらも修業年限を尋常科3年とするものに指定されたので、実質的に変わるところがなかったのである。ただし、尋常科を卒業した後とくに修業しようとする者のために2年制の補習科を設けるみちが開かれたので、29年5月からこれを開設したが、間もなく高等科が設置されたことによって廃止され、この卒業生を送り出したのは30、31年度のわずか2年度にすぎなかった。
八雲尋常小学校(写真1)

開拓が進むにつれて児童数も増加し、さらに補習科の増設もあって校舎が狭くなり、増築問題が取り上げられることとなったのであるが、ちょうどそのころ経営上に問題のあった遊楽部尋常小学校(明28・4改称)を統合のうえ、適当な場所に新築することを決めた。そして、統合許可を得て角田弘業の所有地(現在地)1500坪(約4950平方ノートル)の無償貸与(のち徳川家から寄付される)を受け、明治31年12月15日に新校舎を完成させたのであった。
校舎は、4教室と裁縫室のほかに所要施設が付設され、総面積は158坪(約521平方メートル)、工費3500円で、当時としてはかなり整備されたものであり、いわゆる統合校舎としても初めてのものであった。この工事費のねん出に当たっては、村有軍事公債を担保に徳川家当主義礼から一〇か年賦をもって1000円を借り入れしているが、いわばこれが当町における起債のはじまりでもあった。
学校林の取得と処分
当校創始時代の小学校は住民の公学ということから、学校経営に関する経費はそれぞれの町村で維持するという建て前であった。しかし、戸口も少なく経済的基盤の弱い当時の町村としては、経費の調達は容易なものではなかった。こうしたことから、明治15年には1校につき50万坪(約166ヘクタール)を限度として土地を付与し、学校維持のための基本財産を造成させるみちが開かれた。
八雲村ではこの趣旨に基づき村民協議のうえ「オトナ川とサランベ川の中間にある地帯」の無償下付を出願したところ、これが聞き届けられて仮渡しのあと明治17年に実測のうえ45万3350坪(約155ヘクタール)という大地積が下付されたので、のちに「学校林保護申合規則」を作って認可を受け、資産の保護育成に努めたのである。
こうして取得した学校林であったが、明治31年に校舎を新築した際、徳川義礼から一〇か年賦をもって借り入れした1000円の償還財源として、ここの立木売払処分収入を充当することとなった。
余談ではあるが、この売り払いは大田スツ(半三郎の母)との契約で「代価2850円を33年から39年までの七か年で伐木して代金を完納することとし、その伐木跡地には25戸以上の小作人を入れて開墾させたうえ、43年11月限りで小作人とともに八雲村に引き渡す」というものであった。この契約が履行されたことによって、村としては一〇か年賦を早めて37年度までに返済を終わることができたのである。
なお、これが八雲村に引き渡されたあとは、村有の基本財産で、しかも貸付小作地として管理されることとなったが、これが学林地区(現、春曰1区)開発の端緒でもあった。
高等科の併設
さきの校舎新築を契機に、教育課程の充実を望む声が高まってきたので、村では尋常科を第一類中の4年制とし、さらに2年制の高等科の設置を申請し、明治32年(1899)8月19曰に認可を受けた。こうして、管内唯一の高等科併置校となり、校名を「八雲尋常高等小学校」と改め、名実ともに中心校となったが、これは翌33年8月の義務教育4年制の制度化に先駆けての快挙であった。
さらに、高等科は35年に3年割に、39年に4年制と相次いで改善されたが、41年4月に義務教育を6年制とする改正によって、尋常科6年、高等科2年の編成となってようやく安定し、昭和16年(1941)に国民学校へと変わるまで長くこの体制が続けられることになったのである。
このような制度の改正とともに、児童数の増加が続いたため教室の不足をきたし、37年度を皮切りに39、40、42、45年度、さらに大正5年、8年と相次いで教室を増築した。また、この間の明治41年7月には、遊楽部川鮭魚蕃殖組合の寄付金500円を基にして、屋内体操場80坪を建築するなど、連年のように施設が拡張されていった。
大正11年の校舎増改築
大正8年までの数度にわたる増築によって、いわゆるタコ足校舎となり大幅な増改築の必要に迫られていたが、ちょうどおりからの第一次世界大戦後における不況や人心の動揺のため、やむを得ず延期しなければならない状況にあった。しかし、経済界の不況もさることながら、「校舎の実情は改築の急を告げたり」とする木村町長は、大正11年度から2か年継続事業としての増改築を決意し、10年12月の町会において事業実施が決定したのであった。その計画によると、将来の学級増を考慮しながら、旧校舎の一部222坪余(約733平方メートル)を解体処分し、その跡地に2階建て220坪余(約726平方メートル)をもって11教室を設け、旧校舎の5教室と合わせて16教室とするほか、屋内運動場40坪(約132平方メートル)を増築し、さらに旧校舎の一部を模様替えして事務室・理科器械室・湯飲場・その他の所要施設を設けるなど、工事延べ坪数は472坪(1558平方メートル)で、総面積は実に592坪余(約1954平方メートル、別棟の奉置所・倉庫・便所など11坪を除く)であり、総工費2万9962円余を見積もる本格的なものであった。
しかし、翌12年度に中学校校舎の建築問題が起こったため、財源に基本財産蓄積金のうちから2万5000円を運用して単年度施行に変更し、完成期限は9月30日で請負人松原勝治により施行したのであるが、経済の不況を反映して資材の入手などに困難をきわめて工事が遅れ、これが完成したのは12月11日であった。この時の児童数は1087名を数えていた。
こうしてこの校舎は、当時理事者をして「郡部随一の校舎」と自賛させるほどりっぱに整備されたのであるが、一方、工事の遅延による過怠金の徴収免除処分をめぐって、大正13年1月の町会において「町長の独断による権利放棄は越権行為である」として、一部議員から町長を問責する建議案が提出され、これをめぐって激しい議論が交わされたが、結局この建議案を撤回することで決着したという政治的な一幕もあった。
八雲尋常高等小学校(写真1)

昭和初期の校舎拡充
大正15年(1926)4月に当校校舎を併用して家政女学校が開設されたので、2階建て2教室を増築してこれに対応したが、この家政女学校も年を追って学級が増加するとともに、児童生徒も増加して間もなく教室が不足するという状況になった。
そこで町は、隣接地の2156坪(約7115平方メートル)を買収して校地を拡張し、昭和3年(1928)に2階建て4教室を増築、さらに翌4年には第二屋内体操場90坪(約297平方メートル)の新築と一部校舎を解体のうえ、2階建て12教室をはじめ事務室その他417坪余(約1376平方メートル)を新築するという大工事を行った。
こうして校舎は総2階建てともいえるほど堂々としたものとなり、28教室と2つの屋内体操場を擁し、尋常科18学級、高等科6学級に併設家政女学校4学級という体制が整えられたのである。
さらに、9年度に1学級増設、10年度に裁縫室と工作室などを増設、11年度に職員便所を増設するなど、校舎総面積は1180坪余(約389回平方メートル)に及ぶ大規模なものとなった。その後12年に実科高等女学校の校舎が新築されたこともあってようやく校舎に余裕ができ、これまで毎年のように続いた増改築も一段落したのである。
国民学校を経て小学校へ
昭和16年4月には「八雲国民学校」と改称され、初等科6年(20学級)、高等科2年(6学級)、児童生徒教およそ1500名という大規模校となり、戦時下という状況によって軍国調の教育が展開されていった。特に高等科の生徒は勤労奉仕という名のもとに、ほとんど授業が行われないという状況であった。
昭和22年4月の新教育制度の施行によって高等科が廃止され、別に中学校の課程が設けられることになると同時に「町立八雲小学校」と改称し、修業年限を6年とする学校となった。しかし、中学校の校舎ができるまでは同校生徒の一部が同居していたうえ、戦後の戸口増加によって児童教も急激に増え、32学級にも達して校舎はまたまた狭くなり、第二屋内体操場の間仕切りによって2教室を設け、急場をしのぐという状態であった。
しかも学級定員の引き下げもあってさらに学級は増加して教室が不足となり、また、大正11年建築の校舎も老朽化が進みつつあったので、いちじは第二小学校新設の意見が出されるほどであった。
ブロック校舎の誕生
校下とくに八雲市街地の児童数増加による恒常的な教室不足を解消することは、町政関係者にとって緊急の課題となり、昭和20年代後半において通学区を二分する第二小学校の建設問題が真剣に取り上げられるようになった。しかし、その後行われた調査研究によると、児童教の増加傾向はしだいに鈍化し、これ以上大きく増加する見込みはないという見通しとなったので、町の財政事情や学校管理面のメリットを考慮してこれを見送ることとし、差し当たって必要な部分の増築をもって対応する方針がとられることになった。町議会においてもこの方針が確認され、町内初のブロック造り校舎の増築について議決されたのは、昭和31年2月のことであった。こうして旧屋内体操場と渡廊下126坪(約416平方メートル)を解体し、その跡にコンクリート・パスキンブロック造り2階建て215坪(約710平方メートル)に渡廊下を付する増築工事が行われた。校舎は6教室の増設で、先に第二屋内体操場に急造した2教室の間仕切りをはずしても、なお全体として余裕ができ、特別教室も確保できるという計画のもとに、工費およそ977万円をもって31年8月に完成した。
一方、この校舎の増築と並行して体育館の建設計画が進められ、同年9月に議会の議決を経て31、32年度の2か年継続事業により施行することとし、10月に起工した。この体育館は、鉄骨補強ブロック造り840平方メートルで、内部にはステージと観覧席も設けられ、渡り廊下を含めて総工費は492万余円に達し、32年6月に完成したのであるが、当時としては道南はもちろん道内でも屈指のものといわれた。
完成後はこの施設の有効な活用という観点から、学童の使用に差し支えがない限り、一般に開放して社会体育や演劇その他の諸行事に使用させることとした。
校舎の全面改築
昭和31、32年度の校舎および新体育館の建築によって、一応不便は解消されたかにみえたが、大正11年から昭和4年にかけて建築された木造2階建ての校舎が老朽化したことにより、改築問題が重要課題としてクローズアップされたのである。
このため町は、教育委員会・学校・町議会などと連携を保ちながら、改築問題について検討を続けたのであった。この結果、昭和37年に木造旧校舎のすべてを不燃質の校舎にするという結論に達した。こうして、37年度から40年度までの4か年継続事業をもって、鉄筋コンクリート造り3階建て、延べ面積5204平方メートル、総工費およそ1億1000万円の巨費を投入して建築する計画が立てられた。これは、当時の町財政がようやく赤字から脱出して若干好転しつつあったとはいえ、決して容易ではない決断であった。
工事は、建築主体工事を請け負った坂本建設株式会社ほか2業者によって施工され、現木造校舎の裏側に並行して建築する方法をとり、37年10月に起工し、順調な経過によって40年10月20日に全工事が完了したのであった。完成された校舎は、さきのブロック校舎と合わせて普通教室33と特別教室1のほか、近代初等教育の施設として必要なほとんどのものを備えたりっぱなものであった。
この校舎の完成を祝って、PTA・同窓会などが、記念事業として寄付金を集めて多くの設備備品を寄贈した。このほか行事としては、11月1日に鼓笛隊を先頭にした児童の市中パレードが行われ、図画・習字・工作などの展示会も開催された。また、3日には関係者多数の出席のもとに、盛大な祝賀会を開催したのであった。
学校統合の推進
教育条件の格差解消や教育内容の充実などをねらいとする学校統合が進められつつあった昭和40年代の初め、管内のトップを切って実現したのは、久留米小学校と上鉛川小・中学校の八雲小・中学校への統合であった。
八雲小学校(写真1)

校舎改築工事の完成を間近に控えた昭和39年(1964)8月、まず第一に比較的通学区に近い花浦地区の久留米小学校を統合する方針が決定された。これにより、教育委員会を中心に学校統合推進協議会ともども関係者と協議が進められた結果、40年4月1日をもって統合したのであった。また同時に、児童数が極度に減少していた上鉛川小学校についても話し合いが進められ、その理解が得られたことによって、ここに2校の統合が実現したのである。
さらに、農村地帯における児童数の減少という事態を要因として、42年4月には鉛川小学校がこれに続き、次いで47年12月に熊嶺小学校、51年4月に熱田小学校をそれぞれ統合して現在に至っている。なお、この間の45年3月にはひまわり分校を廃し、北海道八雲養護学校に引き継いでいた。
こうした推移をたどるうちにも、児童数は大きな変化をみせた。すなわち、昭和22年の1221名(24学級)に対し、28年には1554名(29学級)、34年1972名(38学級)を数えた。とくに最高を示した34年には、2000名を超える時もあったのである。
しかし、この年を頂点として、以後は急激に下降線をたどりはじめ、37年1609名、40年1381名と激減し、46年には1200名台に落ち込み、その後は足踏み状態を続け、56年度では1292名(32学級・教員数43名)となっている。
第14節 八雲中学校
新制度下の対応
昭和22年(1947)教育制度の画期的な改正にともない、いわゆる6・3割が実施され、全国的に新制の中学校が設置されることになった。
八雲町ではこれに対応するため関係者が協議した結果、同年5月に取りあえず本校として「八雲中学校」を設置し、これまで高等科を併設していた小学校、すなわち、黒岩・山崎・大関・八雲鉱山・山越内・野田生の6校に、それぞれ八雲中学校の分校を併設するという方針を定めて発足させた。
しかし、これらの分校を独立させるための専用校舎の建設については、戦後の窮乏した町の財政下にあって容易なことでなく、町では校下父母など関係者に、資金の寄付を求めるという苦肉の策を講じたのであるが、よくこれに応じて施設の整備に協力を得たため、翌23年4月には前記6分校とも独立校となったのである。
本校として発足した八雲中学校といえどもその例外ではなく、独立校舎もなかったので、取りあえず八雲小学校と八雲高等女学校の教室の一部をこれにあてる分散方式とし、初代校長には八雲高等女学校長桑山誠一の兼任をもって授業を開始したのであった。
その後町では、専用校舎に充てるため旧軍用建物を借り受け、内部の模様替えを行って23年3月に移転し、第一回卒業生をこの独立校舎から送り出したのである。そしてこのあとも引き続き整備を進めたのであるが、昭和25年4月中旬札幌特別調達局から、突然旧飛行場を接収する旨の内報を受けたのであった。その通知によると、校舎敷地は接収地と余りにも近すぎ、そのうえ予定していたグラウンド用地を失うこととなって、学校としての機能充実が期待できないことになり、既定方針の変更を余儀なくされ、校舎新築の問題が取り上げられることとなったのである。
新制八雲中学校仮校舎(旧飛行場兵舎)(写真1)

校舎の移転新築
校舎の移転新築については、かなりの資金を要し、当時の町財政にあってはまさに重大問題であった。そのため町は議会と協調してこれに対処し、道教委の協力を得ながら文部省などに積極的に陳情を続けた。その結果、国庫補助や起債に一応の見通しを得たので、場所を旧競馬場跡の国有地中央から北側を適地と定め、早期着工を目指して設計を進めた。
昭和25年10月に地元業者など12社を指名して入札を行ったが不落札となったため、最低入札者の株式会社熊谷組と随意契約の交渉を行い、同月16日町議会の議決を経て1650万円で契約を締結した。
工事は直ちに着工されたが、既に凍結期に入って続行は不適当となり、当該年度は基礎くい打ちと玉石や砂利の搬入にとどめるという状況であった。
翌年4月に工事は再開されたのであるが、折からの朝鮮動乱によって資材が高騰したばかりでなく、入手することさえ困難となり、請負金額の増額が要求されるなど、その進展が危ぶまれたのである。しかし、業者の努力と町理事者や議会の適切な対応によって、当初の予定工期よりかなりの遅れがでたものの、26年12月29日に新校舎は完成した。この校舎は、20教室とそのほか6室を擁し、木造モルタル仕上げ2階建て延べ984坪余(約3248平方メートル)に達するもので、当時の中学校としては堂々たるものであった。なお、この工事は請負金額の変更こそなかったが、時勢の特殊性をとり入れ、熊谷組に対し新築工事報償金として200万円を支給したことに特色があったほか、一部設計変更やその他の諸費を含めて、建築工事費総額は最終的に1961万余円となったのである。
旧八雲中学校(写真1)

一方、屋内運動場も旧校舎の運動場を買収のうえ、校舎の新築に合わせて移築することとし、26年11月に松原組と請負契約を締結、予定どおり12月30日をもって完成させた。この屋内運動場は木造270坪(約891平方メートル)で、工事費と買収費を合わせて490万余円であった。
こうして、飛行場の再建設に端を発して新築された校舎には、3学期から移転して授業を開始し、翌27年2月8日に落成記念式を行ったのである。
産業教育研究校の指定と整備
文部省は昭和26年(1951)6月に公布された産業教育振興法に基づき、産業教育の改善と地方の産業振興を図るため、研究校を指定することになっていた。
この施策によって当校は30年12月に「産業教育を推進するための教育計画の検討」と「酪農業を基盤として発達した小都市の学校における実践的効果的な産業教育の検討とその指導法の研究」を課題として研究校に指定された。このため、産業教育推進の設備として30年度には、自動かんな・昇降丸のこ盤・ミシン糸のこ機・電気グラインダー・万力など、31年度には角のみ機・帯のこ機・本工万力などを購入整備した。
また、研究校の指定にともない施設の整備が急務となったので、31年12月に木造2階建て353平方メートルの特別教室建築に着工し、翌年6月に完成した。この特別教室は、階下が動力機械と工作室、階上が家庭科被服室になっており、既設の校舎と渡り廊下でつなぐという、いわば2線校舎のはじまりでもあった。もちろんこの特別教室建築のねらいは、近代的な機械や動力についての理解を深め、将来どのような職業についても、常に科学的に考えることのできる人間教育を本質とするものであると同時に、当校だけではなく、町内各中学校や一般にも公開しようとするものであった。
なお、この特別教室整備後の10月には当校を会場に、全道的な規模で産業教育研究大会が開催された。
施設の整備と改築計画
昭和32年6月には特殊学級ひまわり学院を開設した。
また、36年度に見込まれる生徒の急増に対応して、36年2月普通教室4室の増築に着工し5月未完成、さらに36年度事業である普通教室2室の増築も、8月に完成させて授業に支障のないようにした。その後38年1月には全校放送施設が完備した。また、この年12月には特殊学級ひまわり学院が分校に昇格し、国立療養所八雲病院内に設置されることとなって移転した。
39年12月に特別教室(理科室・家庭料理室)を増築して、施設のより一層の充実が図られたのである。
40年3月には上鉛川中学校が廃校となって4月から統合され、スクールバスによって通学生を収容することとなった。
また、冬期間の遠距離通学生徒のため、42年12月収容定員32名の寄宿舎「恵雲寮」(ブロック造り平屋建て401平方メートル)が、工費975万円で新築された。
その後44年6月には、学校水泳プール(鋼板製7コース)の新設に着工、翌年8月循環浄化装置などの付属施設を完成した。
さらに45年8月から2か年継続をもって、新体育館(鉄骨、一部鉄筋コンクリート造り1080平方メートル)の建築に着工し、翌年6月に完成するなど、教育環境の近代化が図られたのである。
統合中学校新設への移行
前述のとおり当校の環境整備については、年々近代化が図られつつあったが、本校舎は建築以来すでに30年近く経過し、しかも戦後の資材が乏しいころに建てられたこともあって、昭和52年7月の老朽度測定では、木造部分のすべてが危険校舎として指定され、改築が避けられない情勢となった。
そのため町教育委員会では、おりから進めていた当校を含む黒岩・山埼・大関・山越・野田生の6中学校統合の56年4月実現の目標と並行して、老朽危険校舎の解消に取り組むため、52年11月に仮称八雲中央中学校基本設計特別委員会を発足させ、統合実現の場合を想定した新校舎の段階的建設の設計に着手し、53年度にその計画をまとめたのであった。
新校舎は、旧校舎の1線校舎と2線校舎の中庭で、工期を二期に分け、一期工事は55年3月、二期工事は同年12月に完成、鉄筋コンクリート造り4階建てで、200人程度収容できる音楽室、英語会話等語学実習装置を備えたLL特別教室、企画室、調整室、スタジオをもつ放送関係室、物理・化学の理科教室、生物・化学の第二理科教室なども取り入れ、全校電気暖房式の近代的なもので、延べ面積は5455平方メートル、工事費と備品購入費などを合わせ総事業費は8億6804万6000円を投じたものであった。
こうして新装なった校舎の落成式は、56年2月6日に挙行され、新学期からは大関と山崎の両中学校が統合されたのである。
今後は統合対象地区との話し合いを進め、各地区の了解を得て統合分の施設を増設し、21学級・2特殊学級規模の校舎とする予定である。
八雲中学校(写真1)

生徒数の推移
当校の生徒数の推移は、昭和27年現在地に移転した当時は885名(18学級)を数え、さらに増加傾向をたどって31、32年度に1000名を超え、その後は若干減ったものの、36年度には一挙に1121名(24学級)となり、37年度では2101名(同)を数えた。しかし、これを頂点として下降線をたどりはじめ、41年度で1000名台を、44年度で800名台を、そして50年度で700名台を下回わり、56年5月現在では、生徒数630名、17学級となっている。
第15節 大新小学校
特別教授場の開設
明治の末期に徳川農場が経営していた常丹牧場のあった大新高台地は、大正初期に開墾地として開放され、小作人を入れるようになった。またこれと時を同じくして、この周辺に尾崎・佐藤・平手などの農場が創設され、それぞれ入植者を迎えていたので、急速に戸口の増加が見られるようになった。
しかしこれらの地域は、既設の八雲・常丹・上砂蘭部各校の中間地帯に当たったが、このころは常丹校の通学区とされていたので、大正4年度(1915)の学齢児童52名のうち、通学中の者は32名と記録されているように、出席率はもちろんのこと不就学児童も多くなるという実情であった。これを憂慮した住民は、協議のうえ大正4年12月木村村長に対し「大正ノ聖代ニ生存シナガラ子孫ニ普通教育ヲモ授クル能ハザルハ父兄タルモノ実ニ忍ブ能ハザル」ことと訴え、校舎および設備の寄付を要件として、特別教授場の設置を陳情したのである。これを受けた村では、翌5年早々に村会に諮ってその設置を決め、4月を期して授業の開始を図ったが、地域側での校舎建築が遅れ「八雲尋常高等小学校付属大新特別教授場」と名付けて授業を開始したのは6月2日で、このときの児童数は37名であった。
大新小学校(写真1)

なおこの校舎は、現校地の道路を挟んだ向かい側で、徳川農場が提供した900坪(約2970平方メートル)の校地に、教員住宅を併設した28・5坪(約94平方メートル)のものであったが、翌年9月に強風のため倒壊したので、再び住民の手によって現校地に移築されたのである。
国民学校から小学校へ
昭和16年の学制改革によって特別教育規程が廃止され、4月1日から「八雲国民学校大新分教場」と改称された。
戦後の緊急開拓により熊嶺地区に15戸が入植し、13名の児童が大新分教場に通学していたが、25年4月1日には小学校に昇格して八雲小学校から離れ「大新小学校」となり、熊嶺分校も付設し、初代校長として中村芳雄が任命された。25年には校舎の一部を改築したのであるが、そのほかの部分の破損が著しくなったので、29年9月に65坪(約215平方メートル)の校舎新築に着手し、10月完成した。
なお当校では、41年9月に”学校ぶろ”を設置し、毎週1回入浴日を定めて児童を入浴させ、これを教育課程の中に位置付け年間を通して実施するという、全道でただ一校の特異な存在として効果を上げている。
昭和56年現在の児童数は5名で、3学級編制である。
第16節 春日小学校
上砂蘭部分校の創設
当校通学区のおよそ7割に当たる地帯は、明治29年(1896)に桜井郁次郎・鈴木義宗・畠山禎治の三者の共同出願により、当時、八雲小学校付属の学校林であった土地の上手一帯一一七〇町歩(約1170ヘクタール)にわたる大地積の貸付を受け、いわゆる鈴木農場を創設した。そして、その年20戸の小作人を入植させたのをはじめとして、逐年入植者を入れて積極的な開発が進められた。その後も山間部地帯に中島・横谷・大林などの各農場が創設されていくが、その素地もまた鈴木農場の開発に負うところが大きかった。なお、八雲小学校付属学校林の処分跡地に入植開拓が進められたのも、これと相前後するころであった。
こうしたなかで農場主の鈴本義宗は、いち早く入植者たちの子弟教育の必要性を痛感し、明治31年11月に自費を投じて加老地区に掘立式の仮建物ではあるが30坪(約99平方メートル)の教場を造り、教員に田中雄道を雇い、児童41名を収容して授業を開始した。しかし、このように大規模な教育の揚が、私設として永続できるはずもなく、翌32年10月18日には久留米分校と同時に「八雲尋常高等小学校上砂蘭部分校」となり、早くも公設の学校となったのである。
校勢の拡張
明治34年(1901)4月に独立校となって、「上砂蘭部尋常小学校」と改称し、同年12月には初代校長に佐藤新が発令された。しかし、仮校舎は火災のため焼失しており、このときは農場の板蔵15坪(約50平方メートル)を仮校舎に当てていたという。 開発が進むにつれて36年ごろから児童数が急激に増加しはじめたので、翌37年に校下父兄が協議した結果、農場主が現在地を永久無償という約定で提供し、このほかに住民が建築費1100余円を出し合って、教員住宅を併設する50坪(約165平方メートル)の校舎を新築落成させたのは7月20日であった。こうして整備された校舎は、桜井郁次郎ほか90名から村に対して寄付申し出があり、10月の村会で議決のうえ採納した。
上砂蘭部小学校(写真1)

その後は義務教育年限の延長もあって、39年に96名、41年に133名と在籍児童の増加が続いた。このため、41年4月からは取りあえず2部授業で対応し、翌年20坪(約66平方メートル)の教室を増築模様替えするとともに、教員住宅1棟2戸建てを新築して二学級編制としたが、児童数は既に145名に達していた。以後も依然として戸口の増加が続き、大正5年(1916)には児童数が165名に及び、またまた二部授業に追い込まれたので、翌6年さらに40坪(約132平方メートル)を増築して三学級編制とした。なお、2年後の8年度には校下の戸数が200戸を超え、児童数も187名を数える状況であった。しかし、たまたま襲った第一次世界大戦終息後におけるでんぷん・小手芒などの価格暴落によって営農困難に陥り、離農転出するものが続出したため、児童の増加傾向もこの時点をピークとして下向線をたどることとなった。
学制改革から現在まで
大正15年4月1日全国一斉に青年訓練所が開始されたことによって7月訓練所を併置し、昭和10年の青年学校令により「上砂蘭部青年学校」と改称、さらに16年4月の国民学校令によって「上砂蘭部国民学校」と改称して戦時中を経過したのである。
昭和22年の6・3制の学制改革によって「上砂蘭部小学校」と改称、31年5月の字名改正の際「春日小学校」と変更して現在に至っている。32年10月には屋根レヂノ鉄板ぶき木造平屋建て102坪(約337平方メートル)の校舎改築に着手、教室・理科実験室・給食室・子供銀行室・図書室・職員室・宿直室・用具室など、総工費365万円余をもって12月に完成し、翌年3月に落成祝賀会を開催した。
校舎改築当時の児童数は85名を数えたが、しだいに減少傾向をたどり始め、56年度現在では児童数14名、3学級編制である。
春日小学校(写真1)

第17節 大関小(中)学校
大関分校の創設
大阪の人、長谷川寅次郎・井上徳兵衛と、下関の人、安井作次郎・大井重吉ら4名が共同出願して、明治30年(1897)2月にペンケルペシベ川以北におよそ一〇四三町歩(約1043ヘクタール)の貸付を受けた。そしてここに「大関農場」を創設し、入植者を募集して38戸を入れたのをはじめとし、地域の本格的な開拓を進めるようになった。また、同川以南の鉛川地区でも同年「藤川農場」が創設され、開拓が進められつつあった。
このような入植者の増加という状況のもとに、大関農場が中心となり、その子弟教育のため農場事務所の一室を当てることで村当局と折衝し、明治33年5月1日に「八雲尋常高等小学校大関分校」が開校されるに至った。ペンケルペシベ7線地区(トベトマリ・現、上八雲一区)内の校地375坪(約1238平方メートル)に建物16坪(約53平方メートル)という体制をとり、通学区は鉛川地区も含め、児童数は42名で最初の教員は大橋栄松であった。
小学校独立とその発展
分校創設の翌34年4月に村当局はこれを昇格させて「大関尋常小学校」とした。37年5月には実業補習学校を併設(大正13年1月まで存続)して充実が図られ、39年6月に教員2名で2学級編制となった。その後、奥地の開拓が進められるにつれて、校舎の位置が偏ってきたことが問題となり、村で調査検討の結果、農場のほぼ中央に当たる現位置に移転することに決め、40年4月に48坪(約158平方メートル)の校舎新築に着手し、6月に完成移転した。初代校長には41年5月に中田千蔵が発令され就任した。
またこの当時は、周辺地域の開拓が盛んに進められており、当校の付属として38年4月設置のサックルペシベ特別教授場をはじめ、40年4月の鉛川特別教授場(大正2年八雲尋常高等小学校付属となる)、41年12月のトワルベツ特別教授場、43年6月のペンケルペシベ特別教授場などが相次いで設置されていた。
充実期から現在まで
大正元年(1912)12月に旧職員住宅を改造して教室を増築したのをはじめ、随時需要に応じながら推移したが、昭和14年(1639)4月に児童の就学機会を拡大するため、2年制の高等科を併置して「大関尋常高等小学校」と改め、さらに16年4月に「大関国民学校」(3学級)となり、22年4月からは現在の「大関小学校」と改称された。なお、同年5月には「八雲中学校大関分校」が併置され、翌年4月からはやはり併置ではあるが、独立して「大関中学校」となり、昭和56年八雲中学校新校舎完成により廃校、これと統合することとなり、4月1日から生徒はスクールバスにより通学している状況である。
校舎は明治40年(1907)に建築以来、幾度か増改築の変造を経たのであるが、老朽が激しくなったため昭和35年(1960)に旧小学校校舎92坪(約304平方メートル)を取り壊し、木造平屋建て112・75坪(約372平方メートル)に改築、これに旧中学校校舎55坪(約182平方メートル)を移設して面目を一新した。その後、38年に特別教室(109平方メートル)とへき地集会室(約426平方メートル)、41年に普通教室1が増築拡充された。さらに42年には、遠距離通学の生徒を収容する寄宿舎「清心寮」が建てられ、教育環境の整備が図られた。
旧大関小中学校(写真1)

大関小中学校(写真2)

一方、児童生徒数をみると、古くは明治43年で100名を超え、大正2年の124名、昭和2年の125名となっており、近くでは校舎改築の35年に小学校児童115名、中学校生徒50名を数えたのを頂点として、以後は人口流出の影響を受けて減少しはじめ、55年度現在では小学生8名(3学級・教員4名)、中学生2名(1学級・教員3名)の小規模校となり、中学生は56年4月1日から八雲中学校へ通学している。
第18節 山崎小(中)学校
簡易教育所の創設
明治28年(1895)に愛知県の人、蟹江次郎が大規模地積の貸し付けを受け「蟹江農場」を創設した。その後31年には、同じ志を抱いていた孫の石川錦一郎がこれを譲り受けて「石川農場」と改称し、その翌年から小作人を入れて、本格的な拓殖事業を開始した。こうして山崎地区は、この移民受け入れによってにわかに活況を呈することとなったのである。
石川農場に入植した人たちの子弟は、既設の久留米校に通学させられていたが、通学距離は最高で8キロメートル以上にも達し、「常ニ幼少ナル児童ノ通学殆ト困難ヲ極メツツアリ、況ンヤ秋季ニ於ケル通路泥濘、冬季ニ於ケル積雪奄道ノ候ハ全ク通学杜絶」(明治38年開設のための議決書)という状況であった。一方、久留米校では地元の久留米農場の戸口が増加したこともあって児童数が増え、教室も狭くなって増改築の必要に迫られていた。このため、村をはじめ関係住民が協議した結果、山崎地区を分離して簡易教育所を設置することについて、38年8月の村会で議決を得た。そして翌9月30日正式に認可を受け、地域において急きょ校舎建設の準備にかかり、山崎神社の南側に600坪(約1980平方メートル)の校地を定め、農場主石川錦一郎が経費1030余円を負担し、このほか住民の奉仕作業により44坪(約145平方メートル)の校舎を建築して翌年1月これを村に寄付するなど、積極的にその開設に備えた。こうして、児童52名を収容し、翌39年4月1日を期して「山崎簡易教育所」が発足したのであった。なお最初の教員には、奥山鈴代という女教師が任命された。
開設後間もない41年4月に義務教育年限が延長されたことによって、児童数は当然増加し、これに対応すべき必要な校舎の増築と学級増設を、村費により措置するよう請願がなされた。しかし、村においては財政事情からこれに応ずることができないとしたばかりでなく、この教育所を再び久留米校に統合することを決めるなど、早くも存廃の危機に直面したのであった。こうしたことから農場主石川錦一郎は、事態の悪化を食い止めるため、苦しい経済状態にもかかわらず「設備および教員俸給の負担寄付」の条件を提示し、全学年の収容と2学級編制を出願してようやく存続することができたという。
ちなみに、41年度分経費として271円余の寄付を申し出ているほか、42年8月には1200円(うち住民負担130円)を投じて校舎32坪(約106平方メートル)を増築するなど、石川農場主にとってはまさしく大きな苦難であったわけであるが、学校創立の父として住民から称賛されているゆえんでもある。
小学校昇格の前後
明治42年8月に教室が増築されたあと、村から当局に対し簡易教育所のままでの学級増設について認可申請が出されたが、当時の特別教育規程による教育所は特別教授場とともに単級に限られ、2学級以上となる場合は尋常小学校とするという制度であったので、この申請は認可の対象とならなかったばかりでなく、遂に9月1日付をもって支庁から、尋常小学校に組織を変更するよう勧告されたのであった。 これを受けた村では、村会と対応策を協議したが、財政上の都合で直ちに実現は困難であるとして、翌43年度から変更することとした。このため、せっかくの2教室も公式には活用されないという状態に甘んじなければならなかった。そのうえ43年度になってもそのまま放置され、その年8月の村会で校舎や設備のいっさいを公有財産とする寄付採納の議決を経て、条件を整備してからようやく手続きが進められるという状況であった。このように難航した末、小学校令に基づいて組織を変更し「山崎尋常小学校」と改称されたのは、年の瀬も押し詰まった12月24日のことであった。昇格後の初代校長には、既に訓導として在勤中の近田久夫が発令され、学級もまた公式に2学級となり、面目を一新することができたのである。
しかし、関係書類がそろっていないこともあって、その理由が明らかではないが、この直後の44年3月に石川錦一郎は、私立小学校を設置する認可申請書を提出し、村役場を経て支庁に送達された。村としてもこれに賛成であったらしく、その後の支庁との照復の間に、山崎校の校舎および付属物いっさいを永遠無償貸付の見込みであることを報告している。結局9月になって「公立小学校ヲ廃止シテ私立小学校ヲ設立セントスル如キハ詮議不成相」としてこの願いは却下され、実現を見ずに終わっているが、他に例のない特異な出来事でもあった。
なお、簡易教育所の校舎を建築する際、石川錦一郎から校地として寄付採納の申し出がなされていた二反歩(約1980平方メートル)の土地は、大正2年に分筆整理されたが、これと同時に「教育普及進展は開拓の基盤である」という信念に立つ石川は、隣接する私有地六反歩(約5940平方メートル)をさらに提供して十分な校地の確保に努めるなど、教育環境の整備に協力を惜しまなかった。
大正13年4月からは3学級編制としたが、当時の八雲町は、1学級の定員を規定内最大限の80名と抑えていた関係で、児童数126名における学級増はその枠外の措置であるとして、増加負担分の全額について住民の寄付に依存しなければならなかった。このため、昭和2年4月から経費負担の都合で2学級編制に戻したが、昭和7年度には児童数が166名に達したので再び3学級編制としたのである。
中学校併置と校舎の移転新築
昭和16年(1941)4月に「山崎国民学校」と改称し、20年4月から高等科1学級を併置したことにより11月に高等科の教室を増築した。22年4月には「山崎小学校」と改め、同年5月に八雲中学校山崎分校が併置されたが、翌年4月から独立して「山崎中学校」となった。
校舎は次第に老朽化が激しくなり、改築の要望が高まってきたが、これと同時に漁家地帯や国道沿線の父兄から、児童生徒数の割合と通学距離などの関係で、校舎位置の変更を求める声が強く出された。一方、従来の学校所在地である山間部の父兄は、自然環境・由緒沿革・飲料水の適否などを挙げて、移設に反対する状況であった。
町においては、23、24年度と相次いで新築予算を計上して早期解決を図るとともに、24年10月町議会内に特別調停委員会(委員長・小川四郎)を組織して調停に乗り出したのであった。しかし、翌25年3月には「数次にわたる調停も今のところ成立の見込みがないため、部内双方の話し合いがつくまで敷地決定の件は延期するより外なし」という結論が報告される状況であり、以後も意見が対立し、問題は未解決のまま時を経過するだけであった。
こうしたうちにも昭和26年度には小学生178名、中学生73名を数えるに至り、早期解決に腐心していた田仲町長は、町議会や関係者と数次にわたって協議を重ね、27年3月の議会に対して予算および関連議案を提案し、校舎建築の方針を決定したのである。ちょうどこのころ十勝仲地震の影響を受けて、校舎の危険度はますます増大する状況であったので、その後協議は積極的に進められ、敷地を現位置(山崎375番地)に決定し、6月に石川斌郎・八未勘市からそれぞれ3000坪(約9900平方メートル)の寄付採納を議決するなど、実現に向かって着々と進められた。
こうして9月に入札を執行して10月に着工し、翌28年1月の仮検定を経て2月6日に移転のうえ授業を開始した。校舎は、木造平屋建て275坪(約908平方メートル)で、工費はおよそ580万円で、4月30日をもって落成したが、この間地域においては建築工事協力会を結成のうえ工事の早期完成に協力し、また、落成式協賛会を組織して7月2日に盛大な祝賀会を開催したのであった。
校勢の推移
児童数は昭和26年の178名、生徒数は29年の86名をそれぞれ最高とし、以後は児童生徒数ともに減少傾向をたどりはじめたが、38年に技術科特別教室など47坪(約155平方メートル)、39年に職員室など14坪(約46平方メートル)、41年12月には体育館116坪(約383平方メートル)を増築して、教育環境の充実が図られた。 その後も必要に応じて増改築が行われているが、児童数は40年度で100名以下、48年度には50名以下と減少して最盛期のおよそ4分の1となり、また、生徒数も47年度以降30名台に落ち込む状況となった。55年度現在では小学校児童数38名(3学級・教員5名)、中学校生徒数17名(2学級・教員6名)となり、八雲中学校新校舎完成によりこれと統合し、4月1日から生徒はスクールバスにより通学することとなった。
第19節 黒岩小学校
黒岩分校時代
海岸に奇岩があることから、古来アイヌ語で「クンネシュマ」と呼ばれ、やがて「黒岩」と称されるようになったこの地方は、早くから駅逓が設けられ、また、明治13年(1880)1月には郵便局が設置されるなど、交通通信の要衝として、また、漁村として開けたところである。しかし、児童の教育に関しては、明治13年に公立八雲学校が開設以来その通学区に属し、事実上は学齢児童全員が不就学という状態であった。
山崎小学校(写真1)

こうしたことを憂慮した住民は、16年5月に学校設立について協議を行い、村当局と折衝を続ける一方、寄付金を出し合って民家を買い求め、12坪(約40平方メートル)の教場を整備した。校地は吉田幸太郎の所有地を無償で借り受けてこれに当てた。こうして準備が整った17年1月23日「八雲小学校黒岩分校」として発足し、児童7名、教員には根岸善政が当たって授業を開始した。
明治23年9月に森田和平治から校地198坪(約653平方メートル)の寄付を受け、校舎をこれに移設(黒岩19ノ1)したが、その後も児童数が増加して校舎が狭くなったので、31年12月に増築し25坪余(約83平方メートル)の校舎とした。
学校の性格としては、当時の制度によって「変則小学」の初等科三か年を課程としてはじまったが、20年4月に「小学簡易科」三か年の課程へと移行し、さらに28年4月には「八雲尋常小学校黒岩分校」となり、第一類尋常科三か年の課程へと推移した。また、児童の学力向上を願う住民の希望によって、29年5月から修業年限二か年の補習科が付設された。なお、32年8月に本校である八雲尋常小学校が、第一類尋常科四か年制・高等科併置となったことにより、当校も「八雲尋常高等小学校黒岩分校」と改め、翌33年4月から四か年制へと移行した。
小学校に独立
明治34年(1901)4月には独立して「黒岩尋常小学校」となった。これは、上砂蘭部・大関・久留米の3校との同時昇格であったが、専任校長は直ちに発令されず、山県光麓が訓導兼初代校長として発令されたのは39年のことであった。この独立とともに住民の寄付によって校舎を増築し、46坪余(約152平方メートル)とした。
明治36年に若松農場、39年には中藤農場と相次いで開設され、これに100戸を超える入植者があり、そのうえ41年に修業年限が6年制となるなどもあって、児童数は急激に増加し、41年度で94名、43年度(4月から木村広胖校長、以後約18年在勤)で107名に達するという状況であった。このため校舎は再び狭くなり、41年度から二部授業をもって急場をしのいだが、いわゆるすし詰め教育を避けることができなかったので、44年4月から二学級編制に改めた。しかし、校舎を増築する資力もなかったので、及川兵発が私有建物を自費をもって改造し、12坪の教室を含む24坪を第二校舎として急ぎょ提供したのであった。
翌45年度にも児童が急増したので、第二校舎を一部増築して教室を16坪に拡張するなど応急対策を試みたもののこれも限界に達した。そこで住民協議のうえ、大正2年(1913)に新校地909坪(約3000平方メートル)を選定して買収し、地ならしをして村に寄付、校舎の移転増築を要請した。村もその実情を認め、旧校舎を移設のうえ増築して2教室、66坪余(約218平方メートル)の新校舎とした。この完成け12月26日のことであり、翌年1月からこれに移って授業を開始したのであった。
大正9年黒岩字区画に富岩特別教授場を開設し、児童28名を収容して授業を開始したが、この教授場は昭和14年3月に廃止された。
15年4月から修業年限二か年の高等科を併置して「黒岩尋常高等小学校」と改称し、全校4学級編制となった。高等科を併設したことにともない、同年5月に一教室を含む43坪余(約142平方メートル)を増築し、総坪数133坪(約419平方メlトル)、児童数218名となった。またこれと同時に、校門や石段を住民の奉仕作業によって設置した。
黒岩小学校 (写真1)

学制改革から現在まで
昭和16年の国民学校令によって「黒岩国民学校」となり、旧尋常科は初等科、高等科はそのままで授業が続けられたが、22年の教育制度の大改革により6・3制が実施され、小学校六か年、高等科が廃止されて新たに中学校三か年の義務制となって小学校内に併置され、「町立黒岩小学校」、「八雲中学校黒岩分校」とそれぞれ改称された。
27年には全住民とPTAから校内放送施設が寄付され、30年には林 一種、長谷川鎰、奥寺文雄の3名と八雲町漁業協同組合から新校舎敷地として1850坪余(約6150平方メートル)の寄付を受け、これに町が鉄道用地3000坪(約9900平方メートル)を購入し、31年6月にかわら棒ぶき木造2階建てモルタル仕上げの現校舎320坪(約1056平方メートル)を黒岩212番地に新築移転した。
昭和42年9月に鉄骨造116坪(約383平方メートル)の体育館が完成し、教育設備の充実が図られた。昭和56年5月現在では4学級、児童数43名という状況である。
第20節 黒岩中学校
併置中学校から独立技へ
昭和22年5月に「八雲中学校黒岩分校」として黒岩小学校に併置され、単級複式で授業を開始し、翌23年4月に独立して「黒岩中学校」となった。この当時の校長は小学校長が兼務で、28年6月に専任校長として高橋修造が発令された。この間、校舎は連年のように増改築が行われてきたが、31年6月に小学校が新築移転したことによって、旧校舎は中学校の専用となり名実共に独立校となった。このときの生徒数は110名で、三学級編制であった。
しかしこの校舎は、老朽化していたうえに国道と函館本線に挟まれた狭い敷地で、騒音やほこりに悩まされるなどの悪条件下におかれ、移転新築の早期実現が望まれていた。
たまたま昭和38年から国道5号線の拡幅工事が行われることとなり、校舎の一部がこの路線にかかるという問題が生じたので、ようやく移転が実現することになった。こうして翌39年に黒岩小学校の北側、黒岩644番の19に校地7920平方メートルを求め、7月に校舎新築工事が起工され、10月28日に1040万余円を投じた木造平屋建て822.36平方メートルの現校舎が建設されたのである。
さらに、43年12月には軽量鉄骨造376平方メートルの体育館(ほかに渡廊下34平方メートル)が建築され、教育環境の改善が図られつつ現在に至っている。
なお、生徒数は昭和40年度まではおおむね100名を超える状況ではあったが、以後はわずかずつ減りはじめ、52年度で50名を割り、56年度では40名、3学級となっている。
黒岩中学校(写真1)

第1節 白滝特別教授場
下の湯の開拓と教育
明治36年(1903)に岐阜県の人後藤光太郎が、隣村上濁川から落部川の左岸に国有地の払い下げを受けて移住し「後藤農場」と名付け、また地名も郷里にちなんで「加賀野」と称して開拓に着手したのをはじめ、これと前後して牧場を経営するものが相次いだ。すなわち、相木国太郎の相木牧場、瀬川安五郎(秋田県)の瀬川牧場、渡辺文八郎(同)の渡辺牧場などがそれである。しかしこれらは、農耕主体の開拓というよりも、その名のとおり牛馬の繁殖を目的とするのと同時に、地内の立木を利用する炭焼き人の入植が主体という状況であった。
こうした入植者たちにとって、直ちに問題となったのが子弟の教育であった。しかし、当時この地帯には本格的な道路もなく、本村の落部へ出るにもがけの上の小道によるか、または川を渡らなければならないという状況のもとでは、児童が落部校まで通学することは至難なことであった。そのため、この地帯の児童はほとんどが不就学のまま過ごさざるを得ない状況であった。ただひとり後藤農場主の長男光男だけは、幸い落部の知人宅に預けられて通学することができたという。
特別教授場の開閉
こうした状況を憂慮した農揚主後藤光太郎は、地区内の有志らにはかるとともに協議をまとめて学校設立に奔走し、明治42年1月に瀬川牧場のきゅう舎の一部を改造して教場に当て、私立教授所を開設した。当初はこの教授所を「光栄」と名付けたが、間もなく土地にある滝を象徴として「白滝」に改めたという。
開設後間もない4月1日には茂無部(現、栄浜)の「恵海」と同時に、特別教育規程に基づく「落部尋常小学校付属白滝特別教授場」と公称されるに至った。しかしこれまた恵海と同じく4年生までを収容するもので、5、6年生は落部の本校に通学するものとされていたので、事実上は停級のまま学齢を超過し、中途退学となるのがほとんどであった。なお校舎は、大正2年(1913)8月の暴風雨によって倒壊するという事故にあったが、地域住民の協力により新たに教場を建て、9月21日に授業を再開した。
大正13年にはこれまで交通上の難所であったがけ下に道路が開削され、交通事情も好転したので、比較的落部にも近く児童数も少なかったため、翌14年3月限りをもってこの特別教授場を閉鎖することとなり、開設以来わずか16年をもって幕を下ろしたのである。このときの在校生は36名であり、このうち白水沢方面の児童6名は、上の湯特別教授場に通学することになった。
第2節 上の湯小学校二股分校
開拓分校の設置
戦後緊急開拓事業の開始とともに、各種の開拓用地として国有地が解放されると、落部上の湯の二股地区へも入植者が多くなり、これらの子弟に対する教育も解決しなければならない大きな課題であった。特にこの地区は、上の湯小学校までの通学距離が8〜10キロメートルと遠かったため、低学年の通学は体力的にも無理で、冬期間は不就学児童も出るという状況であった。
また、こうした辺地への入植者の中には、入植してはみたものの経営が困難なうえ不便なため離農するものも出はじめ、二股32番地に入植した松田兼松も住宅(ブロック造)建築後まもなく離農し、その後に入植するものもなく空き家となっていた。そこで住民は、この住宅を仮校舎として分校を設置するよう村に要請した。これにより昭和31年10月に認可を受け、翌年1月から「上の湯小学校二股分校」として、10名の児童によって開校したのである。
32年4月の落部村と八雲町との合併条件のなかにも「落部開拓分校新築」の一項が入れられた。
32年7月には上の湯小学校の寺沢栄二が分校勤務を命ぜられた。分校は1年から4年までの低学年を対象にし、5、6年生は本校である上の湯小学校へ通学させるというものであった。
昭和32年8月20日に二股分校新築工事の入札を行い、小山田組が140万円で請け負って工事を進めた結果、同年12月10日に木造亜鉛鍍鉄板ぶき平屋建て、建坪45坪(約148・5平方メートル)で、教室・職員室・廊下・昇降口・水飲場・宿直室・その他が完成して26日に落成式が行われ、児童14名、教員1名をもって新校舎で授業が開始された。
この分校は、高度へき地学校ということで、40年から業者との特別契約による学校給食が実施され、また道職員が行っているへき地校へのテントや図書などの寄贈もあって、教育環境の整備が進められた。
しかし、35年以降は開拓者の離農が相次ぎ、児童数も37年に1けた台となり、42年には2名の児童が5年生になって本校へ通学することとなり、在籍数はゼロになった。このため、分校として開校以来11年をもって、その歴史を閉じることになったのであるが、この間の在籍児童教は99名であった。
第3節 桜野小・中学校
草創期の寺子屋教育
野田追川を20キロメートルほどさかのぼったところ、横山や小鉾岳のすそに広がる野田生原(現、桜野)は、明治36年(1903)に60余万坪(約200ヘクタール)の未開地が野田追原殖民地として区画、解放されたことにより、その貸し付けを受けた森田市太郎ら6戸が37年6月ここに入植したのをはじめとし、以後も年を追って入植者も増え、開拓が進められた所である。
もちろん当時はこの地に通ずる道路もなく、およそ10年後の大正3年(1914)6月に野田生原殖民道路が開通するまでは、落部村の野田追から蕨野を経て山を越え、野田追御料地からさらに川を越えて当地に至るという径路であったという。
このような地理的悪条件下にあった入殖者たちは、子弟教育について直ちに苦慮することになったが、公設教役場の設立を村に申請しても、いまだ戸口が少ないという理由で容易に聞き入れられなかった。このため住民は、入植直後の困窮の中であったが、やむを得ず私設教授場を設置することとし、掘立式で板張りの粗末なものながら、21坪(約40平方メートル)の教場を造り、これに「野田生原教育所」と名付け明治40年5月17日に授業を開始したのであった。このときの入植者は12戸で、教師には館下慶三郎を雇ったが、病気のためおよそ1年後に辞職したので、その後は酒田久太郎に引き継がれている。
なお当校の沿革誌によると、この教育所は寺子屋式で読書・習字・そろばんを主体とし、修業年限や授業時数などは特に決まりはなく、農繁期には休み、余暇があれば随時集めて際限もなく続けたり、秋の夜長には夜学もする状況であったと記されている。
野田生原特別教授場の公設
私設の教育所を設け、自力で子弟教育に努めたのであるが、入植後日も浅い少数の住民にとって、教員の俸給その他いっさいの経費を負担し続けることは容易なことではなかった。しかし、その困難に耐えつつ3年を経過したのであるが、明治43年(1910)には入植者20戸、児童数も16名となり、既設の建物では狭くなった。また、地区内の開拓区域が広がるにつれて、教育所の位置が偏りすぎて通学の不便を訴える声が高まり、早急に移転改築しなければならないという事態になった。
こうした問題を打開するため、住民は村当局に対して教授場の公設を要請し続けた結果、ようやくこれが認められることになり、位置を地区の中央に定めて校地900坪(約2970平方メートル)を求め、住民の寄付と労力奉仕によって校舎20坪(約66平方メートル)を建築して開設に備えた。こうして、住民念願の「大柏野教育所付属野田生原特別教授場」が設置され、教員に吉田宇太郎を迎えて授業が開始されたのはその年8月1日であった。ただし、翌44年4月には本校である大柏野教育所が野田生尋常小学校と改称されたので、当校の呼称も自動的に「野田生尋常小学校付属」となった。
なお、古田宇太郎は教育熟心な教師として、校下父兄の信頼を集めていたが、大正2年3月9日の夜、公務による外出の帰途猛吹雪のため道に迷い、学校付近の雪の中で凍死するという事故に遭った。その死を悼んだ住民は、地域住民葬をもって手厚く弔ったという記録が残されている。
尋常小学校への昇格
校勢に直接影響を及ぼす地域の入植状況は、大正3年新たに特定地15万坪の貸付が行われたこともあって、同5年には30戸を超え、10年には50戸、さらに15年には36戸と増加し、現在では想像もできないような活況を呈した。こうしたことから児童数も大幅に増加し、大正10年には62名を数える状況であった。なおこれには、落部村に属する野田追御料地への入植者の子弟受け入れによるものもあり、6年1月の村会の記録に、
「隣村落部村ノ委託ニヨリ仝村御料地附近ノ児童約十名ヲ野田生原特別教授場へ収容セントスルニアリテ一昨年来ノ懸案ナリシカ今回大正六年度ニ於テ委託料百円大正七年度以隆ニ於テ五十円宛提供スル条件ヲ附シタルモノニシテ……。」
とあり、正式にこれらの児童を当校に受託することになっていた。
こうした情勢に対応して、校舎は大正7年に併設住宅を独立住宅に移し、内部を模様替えして教室を広げたのをはじめ、以後もしばしば増改築を行い、昭和4年(1929)には創設以来のささ屋根をまさ屋根に改修したのであるが、これらはすべて住民の奉仕作業によって維持されたのであった。
第一次世界大戦終了後に訪れた農村不況の余波と、木炭業者の転住続出により、昭和初期から減少しはじめていた戸数も9年には36戸となり、児童数も48名まで減少したのであったが、町では4月1日に認可を受け、同じく特別教育規程による「野田生原尋常小学校」に昇格させた。そして初代校長に斉藤堅造を配して体制を一新すると同時に、同年8月には一教室20坪(約66平方メートル)を主体とする校舎38坪(約125平方メートル)を整備して環境の改善を図った。
さらに、翌10年4月には時局の要請に応じ、教育の普及向上を図るため、八線・鉛川・赤笹の各校とともに、小学校令による小学校に組織変更され、その面目を整えたのであった。
中学校併置と小学校の廃校
昭和16年4月に「野田生原国民学校」と改め、22年4月には「野田生原小学校」と改称されるなどの経過をたどったが、このときの児童数は22名にまで減少していた。したがって、27年4月当校に「野田生原中学校」が併置され、新たに生徒12名を収容することになったのであるが、さしあたっては既設の教室を二分することで対応できたのである。
昭和31年4月には、野田生原という校名は他に類似名が多くて紛らわしいということから、翌月実施された字名改正に先駆けて「桜野小学校」と「桜野中学校」にそれぞれ改めた。34年10月には教育環境の改善と地域の振興という観点から、集会場を兼ねるへき地集会室や中学校の専用教室10坪など計33坪(約109平方メートル)を増築した。
しかし、その後に訪れた離農転出者の続出により、児童も急激に減少しはじめ、小学校においては過去30年にわたって20名台を保ってきたものが、4.年度にはついに17名となり、さらに44年度は9名と激減し、47年度で最小限の1名が卒業してしまい、在校生はゼロとなった。このため、48年3月限りをもって小学校は廃校したのであった。
輝かしい校史に幕
小学校は廃校となったのであるが、中学校には生徒5名が在校していたので単独校となり、校地や校舎もすべてこれに引き継がれたのである。しかし翌49年には2名、50年度には1名となる見通しになったので、4月からこれを格下げして「野田生中学校桜野分校」とし維持すること1年、同年度の終了とともに在校生がなくなったため、51年3月限りをもって姿を消すことになった。
こうして明治43年特別教授場として開設以来、中学校が廃止となるまで、通算66年の輝かしい校史に幕を下ろし、いまは桜野24番地に校跡碑を残すのみとなった。
桜野小中学校(写真1)

第4節 熟田小学校
開拓の創始と寺子屋教育
この地帯はハシノスベツ川とボンオコツナイ川に挟まれており、古来「常丹(とこたん)」と呼ばれていた。明治26年(1893)俗に出戸(でど)といわれる海岸近くの段丘地に、愛知県の人水野鎌吉ら5名が入植して開拓を進めたのを初めとし、その後も奥地一帯に29年の27区画、30年の20区画というように未開地が解放され、多数の入植者によって本格的に開拓が進められるようになった。
当時この地帯は山越内村に属していたが、山越内村は財政力が弱く、村内ただ一校の山越内尋常小学校を維持するのが精一杯という状況だったので、常丹地区も山越内校の通学範囲に含まれていたのである。したがって通学距離はあまりにも遠すぎ、子弟にとっては非常な困難がともない就学率もきわめて低かった。しかしこのまま不就学で過ごさせるわけにもゆかず、住民は入植直後の貧苦にめげず協調し合い、私設教授場を設けることを決め、現在は河井氏所有地の一角に教場を建て、入植者のひとりである寺島某を教師に、児童7、8名を集めて寺子屋式教育を始めたと伝えられている。なお、これ以上の詳細を伝える記録は残されていないので、開設時期、期間、規模などについては、いっさい不明である。
常津内簡易教育所
明治35年(1902)に山越内村と八雲村が併合され、二級町村制施行の新生八雲村となったのであるが、これを契機として地区の人々は、同じ状況下にあった野田生地区の人々と提携して運動を続けた結果、簡易教育所の設置について村会の議決を得たのであった。(この項野田生校参照)
この簡易教育所は、時を同じくして開拓が進められていた奥津内地区との合同設置とするものであったので、両地区協議のうえ、校地は双方の中間に当たる通称西の沢の常丹地区内(現、浜松の林氏所有地)に定めて上申の結果、同年8月3日に「常津内簡易教育所」として認可となり、初代教員に折居精一郎を迎えて開校したのである。しかし、これについても詳細な記録がないので、校舎の規模や開校日などは不明であるが、当時の情勢から推測すると、校舎の建設は認可後において行われるのが通例であり、また、村役場から山越内小学校長にあてた関係児童に対する転校通知書によると、実際の開校日は11月5日かもしくはそれ以後のことと思われる。
常丹(簡易)教育所
常丹、奥津内の両地区とも、それぞれ奥地へ向かって開拓が進められるようになると、この簡易教育所も双方にとって通学不便となり、これを二校に分離することについて協議がもたれるようになった。その結果、明治37年2月に村会の議決を経て、翌38年5月認可の手続きを行い、その年6月に奥津内簡易教育所が開校されて関係児童が転校した。これにより、それ以後常津内簡易教育所は常丹地区の単独校となった。
(この項浜松校参照)
こうした経過をたどり39年7月16日に認可を受け「常丹簡易教育所」と改称されたが、41年4月に簡易教育規程を吸収して制定された新特別教育規程の適用により、自動的に「常丹教育所」と改められた。なお、このときから義務教育年限が六か年に延長されたが、当教育所はこれまでどおり4年生までの収容にとどめられ、5、6年生は八雲校に通学させるという措置がとられていた。
しかしこうして単独校になってみると、校舎位置の偏りが問題となり、とくに明治42年に野呂山と呼ばれたハシノスベツ方面(現、町営育成牧場)の入植が進められてからは緊急課題となった。そこで住民は話し合いのうえ、地区の中央に移転することとし、同年11月に現熟田225番に一教室とその他を合わせ38坪(約315平方メートル)の校舎を建築して移転した。
なお、このあと大新高台の常丹牧場跡に入植した開拓者の子弟も、この教育所に通学することとなった。
尋常小学校への昇格
明治43年には地区内の戸数が100戸に達するようになり、児童数も増加したので翌44年には校舎の一部を増築した。しかし大正2年(1913)村では、
「現在児童数八十余名ニ達シ新入学児童ヲ見積ルトキハ到底一教室ニ収容スル事能ハサル……。」(同年第一回村会会議録)
とあるような状況に対応して、一教室の増設を含む29坪(約96平方メートル)を増築するとともに、これまで八雲校に通学させていた5、6年生もすべて収容することとした。こうして6月20日に2学級編制が認可となり、さらに翌3年5月29日には組織変更の認可を受けて「常丹尋常小学校」と改称し、初代専任校長に福田三良を迎えたのであった。この時点では地区内の戸数も120戸を数え、大正4年度の児童数は実に139名に達するという絶頂期でもあった。
しかし、大正5年4月に大新特別教授場が設けられたことにが設けられたことによってその方面の児童が分離し、さらに8、9年以後の農村恐慌によって多くの離農者が続出、校勢も衰退の一途をたどることになった。のちの学校火災によって記録の一切を焼失したため、詳しい史料は得られないが、昭和8年には児童数が49名で 既に一学級編制となっており、以後しばらくの間は50名を前後するという状況が続いていた。
学制改革から廃校まで
昭和16年4月「常丹国民学校」と改称、戦後22年4月には「常丹小学校」と改められたのち、31年5月の字名改正により「熟田小学校」と改められたが、結果的にはこれが最終校名となったのである。
一方、校舎は全体的に老朽化したため、26年に普通教室1を主体とする56坪(約158平方メート
常丹小学校(写真1)

熱田小学校(写真2)

ル)をもって改築したのであるが、35年2月24日に給食堂の天井裏から出火してこれを全焼するという災禍に見舞われた。そのため復旧が急がれ、新年度早々に校舎建築に着手し、同年6月に2教室など55坪(約182平方メートル)が完成、それまで部落会館を使用して行われていた授業は7月1日をもって解消されたのである。
記録のある限りにおいてみると、33年までは30名台にまで落ち込んでいた児童数が、34年から38年までの5年間だけは再び40名台になっていた。そのため38年4月から2学級編制で3教員が配されるなど、質的な向上が図られたのである。しかし、このころから急速に進んだ離農によって児童教の減少もはなはだしく、40年の31名、42年の21名、44年の12名という状況が続き、1学級への後退を余儀なくされた。
さらに、47年9名、50年6名と減少の一途をたどり、しかもこの年には6名のうち4名が卒業して新入学予定者なしという事態を迎えた。こうしたことから関係者協議の結果、51年3月31日をもって廃校することに決定、創立以来74年にわたって、地区の歴史とともに歩み続けた長い校史についに幕を下ろし、八雲小学校に統合したのであった。
第5節 熊嶺小・中学校
分校設立の前後
昭和21年に戦後の緊急開拓地として大新の奥、砂蘭部川沿いの国有地が解放され、これに15戸の入植者を迎え入れたのが いわゆる能嶺地区開拓のはじまりである。開拓当初のこの地には教育施設がないのは当然で、就学対象児童は最寄りの大新分校に在籍し、これに通学しなければならなかった。
しかしこれら児童の通学が困難をきわめたことは当然だったため、旧軍用建物の解体材を使い、教員住宅を含めてわずか7坪という仮校舎を地区内に建て、昭和24年4月の分校開設を目指したのであるが、設備が不十分ということで延期され、大新分校に通学していた児童13名を収容し「八雲小学校熊嶺分校」として開校したのは、その年7月1日のことであった。
翌25年4月に大新分校が昇格して大新小学校となった機会にこれの付属となり、校名も「大新小学校熊嶺分校」と改称された。また、同年8月には開拓事業入植施設補助規程による国費補助を受け、新校舎45坪余(約149平方メートル)と教員住宅16坪余(約53平方メートル)を建築して整備を図った。
一方、中学生については、入植当初から13キロメートル余りも隔てた八雲中学校の通学区域とされていたが、事実上は通学不可能な状態であった。こうした不便を解消するため、町では昭和26年7月から熊嶺分校(小学校)の教員による委託授業方式を採用したのであった。
小・中学校の独立から廃校まで
体制の整備が進められるにともない、昭和27年4月独立して「熊嶺小学校」と昇格したあと、その年11月には「熊嶺中学校」の設立が認可されるなど、併置校ではあるがいずれも独立校となり、学校としての面目を整えたのである。
熊嶺小中学校(写真1)

熊嶺小・中学校校門(写真2)

熊嶺小・中学校校跡碑(写真3)

しかしこの地区は、引き続き新規入植者を迎える素地がなかったことから、児童生徒数も増えることなく、小学校では昭和32、33年の21名、中学校では28年の11名が最高であった。
しかも、昭和40年代に入って訪れた山間辺地における離農者の続出は、この地区においても例外ではなく、年を追って離農者をみるようになった。この結果、47年度当初は小学校児童6名、中学校生徒5名が在籍したものの、小学校では10月に2名の児童が転出したので、教員の子4名だけが在籍することとなり、中学校においては同月15日をもって在籍生徒がゼロになるなど、学校の存在意義を失うに至った。こうしたことから廃校のための準備が進められ、同年12月1日八雲小・中学校にそれぞれ統合という形式をもって、大新431番地に校跡碑をとどめ廃校したのであった。
第6節 上鉛川小・中学校
開拓当初の私設教育
明治40年(1907)に遊楽部川と鉛川の合流点からさかのぼることおよそ10キロメートルから22キロメートルにわたって広がる地域の官地が区画解放された。すなわち、ペンケルペシュベ殖民地中の基線地帯で、当時の入植者はこれを奥鉛川と呼び、のちに上鉛川と呼ぶようになった地域である。
41年には渡辺久三郎ら5戸が入植して開拓を進めたことを初めとし、年を追って入植者が増加して44年には早くも40戸を超えるという状況であった。しかし当時のこの地域にはまだ道路もなく、入殖者たちは山越えして入地するという実情であったといわれ、開拓の進展と並行して、雲石街道の開削が進められていた。
こうした状況のもとに入植した人々の懸案となったのは、子弟の教育であった。地域は鉛川に沿った細長い地形であるため、下流地帯の児童は鉛川特別教授場に通学することができたが、上流地帯の児童は、 「憐ムベシ其ノ教ヘヲ受クルコト能ハズ。然リト雖治勢ノ為スガ儘ヲ待ツコト暫クナリ。」(明治45年1月の陳情書から)
という状況であった。このため、住民=鉛川親睦組合は期成同盟会を組織して総力を結集し、村当局に対して前記のような事情を訴え、教育所の創設を陳情したのである。さらに雲石街道工事に使用した土工部屋を買い受け、これを修繕して教場用に整備し、11月ここに公設の「奥鉛川簡易教育所」の設立を請願し、児童に教育の場をと訴えたのであった。
この実情を認めた村当局では、大正2年(1913)1月の第一回村会に諮り、特別教授場の新設について議決を得たのであるが、その見通しを得た入植者たちは、公設に先駆けて同年2月教員に末松謙を雇い、児童を集めて私設教育所を開設した。しかし、期待に反して公設が容易に実現しなかったため、入植早々の住民にとっては、私設のままこれを維持し続けるだけの資力もなく、翌3月限りで廃止せざるを得ないという悲哀をかこった。
特別教授場の開設
前述のように大正2年の村会において特別教授場の新設が議決されたものの、村は地域民が準備した建物が公設教授場の施設としては不適当であるという理由で、開設を見合わせるという状況になった。この当時は、特別教授場の施設や設備は地区の負担で整備し、村では教員の俸給だけを負担するというのが通例だったので、村がその建物や設備を不適当と認めた以上やむを得ないことでもあった。
しかし村としても、いつまでもこれを放置しておくこともできず、これを仮校舎に当て「八雲尋常高等小学校付属上鉛川特別教授場」を創設し授業を開始するに至ったのは、設置議決以来実に1年以上も過ぎた大正3年四月10日のことであった。このときの戸数は42戸で、入学児童は24名、教員には大江安藤が任命された。
翌4年には児童が32名に増加したのに加え、仮校舎が余りにも粗末なばかりでなく、建築場所が低湿地だったため早急に改築を迫られることとなった。そこで住民協議のうえ、校地にペンケルペシュベ基線10号58番地(当時田中今吉所有)を選んで借り受け、寄付金160円余を集めて村からの補助金100円と合わせ、出役奉仕をもって同年9月に新校舎を完成し、ようやく施設の整備を完了したのである。なおこれ以後も、資力に応じて連年設備の整備に協力が続けられたという。
昇格と中学校の併置
大正5年度には児童敬36名を数え、以後も引き続き増加が予測されたが、結果的にはこの年が頂点として記録されることになった。しかし、12年度までは30名台を維持したのであるが、13年度に20名以下に落ち込み、その後昭和3年になって再び20名台となり、以後は約10年間この状態を続けた。
昭和16年4月の国民学校令とこれに関する訓令などの施行によって、自動的に「八雲国民学校上鉛川分教場」と改められ、さらに22年4月「八雲小学校上鉛川分教場」と改称、その後25年10月1日に昇格し「上鉛川小学校」として独立したのである。その直後に初代校長として白井正二が任命され、26年2月には初めて二教員制となり、教育内容が充実されたのである。
一方、これよりさきの26年1月からは、八雲中学校まで遠距離通学を強いられていた中学生(当時3名)を、小学校で委託を受けて教授する方式が取り入れられていたが、翌27年9月正式に「上鉛川中学校」が発足して小・中併置校となった。
また、建築以来およそ40年を経過して老朽化した校舎の改築が急がれることとなり、町は29年10月に49坪(約162平方メートル)の校舎を建築した。
上鉛川小中学校(写真1)

校勢の退潮と統合
小学生20名、中学生8名という体制で、校舎も改築して面目を新たにしたのであるが、間もなく過疎化現象の影響を受け始め、昭和34年には小学生10名、中学生6名とほぼ半減し、5年後の39年には小学生3名、中学生が4名となるなど、予想外の退潮ぶりを示したのであった。
こうした状況によって、折から町教育行政の課題となっていた学校統合における最初の対象校として取り上げられたのである。そして、残ってレるわずかな住民たちと協議が進められた結果、児童生徒の通学輸送を要件として円満に話し合いがまとまり、昭和40年3月31日限りで廃校し、4月からは八雲小・中学校へそれぞれ統合されることになった。
こうして、創設以来51年間にわたり、常に地域の苦楽とともに歩み続けてきた上鉛川校史にピリオドが打たれ、いまは鉛川456番地に校跡碑をとどめるのみとなったのである。
第7節 八雲鉱山小・中学校
特別教授場の開設
古くは遊楽部鉛山と呼ばれ、延宝2年(1674)には既に銀・鉛・金などを採掘していたといわれるこの八雲鉱山は、八雲市街地からおよそ24・5キロメートルも離れた山間部にあり、鉱山としてもその生産高に限界があったため、幾たびか経営者が変わり、大きく発展することもなく時機に応じて受け継がれてきたにすぎなかった。
しかし、昭和6年(1931)に八雲鉱業株式会社が経営するようになり、当時の主産物であるマンガン拡が脚光を浴びるようになってからは、経営規模もしだいに拡張されて稼働者が続々と入山するようになった。
これにともなって義務教育対象児童も増加し、昭和9年当初には戸数24戸、児童20名を数えるようになった。このため会社では、これら子弟の教育を1日もゆるがせにでぎないこととして町と折衝し、将来において校舎や設備は会社側で建築整備するが、取りあえず鉱夫長屋を仮校舎に当て、机や腰掛けなど設備の全部を負担すること、教員の俸給や消耗品など経常経費の半額を会社で寄付することを条件に、児童20名をもって9年5月20日「八雲尋常高等小学校付属八雲鉱山特別教授場」として開校し、教員には斉藤左一郎が任命された。
その後会社は、27坪(約89平方メートル)で教室12坪・教員住宅併設の新校舎を10月に建築したのであったが、以後も児童が増加したので、11年11月には教室6坪を増加するなど施設の充実を図った。
尋常高等小学校に組織変更
昭和11年に八雲鉱山は中外鉱業株式会社の経営となり、日中事変による軍需の増大にともなってマンガンの増産が要請され、事業規模を拡張していた。そのため児童も急激に増加し、そのうえ尋常科を修了した者に対する教育にも配慮しなければならないという状況に直面していた。
こうしたことから昭和15年に会社では、新たに校舎を建築して会社経営の継続中は無償で町に貸与すること、需用費など経常経費の一切を寄付することなどを条件として提示し、これまでの特別教授場を廃して高等科を併設する小学校に組織変更するよう、町に対して請願を行った。町はこれに応じて同年2月に町会の議決を経たうえ「八雲鉱山尋常
高等小学校」の設置を決めて申請の結果、3月26日に認可されたのであった。その後、校地(国有林八雲林班736坪=約2429平方メートル)の使用認可を受け、新校舎98・75坪(約326平方メートル)を9月に完成、児童数は60名で2学級編制をもって発足し、初代校長として斉藤順蔵が赴任した。
翌16年4月に「八雲鉱山国民学校」と改称されたあと、22年4月に「八雲鉱山小学校」と改められたが、これとともに新制度による「八雲中学校八雲鉱山分校」が併設された。同分校は翌23年4月に独立して「八雲鉱山中学校」となり、小・中併置校となった。このため校舎が狭くなり、25年に中学校専用校舎として27・5坪(約91平方メートル)を増築した。さらに31年6月には地区内の各種会合に供用する目的をもって、へき地集会室41坪(約135平方メートル)などの増設が行われるなど施設が整備されていった。
なお、学校の経費に対する会社側の寄付も、その後は全く廃止され、校舎も町に寄付されたのであった。
校勢の衰退から廃校へ
昭和30年に小学校児童129名(3学級)、中学校生徒62名(2学級)を数えたうえ、さらに増加傾向を示し、中学生は50名前後と横ばいながら、小学生は34年から36年にかけて150名を超えて4学級となり、いねば最盛期といえる状況であった。
このような児童生徒の急増により教室が不足したため、町は35年に中学校専用校舎として2教室を増築するとともに、小学校校舎の一部増築と修繕工事を行い、9月にこれを完成させるなど施設の充実に努めた。
しかし鉱山が、主鉱であるマンガンの埋蔵量に限界との見通しになってきたのはこの直後であり、37年には大規模な縮小配転が行われたことによって、翌38年当初の在籍数は小学校90名、中学校37名と激減し、その減少傾向はなおも続いたのである。
こうした情勢のうちにも、町は39年に理科実験室35・75坪(約118平方メートル)、40年にはへき地集会室66坪(約218平方メートル)を新築するなど整備に努めた。
一方、中外鉱業株式会社では40年から八雲鉱業株式会社にその経営を移して継続を図ったのであるが、生産額の減少やその他の悪条件が重なり、ついに44年4月限りで採鉱中止のやむなきに至ったのである。
したがって44年4月当初では、小学校39名、中学校14名が在籍していたが、採鉱中止の決定によって転出者が続出し、会社の残務整理の進行とともに児童生徒はゼロとなったので、同年7月31日限りをもって廃校となり、特別教授場として開校以来35年にして校史に暮を下ろしたのであった。
八雲鉱山小中学校(写真1)

第8節 八線小学校
特別教授場時代
当校下の区域は、ペンケルペシュベ殖民他区画の6線から9線、4号から12号に囲まれた区域で、俗に「八線」と呼ばれた他帯である。この他の開発は、明治38年(1905)3月に福島県の人石川竹三郎が、5戸の小作人を引き連れて入植したのにはじまるが、以後も逐次入植者を迎えたことにともない、その子弟教育に配意した石川夫妻が、40年6月自宅に子供たちを集め、寺子屋教育を始めたのがこの地帯における教育の芽生えであった。
しかし、このような私設の状態を長く続けることもできないばかりでなく、幼い子女を大関校まで通学させることも困難であった。そのため、戸口も増加してきたこともあって、村当局に対して公設教授場の開設を要請し続けた結果、明治43年の村会において議決がなされ、ようやく実現の見通しが得られたのである。そこで、石川竹三郎を中心に住民は協力し合い、ペンケルペシュベ406番地に校地を定めて校舎を建築し、懸案の教授場開設に備えた。村ではこれに「大関尋常小学校付属ペンケルペシベ特別教授場」と名付け、教員に猪巻安千代を迎え、同年6月1日から授業を開始した。しかしこの校舎は、翌年5月に野火のため焼失するという災厄に見舞われたので、住民は再び協力し合って再建に努力し、その年の暮れも迫った12月、教員住宅を併設の校舎26・5坪(約87平方メートル、うち教室46平方メートル)を建築した。なお、この特別教授場は、開設当初から4年生までを収容するものとされ、5年生以上の児童は本校である大関校に通学させるという措置がとられていた。
仮名書きの校名は「不便不尠」という支庁からの勧奨(明治44年)もあって、大正4年(1915)4月に「八線特別教授場」と改称した。この八線という名称は、教授場の位置を表し、また、一般に地区の総称として用いられてきたことから名付けたものであったが、村の改称案に対して、支庁から「数詞と誤解セラルベク」とし、ペンケルペシュベを意訳した「上路(うわじ)」とするよう再考を求められたが、村では原案で押し切ったという経緯もあった。
尋常小学校への昇格
入植者が引き続き増加の傾向を示し、大正9年には児童数も52名を数えたため、町は鉛川・赤笹の2校とともに認可を受け、4月1日から「八線小学校」と昇格改称することとした。これと同時にこれまで大関校に通学していた5年生以上の児童も収容することとしたのである。しかし、制度的には特別教育規程による小学校であって、小学校令によるそれとは異なる取り扱いを受けるものであった。
第一次世界大戦後に訪れた不況は、山間辺地の農業地帯を直撃し、大正10年の児童数60名を頂点として減少しはじめていた。そのため小学校令による小学校へ昇格させるべき体制が整わず、大正15年と昭和7年の2回にわたって、特別教育規程の適用延長について特認を受けるという状況が続いた。
明治44年に建築した校舎の老朽化と校下居住者の分布状況の変化に対応して、昭和8年(1933)にペンケルペシュベ263番地(現、上八雲769番地)に校舎を移設、模様替えの工事を行い、29坪(約96平方メートル)に別棟の教員住宅を配して整備した。また同時に、教育の普及向上を図るため、鉛川・赤長の各校とともに過去15年にわたる
八線小学校(写真1)

特別教育規程の長期適用を脱して、これを小学校令による小学校に昇格させたのである。ただし、この昇格時の児童数は32名にまで減少しており、15年には25名となるなど、退潮傾向は依然として続いていた。
このあと制度の改正によって昭和16年4月「八線国民学校」となり、22年4月には「八線小学校」と改められるという経過をたどるが、この間にも児童数は減り続け、18年には14名、終戦時の20年には9名というところまで減少していた。
校史に幕を下ろす
戦後、新規入植者の迎え入れもあって、児童数も若干増加の傾向を見せるようになり、低い水準ではあったが常に10数名前後で定着していた。そのうえ39年9月には児童15名ながら教員配置基準の改正によって、初めて二教員割となり教育機能の質的な向上が図られていった。
しかし、このころから始まった離農による転出が急激に進み、昭和46年に4名となった児童がその年2名の卒業生を送り出し、その後は新規入学もなく翌年2名で継続したが、そのうち1名が中途で転出したので12月には最小限の1名となった。しかも将来において入学する児童もなく、その教育効果が期待できない状況と判断されるに至ったので、町は48年1月限りをもって廃校とし、2月から大関校に統合して開設以采63年の校史に幕を下ろしたのであった。
第9節 大関小学校夏路分校
教育の草創期
サックルペシベ(略称サックル)と呼ばれたこの地帯は、明治33年(1900)に利別−八雲間の仮定県道が開通し、翌年11月旅行者のためここに夏路駅逓所が設けられ、その管理人となった岩間儀八の努力によって35年に官林が解放されることとなり、にわかに開発が進められるようになった。 岩間は、こうして急激に増加した入植者たちの子弟教育に種々腐心したのであるが、この地域から大関校まで通学させることは、きわめて困難なことであった。そこで入植者を説得し、駅逓の物置9坪(約30平方メートル)を改造して5坪の教室のほかに所要施設を設け、入植者一同で教師を招くこととした。
こうして岩間の縁者である大岡兎喜男を美唄から迎え、37年6月児童6名を集めて私設教育所を開設したのが、この地帯における教育のはじまりである。しかしこの教育所は、教科書はおろか教具らしいものもなく、机や腰掛けなども各自が持ち寄ったものであり、そのうえ生徒一人五〇銭ずつを集めて教員の給料とし、教員の食糧も住民が負担する状況であったという。
このような私設教育所の維持は、新開地の住民にとって大きな負担であり、38年3月に住民12戸は、連署をもってこれを公設にするよう村当局に願い出たが、村の財政困窮もあって直ちには認められず、これが実現したのは9月になってからであった。こうして「大関尋常小学校付属サックルペシベ特別教授場」が創設され、このとき建てられた12坪(約40平方メートル)の校舎は、住民の寄付によるものであった。
このようにして設置された教授場ではあったが、児童教が予想外に伸びず、しかも一方ではトワルベツ地帯の開拓が進み、ここにも41年12月に仮校舎ではあるが特別教授場が開設されており、当然その校舎を建てなければならない情勢であった。こうしたことから村当局は財政上の事情により、この二校を統合する目的で、42年8月にサックルと
トワルベツの境界付近に統合校舎22坪(約73平方メートル)を建て、既設の教授場を廃止した。
しかし、サックル側では通学困難を理由にこれに応ぜず、従来の施設を利用しそのまま私設教授場として教育を続けた。また、トワルベツ側でもこの統合を不服として拒否し続けたため、事実上統合は失敗に終わり、再興を願う住民の運動が実って、43年5月1日に再び「サックルペシベ特別教授場」として公設されることとなったのである。
夏路分校
大正4年(1915)4月に仮名書きの校名を廃し「夏路特別教授場」と改称したが、このころから通称越後団体へ入植する者が多くなるにつれて学齢児童も増加し、校舎増築の必要に迫られてきた。このため住民は協力し合い、6年11月に村からの補助金50円と住民や篤志家からの寄付金227円余を合わせて29坪(約96平方メートル)の校舎を新築した。その後13年には児童数も38名を数えるに至ったので、再び住民の協力により5坪余を増築し、教育に支障のないよう取り計らわれた。
昭和16年4月に国民学校令の施行により「大関国民学校夏路分校」と改め、22年4月学校教育法の施行によって「大関小学校夏路分校」と改称するという経過をたどった。しかし、通学区域内の戸数は大正13年の34戸を頂点として減少し、昭和22年ではわずかに5戸となり、23年には在籍児童数が2名となって、日本一小さい学校ということでニュース映画によって全国に紹介されたほか、テレビでもしばしば紹介された。
昭和39年にはこれまで数次にわたって改修維持されてきた校舎も限界となったため、町ではこれを全面的に改築して29・75坪(約98平方メートル)の校舎としたが、依然として超ミニ校であることに変わりはなかった。32年と36年に8名の在籍児童を数えたものの、このころから転出者が相次ぎ、45年には一家族の姉弟だけ4名という特異な現象となった。こうして姉弟だけの学校として存続し、全員が卒業してしまった51年3月限りをもって在籍数はゼロとなり自然廃校となった。校跡は富咲455番地である。
大関小学校夏路分校(写真1)

第10節 富咲小学校
富咲分校の設立
昭和15年(1940)3月に「富有別特別教授場」が廃止され、その後は荒廃地と化したトワルベツ地区が、戦後緊急開拓地として拓殖計画が進められることになったことにともない、22年の7戸をはじめとし、24年15戸、29年2戸、30年6戸などと年々入植者を迎え、農業地帯としての再興が図られた。
しかし、この地区の児童たちは、最寄りの大関小学校の通学区とされていたのであるが、山間部のうえ遠距離や悪路などの条件が重なって、通学はきわめて困難な状態であった。
こうした状況によって地区住民から分校設置の要望が高まり、町もまたこれについて検討中のところ、たまたま昭和31年度において開拓事業施設補助制度により、分校建築費が交付される道が開かれたので、開拓地内のほぼ中間地点に当たる富咲88番地を校地に定め分校を設置することとした。
新築校舎は、一教室に教員住宅併設の60坪(約198平方メートル)という規模で10月下旬に完成、児童13名を収容して11月7日に開校式を行い、「大関小学校富咲分校」として発足したのであった。
富咲小学校(写真1)

小学校昇格から廃校まで
校下の富咲1区は、その後は入植者もなく、むしろ減少をたどりはじめていたが、時代の推移に応じ昭和42年4月昇格して「富咲小学校」と改称した。しかし、このころから始まった山間部における離農は、この地区もまた同様で、児童教は急激に減少して47年度にはわずかに3名となり、このうち教員の子が2名という状況になった。さらに将来においても増加の見通しがなく、学校存立の意義も認められなくなったので、47年3月限りをもって廃校したのであった。
第11節 富有別特別教授場
開拓草創期の教育
当校下のトワルベツ地区は、川沿いの主要地を占める大関農場の開拓を中心として、明治36年(1903)に三三〇余町歩(約330ヘクタール)の貸付を受けた萩原農場をはじめ、同じころこれも三三〇余町歩の貸付を受けた吉植農場、さらに、増田・田下・久保などの牧場が開設され、農地開拓の入植者や炭焼き業者などを迎えて開発が進められたところである。
どこの開拓地でもそうであるように、問題となったのはやはり児童の教育であった。この地区から約8キロメートル離れた大関校まで通学させることは到底不可能なことであり、独自の解決を迫られることになったのである。そこで住民は協議のうえ、入植者高橋忠蔵のでんぷん乾燥場を改造して教場を造り、伊能大吉を教員に雇って私設教育所を開設し、児童を集めて授業を開始したのは明治40年1月のことであった。しかし、地域でこれを維持するのは容易なことではなく、やむを得ず5月から休校し、11月に木戸忠之助のでんぷん乾燥小屋を借りて教場に当てて再開したものの、依然としてその経費負担は容易なものではなかった。
こうした状況の中で、41年4月に増田鶴寿ら38名が連署のうえ、公設教授場の開設について村当局に要請した結果これが認められ、同年12月15日「大関尋常小学校付属トワルベツ特別教授場」として発足することになったのである。なおこれと同時に、校舎は久保市蔵所有のでんぷん置場10坪(約33平方メートル)を当ててこれに移転し、教員には引き続き伊能大吉が命ぜられていた。
こうして難航のすえ誕生した特別教授場ではあったが、村当局としては児童数の少ない数多くの教授場を設置しておくことは、経済的な面からも妥当ではないという理由から、当教授場とサックルペシベ特別教授場の統合を計画し、42年8月に新校舎(22坪)を両地区の境界付近に建築した。これには5坪余の教員住宅も付設してあったが、教員自体も不便を理由に移転せず、またサックル側からも児童が登校しないということもあって、従来の教授場に居すわり続けたため、この統合計画は事実上失敗に終わったのであった。学校統合の難しさは、昔も今も変わりないようである。なお、この新校舎は無人のため、12月には積雪によってつぶれてしまったという。
富有別特別教授場
これまでの仮校舎を教授場として授業を続けたのであるが、44年7月に高橋勝次のまき小屋8坪(約26平方メートル)を仮校舎に当てたあと、同年10月には増田農場事務所の傍らに22坪(約73平方メートル)の校舎を新築した。
45年3月支庁からの通達によって校名を漢字に改めることになり、当て字を用いて大正4年4月1日から「富有別(とあるべつ)特別教授場」と改称した。
この名称改正にあたっては、初めは地域の人たちが用いつつあった漢字読みで「都有別」とすることを上申したのであるが、支庁では読み誤りをするおそれがあるので、トワルベツを意訳して「温川(ぬるかわ)」としてはどうかなどの照復があったあと、村では、「学校ノ名称ハ概シテ所在地又ハ其部落ヲ代表スル特殊呼称ヲ冠セザルナク」として、結局文字は改めたが「富有別」で押し切ったといういきさつがあった。
その後教授場は、地域の中心的な施設となって継続されたが、地域が山間辺地のうえ、トワルベツ川に架けられる橋が出水の都度流れてしまうという交通事情と、地力の低下や薪炭材の皆伐などという悪条件が重なり、転出者が続出して児童数も激減し、昭和15年には3名だけとなった。そのうえ、近い将来においても戸口の増加は期待できなくなったので、町では在校生に対し1人月額5円の就学奨励費を支給する措置をとり、以後は適当な方法によってこれを大関小学校に就学させることとして、同年3月31日限りをもって廃止したのであった。
第12節 鉛川小学校
別教授場の発展
鉛川は明治30年(1897)に大阪の人藤川清蔵が「藤川農場」を創設し、入植者を迎えたことから本格的な開発が進められるようになった。
藤川は農場創設後間もない34年、志半ばにして死亡したため、翌年小作人14戸に対して権利を譲渡することとなった。こうして入植者はいち早く小作を脱し、自営農業に入るという特異な開発形式がとられたところである。
その後、37年高台地に「茂木農場」が創設され、三か年で20戸の入植者を迎えたのをはじめ、中途でざ折したのではあるが「船越農場」も開設され、このほかにも個々の入植などがあって戸口の増加をみるようになった。これら入植者たちの子弟は、33年5月に創設された大関分校=大関小学校に通学していたので、この時点ではとりわけ支障がなかったのである。
しかし奥地の開拓が進められてきたことにともない、40年に大関小学校が現位置に移転することとなったので、この地区の児童は遠距離のため通学不能な状態におかれることになった。そこで鉛川住民は善後策を協議し、特別教授場の公設を村当局に請願するとともに、校地の選定や建築資金の募金など、開設についての準備を積極的に進めた。この結果村当局もこれを認め、現鉛川25番地に「大関尋常小学校付属鉛川特別教授場」の設置を決め、掘立式草ぶき板囲いながら26坪(約86平方メートル)の仮校舎を造り、40年4月15日に開校したのであった。このときの児童数は20名で、教員には北海道庁事業手であった村田順敬が任命された。しかし、翌41年4月からは義務教育年限が6か年に延長されたが、この特別教授場は4年生までの収容にとどめられ、延長の対象となった5、6年生は大関小学校に通学させることになっていたのである。
その後、仮校舎が授業に不便なばかりでなく、構造や外見からも学校としての体裁上好ましくないということで、住民は再び寄付金200円を集めて村当局に建設を要請し、大正元年(1912)8月に総面積44坪(約145平方メートル)、うち教室20坪、教員住宅10坪の新校舎を実現させたのである。こうした整備状況や地理的条件を勘案した村当局では、翌年5月から付属本校を八雲尋常高等小学校に変更すると同時に、6年生までの全児童を収容することとした。なお、3年4月に上鉛川特別教授揚が開設されたことにより、通学区を変更して一部の児童をこれに通学させるという経過をたどった。
小学校独立後の変遷
特別教授場として開設以来、13年を経過した大正9年には児童数が67名(結果的には、この年か最高となる)に達し、また設備も整ったとして、町は同じ特別教育規程の適用ながら「鉛川尋常小学校」と改めることを決め、4月1日から実施した。しかし、その直後に訪れた不況によって、離農転出者が続出して児童数も減少しはじめ、11年(9月に初代校長佐藤千別が発令)には49名、昭和2年で25名という経過のあと若干増加をみせ、7年には46名を数えたものの、当時としては小学校令による昇格を望める状況ではなかった。このため、同規程の運用により、大正15年と昭和7年の2度にわたって特別教育規程による尋常小学校存続期限延長の手続きがとられていたのである。しかし認可期間の半ばではあったが、町の教育内容向上という方針に基づき、昭和10年4月から名称は同じであるが、制度的には小学校令による正式な小学校となり、面目を改めることになった。
その後制度の変遷に応じて、16年4月に「鉛川国民学校」、22年4月に「鉛川小学校」となり、23年10月には単級小学校のうち、児童数35名以上の学校に補助教員を採用することが認められてからは2教員制となった。
八雲小学校に統合
昭和22年に45名を数えた児童も、28年には30名に減少し、以後はしばらく横ばい状態を続けたものの、30年代後半の人口流出によって37年には18名に激減、配置教員も1名とされる事態となった。幸い39年度には児童14名ながら2教員制の復活となったが、このころ町教育委員会では、教育水準を高めるために小規模校の整理統合を計画していたときでもあり、その対象校として取り上げられたのであった。39年10月には第一回の話し合いがもたれ、地区側としては原則的に賛成の意向を示したが、学力差是正のため1、2年の猶予を申し出た。これを了承した教育委員会では、翌40年11月に再び早期統合を申し入れた結果、翌41年度限りをもって廃校とすることを確認した。
こうして42年4月1日には、最終在校生7名を八雲小学校に送って統合し、開設以来60年の歴史を閉じたのであった。
鉛川尋常小学校(写真1)

第13節 久留米小学校
分校の創設
流泉花(立金花とも)の群生している沢という意味で、古くから正式な字名に用いられ「ブイタウシナイ」と呼ばれた花浦地区内陸部の開拓は、明治31年(1898)の「久留米農場」の創設に始まる。元久留米藩士を父に持つ井上岩記らが、30年に官有地150万坪(約500ヘクタール)の貸付を受け、翌年福島県からの移民22戸を率いて入植し、その後も連年積極的に入植者を迎え入れたことにより、この地区の戸口はにわかに増加することとなった。
井上農場主は、子弟の教育に早速意を配り、32年に隣接地山崎の石川農場主と協議のうえ、両地域を通学区とする学校を造ることとし、久留米農場事務所に12・5坪(約41平方メートル)を増設して仮教場に当て、入植者のひとりである関村恒介を教員に雇い、私設の久留米簡易教育所を開設するとともに、これを公設とするよう村当局に対し要請した。これを認めた村では、その筋に上申手続きの結果、同年10月18日に上砂蘭部校と同時認可となり、「八雲尋常高等小学校久留米分校」と称して公式に発足したのである。このときの児童数は30名であった。
上砂蘭部の各分校
明治33年末には早くも児童教が50名に達し、34年4月に黒岩・大関・小学校への独立初期とともに独立して「久留米尋常小学校」と改称した。児童数はなおも増加し続けていたので、翌年4月に教室などの一部を増築したが、38年には77名を数えるに至り、さらに校舎の増築を迫られることになった。こうしたことから再び久留米・石川両農場が協議の結果、これを2校に分離して山崎にも学校を設置することで合意し、いわゆる久留米地区単独で校舎を建築することとなった。そこで地区内協議のうえ、農場地内ブイタウシナイ97番地の2を校地として370坪(約1221平方メートル)の提供を受け、同年10月に移設を行いこれに増築し、計51坪(約168平方メートル)の校舎を整備したあと村に寄付した。一方、開設準備が進められていた山崎地区の学校も、翌39年4月に発足したため、通学区域の変更によりこの年の当校の児童数は39名となった。
校舎の再移転
開拓が進められるにしたがって再び児童数は増加し、41年で60名、43年には74名に達し、同年10月に初代校長原復造が赴任、翌年4月には2学級編制となるなど、急激に充実が図られていった。
こうした校勢の伸展によって再び校舎が狭くなり、42年に久留米農場を継いでいた岡田農場(場主・岡田正三、現地管理人・石井養太郎)では直ちに改築について協議を行い、隣接地の適当な用地を寄付すること、移転費用は農場と住民で半額程度を負担すること、などを条件として示し村当局と交渉を続けた。その結果、大正3年に村会の議決を経て実現の運びとなったのである。これにより、校地をブイタウシナイ146番地の600坪(約1980平方メートル)に決め、従来の校舎を一部移設したうえ36坪(約119平方メートル)の新増築を行い、計72坪(約238平方メートル)の校舎とすることに決定した。工事は経済的な面も考慮して地域がこれを請け負って施工し、10月末に完成、面目を一新したのである。以後も幾多の変遷があったが、結果的にはこれが当校の最終校地、最終校舎となったのである。
久留米小学校(写真1)

安定期の校勢
大正9年(1920)4月には鷲の巣地区のうち岡の山を通学区に編入し、在籍児童107名という最盛期を迎えた。しかし、その後に襲った経済恐慌により、緩やかではあるが減少しはじめ、11年の95名、15年の79名というような状況を示した。このため、当時の法定学級70名、特認最高定員80名までという枠の中で、町は財政上の都合で80名としていたこともあって、大正末期から昭和の初期にかけて一学級編成に縮小の動きも出たが、地域の反対が根強く、その実施を見合わせたといういきさつもあった。幸いこれ以後は校勢も安定し、常に70名から80名台を保っていた。昭和16年(1941)4月に「久留米国民学校」となり、22年4月には「久留米小学校」と改称されたのであったが、この間も依然として二学級編制を維持し続け、しかも26年には三教員配置となるなど、その質的向上が図られたのであった。
近代統合の第一号
昭和30年代の初期ごろまでは常に60名台を保ってきた児童数も、高度経済成長の影響を受けた農村地帯における人口流出は、この地区もその例外ではなく、35年に46名、37年には34名にまで落ち込んだのである。
一方では、大正3年建築の校舎が既に約半世紀を経過し、老朽がはなはだしく危険な状態になったため、住民は代表を挙げて昭和38年の初頭に町と議会に対して改築を請願し、これを受けた議会では、2月13日にこの採択を決定したのであった。したがって校舎は遠からず改築される見通しとなったのであるが、折から町教育委員会が中心となって検討を進めつつあった学校統合の対象校として取り上げられ、これによって八雲校への統合を迫られることになった。
39年8月第一回の学校統合促進協議会において、統合方針が打ち出されたあと、10月10日の現地での話し合いをはじめ、数度の折衝が行われた結果、現状維持を強く望む立場から根強い反対意見もあったが、翌年1月9日の地域代表と町長、教育委員会などとの最終協議によって、地域側ではその統合案を受け入れることに合意した。これにより近代統合の第一号として、40年3月31日限りをもって廃校し、4月1日から八雲小学校に統合という方針が確定したのである。
この統合実施の具体的な方法についてはさらに協議を重ね、1月28日に町と地域代表との間で交わされた確認書によって明らかになったが、要約すると、
(1) 児童通学用バスを運行させること。
(2) そのための待合所を3か所に設置するとともに、道路整備に努めること。
(3) 40年度中に地域集会所を建設すること。
などを柱とするものであった。
こうして分校として公設以来65年の長きにわたり、地域の盛衰とともに歩み続けてきた久留米校は、花浦225番地に校跡をとどめ、教育の質的向上に願いを託して発展的廃校となったのである。
第14節 富岩特別教授場
トワルベツ区画地での教育
トワルベツ川の上流地帯で黒岩側稜(りょう)線寄りの高台地が区画地として解放され、明治末期から大正初期にかけて開拓者が入植するようになった。この地帯ではトワルベツ特別教授揚が最寄りの学校ではあったが、これにしても8キロメートル余という遠距離のため、児童の通学は到底不可能であった。
このため、住民は協議のうえ私設教育所の設置を決め、伊藤栄記所有の建物6坪(約20平方メートル)を借り受け、仮りの教場として大正3年(1914)早々に児童12名を集め、教員に佐藤乙吉を招いて授業を行った。5月には地域住民からの資金拠出と労力奉仕により、公共用地内に教員住宅併設の教場12・5坪(約41平方メートル)を造ってこれに移った。もちろん新開地の小地域のこととて、教員の俸給など一切の運営経費を負担することは容易ではなかった。
このため、教員の食糧は現品で提供したほか、地区内の公有地一町歩(約1ヘクタール、当時の陳情書から)を児童の試作地にあて、これを住民も協力して耕作し、その収穫で俸給の一部を補うなど、苦労が重ねられたのである。したがって、同年11月にはこのような苦境を村当局に訴え、函館山特別教授場と名付けて公設されるよう陳情したのであるが、翌4年1月に村から「村経済ノ関係上当分開設シ能ハサル」との回答を受けてこの願いは受け入れられず、私設のまま継続せざるを得なかったのである。
里岩原野側の教育
トワルベツ区画地の開拓と前後して、黒岩の高台奥地のいわゆる黒岩原野が解放され入植者が迎えられていた。しかしこの地区でも、児童が最寄りの里岩校まで8キロメートル余を通学することは、これまた不可能なことであった。このため、入植者一同は協議のうえ、大正5年(1916)5月に児童8名を収容し私設の教育所を開設した。これに要する諸経費も当然住民が負担するものであったので、維持して行くことはかなり困難がともなったことは明らかだったが、翌年11月には教員が退職するという事情もあって、早くも閉鎖されたのであった。
特別教授場の創設
以上のような状況におかれていた両地区が、それぞれ公設教授場の設置を要請し続けていたのは当然であった。しかし村では、両地区がそれぞれ独立した特別教授場を設置する規模には達していないうえ、村の財政上からも、近接する位置に二か所を設置することは妥当ではないという判断から、両地区が合議して場所を決め、一か所の施設として運営するよう説得を続けたのであった。もともと両地区は、その間に約700メートルの幅の官林を挟んで隣接する地帯であり、大正7年には双方を連絡する道路が開通して交流が生まれつつあったのである。
こうした村の説得に対し、両地区は互いの利便を主張し合って協議はなかなか進展しなかったが、大正8年から始まった経済変動によって物価が高騰し、入植者自らの経済も不安な状態が続くなかで、辛うじて命脈を保ってきたトワルベツ側の教場においても教員俸給の値上げが要求され、もはや一地区での運営も限界というところまで追い込まれたのであった。
このため、双方の協議もにわかに進展して合同による一特別教授場を設置する計画が立てられ、9年3月にトワルベツ地区(8戸)総代伊藤栄記、黒岩地区(22戸)総代岩渕音作が連署して、町当局に対し出願したのである。この出願に際しては、教授場の建物やこれに要する一切の設備は、住民が負担することを条件として示し、ただ「教員俸給ヲ町費ヨリ支出ノ事御聴許相成度」というものであったが、これを受けた町では4月の町会で議決を経て設置方針を決めるに至った。
こうして町では、双方の地区名から一字ずつを取って「黒岩尋常小学校付属富岩特別教授場」と名付け、場所を黒岩原野一線とトワルベツ区画線の中間に定め、5月1日の開設を告示した。開設時の児童は32名で、初代教員にはトワルベツの私設教育所から引き続き宍戸茂七が任命されていた。しかし、実際には発足と同時に指定の場所へ移転することは困難だったので、取りあえずトワルベツ地区の旧教場を使用し、その移設と一部増築により教員住宅を併設した18坪(約59平方メートル)の校舎を建築したのは、その年11月のことであった。
児童数の減少と廃校
種々の難問を乗り越えて誕生した教授場ではあったが、山間辺地のことでもあり、間もなく両地区とも転出者が出はじめて児童数も減少を続け、昭和7年(1932)に9名、13年にはわずかに4名となったのである。このため、町では将来も増加を見込むことができないということから、児童1人につき月額5円を就学奨励費として支給し、適当な方法によって黒岩の本校に通学させるような措置をとり、14年3月限りをもって廃止したのであった。
第15節 遊楽部尋常小学校
官設アイヌ学校の創設
遊楽部川の河口付近に栄えたユーラップコタンは、明治初期における顕著なアイヌ集落として、北海道の最南端に位置していた。しかし、遊楽部原野にも和人が入植するようになると、アイヌたちの収入源であった遊楽部川のサケも自由に捕獲できなくなるなど、これまでの生活様式も一変し、長い間教育らしい教育を受けられなかったかれらは、和人の要求によって使役に応じ、その日暮らしをするのがやっとという状態にならざるを得なかったという。
こうした現実を直視した函館県令は、かれらにも新時代に順応しうる学問の機会を与えることとし、まず主要なコタンである遊楽部にアイヌ学校を設立することを試み、明治15年(1882)に県御用掛永田方正を現地に派遣した。遊楽部を訪れた永田は地域内を説いて回り、児童を集めることに努力し、竹内嘉吉(旅籠兼漁業経営)宅の一室を借りて5月10日に児童4名(翌月には15名となる)をもって授業を始めたのである。この様子について6月13日付の函館新聞は次のように報じている。
五月十日
「オベスク、シークの二人生徒四人携え来る。因て武内氏の一坐敷を借り、教ふるに以呂波を以ってす。四名の中サンチョ、シシマヲは頗る敏にして忽ち記誦せり。因て四生徒に与ふるに菓子を以てし、オペスク、シークに飲ましむるに酒を以ってし、日々に之を与ふるにはあらず。今日開業を祝するため県庁より賜るなり。皆謹で拝す。」
(明治十五年六月十三日発行第六九五号)
その後、永田の努力によって児童も15名を数えるようになったので、学校を新築しなければならなくなり、同人は県の許可を受けて同年7月遊楽部7番地(当時)に校舎建築に取り掛かった。この状況を函館新聞は、
「遊楽部の新築学校は材木並にガラス、畳等夫夫取揃えたれば、已に棟上もすみ、四、五日中には落成すべしといふ。その敷地は去月勧業課員遊佐尚一氏が飛蝗駆除出張の帰り大に尽力され、人夫三十人程にて夫々切り開き、凡て六百坪とし其四方へ溝を掘り、敷地の姿をなせり。永田方正氏の骨折にて大に教育の見るべきに至る。」
(明治十五年八月六日発行第七二二号)
と報じているので、すくなくとも8月中には校舎が完成しているものと思われるし、しかも官費による学校設立であった。
なお、永田方正は19年の北海道庁設置と同時に、八雲を去って札幌本庁に転勤した。同人は、アイヌ語をはじめ風俗・習慣などについての著名な研究家で、のちに「北海小辞典」や「北海道蝦夷語地名解」などを著している。
公立学校への移管
こうして学校が設立されたが、これはアイヌの子弟教育を目的とするものであったため、和人の子弟はこの学校の近くに住んでいても、遠い八雲学校まで通わなければならないという不便さが取り上げられるようになった。
このため官に出願して、16年7月に校地・校舎その他の付属物件すべての下付を受け、「公立遊楽部小学校」と改めた。こうして和人子弟との共学の場となったのであるが、アイヌの子弟には「貧民子女学資給与規則」が適用されて学資が給与されるという保護策がとられ、教員俸給の補助も合わせて年額180円にも達していた。しかし20年に規則が変わって補助金も教員の俸給だけのわずか72円となり、アイヌに対する学資給与も打ち切られることになったので、その児童は学資に窮したうえ、教育そのものに対する父兄の関心が低いということから、次第に退学するものが増え、児童も1、2名に落ち込む状況となった。さらに同年4月からの小学簡易科時代には、史料不足もあってはっきりはしないが、温習科を設けて教育内容の充実が図られたというものの、教員の欠員などもあって、ついに一時休校(時期不詳)のやむなきに至った。
学校統合の第一号
明治23年には教員の補充もあって再開することになったが、当時における村の財政事情からこれを維持してゆくことは容易なことではなかった。このため村では、25年に学校運営費全額の補助申請を行い、これが認められない場合は八雲小学校に統合せざるを得ないと訴えた。
これにより実情を調査した道庁では、アイヌの児童の就学不振については、経済問題もさることながら和人児童との共学にも原因があるとして、再びアイヌだけの収容校としたうえ、経費全額を補助するとともに、和人は八雲小学校に通学させることとした。そのため児童は12名に増えて学校経営も軌道に乗りつつあったが、この全額補助の恩典も翌年にはまた教員俸給だけに変わるなど、安定するいとまもなく再び和人児童も収容するという状態に戻った。
こうした苦しい運営を強いられてきた村当局では、31年に八雲小学校の新校舎を建築するにあたってこの統合を打ち出し、9月に認可を受けて双方の通学の便を考慮し、現八雲小学校の位置に決めたのであったが、12月15日の新校舎落成をまって「遊楽部尋常小学校」(28年4月に改称)は、これに統合されたのであった。
なお、これが当町管内における学校統合の、記念すべき第一号となったわけである。
第16節 八雲聾唖学院
特殊教育として誕生
八雲聾唖(ろうあ)学院が設立されたのは昭和3年(1928)11月であった。院長辻本繁は函館盲唖学院に9年間学び、篠崎清次の感化を受け、さらに東京聾唖学校師範科に入学、同校卒業後は函館に帰り母校の教壇に立っていた。このころ、函館盲唖学院へ入学するのはほとんどが函館市内のものに限られ、地方からの入学者がないのを見て、これらの不幸な児童たちの教育のため、自ら田舎に入って独創的な学校を起こそうと志を固め、八雲への移住を決意したのである。当時は村民の理解も少なかったが、内田町長をはじめ大島徳川農場長、小川乙蔵、河野武一らの奔走により、住初町の裏通りの借家を臨時校舎にあて、男女2名の児童を収容して11月20日に開院したのであった。
その後、5年7月には篤志家の寄付と経営者の努力によって、砂蘭部(現、末広町)に新校舎を建設した。
聾唖学院としての成果
生徒は4、5名にすぎなかったが、全員を寄宿舎に収容し、しかも私立のうえ生徒から月謝を徴収せず、経費は院長の私財と篤志家の寄付、地方費や町費の補助によったため、経営はきわめて困難であったが、辻本院長夫妻は報酬を返上してよくこの困難に耐え、献身的な努力を続け、教育については院児に対して口話法による聾唖教育を取り入れた個人教授を主とし、少数の生徒ではあったがその成果は大きなものがあった。
学院の閉鎖
院の経営は、前述のように院長夫妻の奉仕と、有志75名によって設立された「八雲聾唖学院後援会」の会員によって運営された。また、これら後援会員の尽力で、道庁学務部へ学院の設立認可願と同時に、奨励金の下付申請が出されたのであるが、「個人経営」ということで両方とも却下になったのであった。
こうした状況のもとに経営は続けられたのであるが、11年に至ってこの地方の特殊教育は一段落したので、この学院を閉鎖して室蘭市に進出することになり、辻本夫妻はこの年11月室蘭市で私立聾唖学院(のちの道立室蘭ろうあ学校)を開設して教育に専念した。昭和36年にはその功績が認められて、夫妻に対し北海道文化奨励賞が授与された。
八雲聾唖学院(写真1)

第5章 高等学校
第1節 八雲高等学校
高等学校への改編
昭和22年(1947)3月に教育基本法と学校教育法が同時に公布され、4月1日からいわゆる6・3・3・4制が施行された。この教育制度の改革にともなって、翌23年4月には町内に高等学校が2校設立された。すなわち、旧庁立八雲中学校が「道立八雲高等学校」となり、旧庁立八雲高等女学校が「道立八雲女子高等学校」となったのがそれである。こうして男・女の2高校は、それぞれ新時代の教育に対応することとなり、八雲高等学校にはその年11月15日に定時制課程(夜間)が付設され、働く青少年に就学の道が開かれた。
24年4月には新教育制度が目指す男女共学の精神に従い、この2校が統合して名称を「北海道八雲高等学校」と改め、旧男子校を西校舎、旧女子校を東校舎と称した。当校の創設当時は普通科だけであったが、翌25年から商業科1間口を付設し、さらに26年から農業科1間口を付設して体制を整備した。29年4月の時点では、全日制普通科3間口9学級、同商業科1間口3学級、同農業科1間口3学級、定時制普通科1間口4学級という体制になった。
また、当初の通学区は、森・落部・長万部を含む三町一村を対象としていたが、森町では23年4月に町立森高等女学校が道に移管して森高等学校が開設され、24年には道教育委員会の指令で寿都町に八雲高等学校寿都分校(25年独立)、25年長万部町に同長万部分校(26年独立)、26年黒松内村に同黒松内分校(28年独立)をそれぞれ設置するなど、近隣各町村における高等学校設立の過渡期にあって、よく中心校としての役割を果たしていたのである。
なお当校は、旧制八雲中学校の開校をもって創立とすることにしていたので、昭和28年に創立30周年記念事業として造成した陸上競技場は、29年3月日本陸上競技連盟から第三種に公認され、当時の高校としては唯一のものであった。
教科・学級数などの推移
昭和39年(1964)には生徒の急増に対応して普通科1学級を増設したが、41年4月から農業科の募集を停止して商業科を2間口とすることになり、さらに翌42年度には商業科が3間口募集となったのであるが、43年度には普通科を3間口に減らすというように、めまぐるしい変遷をたどった。
しかも、43年11月27日に道教育委員会が打ち出した公立高校再編計画によって、通学区内における中学卒業生約100名の減少を理由に、44年度からさらに1間口を削減する方針が明らかにされたことにより、町内においては、にわかにあわただしさを増した。こうした一方的な道教委の削減案に対し、「地元高校への進学希望者を締め出すもの」として直ちに反対の声が沸き上がり、29日には田仲町長・石垣教育長らのほか、町校長会・PTA代表・地区労代表らが渡島教育局を訪れて反対を申し入れたのをはじめ、30日には道教育局に出向いて陳情するなど、町ぐるみの反対運動に発展した。
このような動きとともに、町議会においても同年12月2日、有史以来ともいわれる議員請求による臨時町議会を開会し、佐々木繁議員ほか5名提案の「道立八雲高等学校学級減に関する意見書」を審議し、これを原案どおり満場一致で可決した。そしてこの取り扱いについて協議した結果、翌3日に町長・正副議長・教育長・PTA代表の関係者らが出札し、道知事・道教育長・道議会議長ら各関係機関に提出するなど、積極的な運動を展開することとした。
また、これと並行して進められた八雲中学校PTAの反対署名運動や町民大会の開催など、町ぐるみの運動が功を奏し、道教委では12月7日ついに学級削減の実施を見送る旨の発表をするに至り、住民パワーの成果として互いに喜び合ったのである。 しかし、生徒の自然減少はなおも続く傾向にあったため、地元PTA関係者らの強い要望にもかかわらず、45年4月には商業科1間口減が実施されたのは、やむを得ない情勢であった。
東校舎の焼失と関連整備
昭和12年(1937)12月に新築し、八雲高等女学校時代を経て八雲高等学校東校舎と呼ばれていた校舎(現、サッカーグラウンド)は、41年10月19日午前2時半ごろ、無人の農業実習室から出火した不慮の災禍により、普通・特別教室各7のほか、図書室・職員室など木造2階建て校舎と体育館など、計2656平方メートルを全焼するという事故が発生した。
そのため学校では、西校舎の特別教室や臨時の間仕切り室を利用して授業を開始するとともに、これと併せて災害応急対策工事が進められ、翌年3月に商業実践室とタイプライティング室を新築、9月には特別教室棟、11月には商業棟をそれぞれ新築し、また、43年12月には新体育館が新築落成して着々と整備された。
校舎の改築
昭和18年の秋に戦時の緊急工事で旧制八雲中学校校舎として建てられた校舎は、建設以来すでに30年近くを経過し、老朽化が目立つようになってきた。このため、体育館整備後の44年秋ごろから校舎改築を求める声が高まり、町長ら関係者からおりにふれて道などに陳情が続けられた。
その後さらにその機運が熟し、46年12月には関係機関を網羅した「校舎改築促進期成会」(会長・北口町長)を組織して機会あるたびに間断なく陳情を続けた結果、48年度の道予算に調査設計費が計上され、明るい見通しが得られたのであった。
こうして49年10月第一期工事に着工、商業棟の移転工事が終わったが、翌50年度には道の財政的な都合もあって中断され、51年度に第二期工事として校舎建築、52年度第三期工事として外構防寒工事がそれぞれ施行され、同年11月に全工事が完成した。新校舎は、鉄筋コンクリート造り4階建て3486平方メートルで、このほかの既設建物などを合わせると6790平方メートルにも及び、これに要した総工事費は実に6億2870万円であった。
八雲高等学校(写真1)

この新校舎の落成を祝って校舎落成記念協賛会(会長・長谷川克巳)を結成し、PTA・同窓会など広く働きかけて募金を行い、12月10日に盛大な落成記念式典を挙行したのをはじめ、前庭舗装や外周整備を行って環境を整えた。
校舎改築とともに、野球場・テニスコート・サッカー場などの整備拡充が進められて面目は一新されたが、さらに53年11月には鉄骨造り平家建て310平方メートルの各技場が新築され、機能の充実が図られたのである。
第三種公認陸上競技場
昭和24年(1949)道立八雲女子高等学校を道立八雲高等学校に統合し、名称も北海道八雲高等学校と改めた。これにより普通科15学級編制となって生徒数も増加したことから、生徒の体位向上を図るため総合グラウンドの設置計画が検討されていた。
昭和28年学校創立30周年を迎えるにあたり、その記念事業として総合グラウンドの整備が計画された。このため、26年に東西両校舎の中間にある土地を買収して校地の拡大が図られたことから、これをグラウンド用地にあて、教育上支障のない限り一般に解放することとして事業が進められた。
資金は同窓生や一般町民からの寄付と町の補助を受け、総面積1万6500平方メートル、トラック1周300メートルのほか投てき場、跳躍場、その他付属設備の整備を行い、28年10月日本陸上競技連盟に三種公認陸上競技場としての認定申請をして、翌29年3月に認定された。
このグラウンドの三種競技場公認によって、それまで函館市で行われていた道南郡部の高校各種競技大会を、分離して開催できるようになり、さらに町体育大会や小・中学校の大会にも利用されるようになった。
その後、48年9月に全面改修を行い現在に至っている。
第2節 旧制八雲高等女学校
女子教育の台頭
大正11年(1922)12月に実業補習学校ながら「八雲高等国民学校」が開設され、さらに翌12年4月開校の「北海道庁立八雲中学校」の校舎建設事業も軌道に乗るなど、男子教育機関の整備が先行しつつあった。
13年1月の町会において、提出者鈴木永吉、賛成者中島末吉ほか4名をもって「教育上の施設整備の件」という建議案が提出され、論議が交わされた。建議の趣旨としては、高等国民学校が開設されてから、その施設を利用して任意の女子講習をしているのであるが、経費が不十分で永続が不可能な情勢にあるので、これを公設として位置付け、恒久的なものとするなど、女子教育が緊要であることを訴え、大正13年度から直ちに教育関係機関を整理して、高等国民学校に女子部を設置することを検討するため、委員を挙げて調査しようというものであった。
ちょうどこのころは、農村地域戸数の減少期にあることも反映して「通学区ヲ故意二変更シテ児童ノ減少ヲ防止シ、学級ヲ維持スルガ如キ情実」(町会会議録)もあるので、これらを整理して合併できるものは合併すれば、その経費は容易に生み出すことができるという意見もあり、また、女子部の設置と、人情にほだされて実行不可能な統廃合とは別の問題として考えるべきであるとする意見もあり、さまざまであった。ともかく一応は経費調査委員を挙げて調査に乗り出すなど積極的に取り組み、女子部の設置の必要性については議員の意見は一致したものの、当時の経済情勢下にあって、町民負担のともなわない財源の工面という点て暗礁に乗り上げた。しかし、その趣旨は理解できるとしてこれを採択し、実現方については理事者が研究するよう要望するにとどまった。
こうした意向を受けた木村町長は、同年4月の町会で高等国民学校に女子の教養施設を設けるため、500円の予算追加を提案したところ、なお十分に調査研究の必要があるとして全額削除するということなどもあった。
家政女学校の開設
その後、女子教育施設について検討を続けてきた木村町長は「八雲女子職業学校」の設置を計画し、大正15年1月に町会の議決を経て文部省へ設置申請書を提出した。しかし道庁の視学官から、諸般の事情から設置の根拠を実業補習学校規程におき、学科課程は職業学校規程を運用することとすれば、道庁限りで設置が認可できる学校となり、しかも名称を八雲家政女学校としてはどうかという指導があったので、これを3月5日の町会に提案のうえ満場一致でさきの議決を変更し「町立八雲家政女学校」の設置を道庁長官に申請、3月19日に認可を受けたのであった。
こうして3月20日に生徒の募集を開始し、60名の募集人員に対して68名の応募者があり、全員に入学を許可した。学校長には八雲小学校長平尾覚次郎を兼任発令し、校舎は八雲小学校を当てて4月10日に開校式を挙行した。当時の教科課程は、本科4年と季節的に修学する別科3年の2本立てで、入学資格は小学校尋常科の卒業者は本科1年に入学させ、小学校高等科の卒業者は本科3年に編入させるというものであった。また、生徒の制服は白線2条のはかまとした。
実科高女への改編計画の挫(ざ)折
家政女学校は設立以来順調な経過をたどっていたが、実業補習学校規程を根拠とする学校であるため、卒業しても上級学校への進学資格が得られないこと、あるいは実業社会においても直ちに進出資格が認められないという、いわゆる中途半端なもので必ずしも時運に適した教育機関とはいえないという問題も生じてきた。こうしたことを考慮した内田町長は、これを高等女学校令による実科高等女学校に改めることを計画したのである。
また、道学務部長からの勧奨もあったので、昭和3年1月の議員協議会に諮ったうえ、2月開会の町会に「実科高等女学校設置ノ件」ほか関連議案を提出した。しかし当時は、経済界の不況に加えて町の教育施設に関する案件が集中し、一部議員のなかには強く反対する空気もあり、成立の見通しがつかない状況となったため、これらの議案を本会議上程前に撤回したのであった。さらに3月には家政女学校の学則を改正して、入学資格を高等科卒業生だけとする本科2年制とし、別科については事実上は有名無実の状況で廃止するという、後退の道をたどったのであった。
しかし、時勢の推移とともに高等女学校設置の要望が年を追って高まり、9年1月の町会では梅村多十郎以下19名(当日出席者全員)により「高等女学校ヲ設置シ昭和10年4月1日ヨリ開校セラレンコトヲ望ム」との建議案が審議され、内田町長もこれに対し、「建議ノ主旨ヲ体シ之ガ実現ニ満全ヲ期シタシ」との意向もあって、満場一致で採択されたのである。
この実現を期すには、町民の理解と協力が不可欠であることから、町では設置方法・設置の所要経費・資金の調達方法・最近における地方費移管条件の実例などを調査して「高等女学校設置ニ関スル調書」を作成した。そして同年12月に役場会議室において、町民大会ともいうべき会合を開いて協議を進めたのであるが、農作物の減収・起債の不可・寄付金募集の不能などの理由を挙げて真っ向から反対する声もあり、なかには家政女学校そのものすら廃止を主張する声が出た。また一方、高等女学校の問題は多年の懸案であり、町百年の大計であること、たばこや酒の消費金額が20万円を超える余力があること、八雲から他市の高等女学校へ入学する者は20人、その費用年額8000円を超える状況であることなどを挙げて、設置に賛成する声も当然あった。しかし協議会全体の傾向としては、内田町長が期待した町民からの寄付が受けられるような情勢ではなく、結局は資金調達という難問を打開する方策を見いだせないままに、町会の決議もむなしく葬り去られる結果となった。
なお、これより先の8月1日から青年学校令が公布され、実業補習学校規程を吸収したことにより、八雲家政女学校は「公立青年学校八雲家政女学校」と改称された。
実科高等女学校の設立
高等女学校の早期開設を望む声は依然として根強く、町会議員の中にも「高等女学校問題は早急に目鼻をつけるべきだ」という督励もあった。しかし、就任間もない宇部町長は、過去2度にわたる苦い経験から、あくまでも健全財政の建前を堅持し、各種施設の緩急度を勘案しながら検討を加え、まず実現可能と認められる実科高等女学校の設立を図るべきであるという結論に達し、議員とも協議を重ねつつ昭和11年4月の開校を目標に準備を進めた。
幸い協議や計画も順調に進み、11年2月8日の町会において、いよいよ11年度から八雲尋常高等小学校に併設する「実科高等女学校」開設の議案を審議し、満場一致で可決したことにより、長年の懸案であったこの問題もようやく実現の運びとなったのである。この設置申請書が道庁から文部省に上申されたのが3月中旬になったので、認可促進のため町長が上京して折衝を重ねるなど努力を続けた結果、次のような認可指令を受けるとともに、関係告示も相次いで令達された。
北普一三号 北海道山越郡八雲町
昭和十一年二月十五日教第一三九号申請北海道八雲実科高等女学校設置ノ件左記条伸二依り認可ス
昭和十一年三月二十七日
文部大臣 平生釟三郎
一、昭和十二年度二於テ予定計画通教室ヲ増築スルコト
文部省告示第二十九号
高等女学校令二依り左記実科高等女学校ヲ設立シ昭和十一年四月ヨリ開校ノ件昭和十一年三月二十七日認可セリ
昭和十一年三月三十一日
文部大臣 平生釟三郎
名称 北海道八雲実科高等女学校
位置 北海道山越郡八雲町
修業年限 二年
設置者 北海道山越郡八雲町
北海道庁告示第三百九十三号
山越郡八雲町二於テ昭和十一年四月ヨリ設置ノ北海道八雲実科高等女学校ノ位置及授業料額左ノ通り定ム
昭和十一年四月十日
北海道庁長官 佐上 信一
一、位置 北海道山越郡八雲町大字八雲村字サランベノ七番ノニ、七番ノ三、七番ノ五、十番ノニ(四七九・六坪)
一、授業料額 一人一月 二円五十銭
こうして「北海道八雲実科高等女学校」は正式に発足することとなり、生徒の募集も終わり、学校長(小学校長・平尾覚次郎兼任)はじめ専任・兼任の教職員も発令され、4月12日に開校の式典を挙げたのであった。
実科高女の充実
八雲実科高等女学校は、当初の生徒数は本科80名をもって発足したが、翌12年には100名に増員し、また、定数50名の補習科(一か年)を設けるなど内容の充実が図られた。
これとともに、女子中等教育機関としての独立校舎の必要性が痛感されたので検討を重ねた結果、12年度において建築する方針を立てた。このため「八雲実科高等女学校建築期成同盟会」を組織し、建築資金は大部分を有志からの寄付によることとして募金を行ったところ、各方面から順調に協力が寄せられるとともに、これに合わせて町の蓄積基本財産2万円を充当することで、資金調達のめどをつけることができた。こうして12年2月町会の議決を経て、6月に校舎建築についての認可を受けたのである。もちろんこの新校舎は、将来において地方費移管(庁立)を期待するものであったため、これに支障のないよう調査設計を道庁に委託し、工事期間中もしばしば校術官の派遣を得てその万全を期したのである。
工事は、札幌、函館、地元業者など13社を指名して郵便による入札の結果、5万円88円で地元の松原組に落札した。そして8月4日に着工し、順調に進められ2階建て570坪余(約1881平方メートル)の新校舎が12月4日に完成、15日に落成の式典が行われた。
独立校舎の新築を契機に、13年度から入学資格を小学校尋常科卒業としてその修業年限を4年にし、また、生徒の定数を200名とする組織変更を計画、町会の議決を経て文部省に申請した。この組織変更は初年度において実施しようとするもので、尋常科卒業生を1学年に入学させるほか、高等科1年修了者を2学年に、同2年卒業者を3学年に、実科1年修了者を4学年に、それぞれ入学・編入・昇級させるという案であった。これに対しては、いろいろな問題もあって文部省でも難色を示したが、町が先に示された条件を超えて独立校舎を建築した誠意が認められ、ついに3月11日には文部大臣から認可指令が出されて校勢の充実が図られたのである。
八雲実科高等女学校(写真1)

高等女学校への昇格
校勢の充実を図りつつあった実科高等女学校は、昭和15年度には専任初代校長に子野口信一郎(前小樽商業学校教頭)を迎え、多年の懸案である高等女学校への組織変更の体制づくりを進めた。
当時は日中戦争から米英に対する国際情勢が悪化し、国内においては戦時体制が強化され、資金・物資・労務などの調達に大きな困難がともなった。こうしたなかにあっても、15年8月に町会の議決を経て、翌16年4月から高等女学校(修業年限4年)を設置することを決め、12月20日に文部省へ申請するとともに、町長が上京してその促進に努めた結果、2月27日をもって認可となり、多年の懸案がいよいよ解決されることになった。
これにより16年4月から「北海道八雲高等女学校」と改められ、施設整備のための特別教室など4教室の増築工事を松原組の請け負いによって着工し、9月に2階建て110坪(約363平方メートル、理科室40坪・図書室20坪・音楽室20坪・廊下30坪)が落成して機能の充実が図られたのである。
このころは、近隣各町村にとっても唯一の女子中等教育機関であり、他町村からの通学者も相当数にのぼっていた。16年時点では長万部村の51名をはじめ、落部村15、森町12、利別村8、東瀬棚村3のほか、後志管内の黒松内村からも2名が通学するという状況であった。
地方費(庁立)移管
当初に予定したとおり、高等女学校への昇格だけにとどまらず、早急に地方費への移管を実現するため、昭和16年5月には道庁長官に陳情書を提出した。さらに7月には通学区域に属する各町村長に呼びかけて連署による陳情書を提出するなど、積極的な運動を進めた結果、8月以降学務部長をはじめ関係者が相次いで調査に来町し、地方費移管実現への期待が深められていった。さらに、当時の町出身道議会議員である米沢る。
高等女学校への昇格
校勢の充実を図りつつあった実科高等女学校は、昭和15年度には専任初代校長に子野口信一郎(前小樽商業学校教頭)を迎え、多年の懸案である高等女学校への組織変更の体制づくりを進めた。
当時は日中戦争から米英に対する国際情勢が悪化し、国内においては戦時体制が強化され、資金・物資・労務などの調達に大きな困難がともなった。こうしたなかにあっても、15年8月に町会の議決を経て、翌16年4月から高等女学校(修業年限4年)を設置することを決め、12月20日に文部省へ申請するとともに、町長が上京してその促進に努めた結果、2月27日をもって認可となり、多年の懸案がいよいよ解決されることになった。
これにより16年4月から「北海道八雲高等女学校」と改められ、施設整備のための特別教室など4教室の増築工事を松原組の請け負いによって着工し、9月に2階建て110坪(約363平方メートル、理科室40坪・図書室20坪・音楽室20坪・廊下30坪)が落成して機能の充実が図られたのである。
このころは、近隣各町村にとっても唯一の女子中等教育機関であり、他町村からの通学者も相当数にのぼっていた。16年時点では長万部村の51名をはじめ、落部村15、森町12、利別村8、東瀬棚村3のほか、後志管内の黒松内村からも2名が通学するという状況であった。
地方費(庁立)移管
当初に予定したとおり、高等女学校への昇格だけにとどまらず、早急に地方費への移管を実現するため、昭和16年5月には道庁長官に陳情書を提出した。さらに7月には通学区域に属する各町村長に呼びかけて連署による陳情書を提出するなど、積極的な運動を進めた結果、8月以降学務部長をはじめ関係者が相次いで調査に来町し、地方費移管実現への期待が深められていった。さらに、当時の町出身道議会議員である米沢勇の協力も得て間断なく運動を続けたところ、10月24日に行われた宇部町長、米沢道議と戸塚長官との会見において、地方費移管への内諾が得られたのである。
こうして昭和17年度の道費予算を決定する16年秋の道会に、八雲高等女学校移管費が提案されたが、これは米沢道議の努力が寄与するところも大きく、道会においては満場一致で可決されたのであった。
なお、この地方費移管に当たっては、校地、校舎および設備など既存財産のすべてを寄付するほか、校長住宅の建築と一か年間の運営経常費などを寄付するという条件が付されたものであったが、17年2月5日の町会において、これらについては満場一致で承認可決された。
町立高等女学校移管及之二伴フ寄附ノ件
当町立高等女学校ヲ昭和十七年四月ヨリ北海道地方費二移管シ其ノ為左ノ通北海道地方賢二寄附スルモノトス
第一、移管ノ時期ハ昭和十七年四月トス
第二、八雲町(以下甲ト称ス)ハ北海道地方費(以下乙ト称ス)ニ対シ左ノ既存設備ノ一切ヲ寄附スルモノトス
一、校 地
山越郡八雲町大字八雲村字サランベノ十三番 面積 二百四十三坪
〃 十四番 面積 三百八十二坪
〃 十五番ノ四 面積 二千二百六十九坪
〃 七番ノ六 面積 三千九百六十七坪
合計 六千八百六十一坪
二、校舎及附属建物
延 六百八十坪八合一勺二五
三、内部設備 一切
第三、甲ハ北海道庁ノ指示二基キ左ノ設備ヲ昭和十八年度迄二乙二寄附スルモノトス
一、校長住宅
建坪 凡三十坪
敷地 凡百坪
附属物置 凡五坪
塀 凡三十間
第四、甲ハ乙ニ対シ其ノ移管後一年間当該学校ニ要スル経常費(授業料其ノ他ノ収入ヲ控除シタル金額)五千二百六十四円ヲ寄附スルモノトス
こうして昭和17年4月1日から、北海道庁立八雲高等女学校と改称することについて3月4日に文部大臣から認可され、懸案の地方費移管が実現して、さらに堅実な歩みが続けられることになったのである。しかも22年4月からは5年制へと発展したのであるが、翌年4月の学制改革によって「八雲女子高等学校」と改称され、新しい時代に応じた教育機関として機能し続け、24年4月には男女共学という精神のもとに「八雲高等学校」に合併することとなり、発展的解消を遂げたのであった。
第3節 旧制八雲中学校
農学校の誘致運動
大正10年(1921)の秋、道庁の尾崎内務部長が転出したあとで、いわゆる尾崎案という中等学校増設計画が新聞によって報道された。その案によると、七か年計画で全道に中等学校14校を新設するというもので、そのうち渡島半島部に農学校1校が予定されていたのである。この情報に接した農村八雲としては絶好の機会とばかりに、木村町長は町会議員をはじめ有志の参集を求めて協議するとともに、11月5日には八雲座において町民大会を開催して協議の結果、”建設費その他当局の要求する寄付金は全部負担する”という力強い決議を承認し、農学校の誘致を満場一致で可決、「農学校期成同盟会」(会長・木村町長)を結成して強力な運動を展開することになった。このように態勢を整備したあと、同月8日宮尾道庁長官に対し農学校設置請願書を提出したのをはじめ、20日には町会もその請願を議決するなど活発に動き出したのであった。
中学校の設置運動
しかし、宮尾長官の構想としては、第一次大戦後の社会情勢の変化に対応しつつ北海道の開発を促進するためには、人材の養成を図ることが急務であるとして、尾崎案とは別に画期的な中等学校の増設拡充を企図し、道会の諮問を経て大正11年度から五か年計画で中学校の15校をはじめ、高等女学校9、師範学校3、その他の実業学校15、計42校の新設計画が決定されたが、このなかで大正12年度に八雲町に中学校の設置が予定されていることが明らかとなった。
こうした情勢の変化によって、12月18日に改めて遊楽座で町民大会を開いて経過を報告し、その実現に向けて努力する必要を認め合い、既に結成していた農学校期成同盟会を「八雲中学校期成同盟会」と名称を変更、続いて決起祝賀会を開催してその夜は盛大なちょうちん行列を行うなど、やがて中学校の設置を迎える町民の喜びはひとしおであった。
しかし、大戦後の不況に加えて、11年8月に本道を襲った台風による水害などの影響もあって地方財政は窮迫し、12年度の道費予算は、新規事業の中止や繰り延べをしなければならない状態となった。このため、新規事業である八雲中学校の実現も危ぶまれる情勢であった。この事態に直面した町では、11年11月4日に三たび町民大会を開催して対策を協議したところ、「道財政の都合で繰り延べとなるのはやむを得ない。無理をせず13年度に期待すべし」という意見もあったが、木村町長は「明12年度において実現を期さなければ、八雲中学校はいつ開校できるか見通しはつかない」と唱え、一歩も譲らぬ熱意をもって説得した結果、全員がこれを了解し、12年度実現を期すため、さらに次のような決議をして強力な運動を進めることとした。
決議
本道地方費五か年計画に或る中等学校増設案は、大正十二年度に於て我が八雲町に中学校設置を議決せられたり。而して今や地方財政緊縮の方針は、新事業の繰延べを伝うと雖も中等学校の増設は時運に鑑み優先急施を要するものたるを信ず。仍て挙町一致大正十二年四月一日より八雲中学校の開設を期す。
大正十一年十一月十四日
八雲町民大会
中学校の開設 大正12年度に設置実現の第一要件は、校舎建築に要する寄付金の確保であった。したがって期成会では早速募金にとりかかり、徳川家6万円、梅村多十郎・中島末吉の各1万円をはじめ、10万余円の記帳を得ることに成功し、校舎や校地の寄付を条件に、12年度設置の実現を道庁に要請した。これに対し道庁では、敷地の下調べを経て大正11年秋の道会に諮問し、翌年度開設の採否は参事会の決定に委任するというところまで進んだのである。
しかし、大正11年度設置の学校のなかには、道庁との約束を履行せずに遅延している例があるという実情から、道庁ではその設置決定の要件として、さらに厳しい履行上の保証を求めることになり、単に校舎建築費の寄付人名簿を提出するだけでは済まされないということになった。このため木村町長は、実現の成否がかかる参事会に、保証物件として国庫証券や約束手形などを担保とする手段を講じて最後の折衝を行った。こうした誠意と努力が認められて、大正11年12月20日の最終参事会において、ついに大正12年度八雲中学校開設が可決確定したのであった。
中等学校42校の増設五か月計画が、道財政の緊縮方針によって、13年度に一部が実現したほかは14年度以降すべて中止となり、しかも、13年度からは町村設置の中等学校を地方費に移管する場合、校舎や校地を寄付しなければならないことはもちろん、さらに1年間の経常費地元負担を求められるようになったのである。こういう経緯からみても、第三回町民大会における木村町長の力説は、まさしく先見の明とたたえて特筆すべきことであるとともに、当時の町出身道会議員である大田半三郎の多大な協力も忘れることのできないことであった。
北海道庁立八雲中学校は、こうして大正12年4月25日に八雲小学校の2教室やその他の施設を仮に当て、第一学年91名を収容し、初代校長に函館師範学校教頭瀬谷真吉郎を迎えて開校の式典を挙げ、当日町民はこぞって国旗を掲げ祝ったのである。
校舎の建築
校舎は錦ケ岡(現、自衛隊基地内、片桐・小泉・竹内・川口四氏の畑・牧場の提供)に予定どおり大正12年10月に完成した。初めの計画では、三か年継続事業として逐次校舎や付属施設を完成すればよいことになっていたので、さきに記帳した寄付金も三か年分納を条件にしていたのは当然であった。しかし道庁側の条件強化によって、初年度にすべてを完成させなければならなくなったので、資金確保のためこれらの寄付金を直ちに集めなければならないという難問題に直面した。このため最終的な解決方法として、寄付金の繰り上げ納入に対しては、銀行利率に相当する利息を寄付者に支払うという苦肉の策を考え出すなど、並々ならぬ努力が続けられ、資金の確保にことなきを得たのであった。
一方、主体工事である校舎(836坪=約2762平方メートル)の建築は、11業者を指名して入札を執行したが不落札となり、結局は5月11日に町会の議決を経て、工事費7万5000円、完成期限10月20日をもって随意契約を締結して着工し、予定どおり施行されて10月25日には生徒を新校舎に移転させ、11月8日に落成記念式が行われた。
また寄宿舎は、はじめ岡部五郎の所有建物を借りてこれに当て、舎生24名を収容していたが、寄宿舎の建築は、万難を排して設置された中学校の趣旨からも、さらに生徒募集のうえからも早急に必要とするものであった。そのため当初から予定に含め、中学校建築寄付金に余剰が生ずるという見込みのもとに計画を進めたのであるが、事業の繰り上げや追加工事などのためそれが不可能となり、計画を変更しなければならなくなった。
そこで町では、基本財産のうちから2万8000円を充当して、生徒100名を収容できる平屋建て257坪余(約848平方メートル)の寄宿舎を13年12月末に完成(大鵬寮と名づく)し、翌年1月舎生を仮の寄宿舎から移転させたのである。しかしこれは地方費に対する寄付ではなく、町有のまま道に有料で貸与し、その使用料で基本財産の支出額を補填していくというものであった。
校勢の充実
こうした苦難の末に開校された中学校ではあったが、開校当初の生徒の応募状況は必ずしも順調とはいえず、2学級定員100名を充足するため第3次募集もしなければならないという状況を示すこともあった。しかしその後は、不断の努力による伝統の重みと、社会の進展につれて進学希望者も増加し、これまでの2学級編制では対応できなくなったので道庁に要請した結果、昭和18年度から1学級の増設が認められ、定員も150名となったのである。
これにともなう校舎3教室の増築と作業室移転工事は、八雲中学校後援会が主体となって17年秋から着手したが、たまたま太平洋戦争の激化によって建築資材や労務の調達が困難となり、翌年4月の新学年を迎えても工事はようやくその半ばに達する程度という状態であった。
旧制八雲中学校(写真1)

校舎の移転
こうした工事半ばの昭和18年(1943)8月、突如として当町に陸軍飛行場が建設されることになり、八雲中学校の敷地全部がこの設置区域内に含まれることになったのである。このため、校地や校舎のすべてが軍に接収され、新たに校地を選定して移転しなければならないという非常事態を迎えたのであるが、戦局が深刻化するなかでの早急な問題解決は、不可能とさえ思われたのであった。
このため宇部町長は、ぜひとも陸軍当局で敷地の問題から新校舎の建築まで、一貫して解決するよう要請し続けたのである。当時戦局はますます緊迫の度を加え、5月29日アッツ島玉砕の報が入るなど、条件は非常にきびしかった。しかし幸いにも教育の重要性について軍関係者の理解が得られ、敷地の選定(住初町の現位置)から資材や労務の確保に至るまで順調に進み、飛行場工事の地鎮祭当日である6月27日に上棟式を行い、9月には工期を予定より短縮して落成し、22日から新校舎で授業を開始することができたのである。
なお、寄宿舎の「大鵬寮」は、これより前の8月に移転工事が終わり、仮寄宿舎にしていた安楽寺から全員が移ったのであった。
高等学校への移行
こうした経過をたどった北海道庁立八雲中学校も、戦後の学制改革によって昭和23年4月1日「北海道立八雲高等学校」と改められたのである。
旧制八雲中学校(昭和23年八雲高等学校)(写真1)

第6章 特殊・各種学校
第1節 特殊学校
特殊学級の設置
昭和28年(1953)4月に国立八雲病院が結核患者の施療を主体として、入院病床300を有する療養所に転換し、名称も国立療養所八雲病院と改められた。したがって、入院患者のなかには多くの学齢児童生徒がいることは当然であったが、これらの児童たちはその間勉学の道を閉ざされ、場合によっては長い間留年という結果を強いられる者も少なくなかった。
このような不幸な子供たちを、入院中でも可能な限り必要な教育を行い、長い間の休学や留年という弊害をなくしようとして考えられたのが、特殊学級の開設であった。すなわち、昭和32年6月この病院内に八雲小・中学校の特殊学級である「ひまわり学級」を開設し、第三病棟の3室を教室に当て対象者(当時児童37名、生徒9名)をそれぞれ八雲小・中学校へ転入させ、両校の児童生徒として授業させるというシステムをとったのである。
学級から分校へ
こうして児童たちの授業は、専任の教師がそれぞれ1名、アフターケアの先生2名によって運営されていたが、38年12月に認可を受けて「八雲小学校ひまわり分校」、「八雲中学校ひまわり分校」として正式に運営することになった。
道立移管への運動
昭和40年(1965)4月以後は、国立八雲療養所がこれまでの結核療養施設から進行性筋ジストロフィー症と重症心身障害児(者)を収容する医療機関へと性格転換が図られたことによって、その対象もさらに広がり全道各地にまたがるようになると、児童生徒も急激に増加するようになった。このため町としては、町立の分校として維持することは適当でないと判断し、道立移管について機会あるごとに関係機関に働きかけた結果、45年4月から「北海道八雲養護学校」として開校することとなった。
こうして、昭和32年以来13年間にわたってその使命を果たしてきた町立ひまわり分校は、この年3月をもって発展的に廃校となったのである。
北海道八雲養護学校
昭和45年4月に八雲小・中学校の分校から昇格して道立となった当校は、特殊学校として発足したのであるが、独立した校舎を持たず、非常に不便なことが多かった。このため校舎建築期成会を組織して関係機関に陳情を続けた結果、48年度の道予算に調査設計費が計上され、49、50年の二か年をもって延べ面積4351平方メートルの近代的な校舎と体育館が完成した。52年4月からは高等部も設置され、53年現在では、小学部75名、中学部45名、高等部30名を定員として運営されている。
また、道立に昇格と同時に後援会(会長・長谷川克巳)も組織され、物心両面にわたって援助を続けている。
北海道八雲養護学校(写真1)

第2節 各種学校
八雲自動車学校
経済成長時代に入ると自動車の普及度は徐々に上昇線をたどり、当町でも免許取得のために函館や札幌方面へ出向く人たちが増えはじめたことから、関係者の間に八雲地域に自動車学校を設立しようという声が高まってきた。
たまたま昭和28年に八雲町交通安全協会が、内浦町211番地(所有者・東鶴太郎)に自動車練習場を設置して使用していたが、33年11月「八雲自動車学校運営協会設立総会」を、八雲商工会において出資者約40名が出席して開催した。これは、八雲自動車学校の運営を目的として設立されたもので、設立総会当日で出資者66名、出資金額は121口で121万円、場所は内浦町210番地で敷地990平方メートルは民有地を借り上げ、校舎の規模は、学習室2・実習室・職員室・休憩室各1、その他2室、校舎総延べ面積は213平方メートルというものであり、このほかに車置場1棟50平方メートル、教材としての練習用自動車は約100万円で5台を購入、教職員は5人で、本科・速成科の2科を設置しようとするものであった。
こうして翌34年1月14日に各種学校として知事の認可をとり、校長には加藤慎一が就任し、「八雲自動車学校」として発足したのである。
昭和35年8月19日「社団法人八雲自動車学園」として知事の認可を受け、学園理事長には服部内匠が就任してその運営に当たり、38年1月には北海道函館方面本部公安委員会の指定校となったのである。
学校設立以来、免許取得希望者は年々増加し、特に40年以降は時代の動向によって車両は著しく増加の傾向を示した。さらにこれに加えて、農村における機械化の進展にともない、指定校となるまでに年間約1500名の卒業者を送り出していたのである。
公安委員会の指定後は、教習科目も大型・大型特殊・普通自動車と内容を充実し、指導員も14名となり、教習車両は大型2・大型特殊2、普通車18台を配備して、近代的な自動車教習施設としての整備を図った。
八雲自動車学校(写真1)

昭和40年には国道5号線の線形改良工事によって、従来の八雲交通安全協会の練習コースが使用不能となったので、4月に隣接の民有地を買収し、コース敷地1万4310平方メートル、コース面積1万484平方メートル(全舗装)を完成させ、新しい形式と規模を持った自動車学校となった。
八雲文化服装学院
衣服の洋裁知識と技能を研究し、職業的にも自立し得ると同時に家庭生活にも寄与し、技術を通じて婦人としての徳義を養成する目的で、昭和22年11月八雲町立岩88番地に「八雲文化服装学院」が創立され、翌23年6月30日子学第二三六一号をもって、各種学校として知事の認可を得た。
本科・師範科それぞれ修業年限1年、昼間・夜間50名の定員をもって開院、その後34年7月東雲町64番地に新築移転し現在にいたっている。
昭和39年ごろは最盛期を極めたが、その後、社会情勢の変化にともない中学・高校生の進学・就職率が高まり入学生徒は減少傾向を示しており、現院長は谷川光子が創設以来つとめている。
第7章 幼稚園・大学
第1節 幼稚園
幼稚園
戦前都市を中心に増加していた幼稚園は、戦争ぼっ発とともにしだいに減少し、戦後昭和22年「学校幼稚園教育法」の制定により、幼稚園を家庭教育を補うための教育機関から、正規の学校教育機関の最初の段階として規定し、教員についても「教育職員免許法」によって規定し、さらに27年には「幼稚園基準」を設定して振興充実をはかった。このため幼稚園の設立は漸増し、設立主体はほとんどが私立で、特に宗教法人によるものが多い。
私立八雲幼稚園
昭和26年(1951)元八雲町長眞野万穣が、任期満了退職後、幼児教育を目的として、末広町122番地の日本基督教団八雲教会と併設、26年8月学校法人の認可を得て私立八雲幼稚園を開設し、4歳および5歳児を教育したことにはじまる。現園長は中村周行で2学級80名の園児を収容し、園長以下6名の教諭によって幼児教育が進められている。
私立マリア幼稚園
昭和33年(1958)3月、八雲カトリック教会は幼児教育を目的として、東町19番地に教会と併設してマリア幼稚園の設立認可を得、同年4月1日初代園長奥田礼子により開園したのがはじまりで、現園長はロバート・ジュニイエで、認可学級数3、園児数120名、教員5名によって運営されている。
第2節 大学
日本大学農獣医学部八雲演習林実習所
日本大学と当町とのかかわりは比較的古く、戦後の昭和22年に富咲(トワルベツ川左岸)から山崎にかけて、およそ2400ヘクタールに及ぶ広大な林地を鳥獣医学部の演習林として取得したことから始まる。しかし同大学ではこれを直ちに造林する計画をもつこともなく、長い間自然林として管理するだけにとどめていた。
昭和40年代に入り、同大学では本格的な造林計画を立てることになった。すなわち、土地提供者として日本大学、資金提供者として森林開発公団、作業提供者として八雲町森林組合というように、この三者によって分収造林の協議が整い、45年秋から55年春までの計画で、当面の造林可能地983ヘクタールにトドマツの新植事業が進められたのである。またこのほかに、大学の単独事業として53年春から55年秋まで、およそ210ヘクタールの新植事業も行われた。
こうしてようやく造林の手が加えられるようになったのを契機に、植林地をはじめとする演習林の巡視管理や育成状況の調査などのため、これまでよりは関係者の来往が多くなることが予想された。また、この広大な林地を、本来の目的にかなう教職員や学生の実習地として活用することを考慮した大学当局では、上八雲市街の一角に適地を選んで実習所を新設する計画を立て、52年10月に鉄筋コンクリート2階建てで、30数名を収容できる施設の建築に着手し、翌年春にこれを完成させた。
日本大学農獣医学部八雲演習林実習所(写真1)

こうして「日本大学農獣医学部八雲演習林実習所」として8月から使用を開始し、関係者によって活用されることになったのである。なお、この実習所敷地に隣接する約2ヘクタールの土地には、将来各種の樹木を植えて見本林にする計画がもたれているという。
北里大学獣医畜産学部付属八雲牧場
昭和47年(1972)に当時過疎化が進みつつあった上八雲(主として旧八線地区)の土地の有効利用に着目し、肉牛の育成牧場経営を計画した東京の人香川治義(当時財団法人全日本空手道連盟理事・事務局長)が、土地の所有者らと協議を進めて約260ヘクタールの確保に成功した。そしてこれら所有者と協調して同年10月に農業生産法人「有限会社八雲牧場」を設立した。こうして早々に施設の整備に着手し、事務所兼管理舎・牛舎・機材庫など各一棟のほかに豚舎二棟を建て、翌年から逐次面積を拡張しながら肉牛と豚の育成を主な事業として経営を開始したが、間もなく経営不振に陥るという状況を迎えた。
ちょうどこのころ、秋田県十和田市に本拠をおく北里大学獣医畜産学部が、既設の牧場や施設が手狭になったので、より充実した学生の研修牧場を造成するための適地を探していた。こうしたおりから、さきの八雲牧場に着目して検討を進めた結果、この周辺地域が純酪農地帯であること、八雲牧場による草地造成が進んだ土地であること、などを適切な要件と認め、これを買収して活用したい旨の意向が、昭和50年春に町に伝えられた。
この申し入れは、当時、大学の誘致に熱意を示し、将来における土地資源の有効活用に期待を寄せていた町の希望にかなうものとして歓迎されたが、さらに50年12月には町議会でも「北里学園誘致に関する決議」を行い、積極的にこれを迎える姿勢を示すなど要件が整った。これにより町を仲介として順調に協議が進められ、北里大学では有限会社八雲牧場の所有地約260ヘクタールと既存施設を含め一括買収して進出することをここに決定したのであった。こうして51年早々に「北里大学獣医畜産学部付属八雲牧場」と名付け、既存施設を利用して、短期、小規模ながら研修牧場として使用を開始したのである。
昭和51年7月から旧八線地区において本格的な建設工事が着手され、鉄筋造り円形牛舎三棟をはじめ、関連施設の整備が進められたが、これに併せて北里大学PPAの寄贈による「八雲綜合実習所」の建設も行われた。この実習所は、鉄筋コンクリート三階建て、延べ1284平方メートルで、研究室・会議室のほか、約100名を収容できる宿泊施設が設けられており、全学部の教職員や学生らの研修施設として使用されるもので、53年7月に開所された。
また、この実習所の隣接敷地には、北里研究所に所属して各種ワクチン製造用のSPF卵生産を目的とする「SPF鶏舎」いわゆる無菌鶏舎二棟、延ベ1153平方メートルが建てられ(53年12月完成)、牧場に一段と光彩を添えた。
こうして整備は着々と進められ、学生の研修施設としてきわめて高い水準を誇る施設となった。一方、牧場面積も逐次拡張し、山林を含めて既に380ヘクタール余りとなり、積極的な草地造成を進め、肉牛を主として乳牛・めん羊・鶏などを飼育しながら、学術向上をめざして運営されている。
北里大学獣医畜産部八雲綜合実習所(写真1)

第8章 社会教育
第1節 社会教育のあゆみ
制度上の一般学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年や成人に対して、随時、随所で行われる組織的な活動を社会教育と呼んでいるが、最近では「生涯教育」ともいわれ、こうしたことから人間の教育は”ゆりかごから墓場まで”絶えずなんらかの形で学習し、成長し続けるものであるといえよう。
社会教育が通俗教育という名のもとに進められたのは、日露戦争以後のことであるが、八雲村ではそれ以前に既に青少年に対する社会教育が進められていたといえる。
青年団活動の兆し
明治11年(1878)に徳川家開墾試験場では、移住後間もなく青年4名を開拓使七重勧業試験場に派遣し、2年間泰西農法の習得をさせ、かれらが帰った翌年の14年に独身舎を設け青年を収容して開墾を助けさせた。翌15年これらの青年有志の中から20歳前後のものおよそ10名が鷲の巣耕舎を設立し、欧米の農具を使用して大農経営を始め、大きな収穫小屋を建てるなど青年たちの意気は盛んであった。こうした建物の材料などを伐木の際、有為な青年2名が犠牲になったが、この補充には犠牲者の弟が参加し、21年ごろまで続けられた。明治17年にはこれと同じ方式で、野田追耕舎が創設されている。
徳川家開墾試験場へ入植してから満3年を経過した明治14年ごろから、当初の開拓精神がしだいに薄らいできたので、これを憂うるものが集まり「松葵会(しょうきかい)」を起こし、士気の振興に努めた。また「攻玉会」を組織して移民全員を加盟させ、申合罰則を設けたり、農事改良や将来の方針などを話題に討論会を開催し活発な論議を交わすなど、青年団活動の兆しがみられたのであった。
青年団の推移
青年団活動がしだいに具体化し、明治15年(1882)8月には、「青年党」が組織された。そして団則に相当する「八雲村開墾地青年党郷約」を定め、
第一条 知識を増殖し品行を矯正し当場の維持進歩を以て己が任とするを要す
第二条 党中に於て怠惰不品行の者あるときはこれを忠告切諫すべし
(第三条以下略、大島 鍛著「八雲開墾五十年史稿」)
と約し、党費は月5銭、修養のため月一度の例会を開催して、書籍の購読・討論会・演説会を行うほか、村内に困窮者や災害を受けたものがあるときはこれを扶助するということなども決められ、党員49名によって発足した。これが八雲村における青年団活動の始まりであるばかりでなく、北海道において最初に結成された青年団体であろう。
なお、これより時代的にはかなり後になるが、野田生には杉立正義を会長とする青年会があって、夜学などを続けており、またこれとは別に、明治35年(1902)野田生青年同志会が組織され、夜学を開き学科の補習を行ったりしていたという。
これらのほか、明治の末期から大正にかけて、各地域に青年会が結成された。もちろん地域の生活に密着した青年の自主的な組織であり、八雲村では明治40年の大新青年会、42年の鷲の巣青年会などが結成の早期に属し、それぞれ夜学会を開いて教養を高め、弁論会や試作・研究・品評会などを開催、活発な活動を続けた。その他市街地の八雲青年会(結成年代不詳)をはじめ、44年の黒岩・久留米、大正2年(1913)の大関・常丹などと次々に結成され、6年には連合青年大会が開催されるという発展ぶりであった。なお、この時期落部村でも同様であり、明治38年(1905)の落部、40年の川向、44年の茂無部・野田追、45年の蕨野などと相次いで結成されていった。しかしこれらの青年会の結成は、日露戦争後において内務省や文部省の通達により、既存団体の指導とともに新設を促すなど、積極的な保護育成に乗り出し、青年団体の官製化を図ったことによるものであった。こうして大正4年にはこれら青年会の性格が「修養団体」とされ、その活動は主として各種修養のための夜学会・弁論・剣道・相撲・立毛品評会の開催や道路愛護などの社会奉仕であったが、一方では広範な国民教化政策の中に組み込まれ、国の定めた方針に基づいて市町村が育成指導することになっていた。
大正10年6月には文部省の官制改正に際し、「通俗教育」を「社会教育」と改め、社会教育行政の整備に力が注がれた。また、大正末期にはこれらの青年会はすべて青年団と改称され、その活動分野もしだいに産業活動やスポーツ振興に向けられるようになっていった。
そしてこれらの全町的な連合体も組織されて「八雲連合青年団」と称し、会長には町長が当たるという性格のものとなり、昭和3年度(1928)からはこれら連合青年団、同女子青年団、少年団に対して町費が補助されるようになった。単位団体は昭和10年に例をとれば、20団体、605名を数えていた。この連合会は、毎年陸上競技大会を開催し、選手を茅部・山越郡の町村対抗に派遣して覇を競うのが年中行事の一つであった。
しかし、日中戦争が激化して戦時体制が浸透するにつれ、社会教育に関する種々の団体の統合や中央集権化が進んでいったなかで、昭和16年(1941)には男女青年団と少年団の組織統合が行われ、全町の団体が一体化されて町長を会長とする「八雲町青少年団」となり、戦争遂行の協力機関となっていったのである。
こうして青年団体の歩んだ道は、単に八雲町だけではなく全国的なもので、もちろん落部村でも同様であった。
落部連合青年団弁論部(写真1)

女子青年団
明治末期から大正にかけて男子青年団が結成されるのと並行して、女子青年の団体としていくつかの「処女会」が結成されていった。明治41年(1908)2月に大新で婦人会創立総会が開催され、会員22名をもって発足したのをはじめとして、45年落部に、大正6年(1917)野田追、8年には野田追処女明倫会が、さらに翌9年には野田生緑会、14年に久留米処女会(松操処女会)などが結成されていった。しかし、これら女子青年団については、詳しい記録が残されていないので不明な点が多い。
こうして各地に女子青年団が結成され、大正末期になると女子青年の修養機関として積極的な組織づくりが進められるとともに、その名称も「女子青年団」と統一されるようになり、昭和2年(1927)で12団体370名(落部村不詳)、同10年で16団体293名と記録されている。これら女子青年団も「八雲連合女子青年団」を組織し、毎年連合青年団大会を開催、講演会やレクリェーションなどの行事を催して盛会をきわめたが、昭和16年に「八雲町青少年団」に統合された。このことは落部村でも同様であったと思われる。
戦後における青年団は、ほとんどが男女青年の組織に再編され、特殊なサークル活動団体は別として、いわゆる女子青年団に類するものは姿を消している。
少年団
少年団は、大正11年(1922)に皇太子の来道を記念して結成するものが増加し、翌年6月には道庁長官を総裁とする少年団北海道連盟が結成されるようになっていた。八雲町においてもこうした情勢を背景として、大正13年10月には佐久間橘右衛門らの提唱により、長江時三郎を初代団長に八雲少年団が発足した。 この少年団は、
「神明を尊び、皇室を敬い、人の為世の為国の為に尽し、少年団のおきてを守る」
という三つの誓いをたて、日本少年団連盟(のちボーイスカウト連盟となる)に加盟し、地元小学校の教師を指導者として訓練や社会奉仕を行い、固定・移動キャンプなどに活動したのである。しかし、指導者の転勤などによって、後継者が得られないまましだいに組織的な活動ができないようになってきた。そのうえ、昭和16年には戦時統制強化のもとで青少年団体は町長を団長とする「八雲青少年団」に統合され、いわゆる第一期時代を終わった。
戦後の昭和24年(1949)に公認指導者となった小泉武夫が、元団長松田武策、元隊長山本猛らとはかり、隊の精神的、財政的な援助育成を目的とする育成会を9月23日に組織し、会長に西亦治信を選んで準備を進め、翌25年11月23日にボーイスカウトを結成した。そしてテントその他の訓練資材を整備し、制服も整えられて所定の訓練もできるようになったので、28年10月に日本ボーイスカウト連盟に加盟し、「山越第二隊」として登録されたのである。それ以後は活発な活動が続けられていたのであるが、再び中心的な指導者の転住などにより、36年を最後に自然解散のやむなきに至った。
八雲少年団(写真1)

ボーイスカウト山越第二隊(写真2)

昭和43年(1968)には浅尾一夫の提唱により、旧ボーイスカウト関係者やその他有志の手によって、「ボーイスカウト育成会」(会長・浅尾一夫、団委員会委員長・長谷川克巳)が組織され、同年9月30日に「八雲第一団」として加盟承認されたのである。こうして11月11日に佐久間力蔵を隊長に、31名の隊員によって結団式を挙げ、新たに発足したのであった。
結団後は、ライオンズクラブなどからの援助を受けて設備を整え、野営訓練・隊集会・班長・次長訓練・奉仕活動などが続けられ、日本ジャンボリー大会に参加するなど、昭和初期の全盛時代をよみがえらせている。
ガールスカウト
ボーイスカウトの活動に対応し、昭和28年(1953)にりっぱな社会人となるよう少女の心身を鍛えることを目的として、ガールスカウトの結成について準備を進め、同年12月6日団委員長に服部レイ、リーダーに太田武子を選任して結団式を挙げ、「北海道第十一団ガールスカウト」として発足した。
しかし、ボーイスカウトのような伝統もなく、あまり活発な活動もみられないまま、昭和31年ころには自然解消になってしまうという短い運命であった。
地域子ども会
当町の子ども会は、一部の篤志家の活動によって2、3のグループができていたが、昭和41年(1966)11月に相生児童館が完成し、専任の職員が管理して館を利用する子どもたちを世話するとともに、各町内に子ども会結成の呼びかけをするようになってから、次第にその数が増えてきた。さらに、昭和43年3月に青少年教育の一元化を図るため、児童館の管理を町民課から教育委員会に移管してからは、その動きがいっそう活発になった。また、昭和44年3月に北海道地域子ども会育成連絡協議会から講師を招いて、第一回八雲町地域子ども会のつどいを開催して指導を受け、研究協議してからは運営と指導が一段と活発になり、町費から助成金を出すなどして育成に努めている。昭和56年現在では前ページ以下の45団体が登録して活動を続けている。
|
子ども会名 |
会員数 |
住 所 |
育成会長名 |
|
東 町 1区 |
26 |
東町 10 |
泉 功 |
|
〃 2区日の出 |
32 |
〃 289の1 |
鈴 木 英 雄 |
|
〃 3区 |
64 |
〃 240 |
安 藤 兵一郎 |
|
〃 4区たんぽぽ |
22 |
〃 48の2 |
池 口 昭 秋 |
|
〃 5区 |
28 |
〃 153 |
藤 原 宏一郎 |
|
〃 6区 |
29 |
〃 206 |
小 島 秀 雄 |
|
東雲町 1区 |
21 |
東雲町51 |
永 井 正 秋 |
|
〃 2区あさひ |
35 |
〃 24 |
佐々木 重 雄 |
|
〃 4区ポプラ |
45 |
〃 9の1 |
東 勝 之 |
|
〃 5区 |
28 |
〃 51 |
服 部 内 匠 |
|
栄 町 1区 |
23 |
栄町 30の13 |
岩 本 晨 |
|
〃 3区 |
69 |
〃 47 |
石 川 潔 |
|
〃 4区竹の子 |
50 |
〃 |
中 村 浩 造 |
|
住初町 1区 |
28 |
〃 15 |
稲 垣 亀治郎 |
|
〃 4区なかよし |
16 |
住初町88 |
小 林 晶 二 |
|
出雲町 3区のばら |
47 |
出雲町40の22 |
小野寺 幸 男 |
|
〃 5区コスモス |
41 |
〃 60の115 |
藤 田 公三郎 |
|
内浦町 1区はまなす |
53 |
内浦町60 |
船 田 正 一 |
|
〃 2区しおかぜ |
50 |
東雲町21の5 |
能 戸 昇 |
|
宮園町 2区 |
41 |
宮園町44 |
津 坂 忠 |
|
三杉町 三 杉 |
42 |
三杉町25の14 |
藤 本 富 一 |
|
富士見町 ひまわり |
62 |
富士見町127 |
伊 藤 弘 |
|
豊浦町 ユーラップ |
40 |
豊河町 5 |
金 山 嘉 重 |
|
立 岩 青 空 |
36 |
立岩 73の8 |
若 林 松 彦 |
|
山 崎 |
50 |
山崎 375 |
吉 田 清 |
|
黒 岩 なかよし |
43 |
黒岩 212 |
黒 川 信 勝 |
|
大 新 |
33 |
大新 318 |
竹 内 宏 之 |
|
赤 笹 |
12 |
桜野 28 |
横 田 基 |
|
東 野 |
80 |
東野 774 |
林 兼 明 |
|
野田生 みらい |
43 |
野田生 |
金 沢 光 栄 |
|
〃 ゆずりは |
31 |
〃 420 |
高 野 勝 |
|
〃 あすなろ |
43 |
〃 |
長谷川 一 男 |
|
落 部 1 町内 |
41 |
落部 350 |
豊 岡 善 哉 |
|
〃 2 |
11 |
〃 328 |
宮 本 新 一 |
|
〃 3 |
23 |
〃 76 |
菅 原 勝 市 |
|
〃 4 |
26 |
〃 545 |
小 川 昭 二 |
|
〃 5 きたかぜ |
41 |
〃 38 |
高 谷 貞 失 |
|
〃 6 ちどり |
27 |
〃 20 |
大 島 則 雄 |
|
〃 7 若 草 |
61 |
〃 850 |
山 内 英 二 |
|
〃 8 |
43 |
〃 505 |
相 木 一太郎 |
|
〃 9 |
44 |
〃 135 |
村 上 克 失 |
|
〃 10 浜の子 |
39 |
〃 631 |
佐々木 国 彦 |
|
栄 浜 |
44 |
栄浜 96 |
淡 路 光 芳 |
|
浜 松 |
39 |
浜松 239 |
石 引 戦 治 |
|
元 町 |
50 |
元町 49 |
伊 藤 政 一 |
戦後の青年団
昭和16年に戦時体制という枠組みのなかで、やむなく八雲町青少年団に続合された各団体も、戦後再び自主的、民主的な団体として生まれ変わり、各地に次々と結成されていった。そのほとんどは従前のように地域を単位とするものであったが、とくに有志青年の集団というか、サークル的な青年団体が誕生したことに特色があった。
こうして結成された青年団体は、その融和連携を深めて相互の向上を図るため、昭和24年(1949)12月に「八雲町青年団体協議会」を結成して活発な活動を展開した。特に翌25年度から始まった町体育大会への強力な参加母体となり、その盛衰に大きな影響を持つほどであった。
しかし、社会情勢の変化にともなって青年の属する集団は、20年代後半には年齢・職業・性別・趣味などを同じくする青年の集まりが多くなり、討議にも新しい方式が取り入れられるなど変化がみられるようになった。また、農業改良普及事業の発足にともなう農村青少年クラブ(4Hクラブ)の結成など、種類の多様化がみられ、地域を単位とする一般青年団は退勢の傾向を示すに至った。昭和34年(1959)当時は34団体、771名を数えていたのに対し、44年では12団体、173名、50年では10団体、94名となるなど、団体数が少なくなると同時に単位団体当たりの団員数も減少し、小規模となる傾向が強くなっており、その育成が大きな課題となっている。56年現在では次のとおりである。
青年団体名
1 八雲町青年団体協議会加盟単位団体名
|
団体名 |
団員数 |
|
立 岩 青 年 団 |
6名 |
|
山 崎 青 年 団 |
10名 |
|
熱 田 青 年 団 |
6名 |
|
大 新 青 年 団 |
5名 |
|
八雲農協軽音楽同好会 |
9名 |
2 青年グループ、サークル
|
人形劇研究会「やまんば」 |
7名 |
|
映画同好会「ポチョムキン」 |
15名 |
|
うたごえサークル 「コール八雲」 |
7名 |
|
写真同好会「無影」 |
8名 |
|
童話サークル「ピーターパン」 |
5名 |
|
読書サークル 「め」 |
4名 |
3 その他
八雲町青年連絡会議・漁業協同組合青年部(八雲・落部)
農業協同組合青年部(八雲・落部)・商工会青年部
4Hクラブ
産青連の設立
一般青年団の衰退傾向がしだいに顕著になっていたころ、町内主要産業団体に所属している青年部が、相互の融和と提携を図り町産業の総合的な発展に寄与することを目的として、昭和42年(1967)3月に「八雲町産業団体青年部連絡協議会」を設立した。すなわち、八雲・落部両農協、同両漁協、八雲商工会に所属し、従来はそれぞれが何のつながりももたず、独自の活動をするにすぎなかった5青年部が共同の場を設け、各産業間、団体間の壁をとり除きながら研究を積み重ね、意見発表会・視察旅行・交歓スポーツ大会・産業まつりなどの事業を通じて、より一層の連帯を深めつつ活動を続けようとするもので、他にあまり例のない独得な団体として評価され、今後の活動に期待が寄せられている。
社会教育の振興
戦後、民主化の推進にあたり、主権者である国民の社会人としての教養向上、すなわち、公民教育の重要性が強調された。こうしたことから眞野町長は、昭和22年(1947)に早くも社会教育推進の中心となる公民館の設置に着目し、社会教育法施行(昭和24・6・10施行)の前に、24年5月3日公式に開館した。また、翌6月には図書館も付設して整備を図るとともに、青年学級8学級を開設するなど、その活動を通じて社会教育の積極的な推進を図り、現在の基礎をつくったのである。
社会教育法の施行に基づき、翌年1月に公民館運営審議会委員と社会教育委員を委嘱して体制を整備した。7月には公民館敷地内にテニスコートを造成、さらに9月には八雲町体育大会を創始し、スポーツを通じて健全な心身の育成に努めた。また、27年10月には公民館内に郷土資料室を設けるなど、社会教育事業は着々と推進されていった。
一方、昭和24年12月の八雲町青年団体協議会の発足をはじめとし、25年4月の体育協会、26年10月の婦人団体連絡協議会、そして30年9月の文化団体連合会など、社会教育団体が相次いで組織された。
社会教育推進指導員
社会教育振興策の一つとして、北海道教育委員会が昭和51年度から実施した事業に「社会教育有志指導者育成事業」がある。これは、社会教育に関する活動に対し、ボランティアとして本人の意志から進んで参加しようとする有志を「社会教育推進指導員」として登録し、これを育成しようとするものである。
当町でも、この趣旨に賛同のうえ率先して登録に応じた者もあり、昭和55年現在で19名が民間指導者として活動を続け、社会教育の充実と発展に尽くしている。
青少年問題協議会
昭和35年(1960)6月に町長の付属機関として「八雲町青少年問題協議会」を設置した。
これは昭和28年(1953)に制定された青少年問題審議会および地方青少年問題協議会設置法によって、青少年の指導、育成、保護および矯正に関する総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議し、その実施を期するために行政機関相互の連絡調整を図ることを目的として組織したものである。
この協議会は、町議会議員が2名以内、関係行政機関の職員と学識経験者各6名以内の委員をもって構成し、町長が会長を務めることとされており、また、運営を円滑にするため、関係行政機関の直接事務担当者などを幹事に委嘱して、具体的な調査・立案・実施の業務に参画させることとしている。
こうして、常に青少年の健全育成を主眼に環境の浄化を進め、スポーツ、レクリェーション、研修会などを通じて、非行防止に努めている。
また、次代を担う青少年の知識見聞を広め、豊かな人間性を養うことを念願して、昭和48年度から隔年実施の青少年海外派遣事業「道民の船」に協賛、積極的に参加を奨励し、47年度3名、50年度8名(ほかに道費負担2名)52年度4名、54年度5名、56年度3名を派遣したのである。
このほか、49年度から町の単独事業として、毎年(ただし53年度は都合により中止)マイクロバスによる道内バスツアーを実施、25名内外の青年男女の研修に努めている。
農業後継者の育成
大正12年(1923)に開設し、昭和18年(1943)に青年学校に統合されるまで、継続して酪農後継者を育成した八雲高等国民学校の伝統を継承し、酪農青年の育成に努めようと、昭和27年(1952)から4年間、徳川義親を校長として八雲高等農業学院を開設した。この学院は、新制中学卒業生で農業に従事している者、あるいは将来農業に従事しようとする者を対象に、二か年を修業年限として、普通教科、実業教科、課外講演などを行い、教養と知識技能を身につけ希望をもって農業に従事できるような、農村の中堅人物の育成を図ったのである。
その後、昭和31年度からは野幌機農高等学校の通信受講生として育成することになった。
八雲町農業学園の開設
農業の近代化にともない、これにふさわしい農業後継者を養成することを目的に、昭和40年(1965)7月道が奨励した「北海道八雲町農業学園普通科」(酪農と家庭科、学園長・町長)が開設された。この学園は、道と町がそれぞれ費用を分担して運営するもので、渡島管内では当町と大野町に設置されたのである。
対象者は、中学校を卒業して農業実務に従事する男女で、修業年限は二か年とし、合宿訓練や通信教育によって農業経営のため優れた知識と技能を習得させようとするもので、公民館が直接担当して学習はもちろん冬期合宿教育も公民館で行ったのである。
その後、農業事情が変わったこともあって、入園者もしだいに減少傾向をたどり、近隣町村にも呼びかけたのであるが普通科への希望者は数人となった。なお、特別教務としては大島日出生が委嘱されていた。開園以来の在学状況は上表のとおりである。
渡島支庁農業学園への移行
昭和45年(1970)になって前記の農業学園普通科は、中卒者の八雲高等学校農業課程に進学する者との関連で、専門課程にすべきであるとの見解から、渡島支庁にその旨を要望のうえ道の認可を受け、昭和45年度から「渡島支庁農業学園酪農課程」として、特別教務に大竹良一を委嘱し新たに発足したのである。なお、現在の特別教務は友善功が委嘱されている。
学園長は渡島支庁長、副学園長は八雲町長があたり、51年4月から事務所を農業改良普及所に移し、酪農後継者の育成に努めている。昭和54年度までの在学状況は別表のとおりである。
冬期酪農学校
冬期酪農学校(ウインタースクール)は、戦後間もない昭和21年(1946)1月に八雲科学研究所の仲間が中心となり、恵庭の牧場主福屋茂見を招いて8、9、10の3日間、酪農に関する講習会を開催したことにはじまる。
八雲町農業学園在学状況
|
学年/年度 |
1年 |
2年 |
計 |
町の生徒 |
他町の生徒 |
|
40 |
46 |
− |
46 |
46 |
− |
|
41 |
20 |
41 |
61 |
60 |
1 |
|
42 |
19 |
18 |
37 |
31 |
6 |
|
43 |
19 |
19 |
38 |
23 |
15 |
|
44 |
15 |
17 |
32 |
13 |
19 |
渡島支庁農業学園在学状況
|
年度/学年 |
1年 |
2年 |
計 |
町の生徒 |
他町村の生徒 |
|
45 |
21 |
4 |
25 |
16 |
9 |
|
46 |
12 |
12 |
24 |
14 |
10 |
|
47 |
12 |
10 |
22 |
11 |
11 |
|
48 |
13 |
7 |
20 |
12 |
8 |
|
49 |
10 |
9 |
19 |
17 |
2 |
|
50 |
6 |
10 |
16 |
16 |
− |
|
51 |
9 |
6 |
15 |
11 |
4 |
|
52 |
10 |
6 |
16 |
13 |
3 |
|
53 |
11 |
9 |
20 |
13 |
7 |
|
54 |
9 |
10 |
19 |
12 |
7 |
当時の酪農界は不況のどん底にあり、いかにしてその危機を乗り越えるかという大きな問題に直面していた時代であった。昭和22年には北海道酪農協同組合が「酪農青年研究会要綱」を全道の系列工場に配布して、いわゆる「酪青研」の結成を促したことにより、昭和24年4月には「酪青研八雲地方連盟」が結成され、各地域に単位団体が組織された。
こうして結成された酪青研が主体となって、関係機関団体の協力により、毎年1月8、9、10の3日間が学校の開設日として定着している。講師はその道の権威者が選ばれ、第一回の開催から中断することなく継続し、30年からは会場が公民館となった。57年で37回を数え、酪農振興発展のため大きく寄与している。
第2節 婦人団体の変遷
愛国婦人会
明治33年(1900)義和団事件(北清事変ともいう)に際し、軍の慰問から帰った奥村五百子が、その経験によって傷病兵や遺家族救護の重要性を説き、34年3月3日を期して「愛国婦人会」を創設のうえ、全国を行脚して多数の会員を集めるなどその拡充に努めた。この愛国婦人会は、皇族が歴代総裁となり、上流婦人多数を会員として発展し、昭和15年(1940)末の全国会員数は650万人を数え、わが国最大の婦人団体となっていた。
八雲や落部においては、明治37、8年の日露戦争当時すでに愛国婦人会に加入していたものもあるといわれるが、第一次世界大戦を経て入会者が次第に増加し、やがて八雲・落部それぞれに委員区が置かれた。愛国婦人会は第一次大戦後、農村託児所などの社会事業を行い、昭和3年に八雲委員区では、元町の西教寺本堂に「愛国婦人会八雲託児所」を開設し、町費の補助もあって3年間継続して実施、働く婦人のために寄与した。しかもこの託児所は、当町における保育施設の初めでもあった。
昭和7年(1934)には市町村に分会をおくこととなり、八雲町分会、落部村分会などと称し、分会長にはそれぞれ町村長夫人があたるのが通例となった。各分会は、会員の増加とともにその活動が活発になり、町内外を問わず災害時の慰問などにあたったが、特に昭和9年の函館大火の際は、衣料その他救援物資のとりまとめや縫製などに、分会幹部をはじめ多数の会員が出動して活躍した。
満洲事変そして日中戦争から太平洋戦争へと進むにしたがい、活動の主力は出征軍人やその家族の慰問、戦没者および遺族への弔慰、勤労奉仕、廃品や茶殻の回収、座布団その他の物資献納に向けられていった。特に八雲町分会では軍人の着用するじゅばんや袴下(こした)の「委託縫製作業」の指定を受け、八雲小学校校舎の一部、軍人分会の会館などを作業所にあてて奉仕活動を行ったのであるが、昭和17年(1942)には軍部と官庁の監督のもとに組織された「大日本婦人会」に統合された。
愛国婦人会八雲託児所(写真1)

愛国婦人会による縫製作業(写真2)

国防婦人会
満洲事変ぼっ発後の昭和7年(1932)に大阪で結成されたのを初めとし、次いで東京にも結成された軍事援護団体で、昭和9年にはこれらを統合して「大日本国防婦人会」と称した。この婦人会は、軍の監督と後援を受け、しかも幹部は陸海軍大臣などの現役将官夫人があたり、戦時体制における婦人の国家協力を唱え、傷病軍人や遺家族の後援、慰問品の募集、防空訓練などの活動にあたった。しかし末端町村においては、愛国婦人会の会員と重複する形となるため、容易に浸透しなかった。
昭和12年(1937)に日中戦争が起こり、国防の重要性が叫ばれるようになると、半ば強制的に各市町村に国防婦人会分会が結成されるようになったが、会員はほとんどが重複し、ただ愛国婦人会は国防色(カーキ色)の上着に白たすき(愛国婦人会と黒書)を掛け、国防婦人会は白のかっぽう着に白たすき(国防婦人会と黒書)を掛けたが、役員は双方を兼ねるのが実情だったので、必要に応じて使い分けする程度であった。
国防婦人会は、出征兵士を送迎するほか、防空ずきんをかぶってもんぺをはき、突破器や火たたきを持ち、バケツなどを使って防火訓練を行い、また、市街地の婦人たちは援農などの奉仕活動を主としたが、昭和17年に愛国婦人会とともに大日本婦人会へ統合された。
愛国婦人会の廃品回収(写真1)

大日本婦人会
昭和17年2月閣議決定によって、既存の愛国婦人会や国防婦人会をはじめ大日本連合婦人会などを統合し「大日本婦人会」が結成された。この婦人会は国家奉仕を根本方針に、軍部や官庁の監督のもとに活動し、軍人援護・防空訓練・廃品回収・貯蓄増強などに協力したのである。
八雲と落部にはそれぞれの支部が結成されたのは当然であり、しかも20歳以上の婦人は強制加入とされ、太平洋戦争の重大時局下における婦人の総力結集という形のもとで、各種の運動を展開したのであったが、昭和20年(1945)6月に国民義勇兵役法が公布され、義勇隊の編成とともに解散した。
以上の3団体は、少なくとも軍事援護協力団体であって、社会教育における婦人団体とはいえないかも知れないが、あえてここに掲記する。
戦後の婦人団体
昭和20年終戦によって、婦人の地位向上と親睦を図るとともに、家庭生活の合理化や社会奉仕などを目的に、地域・職種・宗教などを単位として自主的な団体が結成されるようになってきた。また、町内会や地域会ごとに婦入部を設けるところも少なくなかったが、これらは区域内で葬祭などがあったときの手伝い程度にすぎなかったのである。
1 八雲町婦人団体連絡協議会加盟単位団体名
|
団 体 名 |
会員数 |
|
野田生婦人会 |
45名 |
|
幸 婦 人 会 |
32名 |
|
八雲農協婦人部 |
250名 |
|
八重垣婦人会 |
5名 |
|
たちばな会 |
7名 |
|
落部婦連協 |
320名 |
|
商工会婦人部 |
30名 |
2 その他婦人団体
|
八雲漁業協同組合婦人部 |
142名 |
|
落部漁業協同組合婦人部 |
242名 |
|
落部農業協同組合婦人部 |
78名 |
|
各町内会婦人部 |
|
3 婦人グループ・サークル
|
読書サークル 「みち」 |
|
八雲婦人ボランティア |
|
農協婦人部若妻会 |
|
落部婦人ボランティア |
昭和26年10月には公民館の指導もあって「八雲町婦人団体連絡協議会」が結成された。この結成当時は、わずか6団体の加盟ではあったが、31年から事業として婦人運動会を開催するなど、婦人団体の連絡協調を図った結果、最盛期の34年には70団体の加盟を数えたのである。しかしその後農漁村部では、農協婦入部や漁協婦人部として統括
する傾向となり、各地域ごとの単位団体が姿を消すことになったので、35年には一挙に31団体となって活動が鈍くなる傾向が続き、56年現在では7団体、会員数689名である。
婦人団体名は前ページのとおりである。
第3節 スポーツ
往時のスポーツ
明治11年(1875)以来、遊楽部に入植した旧尾張藩士の中には、柔道・剣道・弓道・槍術・水泳・馬術などに優れた者がいたので、これらの振興については極めて盛んであった。
柔道は、神道流の達人である佐久間成信が指導し、ブイタウシナイ(現、花浦)で漁業を営むかたわら道場を設け、さらに明治30年(1897)には出雲町に道場を設けて多くの門弟を集め、このほかに槍術や水泳も併せて教授した。
剣道は、師範格の伊藤信旧が教えていたが、明治28年には石川錦一郎が出雲町に道場を開設して指導したので、小学校の児童を含めて広く普及した。また石川は、大正12年(1923)に庁立八雲中学校の設立後、剣道教師として嘱託を受け、数年間指導に当たった。
水泳は、前記のように佐久間が指導に当たり、大正9年には徳川農場が主催して、遊楽部川のサケ採卵場で水上運動会が開催された。
馬術は、太田正之丞が指導し、競馬会などを国道で開催した。また、珍しい競技として打毬(だきゅう)という球技を行った。これは唐から伝来したもので、江戸時代中期には盛んに行われたものであるという。八雲神社の境内に馬場を設け、紅白に分かれて馬上から毬杖(ぎつちょう)と称する長柄の叉手(さで)でまりをすくい味方のゴールに運ぶ、それを入れさせないように防御するというもので、明治の末ころまで行われていたという。
弓道は、杉立正憲が日置流尾州竹林派の伝統を指導し、八雲神社祭典には同好者とともに奉納した。この伝統は戦時中まで続けられた。また、庁立八雲中学校の初代校長として赴任した瀬谷真吉郎は、弓道を愛好してこれを普及し、現在その流れをくむ人が数名残っている。
これらのほか、野球は明治20年代に札幌農学校の卒業生によって伝えられたといわれ、明治43年には小学校に普及され、函館の弥生小学校と交歓試合を行って勝利をおさめた。また、大正初期には松田武策を会長とする社会人のクラブが結成され、函館太洋クラブを招いて交歓試合などを行っている。
運動会は、明治43年(1910)8月に鷲の巣・大所両青年会連合で開催したのが最初であり、また、大正4年 (1915)から八雲小学校同窓会が主催して、毎年8月15日に校庭で開催し、多くの観客を集めて盛会を極めた。これが発展して12年には徳川農場で直線100メートルのとれる真萩グラウンド(現、道立養護学校)を設置したので、正規のルールによる陸上競技大会が行われるようになった。この大会で優秀な成績を挙げたものを、15年から開始された茅部山越郡管内町村陸上競技大会に派遣し覇を競ったのである。この大会はその後戦争たけなわとなり中断されてしまった。
町民体育大会
昭和25年(1950)健康で明るい町づくりを目指した眞野町長は、スポーツの振興を重点施策として取り上げ、全町的なスポーツ大会を提唱した。そして体育協会など関係団体と協調し、9月30日から10月8日までを期間とする「第一回八雲町体育大会」を実施したのであった。種目は取りあえず軟式野球・軟式庭球・バスケットボール・バレーボール・軟式卓球・相撲・駅伝競走・マラソンの8競技で、各競技にわたって熱戦を展開した。
これがきっかけとなって町民のスポーツ熱は急激に高まり、前に述べた種目以外にも広げて体育関係の組織づくりが進められた。
この体育大会は、以後次第にその種目を増やしながら回を重ねたが、やがて町の主導による大会運営は、形式的に整いはするものの、各団体の自主的な活動を阻害するのではないかという反省が生まれた。そのため大会運営のあり方に見直しを加えた結果、昭和32年(1957)の第八回大会から主管を体育協会に移し、各競技はそれぞれ単位団体によって企画のうえ実施されることになったのである。
こうして多くのスポーツ団体や関係者の協力によって続けられている町体育大会が、スポーツの振興や健康増進に上げた成果は高く評価されている。
スポーツ振興審議会
昭和36年(1961)6月に制定された「スポーツ振興法」は、スポーツに関する国の施策の基本を明らかにするとともに、国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とした法律で、国民があらゆる機会と場所を得て、自主的にその適性や健康状態に応じてスポーツができるよう、地方公共団体はその条件整備に努めなければならないことが義務付けられたのである。
八雲町体育大会(写真1)

こうした国の施策に対応して町では、翌37年4月に「八雲町スポーツ振興審議会」を設置し、スポーツの振興に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議を行い、必要な建議のできる機構とした。この審議会は、5名の委員によって組織され、将来的な展望に立った必要な施設や設備の充実をはじめ、スポーツ環境の整備に活躍している。
昭和56年現在の委員(兼総合体育館運営委員)は上記のとおりである。なお、委員の任期は2年で再任を妨げないとされている。
体育指導委員
町教育委員会は、昭和32年(1957) 12月に体育普及員5名を委嘱し、町民体育の普及と振興に努めてきたのであるが、36年6月のスポーツ振興法施行により、市町村に体育指導委員を必置することとなったため、翌年これを制度化して10名(うち3名は普及員)を任命し、実技指導や助言をさせることとした。この指導委員は任期を2年とする非常勤職員で、地域を分担してそれぞれ第一線で活躍したのである。これにより、スポーツは年々各地に普及されるようになり、指導委員の負担も加重になってきたので、45年には15名に増員した。また、47年から49年にかけて、前述の普及員を19名に増員し、合わせて34名をもって普及指導活動を行ったのである。
こうした活動とともに、社会体育施設の整備や地域住民の意識の高揚などによって、スポーツは年々盛んになっていった。このため教育委員会では、49年に普及員制を廃して体育指導委員を30名とした。以後指導委員は、広域的な各種スポーツ行事にも参画して協力し合い、また、自主的に体育指導委員会を組織し、交流を深めて研修に努めるなど、活動は盛んである。
昭和56年現在の委員(兼総合体育館運営委員)
|
住 所 |
氏 名 |
職 業 |
備 考 |
|
落 部 |
相木鉄三郎 |
団 体 職 員 |
落部体育振興会長 |
|
出雲町 |
杉山秀秋 |
会 社 員 |
体育指導員代表 |
|
野田生 |
菊池建三 |
野田生小学校長 |
学識経験者 |
|
富士見町 |
日南 章 |
公 務 員 |
行政職員 |
|
本 町 |
松永満雄 |
商 業 |
体育協会長 |
この指導委員は、八雲町スポーツ実技指導員も兼ね、競技場の管理・指導・スポーツ教室・各種行事などの実施にあたっている。
八雲町体育協会
町内のスポーツ諸団体が相互に連携を保ちながら体育の健全な普及を図るため、昭和25年(1950)4月に三沢正男(当時道議会議員)を会長に「八雲町体育協会」が設立された。
そしてこの年から始まった八雲町体育大会の強力な推進機関として活躍したばかりでなく、32年の第八回大会からは町に代わって主催することとなり、名実ともに体育振興の中心団体となったのである。なお、この間の27年には渡島体育協会の設立と同時にこれに加盟し、以後は傘下各単協からの各種大会出場には、積極的に支援する体制を築くなど、その活動は目覚ましいものがある。
こうしたことから、昭和36年(1961)10月に秋田県で開催された第十六回国民体育大会秋季大会において、体育優良団体として文部大臣・日本体育協会との連名で表彰を受けたのである。なお、同年12月には北海道体育協会に加盟して現在に至っている。
歴代会長は次のとおりである。
三沢正男(25〜29年)、佐久間省一(29〜43年)、松本初次郎(43〜54年)、松永満雄(54年〜現在)
各種体育団体
スポーツ団体にもその時代によって盛衰があり、既に消滅した団体の経緯については明らかにすることはできないが、昭和56年現在体育協会に加盟している団体は次のとおりである。
昭和56年現在体育協会に加盟している団体
|
体 育 団 体 名 |
創立年月日 |
会員数 |
会 長 名 |
歴 代 会 長 名 |
|
八雲バスケットボール協会 |
昭和20・10・ 5 |
15人 |
石 田 初 男 |
桑山誠一・山内巌・谷田外雄・東郷重雄・松本初次郎 |
|
八雲野球協会 |
昭和22・ 5・ 1 |
210人 |
中 山 勝 明 |
松田武策・山内巌・谷田外雄・長嶋貞一・安藤太郎 |
|
八雲バレーボール協会 |
昭和24・ 4・ 1 |
42人 |
小 林 寿 男 |
水島雲平・浅山英三・永山保夫・正木新一郎・新明幸一郎・都築重雄 |
|
八雲スキー協会 |
昭和25・ 1・19 |
280人 |
高 見 健 生 |
山内巌・園部昌清・畠山利明・野崎正照 |
|
八雲軟式庭球協会 |
昭和25・ 5・ 1 |
40人 |
蓑 島 光 義 |
大沢健太郎・澗山巴五郎・佐久間省一・石垣寿典・日南章 |
|
八雲剣道連盟 |
昭和27・10・25 |
20人 |
水 野 諄 朔 |
田仲慎吉・加藤慎一・石垣寿典 |
|
八雲卓球協会 |
昭和29・ 6・17 |
30人 |
松 永 満 雄 |
飯田健三郎・陳新泉 |
|
八雲柔道協会 |
昭和32・ 5・ 1 |
20人 |
河 野 栄 一 |
斎藤彰・長嶋貞一・服部内匠・河野栄一・住田与三郎・伊藤慶三郎 |
|
八雲陸上競技協会 |
昭和32・ 6・ 1 |
40人 |
杉 山 秀 秋 |
鈴木優・折原徳之丞・桜井正義・阿部明・折登栄雄 |
|
八雲ワンダーフォーゲル |
昭和39・ 7・ 1 |
9人 |
鈴 木 譲 |
鈴木譲・鈴木利明 |
|
八雲体操協会 |
昭和41・ 4・ 1 |
20人 |
友 善 功 |
西亦治信・白川敏夫・斉籐房元 |
|
八雲ソフトボール協会 |
昭和43・ 9・20 |
300人 |
友 善 功 |
梅村朝之・米坂昭一 (注)道代表としてオリエンタルチームは |
|
八雲スケート協会 |
昭和44・12・13 |
10人 |
加 谷 和 夫 |
坂野利水・藤井健 |
|
八雲射撃協会 |
昭和45・ 6・28 |
45人 |
長谷川 孝治 |
村山文彦 |
|
八雲バドミントン協会 |
昭和53・ 4・ 1 |
35人 |
石 川 潔 |
石井周一・真山孝 |
注 体育協会に加盟していない、同好会・愛好会などに類するスポーツ団体も相当数あるが、公式記録がないので省略する。
地域スポーツ振興団体
地域のスポーツを振興し、住民の体位向上や健康増進を図るほか、スポーツを通じて地域住民の交流を強化することを目的として、主要地域に有志による体育振興会が相次いで結成された。
現在の団体は上記のとおりである。
なお、東野・野田生・栄浜・落部・浜松には、冬季のスケート普及のため、育成会が設けられ活動している。
スポーツ少年団
スポーツ少年団は、健康の増進・教養の向上・非行化防止など、次代の八雲を担う青少年の健全育成とスポーツの振興を目的として、昭和41年 (1966)3月にソフトボールやハイキングなどを内容に「出雲町スポーツ少年団」が設立された。続いて同年5月に「八雲町スポーツ少年団本部」が設置され、各地域にスポーツ少年団が結成されていった。
各地域スポーツ振興団体
|
団 体 名 |
代表者名 |
|
落部体育振興会 |
相木鉄三郎 |
|
野田生体力育成会 |
河原 忠義 |
|
西体育振興会 |
岩本 晨 |
|
山崎体育振興会 |
水口 吉忠 |
|
黒岩体育振興会 |
明道 亀三 |
各スポーツ少年団
|
名 称 |
代表指導者名 |
団員数 |
|
卓球スポーツ少年団 |
長 瀬 京 也 |
27 |
|
柔道 〃 |
河 野 栄 一 |
48 |
|
剣道 〃 |
久次米 宣 昭 |
51 |
|
陸上 〃 |
加 谷 和 夫 |
20 |
|
ヤンガース 〃 |
足 立 保 |
22 |
|
落部野球 〃 |
岡 嶋 誠 |
20 |
|
落部ソフト 〃 |
三 品 豊 作 |
22 |
|
落部柔道 〃 |
吉 田 要 七 |
20 |
|
黒岩野球 〃 |
切 明 学 |
15 |
|
黒岩スキー 〃 |
橋 本 靖 夫 |
15 |
|
野田生 〃 |
河 井 英 雄 |
39 |
|
スケート 〃 |
神 田 幸 雄 |
13 |
|
体操 〃 |
桑 原 一 博 |
54 |
|
空手 〃 |
久 保 慶 三 |
30 |
このスポーツ少年団は、日常子どもたちが行っているスポーツを、組織的、計画的に行うため、地域ごとに目的を持ったグループとして自主的に活動させるもので、代表指導者によって一つの目的集団として育成するものである。56年現在では前ページの14団体が活動している。
軽スポーツの振興
町体育大会など各種の競技大会を通じて、高度の技術をもった選手を育成することも必要ではあるが、一般町民が気軽に参加できる軽スポーッ普及の必要性を認めた教育委員会では、昭和34年(1959)ごろから軽スポーツや体育的レクリェーションを奨励したり、普及のための各種講習会を開催し、また、用具を貸し出すなどその振興に努めた。
さらに昭和43年度には「体力づくり」の町として道から指定を受けたので、関係機関の協力によって「八雲町体力つくり推進協議会」を設置して、幅広い活動を展開した。そして44年3月に設定された八雲町教育目標に唱える「豊かな八雲町をつくるたくましい心身をそなえた人」を育成するため、より一層種目を多くしてスポーツ人口の底辺を拡大し、比較的高年齢層に適した″あるく運動″の組織を作ったり、家庭婦人に対するバレーボールの奨励をはじめ、卓球・庭球・バドミントン・ソフトボールなどの普及に努めた。
婦人スポーツの普及
いろいろな体育競技の中に女子の部が設けられ、その振興が図られてきたことは古くからの慣習であった。
町教育委員会では、昭和43年(1968)特に家庭婦人の体力づくりに着目し、「家庭婦人バレーボール」を取り上げ、体育指導委員を先進地である青森県に派遣してルールなどを研修させ、町内の婦人を集めて講習を行いその普及に努めた。こうしたことによって、その効果は急速に上がり、一時は多くのチームが参加して全町的な大会を開催するまでとなった。
これに加えて昭和45年度の道民スポーツ大会の競技種目に主婦の部が設けられ、これに出場した八雲町チームが優勝したのをきっかけに「八雲ママさんバレーボール同好会」(会員50名)が誕生し、翌46、47年と引き続き優勝、さらに47年には渡島代表として全道ママさんバレーボール大会に出場、Bブロックで優勝するという成果を上げたのであった。
こうしたことが動機になって、卓球・ソフトボール・バドミントン・庭球などにも普及の輪が広げられて同好会や愛好会ができ、教育委員会も婦人の体力向上のため積極的な奨励普及に努めた。しかし、家庭婦人層への浸透と維持継続は種々のむずかしさが伴い、特に生粋の八雲人にとっての普及度はいま一歩伸び悩んでいる現状である。
住民スポーツ災害補償
町はスポーツ振興のため種々の施策を講じているが、昭和51年(1976)3月に「住民スポーツ災害補償規則」を定めた・これは、町が主催するスポーツ行事中または教育施設内で行われる児童・生徒の活動中に受けた町民の傷害、あるいはその直接の結果として死亡したり後遺障害を生じた場合には、その被害者に対して(1)死亡給付金(100万円)、(2)後遺障害給付金(障害の程度にょり、それに応じて定める額)の2種の給付を行い、災害を補償することとした。
なお、この規則は55年3月全面改正を行い被害者に対する給付区分を(1)死亡給付金、(2)後遺障害給付金、(3)入院補償給付金の3種類とした。
第4節 社会教育施設
(1) 八雲町公民館
公民館の創設
公民館ということばが用いられはじめたのは、戦後間もない昭和21年(1946)7月に文部省が発した通達で、公民館を地域の総合的文化セソターとして位置付け、公民教育推進の機関としてその設置運営が奨励されたのであった。しかも公民館の設置と活動の助長は、連合軍総司令部(GHQ)の要望するところであったが、新しい施設の建築は禁止され、既設の建物を利用することが適当であるという指導であった。
こうした社会情勢のなかで眞野町長は、公民教育の必要性を痛感し、取りあえず大島文庫が設けられていた旧軍用建物を借用して公民館に準ずる施設に併用、住民の利用に供したのは22年秋のことであった。しかしこの建物は地域的に偏っていることと、施設そのものが不便という事情にあったので、さらに本格的な公民館の設置を検討するため、その年12月に公民館設置準備委員会を発足させることが決議された。そして委員76名を委嘱し、翌23年2月に第一回公民館設置準備委員会を開催して次のような申し合わせを行うとともに、11名の設置委員を委嘱のうえ、設置についての具体的な検討を進めた。
申合
現在八雲営林署庁舎充用建物は速かに返還を願い町民教養上喫緊なる公民館として設置せられるよう最善の方途を講ずること。更に旧在郷軍人会館は公民館に関連をもった適切な施設として活用すること。
つまり現在八雲営林署に貸付している町有建物(現在の公民館敷地内に所在)を返還してもらって公民館に充用し、さらに隣接している旧在郷軍人会館(現、簡易裁判所敷地)を一体として活用することが適当であるという趣旨であった。
昭和23年12月に営林署は庁舎を新築移転し、建物の引き渡しを受けたので、新たに公民館委員15名を委嘱して本格的な設置計画を進め、翌24年5月3日の憲法記念日を期して「八雲町公民館」を開館した。
この公民館の開館は、社会教育法の施行(昭和24・6・10施行)に先駆けるものであり、階上階下合わせて295平方メートルで、階下に図書室・小集会室・事務室・書庫、階上には講堂を設け、専任職員2名を配して活動を開始した。さらに26年5月には、隣接の八雲保健所が庁舎を新築して移転したので、この建物を無償で譲り受け、渡り廊下でつないで公民館別館として利用することになり、延べ面積は901平方メートルに増加した。
また、公民館に付設の図書室は、昭和24年6月に寄贈された大島鍛の元蔵書であった”大島文庫”3000冊余りで開設され、以後は年々新刊図書を購入して充実を図った。さらに26年8月からは、へき地単級複式の学校15に巡回文庫を行い、翌年9月からは図書の貸し出しを始めるなど、逐次活発な活動を展開した。
24年6月からは青年学級8学級を開設して青少年教育に力を注ぎ、また、幻灯機やナトコ映写機の導入により視聴覚教育にも力を入れるなど、公民館設置の目的に沿って成果を上げたのである。
公民館改築の機運
八雲町公民館は、昭和24年5月に社会教育推進のセンターとして開設されたのであるが、この建物は大正7年(1918)ごろ八雲片栗粉同業組合の事務所として建てられ、その後、八雲高等国民学校校舎、八雲営林署庁舎などに使用されて40数年を経過した。また別館も、昭和8年(1933)に八雲町農会事務所として建築され、19年からは八雲保健所庁舎に当てられるなどの経過があったもので、ともに老朽化が甚だしく時代に応じた社会教育推進の場としては、その機能を十分に発揮できない状態になってきた。
このため町は新しい公民館の建設を検討し、昭和38、39年の2か年継続事業で実施する方針を決め、37年3月に公民館建設基金条例を制定するなど準備を進めた。しかしこれに要する経費は4000万円以上と推定され、当時の財政事情は、学校教育施設の整備拡充、諸産業の振興、社会福祉の増進など、多くの問題を抱えている状況であって、公民館の新築整備費を全額町費に依存することは容易なことではなかった。
こうした状況の中で、建設資金の一部を援助しても″新町八雲にふさわしい充実した施設をもつ中央公民館を建設しよう″という声が盛り上がり、37年5月に「八雲町公民館建設期成会」が発足した。期成会は7月中旬から各地区で懇談会を開催し、全町的な協力体制の確立をみたのである。発足当初の期成会の役員は、会長に田仲孝一(町長)、副会長に久保田正秋(議会議長)、徳田又雄(教育委員会委員長)、松川林四郎(商工会長)、服部レイ(八婦協会長)などであったが、38年6月会長に久保田正秋が就任、さらに推進本部長に長谷川克巳を選んで、より一層強力な募金活動を展開した。
そして概算総経費4000万円のうち750万円を募金目標額と定め、募金期間を37年4月から40年3月までの三か年という計画を立て、町内全戸にわたる戸別協力金を中心に大口募金(事業所)、特殊募金(町外事業所・町出身の町外居住者)、寄付金(公職者および一般篤志)などのほか、事業益金で目標額を達成することとした。
このうち事業益金として、「町ぐるみ源平歌合戦」、「有名人かくし芸大会」、「芸能発表会」などの収益積立てがあったほか、八婦協によるバザー収益金や香典返し・法要・追悼会記念・各種委員の報酬など、数多くの浄財が寄せられたことは特筆すべきことであった。
こうして、各方面の協力のもとに募金運動が進められた結果、41年3月末をもって総額594万4400余円の募金があり、当初予定額の79・2パーセントにとどまったが、さらに建物の完成に際して直接寄せられた物品の寄贈がかなりあり、おおむね目標を達成することができたのであった。
公民館新築
こうして内外の期待を集めた公民館は、周辺土地所有者の 理解を得て敷地の拡充も順調に進み、鉄筋コンクリート2階建て、延ベ1996・77平方メートルに計画が決定された。そして昭和39年(1964)6月に入札を執行し、建築主体工事は坂本建設株式会社(札幌市)が請け負い、さらにこのほかの業者によって施行され、直接工事費5105万円をもって翌40年9月末に完成した。
八雲町公民館(写真1)

八雲町公民館平面図(写真1)
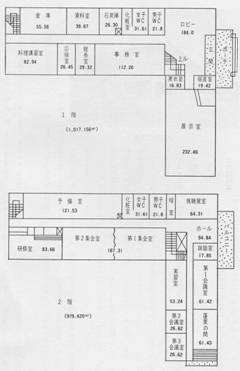
新公民館は、図書室・郷土資料展示室をはじめ各種集会室・講習室・福祉室など公民館活動に必要な施設や設備が整えられ、最終的には敷地購入、備品設備などを含めて5700万円余を要したのであった。
住民の多大な協力のもとに新装なった公民館は、青年団体や婦人団体をはじめ各種団体の研修活動を助長し、また、結婚式や各種会合に利用されるなど、町民の日常生活に直結した文化センターとして機能を発揮したのである。
なお、この公民館の完成によって、それまで役場で執務していた教育委員会事務局をここに移し、教育行政の一本化と効率化を図った。
昭和53年(1978)11月には、公民館開設当時から付設してきた図書室を、元青少年会館を改造のうえ八雲町立図書館として独立させてこれに移した。
(2) 落部公民館
建設期成会の活動
落部地区においても、地区住民の集会の場として、また、社会教育活動を推進して地区内の生活改善や青少年の健全育成を図る場とするため、公民館建設の要望が強く、昭和32年(1957)に八雲町と合併した際の新町建設計画にもこれが取り上げられ、早期実現が望まれていたのである。
しかし一方では、改築整備が望まれていた八雲町公民館が、ようやく39、40の二か年で工事施行の見通しが得られるという状況で、やむを得ず延期されていたのであった。
このような状況のなかで、37年(1962)5月に「八雲町公民館建設期成会」が発足し、全町か一丸とした戸別募金運動が進められていたので、落部地区でもこれに協力すると同時に、落部公民館の早期実現を目指して募金を開始しようとする機運が高まった。こうしたことから、同年9月「落部公民館建設期成会発起人会」を開催して直ちに期成会を設立のうえ常任委員を委嘱した。そして10月3日に常任委員会を開催して募金方法などの協議を行い、八雲町公民館建設の戸別協力金と同額を合わせて募金し、37年9月から40年3月までに総額50万円を建設資金として積み立てることとした。
期成会の会長には伊藤淳一(連合町内会長)を選んで活動を開始し、町内会・部落会ごとに戸別募金を行って資金づくりに努めるとともに、40年12月に町および議会に対して「落部公民館の早期建設について」の請願書を提出した。この請願は議会で採択されたので、さらに41年3月「落部公民館建設実行委員会」を設立し、委員16名を委嘱して計画の具体化や募金活動の強化を図った。
こうした期成会の活動は、最終的には43年6月まで続けられ、芸能大会の事業収益金、団体青年部・婦人部などからの寄付金と合わせ、総額106万円という成果を収め、目標額の212パーセントと大きく上回り、公民館の器具備品購入資金に当てられたのである。
落部公民館(写真1)

建設の実現
地域住民の待望久しかった公民館は、八雲町公民館新築の翌年、すなわち昭和41年(1966)11月に工事入札が執行され、工費1180万円をもって新築されることとなった。敷地は元落部診療所南側の民有地を落部支所(元落部村役場)敷地と交換し、木造2階建て449・09平方メートルの施設を41、42の二か年継続で建設するものであり、11月に着工して42年6月に完成したのであった。
この公民館は、旧診療所の建物を模様替えのうえ充当した役場落部支所に併設して建てられ、集会室・小会議室・調理実習室・研修室・図書室・ロビー展示室などが設けられたもので、新築を記念して元落部村長愛山行永からの篤志寄付があったので図書を購入し、これを「愛山文庫」と名付けた。
落部公民館平面図(写真1)
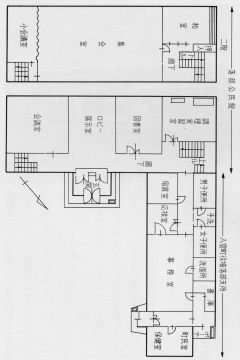
こうして落部公民館は、昭和42年7月10日から開館して、地域における教育文化活動をはじめ諸会合や結婚式などに利用され、社会福祉の増進に寄与しているが、その後図書室は管理の面から支所事務室前の部屋に移し、利用者の便宜が図られている。
(3) 上八雲公民館
市街地から20キロメートル離れている上八雲地区の住民の間に、地域の集会の場として公民館を建設しようという声が高まり、昭和27年(1952)に「上八雲公民館建築委員会」を結成した。そして33万8500円の現金寄付とともに労力提供を申し入れ、早期実現について陳情を続けた。
町ではこれを検討した結果、辺地農山村の産業文化と社会教育の振興を図るため、町立として建築することに決め、翌28年8月に工費217万円余をもって完成したのである。
建物は、木造平屋建て237・6平方メートルで、役場上八雲出張所も併設された。
こうして地域住民の集会、各種会議、講習会などに活用されたのであるが、出張所は33年8月をもって専任職員の配置が打ち切られ、公民館もやがて非近代的な建物となって利用回数も減り、必ずしも所期の成果を上げられないまま老朽化したので、昭和45年(1970)に上八雲会館の建設をまって廃館された。
上八雲公民館(写真1)

(4) 八雲町立図書館
公民館付属図書室の創設
元八雲農会長や徳川農場長を務めた大島鍛の没後、故人が残した多くの蔵書を永く保存するとともに、これを基にして有志の力で補充を行い、将来は農村図書館ともいうべき施設を造る計画を立て、太田正治を中心とする30名ほどの有志が「大島文庫維持会」を組織して維持管理に努めてきた。しかし、時局がらなかなか日の目を見ることもなく経過したが、維持会では、終戦後間もなく旧軍用建物のうち通称ピストと呼ばれた建物を借り受け、これらの蔵書を整理して「大島文庫」と名付け、貸出式の図書館を開設した。
こうして開館された大島文庫ではあったが、これに着目した眞野町長はさらに町民一般に広く公開して有効な活用を図るため、公民館の開館に併せて町へ移管するように要請し、およそ3000冊の寄贈を受けて昭和24年(1949)6月に公民館付属図書室を創設したのであった。
道立図書館八雲分館の併設
北海道立図書館が、地方文化の向上に資するため、道南にも分館を設置する計画があることを側聞した田仲町長は、これを当町に誘致しようと昭和27年以来熱心な運動を続けた。この結果、適地と認められて設置が決定し、29年8月八雲町公民館に道南地方を奉仕地域とした「北海道図書館八雲分館」が併設された。この道立図書館の分館は、全道で名寄・八雲・標茶の3館で、八雲は名寄に次いで2番目に設置されたものであり、分館長は教育長が兼任していた。
八雲町立図書館(写真1)

設立当初、町は分館の活動である巡回文庫のため、特に自動車を購入して「あけぼの号」と名付け、分館の図書を毎月1回町内をはじめ、長万部・落部・森・砂原・鹿部・熊石・今金・瀬棚・北檜山の十か町村46のステーションを巡回して、道南地方の文化活動に貢献した。
しかし、毎年4月から11月まで、ひと月のうち10日余りを費やしての定期巡回は、町にとって大きな負担となったばかりでなく、道立図書館の配本にも限界があり、また、巡回車も古くなったが買換えの財政的負担が困難という事情もあって、昭和34年(1959)にはステーション方式を中止し、直接館に借りにくる町村だけに貸し出す方式をとることとした。
なお、管内の辺地については二十か所のステーションを設置し、年間5、6回の巡回を行い、辺地における文化の向上に力を注いでいる。
分館蔵書数は、56年現在で1532冊である。
図書館の独立
公民館に付属する図書室ではあったが、蔵書数は2万余冊を数え、その活動は移動図書館・高齢者文庫・漁業文庫・読書サークルなどと幅広く、サービスポイントも40数か所を数えるなど、専門の図書館に比べてもなんら見劣りしないほどに発展し、関係者の間では早くから図書館法に基づく図書館として独立すべきであるという意向が高まっていた。
時あたかも昭和53年(1978)8月には総合体育館が完成し、これまで青少年会館を利用していた剣道や柔道などもこの中の小体育室でできるようになったのを機会に、青少年会館の内部を改造して転用する準備を進め、同年11月1日「八雲町立図書館」として開館式を挙行のうえ3日から業務を開始した。
なお図書館には町で直接購入した図書のほかに篤志により寄贈された文庫があるが、それらを簡記すれば次のとおりである。
|
文庫名称 |
開設 年月日 |
主 旨 |
寄 贈 経 過 |
|
小学館文庫 |
昭和48年12月 4日 |
小学館社長相賀徹夫、同常務佐々部承象両名が、 |
昭45・ 8月 258冊 |
|
香 蘭 文 庫 |
昭和49年 5月17日 |
北海道立図書館より寄贈、この図書は香蘭女子短大が閉校に際し、 |
昭49・ 5月 370冊 |
|
徳 川 文 庫 |
昭和51年12月21日 |
51・9・6名誉町民徳川義親死去遺族の篤志により寄贈された。 |
徳川義親死去 1、840千円 |
|
日 出 文 庫 |
昭和53年 8月23日 |
宮園町大島日出生寄贈 |
|
|
山 岳 文 庫 |
昭和54年 9月 1日 |
八雲高校教諭佐々木征一、七飯養護学校へ |
昭54・4月 320冊 |
|
ヤクルト文庫 |
昭和54年 9月25日 |
㈱八雲ヤクルト社長宮下竜輔、図書購入費として寄贈 |
昭54・8月 200千円 |
|
ライオンズ文庫 |
昭和54年12月17日 |
八雲ライオンズクラブより寄贈 |
昭46・12月 50千円 |
|
久保田文庫 |
昭和55年 3月31日 |
54・11・3名誉町民久保田正秋死去遺族の篤志により寄贈 |
図書購入費 1、500千円 |
これらの図書を合わせて、56年現在蔵書数は2万7819冊に及んでいる。
第5節 社会体育施設
体育施設の概況
戦後間もなく陸上競技大会や野球大会などが復活し、いわゆる社会教育の振興がみられつつあったが、とくに昭和25年(1950)眞野町長の提唱によって町民体育大会を創始したことにより、町民の各種スポーツに対する関心は急速に高められ、技術の向上に役立つところが大きかった。またこれと同時に、種目別単位団体の育成と体育協会の強化拡充が図られた。
しかし当時は、社会体育に関する町営の専用施設は全くなく、昭和28年に整備された八雲高校の陸上競技場のほかは、限られた小、中学校のグラウンドや体育館を利用するという範囲のものであった。したがって各競技団体とも不自由を感じていたことは当然で、時代の推移につれて社会体育専用施設の整備を望む声が各方面から高まってきた。
町ではこれらの要請に対し、昭和41年(1966)八雲町公民館敷地内にテニスコート一面を造ったのをはじめ、42年に青少年会館を設置して剣道や柔道に活用できるようにし、また、46年には相生児童館にバレーボールやバドミントン、卓球などに利用できるスポーツホールを併設するなど、種々の施設を整備していった。
こうして社会体育施設の整備が進められるようになったとはいえ、あくまでも応急的なものであるため、これらとは別に、本格的な施設としての総合グラウンドや町民体育館などの建設について検討が重ねられた。そして適地の選定作業を進めた結果、昭和46年(1971)3月に住初町地内の遊楽部川沿い民有地を買収することについて議決を得たことにより、ようやく総合グラウンドの建設に向けて動き出し、46年度用地買収、47年度から「運動公園」の造成に着手したのである。
また、冬のスポーツであるスキーについては、大新の大阪山、山崎の若草山、鉛川、それに落部の北村山、斎藤山など、適当な場所を選んで町体育大会を行ったり町民に利用されるよう配慮してきたのであるが、町営のスキー場といわれるようなものはとくになかった。そのため町はこれの設置について検討を進め、昭和49年に春日地区の民有地を借りて町営スキー場を開設、休憩小屋や夜間照明を設けて町民が利用できるようにし、50年1月オープン冬季間のスポーツ振興を図ったのである。
運動公園
昭和46年度で用地買収や交換などにより、既存の町有地と合わせて4万3464平方メートルの用地を確保した町は、翌47年度整地事業に着手し、たまたま開発建設部が行っていた八雲今金線改良工事による排土の搬入協力を得て順調に進められた。
主管の教育委員会は、これと並行してスポーツ振興審議会や体育協会など関係者の意見を聞き、各種施設の配置や規模について具体的な協議を進め、まず野球場・運動広場・テニスコートの整備を取り上げ、48年度から実施することとした。
野球場は、敷地に約1万3000平方メートルを充て、ホームベースから左右両翼まで90メートル、中堅110メートルという規模で、これにダッグアウト、スタンド、スコアボードと周囲にフェンスをめぐらせ設置され、町内唯一の本格的なものとなった。
さらにこれに隣接して造られた運動広場にもバックネットを備えて、ソフトボールなど多目的に利用できるように配慮された。
運動公園(写真1)

また、高さ1・8メートルのフェンスをめぐらせた3面のテニスコートも設けられ、これらをもって第一次の整備が終わり、49年(1974)7月に「八雲運動公園」として使用を開始した。ただし、テニスコートは昭和52年に着工した総合体育館の敷地に充てられたため、同年現位置に移転した。
こうして造成された運動公園は、昭和50年10月に都市公園の一つとして条例化され、さらに51年2月には都市計画法に基づき「住初公園」として造成することの計画が決定し、52年5月事業決定を受けて、国庫補助により新たに1万1868平方メートルの敷地を買収し、53年度に自転車広場を造成した。
八雲町運動公園(写真1)

また、これと隣接した一角に、八雲町100年を記念して町木のカツラ160本を植え、「100年の森」と名付けて記念碑を建立した。
なおこの公園内には、町民プールや総合体育館も設けられ、総合的な体育施設として整備された。
町民プール
以前は大人も子供も海や川で自由に泳ぎを楽しむ機会に恵まれていたが、海や川の汚濁が進んで衛生上不適当になるとともに、安全性の確保という面からも制約が加えられるようになった。町民の多くは泳ぎに親しむ機会かないため、水泳のできない者が多くなる傾向が強くなっていた。
このようなことから、体力増進と町民皆泳を念願した北口町長は、運動公園の一角に「町民プール」の設置を計画し、昭和49年度早々に着工を予定した。しかし、折からの経済変動による国の総需要抑制策や、建設資材高騰などの影響を受けて着工は6月にずれ込み、このため落成式はシーズンも終わりに近い9月20日となったのであるが、翌21日から一般町民の利用に供されたのであった。
このプールは、一般利用25メートル・7コースのほか、児童用18メートル、幼児用7メートルの3面をセットしたアルミ製で、これに約1300平方メートルの上屋をかけ、水道用水の導入とともに所要の衛生設備を設けた近代的なもので、総工費は9478万円余を要した。
町民プール(写真1)

こうして一般町民の積極的な利用が期待されてきたのであるが、水道用水の利用と自然温化の方式であるため、直接外気の支配を受けやすく、残念ながら利用期間が短くなるという状況であった。したがって、できる限りこれを延長するため、53年度に新設した総合体育館の暖房を利用し、7月から9月までの3か月間水温を23度に保つようにしている。
総合体育館
運動公園や町民プールの整備が進むにつれて、きびしい財政事情によって容易に実現できなかったスポーツセンターの建設を望む声が急激に高まりをみせていた。
こうしたときの昭和51年(1976)、航空自衛隊第二十高射隊の駐屯受け入れに際し、町が民生安定対策の一つとして総合体育館建設の実現を要望、防衛施設周辺整備事業としての採択とともに、八雲町100年の記念事業としても取り上げ、関係筋と折衝を続けたのである。
幸い町の要請がいれられ、52、53年度の二か年継続事業で実施することとなり、52年6月に入札を執行し松原組ほかの業者の請負によって同月17日に着工、53年8月31日に完成した。
この体育館は、鉄筋コンクリート2階建てで、建築面積2760・6平方メートル、延べ床面積3840・2平方メートルの規模をもち、工事費・設計監督委託料・外構整備・内部備品整備を合わせて実に6億円余(うち国庫補助2億円余)の巨費を投じたものである。
こうして待望久しかった体育の殿堂は、管内町村屈指のものと称賛され、9月20日に関係者約400名が出席して盛大に落成式を挙行した。
八雲町総合体育館(写真1)

また、同月23、24日の両日にはこけら落としとして、世界選手権に出場の全日本女子バレーボールチームの合宿練習を兼ね、優秀チーム(日立・ユニチカ)を迎えて招待試合を行い、一般町民とともに喜びを分かち合った。
なお、体育館内には教育委員会体育課が配置され、社会体育事業推進のセンターとしての役割を果たすとともに、運動公園内の各施設の一体的な管理体制が図られた。
八雲町総合体育館施設概要
|
1 位 置 八雲町住初町185番地 |
|
2 構 造 鉄筋コンクリート造り2階建 |
|
3 敷地面積 5,8882㎡(運動公園全域) |
|
4 建築面積 2,760.6・㎡ |
|
5 延床面積 3,840.2・㎡ |
|
6 工 期 自 昭和52年6月17日 |
|
至 昭和53年8月31日 |
|
7 設 計 北海道開発コンサルタント株式会社 |
|
8 施 工 株式会社松原組 (八雲町) |
|
末広屋電機株式会社(札幌市) |
|
大信工機株式会社 (札幌市) |
|
9 事 業 費 建築工事費 390,000,000 |
|
電気設備工事費 100,000,000 |
|
暖房衛生給排水工事費 57,400,000 |
|
設計監督委託料 19,500,000 |
|
外構整備・備品購入費外 55,162,000 |
|
合 計 622,062,000 |
八雲総合体育館1階平面図(写真1)
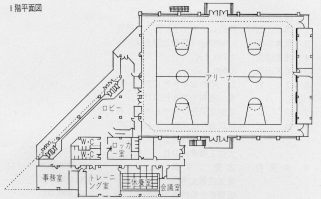
八雲総合体育館2階平面図(写真2)